中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編
立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!
- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>
- 企画・連載>
- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>
- 【ブログ】2017年のゲーム業界はIP主導の時代へ

中村彰憲
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。
アクセスランキング
新着記事
-
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
-
【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係
-
【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!
-
【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋
-
【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン
-
【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話
-
【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)
-
【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)
-
【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話
-
【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報
連載一覧(すべて見る)
【ブログ】2017年のゲーム業界はIP主導の時代へ
2017-01-05 13:00:00
2016年前半は、バンダイナムコグループの「VR ZONE」が世間をにぎわせ、後半はソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)によるPlayStation VR(以下、PS VR)が発売で在庫不足なども含め話題となるなど、まさに「VR元年」と称するにふさわしい1年となった。
同時に、『Pokemon Go』の電撃的なローンチとその社会現象化は、「AR」や「位置情報ゲーム」というものを一般大衆にまで広く浸透させる好機となった。つまり、ゲームの「新しい遊び」が常に話題となった1年と言え、そのような視点からも結果的に「ゲーム新時代到来」の1年であったと言えよう。
というわけで例年に引き続き今年のゲームシーンを「占って」みた。
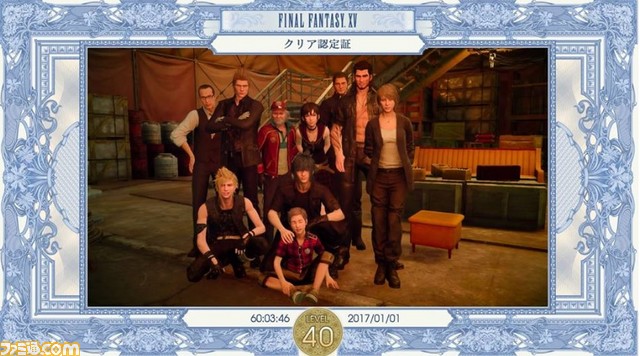
|
|
昨年のニューヨークと打って変わり今年はルシスで年越し |
「A.I.」や「オープンワールド」-技術や欧米で発展したデザインコンセプトの取り込みがさらに強い日本のIPを生み出す-
昨年末発売されたタイトルの中でとりわけ、際立ったのが、『人喰いの大鷲トリコ』(以下『トリコ』)と『ファイナルファンタジーXV』(以下、『FF XV』)であった。そしてその両タイトルの共通項として筆者が注視したのが、作品におけるA.I.(人工知能、以下、A.I.)。
『トリコ』においては、動物のようにリアルでかつ感情移入可能な挙動を見せるトリコが高く評価され、『FF XV』は、登場するメインキャラクターによるセリフや、NPC並びにモンスターの自然な行動パターンなどに実装された。
A.I.開発において従来にない様々な挑戦が行われたことが、CEDECなどで発表されてきた。同時に『FF XV』では、欧米企業により技術的展開が進んだオープンワールド的なゲームシステムと日本で培われてきたRPGにおけるストーリーテリングの技法を完全に融合させた。
確かに『シェンムー』シリーズ、『ゼルダの伝説』シリーズ(とりわけ『時のオカリナ』以降の3D版)、『龍が如く』シリーズ、『ドラゴンズドグマ』シリーズなどもオープンワールド型だが、欧米的なオープンシステムを積極的に踏襲しつつ、既存シリーズで培われた要素との完全統合を試みたのは、2015年に大成功を収めた『メタルギアソリッド5 ファントムペイン』と2016年の『FF XV』からだろう。
だがこれらのムーブメントは、まだ序の口にすぎない。他文化で発展したものを自文化へと統合させる力こそまさに日本のお家芸であり、それこそが日本的ゲーム作りの神髄と言えるが、それがさらに開花するのが2017年なのだ。
『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の成功や『Pokemon GO』の社会現象化が示すプラットフォームからグローバルIP中心の時代

|
|
外伝の大きな成功はトランスメディアストーリーテリングのポテンシャルに対する認識を刷新する契機に |
2017年の展望の予兆のようなものに、『Pokemon GO』の世界規模での社会現象化や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(以下、『ローグ・ワン』)の興行的成功がある。
『Pokemon GO』については、これまで特定層の間でプレイされてきた、「位置情報ゲーム」や携帯電話の写真撮影機能を使った簡易な「AR」のエンターテインメント的用途を広く一般の人にも認識させたという点において意義があったと同時に、『Pokemon』という知的財産(Intellectual Property、以下、IP)のブランド力を改めて世界に示した。
ゲームソフトが流通していない国々でも広くプレイされている状況を垣間見る中で、『Pokemon』は、「ゲーム」というひとつのメディアではなくアニメ、カードゲーム、その他マーチャンダイズといったあらゆるものが複合的に重ね合わせられて認識されているコンテンツであるということが事業効果を伴う形で確認できたのだ。
同時に「位置情報ゲーム」の訴求点を新規IPで示した場合、一旦ハマると非常にディープにその楽しさを理解するユーザーが多数輩出される反面、そこまで面白さを伝える上で時間と費用が掛かるという点においても同じくNianticが開発した『Ingress』や、コロプラ発展の契機となった『コロニーな生活』などからも確認できる。
したがって、今後、「位置情報」ゲームを展開することを事業者が考えた場合、どうしてもこれが前例として捉えられるだろう。つまり「位置情報」を応用したコンテンツは、認知度が高く、既存のIPでかつ地域性と絡めることに違和感を抱かせないコンテンツと親和性が高く、可能であればグローバル規模でそれを実装できるIPであることが望ましいということだ。
一方で、『ローグ・ワン』は『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(以下、『新たなる希望』)で重要な役割を果たした帝国軍の宇宙要塞“デス・スター”の設計図をいかにして盗み出したのかを描く物語だが、作品は文字通り、『新たなる希望』の10分前、ドラマ的にも、ワンシーン前までを描き、単なるプロローグにとどまらない連続性を持つ「直前譚」として構成されている。
実際、本作と『新たなる希望』をつなげてみても何の違和感を持つこともなく視聴できるという点が従来の「連続劇」とは違ったつくりとなっている。
ただ、それはあくまでも物語世界の継続性という点においてであり、劇場映画シリーズ本編が一貫して示してきたスカイウォーカーの血筋やジェダイ騎士の盛衰、並びにこれらに関わる人たちの群像劇という点で見ると、時間及び空間的継続性はあっても『ローグ・ワン』は「外伝」的位置づけとなり、英語版タイトルにもあるとおり、本作はこれらの銀河間戦争という未曾有の時期における文字通りの「あるひとつのスター・ウォーズの物語(A Star Wars Story)」ということになる。
このような作品が世界的興行収益において、1月3日の段階で、全世界で7億8970万ドル強をたたき上げた。
規模は違うものの、国内においても『ファーストガンダム』の前日譚を描く『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』シリーズのイベント上映や、ブルーレイ販売が成果をあげており、2017年秋からは、同作『ルウム編』が2話構成で展開されることが決まっている。これらも文脈を埋めるほど魅力のある世界観の整合性が、これまでの作品群に存在しているからに他ならない。
つまりここにきて、物語の整合性を更新させながら作品の世界観(Universe)を拡大させることが、いかに収益をもたらすかを数字として確認することができるようになった。つまり、もしコアの物語が魅力的であれば、その文脈を埋めようとする物語展開やキャラクター群に対してもファンはしっかりとお金を払って、それを確認するということが明確となったからだ。
さらに既存ファンの消費動機のみに着目し、ストーリーテリングにおける整合性を意識しなかった作品の場合、コアファンを中心とした販売数は見込めつつも、『ローグ・ワン』のように新規ユーザーを取り込むことは難しくなる。
つまり、これらの状況から、各企業において、自社が所有するコンテンツの「棚卸」が改めて行われていくことになるだろう。その視点はふたつ、ひとつは「トランス・メディア・ストーリーテリング」が、実施可能なIPについて。もう一方は、世界的競争力の高いIPについてだ。
したがって、2017年はおのずと、これらのIPが大々的に展開されるプロジェクトの発表、または展開が行われることになる。前述の『スター・ウォーズ』シリーズのここ2年のパフォーマンスや、昨今の「ハローキティ」のグローバルライセンスプログラムを見れば明らかなとなっており、世界的に大きな認知度と人気を誇るコンテンツは、もはやそれ自体が「プラットフォーム」となりうることを示している。
つまり、2017年は従来のハードウェアのプラットフォームが主導した時代から、IPがプラットフォーム的役割を主導することがより顕在化する1年となるだろう。
参考
2016年はゲーム新時代の到来
2015年のゲーム業界、トレンドは「王道コンテンツ」としての「ゲーム」の躍進










