中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編
立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!
- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>
- 企画・連載>
- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>
- 【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは

中村彰憲
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。
アクセスランキング
新着記事
-
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
-
【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係
-
【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!
-
【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋
-
【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン
-
【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話
-
【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)
-
【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)
-
【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話
-
【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報
連載一覧(すべて見る)
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
2024-11-27 15:00:00
現在放送中の完全新作TVアニメ『魔法使いになれなかった女の子の話』(『まほなれ』)の制作陣によるトークショーが10月14日、立命館大学衣笠キャンパス(京都市北区)の充光館地下シアター型教室で開催された。
立命館大学映像学部では、2009年にアニメ監督を招いてのアニメ特別上映会を開催したのを皮切りに、実践科目の一環としてアニメ作品とのコラボイベントを行っており、今回もその取り組みの一環だった。会場となった充光館では、10月4日から11月8日まで約1ヵ月にわたり『まほなれ』のメイキングに関する特別展示が行われたほか、キャンパス内の存心館生協食堂では、11月4日から8日まで同作のメインキャラクターをモチーフとしたコラボメニューが提供された。
トークショーには松根マサト監督とプロデューサーの有田真代氏が登壇。月曜日10時40分開始という早い時間帯ながら学生や一般視聴者など多くの受講生が参加した。
商業アニメ制作を構成する「四大エレメント」
トークショーの冒頭20分は、『まほなれ』を例にとった商業アニメの制作をテーマに進められ、その後、放送に先駆けたTVアニメ第3話の最速先行上映を挟んで、『まほなれ』の世界観や今後の展開についてのトークが繰り広げられた。
まず、有田プロデューサーが、アニメ制作における「製作プロデューサーの役割」について語った。『まほなれ』の魔法世界でもおなじみの四大元素(エレメント)になぞらえ、商業アニメ製作に必要な4つの要素を「モノ」、「おカネ」、「ヒト」そして「観客」であるとし、それぞれについて解説した。
まず、「モノ」は作品であると説明したうえで、一般的に作品を作り上げるためには自社による完全オリジナルでない限り、原作者や版元との交渉が不可欠であることに言及した。『まほなれ』の場合はオリジナルIP創出を目指すProject ANIMA(DeNA、文化放送、創通、MBSの共同プロジェクト)第2弾「異世界・ファンタジー部門」の大賞作品として一般公募から選ばれた作品であるものの、初出が小説投稿サイト「エブリスタ」での投稿・掲載であったため、原作者と同時にエブリスタとも契約が必要だったという。他の作品であっても同様のプロセスになると有田プロデューサーは語った。
「おカネ」にあたる製作費の資金調達については、日本のアニメでは製作委員会方式がとられており、幹事会社はテレビ局、音楽会社、パッケージソフトメーカー、グッズ販売会社、広告代理店などをパートナーとして委員会を組成する必要があるとした。
「ヒト」はアニメ製作の場合、制作スタジオが該当するという。『まほなれ』の場合、J.C.STAFFが担当しており、さらにその先には美術・音響・編集など各領域を担う会社が複数あり、一体となって作品づくりに取り組んでいると有田プロデューサーは説明した。
また、最後の元素に「観客」が入る理由として、ファンがいない限り商業作品は成立しないと有田プロデューサー。松根監督も「一番大事な要素」と「観客」の重要性を改めて指摘した。さらにファンと作品をつなぐ「宣伝プロデューサー」の役割についても言及。1クールあたり平均70本のアニメが放送される中、どう作品を伝えていくのかが重要であると強調した。そして、様々な立場のひとたちの希望を調整し、「全員がハッピーになるように取りまとめる」のがプロデューサーの仕事だと有田氏自身の職務を解説した。
ただ、「前述の四者の希望が完全に一致しているわけでもない」とも有田氏は語る。例えば、原作者や版元は早期のアニメ化を望むが、制作スタジオは制作期間を長くとりたい。ファンからすれば「平日深夜ではなく週末朝に放送してほしい」との声があるが、委員会の予算上、実現が難しい場合も。このように異なる立場からの要望が複数ある中で、どう調整すれば全員が満足できるかを考えることがプロデューサーとして大切と有田氏は語った。
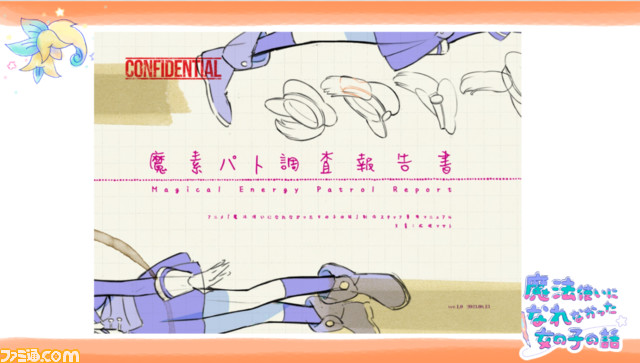
|
|
▲「魔素パト調査報告書」と題された文書の正体は、制作マニュアル。トークショー開催時の最新版では4〜5ページに凝縮 |
一方、アニメ監督の仕事について語るにあたり、松根監督がスクリーンに映したのが、「魔素パト調査報告書」という文書の表紙。「魔素パト」とは、劇中でクルミらが入部したマジック研究会が「レットラン七不思議」(※レットランとは本作の舞台となる魔法学校の名称)とその原因とされる自然エネルギー「魔素」をパトロールする活動を指すが、松根監督がここで示した文書は実はスタッフ用マニュアル。アニメ制作の最初にこうしたマニュアルを作成してビジョンの共通を図るという。例えとして、松根監督は「プロデューサーから『親子で楽しめる魔法少女のアニメにしてほしい』と言われているのにいきなりデスゲームとか始まったらまずいですよね」とユーモアを交えて説明し、会場を沸かせた。このようにマニュアルではコンセプト、世界観やキャラクターの等身等、作品の指針となるガイドラインを具体的に示しているという。
また、マニュアルには作品づくりにおける注意事項も記載されている。例えば、『まほなれ』の場合、「子供向け」を意識したことから物語進行については「アップテンポにしない」ことや、キャラクターの表情を引き立てるため「寄りのレイアウト」を多用する方針が示されているという。これにより、作品の親しみやすさや見やすさが向上すると同時に情報もシンプルに伝えられるとのこと。
なお、マニュアルはスタッフのためだけではなく監督自身のためでもあるという。チェック項目が膨大なため、制作中に細部を見失いそうになることが監督ですらあるという。したがって、自分を含めたスタッフ全員もいつでも振り返ることができるように作成したとのこと。監督としてマニュアルをつくりはじめたばかりの時は数十ページにわたる内容だったが、忙しいスタッフがすべてを読むのは難しいことに気づき、現在は4~5ページほどにまとまっているとのこと。
また、松根監督は「監督と演出との違い」についても言及。(実写ドラマでは「監督=演出」であるのに対し)アニメシリーズの場合、エピソードごとに演出担当が配置され、シリーズ全体を監督が統括する。つまり、演出は戦術を担う存在であるのに対し、監督は全体的な戦略を担う存在であると語った。演出家が絵コンテに沿って作画や編集に責任を持つ一方で、監督はシリーズ全体のコンセプトを示したうえで必要に応じて軌道修正をおこなうのが役割であるとのこと。このような観点で見ると、前述のマニュアルづくりは監督として重要な任務のひとつと言えそうだ。
「当初のサブキャラがヒロイン級昇格」の新規IPあるある

|
|
▲松根監督(左)と有田プロデューサー。終始和やかな雰囲気で進行 |
アニメ視聴後には、TVアニメ『まほなれ』が生まれた背景や作品についてのディスカッションがおこなわれた。まず、「原案のウェブ小説からアニメ化する際に意識したこと」について、有田プロデューサーは、初めて原案小説に触れたのがProject ANIMAの審査期間中だったと語った。当時、「異世界・ファンタジー部門」には、2000から3000件もの小説、企画書、漫画が寄せられ、審査員たちは連日会議室にカンズメ状態になりながら、各作品に目をとおしたとのこと。その中で、タイトルだけで話の内容がわかるキャッチーさ、ならびにキャラクターの強さが『まほなれ』をアニメ化作品として選ぶ決定打になったと語った。有田プロデューサーは、アニメ化を進める中で、キャラクターや魔法の設定に改変を加えたものの、「誰もが経験する挫折から物語が始まり、そこからどう生き抜くかというドライブ感」は変えることなく本作の制作における指針になったと述べた。
これに対し、松根監督は、まず『まほなれ』の世界観の深さに驚かされたと語った。物語設定が年表から始まり、クルミの一世代前からスタートしていたことから、「8クールは必要だ」と感じたという。本作の終了後、「7クールほどでようやく原案の最初のチャプターが終わるほどの重厚さだった」と当時の印象を述懐しつつ、だからこそ、作品の入り口をわかりやすくする方法をと考えながら楽しく原案を読めたと語った。
次に話題となったのがスタッフの間で人気の高いキャラクターについて。松根監督が特に推すのが、第3話から登場するマジック研究会(マジ研)の部長と副部長。実は、この2人がスタッフの中で特に愛されているキャラクターだという。「インタビューするとすごい確率で部長や副部長が好きだと答える」と松根監督は補足した。また、有田プロデューサーは、シリーズ構成・脚本担当の金杉弘子さんも「とにかくマジ研の2人が出るまでは絶対に見ていてください」とインタビューで強調していたというエピソードを紹介しつつ、「セリフが支離滅裂ながら、部長役の杜野まこさんと、副部長役の橘 龍丸さんによるセリフの掛け合いの楽しさだけでずっと見続けてしまう」とその魅力を伝えた。松根監督も「2人がセリフをしゃべり終わると、 アフレコブースからちらって振り返って、『これで合っていますかね?』という表情でこちら見てくるんですよ。もちろん完璧でした。」と笑いながら当時の様子を振り返った。
一方、有田プロデューサーのお気に入りのキャラクターはユズ=エーデルだという。「ユズは非常に人間らしく成長するキャラクターで、彼女の気持ちに感情移入することも多い」と有田氏はその理由を述べた。シリーズの序盤ではクールな印象が強いユズだが、中盤以降は笑顔を見せるシーンや出番も増えていく予定となっておりファンにとっても楽しみな展開である。
この話を受け、松根監督は「当初、脚本を作った時にはユズがここまで重要な役割を担うとは思っていなかった」とユズの変化について語りつつ、「クルミだけだとずっと迷子になりやすく、誰か導いてくれる存在が必要だった」と語った。有田プロデューサーは、「ユズはリーダーシップがありつつ、挫折を経験した人物でもあることから、クルミとユズの対比でファンも物語が追いやすくなる」とユズの存在意義をあらためて強調した。松根監督は「当初、脇役だったキャラクターがあれよあれよという間にスターとなりポスターのキービジュアルにまで採用されるのは新規IPのあるあるだよね」と感慨深げに語った。
TVアニメでは異例の水彩タッチと若手声優起用のこだわり

|
|
▲産学連携の試みとして、トークショーと前後して約1ヵ月、シナリオや絵コンテ、キャラクターデザインや美術設定などの資料が見られる特別展示が実施された |
作品に対してのこだわりポイントについて、有田プロデューサーはキャラクター設定に加え、背景の水彩タッチや画用紙のようなテクスチャをあげた。このような特殊な色彩設定は劇場映画では時折見られる手法だが、シリーズアニメでここまで作り込むのは珍しいとのこと。松根監督も当初はスタッフにこの要望を出すことを躊躇したが、「絵本のような世界観を描く機会がなかなかアニメではなかったこともあり、積極的に取り組んでいただけた」と述べた。
キャスティングに関しては、学園モノらしいフレッシュな雰囲気を出すため若手声優を中心に起用したとのこと。その中でベテラン声優である堀江由衣さんが務めるミナミ=スズキ役と、緑川光さんが務めるノーザン=ハリス役が双方とも先生という役割。その結果、収録現場は、新人の中にベテランが混ざりながらも賑やかにいかにも学園らしい雰囲気に包まれたとのこと。
さらに、クルミ役の菱川花菜さんと、ユズ役の山田美鈴さんが実は養成所時代の同期だったことを、収録が始まってから本人たちから監督に明かされ非常に驚かされたと松根監督は語った。
このように終始なごやかな雰囲気でトークショーは展開された。最後に、アニメ業界を目指す受講生に松根監督は「なりたい職業を考えることも大事だが、やりたいことを考えることも大切」とメッセージを送った。「人生は短いようで長かったりするので、長いスパンでやりたいことを探せば良いと思います。ただ、やりたいことも変わるものなので、一つに絞る必要もないかな」と語り、自身がもともとデザイン会社に就職してからアニメ業界へと転職した経験を振り返った。
一方、有田プロデューサーも自身がIT企業でWeb小説サイト「エブリスタ」のPR担当をしていたことがきっかけでProject ANIMAに関わり、やがてプロデューサーとなった経験を例に挙げつつ「学生の頃は特定の業界を目指して就職活動をするイメージがあるかもしれませんが、 社会人生活はとても長い。実際、偶然のチャンスや人との縁でお仕事がつながっていくことが非常に多いので、何か一つの道を頑なに目指すよりも、チャンスが来た時にいつでも対応できる力を蓄えることが重要」という含蓄あふれるアドバイスでトークショーを締めくくった。
『まほなれ』は毎週金曜日深夜に放送中。まだ未見の読者は是非見てみてほしい。










