中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編
立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!
- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>
- 企画・連載>
- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>
- 【ブログ】トランスメディア・ストーリーテリング:ジ・オリジン(最終章)

中村彰憲
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。
アクセスランキング
新着記事
-
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
-
【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係
-
【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!
-
【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋
-
【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン
-
【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話
-
【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)
-
【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)
-
【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話
-
【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報
連載一覧(すべて見る)
【ブログ】トランスメディア・ストーリーテリング:ジ・オリジン(最終章)
2020-12-29 13:30:00
ハリウッドで、トランスメディア・ストーリーテリングという概念を普及させ、トランスメディアプロデューサー」というクレジットをアメリカ・プロデューサー協会に働きかけ、認めさせた張本人でもあるStarlight Runner Entertainment CEOのジェフ・ゴメス氏(Jeff Gomez)に立命館大学映像学部中村彰憲が直撃。その起源について直接聞いた。
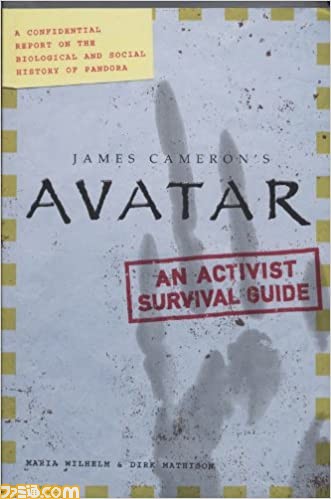
|
|
▲『アバター」プロジェクトのためにゴメス氏率いるStarlight Runnerが作り上げた世界観マニュアルの一部は商品化された(Photo Provided by Jeff Gomez) |
ディズニーから「パイレーツ・オブ・カルビアン」フランチャイズのガイドラインをつくるよう依頼を受け」、ついにハリウッドへ進出
単なるキャンペーンというよりは、玩具を中心としたトランスメディア・ストーリーテリング型(以下、TMS)であった「Hot Wheel World Race Highway 35」プロジェクトは、瞬く間にハリウッド界隈でも話題となった。とりわけ、3DCGアニメも展開されたという点が注目され、同時にこれらをプロデュースする立場であったStarlight Runner Entertainment(以下、SRE)もその名が知られるようになる。このような中、ディズニーの関係者もそのバイブルの存在をしることとなった。そして2005年ごろディズニーマーケティングがSREにコンタクトし、「パイレーツ・オブ・カルビアン」においても、同類の資料集を作れないかとオファーをしてきたのだという。
そこで、「Hot Wheel World Race Highway 35」プロジェクトの際と同様に、これまでディズニーで製作してきた「パイレーツ・オブ・カルビアン」に関わるあらゆる設定資料を提示するように依頼した。だが、ゴメス氏たちの予想に反し、彼らが提供したものは貧弱だったという。世界観の統一感や連続性に関する理解が全く感じられないのが設定素材からも読み取れたのだ。そこで、改めてディズニー側へ、SREチームにディズニーの各拠点を視察させるように依頼し、ホームビデオ事業部、テーマパーク及びリゾート事業部、イタリアのディズニーパブリッシングなどで「パイレーツ・オブ・カルビアン」シリーズに関するあらゆる資料を入手した。そこで、SREは当時のディズニーグループが、IPのフランチャイズ展開をする際、作品世界の統一感や連続性を全く意識していなかった事実を目の当たりにする。
「イタリアのコミックでは、ジャック・スパロウが、レーザー銃でナチスと闘っていたんだ!または、天馬にまたがって戦うとか。その一方で小説部門では、ジャック・スパロウが無実の人を殺すといった話を商品化しようとしていたんだ。「なぜ?」と聞くと彼が海賊で海賊は人を殺すものだからと返答してきたよ。」(ゴメス氏)
このような展開が進めば、確実に「パイレーツ・オブ・カルビアン」シリーズのブランドを傷つけることになると実感したという。
「すぐれたTMSでは、IP、そしてその物語の世界観が最上位にある必要があるんだ。単に権力があるからといって、自分がやりたいことを気分にあわせてやってはならない。まずジャック・スパロウがどのような人物なのかを理解し、その物語における神話体系をリスペクトしなくちゃならない。この世界観にナチスやレーザー銃を入れてしまうと、それは何でもアリな世界観のファンタジーになってしまうんだ」とゴメス氏は強調した。
ただ、「パイレーツ・オブ・カルビアン」シリーズの世界観を把握するのは容易ではない。そこで、SREでは、歴史研究家を招き入れ、劇中に古語の英語で描かれていた海賊の暗号を現代英語に翻訳し、誰もがそれらを使いやすいようにしたり、東インド会社の詳細を解説したりした。それでも課題は残る。ジャック・スパロウだ。そこで、ゴメス氏は独自のネットワークを使い、なんとか、ジョニー・デップ本人とコンタクトをとったのだ。この世界における海賊を理解していたのは、ジョニー・デップしかいないと踏んでいたからだ。
「初日、彼も苦心していたんだ。でも、ジョニーは仕事が終わった後、コスチュームを着たまま、鏡越しに自分を見た。どうやって自分の野蛮性と崇高さで均衡をとれるかを考えるためにね。すると、ジャック・スパロウとしておなじみの、手足を常に動かしながら移動する動き方が自然に生まれていたんだ。バランスをとろうとしていたんだよ」とゴメス氏はインタビュー時の状況を回想回想して、こう続けた。「映画全体を見ても、規律の厳しい大英帝国連隊とデイヴィ・ジョーンズをはじめとした荒々しい自然の統治者や神々、残忍な存在との間に絶妙なバランスがあるのが素晴らしいんだ。この理解を元に世界における均衡関係を神話体系として整理しつつ、ジャック・スパロウが如何なるカオスにいても野蛮性と崇高さの間で均衡を保つことで生き残る存在であるという設定として整理したのさ。」(ゴメス氏)
また、ゴメス氏は、IPのマルチ・プラットフォーム展開をするために必要な条件を整えそれを契約へと落とし込む作業をしたという。これまでは、 例えば、ジャック・スパロウの意匠を活用した物販を作るのであれば、それを演じたジョニー・デップ側から許諾が必要になり、役者によってはその許諾を得るのにかかる時間がまちまちとなっていたからだ。
「いまはこれをトランスメディア・クリアリングハウス(Transmedia Clearing House)と言うのさ。その頃、ディズニーでは「パイレーツ・タスクフォース(Pirates Taskforce」と呼んでいたけどね。」(ゴメス氏)
ディズニーテーマパークがこれまでに提供してきたライド、「カリブの海賊」に対しても如何なるメタ・ナラティブ(大きな物語)を付加出来るか相談を受けたゴメス氏は、このライドが、シリーズのどの時間軸に位置づけられるか各要素を確認し、前日譚であると整理した。これを受けて、あらためてシリーズ全体のテーマである「野蛮性と崇高さの均衡」を意識しつつアイデアを統合していったという。この「カリブの海賊」アトラクションをリ・デザインをするうえでは、自身のTRPGでの経験が活かされた。観客が様々な要素から物語体験を得るという参加型の特性があるからだ。ただ、自身のアイデアを実装するうえでは、テーマパークでのプロダクション過程も修得しなければならなかったという。「ディズニーのイマージニアリングチームとともにディズニー内で開講している講座をとって、やっと何をしてもらいたいかを伝えられるようになった」とゴメス氏は当時の苦労について語った。
この他、ディズニークルーズでパイレーツナイツも任されたという。このイベントでは、クルーズ内で皆が仮装をし、4DX的効果のある特別シアター内で作品を鑑賞するのだ。この他、ディズニーグループは、「ディズニーフェアリーズ」や「トロン: レガシー」でもTMSプロジェクトを展開したという。これら、ゴメス氏のディズニーグループに対する貢献について聞いたところ、
「メディア・フランチャイズにおける統合性と、正史を合致させること(canonicity)、つまり物語としての統一性、そしてこれらを実現するために複数の部局と協調、協力を実現するために何をすべきかをノウハウとして蓄積出来たのは私たちとのプロジェクトが始まりだと思っている」
とSREの果たした役割をゴメス氏は誇らしげに答えた。更に契約などの手続きなどにおいて、「パイレーツ・オブ・カルビアン」シリーズで構築した手法も重要だったであろうと分析している。ゴメス氏によれば、この際、契約内容を従来よりも監督、主要演者ならびに担当プロデューサーの権限を限定的とし、エグザクティブプロデューサーの権限を高めたのだ。契約上、必要であれば監督や演者を解雇することも出来るようにした。これで、作品どうしの間テクスト性(intertextuality)を妨げるような演者や監督のエゴからIPを守ることが出来る。つまり、個人が追求する作家性や芸術性の上位にIPを据えることが出来る。
「もちろん、監督や、脚本家、演者はとてつもない才能をもっている。だが、企業が所有しているのは数十億ドルの価値がある知的財産だ。如何に優れた才能であってもサードパーティまたはフリーランスである人たちにその権利を手渡し、好きなようにやってくれ、という会社は他の産業には無いんだ。」(ゴメス氏)
『Avatar』プロジェクトでは、ジェームス・キャメロン監督と意気投合
「パイレーツ・オブ・カルビアン」シリーズを手がけたことで、ゴメス氏率いるSREの仕事は業界に伝わっていた。制作したバイブル、「パイレーツ・オブ・カルビアン・バイブル(Pirates of the Caribbean Mythology)」は300ページにも及ぶ。革製表紙の中心に骸骨を据えた豪華ものだ。そのようなこともあり、次は、このバイブルを偶然目にした20世紀フォックスのエグザクティブが連絡してきた。オーダーは「ジェームス・キャメロンが『Avatar』の制作過程で生み出した資料や膨大な設定をバイブルにしてほしい」というもの。制作にあたっていたLighting Stormスタジオにてプリビジュアル関連の素材などを見せてもらった当日、ジェームス・キャメロン監督自らがその場にあらわれた。そこでゴメス氏がキャメロン監督作品に対する愛や、『Avatar』作品の世界観の緻密さなどを伝えたところ、その場でバイブル制作についてゴーサインを得た。これについては「もうその日から仕事がはじまったんだ。これまでの仕事で最速だったね!」とゴメス氏。以降は、SREスタッフが撮影現場に入り込み、とりわけ、ナヴィ族の文化背景について注意深く分析を進めたという。彼らが存在する背景、「あなたが見える」( I see you)といった慣用句に隠れるナヴィ哲学、そしてこれらがキャメロン監督のメッセージとどう関係しているのかなどを調べ上げ、そこから、神話体系をつくりあげたという。ただ、ここで、TMSを展開するうえで障害が生まれてしまった。それはなんと、当時の20世紀フォックスCEO自身。
「彼は信じなかったんだ。つまり他のメディアで作られる「Avatar」ワールドの拡張に関する費用はライセンシーが支払うべきで、ライセンサーである20世紀フォックス側が払うものでないと主張したのさ。」(ゴメス氏)
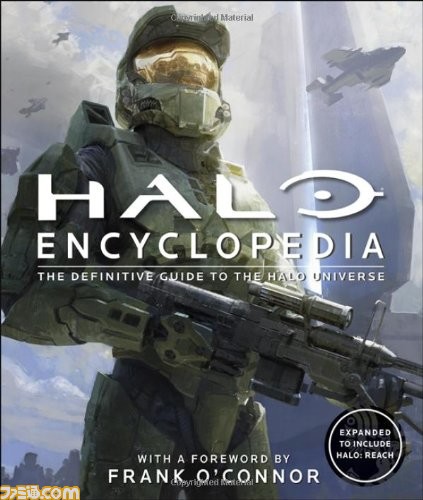
|
|
▲「Halo」シリーズはゴメス氏が関わったプロジェクトの中で最もTMSが成功したプロジェクトだという。ただすべてがスムーズに展開されるわけではない |
20世紀フォックスのCEOは、ゴメス氏のチームが提案した、「キャメロン氏監修のもと、SREとともにインハウスで「Avatar」ワールドを創り上げ、それをベースに「Avatar」関連コンテンツの他メディア化権をサードパーティに授与するという案」を退けた。結果的に、ゲームは、映画の前日譚として開発され、人間側とナヴィ族側の双方がプレイ可能となったと同時に、ゴメス氏たちが作り出したバイブルをもとにした、パンドラペディアという惑星パンドラに関するデータベースも挿入され、同様のコンテンツが公式ウェブサイトにも展開するといったTMS的展開が行われたが、ゴメス氏のチームが関わることが無く開発が進められている。ゲームは全世界で270万本を売ったものの、ゲームそのもの評価が低くなっていた(※)。だが、続編の展開が明確になった2016年からは、公式ホームページが刷新され、そこにはPandora Research Foundationという世界観の延長戦に実在する架空組織のサイトをつくりあげ、惑星パンドラや、生態系ならびにナヴィ文化やその行動様式について詳細が示された。つまり、続編の制作と同時にパンドラユニバースの情報をユーザーにコミュニケーションするチャンネルがデザインされたことを意味しており、結果的にゴメス氏の提案を間接的に採用したことになる。ただ、ゴメス氏は自分たちが第1作目の段階で積極的に関わることが出来なかったことに対していまでも悔いを残しているようだ。「第1作目の際に本格的に展開すればユーザー側の満たされていなかった巨大な需要をがっちりと満たすことが出来ただろう。」とゴメス氏は分析する。
2000ページにも及ぶバイブルで10年ものコンテンツ展開を構想した「HALO(ヘイロー)」シリーズ
その後、ゴメス氏は、マイケル・ベイ監督による「トランスフォーマー」プロジェクトなどのハリウッドプロジェクトをはじめ、多様なコンテンツのTMS展開について包括的、または部分的に関わりながら、自身が携わったプロジェクトの中で最も理想的に展開が出来た例として「HALO(ヘイロー)」シリーズをあげた。2007年から2010年までの3年間、マイクロソフトゲームスタジオ(当時、現Xbox Game Studio、以下、MSG)から依頼を受けて、コンテンツ展開におけるメタナラティブ(大きな物語)の構築及び展開上の戦略立案を担当したのだ。その結果、「HALO(ヘイロー)」シリーズのために作り上げた「Halo(ヘイロー)」(以下、『Halo』)のバイブルは2000ページにも及んだという。内容は宇宙観、マスターチーフやその他、すべての主要キャラクター、登場拠点、クリーチャー、宇宙船、武器、デバイス、空想科学技術、形而上学、異星人の信仰体系、歴史、そして物語案等、詳細設定を網羅している(※)。また、SREはこのバイブルをベースにしつつ『Halo Reach』から『Halo Infinite』ならびに新型コロナの影響で遅れているテレビシリーズまで10年にも及ぶコンテンツ展開についても提案した。これに対し、MSG参加の343 Industriesは、トランスメディアプロデューサーを任命し、以降、若干の変更があったものの、概ね計画通りコンテンツ展開が進められたという。また、期間中、継続的にユーザーとのコミュニケーションチャンネル、Halo Waypointを運営している点も高く評価した。
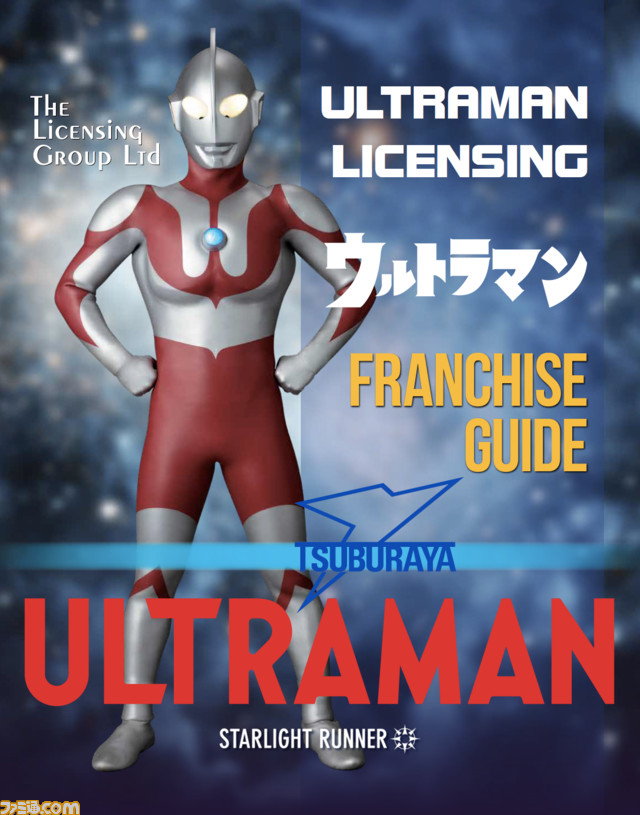
|
|
▲Starlight Runner社の最近のプロジェクトは「ウルトラマン」シリーズの北米展開だ。(Photo Provided by Jeff Gomez) |
現在、SREは「ウルトラマン」シリーズの北米展開におけるTMSプロジェクトに関わっている。本来「ウルトラマン」はシリーズ間の整合性などにとらわれていない一般的なメディアミックスだが、SREは「ウルトラマン」の宇宙観や哲学を体系化したうえでこれらを北米ユーザーに伝えつつ、ウェブ、アメリカンコミックならびに過去映像資料を体系化しながら、TMSとしてリ・イマジネーションを開始したばかりだ。また、こういった経験を踏まえ、効果的なTMS展開に関し、ゴメス氏は以下のように結論づけた。
「TMSを効果的に実行するうえでは、それぞれを展開するプラットフォームにおける物語の制作過程を熟知するのに加え、これらのプラットフォームとユーザーが如何に関わっているかについても理解しなければならない。例えばモバイルであれば、ユーザーと密接につながっており、さらにカスタマイズが出来る機能が備わっている。従って、携帯向けに物語をデザインする際、物語展開における要素として、「ユーザーとの密接な関係」を活用する必要がある。コミックであれば、そのビジュアルデザインを繊細に表現できるという特徴を活かし、劇場用映画やテレビなどで表現するには高コストになってしまうような画面を多くつくりあげるといった具合だ。劇場用映画の場合、全フランチャイズを次の展開へと持っていくのに適している。そこで起きるイベントも金字塔的なものである必要があるでしょう。」
また、これから注目するべきメディアプラットフォームとして、動画配信サービスとオーディオ(音響)をあげた。動画配信で展開されるコンテンツこそが次世代のTMSにおいて最も収益を生み出す可能性があり、オーディオプラットフォームは新技術により、これまで以上の没入感を生み出しているのと同意に、ユーザーの声に反応し、音声もインタラクティブに反応する技術が発達しているからだという。
また、経営的視点からTMSを成功させるうえで受容なのは、如何にトップダウンでクリエイティブな判断が出来るかだとゴメス氏は語る。また、ユーザー参加はTMSデザインに重要な役割をこれまでも果たしており、前述のようなオーディオプラットフォームの台頭はユーザー参加の重要性をさらに高めると予測しつつも、現在、ユーザー参加を阻害するマネジメントが多いことに苦言を呈した。これらを踏まえ、スタジオとファンのコミュニケーションを奨励しつつ、強力なリーダーシップを発揮し、短期的な利益還元やクリエイターや役者のエゴから隔離したより上位的存在として明確にIPを据え、そのビジョンに対して忠実に関係者を束ねることが出来る人たちのみが成功出来ると主張した。
最後に、日本のIPホルダーのトップ層に是非、TMSについて理解をしてもらいたいと主張し、以下のように締めくくった。
「あるIPに関する映画が出て、顧客が次の展開を単に待つという図式は、IPの潜在性を効果的に発揮しているとは言えません。これほどもったいないことないでしょう。私自身日本製IPのファンですが、だいたい一つの作品が出ると、あとは数年間待たなければならないのです。個人的には、東映のキカイダーや仮面ライダーの世界観を北米ファン層がハマる形で展開出来たらうれしいですね」
動画配信サービスの台頭とともに日本製アニメをはじめとしたIPが注目されはじめた現在、これらのIPがMCUやスターウォーズ並みに欧米圏で熱狂的に受け入れられるうえで、ゴメス氏のTMSに関する知識や、ハリウッドとの経験ならびにノウハウが活かされるときが近いうちに来るかもしれない。
※インタビュー実施日 2020年10月30日










