中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編
立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!
- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>
- 企画・連載>
- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>
- 【ブログ】akinakiのJust Watched『メアリと魔女の花』に見る、師から離れるということ

中村彰憲
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。
アクセスランキング
新着記事
-
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
-
【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係
-
【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!
-
【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋
-
【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン
-
【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話
-
【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)
-
【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)
-
【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話
-
【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報
連載一覧(すべて見る)
【ブログ】akinakiのJust Watched『メアリと魔女の花』に見る、師から離れるということ
2017-06-23 18:30:00
今回、筆者は恵まれて、『メアリと魔女の花』の試写会に当選し、同作を見るチャンスを得た。『メアリと魔女の花』は、『借りぐらしのアリエッティ』(以下、『アリエッティ』)、『思い出のマーニー』(以下、『マーニー』)を経た米林宏昌監督による劇場用アニメ3作目にして、同氏が、おなじくジブリ時代、『マーニー』の担当プロデューサーとして、ともにしてきた西村義明氏が創立したスタジオポノックの1作目作品。
声の出演に、若手の実力派俳優である杉咲花、神木隆之介ならびに 満島ひかりを揃えるとともに、演技派俳優、小日向文世にとって初となる声優役をオファーしたり、主題歌にSEKAI NO OWARIを起用したりするなど実力や話題性ともに最強の布陣で挑んだ渾身の一作と言える。
しかして、鑑賞後の率直な感想だが、『メアリと魔女の花』はジブリ的な作品としての面白さの醍醐味をみごとに継承し、且つ同系列作品としても、『風立ちぬ』、『かぐや姫の物語』、『思い出のマーニー』と続いた中で、久々にクライマックスにおいてカタルシスを感じさせる、手に汗握る冒険譚であることから、文字通り老若男女誰もが楽しめる快作となった。

|
|
試写会チケット |
『メアリと魔女の花』は文句なく万人に薦められる作品に
『メアリと魔女の花』は、田舎町に引っ越してきた少女・メアリが、森で7年に1度しか咲かない花「夜間飛行」をその手にすることで魔法の力を獲得することをきっかけに、魔法世界の最高学府「エンドア大学」への入学を許可されるも、そこでのトラブルが世界の命運すらかけた一大事件へと発展するという冒険譚。
なお、キービジュアルではメアリが前面に押し出されており、物語の主軸が「魔女」であることから女性向けと勘違いされる人も多いと聞くが、鑑賞して感じたのは、本作はメアリとピーターによるダブル主演であり、『魔女の宅急便』というよりはむしろ、『天空の城ラピュタ』に近いことから、男女双方が楽しめる作品となっている。
このようなあらすじからも明らかな通り、本作はスタジオポノックとしての独自色を出そうとした作品というよりは、むしろこれまでの米林監督がジブリで学んできたことを全て出し切った、米林監督にとっての集大成的作品と言える。
これらを踏まえ、改めてジブリ時代の米林作品を振り返ってみると、むしろそれらの作品のほうが本作よりも米林監督としての独自色を打ち出そうと必死になっていたと思えてくる。
例えば、『アリエッティ』の場合、小人世界といったファンタジー色溢れる世界を舞台にしているのにも関わらず、敢えて劇的な展開は抑え、日常劇的な表現に終始した印象を与える。また『マーニー』では、思春期にありがちな恋愛的状況を封印し、その時期において女の子が女性へと変化しつつある心の揺れに焦点を当てた、いずれにおいても「宮崎+α」を狙おうとしている作り手の心情が垣間見える。
「ジブリ的」というものが作家性や企業ブランドから、 アニメ表現の一つのパラダイムへと昇華したとき
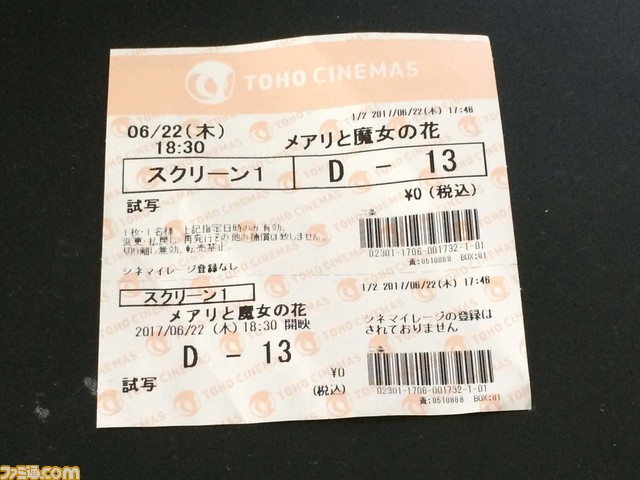
|
|
試写会のチケットは試写、0円となることをはじめて知った |
だが、今回は、ある意味で「奇をてらう必要もなければ」「奇をてらう余裕もない背水の陣」といった状況である。とにかくジブリ時代に学んだ全て(その世界観づくりからストーリーテリングまで)を完全投入する必要があった。
しかして、それは作品全編にわたり見事に表れていた。既にメディアなどで報じられていた、米林監督が得意としていたダイナミックな動画表現はもとより、これまでの同監督作品では欠如していた宮崎監督作品のお家芸であるクライマックスにおけるカタルシスや、テクノロジーと魔法が融合したような摩訶不思議で緻密な世界観がきっちりと描かれている。もっとも『メアリと魔女の花』という原作自体が、こういったジブリで得た経験をすべて表現できると踏んでの選択であったともいえる。
つまり宮崎駿氏、高畑勲氏、そして小田部羊一氏ともに東映動画と袂を分かち、『長くつ下のピッピ』から『アルプスの少女ハイジ』、『未来少年コナン』、『ルパン三世 カリオストロの城』そして『名探偵ホームズ』と、ジャンルは多岐にわたるものの、これらの物語表現において築き上げてきた一貫した表現での方向性(同時にそれがファンに対する訴求ポイントとも言えるが)を正確に表現することが出来たと言える。かくして、その表現はひとつの会社の色やブランドといった枠をこえ、一つのパラダイムへといきついたのだ。つまり伝統工芸品における「〇〇派」といったものに近いものの誕生である。
ジブリズムの中にわずかに見え隠れした米林監督の作家性

|
だが、同時に米林監督の色も出ているのは間違いないだろう。まずは全編をとおして、意識されたと感じられたのは若年層が好む原色に対するリスペクトとも言えるような色使いだ。乱闘や戦闘シーン、爆発など様々なシーンであっても、モブシーン(動物たちによる群衆シーンなども含む)では、原色が多用されそこに「色のくすみ」といったものは見られない。洋館や、田畑などの背景もよりリアルなデザインとなっており、その点にいては、従来の宮崎監督らが追及した「丸み」は失われた。
ただこれは、これまで米林監督が一貫してつらぬいてきた表現方法であることから、これらがむしろ 監督としての「色」なのかもしれない。
つまり、「動画としての躍動感」、「血湧き肉躍る冒険譚」「小さな世界から大きな世界へと踏み込んだときの心情の変化に対する繊細な表現」といったジブリ的要素を物語表現に盛り込みながらも、監督の作家性も維持したこととなる。
いずれにしても、『メアリと魔女の花』において、スタジオポノックは、自らがジブリの価値観や物語表現をたしかに継承したという点を世に示すことが出来た。だが注目すべきはこれからだろう。ここでの実績や成功を基盤に、これからは如何に「ジブリズム」ともいえる物語表現を維持しつつ、米林監督ならびにスタジオとして「色」を発展させていくのかという点だ。まずは、『メアリと魔女の花』を素直に賞賛しつつ、さっそく今から同スタジオ及び米林監督の次の作品に期待を寄せたい。










