中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編
立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!
- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>
- 企画・連載>
- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>
- 【ブログ】2016年は「ゲーム新時代の到来」

中村彰憲
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。立命館大学ゲーム研究センター長、日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 、東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザーなどを歴任。おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』がある。
アクセスランキング
新着記事
-
【ブログ】TVアニメ『まほなれ』制作陣が未来のクリエイターに語った新規IP作品制作のいろは
-
【ブログ】「Replaying Japan 2024」ヨコオタロウ氏基調講演 ヒット作『NieR:Automata』に見る「AI融合社会」と「人間性の本質」の危うい相関関係
-
【ブログ】【ChinaJoy 2024】開催まであと1週間弱!ChinaJoyの見どころを勝手に推測!
-
【ブログ】『Stellar Blade』の高評価から読み解く、新規IPに仕掛けられたシリーズ化への処方箋
-
【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン
-
【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話
-
【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)
-
【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)
-
【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話
-
【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報
連載一覧(すべて見る)
【ブログ】2016年は「ゲーム新時代の到来」
2016-01-15 16:30:00
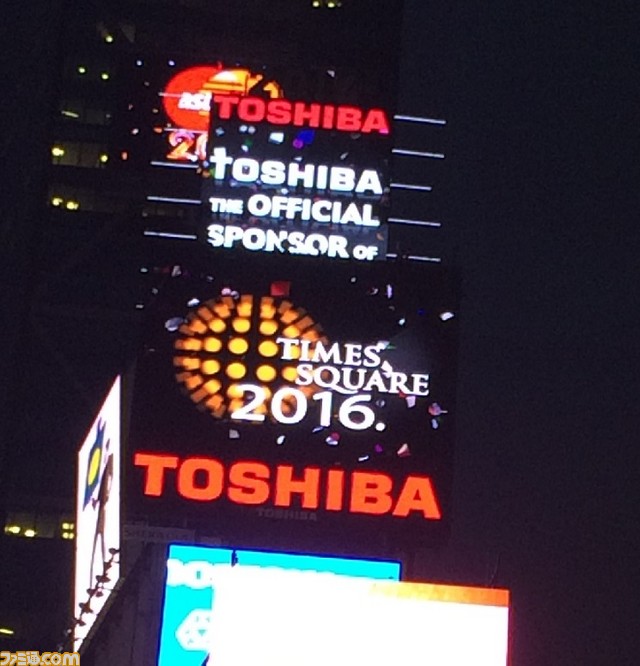
|
|
▲今年はタイムズスクエアのNew Year's Eveに行ってきた。ここでの体験はまさに2016年のゲームシーンを象徴するものである。 |
2015年のゲームシーンは、『Splatoon(スプラトゥーン)』、『METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN』、『Bloodborne(ブラッドボーン)』、『スーパーマリオメーカー』などが欧米にてその優れたゲーム・デザインが高く評価され、日本人ゲーム開発者の「ゲーム・デザイン」や「重厚なストーリーテリングの中に新たなゲーム・デザインをシームレスに統合させる力」に対する鋭い感性があらためて再認識された年であった。
また、リメイク版『FINAL FANTASY VII』の開発が現行機向けで進んでいることや、『シェンムーIII』がKickstarterで募集開始後、約8時間で目標金額の200万ドルを達成し、その後の追加募集もあわせ650万ドルに到達するなど、久々に日本からのゲームが世界のメディアを大きく沸かすことがかなった一年でもある。
というわけで例年に引き続き今年のゲームシーンを「占って」みた。
トランス・メディア・ストーリーテリングを前提としたゲーム企画の躍進
「トランス・メディア・ストーリーテリング」とは、ひとつの「世界観(Universe)」を共有し、複数の物語を語ることを言う。従ってこのような物語体系を企画する場合、あるひとつの「世界観(Universe)」、すなわちそこに存在するキャラクター、テクノロジー、社会、政治形態といったあらゆるものから、今後新たに企画するすべてのキャラクター、テクノロジー、社会的変容が首尾一貫して継続性があるようにデザインする必要がある。

|
|
▲ニューヨークのIMAXシアターは、大晦日にも関わらず朝8時45分の上映回に長蛇の列が |
これを商業的にかつてない規模で目下成功させているのが『スター・ウォーズ』シリーズである。『スター・ウォーズ』シリーズはLucas Artsがディズニーの傘下に入る前から既に「拡張世界」(欧米では文字通りこれらをExpanded Universeとしている)が展開されてきたが、小説、ゲーム、コミックなどで統一感がなかったりという状況があった。これは、作品の人気とライセンスビジネスという形で五月雨式に生まれてきたコンテンツなので仕方がないとも言えよう。
だがディズニーは旧6作の劇場用映画とアニメ及び3DCGアニメ『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』シリーズならびに現在放送中の3DCG『スター・ウォーズ 反乱者たち』(これらをキャサリン・ケネディらは「Canon(正典)」と呼んでいる)以外は一旦ご破算にして(レジェンドとして扱われることになる)、『スター・ウォーズ』の世界観を再構築しているのだ。現在小説、コミック(もちろん、今回はディズニー傘下のマーベルから発売している)などインタラクティブでないものはこの世界に忠実に、ゲームのようにインタラクティブなものは、これまでの作品の追体験型と新たな物語体験をうまく組み合わせてデザインされている。つまり各メディアの特性とプロジェクトの規模に最適化した物語をユーザーに提供するべくコンテンツのラインナップを整えているのだ。
国内では『.hack』シリーズもトランス・メディア・ストーリーテリングを進めてきた
このように企画段階から意識して実行しているトランス・メディア・ストーリーテリングは、欧米では『マトリックス』三部作、国内では『.hack』シリーズがおこなってきているが、ここまでの規模で脚本段階から新たに作り起こすというのは、見られなかった。「Marvel Cinematic Universe」は、映画においては統一された世界の中で存在するが、コミック、アニメとは独立した世界観になっている。また、『機動戦士ガンダム』シリーズも一部においては、トランス・メディア・ストーリーテリングを成立させつつも、コンテンツ群全体としてはそこまで厳格に世界観が統一されていない。これは従来の『スター・ウォーズ』シリーズと同様に、世界観が後々作り込まれてきたという点と関係している。
ただ、トランス・メディア・ストーリーテリングが多くの人たちを熱狂させてしまう「事業モデルの一形態」になりうることが明らかになった以上、「物語」を生業にしている企業やスタジオがこれにチャレンジしないことは考えられない。従って、今後、こういった取組が行われる、または『スター・ウォーズ』のようにリブートが行われる場合は、企画段階から周到に準備し展開するものが増え、その中核にゲームが存在するようになるのが2016年なのだ。
イマージョンからエモーションへ

|
|
▲「玩具」専門店トイザらスのタイムズスクエア店が2015年12月30日に閉店したのも象徴的だ |
「トランス・メディア」に加え、大きな潮流となりそうなのが、「イマージョン」から「エモーション」への転換となる。
以下解説しよう。
オキュラス社によるRiftの予約がはじまり、PlayStation VR、HTC Vive などの最新バージョンが、最近開催されたCESで展示されるなど、高価でありながらもVR体験は2016年、たとえ一部の消費者にしかとどかなかったとしても何らかの形で多くの人たちに伝わってくる年になるだろう。
だがここで重要なのはVR体験でのImmersion(没入感)ではなくEmotional Involvement-つまり「感情移入」が体験を評価するうえでの鍵になるということだ。つまり、「没入感」はあくまでもつかみでしかなく結局、人をコンテンツに惹きつけるのは、何らかの形でそこから「感情移入」が出来る体験があるかないかということになる。
この評価軸は、VR体験をした多くのジャーナリストも言及しつつあると同時に現行機の大作を評価するうえでも起きつつあるというのが筆者の印象だ。一部の人たちが熱狂的に支持している『Ingress』もその世界に「感情移入」が出来たか否かが鍵となっていた。そしてこの傾向がより顕著に表れるのが2016年ということだ。
元旦、筆者は、ニューヨーク市のタイムズスクエアにいた。
100万人以上が訪れ日本の早朝の地下鉄以上の混雑の中、立ちっぱなしで16時から8時間。終了後の混乱もひどく結局ホテルに戻ることが出来ず、8th Aveのカフェやレストランをはしごした。だがそれでもたった数分のスペクタクルのために待ち続ける価値があったと確信している(学生時代にやるべきだったとは真摯に思ったが)。それがまさに「Emotional Involvement」なのだと思う。我をも忘れる体験をデザインできる企業がこれからの市場を制覇することになるだろう。










