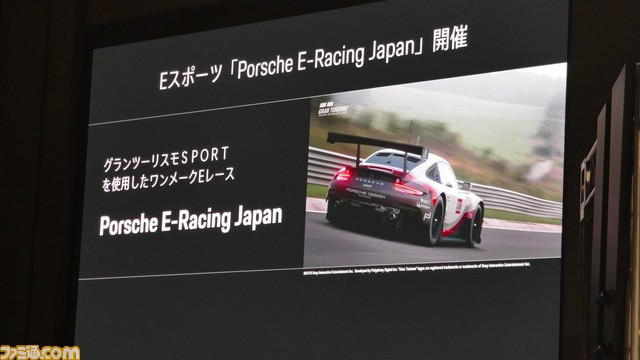『グランツーリスモSPORT』を通して見る“eモータースポーツ”の未来図
昨年実施された国際自動車連盟(FIA)公認の“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”を皮切りに、今年もさまざまな“eモータースポーツ”に取り組んでいく『グランツーリスモSPORT』(以下、『GT SPORT』)。同イベントのマニュファクチャラーシリーズ初代チャンピオンとなったチーム・レクサスのドライバー、川上奏選手のインタビューも交えながら、“eモータースポーツ”の未来を考察していく。
2018年は(日本国内での)eスポーツ元年とうたわれたように、全国各地でさまざまなタイトルを用いた大会が行われるようになってきている。そんなeスポーツブームの潮流とタイミングを合わせるかのように、“eモータースポーツ”というジャンルも近年、盛り上がりを見せてきていることをご存じだろうか。
リアルドライビングシミュレーター『グランツーリスモ』がかねてより標榜していた“ドライビングプレジャー”のひとつとも言える、モータースポーツ。2017年10月19日に登場したプレイステーション4用ソフト『GT SPORT』は、“eモータースポーツ”というジャンルを打ち立て、人車一体の新たなステージを打ち出してきた。
前述のとおり、昨年は“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”を実施し、ワールドファイナルをモナコで開催。この世界大会の優勝者は、12月に行われたFIA授賞式(FIA Prize-Giving Ceremony)で、同じくFIAが統括するF1(Formula1世界選手権)やWRC(世界ラリー選手権)のチャンピオンらとともに表彰されるという偉業を達成した。
モータースポーツとは、エンジンやモーターといった動力源を持つ乗り物を人間が操り、速さを争う競技で、自動車の誕生とともに進化・発展を続けてきた伝統ある“スポーツ”である。その種類は使用する車種やレギュレーション、走行フィールドなどによってさまざまなカテゴリーが存在しているが、2018年はドライビングシミュレーター『GT SPORT』を用いた“e-モータースポーツ”が、新たにその仲間に加わった瞬間と言えるだろう。
人間が戦うからこそ生まれる、筋書きのないドラマがここにある
一部の人の中には、「モータースポーツって、スポーツなの?」という疑問を持つ人もいるだろう。そういった人は「ただクルマに乗って走っているだけで、結果はクルマの性能次第でしょ」といったイメージを持っている人がいるかもしれない。しかし、クルマ(あるいはバイクなど)といった道具を使うとはいえ、そういった要素はあくまでも副産物でしかなく、本質は人間同士の極限の戦いそのもの=スポーツなのである。
これは、近年ますます関心度が高まっているeスポーツにも共通しているテーマとも言えるが、スポーツ=人間同士が持てる能力のすべてを発揮する競技として捉えれば、どちらも立派なスポーツに違いないはずだ。さらに言うと、『GT SPORT』が取り組んでいる“eモータースポーツ”は、その特徴として“リアルとバーチャルの垣根の低さ”というものがあることを知っておいてもらいたい。
たとえば、格闘ゲームのプレイヤーと格闘家に共通する部分を考えると、動体視力や反応速度、闘志といったものが考えられるが、勝負に必要なスキルやトレーニング法はまったくの別モノであることは容易に想像できるだろう。だが、モータースポーツに関して言えば、バーチャルでのドライビング技術は本物のドライビングと遜色ないテクニックが求められることになる。
また、近年は実際のマシン開発にも高度なレーシングシミュレーターが導入されており、その精度の高さからドライバーのトレーニングやマシンセッティング目的にも利用されているのは最早当たり前のことになっている。さらにバーチャルドライバーをリアルレーサーにする育成プロジェクト“GTアカデミー”出身のドライバーが実車レースで優勝したり、後述するブラジル人ドライバー、イゴール・フラガ選手のように、リアルとバーチャルの世界の両方で活躍を見せるドライバーも進出してくるなど、その垣根はほぼ無きに等しいといっても差し支えないほどのところまできているのだ。
“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”の世界チャンピオンに、『GT』の取り組みを聞く
そんな“eモータースポーツ”の最前線で戦い、見事“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”マニュファクチャラーシリーズの初代チャンピオンとなった川上奏選手に、これまでの『GT』歴や大会に挑んでみての感想、今後の展望などお話を伺ってみた。
※本インタビューは2019年3月に実施したものになります。
川上奏
『GT SPORT』の非公式大会や、数々のレースでは“Kawakana222”名義でも出場し、多くの好成績を収めてきた選手。2019年4月より自動車会社に就職されるとのことで、これからは社会人としてどのように“eモータースポーツ”に取り組んでいくのか。今後の活躍が期待される。
――『GT』はいつ頃から始めたのか、教えてください。
川上父がクルマ好きで、初代『GT』から遊んでいたそうですが、その影響で小学校に入る少し前から『グランツーリスモ3 A-Spec』(プレイステーション2)で遊んでいました。その後のシリーズも新作が出る度にプレイしていましたが、本格的にやり込み出したのは『GT SPORT』からになります。
――『GT』をプレイするときは、どのくらいの時間走っているんですか?
川上新しい作品が出たばかりのときは、何時間も遊び続けていましたが、普段は1日1〜2時間走るかどうかでした。でも、『GT SPORT』が出た当時は大学生になっており、時間的なやりくりも自分でできるようになっていたので、帰宅してから毎日3〜4時間、走り込んでいました。
――『GT』で走りを覚えていったと思いますが、本物のモータースポーツには興味は持っていますか?
川上クローズドコースでの走行はカート経験くらいしかありませんが、クルマを走らせることは大好きです。また、小さい頃からF1観戦に連れて行ってもらっていたので、モータースポーツを見るのも好きですね。
――F1好きということですが、どのドライバーが好きなんですか?
川上もう引退してしまいましたが、フェリペ・マッサというブラジル人ドライバーです。2008年にあと一歩のところでワールドチャンピオンを逃しているんですが、いつかチャンピオンになってもらいたいと思って、ずっと応援していました。最終的にタイトル獲得はできませんでしたが、記憶に残るドライバーだったと思います。
――2008年に、そのマッサからタイトルを奪い取ったのがルイス・ハミルトン選手でしたよね。ハミルトン選手には、モナコでの“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018 ワールドファイナル”と、ロシアで行われた“2018年FIA授賞式”でお会いされていますが、どのように感じましたか?
川上強くて速くて隙がない、どこを取ってみても一流のドライバーですよね。そんな雲の上の存在のような人を間近で見て、さらにいっしょに写真を撮ってもらえるなんて、言葉では言い表せない想いです。
――今度は“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018 ワールドファイナル”のときの話を聞かせてください。マニュファクチャラーシリーズのチームは日・米・欧の合同チームでしたが、コミュニケーションはどう取られていたのでしょう。
川上基本的に英語でのやり取りで、チームメイトが話していることはなんとなく理解できるのですが、自分はあまり英語が得意ではないため、こちらから意見を伝えるときにはスマホの翻訳機能を利用しました(笑)。ですので、戦略面は主にふたりに考えてもらい、あとはその指示に従って自分の役割をこなすことに集中するように心掛けていました。
――レースではスターターを務めることになりましたね。2番手という好位置からのスタートでしたが、プレッシャーは感じましたか?
川上スターティングポジションの前後が走り慣れている日本人選手だったこともあり、また本戦に向けてかなり練習もしてきたので、思ったほど緊張はしませんでしたね。
――オープニングラップ、ニュルブルクリンクのGPコースでトップに立ったのは狙い通り?
川上(ポールポジションはミディアムタイヤ、自分はソフトタイヤでスタートという)タイヤの違いがあるから早めに抜こうと決めていました。GPコースの中で抜かないと後々厳しくなるというのはわかっていたので、どこかで仕掛けようというのは頭に入れていましたが、うまくいってよかったです。
――レース中は、海外の選手ともバトルがありました。日本人選手と海外選手の走りの違いは感じましたか?
川上海外選手の方たちは攻めるときも守るときもかなり積極的な走りをしてくるので、そこは日本人選手と少し違うかなと思いました。こういった走りのスタイルの違いは文化の違いによるものかもしれませんね。でも、日本人選手でも積極的な選手はいますし、そこまで大きな違いはないと思っています。
――実際にレースが終わり、表彰台の真ん中に立ったとき、どんな気持ちでした? 優勝の実感はすぐに湧いてきた?
川上いや、すぐには湧いてきませんでした。レースが始まる前はまさか勝てるなんて思ってもいませんでしたから。レース後は初めての世界大会の場で勝てたという驚きとうれしい気持ちが混ざり合っていて、気持ちの整理がついたのは表彰式が終わって部屋に帰ってからです。部屋でトロフィーを眺めて「本当に勝ったんだな」って(笑)。
――チャンピオンになって、何か変化はありましたか?
川上大きく生活が変わったということはありませんが、海外のプレイヤーと接する機会が増えましたね。また、通っていた大学でもeスポーツに興味を持ってもらったようで、学校から取材を受けたり、周りの友だちも見てくれていたりと、細かな部分では変わってきた感じはしています。
――両親は今回の活躍を見て、どのような反応をしていましたか?
川上昔からゲームを遊ぶことにたいしては寛容でしたので、『GT SPORT』でオンラインシーズンに挑戦していることは知っているようでしたが、まさか世界大会に出場するほどとは思っていなかったようです。昨年の10月頃、「モナコの世界大会に行けそうだ」って話をしたときは驚いていました(笑)。
――その後の12月にはFIAが管轄する各カテゴリーのチャンピオンを表彰する“2018年FIA表彰式”に出席するため、ロシアのサンクトペテルブルクに行くことになりましたね。こちらの雰囲気はいかがでしたか?
川上まさに、夢のような時間でした。周りはリアルなレースで活躍している、世界的に有名なドライバーたちばかりでしたが、その中でバーチャルレースのドライバーとして同じ場に立てたということは光栄であるとともに、新しい時代の一歩を築けたのではないかと思っています。
――そんな余韻を感じてるいままさに、新たに2019年のシーズンがスタートします。今年の大会にも挑戦されますか。
川上当然、そう思っています。チャンピオンとして少なからずのプレッシャーは感じていますが、それに打ち勝ってこそだとも思っているので、がんばりたいです。
――今年開催される茨城国体(※)は、出場は考えていますか?
※……第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」文化プログラム“全国都道府県対抗eスポーツ選手権『グランツーリスモSPORT』”
川上この春より就職で愛知県に引っ越しすることになるので、愛知代表を目指してがんばりたいと思います。
――『GT SPORT』では頂点に立つことができましたが、今後リアルなモータースポーツに挑みたいという考えはありますか?
川上年齢がもう少し若かったら、どこかのプロチームの門戸を叩いてみるという道もあったかもしれませんが、いまは就職先も決まっているので、リアルなモータースポーツの世界に足を踏み入れるということはとくに考えていません。でも、仕事としてシミュレーターを用いた自動車開発には興味があるので、シミュレーターを使ったマシン開発から実車のテストを行い、自動車開発に繋げるといったことができたらいいですね。
――最後に、今後の目標を教えてください。
川上多くの人にモータースポーツとeモータースポーツのおもしろさを知ってもらいたいと考えているので、いまのチャンピオンの立場を利用して協力できることは積極的に行っていきたいですね。選手としては今年以降もトップを競い合えるドライバーで居続けたいと思っています。今回の大会には年齢制限で参戦できなかった若手ドライバーもたくさんいましたが、その中にもまだまだ、速い人がたくさんいます。そんな人たちからも追われる立場になりますが、これまで培ってきた経験値を活かして負けない、強いドライバーになりたいですね。
2019年、“eモータースポーツ”への取り組みはさらに加速していく
『GT SPORT』では、昨年実施した“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”に引き続き、2019年も“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2019”を開催。初戦となる“グランツーリスモワールドツアー 2019 パリ”が2019年3月16日・17日(現地時間)にフランス・パリにて行われ、今シーズンの幕が開いたのは既報の通り。
『GT SPORT』の“eモータースポーツ”活動は“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2019”以外にも、2019年10月に開催される国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体・文化プログラム“全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI”)の競技タイトルにも選定されていたり、ポルシェ ジャパンも『GT SPORT』を用いたワンメイクeレースの開催を宣言。
また、TOYOTA GAZOO Racingも“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ”のオフィシャルパートナーとなり、トヨタGRスープラRZを用いたグローバルワンメイクレース“GR Supra GT Cup”の開催を表明するなど、今年はさらに“eモータースポーツ”を盛り上げるべく、積極的な取り組みが行われていくことになる。
“GR Supra GT Cup”開催概要
レース名称:GR Supra GT Cup
開催期間:2019年4月~8月
開催場所:予選:オンラインでグローバルに実施/決勝:10月東京モーターショー会場にてリアルイベントを開催
ラウンド:年間13ラウンド(予定)
参加条件:PS4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』の所有者(年齢6歳以上)
エントリー方法:TOYOTA GAZOO Racing「GR Supra GT Cup」特設サイトにて後日公開予定
URL: https://toyotagazooracing.com/jp/e-motorsports/
※各ラウンドのサーキットの詳細情報などは順次“GR Supra GT Cup”のTOYOTA GAZOO Racing特設サイトにて公開します。
リアルとバーチャルの境界を飛び越えた『GT』の未来はどこに向かうのか?
『GT』はこれまで、カーライフのリアルな世界(自動車の見た目や走行フィーリングだけでなく、光や音といった空間まで)をバーチャルな世界で再現することに重きを置いてきていたが、バーチャルとリアルの境界が曖昧になってきている現在、架空のマシンが実車化されるという、逆現象も実現。
2018年8月には、独の自動車メーカー・アウディが『GT SPORT』に登場するコンセプトカー、“Audi e-tron Vision Gran Turismo”を、本当に走れるマシンとして製作するという大きな出来事でも話題を集めていた。
また、前述の“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”ネイションズカップで優勝を遂げたブラジルのイゴール・フラガ選手は、アメリカで開催されているインディーカー選手権のカテゴリーのひとつ、US-F2000にも参戦しているほか、F1の老舗チーム・マクラーレンが独自に行っているeスポーツ活動を通じて、同チームのシミュレータードライバーに就任するなど、リアルとバーチャルのモータースポーツ界で活躍が期待される、要注目選手だ。
今後、“eモータースポーツ”がさらなる発展を目指すには、今回お話を聞いた川上選手や、このフラガ選手のようなスター選手の誕生と活躍が必須になってくるはずだ。
“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ”に関しては、参加する時点で18歳以上であることといった年齢制限が設けられているが、『GT SPORT』は老若男女問わず楽しめるコンテンツのため、現時点で18歳に満たないスタードライバーも世界中に多数いるものと思われる。とくに若い世代のドライバーは飲み込みや適応力、反応速度ともに高いことから、まだ見ぬ逸材が身を潜めている可能性もあり、この先のチャンピオンシップはさらに激戦になっていくのではないだろうか。
筆者の幼少時代には(当然のように)『GT』のようなドライビングシミュレーターは存在しておらず、レーサーになるにはカートの経験を経て、サーキットライセンスを取得してレースに参戦し、スポンサーやチームを見つけるなどしながらステップアップをしていくという道が一般的なものであった。
しかし、『GT』がある現在は、幼少期に『GT』で先にドライビングテクニックを学び、後にリアルなクルマを運転するという、一昔前とは逆転した現象が起きている。
今回インタビューを行った川上選手を始め、“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”に参戦している選手の大半が、幼少期より『GT』を遊び始めているとのこと。物心がつく前に意識することなくドライビングテクニックを習得しているというのだから、時代の変化には驚くばかりだ。
何より、リアルレースに参戦するにはマシン費用(タイヤやブレーキなどの消耗品・整備代、燃料代含む)、サーキットへの移動費、マシンを運ぶトランスポーター代など、相当額の費用がかかるのが当たり前だったが、『GT』であればプレイステーション4本体とゲームソフト、ステアリングコントローラさえ取りそろえば、だれでも気軽に挑戦可能というのは、大きな魅力だと言える。また、試したい走りがあれば怪我の心配もなく、マシンクラッシュで多額の修理費が嵩むこともなく何度でもチャレンジし研鑽できるというのも、バーチャルならではの利点に他ならない。
実際に『GT』でもバーチャルドライバーをリアルレーサーにする育成プロジェクト“GTアカデミー”の取り組みを行ってきていたが、レースゲームは余興として遊ぶ時代から、真剣にモータースポーツを目指すための本格的なツールになったといっても過言ではないだろう。もちろん、野球やサッカーのようなスポーツでプロを目標としなくても誰もが気軽に楽しむことができるように、『GT SPORT』も真剣なレースに挑むのではなく、もっと楽な気持ちでクルマの楽しさを味わうこともできる。さらに言えば、そのツールが本物同様であれば、さらなるおもしろさが体感できるに違いない。
近年では、(フェラーリを除く)F1の全チームが公式のeスポーツチャンピオンシップを開催していたり、前述のポルシェやトヨタ、マクラーレンのようなマニュファクチャラーが独自にeスポーツを採り入れた活動を実施。『GT SPORT』のチャンピオンシップも、モータースポーツの裾野拡大を目指すFIAとの理念が合致して開催実現に至ったなど、リアルな自動車メーカーやモータースポーツ関連団体が、ドライビングシミュレーターの未来に注目していることがうかがえる。
幼少期のカート参戦からステップアップしてプロドライバーになるというこれまでのセオリーとは異なり、『GT』で運転を始めたドライバーがモータースポーツのトップカテゴリーの世界を席巻する、そんな未来はすぐそこに来ているのかもしれない。また、“eモータースポーツ”というカテゴリーそのものも、この先さらなる盛り上がりを見せるに違いない。『GT SPORT』と、そこで活躍している選手たちを見ていると、そんな予感と期待がこみ上げてくる。