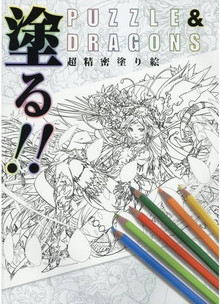- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第4章 視力障害センター
劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第4章 視力障害センター
公開日時:2018-11-01 19:00:00

|
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
第4章 ■1. 函館視力障害センター†
2007年11月26日。
室蘭の自宅から汽車とタクシーを乗り継いで、午前中のうちに辿りついた2度目となる函館視力障害センターは、希望半分不安半分のため、何とも言えない気持ちにさせる場所だった。
到着するとまずは荷物の整理もあるだろうと、これから暮らすことになる部屋に案内された。一応全盲で、ひとりで歩くことも慣れていないことを考慮して、3階のエレベーターからいちばん近い部屋を用意してくれていた。
ただでさえ広い部屋はまだ何も置いていないため、持ってきたボストンバックひとつを隅に置いても殺風景な状態である。生活に必要そうな物で持ってこれない物は後から送ってもらうこととし、とりあえず少しの間もたせる分の飲み物などを母と買いに行くことにした。
視力障害センターの隣には大型スーパーがあり、ある程度のものはここで調達できるため、とても便利だ。そのうちひとりで買い物に出ることもできるのだろうか?
寮には各階に共同の大きな冷蔵庫が置いてあり、自由に使ってもいいそうなので、買ったものをしまってから職員の元へと向かった。
これから受ける自立訓練では支援課と言われる部署の職員が担当するらしく、他に専門課程や職業訓練の教師も別にいるらしい。まずは支援課の先生と、今後どんな訓練をしていくかの詳細を話し合った。
基本的な日常生活訓練と、歩行訓練。身の回りの必須家事である掃除や洗濯や整理整頓などと、白杖を使ってひとりで外を歩く訓練である。
次に、調理訓練と感覚訓練とスポーツ訓練。全盲でも安全かつ簡単に料理する方法を習い、視力が欠損した分を他の五感で補う訓練と、なるべく体を動かして健康を維持するための訓練である。
他には、習っておいたほうがいいと勧められて、点字とパソコンの訓練も入れてもらった。まだこの時には決められなかったが、もし今後、専門課程という資格を取得するならこれらは必ず必要な条件だという。
それはともかくとして、全盲者の文字代わりと言われている点字は習いたかったし、パソコンもできるようになれば便利だろうと考えて、今回はお願いすることにした。
そのため、点字とパソコンの道具を揃えるために市に申請手続きをした。障害者は日常などに必要な専用グッズを市に申請すると、上限はあるものの料金が免除になり、受け取ることができる。
今回は免除になる対象のグッズのため、点字専用の板に点筆と言われるものと、パソコンにインストールする音声ソフトをお願いした。これらが届くまでは、とりあえず日常訓練のほうを集中して進めるらしかった。
それから、今後の各訓練の目標などを話してから話し合いは終了した。この面談だけで約2時間も費やしてへとへととなってしまったので、部屋に戻るなり畳の上に寝転がった。
ひとまず慣れるまでの間は、食事やお風呂など職員がついていてくれるらしい。夕食は5時半のため、まだ時間が空いて休憩していたが、間もなく母が帰る時刻となってしまった。
母が帰ればもちろんひとりぼっちとなり、その上、部屋の外はひとりでは歩けない状況である。そのことが心配で母も帰るのを渋ってしまったが、無理やり強がって大丈夫だと必死に言い聞かせて、明るく振舞いながら母を説得した。
そうして、母はついに地元へと帰り、部屋にひとりとなった。
何もない部屋。自分以外、誰もいない部屋。母には強がっていたが、段々と不安や恐怖が心を埋め尽くす。
これまでの自分は、周りの家族や友人がいなければ何もできなかったとすごく痛感する時間だった。ひとりではまだ冷蔵庫にも行けない、食堂にも行けない、喫煙所にも行けない、唯一教えてもらった共同トイレにも行く自信がない。
いまの自分は所詮こんなものだ。だから、これから自分がどんな風に変わっていくのか。何もできない自分が、どれほどのことができるようになるのか。
希望と期待で不安や恐怖を無理やり封じて、壁におでこをぶつけながらトイレへと行ってみたのだった。この時、かなり大きなたんこぶができた。
午後5時半。館内にチャイムが鳴り響いた。
この施設では、何かを知らせるためなのかたまにチャイムが鳴り響くので、急に鳴り響く音に驚いて慣れない内は身体をいつも震わせていた。
恐らく、さっきのチャイムは夕食の合図なのかなと考えていたら、支援課の職員が迎えに来た。やたらと背が高くて体格のいい、その職員の腕を掴んで連れて行ってもらうが、細身である自分がこんな腕組み状態でいたら何だか恥ずかしくて周りが気になってしまった。
そういえば、昼間は静かだった廊下にたくさんの人が行き交うようになっており、廊下全体にたくさんの声が響いて騒がしくなっていた。皆、食堂に向かっているらしいが、スタスタとひとりで歩いていた。誰が全盲で、誰が弱視で、誰が健常者なのかはわからないが、そのうち自分もこんな風に歩けるようになるのかなと羨ましかった。
部屋から食堂までの道はやはりまったくわからなかったが、何度も曲がっていた感じはあった。聞くと、寮のある宿舎棟から食堂のある厚生棟まで行くのに、ジグザグになった渡り廊下を通るらしく、全盲者は最初ここで戸惑う人が多いとのことだった。
話しながら辿りついた食堂は広大な空間で、すでに多くの人の話し声で賑わっていた。食堂内も徐々に訓練すると言われ、今回は直接椅子に座らせてもらい、目の前に夕食の乗ったお盆を置いてもらった。慣れたら自分で、カウンターからお盆を持ったままテーブルに移動しなければいけない。
ここでひとつ、大問題が起きた。
ざっと今日のメニューは教えてもらったのだが、どこに何が盛られているのかがわからない。自宅では決まりきった配置に慣れてしまっていたし、多少汚く食べてしまっても問題はなかった。しかし、周りに他人がいるこの状況では、そんなことはできない。
それと、恥ずかしいことだが好き嫌いが多いので、恐る恐る料理を口に運んでいた。するとやっぱり、大嫌いなトマトを口に運んでしまい、悶絶することとなった。
たっぷり時間をかけて夕食を何とかを終わらせた後、帰りも食堂から部屋までは連れて行ってもらった。トマトのせいでだいぶ精神を削られて、またもや畳の上に寝転んで唇を噛みしめていた。
そして数時間後には、お風呂の案内をすると部屋から連れ出された。お風呂はこの施設の自慢らしく、湯の川という土地を活かして温泉を引いているらしい。
宿舎棟の1階にある風呂場に到着すると、10畳ほどの広さの風呂場に何人かの人が先に入っていた。挨拶してから風呂場に入り、まずは中の環境認知をしてもらった。
ちなみに、この施設内では風呂場に関わらず挨拶は必須で、全盲の人も多くいるため、声を掛け合ってお互いの存在を確認し合わなければならない。そうでなければ、誰もいないと思って移動してぶつかってしまい、トラブルが起きてしまうのだ。だから、共同の部屋に入る時や廊下で足音が聞こえた時は、お互いに元気に挨拶することが当たり前となっている。
こうして、自慢の温泉をゆっくりと堪能してから部屋へと帰されて、この日は終了だった。 確かに、温泉に毎日入り放題というのは贅沢すぎる設備だ。おかげで身体も軽い気がする。
ここでは夜10時が消灯の時間で、寝る前に宿直している職員が各部屋を訪れ、点呼をしてから就寝となる。点呼を始める音楽として館内に流れた曲は久保田利信の曲で、それを子守唄にいつの間にか寝てしまっていた。
第4章 ■2. 自立訓練生活†
2007年11月27日。
次の日、早速本日から訓練が始まる。
顔を洗うためにエレベーターや壁にぶつかりながら洗面所を訪れ、その後、部屋で待機していると、朝食のために支援課の職員が迎えに来た。
2回目となる食堂までの道は、やっぱり全然理解不能だった。そして、問題の食事も恐る恐る口に入れていたのだが、案の定トマトを口に放り込み、悶絶していた。ここで食事を続ける内に、好き嫌いはなくなってくれるだろうか。そして、付け合せにトマトというのは絶対なのだろうか。
食後は一度部屋に戻され、程なくして再び迎えが来た。
自立訓練課程コースは、1日の始まりにまずは教室で所謂ホームルームのようなことを行う。そこから訓練生は各々の訓練を行うのだ。
同じ自立訓練生は他に3人いたが、顔を合わせるのはホームルームと食堂くらいで、たまに共同訓練と評していっしょになる程度だった。同じ視力障害同士なのだから、ゆっくり話して情報交換をしたかったのに残念だ。
それから、今後の訓練スケジュールを聞いて何だか唖然としてしまった。なぜなら1日に行う訓練は、たったの2~3時間のみ。ひとつの訓練は50分の授業として行うため、2つか3つの訓練をするだけで1日は終わるという。
ふつうの学校のように6時間とか、日が昇っている間はいっぱいいっぱい訓練かと思っていたのに、拍子抜けしたまま訓練へと移行することとなった。実際には、目が見えなくなったばかりで生活すらままならない人たちの訓練ということで、ゆっくり時間をかけて無理なく進めていくこのカリキュラムは、施設側の考えられた構成なのだったが、この時はそのことには気づかずにいた。それだけ早く自立したい、という気持ちが先走ってしまっていた。
それからの日々はもちろん、訓練の毎日だった。
歩行訓練は実際に白杖を使い、はじめのうちは素振りをするのみだった。単純に左右均等にリズムを崩さず振る訓練。それから、体育館などの広いスペースで、覚えた間隔とリズムで歩いてみる。それが合格したら、やっと外を歩いてみることとなった。これまでで1ヵ月ほど費やしただろうか。
外で歩くためにまず必要だったのは、頭の中での地図作成であった。いまいる場所から目的地までに何を目印にして目指すか。少し歩くと信号があり、ここを越えて白杖で看板に触れたら右に曲がるなど、とにかく頭の中の地図と照らし合わせながら進まなければならない。時にまったく違う道に出てしまうと、すぐにパニックになって恐怖してしまった。自分がいまどこにいるのか、どっちに進まなければいけないのか、少し気を抜いてわからなくなってしまうだけで、何もできなくなってしまう。
時には車道を歩いてしまっていた。時には他人の家の敷地内に入ってしまっていた。時には置いてあった自転車にぶつかり、倒してしまった。時にはぶつかった弾みで白杖を落とし、どこにあるのかわからなくなってしまった。
昨日まではなかった路上車、毎日変化する降り積もる雪、様々な速さで行き来する人や車。頭の地図を見ながら、周りの音に気を配りながら、白杖の触覚に集中しなら。目が見えないというだけで、「歩行」という単純な行為がこんなにもハードなものになるのとは、思いもしなかった。
次に、日常訓練ではおもに掃除・洗濯・整理整頓などを訓練した。
掃除で問題となるのは、ゴミやホコリや落ちているものがわからないということ。正直、これは万遍なくやるしかないのだが、できるだけスムーズ、かつ効果的な拭き掃除や掃除機かけの仕方を習った。
洗濯に関しては、いい時代となったもので、ボタンひとつですべて終わってくれる。しかし、乾燥機から取り出して箪笥にしまおうとした時に、似たような生地のジャージの上下、何足もの靴下など、対となる組み合わせがわからなくなってしまった。もちろんメーカーや色、模様なんてわからない。これに関しては、安全ピンなどでまとめておくことや、何か目印をつけておかなければならなかった。それでも洗濯中に取れてしまい、いまでもジャージや靴下が色違いなんてことはよくやってしまう。シャツを裏返しに着てしまっていた時は、本当に恥ずかしかった。
物の整理整頓は、とにかく何をどこに置くか、どこに収納するかを徹底しなければならない。少しでもいつもと違う場所に置いてしまうと、翌日にはわからなくなってしまう。雑貨や衣類はもちろん、リモコンなどどこに置いたのかわからなくなって、半日探していたこともある。なので、配置場所・収納場所はしっかり決めておく。とにかくこれを徹底することとなった。
点字の訓練は、点筆での「書く」訓練と、指を使っての「読む」訓練。
「書く」訓練でまずやらなければいけなかったのは、単純に覚える作業だった。五十音・数字・記号など、思ったより簡単そうだと思うかもしれないが、目の見えない状態でイチから平仮名や漢字を覚えなければならないと想像したら、どれだけ大変かわかってもらえるだろうか? なので、最初はひたすら覚える作業を行い、多少覚えてきたところで後は書くことで慣れていくこととなった。
でも、大変ではあったが、訓練では好きな曲の歌詞を書いて、この歌詞の意味や思いなどを考えて進めたので、とても楽しく覚えることができた。終了するころには、じつに数十曲もの点字歌詞カードができあがっていた。
「読む」訓練で、ひとつ問題となることがあった。以前、抗がん剤治療をしてから指先がずっと軽い痺れに苛まれていること。軽いとはいえ、細かい点に触れて認識しなければいけない点字にとって致命的な障害となってしまった。しかし、こればかりはどうしようもないので、難しくてもとにかく読んでみることになった。紙に書かれた点字を読むことは最後まで苦手だったが、エレベーターなどにある硬い点字なら読めるようになったのはよかったと思う。
調理訓練は、簡単なコンロや包丁の使い方、それと火を使わずレンジで調理できる料理をいろいろ教えてもらった。いちばん大変そうに思える調理だが、見えている時はそれなりにやっていたおかげで、そこまで大変に思うことはなかった。あえて苦戦することを挙げるとするなら、火の通り加減や揚げ物などが判断し辛いことくらいだった。
パソコンの訓練は、点字同様にまずはキーの位置を覚えることから始まった。あまりパソコンを触ったことがなかったため、大変な作業だったが、パソコンが使えたら目の見えない世界が少しでも広がるという期待が意欲に繋がった。パソコンは「PCトーカー」という音声ソフトをインストールすることで、音声携帯同様にすべてを音声で表現してくれる。タイピングから始まり、もちろんマウスは使えないのでキー操作だけでワードやエクセル、インターネットやメールのやりかたを習った。慣れてきたら見なくてもキーを打つブラインドタッチをする人が多いのだから、とにかくパソコンを使い続けることで自分も慣れていくのだと思う。
感覚訓練は、視力の代わりとなる、おもに聴力と触覚の訓練だった。外に出て3分間、何もせずに耳で聞こえるものだけに集中してみると、ふだんは気にもしていない音まで聞こえてきて新鮮な気分だった。触覚の訓練は、何も聞かされず目の前に置かれたものを触って、それが何なのか当てるもの。たまにバラエティ番組などで、箱に手を入れて中に入っているものを当てるゲームなどがあるが、それに似ているのかもしれない。いろいろな訓練を試したが、いずれも楽しみながら行えるものだった。
スポーツ訓練では、希望を出したこともあって、おもにブラインドサッカー(盲人サッカー)の訓練というか練習につき合ってもらった。見えているころはよくサッカーをしていたが、やはり全盲でボールを扱うのはとても難しく、軽いドリブルですらまともにできなかった。一応、ボールの中には鈴が入っており、転がるだけで音は鳴るのだが、それでもはたから見たらボールにじゃれている猫のように思えるだろう。他にもBTT(盲人卓球)なども行ったが、やっぱり身体を動かすのは気持ちよかった。ほとんどひとりでは運動することすら困難だったこの時は、スポーツの時間が何よりも楽しかった。
このような訓練の日々を送り、徐々に施設内もひとりで歩き回れるようになってきたころ、少しずつ施設内での出会いも増えてきた。
やっとひとりで喫煙所に行けるようになり、一服していると職業訓練課程に在籍する先輩に声をかけられた。その人はとても人懐っこい印象で、少しの時間話していただけですぐに打ち解けて仲よくなった。そして、その先輩に誘われるがまま入ったのが、クラブ活動のひとつであるスポーツクラブだった。
この施設にも、ふつうの学校と変わらずいろいろなクラブ活動があるらしく、スポーツクラブはその名の通り、視力障害者でもできるスポーツを行うクラブだった。おもに力を入れているのはフロアバレー(盲人バレー)。
最初聞いた時は、目が見えない状態でバレー? あんな空中をボールが行ったり来たりするスポーツをどうやって? と疑問だったが、実際にやってみてすぐに謎は解けた。本来ならば、バレーは中央に設置されたネットの上をボールが飛び交うものだが、フロアバレーでは逆にネットの下をボールが行き来するのだ。
ネットの下にボールを転がして打ち合うと説明され、転がすなら結構優しいスポーツなのかな? と思いきや、先輩がボールを打った瞬間にその考えは改めることとなった。とりあえずどんな感じなのか耳で聞いていたら、すごい音が響き渡ったのだ。まるで地面に置いたボールを思い切り蹴ったような音。そして壁打ちつけられた音もまた、すごいものだった。この時はまだ何もわからなかったが、フロアバレーはなかなかに激しいスポーツだった。
フロアバレーでは基本的に、前衛(全盲)3人と後衛(弱視か健常者)3人の計6人チームで構成される。前衛は、ネット際で相手からの攻撃をブロックすることと、より近い位置から攻撃する役目。後衛は、後方から前衛に指示を出しながら攻防する。
全盲の自分が行う前衛は、より近い位置で相手の攻撃を防ぐため、なかなかに痛いポジションであった。その先輩が根っからのパワーアタッカーで、スパルタよろしく侃侃攻めてくるのも痛いイメージの原因だったかもしれない。
さらに、ここで今後の人生を大きく左右させる出会いがあった。
その日も訓練を終えて、自室でゆっくりしている時だった。まだまだ知人が少なく、人との関わりもほとんどなかったのだが、珍しく部屋の扉がノックされた。
多少驚きながらも出てみると、聞いたことのない声でひと言、「2階の談話室に来て」。
えっ? 誰かもわからない人に急に呼び出された? よく学園系ドラマとかで見る、校舎裏に来い、みたいな感じ? いまの人も何か雰囲気の怖い人だったし、そう考えると急に恐ろしくなってきてしまった。
でも、ここで無視してしまったらさらに悪化してしまうかもしれない。ひとりで、まずは腕を掴んで背中に捻り上げながら大声で助けを呼ぶ、などと物騒な妄想をしながら、その人について行ったのだった。
連れて来られたのは、談話室という利用者たちが自由に交流を行える部屋だった。中に入って、物音や声だけでその場の状況に集中する。果たして聞こえてきたのは、いかつい怒号ではなくかわいらしい女の子の声だった。
突然の「初めまして」という女の子に茫然としていると、ここに連れて来たお兄さんが「話してみたかったんだってさ」と教えてくれた。
聞くと、彼女は理療課程1年生の幸恵さんという名前で、若い男の子が施設に来たと聞いたから一度話してみたかったらしい。そして、自立訓練課程との接触の機会がないため、同じ男子寮にいるお兄さんに呼び出してもらったとのことだった。
この視力障害センターには、基本的に社会復帰を目的として資格を取得するために中途で全盲や弱視になった人が訪れる。そのため利用者の年齢は中年者が多い。若い人で視力障碍者になってしまう人は少ないし、生まれつきや20歳以下だと盲学校から通常の勉強を始めるのがふつうだった。
そのため、22歳の自分や20歳になったばかりの幸恵さんがいるのは少し珍しいことだった。それも利用者のほとんどが弱視(少しは見えている)中で、全盲どうしというのも興味を惹かれたようだ。
談話室でしばらく、幸恵さんとの会話を楽しんだ。もうひとり、お兄さんは寝そべってくつろぎながら、黙ってふたりの会話を聞いていた。
幸恵さんは、高校3年生のころに交通事故で視力を失ったらしい。自分とは違う環境にしろ、同じように見えなくてもこれから社会復帰するためにがんばっていた。
そんな幸恵さんの第一印象は、とにかく明るくて前向きで元気いっぱいな子だった。全盲になったことを悲観せずに、いまを精一杯楽しんでいる。すごいと思った。なぜ彼女はこんなにも希望にあふれて光っているのだろう?
そんな彼女に、自然と惹かれていった。もっと彼女のことを知りたい。もっと彼女といっしょにいたい。初めて会ってから、そんなことばかり考えるようになっていた。
そして、しばらく幸恵さんとメールのやりとりやたまに談話室で会話していく内に、彼女からカラオケのお誘いがあった。歌うことが大好きと言っていたので、ふたつ返事でいっしょに行くことを決めた。たぶん、お友だち何人かでのカラオケに誘ってくれたのだと思っていた。しかし、当日玄関で待っていたのは幸恵さんただひとりだった。
「え? ふたりで行くの?」と聞いたら、「そうだよ?」と逆に何でそんなこと聞くの?と言わんばかりな様子。幸恵さんはそんなこと気にせずに、白杖を振りながら玄関から歩き出したので、それについていく形となった。
移動はタクシーで、カラオケ店まで来ると受付の店員に部屋まで手引きしてもらった。幸恵さんは終始慣れた感じで、店員に選曲を頼んでいた。そして流されるまま、ふたりで歌を歌って、たまに雑談しながら過ごしていた。
しばらくして、選曲してもらうために店員さんを待っている時だった。
突然だが、自分は女性に告白したことがない。何度か交際経験はあるが、自分から思いを伝えたことはない。
たぶん、どんなにふつうに暮らしていても、病気のことや片目であったことがコンプレックスとなり、自分に自信が持てなかったから。ふられて傷つくのが怖くて、奥手になってしまっていた。なので、好意を寄せた人に思いを伝えて交際したことはない。
そんな自分自身をよくわかっていたし、目が見えなくなったいま、さらにマイナスになったと思っていた。だからこんな行動に出たのは自分でも不思議だった。
自分は改まって言った。
「大事なお話があります」
幸恵さんは「何?」と、キョトンとしながら次の言葉を待った。
「僕とつき合ってください」
人生初めての告白。少しの間、沈黙が流れたと思う。それはそうだ。幸恵さんからしたら、友達とただカラオケを楽しんでいた最中なのだ。急にそんなことを言われて、すぐ対応できるはずがない。それもまだ出会って間もないのだ。
お互い顔も知らない。どんな姿をしているのかわからない。手でさえ触れたこともない。知っているのは少しだけ話したお互いの過去と現状、そして雰囲気と声だけ。
それだけで、幸恵さんにどれだけ惹かれていたのだろうか。正直、この時好きになっていたのかと聞かれたら自信はない。でも、とにかく幸恵さんといっしょにいて、もっとたくさん話していたかった。幸恵さんの元気がほしいと思った。
結局のところは、その場は幸恵さんの考える時間がほしいとの言葉で終わった。帰りのタクシーで運転手に、「お似合いカップルだね」なんて言われて、何てタイミングでと思ったのもいい思い出だ。
そして、落ち着かない日々が続いた数日後、幸恵さんと交際することとなったのだった。
運命の出会いという言葉を信じるならば、これがそうだったのだと思う。お互い全盲となり、一大決心して自立するために単身函館を訪れ、タイミングよくふたりは出会った。そしてまた、一歩踏み出すための勇気を彼女からもらった。
この日から、資格を取るため理療課程コースに進むことを決めた。幸恵さんとの将来を見据えるならば必要なことだと思った。
理療課程はふつうの学校と同じく、4月から始まる。なので、本来半年以上かけて行う自立訓練を詰めに詰めて、3ヵ月で終わらせることにした。
そのため、これまでは1日3時間程度だった訓練も、多い時で1日8時間訓練となった。すべてはすでに理療課程に入っている幸恵さんに追いつくために。
それからの日々は、本当に忙しくて充実した日々だった。長い訓練をして、スポーツクラブにも参加して、夜はなるべく幸恵さんと過ごした。
いつの間にか、歩行訓練の目的地が飲食店やカラオケ店となっていたのはなぜだろう? でも、そのおかげで、タクシーを使わなくても幸恵さんの手を引いて遊びに連れて行ってあげられたのがうれしかった。全盲どうしで手を繋いで外を歩けるなんて思いもしなかった。ふたりでケンタッキーの目の前に立つカーネルさんにぶつかって謝ったのも、お互い笑い合って楽しかった。
ちょっとした買い物でも散歩でも、必ず自分が幸恵さんの手を引いて先導した。何だか青春時代に戻ったようで、本当に幸せに感じる時間となっていた。
そして、くたくたになりながらも訓練をすべて達成し、無事4月から理療課程コースに進めることとなったのだった。
これから3年間は、按摩指圧マッサージ・鍼・灸の3つの国家資格を取得するために勉強していくこととなる。
勉強に恋愛にスポーツ、すべてに期待を感じながら前へと進んでいく。
第4章 ■3. 按摩指圧マッサージ鍼灸I†
2008年4月。理療課程コース開始。
理療課程とは、按摩指圧マッサージ・鍼・灸の3つの国家資格を取得するためのコースである。
昔から視力障害者の働き口として選ばれることが多いのは、必ず視力が必要というわけではないマッサージの仕事だった。近年、国家資格とされたこれらを取得すれば、病院・治療院・養護施設・ヘルスキーパー(特定の企業の専門按摩師)などの就職先の幅が広がる。
学ぶ内容としては、解剖学・生理学・病理学・東洋医学・経穴(所謂ツボ)など、医師や看護師が学ぶような知識が多い。ふつうの学校にあるような体育や点字、パソコンなども必修科目に含まれていたりする。
初日には、これから使用することとなる教室に自分を含めたクラスメイト10人が集まっていた。今年は珍しいことに若い利用者が多いらしく、半数以上が三十路以下の年齢であった。そして、その中には幸恵さんもいた。
なぜ1年先輩で理療課程2年生のはずの幸恵さんがいるかというと、単純に留年してしまったからだ。もちろん、この理療課程にも成績というものは存在しており、規定以下の成績ならば留年してしまう。事前には聞いていたが、同じクラスメイトとしていっしょに学んでいけるのは正直うれしかった。留年が決まった時、幸恵さんはひどく落ち込んでいたので不謹慎ではあるが、持ち前の前向きな明るさですぐに立ち直って、気持ちを切り替えていたのはさすがだと思う。
そんなこんなで始まった新生活は、自立訓練の時より大変ではあったがとても楽しかった。
何よりクラス皆で協力して勉強したり、休日に余暇を過ごしたりと、再び学生に戻った気分だった。歳の近いクラスメイトが多いため、話も盛り上がり、毎日みんなで集まって何かをしていた。
学ぶことはやはり専門的なことばかりなので、毎日苦戦していた。それもクラスで全盲なのは自分と幸恵さんのみ。基本的に授業はすべて録音して、その場では集中して耳だけを傾けていた。
ふたりとも点字やパソコンに慣れているとは言えないため、授業を聞きながらすばやくノートを取るということができなかった。なので、約1時限分の録音音声を聞きながら勉強しなければならない。それが1日分となればおよそ5~6時間に及ぶ。つまりは、勉強するだけで見えてる人の何倍も時間がかかってしまうのだ。
とにかく録音音声による復習が少なくて済むように、授業自体に集中して理解することにした。とはいえ、遊ぶ時はしっかり遊んだ。だから、周りからしたら放課後や夕方以降に遊んでばかりいるように見えただろう。実際に、授業以外はそうだったのだからウソではない。しかし、1学期の期末テストではほとんどの科目で90点以上、中にはクラスで唯一の満点だったものもあった。
もともとは小学生のころは勉強しなくても成績はよかった。中学・高校では遊びやアルバイトばかりでどんどん成績も落ちて、言ってしまえば不真面目で補修など当たり前なくらい頭が悪かった。でも、今回で自分はやればできるんだと自信がついた。
そんな風に調子に乗って、段々と大変になっていってしまうのはまだ先の話だった。
理療課程となってすぐのこと。
この視力障害センターから徒歩数分の市民センターに、とあるアーティストがライブに来ると母から教えてもらった。
それは、自分と母が大ファンであるGacktさん。母は自分と幸恵さんを誘ってくれ、3人でライブに行くこととなった。
ライブは終始盛り上がり、その熱気に混ざって3人でいっしょに叫んでいたほどだ。
そして、ライブはあっという間に終わり、幸恵さんと「かっこよかったね」とか「また来たいね」と話しながら、帰り支度をしている時だった。
いかにもライブの関係者と思われる人に「こちらへ来てください」と、意味がわからないまま舞台裏へと連れて行かれたのだ。
ここでやっと、母は教えてくれた。どうやらファンサイトの連絡先からGacktさんに直接連絡し、全盲の息子に会って激励してくれないかと頼んでいたのだ。
まさか多忙な方がわざわざ個人のために会ってくれるなんて無理だろうと考えたが、しばらく待って、目の前に本人が現れた時は心臓が飛び出しそうなくらい驚いてしまった。
Gacktさんはしっかりと手を握ってくれながら、「がんばれよ。決して負けるなよ」と激励してくれた。
さらには離れた場所で待っていた幸恵さんを見つけると傍に誘導し、同じように激励してくれた。
最後には、自分と幸恵さんの肩を強く抱いて、いっしょに写真を撮影してお別れとなった。
背が高かったせいもあるが、本当に大きな人だった。何と言うか、雰囲気が大きいと思った。身体も心もすべて包み込んでくれそうなくらい大きな存在。
しばらくはGacktさんの余韻が消えなかった。
もちろん自分と幸恵さんは現在でも彼の大ファンで、たまにテレビなどで声が聴けると本当にうれしい気持ちになっている。これからも誰かを勇気づけるようにがんばってほしいと応援している。
第4章 ■4. 母の異常†
2008年7月。
だいぶ慣れてきた理療課程コースの1学期が終了して、夏季休暇に入ろうとしていた。
そんな時、幸恵さんから宮城に遊びに来ないかという提案が出された。幸恵さんの家族にもご挨拶したかったのもあり、申し訳ないと感じながらも夏休み1ヵ月のほとんどをお世話になることにした。
しかし、宮城を訪れてびっくり。幸恵さんの母は、マンスリーマンションを短期で借りて全盲者ふたりで暮らさせようという。
幸恵さんのお願いだったのか、試しに同棲してみなさいという好意だったのかはわからない。とりあえずは幸恵さん家族への挨拶もほどほどに、マンションでの短期のふたり暮らしが始まったのだった。
買い物などは幸恵さんの母がしてくれたが、その他家事はすべて目の見えないふたりだけでこなさなければならない。しかし、さすがに自立訓練である程度は学んだふたりなわけで、大きな壁にぶち当たることもなく、逆にふたりっきりの生活を大いに楽しんでいた。
幸恵さんは整理整頓や洗濯が得意だった。自分からしたら多すぎるほどの衣類を収納し、しっかり管理しながら着こなしている。こんなにたくさんあったら、どれがどれだかわからなくなりそうなのに。
しかしながら、ふたりで暮らしてみていちばん困ったのも、同じく整理整頓の分野。物をどこに置いたか忘れて行動してしまうことだった。テレビのリモコンが見つからなくて、ふたりで半日探していたこともある。床に小物が落ちていて踏みつけてしまうこともある。危なかったのは、料理の際にコンロの近くに食器が置いてあり、気づかずに加熱してしまっていたことだ。プラスチックの食器は溶けてひどい有様だった。
どちらかがわかっていても意味がない。ふたりがふたりとも何がどこにあるのか、どこに置いたのかを理解していなければいけなかった。
そんな風に、ふたりで改めて気を付けなければならないことを確認して、それでも楽しくて幸せな日々を満喫しているころだった。
誰が予想できただろうか? ここから何度も、幸せに近づいては遠ざかる日々を送らなければいけなくなる。
それは母からの1通のメールから始まる。
「死にたい」
意味がわからなかった。すぐに心配するメールを送っても、「辛い」、「疲れた」などのみが送られてくる。
何度も電話やメールをしていく内に、いつの間にか母は鬱病という疾患に苛まれていることがわかった。母と暮らす弟にも話を聞いて、現在ほとんど寝たきりで、異常なほど大量の薬を服用しているとのこと。食事もろくに取れず、体重も危険である40キロを切っているらしかった。
本当に信じられなかった。あんなにパワフルに自分の闘病を支えてきてくれた母が。最後に別れた時だって元気いっぱいだった。あれから数ヵ月しか経っていないのに。頭が混乱してる間にも、母からは昼夜問わず断続的に暗いメールが送られてくる。
弟を通して母のかかりつけの主治医に対処方法を聞いたら、とにかく寂しい思いをしないようにかまってあげることと、優しく接して決して怒らない、怒鳴らないとのことだった。まるでこれからは子どもを相手にするようにと言われたようで、やりきれないもどかしさだけがこみ上げてきた。
それからはしばらく朝昼晩関わらず、時には深夜にも母の相手をすることとなった。もちろん寝不足にもなり、母の暗いメールに精神的におかしくなりそうにもなっていた。
せっかくいっしょに暮らす幸恵さんには「もっと楽しく過ごしてよ」と言われ、喧嘩までする始末。この時、幸恵さんに当たってしまったこともあり、本当にせっかくの時間を台無しにして申し訳ない気持ちでいっぱいになった。
母の現状を幸恵さんに伝えることで理解してもらい、謝罪とともに幸せなはずのふたり暮らし体験は微妙な空気のまま終わってしまったのだった。
それからも理療課程にいた3年間の離れている時間は、絶え間なく電話やメールに悩まされ、耐えられなくなって無視していると本当に自殺未遂を起こしたこともあった。
連絡が取れなくなって地元の親類総出で捜索して、線路の近くで発見された時は試験前なのに心労で倒れてしまった。
長期休暇に帰省する日に母がスーパーで問題を起こしてしまい、警察沙汰となり、そのまま入院することになったこともあった。記憶が定かではなく、目は虚ろになりながら会計前の商品をカートごと持っていこうとしたらしい。さすがにそこまで堂々と万引きはしないだろうと、精神的不安定なことを考慮していただき、スーパー側からも許してもらえた。
気づいたら入院していた母は、病院で暴れてベッドに固定せざるを得なかったらしい。叔母からは母のあんな般若のような恐ろしい顔は初めて見た、と聞いた。
自分が帰省している時はつねに寝たきりで、たまに夜中に立ち上がり、大きな音を立てて転倒し、急に助けて助けてと泣きながらすがりつかれたこともある。相変わらず食事を取らないので、ゼリーなどを無理やり食べさせると泣きながら嘔吐している。
いちばん驚いたのは、皆が寝静まっている深夜に大声で絶叫し始めたことだ。さすがに恐怖しながらも弟といっしょに必死に宥めていた。
とにかくこの時の母は狂っていた。自分よりもずっと長い間、傍にいなければならない弟の精神的苦痛も計り知れなかった。なるべく祖母に来てもらい、どうしようもない時は無理やり入院させることで乗り切るほかなかった。
本当にどうしていいのかわからなかった。
生まれてすぐ我が子の病気が判明してから過酷な生活になったにも関わらず、決して我が子だけは見捨てなかった母。何度、絶望に落とされようが、我が子を信じていつもいちばん傍で支え続けてくれた母。
産んでくれたことを責めたことなんてない。辛いことがたくさんあったって、全盲になったって、この人生をくれた母を恨んだことなんてない。逆に感謝しかないのだ。
だからこそ、辛くても、怖くても、今度は自分が母を何とか支えてあげたかった。
第4章 ■5. 按摩指圧マッサージ鍼灸II†
理療課程も進み、母の問題を抱えながらも何とか無事、進級を果たすことができていた。
視力障害センターでは家庭の内情は伏せて、あくまでふつうに過ごすよう心掛けた。フロアバレーの大会にも積極的に参加して好成績を残したり、ボランティアで函館の大学の特別講師として視力障害についてのことを講義したりもした。
北海道新聞に自分のことを記事にしてもらったこともあった。全盲者が自立に向けてどれだけ努力しているかを記事にしてもらったのだが、一面に自分がダンベルを持ち上げる写真が載せられたのは少し恥ずかしかった。
時には多忙な毎日に母のことが重なり、精神的にくじけそうになってひとりで涙を流すこともあったが、そんな時は幸恵さんの明るさにいつも助けてもらっていた。
しかし、なかなか授業についていけなくなり、赤点ギリギリで留年の危機もあったりした。母の相手をしながら、ほとんど寝ずに3日勉強して試験に臨んだ時は、身体が自分のものじゃないと思えるくらいフラフラだった。
そして、何とか理療課程最後の1年にさしかかったころ、幸恵さんと真剣にこれからのことを話し合うこととなった。
それは、これから交際を続けて結婚を視野にいれるならば避けられないこと。相手が幸恵さんだったからこそ、真剣に話し合わなければいけないと思った。
ひとつは全盲どうしということ。
少しだけいっしょに暮らしてみたが、将来を考えたらもっとたくさんの困難があるに違いない。自分たちだけではできないこともあるし、それがストレスになってしまうかもしれない。やりたいこと、行きたいところ、会いたい人、すべてに対して制限のある生活になってしまうのだ。
正直言うと、もし相手のご両親から、娘の相手は健常者に任せたい、と言われてしまったら反論のしようがない。もちろん簡単に引き下がるつもりはないが、それだけ全盲どうしというのは大変なことだということだ。
もうひとつは、病気の遺伝のこと。
網膜芽細胞腫は両眼性と片眼性の2種類あり、片眼性は遺伝に関係ないが、両眼性は約5~60%の可能性で遺伝してしまう。そして自分は、両眼性である。
もし将来、子どもを望むならば、遺伝してしまう可能性があるということ。もし遺伝してしまったら、がん治療という過酷な人生を送らなければならないかもしれないということ。もちろん親となる幸恵さんも、想像を絶する苦労を強いられることになるということ。
前々から、幸恵さんから子どもが欲しいという話を聞いたことがあった。だからこそ、早い内に伝えなければならなかった。もし子どもを考えているならば、覚悟はあるかどうか。
もうひとつは、母のこと。
多少話したことはあったが、詳しくどんな状態なのかは伏せていた。こんな母がいることで嫌われたくないという思いが、いまになるまで口を塞いでしまっていた。
果たして幸恵さんは、鬱病で大変な状況の母を受け入れてくれるのか。
そして、少し考えてから、幸恵さんは言った。
「ごめんなさい」と涙を流しながら、謝罪だけを口にした。
だから、「ありがとう。こちらこそごめんね」と最後に抱き締めて、幸恵さんから離れた。
その日からはもちろん、幸恵さんとはただの友だちとして過ごすことになった。
これから先、いっしょにいたって幸恵さんに何をしてあげられるだろう? 目の見えない自分に何ができるのだろう? 病気のことだって母のことだってある。
きっと辛い思いをさせてしまう。それなら新しい出会いを信じて、もっと幸せな将来を送ってほしい。
そんなことを考えながら、ひとり涙を流していた。
この時はいちばん大切なことを考えず、これが幸恵さんにとって最善なんだと言い聞かせてしまった。その大切なことに気づくのはまだ先のことだった。
それは理療課程も3年生となり、ついに卒業と国家試験が見えてきた時期のことだった。
第4章 ■6. 卒業†
幸恵さんとお別れして、母のことに気をかけながらも勉強に集中する毎日を送っていた。
気晴らしと苦しいことを忘れるため、フロアバレーはがんばって続けていた。
とにかく毎日、これまで録音した授業を聞く日々。さすがに2年分以上なので、倍速にして要点だけを頭に入れるように。放課後には復習のため、教師に補修も頼んだ。
風の噂で、幸恵さんが誰かに告白されたと聞いた。それも短期間でふたりからも。やはり幸恵さんの太陽のような明るさに惹かれる人は多いんだ、と誇らしげになった。それと同時に悲しくもなった。もう幸恵さんは違う誰かとつき合っているのだろうか? どうしても気になって仕方がなかった。
そんなある日、按摩の実技の練習のため、幸恵さんに誘われた。
ふたりっきりになるのは久しぶりのため、少し緊張しながらも練習を開始した。最初は授業のことなど雑談しながら、自分がマッサージしていた。
そして、マッサージの練習が終わって休憩していると、どちらからともなくふたりは手を握っていたのだった。
寂しさを我慢できなくなった。いっしょにいないと辛い、離れてみて気づいた、と幸恵さんは寂しそうに話してくれた。自分じゃなければダメだと。だから、告白もすべて断っていたのだという。
もう手遅れだと思っていたが、あの別れ話の時、本当は言わなければならなかったことを今度はしっかりと伝えた。
幸恵さんにばかり覚悟を押しつけようとしてしまった。何があっても幸恵さんを支えていきたい。辛いことがあってもいっしょに乗り越えていきたい。何があっても全力で守っていく。
子どものことでも、家族のことでも、生活のことでも、全部ふたりで悩んで、助け合って、楽しく過ごしていきたい。どんな苦労が待ち受けていても、ふたりでがんばれば乗り越えられる。
こうして、ふたりは再び絆を深めて、交際を再開したのだった。
気分は晴れやかだった。暗く淀んだ世界がまるで太陽に照らされたようだった。やっぱり幸恵さんは太陽だ。
暗闇を照らす太陽。暗闇の向こうにあった光。
その後、勉強もはかどり、卒業に必要な単位は無事すべてクリアできた。
視力障害センターでは、理療課程生の卒業式が行われた。ここに来て3年と数ヵ月。詰め込んだようにいろんなことがあって、少し泣きそうになってしまった。
残すは国家試験のみ。国家試験が不合格になると、再受験は1年待たなければならない。1年も自立が先延ばしになるのは嫌だったので、いままで以上に気合を入れて臨んだ。
初日に按摩指圧マッサージの試験、2日目に鍼灸の試験を終えて、早々に寮を出る準備を始めた。
この施設の決まりで、国家試験の翌日にはすぐ出ていかなければならないのだ。もう少しセンターの余韻に浸っていたいのに、じつにあっけないものだと思う。
センターの職員、クラスメイト、フロアバレーのチームメイトなど、お世話になった人たちに挨拶を済ませて、最後に幸恵さん家族とともに昼食をいっしょした。
とりあえず幸恵さんは地元に戻り、しばらく休みながら国家試験の結果を待つらしい。そして、自分も同じく地元に戻る。もちろん別れは寂しいことだったが、何となくお互いに気を遣って言えないでいた。
次は、いつ会えるのだろう? 会いに行くには遠すぎる距離。お互い地元に戻ったら、ふたりの今後はどうなってしまうのだろう?
ここでもまた、大切な言葉を置き忘れて、そのまま別々の道に進んでしまったのだった。
そして、3年と少しを過ごした函館視力障害センターを後にした。
ーー第4章 おわりーー
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
『エンターテインメントという薬 -光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの-』特設サイトはこちら
- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第4章 視力障害センター