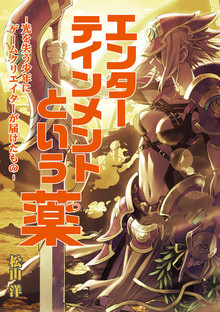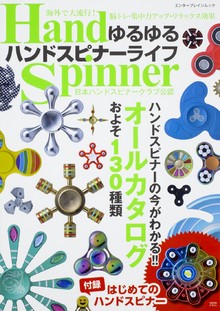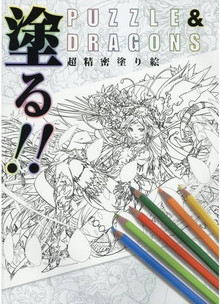- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第3章 全盲生活
劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第3章 全盲生活
公開日時:2018-11-01 19:00:00

|
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
第3章 ■1. 摘出手術後†
目が覚めたという感覚がなかった。
ずっと暗い闇の中にいて、そこから聞き覚えのある声が聞こえる。判然としない意識の中で必死に声の主を探そうとするが、相変わらず暗闇が広がっているだけで何も見えない。
そんなことを考えていたのはたぶん一瞬で、意識がはっきりしたところでいまの自分の状態を理解した。
たぶん病室のベッドで横になっており、すぐ横で母がこちらに声をかけている。
体がしんどいのは麻酔のせいで、喉が痛いのは管を通されていたせいで、何も見えないのは目が分厚いガーゼで覆われているから。ガーゼで覆われているから?
はっとして勢いよく上半身を起こしたが、三半規管が働いていないのか頭の中がグルグル回っているようで、いま自分が立っているのか座っているのか、前はどっちか上はどっちかすべてがわからなかった。
思わずまたベッドに横になって、気持ちを落ち着かせた。そして、心配そうに声をかけた母に状況を聞いてみた。
手術自体は数時間で無事終わり、それからずっと寝ていたため現在はもう夜らしかった。
そう言われて初めて気づく。何も見えないのはガーゼのせいなんかじゃなく、自分の眼球はもうないからなんだと。
意識してしまったら眼球があった部分が痛み始めて、すぐに痛み止めを処方してもらうことになった。
何だかただ目をつむっているのとはまったく違う感じ。うまく表現はできないけれど、ふつうならば目をつむっても瞼の裏が、つまり暗闇が見えているはずである。でも、その暗闇すらない。
言わば、最初から目などない生物のような感覚? 確かに幼少期に摘出した右目はそうだった。片目しか見えてないのに、機能していないもう片方が存在していることを不思議に思っていた時期もある。それがいまは両目となってしまったので、不思議な感覚に襲われている。
うまく起き上がれないのはそのせいで、平衡感覚もおかしくなっているのかもしれない。これからはこの状態に慣れなければいけない。慣れるのだろうか? と、少しだけ不安になった。
目覚めて数十分後に、主治医が検診にやって来た。
母の言葉通り、手術は何の問題もなく眼球を摘出し、いまは義眼代という透明な義眼を入れているらしい。そのうち傷口が回復したら、左目にもちゃんとした義眼を用意しなければならない。
ただ、今回摘出した左目はこれまでしてきた治療の影響から眼窩(眼球が入っていたくぼみ)の形が小さくなっているらしい。時間が経てば少し改善はされるものの、確実に右目とのバランスは悪くなるということだった。すなわち、右目に比べて左目はくぼんでいる状態となる。
なので、もし今後気になるのならば、どこまで改善されるかはわからないが形成外科に相談してみるしかないとのことだった。
その後、とりあえず状態が落ち着くまで3日ほど入院していることとなったのだが、病院での生活は大変なものだった。
以前、白内障の時に少しの間だけほぼ見えない状態を経験してはいたが、その時とはまた勝手が全然違い、今回は光すら感じられない状況。
時間の感覚も狂い、いまが朝なのか夜なのかさえわからない。もちろん何かしたくても、ベッドの上からは怖くて降りられない。
いちばん嫌だったのは、女性の看護師にお風呂に入れてもらった時である。恥ずかしさもあったが、何より介護を受けているようでとても屈辱であった。
目が見えていれば何も不自由なく自分でできるのに、光を失っただけでここまで自分が人形のように動けなくなるとは思わなかった。
1日に1回は、左目のガーゼ交換をしてもらっていた。最初、ガーゼを取った時にじつは見えるんじゃないか? とあり得ない希望を持ったが、そんなわけもなく、ガーゼをしていようがしていまいがもちろん光はなかった。
母もガーゼ交換の様子を同席して見ていたが、眼球のあった箇所には真ん中に穴の開いた透明なものが入っていたらしい。中の目やにを排出するための穴らしいが、確かにガーゼを取ると大量の粘々した目やにがあふれるほど溜まっていた。
術後の左目の痛み自体はわずか1日で収まり、縫い合わせた糸も勝手に溶けてなくなるため、抜糸の必要はなかった。
そんなわけで左目の傷口は順調に回復し、またすぐ経過の検査を予約して、予定通り3日後の午前中に退院する運びとなった。
退院日、入院中はどこに移動するにも車椅子か抱えられてだったため、術後初めて自分で歩くことになった。
ベッドから降りて母の肩に掴まりながらついていく形で歩行する。初めは慣れない感じで、フラフラと恐る恐る歩行をしていたが、もともと運動神経がよかったおかげか、病院を出るころにはふつうに歩くことはできていた。
母も全盲者を手引きしながら歩くのはもちろん慣れていないため、とにかく何かにぶつからないように相当気を張っていたようだ。
しかし、自分の足で歩けたことはいいが、やはり平衡感覚に慣れるまでは時間がかかった。そのせいで車酔いをしたことはないはずなのに、帰りのタクシーではひどく酔ってしまった。
検査もまたすぐに控えているため地元へはまだ帰れず、お馴染みのペアレンツハウスでお世話になることになった。そこでは皆が自分の帰りを待っていてくれて、今回の手術のことを労ってくれた。
早速、お兄さんは目が見えなくなったからって何も変わらないと言い、青森と広島の高校生とともに無理やり全盲者となった自分を外に連れ出したのだった。
お兄さんと広島の子で自分の両腕をしっかりと抱え、背の高い青森の子は危なくないようにすぐ前を歩き、安全に歩行できるように4人でがっちり固めて歩いていた。まるで補導されているみたいに見えたかもしれない。
昼食を食べようと近くのファストフード店に到着すると、店に入るための階段も3人でしっかり支えてくれながらゆっくりと昇り、まったく恐怖することなく座席へと座ることができた。
皆でこうやって協力し合えば前と何も変わらないよと励まされ、やはり心の奥では沈んでいた精神も術後初めて心から笑うことができたのだった。
昼食を食べながら、この時に4人で話し合ったことがある。
自分たちの体験をいろんな人に知ってもらい、いろんな人に生きる喜びと勇気を与えよう。同じような境遇の人にいろんな情報を伝えよう。どんなに苦しくても、笑っていられる助けをしよう。
これが、いつか自叙伝を書いて皆に見てもらおうと決心した瞬間だった。
東京にいる間に、ひとつやらなければいけないことがあった。
それは義眼の作成。摘出した左目には現在、代わりとして義眼代が入れられているが、傷口が塞がったいま、きちんとした義眼を作らなければいけない。
義眼というのはその名の通り擬似的な義理の眼であるが、これをつけているかいないかではまったく見た目も違う。幼少期からずっと右目には義眼をつけていたが、骨格の変形も目立たず、あたかも両目とも健康な状態に見えて、右目が見えないなど言わなければわからないほどであった。それに義眼を眼窩に入れておかなければ徐々に骨格が変形して、目が潰れたようになってしまう。
そんなわけで、義眼を早急に作るために幼少期からお世話になっている東京の義眼の先生に連絡を取った。
義眼の先生はもう何十年も義眼を作り続けている方で、たくさんの患者から信頼されていた。年配の方ながら親身に接してくれる丁寧さや、優しくお茶目な性格もあるが、いちばんの理由はやはり、患者のためならばどこへでも駆けつけるところにあると思う。
その先生いわく、「義眼を必要とする方の中には小さな子どもも多く、わざわざ東京に連れて来るだけで大変である。私はひとりでどこへでも簡単に行けるのだから、私から訪れたほうが患者も家族も楽だろう」と、実際に連絡をしたら些細なことでも日本各地どこにでもわざわざ実費で足を運んでくれるのだ。そんな先生の温かい気持ちを信頼して、頼っている患者は多いのだ。
今回も連絡をすると、すぐにペアレンツハウスへ行くと言ってくれた。
しかし、ここでひとつの問題が発生してしまった。ペアレンツハウスの管理者が、ここで義眼を作ってもらうと商業目的と見なされて問題になってしまうと言うのだ。
これには母たち保護者が抗議した。患者から個人的にお願いしているわけで、別にその義眼の先生がペアレンツハウスに来て宣伝や呼び込みをするわけでもない。
それに、今回の自分のように摘出手術したばかりで、まだろくに歩くことが困難な患者に遠くまで行ってこいと言うのか? 他にも、移動困難な患者やまだ小さい子にも今後は外でやれというのか? 義眼は早急に必要なものでもある。
この保護者たちの猛抗議に、管理側も承諾するほかなかった。ただし、共同スペースにはその先生は立ち入らないという条件付きのため、少し肩身の狭い思いをさせてしまうのは申し訳なかった。義眼は他人が見ても気持ちのいいものではないため、もとから宿泊している部屋でしてもらうつもりだったから何ら問題はなかったのだが。
聞けば、義眼を作成・販売するのは免許や資格などは必要なく、中にはお金を稼ぐ目的だけのために適当な義眼を高額で売る人もいるらしい。そのため、今回の先生も商売目的と疑われたのかもしれない。
これからの生涯を身体の一部としてつき合っていく義眼をそういう風に扱っている人もいるというのは、本当に遺憾に思う。
こうして、無事ペアレンツハウスに義眼の先生を招き入れることができて、早速義眼作りが開始された。この時は左目の義眼を作ってもらうことが目的だったが、どうやら右目のほうも新しく作り直したほうがいいらしく、どちらも作ってもらうことになった。
先生によって作りかたは異なるらしいが、この先生はまず何もない眼窩に特殊な粘土のようなものを流し込み、これによって眼窩の中の正確な形を作り出す。最初はこの目に流し込まれる感覚が嫌で、必死に我慢していた。
眼窩の中のものが固まり、型が完成したら、予備義眼に蝋を用いて型と同じ形になるように調整していく。その間、何度も義眼を付け外しするため、段々目が乾燥して辛くなってくる。それが両目なのだから大変であった。
そして、しっかり型と同じくできたら、あとは黒目の位置の微調整をしてこの日は終了。これから先生は工房に戻り、その型をもとに義眼を作成して送ってくれるのだ。
数日後の検査の前に、義眼は届けられた。
作り直した右目のほうはとくに問題もなく、まるでふつうの目のような仕上がりだった。そして、初めて作る左目のほうは、少し入れるのに手間取りながらも何とかつけてみると、義眼自体は本当の目のようで問題はないが、やはり治療や摘出で骨核が陥没してしまい、どう見ても両目が均等ではなかった。
見た目は左目のほうが、かなり彫りが深いような状態。さらには、瞼は完全には開かずに半目の状態で、逆に寝ようと目をつむろうとしても瞼が完全に下がらない状態だった。母には寝ていても目がわずかに開いてるから、起きてると思ってしまうと言われてしまった。
これを改善したいのならやはり、形成外科に相談するしかないとのことだったが、いまさら見た目なんて気にして手術するなんて馬鹿らしく、このままでいることを決心した。
検査は、もう診察の前に眼圧検査や瞳孔を開く点眼もないためすごく楽であり、あまり待つこともなく、すぐに診察室へと呼ばれた。眼底検査ももうじっくり光を当てて見る必要もないため、義眼を外して中を診るだけの簡単なものだった。
結果はとくに異常はなく、術後の状態も良好らしかった。
そして、血液検査などのいくつかの検査をしたら、もう地元に帰っても大丈夫とのことだった。もし、その検査で他部位に転移が認められなければ、定期的な検査も徐々に間隔を延ばし、あとは何かあった時に来てくれればいい、と言われた。
よく考えたらじつにあっけないもので、摘出したらこうもあっさりすべてが終わってしまうんだと、何だかこれまでの辛い治療が無意味だったみたいで少し悲しくなった。
もし最初から摘出していたら、こんなにも過酷なことはなかったのでは? でも、すぐにそんな考えを思い直した。闘病していたおかげで様々な出会いがあり、自分にとってプラスになることばかりだったんだと。
そして、主治医はこれからの社会復帰について助言してくれた。
全盲、すなわちこれから障害者手帳を持ち、もうふつうの健常者のようには生活できなくなる。だからと言って何もできなくなったわけではなく、選択肢は大幅に減ってしまったものの、生活や仕事も訓練すればきちんと自立することができる、と。
全盲になったばかりで何をどうしたらいいのかあまりよくわからないが、これからは闘病ではなく、自立するためにがんばらなきゃいけないんだという実感は持つことができたのだった。
それから帰り支度をゆっくりして、全盲となってから初めての地元へと帰ることになった。
第3章 ■2. 暗闇の日々†
2007年2月。
久々に自宅に戻ってみると、さすがに弟は目の見えない自分に対してどう接したらいいものかわからず、不自然な対応だった。
もし逆の立場だったら、自分はどう接するだろうか? と考えてみると、中学生の弟の気持ちが少しわかる気がする。だから、なるべくいつも通りにおどけて話しかけるようにしていた。
すぐに駆けつけた祖母も手をしっかりと握って、よくがんばったねと涙ながらに帰りを喜んでくれた。いまの自分にまずできることは周りに心配をかけないことだと、とにかく変わらずの笑顔でみんなを迎えた。
ついに始まった全盲での生活。
目の見えない生活というのは何とも不便で、すぐに何とかトイレやお風呂だけはひとりでできるようになったが、家の中を歩くだけで壁や物にぶつかっていたため、体中に擦り傷などが絶えなかった。
周りの状況も見えないため、弟は母を呼んでるのに自分が返事をしたり、ここにいると思い込んで誰もいない部屋で話しかけてしまったり、部屋やトイレに明かりも点けずにいるので驚かれたこともあった。
光を感じないせいで明かりを点けるという習慣がなくなり、夜中にひとりでフラフラと歩いてるだけで母に驚かれて叫ばれたこともあった。真っ暗な中で、ゾンビのようにフラフラと徘徊してたら驚くのも当たり前である。
たまに家でひとりぼっちになると、何かあっても誰も助けてくれる人がいないことに恐怖を覚え、家のチャイムが鳴ると扉を開けた瞬間に何かされるのではと思い込んでしまい、とても出ることはできなかった。電話することもできないし、外に助けを呼びに行くこともできない。そんな環境で、何かあったらどうすればいいのだろうと恐怖が尽きなかった。
そんな風に家に篭っていると、どんどんよけいな被害妄想をするようになり、考えすぎて頭痛を起こすようにもなって寝不足にも悩まされた。さらには、頭痛がすると痛みで頭の中が支配されて、うまく行動できなくなってしまっていた。
たまに、気晴らしにと外に連れて行ってもらっても、激しく積もった雪に加えて、まともに歩けないほど凍った地面にいまの自分が耐えられるはずもなかった。玄関から出てすぐに凍った地面のせいで転んでしまい、さらに自信をなくしてしまう。
結局、全盲で生活していくことに自信をなくしていく日々だった。
そして、この時期にいちばん大変だったのが食事である。
テーブルの上に何があるのか? どこにあるのか? この皿には何があるのか?
いちいちすべてを説明してもらいながら何とか食べるが、一度手を離したらまた位置が分からなくなる。果てには、テーブルの上を探って飲み物や味噌汁をこぼしてばかり。こんな面倒なことに嫌気が差して、ご飯におかずをすべて乗っけて丼感覚で食事するのが楽であった。
とくに嫌だったのが、魚料理である。箸ではなかなか身はつかめず手づかみで食べていたが、骨がたくさん入っている時にはもう食べるのすら諦めていた。魚は好物なのに段々と食べる機会が減り、食べたとしても骨の少ない鮭やホッケが多かった。
醤油やソースなども加減がわからず、目玉焼きが醤油の海に沈んだ状態になってしまったこともある。ご飯にではなく、味噌汁にふりかけをふりかけてしまったこともある。カップラーメンの中にかやくの袋が残っていて、食べてしまうところだったこともある。
すべてが手探り状態な毎日だったが、それにしてもとにかく毎日が暇であった。
テレビは見えないから楽しめない、ゲームももちろんできない、話し相手もいない、外にも出られない。この時に唯一できる暇つぶしは、音楽を聴くことだけだった。
これまでは何となく流していた音楽も、することがないせいかじっくりと聴くようになった。
メロディーを構成するひとつひとつの楽器の音色。よく考えながら聴くと、すごく深い意味の込められた歌詞。とにかく一曲一曲をじっくり聴いて、自分なりに好きな歌詞を選んだりしていた。
そこでよく聴くようになったのが、Gacktさんとコブクロさんだった。とくにGacktさんの「Dears」という曲とコブクロさんの「轍」、「光」という曲の歌詞が心に響いて、何度も何度も聴いていた。
「Dears」は闘病戦隊の5人のそれぞれの思いのような歌詞で、「轍」はいつも誰かが見守ってくれているように勇気づけてくれるような歌詞で、「光」はまさに全盲者で光を失った者たちに対してのエールのようだった。そんなわけで、すっかりGacktさんとコブクロさんのファンになってしまい、何度もアルバムなどを聴いていた。
とある日、音楽という少しだけの暇つぶしを見つけて過ごしていると、中学からの友人が急に訪ねてきた。
闘病中も頻繁に連絡を取り合っていた友人で、今回、全盲となった自分にいい情報があると教えに来てくれたらしかった。
その情報とは、全盲者でも使える携帯電話だった。もともとは視力が弱くなり、老眼となった年配者用に開発された機種らしいのだが、すべての操作を音声で教えてくれるものらしい。
ドコモの“らくらくホン”という機種で、一度ドコモショップで触らせてもらってみたらいいよ、と友人は勧めてくれた。このころは完全音声対応の機種はこれしかなく、後からわかったのは全盲者のほとんどがこの機種を使用していることだった。
早速、ドコモショップに連れて行ってもらい、その機種を触らせてもらうと、確かにすべての操作を音声で伝えてくれて、これなら目が見えなくてもふつうに使える感じであった。
その場ですぐに契約して、久々の携帯電話がうれしくて無我夢中でいじっていた。電話はもちろんメールもちゃんとできるし、何よりインターネットで暇つぶしもできる。誰かに聞かなくても時間の確認もできる。
もともと機械に多少強かったので、ものの数時間で使いこなし、この時ネットをしながらあることを思いついた。
それは、ホームページの作成。せっかくネットもできるし、携帯でならば文字も書けるのだから、ホームページで自分のことをいろんな人に知ってもらおうと考えたのだった。
早速、レンタルサイトを見つけて、作成に取りかかった。携帯電話で、それも音声だけでの作成はやはり難しく、何度もやり直しながら、気がつけば深夜まで作業に没頭していた。
そうして数日かけて完成したのが、「希望の光の部屋」というホームページだった。できあがったと同時に、家族や友人などたくさんの知人に宣伝し、見てもらった。
ホームページの内容は日記に闘病記、それに網膜芽細胞腫の情報や相談窓口なども作り、慣れてくると小説や詩集などもやっていた。その反響はすごいもので、最初は目が見えない人が作ってるなんて嘘だろうとも言われたが、自分を直接知っている人たちのおかげで、しっかりと全盲者のホームページとして認知してもらえるようになっていた。
ホームページをやり始めてからは暇だった日々が一変し、何かと忙しい毎日となっていた。
ここならば日々の本音も書きやすいと直接言えないような弱音や悩みなどを書いて、その度にたくさんの人から励ましてもらった。逆に、自分と同じ病気で悩む家族たちの相談に乗ったりもして、直接患者や家族どうしで集まれない状況の中でこのホームページは感謝されてもいた。
そんな中でも、遊び半分に匿名での批難や中傷の書き込みもあり、ネット社会の心ない部分に憤りを感じることもあった。なぜわざわざ、自分のホームページに訪れて「かたわは引っ込んでろ」なんて平気で書けるのだろう? と疑問でならなかった。
2007年5月。
1ヵ月に一度、定期検査をしなければいけないため、東京の国立がんセンターへとやって来た。
今回もとくに異常はなく、無事検査も終えて小児科病棟へと向かっていた。先日、闘病戦隊の青森の高校生の子の容態が急に悪くなり、ここに入院したという連絡が入っていたのだ。
タイミングよく東京に来ることになったのでお見舞いに訪れたのだが、青森の子はいつも通りの様子で迎えてくれた。しかし、無理して応対していることが何となくすぐにわかってしまった。何となく、何となくだけど、眼球摘出を決心した時の自分に雰囲気が似ているような気がした。
とても精悍な顔つきで背の高い彼は、きっと通っている高校でも人気のある生徒なんだろうとわかる。過酷な治療によって細くなった身体ながらも、全盲になった自分を気遣って支えてくれていた。そんな心優しい彼だからこそ、いろんな人が周りに集まるのだと思う。
彼は、「病気だからこそ」というブログをしていた。日々の辛さや日常のことなどを書き連ねている。地元の友だちからのたくさんの応援メッセージは、きっといつも励みになっていることだろう。
そのブログの更新が止まったのは、これから間もなくの6月2日のことだった。
地元である室蘭にいる時に連絡を受け取り、母とともにふたりですぐ青森へと向かった。
青森の子の母はとてもおしとやかで優しい方で、はるばる青森に訪れた自分たちを厚く出迎えてくれ、そのまま母とともに葬儀に参列した。
気が遠くなるくらいの長期間、必死に闘い、時には苦悩し、それでも負けずに最後まで闘い抜いた戦友は、とても安らかに眠っていた。ずっとそんな彼に勇気をもらっていた。だから、泣いて言葉にもならない声でひと言、「お疲れ様。本当にありがとう」と手を合わせた。
いとも簡単に平気で自分の命を絶ってしまう人もいる世の中、生きたくても生きられない人たちもいる。生きるために辛いことをたくさん乗り越えなければいけない人がいる。
でも、決してかわいそうなんて思われたくない。彼らは必死に生きて、闘って、やり切って生涯を過ごしたんだ。だから最後は称えてほしい。「本当にがんばったね」と。
そして、ずっと忘れないでほしい。本当にがんばった彼を。忘れないでいてくれたら、必死にがんばってよかったと思えるはずだから。
自分にとってこの出来事は、悲しみを感じるよりも強く決断させるものであった。彼の分まで、生きられるだけ生きなければいけないという使命感。いつまでも全盲だからと怯えて甘えた生活ではいけないと、心を打たれた気分だった。
ここから自立への道を真剣に考えるようになり、とにかくいま自分にできることを探すために行動を始めるのだった。
忘れるところだった。
暗闇の向こうには笑顔を。だから、怖がってはいけない。暗闇の向こうが笑顔の光であるように、くじけるわけにはいけない。
これから自分も誰かの光になれるように。
ガラッと気持ちを切り替えて、家では母や弟と笑い合えるようにつねに明るく振舞った。
家の中を無駄に歩いて壁にぶつかって、わざと転げて笑わせた。狭い部屋で前転して、お尻で壁に穴を開けて笑われた。つねにくだらないことで会話して、笑い合った。
友人が来てくれても、見えていた時と変わらず楽しんだ。見えなくても、いっしょにゲームだってしていた。
何となく気を遣ってくれていた周りから少しずつ笑顔が増えた気がして、自分もよく笑うようになっていた。
そして、さらに暗闇を進み続ける。前へ、前へ。暗闇の先を目指して。
第3章 ■3. 前に進むために†
2007年7月。
まずとにかく、いろんな情報を聞いてまわった。
そして、地元の福祉センターに訪れ、まずは全盲者が歩くための必需品である白杖を申請した。
それからは外出を増やして、できるだけ白杖を使いながらの歩行をするようになった。だからと言ってすぐにスタスタと歩けるわけもなく、母に見ててもらいながら歩き、時には段差に躓き、壁にぶつかってしまったりもした。電柱にぶつかったのを人だと思い、謝ってしまったのは思い出すだけで恥ずかしい。
東京へ検査に行った際には、いろいろな情報を聞くために同じ病気で同じく全盲だという方を紹介してもらった。
その人は全盲でありながらひとりで暮らしており、もちろん身の回りのことはすべて自分でこなしながらしっかりと働いているというのだ。今回、自宅からペアレンツハウスまでも電車を乗り継いで来なければいけないのに、ひとりで訪れた時は驚いた。東京の電車なんて、混雑していて見えていても歩くのが大変なのに、もうすっかり慣れたと教えてくれた。
その人に夢中で生活のことなどを聞いていた。後日、その人の自宅にも招待してもらったが、本当に自分たちを案内するように前方をひとりでスタスタと歩き、自宅の中でも見えているかのように行動し、簡単な料理までふるまってくれた。
聞けば、その人は旅行などもひとりで行き、スキーまでするというのだから驚かされてばかりだった。同じ病気で同じ全盲ということですっかり心を開いてしまい、これから先、いろんな面でこの人から学ばせてもらうこととなった。
この人は自宅の近くに出ている屋台のなんこつつくねが大好きで、ネット内で「なんこつつくね」という名前で、自分と同じく日記を書いたりもしているみたいだった。早速、ネットの中でも繋がりを持って、本当に様々なことを学んで地元へと戻ったのだった。
ある日、母がとある友人から全盲者の行うスポーツの情報をもらった。
それは、「ブラインドサッカー」という全盲者が行う球技であり、まったく見えない状態でサッカーをするというものだった。実際に母が映像を見てみると、確かに選手は全員アイマスクをつけてプレイしており、当時は本当に信じられないようなものだった。
しかし、目が見えている時からサッカーをするのが好きだった自分にとって、全盲でもサッカーができるんだと希望を持たせてくれる情報だった。少し残念だったのは、地方にはチームはなく、それなりに大きい都市に行かなければできないということだ。
それから、このブラインドサッカーの情報を集めつつ、生活の訓練も同時に始めた。掃除に洗濯に加えて、料理もできる限りやってみて、最初は見てもらいながら駄目な部分を改善させるようにしていた。
そんな自己流で訓練していく日々の中、ある施設の存在を教えてもらった。
それは、盲学校というもの。何となく聞いたことはあったが、盲学校は全盲や弱視の視力障害者の人が行く学校である。
ここからいちばん近いところで探してもらうと、札幌と函館に存在するのだという。さすがに室蘭近郊にはないかと少しがっかりしながらも、盲学校について詳しく調べてみた。
どうやら自分のように中途失明で生活の訓練をしたい場合は、函館のほうが合っているということがわかった。函館のほうは盲学校というよりは、視力障害者の自立支援を目的とした施設らしく、視力障害センターというらしい。
早速、住所と連絡先を調べて直接問い合わせてみると、まずは見学も可能ということだったため、すぐに母に頼んで函館へと連れて行ってもらうことになった。自分と母にとって函館は久しぶりとなるわけだが、母はしっかりと道を覚えており、ふたりで街並みを懐かしみながら施設へと向かった。
こうして辿りついた函館視力障害センターは、母が言うには思ったよりもきれいな大きな建物で、4つの建物がそれぞれ渡り廊下で繋がっている変わった造りだった。聞けば改築してまだ間もないというのだから、新しい建物と言っても過言ではないだろう。
正面玄関から中に入って受付に名前を告げると、程なくして職員の方が出迎えに来てくれた。まずはどんな施設なのか説明してくれるらしいので、別室へと移動した。
中は本当に視力障害者のために作られたような設計となっており、室内にも関わらず点字ブロックがあり、廊下にも手すりが付いていた。しかし、ひとつ難点があるとすれば、広大な建物に加えて迷路のように変わった造りの場所もあるため、慣れない全盲者は建物内でも迷ってしまうことがあるらしい。
面談室に入るとまず、どのような訓練を受けたいのかを聞いてきたため、望んでいた通り、自立するためにまずはひとりでも家で暮らせるような訓練を希望した。すなわち、ひとりで家事と外出ができるようになりたい、と。それに関してはもちろん問題ないとのことだった。
次に告げられたのは、もし訓練するとしたら建物内の寮に入るか、近所にアパートを借りて通学するかしなければいけないということだった。しかし、うちは二重生活ができるほど裕福ではないし、何より外出できるようになるために訓練するのだから通学はできるはずがない。そんなわけで、訓練を受けるとしたら寮に入るしかないということを伝えると、寮の部屋も見学させてくれるということで、早速見に行くことになった。
寮に向かいながら言葉で説明してもらった情報によると、この建物は先程外から見た通り4つの建物が繋がっている構造で、宿舎棟、教室棟、厚生棟、管理棟の4つからなるらしい。
宿舎棟はその名の通り、3~5階は男子寮、2階は女子寮とパソコン室、1階には共同洗濯室や共同浴室、宿直室、生徒玄関がある。
教室棟は、様々な訓練や授業を行うための教室が1~3階に並んでいる。
厚生棟は、1階が食堂で、2階が体育館となっている。
最後の管理棟はいちばん道が複雑で迷いやすいらしいが、1階に正面玄関と庶務室と署長室、2階に職員室と支援課室と面談室、3~4階は実習室、5階は図書室と大会議室がある。
これら4つの建物をそれぞれ2階の渡り廊下で繋いでいる建物だった。こんなことを歩きながら説明されたが、歩行に集中していたため、この時は話の半分も聞けずに終わってしまった。
寮に着くとエレベーターで3階へと登り、出てからすぐそばにあった部屋へと通された。
利用者の使うその部屋はとても広くて、恐らく10畳以上はあるのではというほどだった。どうやら以前までは3人部屋として使っていた部屋で、利用者の減少に伴い、現在は3人部屋をひとりで使っている状態らしく、広いのも頷けた。
その部屋には洋服箪笥と机と椅子とロッカーがそれぞれ3つずつ置いてあり、内線専用の電話がひとつ、そして扉と対面する位置に窓がひとつあった。窓の外は外周が繋がっているベランダになっているらしい。
さらにその後、共同スペースや食堂なども見学させてもらい、もし訓練を始める気になったらいつでも連絡をするようにと言われて、その日はひとまず帰路につく運びとなった。
もしここに来れば、望んでいたような訓練が受けられる。でも、寮に入らなければいけないということはほぼひとり暮らしするようなものだ。それに、地元から汽車で2時間もかかるため、家族や友人がこれまでのように助けてくれることは難しくなる。恐らく何らかのサポートはあるのだろうが、それでも全盲の自分が知らない場所、知らない人の中で暮らすのは考えるだけで震えるほど怖かった。
でも、このままではいけない。このままでは何も変わらない。まず一歩踏み出すためには、自分自身の足で進んで行動しなければならない。
視力障害センターを出た時からずっと考え込み、まだ函館の町を移動している間に決心した。母には出戻りになってしまい申し訳ないが、決心した気持ちを伝えてすぐに契約するために、Uターンして視力障害センターへと引き返した。
ただの意地やその場の勢いであったかもしれない。けれど、この時行ってよかったとは思っても、決して後悔はしていない。きっと誰かが、自分の心の中でいまやらなきゃ駄目だと後押ししてくれたのだと思う。
入所の契約を済まして、しばらくは役所とのやり取りや受け入れ準備に時間がかかると言うので、ひとまずは地元へと戻ることとなった。
すぐに地元の親戚・友人・知人に伝え、自己訓練を始めてからなかなか更新できなくなっていたホームページにもこのことを記載した。
地元の皆は、行ってしまったら次はいつ帰って来られるかわからないから盛大に送り出すと、毎日のようにいっしょに騒ぎ、立派になって帰って来い、と熱く激励した。思えば、この何か決意して行動する度に皆で集まって騒ぐのも恒例の行事となってしまった。
そんな皆の気持ちに応えるために、さらにやる気を漲らせ、ひとり旅立つ恐怖が一変してまだかまだかと行ける日を待ち遠しく思うようになっていた。
しかし、時間がかかるというのは本当で、結局数ヵ月手続きに時間を取られてからやっと、入所日が決定した。
その間も自己流での単身訓練は続き、周りの友人たちも協力してくれて、そのうち楽しみながら訓練ということで料理大会なども開催した。友人10人ほどでそれぞれ料理を作って来て、投票にて順位を決めるという催しで、調理訓練になると同時にとても楽しみながらやることができた。
時には気分転換にドライブにも連れて行ってもらい、友人とともに車の中で大熱唱したり、みんなでバーベキューしたりと、このころは本当に行動が活発だった。
そして、そんな楽しみながらの訓練の日々はあっという間に過ぎて、ついにこの日はやってきたのだった。
2007年11月26日。
11月22日に22歳の誕生日を迎えてから、函館へと旅立ったのだった。
ーー第3章 おわりーー
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
『エンターテインメントという薬 -光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの-』特設サイトはこちら
- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第3章 全盲生活