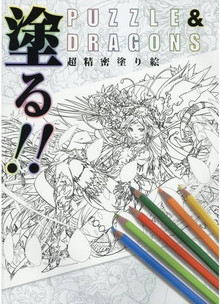- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第2章 再発
劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第2章 再発
公開日時:2018-11-01 19:00:00

|
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
第2章 ■1. 洋の成長と日々のこと†
僕はまだ小さいときに右目を失くした。母から聞いた僕の物語をここに綴っていく。
網膜芽細胞腫の治療を終えてからの数年、定期的に東京の国立がんセンターで検査を受けていたが、途中、眼球内のあやしげな影に不安を覚えることがありつつも、大きな問題にはならなかった。
それは紛れもなく、検査する必要がなくなってきた=再発の危険がなくなってきた、と判断できることで、不安を忘れさせてくれた。
がんには5年説などの話もあるが、小児がんというのは発症も再発も就学前の時期が圧倒的に多く、そこを過ぎると安心できるのだ。
物心がつき、難なく視力を測れる歳となってもつねに1.0の視力を保ち、片目が見えなくとも不自由さを感じさせず、ふつうの子に負けないくらい活発に育っていった。
義眼を毎日洗浄しなければならないため保育園生活も心配されたが、園長先生や他の先生の理解のもと無事に入園できた。もともとの明るい性格から友だちもたくさんできて、運動会や遠足など毎日楽しく保育園に通っていた。
日々の生活の中では猫を飼い始め、近くに住んでいる祖父母や叔母とともに楽しく過ごしていた。
少し気になるとしたら、多少でもばい菌が目に入ると目やにがひどくなるくらいだった。
そうして病気のことを忘れてきた数年後、母は再婚し、義理の父となる人物とともに同じ道内の函館で新たな生活を始めることになった。
いままでお兄さんと呼んでいた人を急に父と呼ばなければならない環境に少なからず戸惑いはあったが、実父の思い出はもちろん、顔すらも知らないため、とくに新しい父という意識もなく、何より母が幸せそうにしているのですんなり受け入れることができた。自分ではわからなかったが、やはり他人の家庭を見て父親という存在が羨ましかったのかもしれない。
経済的には裕福とはほど遠い家庭だったが、両親がいつも傍にいてくれる。そんな3人で過ごす平凡な毎日がいちばんの幸せだと感じていた。
無事にふつうの小学校に上がることもでき、片目では大変なはずの野球・サッカー・空手・習字などを積極的に習い、ふだんは自転車を乗りまわしてどこへでも行くような、活発でチャレンジャーな子どもだった。活発すぎて自動車に跳ねられたことも数回あるくらいなので、両親にはいつも心配をかけていたかもしれない。それでも、ずっと牛乳ばかり飲んでいたおかげで骨は丈夫らしく、大きな怪我はしたことがなかった。
片目で過ごすことにも慣れていて、他の子と違いがわからないほどで、多少遠近感などにハンデを抱えながらも、たくさんの友だちと元気いっぱい遊ぶ毎日だった。
時々、片目が義眼のために斜視(双方の黒目が違う方向を向いている)に見られて、からかわれることもあったが、持ち前の明るさで難なく乗り越えた。時にはわざと義眼を外して、友だちを脅かしながら追っかけまわしたこともある。
そして、そんな楽しい日々を送り、9歳になったころ。弟となる翔が産まれた。
少しの間、親戚の家に預けられて寂しい生活だったが、母が戻って来ると新しい家族が増えていて、とても幸せを感じた。
ただ、幸せな気持ちとは裏腹に、やはり生まれてきたばかりの弟が優先され、一時期かまってもらえない寂しさから「家出をしようかな」という悲痛な詩を書き、それが共感されて市のコンクールに入賞したこともあった。
そんな思いに気づいた母が気を遣ってくれ、何より弟がなつき、慕ってくれたので、再び幸せを感じるようになっていった。
そんな中、10歳の時に事件は起こった。
仕事がうまくいってなかったらしく、何度も転職をくり返していた父が、知らぬ間にサラ金から大金を借りて、ついには返済に困窮してひとりで逃げてしまった。
少し前から出稼ぎと言われ、自宅にしばらく姿を見せなかったため、その意味がわからずにただ唖然としていたが、母は悲しみと怒りに震えて静かに泣いていた。そんな母にかける言葉もわからず、弟を抱きながら人知れず涙があふれてきた。
母は涙を流しながら謝罪し、父の現状をわかりやすく教えてくれたのだった。
「翔まで僕と同じ思いをしなきゃだめなの? そんなの僕だけで十分なのに」
そんな言葉がふいに出てしまって、さらに母を泣かせてしまった。父に捨てられた悲しみを弟も味わうことになると思うと、悔しさでいっぱいだった。
それを聞いた母はふたりの我が子を抱きしめながら、心を痛めてしばらく涙が止まらなかった。
その後、3人での母子家庭を強いられるも、周りの協力もあって裕福でないながらも何とか生活していた。
母によけいな心配をかけまいとこれまで以上に明るく振舞い、弟もまた毎日無邪気に笑っていた。
それでも母は、子どもたちに不自由をさせてしまっていると責任を感じていた。そして、知人の紹介から再婚することを決心した。
自分の父でもなく、翔の父でもないまったくの他人、それどころか今度は一度すら会ったこともない人。母ですら初めて会う人物だった。さらには母と20ほども歳が離れている。
最初は戸惑いを隠し切れなかったが、母と弟がいっしょなら何が起こっても平気だと思い、母を信じることにした。それでも、子どものことだけのために急に決めた結婚で、母は幸せなのか? まだ物心つかない弟はこれからどう感じるのか? 子どもながらに不安でいっぱいでもあった。
とにかくこの時は、長男であり兄でもある自分が母と弟を支えなきゃと、持ち前の明るさで家族を一生懸命盛り上げていた。
母の再婚に際して小学校も転校となり、幼馴染や保育所からの友だちと涙の別れを済ませた。幸い、転校先でもたくさんの友だちに恵まれ、学校生活は変わらず楽しく過ごすことができた。
さらに、捨て犬を拾って新たな家族も増え、いつも家族でどこかに遊びに出かけて、時には弟と愛犬とじゃれ合い、家族がいつもいっしょにいられる喜びを噛みしめることができた。
新しい父親は基本的に出稼ぎに出ていたため、ほとんど家にはいなかった。年に数回帰ってきて、たまに無愛想に散歩に連れて行ってもらうくらいのつき合いしかなかった。そんな数回しか会ったことのない人を父と思うのは、正直無理があったと思う。ほとんど家にいないおかげで、無理やり接しなければならない苦しみは少ないのが幸いだった。
そんな生活に限界が来るのは、そう遠くなかった。
やはり急遽決めた再婚相手で、家族に愛情を感じてくれているのかという疑問が強くなってきた。逆に、家族として父を認められないでいる申し訳なさもあった。そんな思いから、母も少しずつ精神的に疲れを感じ、体調を崩す日が増えてきた。
そして、再婚から2年弱で母と話し合い、最終的に離婚し、実家がある室蘭に戻ることを決めたのだった。
幸せになるために無理をしてしまっては意味がない。母はどんな大変な生活になってもふたりがいてくれればそれだけでいい、と言ってくれ、まだ小さな弟も笑顔を見せてくれて、その日は寂しさを紛らわせるため3人でいっしょに寝たのだった。
数日後、ほとんどかわいがることもしなかったにも関わらず、父方の親戚が翔を置いていけなどと言ってひと悶着あったが、母は父本人との話し合いですんなりと離婚を成立させ、室蘭の祖父母のいる実家の近くへと引っ越した。
再び貧乏な生活となり、最初はお風呂のない団地に住まなければならなかったが、狭い家の中で家族がいつでも見える安心感があって、とても幸せだった。目玉焼きしかない食事も、とてもおいしかった。
何度も転校をくり返すことになってしまったが、明るい性格からすぐに友だちもでき、学校生活で悩むことがなかったのは母にとって救いだったようだ。
母はそれから休む間もなく一生懸命働き、自分も中学校に進学してからは自分のお小遣いと弟にもお小遣いをあげたいと思い、新聞配達のアルバイトを始めた。
何ひとつ不自由に思う生活ではなかった。学校が終わったらアルバイトをして、終わったら仲よしの友人と遅くまで遊んでいた。
家では夜勤の母の代わりに夕食を作り、弟とふたりでゲームをする毎日。勉学には不真面目で成績は褒められたものではなかったが、学校生活も家庭でもいつも楽しく過ごせていたと思う。
時に母が家に彼氏を連れて来ることもあったが、まだ若い母からしたら色恋沙汰も必要なのだろうと応援することにしていた。何より自分も恋人ができて幸せを感じていた時期でもあったので、その気持ちをわかったつもりになっていた。
そして、希望の高校にも合格し、相変わらずアルバイトをしながら、小学生となった弟にお小遣いをあげ、お世話をし、弟にとっては父親代わりのようになっていた。
勉学にはやはり不真面目だったため、長期休暇の補習は常連だった。アルバイトも仕出し屋に魚屋とより忙しくなっていたが、疲れを見せることはあっても、本当に楽しい高校生活を送れていた。
小学生の弟は、体が逞しいことを生かして柔道や太鼓、よさこいなどを習い、毎日楽しそうに過ごしていた。どこで覚えたのか、多少言葉づかいが悪くなってしまったのだけは将来的に少し心配ではあった。
それまで夜に働いていた母は昼間働くようになり、家族3人と近距離にいる祖父母の支えのもと、ふつうの家庭に負けないくらい不安のない時間が過ぎていった。
高校生活にも慣れ始めたころ。突然の訃報が伝えられた。
上京していた母の弟、自分にとって叔父が仕事中の事故で亡くなったというのだ。叔父は高層ビルの窓ふきの仕事をしていて、安全装置不十分による転落事故と聞かされた。
まだ30歳ほどだった叔父。趣味にバンド活動をしながら大型バイクを乗り回していて、いつも優しい叔父を「兄ちゃん」と呼び、本当に慕っていた。
幼少期、闘病している時も学生ながらアルバイトをして支えてくれていた。叔父本人も学生時代にバイク事故で片目の視力を失っており、片目であることにいちばん理解もあった。東京へ定期検査に行った際には、いつもバイクに乗せて東京を連れまわしてくれた。
そんな叔父が亡くなったなんて、本当に信じられなかった。母もまた自分以上に叔父を敬愛していたので、その悲しみは計り知れない。
淡々と進められる葬儀に、ただ涙を流すしかできなかった。
人の命とは、何て簡単に消えてしまうものなのだろう。なぜあんな心優しい叔父がいなくならなければいけなかったのだろう。
初めて大切な人を失う悲しみを知った。
それからしばらくは、自分も母も祖母も立ち直れなかった。
でも、叔父の分まで生きなければいけない。どこかで見ていてくれるかもしれないから、幸せを見せてあげなければいけない。ずっと病気のことを心配してくれていた叔父のために。
そう強く信じて、叔父の死を乗り越えたのだった。
その後、高校を卒業し、片目のため心配だった自動車の普通免許も無事に取得でき、早く自立したかったこともあって地元のパチンコ店へと就職した。
パチンコ屋は二交代勤務で休みも少なく、重労働のため疲労は多かったものの、体力には自信があったので難なく乗り切れたし、上司や同僚にも恵まれて楽しく仕事をこなすことができた。
仕事のためと目押しの練習をしていたら、気晴らしにパチスロを打つようになってしまったのは反省しなければいけないと思う。
こうやって少しずつ時間は流れて、これから働きながら結婚とかして幸せな家庭を作りたいな、とかぼんやり考えていた。
絶望から始まり、何度も崖から突き落とされた人生が、一歩ずつ幸せに向かっている……はずだった。
そんな希望に満ちた毎日をなぜ続けさせてくれなかったのか?
必死で生きてきた自分たちが何をしたと言うのか?
誰でもいいから教えてほしかった。
順調に昇り始めた階段から突き落とされるのは、それから間もなくのことだった。
第2章 ■2. 網膜芽細胞腫の再発†
2004年11月。
19歳の誕生日を終え、仕事は大変ながらも職場のみんなは優しく、楽しくて毎日が充実していた。仕事内容にもだいぶ慣れて、活発に仕事をこなすので同僚にも頼られるようになっていて、こんな日々がずっと続けばいいなと思っていた。
その日、いつものように仕事を終えて、帰宅してからお風呂につかっていた。やはり仕事は楽しくとも重労働には変わりなく、疲れが溜まっていたせいか、いつの間にか湯船の中で眠りに落ちていた。
しばらくして、のぼせる前に目を覚ましたら、何かがおかしかった。唯一、視力のある左目の視界の中に、何かドロドロした虫のようなものが見えている。言うなればアメーバのようなものが視界の一部でうごめいていた。ただ、その時はさほど視力の妨げにもなっていなかったし、疲れのせいだから眠ればなくなるだろう、とあまり気にはしていなかった。
しかし次の日、さらに次の日になっても、それは消えはしなかった。それどころか、日が経つにつれて少しずつ増えているような気がする。
しばらくはすぐよくなると信じ、見えづらいのを我慢して過ごしていたが、ついに仕事に支障が出るほどになり、車の運転も困難となってしまったのだった。
その時点で見えるのは視界のほんの一部(5円玉の穴ほど)で、さすがにふだんの生活すら危うくなってきたため、母と心配して駆けつけた祖母の3人で眼科にかかってみることにした。
地元でいちばん大きな総合病院に到着し、診察の順番を待つ間、売店で本を購入して暇を潰そうとしたが、やはりこの時にはほぼ視界を埋め尽くしていたものが邪魔で、読書すら困難であった。
しばらく待って、やっと簡単な眼底検査してもらった結果は、恐らく何かの弾みで眼球内で出血してしまっただけだから時間が経てばよくなる、というものだった。
単純にその診断結果を信じて安心したが、母と祖母はやはり不安に思うのか、医者にもっとしっかり検査することを嘆願した。
必死に訴えられた医者は再度検査することを了承し、薄暗い別室へと連れて行かれた。
そこでは仰向けにされ、瞼を閉じられないようにする金具をつけられた後、約30分かけてさらに眼底検査をされた。
瞼を強制的に開く金具が思ったより痛いのと、ずっと目を開いていなければならない苦痛に、体だけもがいて我慢するしかできなかった。
長い時間かかったこの検査の結果は先ほどの診断と違い、出血で確認しづらかったが奥のほうに薄っすらと影が見える、とのことだった。
しかし、それ以上はこの病院では調べることはできないらしく、札幌の医大病院を紹介されることになった。
「さっきの診断を信じて何もしなかったら、どうなっていたか」
そう言って怒りを隠し切れない母と祖母とともに、その日は一度帰宅した。
実際、地方の病院では難病や珍しい病気などは発見できず、手遅れになってしまうこともあるらしい。自分が乳幼児のころに発症した網膜芽細胞腫もその例外ではなく、各地の病院でポスターを貼るなどの運動も行っているくらいなのだった。現在では各地の眼科医も知識をつけて対応できるようになってきたようだが、まだまだ安心はできない。とくに小さな子どものことに関しては、家族が知識を身につけて的確な対応をしなければいけないのが現状だ。
次の日、何が起こっているのかと底知れぬ不安を抱えながら、紹介された札幌の医大病院へと向かった。
ほとんど目が見えない状態だったため母に引きずられるように歩き、移動だけでもすごく長く感じながら医大に着くと、いつものように瞳孔を開く散瞳の目薬をさされ、さらに目が見えない状態で1時間以上の待ち時間を何もせずに過ごすこととなった。
暇つぶしもできない状態でただ座ったまま時間が過ぎ、やっと名前を呼ばれてすぐに眼底検査をした結果。やはり、出血の奥に何かケバケバした物体があり、さらに詳しい精密検査が必要とのことだった。
最悪の事態を想定して早急に精密検査をして、結果次第ではレーザー療法で治療を行うなどの説明を受けた。
この診断に母と少し話し合い、最悪の事態を想定するなら東京に行かなければいけないと考えた。
医大の先生としても一刻も早く検査したほうがいいという考えらしく、その日は紹介状を受け取って帰宅し、翌日、朝早くから発つことにした。
急な事態に戸惑う暇もなかったが、たぶん何ともない。すぐに治る、と自分に言い聞かせ、とにかく幼少のころのことをなるべく考えないようにしていた。
翌朝には早速、母とともに東京へ向かっていた。地元の室蘭から東京まではバスや飛行機などを乗り継いでかなり移動に時間がかかるのだが、目が見えづらく、何も暇を潰すことができないため、より長い時間に感じてしまった。
そして、東京に到着するとタクシーに乗り、そのまま国立がんセンターへと直行した。
ここには幼少時からずっと診てもらっている網膜芽細胞腫に関しては権威の先生がいて、この日本の中でもっとも確実に自分の病気について知っている。だからこそ、その先生に現在不安に感じていることをすぐにでも否定してほしかった。たいしたことないよ、と。
病院に到着して、まずは視力や眼圧を測るが、視野は低下してるものの視力は問題なく、眼圧も出血のせいで多少上昇している程度だった。
その検査をした看護師は幼少時にもよくお世話になっていた人で、自分たちを見るなり何かあったのかな? と心配してくれていた。
それからまたしばらく待っていると名前を呼ばれ、懐かしい先生と対面した。
相変わらず無愛想な先生は、慣れた手つきで手際良く眼底検査をした後、じつにあっけなくひと言だけ口にした。
「再発だね」
時が止まる、というのをこの時初めて経験した。
長い時間にも思えたが、実際は数秒間茫然として、それからやっと口が開いた。そんなひと言だけ言われても簡単に実感が湧くはずもなく、いま聞こえた言葉をしつこいくらいに聞き直していた。
がんの5年説というのは? そもそも幼少時の小児がんが19歳になったいまごろ再発なんてあり得るのか?
いつまでも納得できずにいると、先生は淡々と次の言葉を続けた。
「化学療法したほうがいいな」と、抗がん剤治療を提案したのだった。
もう決定なのか? 誤診ではないのか?
さすがにいつまでも動揺を隠し切れないでいると、先生は念のため別の先生にも診てもらうことにし、ふたりは別室に移された。
網膜芽細胞腫のいちばんの権威である先生以外に診てもらって意味はあるのか? という疑問はあったが、どうやらこの権威の先生はもう定年退職で、これから治療を続けていくなら別の先生に診てもらうことになってしまうらしい。
そして、権威の先生の弟子として網膜芽細胞腫の研究を手伝ってきた唯一の先生だったため、 必然的に今後はこの新たな先生を頼っていかなければならなかった。
その人は一見若く、初めて診てもらうので信頼できるかどうかわからなかったが、眼底検査をする手つきはとても慣れたものだった。
検査の結果は、確かに腫瘍らしきものが見られるが、再発と決めつけるのは早いとの見解だった。まずは見えるものの細胞を採取して調べるべきだ、と診断した。しかし、細胞を採取するには眼球に針を刺すため、腫瘍が破裂して飛び散るなど網膜剥離の危険性があるとのことだった。
すぐにでも化学療法で治療するべきと言う権威の先生と、まずは危険を承知で詳しく検査するべきと言う新しい先生。
それぞれ違う意見を説明し、あとは自分自身で決めなければいけないとのことだったが、そんな重要なことをすぐに決められるはずもなく、ただただ混乱していた。どうしたらいいのかわからなかった。それ以前に、現状をとても受け入れられない。
母はそんな苦悩する息子を、涙を堪えながらただ見守っていた。母の中でも昔のことを思い出し、いろんな思いが交錯していたことだろう。
先生たちはどちらにせよ抗がん剤治療は避けられないと説明をつけ加え、ひとまず小児科に向かい、そこの先生から抗がん剤についての説明を受けて、すべてを決めることにした。
国立がんセンターの小児科は眼科と同じ場所にあり、移動することはないのだが、少し考える猶予を与えられ、慣れない緊張感から解かれたからだろうか。安堵とともに胸を撫でおろすことができた。
しかし、やがて始まった小児科医の話は、さらに悩ませ苦しめるものだった。
まず、抗がん剤には各種の腫瘍に効果のある様々な種類があるのだが、そのすべてが人体に有毒で、必ずと言っていいほど副作用が現れ、さらにはつねに様々な合併症や二次がんの危険性と隣り合わせだという。
副作用に個人差はあるが、高熱・気だるさ・嘔吐・血液数値の異常・口内炎・抜け毛など、ほかにもたくさんある。
そして、今回のようなケースでいちばん怖いのは、長期間に及ぶ抗がん剤治療中の腫瘍の破裂や、転移してしまうことで、そうなると命の危険度がさらに増すようだった。眼球内にある腫瘍のため、転移するとしたら視神経から脳に達する可能性が高いのだ。
さらに、腫瘍自体を調べてから始めないと手さぐり状態で抗がん剤を試すこととなる。もし、本当に網膜芽細胞腫なら効果のある薬を用いるが、仮にまったく別のがんだった場合、意味のない抗がん剤を使用することになる。新しい眼科の先生が危惧してまずは検査しようとした理由がこれだった。
小児科の先生は、そのすべてを説明すると最後に、「命を大切にするなら、いますぐにでも眼球を摘出するべきだ」と言った。
国立がんセンターの小児科の先生は様々な難病の子どもたちを診るため、第一に「命を守りたい」という考えのもと治療しているのだ。未来のある子どもたちの命を預かる者として納得できる考えだ。例え、身体の一部が欠損してしまうことになろうが、命には変えられない。
必死に説得してこようとする先生からその気持ちがひしひしと伝わったし、命を心配してくれているのは本当にうれしかった。
それでも、摘出だけは絶対に嫌だった。それだけはすぐに訴えた。
幼少時に右目をすでに摘出している。すなわち、いま残る左目を摘出してしまえば、光を失うことになる。
この時まず思ったのは、光を失い、全盲になることは死ぬことより辛く、これから苦しみながら生きていかなければならなくなるという恐怖。
何も見えなくなる。歩いていてもどこなのかわからなくなる。誰の姿も見えなくなる。テレビもゲームも携帯電話も見えなくなる。
ひとりでは何もできなくなる。そんなの絶対嫌だ。生きている意味がない。そんなの生きていても楽しくない。
だから、泣き出しそうになるのを堪え、「絶対に摘出だけはしない」と強く訴えたのだった。
結局、この日はすぐには決断できず、一時帰ってじっくり考えることになった。もちろん、腫瘍はいつどんなスピードで身体を冒すかわからないため、決断は早くしなければいけない。
この時、看護師から安く泊まれるファミリーハウスという存在が近くにあると教えてもらった。そこは病院からタクシーで20分も離れていない浅草橋という場所で、駅からも徒歩1、2分だという。
「アフラック ペアレンツハウス」
これから闘病中ずっとお世話になり、そして様々な出会いがある施設だった。
ここは、地方から来た小児がん患者の子どもやその家族が通院や入院の際に短期間から長期間までかなり低料金で泊まれる施設で、初めて訪れた時はまだ作られて間もなかったため、利用者も少なく寂しい雰囲気だった。
7階建てのビルで中は宿泊するための個室がいくつもあり、3階は共同で使用する広大なキッチンとプレイルームが完備してあった。7階には無料で使える洗濯機や乾燥機なども置いてある。
全体的に清潔感にあふれていて、様々な企業からの寄附の品々もあり、職員の方もみんな親切。低料金で泊まれるのが本当に不思議なくらいだった。
1階には「がんの子どもを守る会」という団体の事務所も併設されており、患者の支援や情報提供、相談にも乗ってもらえる。
あのがん保険で有名なアフラックが経営しており、難病を持つ家族には経済的にも精神的にもとても助けられる施設だった。
その晩、寒空の中外に出て、ひとり考えていた。
ひとつは、すぐに抗がん剤治療。ひとつは、危険度は増すが腫瘍を検査。ひとつは、すぐに眼球摘出。
摘出という選択肢だけは考えてはいなかったが、どちらにせよすべて過酷な道だけにいっそ何もしないでいたほうが楽なのでは、とも考えた。それが死んでしまうことになったとしても。
何を考えても、これからのことを思うと涙しか出なかったから。
もし神様が本当にいるのなら、なぜ自分がこんな目に遭わなければいけないのか教えてほしい。
その日はとても眠れず、ただただ寒い中、朝までずっと星空を眺めているしかできなかった。
次の日、寝不足のまま再度国立がんセンターへと向かった。
そして、先生の前に座ると、すぐにこのまま抗がん剤治療に望むことを伝えた。正直まだ答えなんて出ていなかったが、ふいに言葉が出た。つまり思っていたことを伝えたのではなく、自然に口から漏れた言葉がそれだった。
本人の決断ならばと、眼科と小児科の先生は反対しなかったが、確認のため再度抗がん剤を行う危険性を説明され、仕方ないことなんだと自分を無理やり言い聞かせて、唇を噛み締めながら了承した。
母もその決定に不安を隠し切れてはいなかったが、自分で決めた道ならばと、納得してくれた。
幼少時とは違い、もう自分自身で何でも決めることができる。だからこそすべてを本人に任せて、それをしっかり支えていくと言ってくれた。
我が子の治療の決断をしなければならなかった母はどんな気持ちだったのだろう? 母が決めたことで我が子を苦しめてしまうなんて、いまの自分自身の心境からしたらとても考えられない。
そう考えると、母に感謝すると同時に謝罪の気持ちが強かった。
こんな病気に生まれてきてごめんなさい。
自分のせいで大変なことばかりでごめんなさい。
ずっといちばん近くで支えてくれてありがとう。
あえていま、母のことを思うことでこの先の治療もがんばれる気がした。
自分自身ではなく他人のために。
抗がん剤治療は、事情があって現在国立がんセンターではできないため別の病院で行う、と言われた。
それならばわざわざ地元から離れた東京でやる必要がないため、道内でできる病院はないかと先生に調べてもらった。その結果、地元の室蘭からさほど離れていない札幌の札幌がんセンターでやってくれるというので、早速紹介状を書いてもらい、一度地元へ帰ることになった。
また長い移動を経て地元に戻って来て、これから長期間の治療が始まるため、とりあえず札幌に入院する前にみんなに挨拶することにした。
まずは職場に訪れ、上司と同僚に現状とこれからのすべてを話した。
同僚とは友だちのように仲よくしていたこともあり、みんな驚きながらも親身になって心配してくれて、いつも厳しい上司も悲しい目をしながら勇気づけてくれた。
そして、いつ戻って来ても大丈夫なようにしばらく会社には名前を残しておいてくれると言う。今後どうなるかは自分でもわからなかったため、すぐに戻れるわけがないとは思ったが、その心遣いはとても嬉しかった。
当時、同僚のひとりで好きだった女性が、別れ際に口づけをしてくれたことがいまもずっと忘れられないでいる。彼女もまた自分に好意を寄せてくれていたのか、ただの励ましだったのかは、いまはもうわからない。先の見えない自分には、これからのことを思うとそれを思い出として受け取るしかできなかった。
次に、連絡先のわかる地元の友だちや知人全員に報告した。
その知らせを聞いた地元の仲間たちは何とその日のうちに自宅に集まり、あまり広くない家の中が一杯になってしまった。
みんなで不安を打ち消そうと笑い話などで盛り上がり、それは夜遅くまで続いた。
最後に、「絶対に元気に帰って来い! 地元でずっと祈って待ってっから!!」と言葉をかけてくれて、その日は解散となった。
次の日、早くに札幌がんセンターに向かった。
やはり東京と違って移動時間も短く、それだけで疲れることはなかった。
このころから眼底内の出血はだいぶ収まり、視力はほとんど回復していた。
第2章 ■3. 抗がん剤治療†
2004年12月。
札幌がんセンターに着くと、まず小児科に案内された。
自分は当時19歳だったが、病気自体は網膜芽細胞腫、すなわち小児がんとして治療していくため、担当するのは小児科で、入院するのももちろん小児科病棟らしかった。
診察ではまた抗がん剤についての説明があり、とにかく辛い、危険など何度も言われた。重要なことだから何度も慎重に説明するのはわかるが、そんな残酷なことをくり返し頭に入れられたら先に頭がおかしくなりそうだった。
あらかたの説明が終わると、早速小児科病棟の病室に案内された。
ここの小児科病棟はふつうの病院と違い、髪の毛のない小さな子どもたちが点滴を引きずって廊下を歩き回っている。みんな、抗がん剤の副作用で髪の毛はすべて抜け、痩せこけている子ばかりだった。
それを見ただけでなぜか悲しい気持ちになり、涙が流れそうになった。この子たちはこの歳で、どんな思いで、どんなに辛い治療を受けているのだろう? その姿を見ただけでそう感じてしまった。
そんな子どもたちとすれ違いながら案内されたのはひとり用の個室で、やがて担当する医師と看護師が自己紹介に来た。
自己紹介をした医者はレジデント(研修医を終えた2年目の医者)で、とても若い先生だった。
正直、最初にその先生を見た感想は、何とも頼りない感じに見え、これからの大事な治療をこの人に任せてもいいのかと戸惑ってしまった。
それから少し身の回りの整理をして、様々な検査が始まった。
血液検査・肺機能検査・エコー検査・心電図・CT検査・MRI検査など。すべて終えたのはもう日が暮れる時間だった。
いちばん辛かったのは、「マルク」と「ルンバール」という検査。
「マルク」は胸骨から骨髄を取る検査で、胸周辺に局所麻酔を施してストローほどの太い注射を胸から刺され、骨に到達したところでさらに細い注射を太い注射の中から刺し込み、骨髄を採取する。これはかなり苦しく、痛みもすさまじいもので、太い注射を刺し込むために体重をかけられるため、息もまともにできなかった。
やっと終わって安心したところで体を起こされ、「ルンバール」を行った。これは腰の背骨に注射をして脊髄を採取する。今度は麻酔なしで細めの注射を刺され、とても辛かった。
それらが終わると、体を前屈しながら車椅子に乗せられ、その態勢のまま病室に戻された。
「マルク」と「ルンバール」を行ったらしばらくは頭を高い位置にしてはいけないらしく、そのままベッドまで運ばれるのだ。
これらの検査を約半日かけて終わらせ、それだけで疲れきってしまったので、その日はそのまますぐに眠りに落ちていった。
次の日、必要な検査もすべて終わり、これからいよいよ抗がん剤治療が始まるんだ。と心構えをしていたら、主治医から「治療開始は年明けからになるから、一度帰省しても大丈夫ですよ」と言われ、何だかホッとしたようなガッカリしたような微妙な心持だった。
でも、検査結果もすぐわかるわけでもなく、いまは病院にいる意味がないし、何よりたった1日の入院で自宅に帰れるというのはとてもうれしいことだった。
帰りの車の中、これから何度通ることになるかわからない病院から自宅までの約2時間の道のりをただ窓の外の風景をボンヤリ眺めて過ごした。
窓の外。道行く人たちがみんな楽しそうに歩いている。家族や友だちと楽しそうに歩いている。自分はまたあんな風に歩けるのだろうか?
これからどうなるかわからない不安への気持ちの整理は本当に苦しかった。
自宅に到着すると、弟と祖母が出迎えてくれた。
病院にいた時間はほんのわずかな時だったが、やはり家族で自宅にこうしていっしょにいるのがいちばん安心する。
一家団欒でゆっくりと時を過ごすのが何年ぶりにも感じられて、これからの長く苦しい入院生活を躊躇させるくらい家族の笑顔が愛おしくて辛くなった。
できることならこのままふつうに暮らしたいけど、みんなが心配してこの笑顔が消えてしまうと思うと、そんなこと絶対に口に出せない。
自宅に帰って来てから楽しい時間を過ごす中で、そんなことをずっと考えていた。
再発と言われてからこれまで、ひとりになった時にだけ涙を流した。母にも弟にもずっと笑顔でいてほしくて、自分が強い心でいれば心配もかけなくてすむ。
痩せ我慢とわかりながらも、家族の前では決して弱さを見せることはしなかった。
帰宅してからの日々は本当に楽しくて、心休まる時間を過ごしていた。
いま思えば、中学生からいままでずっと働いていたような気がする。
平日は学校にアルバイト、休日もフルタイムでアルバイト。高校を卒業してからすぐに就職して休む暇がないパチンコ屋で働いて、いつまともに休んでいたのか。本当の休息といえる時間はもう何年もなかった気がする。
そしていま現在、何もせずただ毎日を家族とともに過ごし、やっと心も体も休めることができていた。
まさに地獄へ向かう前の天国だったのだろうか。
その日はクリスマス。
またもやたくさんの友だちが来てくれて、今回も狭い茶の間に20人以上もの人数が集まっていた。
さすがに暑苦しくてみんな汗だくになっていたが、またひとりひとり応援の言葉をぶつけてくれた。
恋人がいる人、家庭持ちの人や仕事が忙しい人もたくさんいたのにも関わらず、大事なクリスマスの日に自分の元に駆けつけてくれたことがうれしくて、泣きそうになった。でも、自分は涙するより笑顔でいたほうがみんなの思いに応えられる気がして、必死に我慢していた。もう日付も変わったころ。最後に「がんばって完治して戻って来るから」とひとりひとりと固い握手をかわし、みんなその言葉に安心して帰宅した。こんな楽しい時間を早く取り戻すために、みんなを裏切らないために、と思い知り、勇気づけられた。
年明けも母と弟と家族3人で過ごすことができ、バラエティ番組を見ながら笑っていた。
こんなふつうの幸せを来年も感じたい。
だから必死に生きて、またこの光景を目に焼きつけたい。
精一杯がんばって、全部終わった後に我慢した分弱音を吐こう。
そう考えながら、また明日を迎えた。
暫しの休息を終えた2005年1月3日。
これから長い闘病生活を始めるために、札幌がんセンターへと戻った。
前回はゆっくり準備する暇がなかったので、今回は音楽機器やゲームや本など、長い入院生活でとにかく暇つぶしになる物を持っていった。この時は「暇」さえ感じる余裕がないほど苦しみが待っているとは知らなかったから。
病院に到着して、前回案内された病室で片付けをしながら主治医を待っていると、看護師がやってきて突然「部屋を移ります」と言われ、休む暇なく部屋の引越しが始まった。
まだ少ししか片付けていなかったので、荷物をすべてベッドの上に置いて、そのベッドごと移動することになった。
元いた個室は本来、容態の厳しい患者や無菌が必要な患者が使うのだが、前回は他の部屋が空いていなかったらしく、とりあえず緊急で入ってもらっていただけだったようだ。
そして、移動して新しい部屋を見るなり言葉をなくしてしまった。
そこは、6畳ほどの清潔感を感じさせない部屋で、すでにベッドがふたつ置かれており、さらにいちばん手前の空いていたスペースにいま運んできたベッドが置かれた。
この部屋は、昔はひとり部屋として使っていたらしいのだが、患者の増加にともない、現在は無理やり3人部屋として使っているようだ。
元はひとり部屋だった広さに3つもベッドが並んでいるため、ひとり歩くのがやっとのわずかなスペースしか残っていなかった。
さらには、わずかに空いたスペースには患者やその家族の荷物を置いてあるため、掃除もまともに行き届かないのが清潔感を感じさせない原因だと思う。
後から病棟内をちゃんと見てみると、このような部屋は他にもいくつもあり、狭く汚い感じの部屋に治療で苦しむ子どもたちという光景は、まさに牢獄を思わせるものであった。
部屋の引越しが終わり、いつの間にか消灯時間になってしまったが、なかなか眠ることはできなかった。
慣れない環境のせいもあるが、やはりベッドどうしが密着状態のため少しでも動くと柵がぶつかり合う音やギシギシ音が響いて、落ち着いて眠れなかった。
ちなみに、母はベッドのすぐ下のわずか30センチあるかどうかというスペースに敷物を敷いて横になっていた。
ここの病院では小児科に限り家族の付き添いが許されており、網膜芽細胞腫も小児の病気扱いなので家族が付き添うことができた。
母が付き添うことは正直、年ごろの自分にとっては気恥ずかしいことであったが、本心は治療に対する不安や恐怖が強かったため傍にいてくれるのは少し心強かった。
しかし、狭くてホコリまみれの床に眠らなければいけない母を思うと切ない気持ちになり、その日はよけいに眠れないまま次の日を迎えていた。
翌日、朝早くに主治医がやって来て、別の部屋へと連れて行かれた。
そこは前にマルクやルンバールといった検査を行った処置室で、この時はとにかく過酷な処置をする部屋という認識になってしまっていたため、ビクビクしてなるべくゆっくり歩いてしまった。
そんな行動を見た主治医は、「今回はあんまり痛いことではないから」と声をかけてくれたが、「あんまり」ってことは少しは痛いんだ、と覚悟しながら主治医とともに恐怖の処置室へ入った。
処置室に入るとまずベッドに横になり、ふと主治医のほうを見てみると針を手にしていて、「これから点滴をつけるから」と言われた。いよいよ明日から抗がん剤治療が始まるため、事前に点滴をつけておくのだ。
抗がん剤を投与する前後には、体の中の不純物や残った抗がん剤を排除するために「流し」と言われることをするらしい。
恥ずかしい話、この歳になっても点滴が苦手だった。体の中に他のものが入ってくる違和感がどうも気分的に受けつけなかった。
しかし、これから抗がん剤治療を続けていく上で点滴からは絶対に逃れられないので、そこは我慢しなければいけない。
その後、処置室から出た時にはしっかり点滴をぶら下げていたが、表情は歪んでしまっていた。それは点滴自体によってではなく、針を何度も刺されたせいだった。
体質で生まれつき血管が細く、もともと刺しづらいのに加え、処置するのはまだ慣れているとは言えないレジデントの先生。そんなわけで、点滴を刺した左腕は少し痛々しい状態になるくらい打ち直しを強いられ、さらになかなか入らないせいで腕の中で血管をさがすために蹂躙する針に気分が悪くなってしまったのだった。
次の日からはこれとは比べられないほど苦しい治療が待っているのに、腕の痛みと点滴によって少し自由を奪われたことでかなり落ち込んでしまった。
そして、その晩も点滴のことと病室の状況のせいであまり眠れなかった。
次の日、2日間まともに眠れていないため、寝不足の目をこすっていると、この日も早くに主治医が病室に訪れた。
持ってきた台車の上にはいくつかの点滴の薬剤が置いてあり、これが抗がん剤?と緊張していると、主治医はひとつひとつの薬剤の説明を始めた。
まず長方形でプラスチックのような容器に入った抗がん剤。これは強い抗がん剤のため、体調を見ながら月に1度しか流せないらしい。
次に、注射器のような容器に入った抗がん剤。これも体調を見ながら週に1度、容器の中身をその場で一気に流すらしかった。確かオンコビンと呼ばれており、ヘンテコな名称だなと思っていた。
その他は、抗がん剤を体の中に残さないための流し薬だった。
これらの抗がん剤を、1ヵ月を1クールとして体調を気にしながら最大6クール行うらしい。
あらかたの説明を終えると、主治医は早速、点滴から直接注射器の抗がん剤を注ぎ始めた。瞬間、腕の中に何か冷たい液体が入ってくる嫌悪感に必死に耐えなければいけなかった。
すべて入れ終えた時には、刺さっている点滴の針周辺をジリジリと少し痺れた感じだけが残っていた。
そして、長方形の容器の抗がん剤を点滴に取りつけ、いまはその抗がん剤と「流し」のための薬がぶら下がっている状態となった。
ついに始まってしまった抗がん剤治療に、傍で黙っていた母もずっとただただ不安な表情で眺めていた。
抗がん剤を流し始めてすぐには体調に異常はなかったが、地獄の苦しみは翌朝から始まった。
まず、朝目覚めたら身体が重苦しくて自由がきかず、ベッドから満足に起き上がれない状態となっていた。
さらに40度近い高熱があり、嘔気・気だるさ・頭痛・寝不足・点滴部分の腕の痛みなど、もはや具合が悪いことを通り越しているような気分でどうしていいのかわからない。
数日間寝不足だったせいで強い眠気に誘われていたため、体調が最悪でも今日こそはしっかり眠れると思っていた。しかし、夜中の間も点滴により大量の水分が体の中に入ってくるため、眠る暇がないくらいトイレに行かなければならなかった。だいたい1~2時間に1度のペースで尿意に襲われるため、ゆっくり眠れるはずもなく、気づいたらこの過酷な状況になっていた。
起き上がれないと言ってももちろん、夜中だけではなく朝からトイレに行かなければならない。看護師の介助でベッドの上で用を足すこともできたが、変な意地があり、そこまではしてもらいたくなかった。だから辛い体を無理に立ち上がらせ、点滴棒を支えにして何とかトイレまでは行っていた。
もちろん食事など取る気にはなれず、食べ物を見ただけで嘔気がこみ上げてきて、大好物であってもすべてが気持ち悪く感じてしまう。点滴をしているから食事を取らなくても多少問題はないが、もはや空腹という概念が身体から消えているようだった。
何もできずに逃れられない苦しみをただベッドの上で耐えている状態で、さらに苦しめられる出来事が起こっていた。
この狭い病室のいちばん奥の窓側にまだ中高生ほどの子が入院していた。治療により喉の調子が悪いらしく、その子はつねに痰を吐くような行動で頭に響く音を発していた。
その子自身もそれから逃れられなく辛い状態らしいが、痰を吐くような音にさらに苦しめられた。激しい頭痛に悩まされているいま、その一定の間隔で発せられる頭の中に響くような音は終始拷問にかけられている気分だった。
お互いにベッドから起き上がれない状態で、耳を塞いでみてもあまり効果はなく、ただただその拷問のような苦しみをジッと耐えるしかなかった。
そんな地獄の日々は3日ほど続き、気が遠くなるほどの長い時間を過ごしていた気がするが、後から振り返るとその苦しい記憶をあまり覚えていない。思い出したくない過去を勝手に封印してしまったのかもしれない。
この思い出したくもない拷問が、長い闘病生活最初の苦しみであった。
抗がん剤治療が始まってから数日が経ち、点滴で流していた抗がん剤はすでになくなり、いまは「流し」のための薬だけとなっていた。
体の調子もだんだんとマシになってきて、食事もさっぱりしたものをわずかばかりなら口にできるようになってきている。
いちばん楽になったのが、頭痛をさらに苦しいものとしていた同室の子が病室を移動となり、その頭に響く音から解放されたことだった。その子も自分と同じように苦しんでいるのにと考えると、部屋が移動になって安堵した自分が恥ずかしく、とても申し訳なかった。
でも、その時はそんな思いなど浮かばないほどの苦しみだったのだ。と言っても、いまもまだまだ辛く、高熱は微熱になったものの気だるさや頭痛は健在している。
この数日は本当に心が折れて、何度も挫けそうになった。
何でこんなに苦しまなきゃいけない? 何で自分が? 自分が何をした? もう頭がおかしくなりそうで、いっそ死んでしまいたいとも思ってしまった。
でも、苦しみからは逃れたいけどやっぱり死ぬのは嫌だ。死んだらすべて終わってしまう。そんなことを何度も考えて、無理やりにでもこれからの楽しい人生を想像しながら耐えていた。
そして、体調が少し楽になってきたころ、抗がん剤治療をする上でいちばん気になっていたことがついに起こり始めていた。
それは体調の回復のおかげでお風呂に入れることになった時だった。
お風呂は同じ階のいくつかの病棟で共同となっており、それなりに広く、当たり前だがしっかり清潔できれいにしてある。
これまでは体調が悪く、とても入れる状態ではなかったので、蒸しタオルで体を拭いているだけだった。だから、久々のお風呂がうれしくて、ゆったりと湯船につかって鼻歌なんかも奏でていた。
悲劇は、洗髪を始めた時に起きた。
この時、自分は長髪ではないが少し長いくらいの髪だった。そんな髪を洗っている途中、指に絡まりつく大量の髪の毛を見て驚愕してしまったのだ。
抗がん剤の副作用のひとつである抜け毛。まとめたら太いペンほどの量が一気に抜けたのだ。知ってはいたけど、実際に経験してみたらショックが大きく、指に絡まった髪の毛を眺めたまましばらく動くことができなかった。
その後、バスタオルで頭を拭く時、ドライヤーで乾かす時、ふいに髪の毛をいじった時、その度に数え切れないほどの髪の毛が抜けた。さらには、寝て起きたら枕元にも夥しい量の髪の毛。
とにかく少しでも髪の毛に触れる行動ですぐに抜けてしまい、それが3日ほど続いたころ、ある決心をした。
翌日、午前中の内に病院内に設けられている床屋を訪れていた。
この時はかなり抜けたとは言え、まだ見た目では問題のない程度だったが、この調子で抜けていたら1週間もしない内にひどい状態になってしまう。何より絶え間なく抜けていく精神的ストレスが限界だった。それならいっそ、髪の毛をなくしてしまえば少なくとも抜けていく苦痛は消える。
床屋の椅子に腰をかけると、店主はもうすべてわかっているように、何も聞かないまますぐにバリカンを取り出して作業を始めた。
そこで後ろの待合場に座っていたおばちゃんが「まだ若いのに切るのかい? いい髪形してるのにもったいないねぇ」と声をかけてきたが、店主はすかさず「仕方ないんだよ」と言って、おばちゃんに見せるように髪の毛を一部摘んで軽く引っ張った。あえてゆっくりと軽く引っ張っているように見せたが、その摘んだ指にはまとめて抜けた髪の毛があった。
おばちゃんはそれを見て悲しそうな表情を浮かべ、口を閉ざしてしまい、自分もまた言葉が出なかった。
この病院内に設けられた床屋では、自分と同じく抗がん剤治療によって抜け毛を気にして剃ってしまう患者が多いため、店主はこのようなことに慣れている人だった。そのために設けられた床屋と言ってもいいと思う。
とにかくバリカン中の途中経過を見ていたくなかったので、バリカンの音が聞こえる間はずっと目をつむっていた。バリカンが終わると剃刀でまんべんなくきれいに剃って、始まってから15分も経たないうちにあっけなく散髪は終わった。
店主に終わったと声をかけてもらって目を開くと、一気に頭がスースーした感じがして、目の前の大きな鏡にはツルツル頭になった自分がいた。
でも、抜け毛を経験した時ほど不思議とショックはなく、逆に吹っ切れた感じがして抵抗はなかった。それでもこれまで短髪すらあまり経験したことがないため、人目が気になって一応持ってきておいたニット帽を被って病室に戻った。
抗がん剤の副作用による抜け毛。まだ男性は抵抗が少ないと思う。しかし、抗がん剤をしていれば女性であろうと髪の毛は抜ける。
ここの小児科病棟には小さい子から年ごろの子までたくさんの女の子がいて、まだ幼児ほどの子は髪の毛がなくても無邪気に過ごしているが、小学生以上になる女の子はさすがに抵抗があるため、わずかに残った髪の毛も大事にしてニット帽やカツラなどで隠していた。中には病室から出ず、人前に出ることを拒んでしまう子もいたくらいだ。
自分自身が同じ状況になって改めて感じたが、この病棟はそんな子どもたちがたくさん集まる場所なのだ。点滴をぶら下げながらはしゃぐ髪のない子どもたちや、人目が気になって病室から出られない年ごろの子どもたちを見ているだけでも、抗がん剤がいかに過酷な治療なのかと実感した。
そんなことを考えながら、小児科病棟の廊下を歩いて自分の病室に戻り、心配して待っていた母に変貌した頭を披露した。
母はそれを見るなり「似合ってるじゃん」と言ってくれたが、必死に何かを耐えているような切ない目をしていた。そんな母を心配させまいとツルツルになった頭を「ペチン」と手の平で叩いて鳴らし、笑ってみせた。
頭がすっきりして吹っ切れたと思ったが、やはり最初は気恥ずかしさが消えず、ふだんは薄いニット帽を被って過ごした。
抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けると言っても一応、毎日髪の毛は生えてくる。そのためわずかに生えてはまた抜けるのをくり返すので、帽子を被っていたほうが細かい髪の毛を散らかさずに済むというのもあった。
同室のふたりも治療の副作用により髪の毛はなく、隣の高校生の子は気になるのか同じようにニット帽を被っていて、窓側のお兄さんは何も気にせずつねに解放していた。帽子を被っている姿を見たことないせいか似合っているせいか分からないが、そのお兄さんはツルツル頭に違和感がなく、かっこよく思えた。
もうひとつ衝撃だったのが、具合が悪くてお風呂に入れなかった日。
熱もあり、汗もかくので何とか毎日清潔でいたいから、お風呂に入れない時は朝晩に蒸しタオルで体を擦る。ベッド上で全身を擦るためカーテンでベッドを囲い、その時にどうせツルツルならといっしょに頭も擦っていた。すると夥しい量の細かい髪の毛がタオルに付着しており、例えるならそれは小さな虫がへばりついて蠢いているように見えた。
抗がん剤の副作用のせいで体調が悪いから錯覚で見えていたのだと思うが、とにかくそれが気持ち悪くて、それを見る度にさらに嘔気に襲われた。
それにしても、抗がん剤を始めてから毎日が暇だった。具合が悪い時期はそんな余裕などなかったのだが、調子がよくなってきたら何もできずにただ1日をベッドの上で過ごすのは辛かった。
本やゲームや音楽にテレビなど、暇つぶしできそうなものはすべてすぐに気持ち悪くなってしまうので、何もできない状態だった。本当に何もせず、ただベッドの上で抗がん剤の苦しみに耐える日々だ。
そんな毎日を送り、早くも抗がん剤治療が始まってから1ヵ月が経とうとしていた。
体の具合は最初の時ほど最悪な状況にはならなかったが、週に1度の抗がん剤を投入する度にそれから数日は気分が悪くなり、少し調子がよくなってきたころには1週間が経って、また抗がん剤といった1ヵ月だった。
とりあえず1クールの治療が済んだということで、治療の効果を確かめるために今日は眼科にかかることになった。
眼球内に腫瘍があると言っても視界に映るわけでもないため自分自身には腫瘍の状態を知る術がない。そのため、抗がん剤をしながら定期的に経過を確かめるために眼底検査をしなければならなかった。
眼科外来は同じ階にあり、小児科病棟から少し歩くだけで到着した。いつものように瞳孔を開く散瞳の目薬をさして、それを待つ間に眼圧を測ったのだが、いつもなら1回か2回ほどで終わるはずの眼圧検査がなかなか成功しなかった。
腫瘍により眼球が異常をきたしているのか、単純に看護師の腕が悪いのかはわからないが、次第に眼球に眼圧を測るための空気が当たるのも嫌になってきて、やっと計測できたころには疲れ切ってしまった。まさか眼圧を測るだけでこんなに苦労しなければいけないとは思わなかった。
その後、眼圧検査に時間がかかったせいか、すぐに名前を呼ばれた。ここの眼科の先生は落ち着いた雰囲気の女性で、とても穏やかに検査を進めてくれるため助かる。医者によっては眼底検査をするだけでもかなり乱暴に検査する先生もいるため、大事な目を検査される側からしたら嫌悪感を覚える場合も少なくない。
1ヵ月前と違って眼球内の出血はすっかり消えていたため、眼底検査も難なく進み、あまり時間はかからなかった。そこで思い出したかのように、いまさら眼底出血の原因を聞いてみたら、腫瘍のせいでもろくなった血管が破けたせいとのことだった。
そして、もっとも気になっていた腫瘍の状態は、詳しく検査したわけではないので細かくはわからないが、見た感じでは確実に腫瘍の縮小が見られるとのことだった。
さらに眼球の模型を用いて、わかりやすく説明してくれた。腫瘍は眼球内網膜の内側3分の1ほどの範囲でへばりついており、高さもそれなりにあったと言う。現在は範囲こそわからないが、確実に高さが低くなっており、言うなれば3階建てが2階建てになったような感じらしい。
いままでは出血のせいでまともに眼底検査もできない状態だったが、もちろんこの結果には声を上げて喜んだ。
最初に課せられた最悪の三択。
いますぐ抗がん剤治療を始めるか、再発と断定できないため腫瘍を詳しく検査するか、命のためにすぐにでも眼球摘出するか。そして、抗がん剤治療を選んだ。
詳しく検査していないため、眼球にある腫瘍は本当に網膜芽細胞腫だという確証はなかったし、腫瘍の種類によって扱う抗がん剤が異なる。
すなわち、東京国立がんセンターの権威の先生は網膜芽細胞腫の再発と言ったが、もし違っていたら今回の抗がん剤はただの徒労で、意味もなく副作用に苦しんだことになってしまうところだったのだ。だからこそ、別の先生は危険を承知で詳しく検査してみるべき、と主張していた。
これで網膜芽細胞腫の再発だということがほぼ確定し、同時に網膜芽細胞腫は自分のような年齢になっても再発する可能性があると裏づけされたことになってしまった。
網膜芽細胞腫は小児がんで、もともと遺伝や突然変異で乳児期から幼児期に発症する悪性腫瘍と言われている。そのため、小児の内に治療を終わらせなければならない、早期発見が鍵となる小児がんだ。しかし、他のがんと同様に完治したと思っていても治療後に再発してしまうこともあり、それはだいたい5年以内の期間に再発すると言われてきた。
だから、今回の再発は前例がないことで、今後この病気に対して大きな不安にも繋がっていくと思うといたたまれない気持ちになった。
とりあえずいまは、この検査結果にさらなる希望が見えてきたような気がして歓喜し、今後も抗がん剤の苦しみと闘う勇気が湧いてきたようだった。
このまま抗がん剤を続けていれば、腫瘍はだんだん小さくなり、最後にはきれいさっぱり消えてくれると思っていた。
その日の昼はよい検査結果に気分も優れていたので、久しぶりにまともな食事をしようと病院の地下にある食堂に行くことにした。
抗がん剤の余韻でまだ体がフラフラなのにも関わらず、小児科病棟がある2階から地下までエレベーターを使わずに階段で向かっていた。
無茶をするなと母が慌てて止めてきたが、「大丈夫、大丈夫」と引きずっていた点滴棒を持ち上げ、スタスタと軽快な足取りで階段を駆け降りた。体調が上り坂になったため、病弱な体なんて認めないと少しばかりの抵抗だった。
ここの食堂には定食や丼物、麺類など様々なものがあるのだが、決まってお気に入りの醤油ラーメンを食べる。体調が悪い時は麺類のほうが食べやすいのもあったが、他では食べられないスープの味がお気に入りとなって、この食堂に来る度に同じ物を頼んでいた。入院中に何度食べたか覚えていないほどだ。
久しぶりに満腹になったところで病棟に戻ると、主治医が待っていて、病室には戻らずそのまま恐怖の処置室へと連れて行かれた。
抗がん剤が1クール終了し、「流し」の点滴もなくなっていたので次の2クール目の抗がん剤開始までの間は針を外してくれるらしかった。
1ヵ月ぶりに針から開放された左腕は、刺し傷の周辺が赤黒く変色しており、自分で見ても痛々しいものであった。
もちろん主治医の耳にも午前中の眼科の検査結果は入っており、その結果から抗がん剤は効いていると判断され、体調が回復する見込みの次週辺りから再び、抗がん剤治療2クール目を始めることにした。
そして、抗がん剤の開始は3日後の月曜日と決まり、主治医と相談してその空いた土日の帰省を許可してもらった。
本来は強い抗がん剤を使用していると血液の数値(白血球や血小板)が著しく低下しており、つまり免疫力が低いのでウイルスに感染しやすくなったり、外傷などで出血したら血が止まらなくなったりしてしまうので、外泊せず病院にいるのがいちばん安全である。
しかし、この特殊な小児科病棟には長期間入院しなければいけない子が多く、しばらく自宅には帰れないケースが多い。そのため主治医の判断で、少しでも体調がいい時には危険を承知で外泊の許可を出してもらえる。
また1ヵ月に一度の抗がん剤が始まれば帰省することができなくなるくらい体調が悪くなるため、気分転換もかねて帰ることにした。
正直言うと、土日に何もないのなら一時帰りたいと我儘を言って許可してもらった。小児科病棟内では珍しい大人なので、言いたいことを強く訴える自分は主治医を困らせてばかりだったかもしれない。
札幌から地元への帰り道の車中、約2時間は母の好きなGacktさんの曲が流れていた。
激しいロック調の曲もあれば優しい感じのバラードもあり、安心感を与えてくれる歌声にいつも聞き入ってしまう。
自宅に到着すると、今回も弟と祖母が迎えてくれた。
留守中はまだ中学生の弟がひとりになってしまうため、祖母に来てもらっていた。もちろん、長期間弟をひとりにしてしまう状況は心配であったが、祖母が来てくれているし弟も「ひとりで自由にできるからたまにはいいよ」と言ってくれ、安心して治療に臨むことができていた。
1ヵ月ぶりの帰省でゆっくりと羽を伸ばして、自宅にいる間は体調が悪くなることもなく、この2日間は本当に心休まる時間を過ごすことができた。
弟と祖母に初めてツルツル頭を披露して笑い合ったり、久しぶりに家族で外食をしたり、弟とゲームで盛り上がったり、また病院に戻るのを躊躇うくらいに楽しい時間を過ごした。
そんな些細な生活にとても幸せを感じながら、泣く泣く病院へと戻ったのだった。
腫瘍が小さくなってくれたおかげで、はじめより不安な気持ちは和らいでいる。またふつうに暮らせるという希望があるから次もがんばれる。
いまはとにかく生きたい。
何事もなかったかのように、ふつうに暮らしたい。
そして、いつかこんな辛いことも笑い話にしてやるんだ。
2005年2月4日。
病院に戻ると、隣のベッドに新しく高校生の体格の良い子が入っていた。
この子は毎日のように放射線治療を全身に施すらしい。身体に多大な害となる放射線をこれほど浴びなければいけないことに言葉も出なかった。高校生ならば学校生活も青春真っ只中だというのに、ずっと入院して辛い治療を続けなければいけない。無意味だとわかっていながら憤りを感じた。
隣の病室には、小児白血病のため骨髄移植をした小学生がいた。この子は移植後の副作用で顔がパンパンに腫れ上がってしまい、見た目だけで痛々しい。
他にも抗がん剤や放射線治療をしているたくさんの子どもたちが過ごしている。中には数年もの間ずっと入院している子もいた。
改めて見ても、本当に悲しい病棟だと思う。自分のこともあるが、この子たちにどうか明るい未来を、とずっと願い続けている。
日曜日に病院に戻ってからすぐ就寝し、起床して間もなく、早速抗がん剤を流すための準備が開始され、点滴を刺された。
今回も午前中に流しをしておいて、午後から抗がん剤を流すとのことだった。この抗がん剤を流すまでの時間に前回の苦しみが鮮明に思い出され、一瞬逃げ出したい衝動に苛まれたが、何とか楽しいことを考えながらその時を待った。
そして昼食後、身体や血液に異常もないため、予定通り前回同様の2種類の抗がん剤が投与された。
点滴にぶら下げられた抗がん剤から管を通って体の中に注がれていく様子が見えただけで頭痛と吐き気に襲われ、その日はなるべくベッドに横になって大人しく過ごすことにした。それでも抗がん剤が身体に巡る量が増えてくると、前回のように高熱が出始め、徐々に起き上がれないほどの具合の悪さへとなっていったのだった。
ベッドの上でただ苦しみもがくだけの姿に、母もただただ側で見守ることしかできず、歯がゆい毎日だったと言う。
そんな母は少しでも食べられそうだと言ったものは遠くても徒歩で買いに行き、我儘も文句一つ言わずにできる限りの行動をしてくれていた。この時の母は本当に自分の体力の続く限り、我が子のために必死に動き回ってくれていた。
そんな様子が5日ほど続いてから、徐々に体調が回復して多少は歩き回れるまでになった。前回は1週間以上は苦しんでいたので、早くに体調が回復したのがうれしくて、早速食堂にお気に入りの醤油ラーメンを食べに行った。
しかし、後に主治医の話を聞いてみたら、体調の回復が早いのは身体が抗がん剤に慣れてきたためなのだが、それはつまり、眼の腫瘍もまた抗がん剤に慣れてしまい、効果が薄くなっているということらしかった。その説明に一抹の不安を感じたものの、まったく効かなくなっているわけではないし、確実に腫瘍が縮んできているとの言葉を信じて、今後の闘病の活力とした。
2クール目が終わり、3クール目が開始された後も、以前に比べて体調の悪さも軽減されて3日後には自由に生活できるほどとなった。
これまでの2ヵ月はベッドから起き上がるのも大変で、食事もろくに取れず、テレビや本を見てもすぐに吐き気に襲われ、ほとんどの時間を無理やり睡眠に費やしていた。
それは苦しむだけの過酷な毎日であったが、その時は永遠にも思えるくらいに感じていたのに、気がつけばあっという間に日々は過ぎていた。でも、体調もそこまで悪くないのに入院生活を過ごすということがここまで暇なのかと、改めて苦痛に感じてきた。
網膜芽細胞腫を除いてはとくに大きな怪我や病気をしたことがないので、この何もすることのない初体験の入院生活が別の意味で苦痛だった。
そんなわけで、毎日体調がよくなったことでできるようになったゲームを1日中やっていた。
暇つぶしと言ってしまえばそれまでだが、こんな状況の中でその時だけでも病気のことを忘れて意識を集中させてくれるゲームには本当に助けられたと感じている。
そして、診察に来る主治医には隙さえあれば外泊したいと懇願して、まだ若い主治医をいつも困らせていた。
3クール目も過ぎてくるとお互いだいぶ友好的に接するようになっており、暇があれば主治医は病室に訪れ、雑談や愚痴を吐き出しに来るようにもなっていた。
周りの年端もいかない子どもたちの治療に携わってる中で、多少は大人としての会話ができる自分が少しは落ち着ける場だったのかもしれない。
そんな主治医に対して、何とも頼りないと苦笑しながらも、若くして難病に携わり、がんばっている主治医を影ながら応援するようになった。もちろん、担当している自分の病気もしっかり治してくれという意味も込めてだ。
3クールから4クールにかけては前述通り体調の回復が速くなり、これまでベッドの上でばかり過ごしていた生活が一変した。
なので、母はよく他の病室の子どもたちの面倒を見るようになり、他の病室の母親どうしの交流が増えていった。そのため、すっかりなつかれたのか、よく自分の病室に「藤原しゃん!!」と母の名を大声で呼びながら子どもたちが訪れるようになった。
自分も点滴をぶら下げながら病院内を歩き回ったり、母になついた子どもたちと遊んだりと無駄に動き回っていたせいで、よく看護師さんに捜しまわられていた。
何と言っても食欲が回復し、脂っこい高カロリーな食べ物も食べられるようになり、味気の無い病院食は母に食べさせて自分は大好きな唐揚げや焼き鳥の弁当ばかり食べていた。
それでも、抗がん剤を投与していると体重がみるみる減って、もともと痩せ型なのにも関わらず身長170センチで50キロを切るほどにまでなっていた。痩せ型でありながら筋肉質であった身体もこの時には随分細くなり、自分から見てもまるで別人の身体で、とても悲しかった。隣のベッドの高校生の子も、放射線治療の影響で来た当初は熊のようにしっかりした体格だったのにも関わらず、ほんの1ヵ月ほどで見違えるほどに痩せ細っていた。
抗がん剤や放射線治療を行っていると髪の毛が抜け落ち、身体は徐々に衰弱していく。長く治療していればそれだけ身体が弱り、見た目も変貌していってしまうのだ。
病棟の中、そんな身体になってしまい、部屋から一歩も出たくなくなった年ごろの子もたくさんいる。それでも無邪気に走り回る子どもたちにはとても勇気づけられた。
骨髄移植の副作用で顔面が膨れ上がった子も、ろくに食事も取れずにほとんど骨と皮だけとなった子も、小さな子は辛い治療をしながらも健康な子どもたちと同じように無邪気に過ごしている。
だからこそ、子どもたちの母親は我が子のためなら何でもするという覚悟で付き添っているのだろう。この治療の果て、元気に外に出られている姿を願いながら。
しかし、自分が幼少のころからずっと問題になっていたことは現在も変わらず、こんながんばって過酷な治療を耐えている子どもの裏には両親の離婚問題が頻繁にあった。
幼い子どもが長期間入院を強いられると、ほとんどの場合は母親がつねに付き添って父親は二重生活を支えるために働かなくてはならなくなる。そんな中でいちばん辛いはずである我が子を差し置いて、両親のほうが経済的な理由や精神的苦痛に耐えられなくなり、些細なことで衝突し、離婚にまで発展する夫婦が多い。
子どもが必死に闘病している中でそんなことが起こるなんて、とても理解し難い現実だ。我が子がかわいくないのか? 罪の無い我が子より自らの事情が優先なのか?
ただ難病の子どもが重荷となって、親が子を見捨てただけにしか思えなかった。自分の父親がまさにそうだったから。
親に見捨てられたまだ幼い子は誰を頼れるのだろうか? こうやって片親となった母親たちもまた精神的に疲れ果ててしまい、精神を病んでしまうケースも少なくない。
母もそんな境遇の片親として、多くの母親たちの話し相手となっていた。いま思えば、この時くらいから病棟では母は自らの息子は放っておいて、他人の面倒を見る時間のほうが多かったような気がする。それは自分が、手がかからなくなってきたからに他ならず、そんな母を誇らしげに眺めていた。
抗がん剤治療も5クール目に差し掛かろうという時、途中経過の眼底検査でも順調に腫瘍の縮小が見られていたため、一度東京の国立がんセンターで診てもらうこととなった。
やはり発病してからずっと診察してもらっていた東京の主治医に一度状態を診てもらい、現状の把握と今後の方針を考えてもらったほうがいいらしい。
そのため、抗がん剤治療中で弱りきった身体が遠征に耐えられるかの検査をした。血液検査だけだったため、結果はすぐに出たのだが、白血球と血小板の数値がかなり低下していた。
すなわち、白血球の数値が低いため外で病原菌に感染しやすく、また、血小板の数値が低いため少しでも出血してしまうと血液凝固作用が働かず血が止まらなくなる。
それでも東京の主治医に一度直接診てもらいたかったのと、何より気分転換のために病院から少しでも出たかったため、東京行きを決意した。
安全策として、主治医は輸血して血液の数値を回復させる案を強く薦めてきたが、自分は頑なにそれを拒絶した。プライドなのか変な意地なのか、その時は他人の血液は体に入れないと断固譲らなかった。現在では聞かなくなった話だが、昔の輸血によって肝炎などが伝染ってしまう危険なイメージが強かったのかもしれない。
もちろん現在では、最新の注意を払って献血をお願いしているのでほぼそんなことはないだろう。なぜなら自分も、網膜芽細胞腫の遺伝子を持っていることから献血を丁重にお断りされたことがある。しっかり病歴などを調べて、血液に問題がないか調べてから献血しているので昔より断然安全だと思っている。
次の日、5クール目が始まる1週間前に飛行機に乗って東京へ向かった。
道中は何事もなく、無事に到着できたことに安堵しながら再びお世話になるペアレンツハウスで宿泊の手続きを終わらせ、翌日の朝早くから築地にある病院へと向かった。
約5ヵ月ぶりに訪れた国立がんセンターは、何の代わり映えもなく相変わらず混雑していた。
早速、受け付けを済ませて眼科の待合室に行くと、馴染みの看護師さんが出迎えて挨拶してくれた。
特徴的な長い髪に歩きながらボールペンをカチカチ鳴らす癖はとても印象強く、一度見たら忘れられないような人だった。この看護師さんの大らかな雰囲気と柔らかな口調は、難病の子どもたちにとって気持ちを落ち着かせてくれる存在なのだろうと思う。長い勤続の中でどれほどの患者と関わってきたのだろうか。
先に眼圧を検査してから瞳孔を開く点眼をして、待つこと1時間ほどで名前を呼ばれた。札幌の眼科と違い、眼圧検査は一度で済んだので、やはり慣れや技術の問題なのだろうかと思ってしまった。
いい思い出がないお馴染みの診察室では何となく緊張した面持ちとなってしまい、母が心配そうに付き添ってくれている。今まで残酷な診断しかされてこなかった場所なのだから、仕方がないことなのだろう。
診察室に入ると、よく見知った権威の先生ではなく、前に一度診てもらった新しい先生が座っていた。
そのことに多少動揺したそぶりを見せると、それを察した先生はまず権威の先生が定年退職してもういないことを説明してくれた。
小さなころからお世話になっていた権威の先生は、前回の診察で少しだけ聞かされていた通り定年退職となり、現在はフリーで助っ人や研究のため別の病院で活動しているらしかった。
そのため、弟子として眼のがんについて研究してきたこの新しい先生が国立がんセンターで後を継いで診察してくれている。
それでも最初はこの先生で大丈夫だろうか? と不安に思っていたが、眼底検査の手際の良さと丁寧でわかりやすい診察の説明のおかげで信頼するようになるのは早かった。
何より、以前の厳格で物静かな権威の先生と比べると、とても物腰が柔らかく、表情は乏しいものの安心感を与えるような優しい口調に何だか救われる思いにさせてくれたのだった。
病気についてももちろん詳しく診察しながら現状をわかりやすく説明してくれて、抗がん剤により腫瘍は最初から比べると3分の1ほどにまで縮小していることがわかった。
最初は腫瘍の一部を採取してみなければ網膜芽細胞腫の再発かどうかはわからないと言われていたが、今回の診断で改めて、再発が確定的なものと判断された。
再発という事実は受け入れがたいものだったが、抗がん剤がしっかり効果を現しているという事実に確固たる希望が生まれ、思わず笑顔を浮かべながら先生の話を聞いていた。
とりあえずは良好な結果を出しているため、予定通り身体の負担に問題のない6クールまで抗がん剤治療を続けることを話し合い、今回の診察は終了したのだった。
その後は体調のことを考慮して、ペアレンツハウスでゆっくり休んでから札幌の病院へと戻ってきた。
5クール目が始まると、身体が慣れてきたと言ってもやはり最初の強い薬では寝たきりの状態となり苦しまなければならなかったが、もう3日後には気だるそうにはしているものの歩き回るくらいには体調も回復していた。
このころになると週に一度は外泊をしたいと主治医に我儘を言って、無理にでも帰宅しようとしていた。
母もやはり弟をひとり家に残していることが気がかりで、できる限り帰りたいと願っていたこともあって、週に一度は点滴を抜いて週末だけ毎週帰宅できることになった。体調がいいとしても血液の数値は低下しているため、毎回念入りに注意されたことから、本当は病院にいてもらいたかったのだろうと思う。
毎週のように点滴針を抜き差しした代償として、左腕は腫れや傷でかなり痛々しい状態となっていたが、毎週帰れる喜びが大きいため気にならなかった。
本来は長期間抗がん剤治療を行う患者には、IVHと呼ばれる鎖骨の上辺りにある太い静脈に点滴張りを刺しっぱなしにするのだが、自分はそれをしていないため腕に抜き差しをくり返さなければいけなかったのだ。まだ針を刺すのが不慣れかと思われていたレジデントの主治医も相当な経験になったみたいで、後半は失敗することも少なくなっていた。
6クール目に入ると、最初の苦しみを味わってから相変わらず暇な日々を送ることになった。
でも、これが最後の1ヵ月だと思うと気持ちも軽く、一日一日が過ぎるのが待ち遠しく、病院にいる暇な時間がとても長く感じられた。毎日暇だと嘆いていたら、地元の友達が遠路はるばるお見舞いに来てくれたこともあった。
このころには、母は他の子どものよき相談役として小児科病棟の有名人となっていた。
親が付き添っていない子どもに対して看護師の仕打ちが酷いことがあり、母を中心として親たちで婦長さんに訴えたこともあった。
たまに我儘を言う小さな患者に看護師が大声で叱りつけている光景は、確かに何度も聞いたことがあった。親が傍にいないため、看護師も我儘を何とかしなければいけないと必死だったのかもしれない。
確かに年少くらい小さな子も入院しているため、親のいない子どもたちに些細な処置をするだけでも看護師にとっては大変な仕事だというのはわかる。
しかし、この病院に入院している子どもたちは長い間病棟に監禁され、過酷な治療に臨んでいる子ばかりなのだ。本当はこんなところにいたくないはずの子どもたちだからこそ精神的苦痛も計り知れない。みんな死と隣り合わせで、そんなことも知らずに無邪気に生活している。
だからすべてを許して甘やかせろとは言わないが、そんなストレスをぶちまけるように叫ばなくてもいいだろうと思う。せめて子どもたちに安心を与えるように、何度も優しく接してあげてほしい。
もちろん、しっかり患者の立場になって親身になってくれる看護師もちゃんといる。いつも温かい笑顔を向けて一生懸命看護してくれた方には本当に感謝している。
このことがきっかけで小児科病棟の婦長が変わり、子どもたちに対しての対応が徐々に変化していった。
あと半月で長かった抗がん剤も終わるという時、同じ病棟に入院していた小学校低学年のひとりの女の子が亡くなった。
その親子とはとても仲よくしていたため、突然訃報を聞いた時は言葉が出なかった。
その子は白血病を患っていて、先日骨髄移植を受けたばかりだったのだが、それでも先ほどまで元気に廊下を歩いていた姿がしっかりと目に焼きつけられていた。ほんの1時間ほど前だったと記憶している。
すぐに母とともにその子の病室に向かうと、ベッドの上でまったく動かないその子と、傍で涙を流す母親が見えた。
そして、涙声で必死に名前を何度も呼びながら「帰って来い!! 帰ってきてくれ!!」とすがりつく若い主治医の姿があった。レジデントの先生は周りも気にせず、大声を出しながら泣いていた。自分を含めてそれを見ていた周りのみんなも涙が止まらなかった。
本来、患者の死に涙を流す医者は駄目な医者だと言われている。悲しむことで自分が殺してしまったと認めることになってしまうかららしい。医者は患者の生き死にに感情を表してはいけない。とくにがん患者ばかりのこの病院では、なおさら心を無にして非情にならなければいけなかった。そうでなくては、患者に過酷な治療を施していくことはできないのだ。
でも、少なくとも自分は、この先生は間違っていないと思った。ずっと命を救うために頑張ってきたのだ。時にはいっしょに笑いあって、まるで家族のようにずっと支えてきたのだ。悲しいなんて言葉じゃ片付けられない感情があってもおかしくないだろう。
その後、この若い先生にはがんを扱う病院は耐えられなかったようで、しばらくして地方のふつうの小児科へ移動したと聞いた。
それに対して、頼りないとか情けないと非難する人もいた。医者としては失格だったのかもしれないが、しっかり人間味のある心を持った優しい人だったといまでも思っている。
抗がん剤治療が始まってからちょうど6ヵ月が経過した。
最後の抗がん剤が体内に残らないように「流し」が注ぎ終わったところで、点滴は抜かれた。ガーゼに覆われた左腕の局部は、何度も針を抜き差ししたことで広範囲が紫色に変色していたが、これはすぐに見た目も治るとのことだった。
しかし、いちばん気になったのは、指先がずっと痺れていることだった。主治医曰く、抗がん剤の副作用かどうかはわからないが、改善されるかどうか判断できないと言われた。
この時の麻痺が後々、自分に困難を与えることになるとは知らず、とにかくその時は気にしないようにしていた。
その後の身体の状態も正常だったため晴れて退院が決定し、手続きを済ませてお世話になった患者家族や病院関係者一同に挨拶をして、半年間お世話になった札幌のがんセンターに別れを告げたのだった。
退院してからこの監獄のような薄暗い病棟を思い出すとほとんどいい思い出などないが、自分たちが関わった子どもたちや母親たちが少しでも苦しみをわかち合い、それが希望となって救われた人がいたならうれしく思う。
たまにテレビや情報誌などで抗がん剤治療をしている方が報道されることがあるが、映された笑顔の裏では本当に過酷な戦いをしている。
そして、そんな過酷な治療を小さい子どもたちも大人と変わらずに耐えている。
もし家族や親類、知人や友人で周りにそんな子がいたら、ぜひ支えてあげてほしい。そして誇ってほしい。その子は逃げたくても逃げられない戦いを懸命に続けている本当に強い子なのだから。
第2章 ■4. 後治療と社会復帰†
2005年7月。
抗がん剤治療が終わり自宅に戻ると、いつものように弟と祖母が出迎えてくれた。実家のこのいつもの風景が本当に安心させてくれる。さらには、吉報を聞きつけた友人たちも数日の内に会いに来てくれ、喜びを分かち合ってくれた。
最後の眼底検査にて、抗がん剤により腫瘍はとても薄くなっており、あとの治療方針は再度東京の主治医に委ねるとのことだったのだが、抗がん剤が効果覿面だったことで有頂天で、この先のことなど考えずに家族や友人と楽しい日々を過ごしていた。
7月末、検査をしに東京へ向かう日。
弟も夏休みでいっしょに行けることとなり、3人で東京へと降り立った。
毎度お世話になっているペアレンツハウスも本来はふたりでしか泊まれないのだが、うちの事情を知っているファミリーハウスが融通を利かせてくれて、3人でも快く迎え入れてくれた。
翌日に国立がんセンターを訪れ、早速検査をしてもらった結果、明らかに前回診た時よりも薄くなっているとのことだった。
その言葉にまたうれしくなったが、現実は残酷なもので、先生は予期せぬ今後の治療方法を話し始めた。
確かに腫瘍はかなり小さくはなったが、完全になくなったわけではなく、これから弱って小さくなったものを死滅させなければいけなかったのだ。
そして、早とちりして安堵していた自分に告げられた治療内容は抗がん剤よりもさらに想像を絶するものだった。
ルテニウム療法。
以前まではコバルト療法と呼ばれていた治療で、これを聞いた母は唇を噛み締めながら必死に動揺を隠していた。昔、一度同じ治療をしたことがあるため、母にはどんな治療かわかっていたのだ。
放射線を発する金属を眼球にある腫瘍の存在する部分に直接縫いつける、という治療内容だ。
これを聞いた自分はまず全身に鳥肌を立たせて恐怖した。眼球に直接縫いつけるなんてとても想像したくないような処置であり、多少注射や薬などは我慢しなきゃと決心していたのが一瞬で崩れ落ちたのだった。
さらには、治療期間の1週間は放射能が外に漏れないようにするため、完全に密閉された部屋に監禁される。
しかし、嫌だなんて我儘を言いづらい状況の中で着実に話は進み、やらなければという覚悟も中途半端のまま、一気に処置日まで決定してしまったのだった。
いつもは明るく振舞う弟も、さすがにどうしていいのかわからず言葉を失ってしまっていた。
すると母は、同じ治療をした時に見ていたことを涙ながらに話してくれ、そんな過酷な治療と知っているからこそ無理強いをさせたくない、と呟いた。
まだ自分の主張もできないほど幼い我が子が辛い治療を受けながら、誰にも助けを求めることができずにひとりぼっちでいなければいけない状況。母はモニターの中でポツンと座って、玩具を触る我が子に心がはち切れる思いだったと言う。
しかし、その母の話で気持ちが一気に切り替わった。
それならば、逆にこんなの全然平気だったと治療後に教えてあげよう。こんなの恐いイメージなだけで何ともなかったと笑ってみせよう。
まだ生まれて間もない自分が乗り越えられたことなのだから、いまの自分が立ち止まってどうする? と、自分を奮い立たせたのだった。
そして、あっという間にその日はやってきた。
まずは全身麻酔をして、眼球に金属を縫いつける処置を行う。物心がついてから初めての全身麻酔だったのだが、もし眠れないまま処置が始まってしまったらどうしようとか考えて少しビクビクしていた。実際はあっという間に意識をなくしたので、恐怖する暇すらなかったのだが。
次に目が覚めた時には、密閉された小部屋のベッドの上だった。
ぼんやりした視界で周りを見渡すと、6畳ほどの部屋にベッドとテレビ台、それと外部と繋がるモニターが置いてあるだけの殺風景な部屋だった。
壁にはシャワー室とトイレに続く扉、そして厳重に施錠された重い扉と窓がある。
眼球を処置したせいか湯煙の中にいるような視界で、部屋の中を確認しただけで疲れてしまい、とくにすることもないので再びベッドで横になった。
いま本当に眼球に金属が縫ってあるのだろうか? と疑問を感じたが、そう意識すると麻酔が切れてきたのか目がジンジンと痛み始めた。その痛みは徐々に強くなり、すぐにベッドの枕元に設置してあったナースコールを押して痛みを訴えていた。
すると、数分後には機械音が響きながら厳重な扉が少しだけ横に開き、ひとりの看護師が足早に痛み止めの薬を処方してくれた。用が済むと看護師はすぐに部屋を出て行き、また機械音と同時に扉は閉められた。
ここには医者や看護師も必要最低限しか入室せず、扉が開くのは食事を運ぶ1日3回とナースコールで何かを訴えた時のみであった。何だか危険人物として扱われているみたいで切なかったが、実際に放射線を発しているのだからと納得した。
ほとんど視力もない状態のためテレビもあまりつけず、この何もできない暇な時間をただひたすらベッドの上で過ごしていた。
それでも、母と弟が毎日お見舞いに来てくれて、直接は会えないためモニター越しに話すのが唯一の暇つぶしの時間であった。
弟はせっかく東京に来ていたので、東京を見学して回っており、、その土産話がとても楽しく、わずかな時間だけでも目の痛みを忘れさせてくれた。
弟はモニター越しに見ていると、抗がん剤の副作用で頭に毛がないし監禁されているから、まるで囚人のようだとよく笑ってからかってきた。そう言われると、仕返しにモニターの画面いっぱいにハゲ頭だけを映して母と弟を笑わせていた。画面の下からゆっくりツルツル頭を上げて「日の出」というのは、さすがに弟も腹痛を訴えるくらい好評だった。
やはり最初は母も弟も不安そうにこちらを見ていたから、少しでも心配をかけまいと必死だったのだ。
起床して朝食、ぼんやり過ごして昼食、母と弟と話して夕食、シャワーを浴びて就寝。そんな毎日だった。
そして、長い長い1週間の時が流れ、最終日に主治医がこれから金属を取り外す処置をすると1週間ぶりに姿を見せた。
暇な時間をただ目の痛みに耐えるだけの日々がやっと終わる。あとは全身麻酔で起きたら、何もかもが終わってるはず。しかし現実は少しだけ違っていて、最後の最後にいちばんの試練が立ちはだかった。
処置室に連れて行かれ、ベッドに寝かされてから聞かされたのは、局所麻酔で処置を行うということだった。
思わず顔を引きつらせながら恐怖していると、それを察した主治医は全然痛くないよと励ましながら、手際よく処置を開始した。
まずは点眼で表面的に麻酔を施し、眼球を摘んでもほとんど何も感じなくなった。痛みはないが、それでも眼球を人差し指と親指で抓まれるのは決して気分のいいものではない。
次は注射で、眼球周辺に麻酔を施した。この麻酔の作業だけで全身に冷や汗があふれ出し、必死に両手を硬く握り締めて歯を食いしばって我慢していた。緊張しないで楽にしてと言われても無理な話である。
さらには、麻酔をしているからといっても、感触や痛みがないだけで視界はぼんやりと見えている。そのため、注射針やメスのような物が視界の隅で動いているのが見えてしまっているのだ。
もちろん意識ははっきりしているため、処置の生々しい音が眼前ならぬ眼中で聞こえている。ずっとすさまじい嘔吐感を我慢していた。
実際に処置にかかった時間はわずか数十分程度であったが、体感では監禁されていた1週間が比較にならないほど長く感じられた。
やっとのことで処置が終わると、フラフラになりながらも自分の足で立ち上がり、看護師に腕を支えられながら処置室を後にした。
廊下ではずっと待っていた母と弟がすぐに声をかけてくれ、がっちりと固定された目のガーゼに動揺しながらもフラフラな自分をふたりで支えながら歩いてくれていた。
その後、少し休む時間をもらってから、主治医に今後の予定の説明をされ、最後に「本当にお疲れ様でした」と労う言葉をもらった。
この日の内にはペアレンツハウスへと帰れることとなり、到着するなりすぐに布団に横になって、痛み止めを飲みながら必死に目の痛みに耐えていた。
やはり切除や縫合を行っているため、すぐには痛みは引かず、視力も回復するのに時間がかかるらしい。縫合した糸自体は勝手に溶けてなくなるみたいだが、しばらくは目の痛みと違和感にもがく毎日だった。
そして、多少その痛みも落ち着いてきたころ、まったくの偶然に運命的な再会を果たすのだった。
幼少期に国立がんセンターの小児科でいっしょに闘病していたお兄さんが、同じ場所であるこのペアレンツハウスに宿泊していたのだ。
それはおよそ18年ぶりとなる再会で、自分はまだ1歳だったため記憶にはなかったが、お互いの母親とお兄さんはしっかりと覚えていて、再会をとても喜んでくれた。
それからというもの、東京にいる間はお兄さんと毎日のようにいっしょに過ごすようになり、思い出話もいろいろ聞かせてくれた。
当時、完全看護であった国立がんセンターで親が側にいられない状況下、自分より10歳ほど年上のお兄さん含め、数名の年長者は、よく小さい子たちの面倒を見て、いっしょに遊んでくれたりしていた。それは誰かに頼まれたりしたわけではなく、みんな率先して行動していたという。
このお兄さんもまた、自ら難病を抱えて闘病しながらも小さい子たちの面倒を見てくれていたらしく、自分のこともしっかりと覚えていた。
お兄さんは闘病を続けながら様々な病気が併発してしまい、あれからずっと治療のために地元である四国と東京を頻繁に行き来していたらしかった。
そして、お兄さん家族も今回新しくできたペアレンツハウスの存在を知り、感謝しながら宿泊してみたら自分たちと偶然出会ったということだ。
これからお兄さんもしばらく東京に滞在しながら闘病し、外泊できる時はペアレンツハウスに宿泊するというので、ゲームやアニメなどの趣味も合い、暇さえあれば時間をともに過ごすようになった。
弟も交じってみんなでゲームをしたり、誰も知らないようなレトロなボードゲームを買ってきてやったりと、ペアレンツハウスではお兄さんのおかげで夜中まで盛り上がるほど楽しい時間を過ごせた。
数日後、目の状態がだいぶ落ち着いたので、経過観察のためがんセンターの主治医の元へと足を運んだ。
抗がん剤で縮小していた腫瘍は今回のルテニウム療法によって色を失い、活動している様子には見えないまでになっていた。すなわち、治療の効果は覿面で、主治医からも前向きな回答が告げられた。
ただ完全に安心はできないため、これから1ヵ月おきに冷凍凝固とがん導中という治療を後治療として行っていくらしかった。
冷凍凝固というのは低温の物質を局所に当てる治療で、がん導中は眼球に針を刺し込み、抗がん剤を直接眼球内に流し込むという治療だ。
これらは全身麻酔を用いて同時に行うため、身体の負担を考慮して1ヵ月に一度の治療となった。
その都度帰省して治療してとくり返すため、しばらくは地元と東京を1ヵ月おきに行き来しなければいけなくなった。
しかし、主治医からの前向きな診断結果もあり、毎月お兄さんとも会えるため、治療があるとは言え苦には思わなかった。
それから冷凍凝固とがん導中は、4ヵ月間の4度行われた。
これらの治療自体は全身麻酔で行うため、いままでの治療のようにとくに苦痛に感じることはなかったが、治療後は冷凍凝固の影響で数日目が腫れ上がり、何も見えない状況になってしまうため、腫れが引くまでは寝たきりの状態が強いられた。
しかし、腫れさえ引けば身体自体は元気で視力もすぐに回復するため、帰省するまでの間はお兄さんと東京見物したり、遊んだり、美味しいものを食べたりと、病気のことをすっかり忘れて楽しめる時間であった。
それからしばらく治療を続けたが、腫瘍の活動は見受けられなかった。そのため継続治療は止めて、今後は1ヵ月おきに経過観察をして様子を見ることになった。
これでしばらく検査を続けて、再発しないようならば安心してもいいだろうとの主治医の言葉に安堵し、同時に絶対に再発するんじゃない! と強く願った。
本当に、順調にいい方向へと向かっている。これならばふつうに生活できる日もそう遠くないだろうと希望が見えてきたようだった。
ペアレンツハウスに戻ってから早速、お兄さん家族にも結果を伝えると、自分のことのように喜んでくれ、今度は逆にこちらがお兄さんの治療がいい方向へ進むように願う番であった。
お兄さんは幼少期から脳腫瘍の治療をしており、その治療経過にC型肝炎とHIVを併発してしまい、現在までずっと治療を続けているのだ。自らがそんな難病を抱えながらも、いつも周りのことを心配してくれ、応援してくれている。
これから1ヵ月おきに検査に来るものの長時間かかる治療はしないため、いっしょにいられる時間が減ってしまうが、東京に来る度にお兄さんにエールを送り、時には病院までお見舞いにも行って、できる限り会うようにしていた。
ちょうど東京滞在中に11月22日が訪れ、20歳となった日にもお兄さん家族が祝ってくれた。
2005年12月。
抗がん剤治療と数度の後治療による闘病で弱った身体に鞭を打ち、早く社会復帰したいとすぐにアルバイトを開始した。高校時代に一度働いていた仕出し屋で、学生時代からずっと縁の続いている旧友からの紹介であった。
アルバイト自体は初めてではないため、要領よく仕事をこなし、弱った身体で体力が心配だったものの、再発前から鍛えていたおかげかあまり苦ではなかった。よく働き慣れていることもあり、1ヵ月もしない間にいろいろな仕事を任されるほど信頼されるようにもなっていた。
2006年1月。成人式を迎えた。
このころには抗がん剤の影響で抜け落ちた髪の毛も半年である程度は生えそろい、人前に出ても何ら恥ずかしくない見た目に戻っていたため、堂々と成人式に参加することができた。
自分が闘病していたなど少しも知らない懐かしい面々と久々の再会を果たし、みんなで記念写真も撮り、とても思い出深い成人式となった。せっかくなので髪を染めて、まだ目の調子が万全でないため薄いオレンジのサングラスをかけて行った。もちろんスーツ姿だったので、同級生からは「な、なんの仕事してんの!?」と驚かれたりもした。
次の日には無事に成人したことを祝福し、スーツ姿で家族写真を撮ったり食事したりと本当に充実していた。
その後も1ヵ月に一度東京で検査を続けながら、2月、3月とあっという間に月日は流れ、アルバイトをしながら体力回復を計り、社会復帰への道を順調に進んでいた。
そして、4月には弟も中学校に入学し、学校生活のことなどを聞いて楽しい毎日を過ごして、自分も検査の間隔が空いてきたら就職活動だな、と考えていたころだった。
ほんの少しずつ変化していったのか、自分自身でも気づかなかったことが我が身に起こっていた。
希望から絶望へ。
なぜこうも、希望を見せつけてから絶望へ叩き落とすのか?
第2章 ■5. 2度目の再発†
2006年5月。
アルバイトである仕出しの配達中に、それに気がついた。
いつも通り配達先を調べるために地図を見てみると、いままでは見えていたはずの小さな文字がぼんやりして見えなかったのだ。
そういえば、最近地図を見るためにかなり目を凝らして集中していたかもしれない。それでもいままではがんばれば見えていたのに、今回は目を凝らせば凝らすほど視界はぼやけてしまい眩暈が起こるほどだった。
しかし、何度も目に負担をかけるような治療をしていたから視力が下がったのかな? と深くは考えず、小さな文字などは虫メガネを持ち歩き、対処するようにしていた。
あまり深く気にしなかったもうひとつの理由としては、まだ1ヵ月に一度は眼底検査をしっかり行っており、2週間前に検査した時も何も問題はなかったことがある。
まさかこんな短期間で何かが起こるとは思えず、楽観視してしまったのだが、ある日帰宅した際に母がこちらを見るなり目を見開いた。驚きながらも明るい場所でしっかり見てみると、黒目の下半分が白く濁っていることがわかった。
あまり鏡で自分の目など意識して見ることがなかったので、その時初めてしっかり自分で確認してみると、白く濁っているというよりも黒目の下に何か白い粒々が溜まっているように見えた。
母はすぐにでも東京に行こうと提案したが、それでも楽観的に捉えて次の検査で十分だとそれを断った。いや、この時は楽観的というよりも、何かあったらと考えると検査してみるのが怖かった。
しかし、結局は母のしつこいくらいの強い説得により、次の日に急遽、東京へと向かうこととなったのだった。
翌日、朝早くから家を飛び出して、東京には昼過ぎに辿りついた。
検査が近づくにつれて嫌な予感が強くなる気持ちを抑えながら、重い足取りでがんセンターへと入った。
そして、早速眼底を検査した主治医は感情が乏しい表情ながらも優しい口調で、さらに詳しく検査する必要がある、と口にした。
その検査とは眼球に針を刺し、見えている白いものを採取してそれが何なのか調べるというもの。抗がん剤を始める前に勧められたが、腫瘍が飛び散ることや、網膜剥離や眼球破裂する可能性があると言われ、一度は断った検査だった。
しかし、今回ばかりはもう採取して早急に対処しなければいけないと選択の余地はなかった。一応は腫瘍本体に針を刺すわけではないため、事前に説明された危険性は少ないらしい。
早速、診察室から移動して処置室のベッドの上へと寝かされ、瞼が閉じられなくなる器具が取りつけられた。
これからすぐに処置を始めるということはもちろん局所麻酔ということで、以前ルテニウム療法の時の記憶を思い出して、強く拳を握り締めて必死に身体の震えを抑えていた。 それを察した看護師は、処置中ずっと手を握っていてくれて少し気が紛れる思いだった。
今回は目薬の麻酔だけで十分らしく、目の表面を摘まれても何も感じなくなったところで注射針が刺された。確かに麻酔はしっかりと効いており、痛みはおろか刺されていることもわからないが、どうしても頭の中で想像してしまい、その度に看護師の手を強く握り締めてしまった。
この処置はわずか5分ほどで終了して、すぐに開放されたが、気づいたらほとんど目が見えない状態となっていた。
どうやら今回の採取で眼球内の水も取っているから眼圧がかなり下がり、視力にも影響が出ているらしい。それは1日も経てば回復するらしいので安心した。
そして、後日検査結果を聞くために再び訪れる予約を取りつけ、その日はペアレンツハウスへと向かった。
いつものようにペアレンツハウス3階の広い共同スペースに来てみると、今日はすっかりお馴染みとなったお兄さんの他に、見知らぬ家族がたくさんいて室内は賑わっていた。 自分が来たことに気づくと、お兄さんを中心に皆の自己紹介が始まった。
ひとりは青森から来た高校生の子で、背が高くてかっこいい男の子であった。
ひとりは広島から来た同じく高校生の子で、まだ幼さの残る活発な印象の男の子だった。
もうひとりは大阪から来たまだ幼い子で、部屋内を元気に走り回る無邪気な男の子だった。
高校生ふたりはあまり聞かないような珍しい難病で、幼い子は自分と同じ網膜芽細胞腫の治療で、それぞれ母親とふたりで東京に来たらしかった。
患児5人と母親5人を合わせて全員で10人となった部屋はとても賑やかで、皆自分の病気のことも忘れて、楽しく話し合うほど盛り上がり、随分と打ち解けた後に皆で必ず病気に負けず、がんばろうと励ましあった。
互いに難病を抱えるからこそわかり合えること、気持ちを共有できること、それが何よりうれしく、心強く、病気になんか負けたくないと思えた。何よりこの子たちががんばっているのに自分がくじけるわけにはいけない、と思わせてくれる出会いだった。
長く厳しい闘病生活に肉体的にも精神的にも疲労し切った母親たちも互いに支えあい、協力し合うことを誓い、思えば暗く淀んでいた家族たちの雰囲気もすっかり明るく前向きになったと思う。
誰が最初に言い出したのか、5人の患児のことをまとめて「闘病戦隊がんレンジャー」と冗談混じりに言って病気と闘うんだと笑い合っていた。
そんな5つの家族で支えあいながらの生活が続いた後日、予定通り、検査結果を聞くために国立がんセンターを訪れた。
この時には、もう何となくわかっていた。すべてを理解し、受け入れられたわけでも、不安がなくなったわけでもない。でも、この時にはもう、次の治療の心構えを考えている自分がいた。
だからこそ、主治医から「間違いなく再発です」と言われても落ち込むようなことはなかった。採取したものは間違いなく、網膜芽細胞腫のがん細胞で、水晶体という部位で活動してしまっているらしい。それが集まって、白い濁りのように見えていたのだ。
他の皆が闘っているんだから負けるわけにはいかないと、それこそ正義の味方が悪と戦うように自分を奮い立たせた。たぶん他の4人も同じ考えだと思うから。
本人がすんなりと理解したことで主治医の説明はスムーズに進み、これから再発した腫瘍をどう治療するか話し合った。
まず、抗がん剤は身体の負担を考えるとこれ以上はできない。何より、前回の抗がん剤により腫瘍自体が抗がん剤に耐性を持ってしまい、もうこれ以上やっても無意味に近いとのことだった。
さらには、前回までにやってきた冷凍凝固やがん導中のような局所的な治療も今回は難しいらしい。
いままでの網膜に根付いた腫瘍と違い、今回の場合はどこかで潜んでいた小さながん細胞が、目の前方に降り積もった雪のように溜まっているから、局所的に治療しても意味がないと言う。細かいがん細胞が眼球内に漂っていることから、転移の危険性も大きいということにもなる。
じゃあどうすればいいんだ? と、疑問と絶望がよぎる。そこで主治医が提案したのは、放射線治療であった。
放射線治療はその名の通り、腫瘍に放射能を浴びせて治療するもので、多くのがん治療に効果的で用いられることが多い。もちろん網膜芽細胞腫にも効果的だということがわかっており、何より幼少期にも一度これを行い、治療している。
しかし、放射能はやはり人体に悪影響を与えてしまうもので、とくに自分の治療箇所は眼球のため、下手したら目やその周りの骨や筋肉、最悪の場合は脳にまで悪影響を及ぼす可能性があるらしかった。
さらには幼少期にも一度しており、加えてルテニウム療法もやっている。放射能は当てれば当てるほど人体に及ぼす悪影響の危険度が増すため、ふつうよりも危険な治療になってしまうことを説明された。
それでも、現状で効果的な治療はこの放射線治療しかなく、結局は選択の余地はなかった。治療したいなら放射線治療をするしかない。放射線治療をしたくないのなら、諦めて眼球ごと摘出するしかない。
答えはもちろん、わかり切っていた。
腫瘍にとって最大の治療効果を発揮する放射線治療。人体の悪影響は気になるが、他にもう治療の手立てはない。そして何より、これが最大にして最後のチャンスなのだ。
放射線治療を決心したと同時に、すぐ日程が説明された。
これから1ヵ月間、土日以外の月~金曜日で毎日10分ほど眼球に放射線を当てるらしい。そのため、平日は毎日国立がんセンターに通わなければならなくなり、東京滞在も長期間になることになってしまった。
すぐに母は自宅に残っている弟の世話を祖母にお願いし、忙しく手続きなどを行っていた。
その間、自分は放射能を目だけに絞って当てるための固定マスクを作成していた。
何をされるのか分からないままベッドに仰向けになると、「目をつむっていてください。少し熱いですよ」と忠告されながら、顔面全体を覆うほどの半流動体の何かが被せられた。
思わずその熱さに身体が震えたものの、「動かないで」のひと言で必死に我慢していたら、わずかな時間で温度が下がってくれた。
数分ほどで顔面を覆っていたものが外され、気になって見てみるとクリーム色に近いマスクのようなものが見えた。
どうやら放射線を当てる際に頭部がわずかでもずれないようにするための固定マスクらしいが、どうにもそれが『13日の金曜日』に出てくるジェイソンのマスクに見えて仕方がなかった。
こうして着々と準備は進み、早速明日から治療が開始されることとなった。
翌日、国立がんセンターで放射線を当てる部屋に案内された。
そこは厳重な扉で区切られていて、何とも重苦しさを感じる場所であった。外に放射線が漏れないようにするためで、処置中もすべて機械操作で自分以外は誰もいない状態となる。
放射線治療を受けること自体はとくに苦痛を感じるものではなく、あえて言うならば、先日作成した固定マスクでわずかな隙間もないほどがっちり顔面が固定されるため、息苦しいくらいのものだった。あとは動かないまま放射能を10分ほど当てているだけで、その間は当てられていることも気づかないほどだ。ある意味、治療よりもこの10分のために毎日朝早くから通わなければいけないことがいちばん辛かったかもしれない。
そんなわけで、とくに治療は苦痛ではなく、むしろこの治療期間はペアレンツハウスに帰ってからの皆との交流を存分に楽しんでいた。
しかし、治療も前半の半月が過ぎてくると、段々と目がヒリヒリと火傷しているみたいに痛むようになってきた。母が見てみると、白目の部分がピンク色に変色してきており、少し痛々しいようだと言っていた。しかし、放射線治療中は目によけいな刺激物となる目薬は使用できず、我慢するしかなかった。
何も予定のない時はなるべく大人しく目をつむって、少しでも痛みを和らげるようにして、皆といっしょにいる時は楽しく過ごし、痛みを忘れるように残りの期間を過ごした。
そして無事、放射線治療の1ヵ月が終了し、再び主治医に眼底検査をしてもらうと、治療により眼球が軽い炎症を起こしているだけで、溜まっていたがん細胞は見事に消失しているとのことだった。母にも見てもらうと、確かに前は黒目の下方に白いものが見えていたのに、それがきれいさっぱりなくなっているとのことだった。
すなわち、治療は大成功に終わったということで、とりあえずいまのところは放射能による脳への影響もないとのことだった。
もちろんこの結果には満足し、喜び、皆に結果を報告して、ひとり地元に残していた弟のことも心配だったため、すぐに帰省することになった。
今回はとりあえず治ったものの、いつまた再発してしまうかという恐怖もあるため、母と話し合ってしばらくは社会復帰への行動は控えて、定期的に検査しながらゆっくりと療養することにした。もちろん、もう再発しないでこのまま落ち着いてくれるのが最良なのだが、今回の再発で安心できないことを実感し、嫌でも意識するようになってしまった。
もし、次にまた再発してしまったらどうなってしまうのだろう? まだ治療する手立てはあるのだろうか?
とある日、当時気になってプレイしていた『.hack//G.U.』というゲームをしていて、ふと思ったことがある。もし、このゲームの中の世界のようなゲームが現実でも開発されたら、自分が全盲になってしまったとしてもゲームができるのかな? と。
そう考えたということは、この時から少しだけ、覚悟を決めなければいけないと考えるようになってきていたのかもしれない。
第2章 ■6. 様々な合併症†
2006年9月。
北海道はもうすっかり肌寒い季節となって、相変わらず地元と東京を行き来して定期的な検査をしながら、気持ち的に落ち着かない日々を送っていた。
母もこれまでの闘病の付き添いに加え、いつまた長い闘病に入るかわからない生活に肉体的にも精神的にも疲労を隠せずにいたため、生活保護を受けながらの生活を強いられていた。
それでも、家族3人がいつもいっしょにいられる幸せを感じながら、最近テニスに力を入れている弟の話などを聞いて、不安ながらも安らかなひと時でもあった。
そんな毎日の中で、危惧していた予感が的中し、急に目に変化が現れた。
前日までは何の問題もなかったのに、とある朝に起きてみると視界が一変していた。それは例えるならば、湯気で曇ってしまったガラスを見ているような視界で、その曇ったガラスの奥に僅かに明るさを感じられるだけであった。
もう何度こんな目にあったのだろうか? 急に見えなくなることに少しだけ慣れてしまった自分に嫌気を感じながら、すぐに東京の国立がんセンターへと向かった。
国立がんセンターにて主治医から診断されたのは、誰もが聞いたことのあるような単語であった。
白内障。眼球内にある水晶体というガラスのような部分が白く濁ってしまう病気で、悪化するといまの自分のようにほとんど見えなくなってしまうものだった。
白内障が発症するケースは先天性のものや加齢によるもの、合併症によるものなど様々だが、今回の場合は放射線治療からの合併症とのことだった。
そして、いちばん気になっていたのは治療可能なのかどうかであるが、主治医は安心させてくれるような説明をしてくれた。
白内障は手術すれば簡単に治るもので、手術自体も簡単な処置のため、とくに危惧することはないとのことだった。さらには日帰りで帰ることもできるらしく、驚きとともに胸を撫で下ろして安堵した。
もちろん視力はほぼ元に戻るが、水晶体を取ってしまうため遠近のレンズ調整ができなくなるらしかった。つまりは、遠くのものや近いものをよく集中して見ることがあるが、レンズの調整ができなくなるため、遠近感で見えづらいものはいくらがんばっても見えないということ。
水晶体という身体の一部を取り除くということに少しだけ不安になったものの、いまの何も見えない状態よりはもちろんいいわけで、ふたつ返事で白内障手術を承諾した。
手術自体は本当に簡単なもので、設備が整っていればどこでもできるということなので、それならばとなるべく近い札幌の大学病院を紹介してもらった。
早く視力を元に戻したいという焦りから、一度帰省してからすぐに札幌の大学病院を訪れ、白内障手術の日程を話し合った。
ここでは、白内障手術は一応大事を取って2泊3日で入院して行うらしい。後はほとんど東京の主治医に聞いた説明と変わらなかったが、ひとつだけ初めて聞いた説明があった。
白内障手術では、水晶体を取ってしまうだけの場合と、水晶体を取ってから人工のレンズをつけるものがあるらしい。前者の場合は、これからの人生を分厚いレンズの眼鏡をして生活していかなければならなくなるが、後者だとその眼鏡は必要ないとのことだった。
そして、この病院で行うのは後者で、これからの人生、分厚い眼鏡をかけなくてもよいことに少し安堵したのだった。
札幌の大学病院への入院日。
6つのベッドがある広い大部屋を案内され、何も見えないため、ベッドの上から動くこともできなかった。ここの病院は完全看護なので、母も付き添うことができずに病院の近くの安いホテルに宿泊することとなり、トイレなどの用事もナースコールで頼むしかなかった。ただひたすら音楽を聞いているか、寝るしかできない。
そんな暇な時間を過ごしていると、この大部屋には現在4人の患者がいるらしく、隣のベッドのおじさんが話しかけてきてくれた。すると、他のベッドの人たちもいっしょに話に加わり、少しだけ時間を潰すことができた。
目が見えないため、みんなの姿は確認できないが、最初に話しかけてくれた隣のベッドのおじさんは声を聞くにけっこう年配、窓際のベッドのおじさんは張りのある良い声なので凛々しく背の高い印象、向かいのベッドのお兄さんは自分と同じく目の見えない状態らしいが物静かで暗い感じの印象、こうして目が見えない間の暇潰しとして声だけ聞いて頭の中で姿をイメージしていた。
次の日、朝早くに手術予定だったのだが、前の患者さんの処置に手間取っているらしく、結局全身麻酔の準備を始めたのは昼くらいとなっていた。
もうすっかり慣れた全身麻酔も、病院によってやりかたが違うんだなと呑気なことを考えながら意識はなくなり、次に目が覚めたのは同じ日の夜であった。
自分が目覚めたことで医者が訪れ、手術は無事終了したので、とくに違和感や痛みがなければ目の眼帯も外してしまっていいと教えてくれた。
でも、術後で何だか怖かったので、たっぷり2時間ほど迷ってから恐る恐る眼帯を外したのだった。
それはまったくの別世界であった。まさに曇りガラスをきれいに拭き取ってくれたような違い。視界というのはこんなにきれいに見えるのか、と感動してしまうほどだった。
とくに痛みなどもなく、何だかうれしくてひとりで笑ってしまった。
それに気づいた隣のベッドのおじさんが、カーテンを開いておめでとうのひと言をくれた。声だけ聞いた印象では年配の方かと思ったら、じつはがっちり筋肉質なまだ若いおじさんだった。ちなみに、窓際のいい声のおじさんはふくよかな身体で、向かいの目の見えないお兄さんはなかなかにかっこいい人だった。
声だけのイメージだとこうも違うのかと苦笑しながらも、見えない間まったく使えなかった携帯電話で母に報告のメールを送った。携帯の画面や文字を見て気がついたが、最初に説明された通り、人工レンズを入れると確かに近い画面などは見づらく、遠くのものは目を凝らしても見えなくなっていた。でも、ふつうに生活できるほどに見えることがうれしくて、そんな些細なことは全然気にならなかった。
こうして、翌日には自分の目で見て歩きながら、母と同室の患者さんや看護師に挨拶を済ませて自宅へと帰ることができた。
帰ってからいろいろな物を見てみるとしみじみ思う視力の大切さ。テレビも見れるし、ゲームもできるし、何より自分だけで何でもできる。目が見えないと何も楽しいこともないし、何をするにも誰かの手を借りなくてはならなかった。自分だけで自分の行きたいところにも行けない辛さ。今回の短期間ですごく実感し、やはり全盲になってしまったらここまで辛いことなのかと改めて感じてしまった。
白内障手術から月日は流れ、21歳となる11月。
あれから本や新聞などは虫メガネや老眼鏡を使わなければいけなくなってしまったものの、ふつうの生活を送っていた。このまま検査も問題なければ、社会復帰のためにこの視力でも問題のない仕事を探さなければと思い始めたころ。
悪夢の再来?
またもや視界の中に、アメーバのようなドロドロしたものが見えるようになってしまった。さらには目がジンジン痛み、ひどい時には頭痛も併発させていた。
このアメーバのようなものは以前経験したことがあった。まだ働いていた時に眼底出血によって見えたものだ。眼底出血自体は眼球に衝撃が加わり、眼圧が上がったせいなどで誰でも起こりうる症状である。
しかし、自分の場合は再発の引き金となった症状で、その出血を起こしたものが前回は腫瘍であった。
何度希望をもたせ、そこからまた何度、絶望に落とされるのか?
すぐに東京の主治医に電話で相談し、すぐ東京へ行ったほうがいいのか指示を仰いだ。
すると、まずは白内障手術をした大学病院の先生も事情を知っているし、白内障手術後のことだからまずはそちらで一度診察してみてもらったほうがいい、とのことだった。
わざわざ東京に行くよりは札幌のほうが行きやすいため、再び母とともに札幌の大学病院へと向かった。
札幌の大学病院で診てくれたのはやはり、事情を知っている前回と同じ医者で、眼底出血のせいでなかなか検査しづらいところをしっかりと検査してくれた。
そして、診察結果は緑内障と診断された。
緑内障の影響で、新生血管と呼ばれる血管が破裂し、出血を起こしているらしかった。
新生血管とは本来、存在しない血管で、何らかの理由で勝手に作られた血管らしく、耐久性はもろく、少しのショックですぐに壊れてしまう。その新生血管の存在と出血の影響で眼圧も上がってしまい、目の痛みや頭痛まで引き起こしているらしかった。
恐らくは今回も、放射線治療の合併症というのが濃厚らしく、とにかく今後は緑内障の治療を進めなければならない。
しかし、ここで信じられないひと言が伝えられる。
緑内障は現在進行を抑えるための治療しかなく、完治することは難しいらしいのだ。
なので、今後はこれ以上悪化しないための治療をしていくしかないらしかった。そういえば白内障手術で入院した時、向かいのベッドにいたお兄さんは緑内障のせいで目が見えなくなり、長期間入院していると聞いていた。
再発をくり返す厄介ながんの次は完治不可能な緑内障。さすがにもうどんな反応をしたらいいのか自分でもわからず、ただ医者の話に軽い相槌を打っているだけだった。
その日はとりあえず、眼圧を抑える目薬だけ処方してもらい、後日再び治療方針を決めるために再受診することとなった。
帰ってから眼圧の目薬を使用してみると、それはドロドロとしたゼリーのような目薬で、とても不愉快な気分となり、かなり抵抗があった。さらには、目薬後しばらくは目をしっかり開くこともできなくて、いつまでも眼球にドロッとした感覚が残っている。この目薬を続けるだけでも精神的にまいってしまった。
果たして、緑内障を抑えるための治療とはどんな治療なのか? どれほど悪化を抑えられるのか? 結局は目が見えなくなってしまうのではないか?
そんな不安を拭えぬまま数日を過ごして、再び札幌の大学病院へと向かったのだった。
2006年11月。
21歳となって数日後、予約日に大学病院を訪れると、いつものようにすぐ診察は始まらず、とても長い時間待たされた。
やっと呼ばれたかと思うと、案内されたのは見たこともない場所。何やら立派な椅子と机の置いてある部屋に通されていた。例えるなら、学校で言うところの校長室のような立派な部屋。
そんな立派な部屋で再び長時間待たされ、意味もわからず落ち着かない時間を過ごしていると、慣れているいつもの医者ではなく壮年の男性が現れた。この人は教授という立場の人らしく、今回、緑内障に対してある提案があると直接話しに来たらしい。
その話とは、簡単に言うと新薬の実験。まだ日本で認知されてはいないが、外国では成果を挙げている治療法を試させてくれないかということだった。
成果に関しての難しい話は理解できなかったが、外国では8割で完治しているという成功結果を残しており、日本でも大阪などですでに試験的に実用している病院もあるらしい。さらには、一応は実験体という立場になるため、治療費はすべて病院側が負担するという条件付きだった。
実験という言葉に少し抵抗があったものの、完治不可能なものが治るかもしれないという希望が生まれた瞬間でもあった。
教授はすべてを話し終えると、後はゆっくり考えてから答えを担当の医者に伝えてくれと足早にその場を後にした。やっと来たと思ったらすばやく説明し、用事が済んだらさっさと立ち去る。教授というのは何とも忙しない人なんだな、と呆気に取られていた。
待合室に戻ると、母と新薬のことを話し合った。
と言っても、自分の気持ちはすでに決まっており、母もすべての判断を任せているため、ただの確認だった。ただ新薬というのは心配なものなので、何かあった時のために薬の名称だけはメモしておくことを条件とした。
そして、ようやくいつもの担当の医者に呼ばれ、まずは経過を診るためにいつも通り、眼底検査をすることとなった。
まだ出血があるのか、いつもより時間がかかり、医者が眼底検査に手間取っている途中ずっと、新薬は果たして本当に効いてくれるのだろうか? と、先程の教授の話を考えていた。
眼球を摘出していなくても、緑内障ならばいつかは全盲になってしまう可能性が高い。そして、緑内障は完治できない。そこで提案された、治るかもしれない新薬。
自分は一体、いつまで闘っていなければいけないのだろうか。この治療の果てに、満足する結果は迎えられるのだろうか。
このくり返される悪夢は、最後に残酷な審判を下した。
がんばっても無駄だと。希望を持っても無駄だと。諦めろと。
眼底検査を終えた医者は、いちばん聞きたくない言葉を口にした。
第2章 ■7. 3度目の再発から左目摘出†
2006年11月。
札幌の大学病院にて教授から希望の見える話を持ちかけられたすぐ後、眼底検査を終えた医者は苦々しそうに言った。
「眼球内に膨らんだ腫瘍がある」と。
最初は何を言っているのかわからず、目を丸くするしかなかった。
そんな動揺する自分に医者は落ち着いて見えたものを説明し、それは位置的に、一度は活動しなくなった腫瘍と同じ場所にある、と告げた。しかし、まだ専門の医者に診てもらわないことには断定することはできないので、一度東京で診てもらったほうがいいと勧められた。
天国と地獄の往復で何が起こったのかもわからないほどに混乱した自分を母が何とか抱えるようにして、病院を後にしたのだった。
まだ国立がんセンターで主治医に診てもらわなければわからない、と希望を持とうとする母に対して、自分は落ち着きを取り戻しても何も言わなかった。
何を考えているかもわからないほどに表情にも出さず、ただ静かにしていた。それもそのはず、考えることを放棄し、この時は本当に頭が空っぽで何も考えてはいなかった。
抱いた不安が必ず的中する気がして、本当は東京にも行きたくなかった。もうこのまま自宅で何も考えずに生活していたい。とっくに精神的にピークを迎えて、一粒の涙すら出ないほど無心であった。
そんな精神状態の中で、何が自分を突き動かしたのかわからない。結局、何の心の整理もできないままフラフラと東京へと向かった。
それはまるで死刑宣告を受けるための移動にしか思えず、気持ちは暗く沈み込んでいた。
ペアレンツハウスに到着すると、変わらず迎えてくれたのは闘病戦隊の皆とその家族だった。
いつも明るく元気に振舞っていた自分の変貌ぶりに何かを感じ取った皆は、まずはじっくりと話を聞いてくれた。母といっしょにすべてを説明し、いまどんなに辛いかも聞いてもらった。
すると、皆はこう言った。
「何も問題ないでしょ? 今回もいつものようにしっかり治して、また皆に勇気をくれるんでしょ? 今回も俺がしっかり乗り越えたから皆も絶対に乗り越えられるよ、って」
この言葉を聞いたら、何だかいまの自分が急に恥ずかしくなった。自分だけが苦しいわけじゃないのに、弱音を吐いてしまった。皆は自分と同じように苦しんで、それでもいまも生きるために必死に闘っているのに。
これまで闘病しながらも互いに励まし励まされ、お兄さん親子を中心に支えあいながら楽しく明るく闘ってきた。時には悩み、苦しみ、それでもペアレンツハウスで皆と会うと何だかそれだけでがんばることができた。
そんな皆のことを忘れて、自分だけ落ち込んでいるなんてどうかしていた。皆ががんばっている限り、自分もがんばらなければ。また皆で笑顔にならなきゃ。
そして、ひとりひとりにありがとうという言葉を残して、決心したのだった。
翌日、国立がんセンターで主治医は言った。
「治療して大人しくなっていた腫瘍の再発です。もうどんな治療をしても有効な結果は望めないでしょう」と。
この時点で、進む道はふたつに絞られた。残っている唯一の左目も摘出してしまうか、視力を残したまま短いであろう余生を過ごすか。
いざ決断となると思い悩み、考え込もうとしてしまったが、それを振り払ってすぐに決断した。
眼球摘出手術をお願いします、と。ただ、少しだけ時間がほしい。このまだ目が見えている時間に思い残すことのないように、いろんなものを見る時間がほしい。必死に訴えた。
本当ならば転移してしまう危険があるため、すぐにでも摘出するのが望ましいと主治医は言う。もし視神経から脳にまで転移してしまったら、それこそ取り返しのつかないことになると。
しかし、それでも引かなかった。これだけは絶対に後悔のないようにしたい。これから先、何年生きていくのかはわからないが、残り少ない眼の見える時間をしっかりと思い出にしたい。
そして、渋々ながらも、何が起こっても自己責任ということと週に一度検査するという条件で、手術は1ヵ月後に行うことにしてもらったのだった。
2006年12月5日から、光を失うまでのカウントダウンが始まった。
手術は、年明けの2007年1月9日。
翌日から、この残された1ヵ月で自分は何をするべきなのかを考えた。まずは、できる限りいろんな人と会い、しっかり顔を見よう。そう考えて、東京では闘病の仲間たちと時間を過ごし、地元では家族や友人とつねにいっしょにいた。ひとりでいる時間などもったいない。つねに誰かの表情や仕草を目に焼きつけていた。
会いにきてくれる皆と都合を差し置いて夜中までワイワイ騒ぐ日々が続き、寝不足になりながらも本当に充実した時間だった。眠る時間も惜しんで、次から次へと来てくれる友人に会っていた。
学生時代からの友人には、思い出として北海道を車で走り回ろうとドライブに連れて行ってもらった。結局、自分が疲れたせいで北海道一周とまではいかなかったが、晴天の日に見た両低山や札幌や旭川の街並み、たくさんの名物品を食べて、本当に一生の思い出となるものになった。
皆で人数を集めて大好きなサッカーを楽しんだこともあった。皆忙しい中、20人以上が集まって、本格的に試合をしたのは初めてだったかもしれない。自分もこの時にはだいぶ視力も落ちて、ボールが見えなかったりしたが、学生のころのように思い切り身体を動かして楽しかった。
そんな生活の中、東京滞在中にお兄さんと話しながらふと呟いたひと言に、行動を起こしてくれた人がいた。
ペアレンツハウスには、のぞみ財団「がんの子どもを守る会」という団体が同じ建物内で活動している。難病の子と家族のサポートや、様々なチャリティのボランティアなどの活動をしている団体で、自分たちもお世話になることが多かった。
その団体のひとりがちょうど居合わせていた時に呟いたこと。
「このゲームは手術後に発売だから、できなくて悔しいな」
そのひと言に、団体のひとりは秘密裏にゲーム会社へと問い合わせてくれた。そのゲーム会社とは、誰もが知っている有名な「バンダイナムコゲームス」という会社。
のぞみ財団では、未成年限定で難病の患児に対して夢を叶えようとする活動がある。先日、闘病戦隊のひとり、青森の高校生の子がファンであったカナダの歌手、「アヴィリル・ラヴィーン」というアーティストに会いたいと願った。それを聞いたのぞみ財団は必死に交渉し、青森の子の事情を知った本人は快く会うことを了解してくれたのだった。実際に会った後、青森の子はうれしそうにその話を聞かせてくれた。
そんなケースもあるのだが、自分はもう未成年ではないため、のぞみ財団として全面的に動くことはできない。だから今回は、団体のひとりが個人的に動いてくれたのだった。
12月25日。この日もペアレンツハウスで闘病戦隊の皆と過ごしていた。
すると、来客予定はなかったのだが、自分に会いに来た人たちがいると聞かされた。すぐに3階の共同スペースにその来客を案内してもらうと、まさかの人物だった。
ゲーム制作会社「サイバーコネクトツー」の社長である松山さんと、「バンダイナムコゲームス」の内山さん。
まさしく自分が「発売日は手術後だからできない」と呟いた、『.hack//G.U.』というゲームの制作・販売を行う責任者たちだった。わざわざ自分だけのために、ペアレンツハウスを訪れてくれたらしかった。
ふたりの話を聞いてみると、全盲になる前の残りわずかな時間にこのゲームをやりたいと選んでくれたことに感銘を受け、ぜひプレイしてほしいと直接駆けつけてくれたのだった。
そして、ふたりは1枚のディスクを手渡してくれた。それは、眼球摘出後に発売予定の大人気シリーズ最新作である『.hack//G.U.』の試作版であった。
もうほとんど調整は済んでおり、問題なくプレイできるということで、発売前にも関わらずぜひ楽しんでくれ、とプレゼントしてくれた。このプレゼントの裏ではたくさんの人の協力とがんばりがあったのだが、この時は何も知らず、ただ最高のクリスマスプレゼントだと喜んでいた。
他にも、ゲームに出演する声優さんが自分に宛てた応援メッセージやサイン、様々なグッズもプレゼントしてくれた。さらには、このペアレンツハウスにも患児の子が楽しめるようにとバンダイナムコゲームスが発売したたくさんのゲームソフトなどが寄付された。
ふたりともとても気さくな方で、楽しく会話もしてくれて、年甲斐もなく無邪気に盛り上がっていた。
このバンダイナムコゲームスとサイバーコネクトツーにしてもらったことは、一生の感謝と思い出としていまも多くの人に伝えている。そしてこの話は、後に松山社長が出版する本やテレビ番組でも取り上げられることとなったのだ。
年末が近づいてくると、たくさんの人と会いながらも、暇さえあればゲームをして過ごしていた。
その年最後にペアレンツハウスを訪れた時には、テレビ局の取材の話が舞い込んできた。テレビ局と言っても韓国の取材で、今度放送する24時間テレビにぜひペアレンツハウスのことを取材させてほしい、という話であった。
聞くところによると、韓国にはペアレンツハウスのような難病の子とその家族を助けるようなファミリーハウスなどの存在はなく、今回テレビで大々的に取り上げることで今後に活かしたいということだった。
そこで声をかけられたのが、ちょうど宿泊していた自分とお兄さんと広島の子の3人だった。自分たちがどのような治療をしながら生活し、このペアレンツハウスにどれほど助けられているかを説明してほしいとのことだった。もちろん3人とも快く承諾し、後日改めてカメラなどの様々な器材が準備された。
そこで3人で驚いたのが、コメンテーター兼インタビュアーとして訪れたのは、よく日本のテレビでも見ていたユン・ソナさんだったのだ。ユン・ソナさんはテレビで見るよりもずっときれいでおしとやかな方で、自分たちへの気遣いなどもしっかりしていて、とても優しい女性だった。
そして、3人でインタビューを受けた後、それぞれユン・ソナさんと2ショットで記念写真を撮り、最後に皆で集合写真も撮ってくれた。
後日、韓国のテレビ局から24時間テレビの映像が届いて早速、皆で見てみたが、自分のインタビュー中の緊張した顔がまぬけで泣きたくなったのもいい思い出となった。
年末の自宅では、空いた時間で『.hack//G.U.』をひたすらやっていた。たくさんの方の思いを受け取ってプレイしていると思うと、何十倍もおもしろくて夢中になっていた。
弟も気遣ってゲームを我慢してくれていたおかげか、『.hack//G.U.』は年が明ける前には完全にやり遂げ、後日、再び様子を見に来てくれた松山さんと内山さんのふたりに早速報告することができた。予想外のクリアの早さにふたりは驚き、ゲーム感想をうれしそうに聞いてくれていた。ちなみに、自分の感想とお礼は松山社長に録音されて、会社のほうで社員たちに聞かせたとのことはうれしい反面、少し恥ずかしかった。
人によっては、大事なかけがえのない時間をゲームに使ってよいのか? と疑問に思う人もいるかもしれないが、自分はまったく後悔してはいない。このゲームのおかげで出会えた人たちとその温かさにも触れられたし、何より素晴らしい作品を最後にできたことはとても充実した時間になったと断言できる。
2007年1月1日。
眼が見えている最後の年明けは、いつもと何も変わらず家族3人でゆったり過ごしていた。うちでは毎年とくに何かするわけではなく、3人とも自由に食べたいものを食べて、寝たい時に寝る。
元旦も親戚との縁も少ないため挨拶周りすることもなく、毎年お年玉も少ないのが子供のころは悲しかった記憶がある。だから、今年はわずかに残っていた貯金から弟にお年玉を渡してあげた。
地元ではこれまでほとんどの友人やお世話になった人たちに会うことができ、行きたい場所にも連れて行ってもらい、見たいものを存分に見た。家族の顔も一生分と言えるほど飽きるまで目に焼きつけた。
もう満足だった。気にしないようにしていたが、日に日に視力も低下して眼圧が上がっているせいで、つねに痛む目もそろそろ限界だと訴えているようだった。
もう休ませてあげよう。この22年間、いろんなものを見せてくれてありがとう。たくさん治療していつも辛かったね。
自分の眼球に話しかけるなんて馬鹿らしいかもしれないが、感謝の言葉を口にしながらそっと瞼を閉じた。
こうして2007年1月4日に東京に向かい、冬休みでいっしょに来ることのできた弟と母、それにペアレンツハウスの皆と最後の時をゆっくりと過ごした。この時には、もう鏡で自分の顔が見えないほどだった。
そして1月8日、何も抗うことなく静かに国立がんセンターへと入院した。
第2章 ■8. 東京の星†
2007年1月8日夜。
眼球摘出を明日に備えて、ひとり静かにベッドに座っていた。
とっくに消灯時間は過ぎていて、看護師にも寝るように注意はされたが、何だか眠れる気分ではない。だからと言って何もすることはなく、無意識に病室を抜け出していた。
すでに消灯時間だったので、病棟の入り口は硬く閉ざされていたが、気づかれないようになるべく音を立てずにそっと扉を開けて抜け出した。
そこはエレベーターホールで、昼間に面会に来た人たちと患者が話せるようにたくさんの椅子やテーブルが設置してある。
自動販売機に寄って、ポケットに入っていた小銭で甘いホットコーヒーを買ってから、窓際にある椅子に腰を下ろした。
昼間ならば明るく多少賑わっている空間も、いまはエレベーターも停止していて、自動販売機と非常灯だけが淡く光を放っている。周りのものも集中して見なければ、何もわからないほど暗いし、いまの視力ではよけいに何も見えなかった。
そんな中、窓の向こうだけは輝いていた。
現在入院している病棟は16階で、周りには他に高い建物もないため、それこそ昼間ならば遥か遠くまで見渡せるほど眺めがいいのだ。そして、夜中のせいもあるが、周囲に強い光を放っている建物はなかった。
では、窓の向こうで何が輝いているのか?
深夜の空を見上げた。暗い空間を明るく照らすものは、いくつもの星々だった。それは大小様々な形で、いまの自分には色もいろんな色があるように見えた。
田舎に比べたら東京は光を放つ建物が多いせいで星の光が弱いと聞いたことがある。じゃあ地元である北海道の星はどうだったであろうか? こんなにじっくりと見たことがなかったからわからない。
でも、いまの自分から見たら、東京の星もすごくきれいに輝いているように見えた。十分きれいだった。こんな視力でも、ひとつひとつはっきりと光を主張していた。
こんなにきれいな星空は初めてで、それを見ているとなぜだか目から涙が流れ落ちた。
ありがとう。最後の夜にこんなにきれいなものを見せてくれてありがとう。
母、弟、祖父母、叔母、友人、闘病の戦友、闘病を通してお世話になった人たち。皆の顔はしっかりと頭の中に焼きつけている。しつこいくらい焼きつけた。
これから先、どれほど生きているかわからないが、絶対に忘れることのないように。そして、この最後の夜の星空も一生忘れることはないだろう。
明日には自分も、この夜空のように暗闇に包まれる。いつかこの暗闇の中で、輝く星たちに出会えるだろうか? 自分もいつか誰かの星になれる日がくるだろうか?
この星たちはきっと、みんなの姿。これから暗闇の先でいつでも待っていてくれる。
皆の顔を浮かべながら、闘病生活を振り返ってみた。辛いことばかりだった。何度もくじけそうに、諦めそうになった。
そんな自分をいつも傍で支えてくれていた母には、感謝という言葉では足りないくらいだ。
何度も喜び、何度も絶望した。その都度支えてくれた友人たち。
時には死んでしまおうと思った。でも、同じように必死に生きて、必死に耐えている闘病戦隊の皆に助けられた。
そして、これからもそうなのだろう。また皆に助けられながら先に進んでいく。
光を失っても自分はこれから、誰かの光になれるだろうか? きっとなれるはず。
だから、自分は光を捨てて前に進みます。自分がこれから誰かの光になることを信じて。
星空をずっと眺めながら、そんな決意をして病室へと戻った。もう深夜の4時だった。
翌朝、いつの間にか就寝していて、目覚めたのは朝7時だった。
9時から手術開始のため8時半にはベッドにいてと言われているので、もう時間はあまりなかった。とはいえ、とくにすることもなかったので、その後すぐに訪れた母といっしょに外の空気を吸いに行くことにした。
何となく煙草を吸いたくなったが、病院の敷地内は全面禁煙のため、駐車場のほうで携帯灰皿を持って一服することとなった。
その日はとても晴れていて、眩しくて夜中のように空を見上げることはできなかった。
一服が終わると、母の提案で写真を1枚撮影した。急にカメラなど用意できるわけもなく、携帯電話のカメラ機能で撮影したものだが、よく撮れていたと思う。この写真は手術1時間前の記念となった。
いまでも、手術を控えているようには見えないほどいい顔をしていると言われている。昔から写真というのはあまり好きではなく、闘病中なんてとくに貧相な姿だったため、写真を撮ることは嫌だった。だから家族にとってある意味、貴重な1枚となったのだった。
病室に戻って数十分後には全身麻酔の前処置が行われた。あとはベッドごと手術室に運ばれるだけだが、前処置のせいで早くも眠たくなってきている目に映ったのは、母の顔だった。
もはやはっきりと表情を見るほどの視力はないが、何だか悲しそうな顔をしている気がして、最後に黙ったまま笑顔を浮かべた。
最後に見たものが母の悲しい顔なんて嫌なんだけど。と心の中で指摘しながら。
2007年1月9日。
この日、光を失った。
ーー第2章 おわりーー
はじめに
第1章 母の戦い
第2章 再発
第3章 全盲生活
第4章 視力障害センター
第5章 光に向かって
『エンターテインメントという薬 -光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの-』特設サイトはこちら
- ファミ通BOOKS>
- 連載>
- 劇薬 -エンターテインメントという薬の真実- 第2章 再発