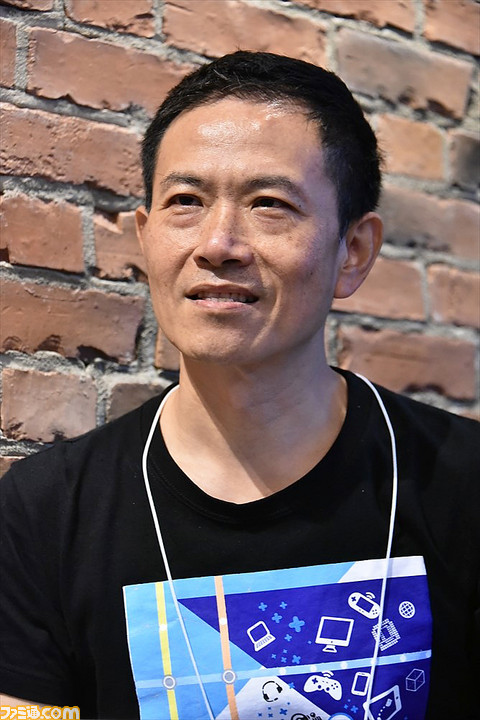日本、そしてアジアへとつなぐ
日本から飛行機で3~4時間弱の距離にある台湾は、距離的にも心理的にも日本と極めて親しい関係にある国だ。気候は温暖で(さすがに夏は暑いかもしれませんが)食べ物は美味しく、人はやさしく……(親日的であることは肌で実感します)と、海外旅行をするなら自信をもっておすすめしたい国のひとつと言える。
ゲームという切り口で見ても、日本と台湾は密接なつながりを持っていて、人材交流や技術交流が盛んだ。東京ゲームショウという場において、そんな両国の親しい関係を物語るのが、会期中に開催される“アジア太平洋ゲームサミット(APGS)”だ。台北ゲームショウなども主催する、台北市コンピュータ協会が企画するこの講演は、日台の技術交流を目的として催されたものだ。日本での開催は今年で2回目となり、今回はApp Annie Japan シニアビジネスデベロップメント マネージャー 上村洋範氏や台湾コーエーテクモ 取締役社長 劉政和氏、HTC NIPPON セールスディレクター 西川美優氏など、そうそうたる顔ぶれが壇上に立っている。
東京ゲームショウ2017の会期中、台北ゲームショウ事務局 CEO呉文栄氏ら台北市コンピュータ協会の方々に取材をする機会があった。CEOの呉文栄氏を中心に、アジア太平洋ゲームサミットや台北ゲームショウのことなどをうかがった。
台北市コンピュータ協会
台北ゲームショウ事務局
CEO
呉文栄氏(中央)
台北ゲームショウ事務局
ビジネス ディベロップメント ディレクター
林立涵氏(右)
台北ゲームショウ事務局
クリエイティブディレクター
蔡宇橞氏(左)
アジア太平洋ゲームサミットは来年も開催予定
――アジア太平洋ゲームサミットを東京で開催する意図をお教えください。
呉 アジア太平洋ゲームサミット自体は、2014年に台湾でスタートして今年で3年目になります。その名の通り、アジア太平洋地域を中心に、ゲーム業界の技術交流はもちろん、人材育成なども目的に企画したものです。東京で行うのは、今年で2回目となります。台湾以外でアジア太平洋ゲームサミットを開催するのは東京の地が初めてなのですが、東京を選んだのには、台湾と日本との交流がものすごく盛んだったというのがあります。そんな土壌もあって、日本市場に対して積極的な台湾のゲームメーカーも多く、“台湾のゲームメーカーが日本に進出する交流の場を設けたい”との意図があり実施しました。一方で、日本のゲーム関係者に台湾のゲーム市場を知ってもらいたいとの思いもありましたね。
なお、取材時にはうかがわなかったのだが、ホームページによるとアジア太平洋ゲームサミットは2014年にスタートしてから3年間で100回以上(!)もの講演をこなしているという。なんとも精力的だが、主催者のアグレッシブさを物語る数字と言える。引き続き、呉氏の言葉に耳を傾けてみよう。
――今回開催されたアジア太平洋ゲームサミット2017 in TOKYOにはどのようなテーマがあったのですか?
呉 テーマは大きくふたつに分かれています。ひとつは日本と台湾のゲーム市場のマーケティング戦略や人事育成について。ふたつ目が、いま注目されているVRです。VRに関しては、HTCの西川さんとJPW InternationalのCEO、董俊良氏などにご登壇いただき、有意義なお話をうかがいました。
――HTCは台湾の企業ですよね。台湾でもVRは盛んなのですか?
呉 VRコンテンツに関しては、発展するのはこれからといった段階です。ただ、各社さん積極的に取り組んでおりまして、たとえばJPW Internationalさんも、今年に台湾各地の5箇所に、VRのアミューズメント施設を展開しています。
トピック的にVRがタイムリーだったということもあり、「内容に自信はあります!」と呉氏は明言。マーケティング戦略のセッションでも、台湾と日本のマーケット戦略の違いや、本社と支社の考えかたの違いに起因する調整の重要さなど、異なる文化圏でビジネス展開をする上での、極めて有意義な内容が語られたようだ。ただし、課題もあるようで……。
――東京でアジア太平洋ゲームサミットを2回開催してみての手応えはいかがですか?
呉 内容的には大きな手応えをつかんでいるのですが、課題は認知度を上げることですね。講演自体の内容はとてもいいものなのですが、いかにそれを広く告知するかが課題になるかと。たとえば、紹介してくれるメディアさんひとつとっても、台湾だったらお付き合いのあるところも多いのですが、日本だとなかなか勝手がわからなくて……。
認知度をアップするというのは、イベントを成功させるうえでの重要なポイントとなるが、リリースの送付先を探すところから始めないといけないというのは、なかなかに苦労が偲ばれる。これも異国ゆえの勝手のわからなさといったところだろうか。ちょっと、気の早い話だが、来年のアジア太平洋ゲームサミットの東京での開催のことを聞いてみると……。
――ちょっと気の早い話ですが、来年東京でアジア太平洋ゲームサミットを開催するご予定は?
呉 もちろんです! 人材育成とVRは来年に東京で実施予定のアジア太平洋ゲームサミットのテーマの候補に上がっています。
と即答。そうやら、アジア太平洋ゲームサミットの東京での展開に関しては、潔いまでの前のめりのようだ。
ちなみに、アジア太平洋ゲームサミットの責任者である林氏からは、「アジア太平洋ゲームサミットを一般の方に訴求していきたい」との意外なコメントが。これまでアジア太平洋ゲームサミットは、東京ゲームショウのビジネスデイに併せて行われてきたので、てっきりビジネス関係者向けのカンファレンスかと思われたのだが、じつはそうではなくて、一般にも広く門戸が解放されているものだという。ビジネスデイに開催されると、どうしても関係者向けに見えてしまうのは致しかたのないところで、その点は林氏も認めつつも、「これからはビジネス面だけではなくて、一般の方、とくに学校関係者に訴求していきたいです」とのことだ。
さらには、“今後の目標”として、台湾、日本に続いて「韓国や東南アジアでも開催したい」(呉氏)との方針も明らかにされた。韓国での実施に関しては、G-Starの主催団体と話し合っている段階で、「うまくいけばつぎのG-Starで開催できるかもしれません」という。つぎのG-Starというと直近では今年の11月。さすがにこのタイミング(東京ゲームショウの会期中)で決まっていないのに、11月に行えるとも思えないが、改めて確認してみると“今年”だという。おそらくは記者の聞き間違いのような気がするが、相当なスピード感であることは間違いない。「アジア太平洋ゲームサミットを通して、アジアのゲーム関係者をつないでいきたい」と呉氏は言う。
台湾、そして東南アジアのゲーム事情のことなど……
台北市コンピュータ協会 呉氏たちとの取材では、せっかくの機会なので……ということで、台湾、そして東南アジアのゲーム事情についても少しお話をうかがってみた。
まずは台湾のゲーム市場規模は、日本に比べると10分の1程度らしいが、台湾に進出する日本企業の数も近年増えているとのこと。たしかに、台北ゲームショウなどを取材してみても、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが中文繁体字版へのローカライズに積極的に取り組んでいることはよくわかる。
――SIEも積極的に中文繁体字版を展開していますね。
呉 SIEさんはとても積極的に展開していますね。台湾でもプレイステーション4がとても調子がいいということが大きいです。とくに日本のクリエイターは台湾でも大人気で、台北ゲームショウでも熱狂的に迎え入れられています。一方で、SIEさんは台湾の人材も積極的に登用しているんですよ。
――日本のメーカーは、市場としての台湾に魅力を感じているのと同時に、人材の面でも台湾を魅力に感じているということですね?
呉 そうです。SIEさんだけではなくて、バンダイナムコエンターテインメントさんやセガゲームスさん、Aimingさん、アカツキさんなども台湾にオフィスを構えています。
――それだけ、台湾の開発力が評価されているということですか?
呉 それもありますが、比較的低いコストですぐれた人材を確保できるという側面も大きいかと思います。そのような需要の高さもあって、台湾ではゲーム業界を希望する人材がどんどん増えています。たとえば、美術部の学生さんがゲーム業界に入るというケースも増えています。台湾人は日本の2次元文化に親しんでいるので、文化的にも理解度が深いというのもあるかもしれませんね。
一方で、台湾のゲーム会社にとって日本市場への進出は難しいようで、「もし日本での成功に結びつけばすごく誇らしいことです」と呉氏。
――台湾発のゲームが日本市場でなかなか受け入れられない理由は、どのへんにあると思われますか?
呉 まずは、日本のゲーマーたちはタイトルに求めるクオリティーが高いというのがあります。あと、日本と台湾とでは、ゲーマーたちの好みも違います。たとえば、日本のゲーマーはストーリー性を求めますが、それに対して台湾のゲーマーは日本人ほどにはストーリー性を重視しません。シナリオはそんなに気にしないんですね。とにかく楽しむ。要は、台湾のゲームメーカーが日本に進出しようと思ったら、いろいろと調整すべきところが出てくるということです。
正直なところ、ストーリー性を求めるのは世界共通のような気もするが、“比較的台湾のゲーマーは求めない”という傾向はあるのかもしれない。いずれにせよ、日本と台湾という近い国ながら、文化の違いを乗り越えるのは、相当な高い壁となるようだ。だからこその、アジア太平洋ゲームサミットの意義ということが言えるのかもしれないが。
おつぎは東南アジアのゲーム事情に関して。さきほど、アジア太平洋ゲームサミットに関して「韓国や東南アジアでも開催したい」との呉氏の言葉を引用したが、東南アジアということで呉氏が想定しているのはずばりフィリピン。フィリピンにはESGS(E-SPORTS AND GAMING SUMMIT)というイベントがあり、ただいま呉氏らは、その主催団体と話し合いを進めているという(公式サイトの同イベントの謳い文句は、“東南アジアでもっとも大きなゲームイベントのひとつ”!)。
――フィリピンではゲーム産業は盛んなのですか?
呉 ただいま成長中といったところですね。個人的にはまだまだ課金の仕組みが整っていないという印象があります。台湾のゲームメーカーがフィリピンという市場に注目しているもっとも大きな理由は、英語圏に進出する際のモデルケースになり得るからです。これはおもにモバイルゲームになりますが、台湾のメーカーがグローバルへの進出を考えたときに、ひとつの“実験の場”として、まずはフィリピンを選ぶケースが多いんですね。フィリピンの使用言語は英語であるうえに、台湾とは距離的にも近い。いきなりヨーロッパやアメリカで展開するには、距離的にも遠いし、リスクも高いので、まずはフィリピンで試してみて、成功すれば西洋圏に打って出るというわけです。
いま、台湾から複数のゲームメーカーがフィリピンに進出しているというから興味深い。では、フィリピンのほかに有望な国はどこになるのか……。「個人的なご意見で構いませんので」とお願いしたところ、林氏が答えてくれた。
――個人的なご意見で構いませんので、東南アジアで注目している国を教えてください。
林 フィリピンのほかにはタイですね。先日台湾のメーカーがタイでゲームをリリースしたのですが、いい業績を上げていますよ。
――タイのどのへんが期待できるのですか?
林 ひとつは、国自体の環境や文化が台湾と似ていること。ふたつ目はタイのゲーマーの習慣は台湾のゲーマーの好みと似ていることです。RPGや戦略系のゲームが好きで、実況配信を見るのも大好きです。
よく考えてみると、台湾はフィリピンやタイ、シンガポールといった東南アジアとも地理的に近い。東南アジアにもビジネスを広げられることが、台湾ゲームメーカーの強みとなるのかもしれない。
台北ゲームショウ2018への参加日本企業は現時点で2017を超えている
最後に、せっかくなので台北ゲームショウについて聞いてみた。毎年1月下旬の旧正月に合わせて実施される台北ゲームショウは、来場者の熱狂的な歓待ぶりなどが印象的な熱気あふれる催しで、記者も大好きなゲームイベントのひとつだ。
――せっかくの機会ですので、台北ゲームショウの意義についてお話ください。
呉 産業の国際的な見本市として、毎年世界で最初に開催されており、その年の最新のゲーム事業がわかるようになっています。出展社も年々増えておりまして、まだ申し込みの期間中なのですが、日本のゲームメーカーも、2018年はすでに2017年を上回る見込みです。
――すでに上回っているのですか? 台北ゲームショウに対しては、日本のゲームメーカーも積極的ですね。
呉 台湾のゲーム市場は自由度が高く、コンソールでもモバイルでもPCでも、偏りなく受け入れられています。そういったモデルケースとしての側面が、各社さんの出展を促すのかもしれません。
というわけで、台北市コンピュータ協会のお三方に、アジア太平洋ゲームサミットから台北ゲームショウまで話を聞いた。日本やフィリピン、タイなどアジアをつなぐ台湾の取り組みに、今後も注目していきたい。