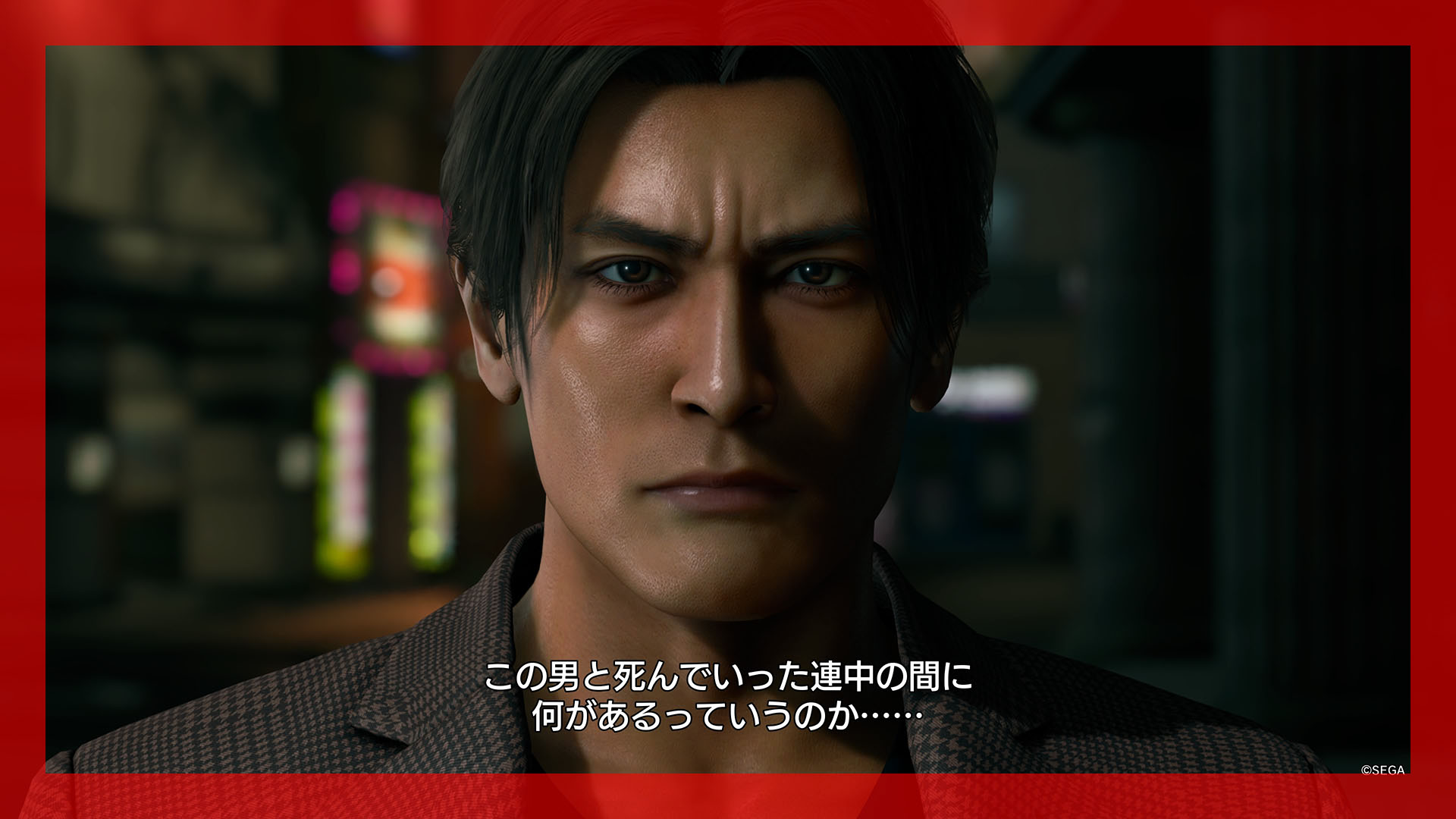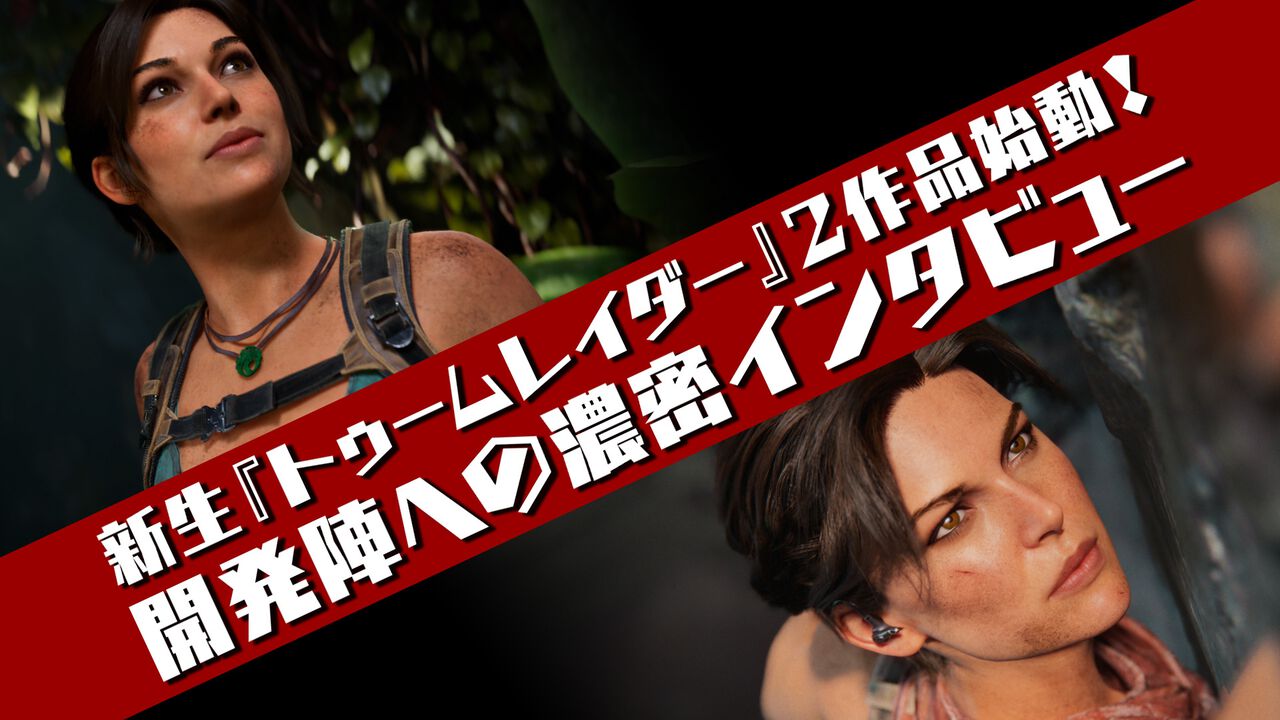2025年6月19日にNintendo Switch/PC(Steam)向けに発売予定のコロニーシミュレーション『はらぺこミーム』(Nintendo Switch版はクラウディッドレパードエンタテインメントより、PC版はドリコムより発売)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
絵本のような温かみのある世界を舞台に、プレイヤーは不思議な生き物“ミーム”たちを導きながら世界を探索したり、ミームの村を発展させていくことになる。
しかし、一見“ほんわか系”のゆるい雰囲気ゲーのようで、台北ゲームショウでの試遊台や体験版(Steamで配信中)をプレイした人々からは、ガチなコロニーシムとしての難度の高さに驚いたという意見も聞かれ、意外な顔を持ったタイトルであることも明らかになっている。かくいう筆者も、予想以上に挑戦的な難度であることに驚いたプレイヤーのひとりだ。
そんな『はらぺこミーム』について、先日掲載した体験版のレビューに続き、今回は制作陣にインタビューを敢行。本作のディレクター・人見楽氏と世界観デザイン担当の森川幸人氏のおふたりにお話をうかがい、開発の経緯や魅力に迫るとともに、試遊や体験版配信を受けてのユーザーの反応とそれに対する解決策など、本音の部分も語っていただいた。
森川 幸人(もりかわ ゆきひと)
モリカトロン代表取締役。ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイターとして活躍中。ゲーム制作での代表作に『がんばれ森川君2号』、『アストロノーカ』など。本作では世界観アート、AI設計を担当。
人見 楽(ひとみ がく)
ドリコム ゲームカンパニー第3スタジオ長。『はらぺこミーム』では、ゲームディレクション、世界観設定を担当。
“バトルなし”、“ミームは死ぬ”、こだわりが生んだ独特のシステム
――まずは『はらぺこミーム』誕生の経緯を教えていただけますか?
森川
もともとは西さん(※)が「育成ゲームを作りたい」と持ってきた企画でした。それで、せっかく僕のところに持ってきてくれたのだから、AIを使ったものを考えてみようか、と。
※西さん……本作の原案を手掛けた西健一氏。代表作に『moon』、『ちびロボ!』など。
――“はらぺこミーム”というネーミングの由来は?
森川
西さんが考えてた『はらぺこあおむし』のような絵本的世界観の企画と、私が作っていた別の企画書でミームというキャラクターをよく使っていたので、それが合わさったタイトル名となっています。じつはそれが、西さんと初めてちゃんとお話をした機会だったんですよ。お互い、この業界で20年以上もやってきたのに、ほとんど会ったことがなかったんです(笑)。
それからふたりでもう一度企画を作り上げて、「こういうゲームを作ってみませんか」とたくさんのゲーム会社を回ってプレゼンをしました。そんな中、賛同してくれたのがドリコムさんだったんです。
人見
最初はもっと違うゲームでしたよね。育成という要素と、AIを使うという世界観のコンセプトはありましたが、ゲームシステムに合わせて、世界観、ストーリーを森川さん西さんたちといっしょに開発内で練り直しました。それ以外のシステムはほぼ別物になりましたね。われわれも、最初はフリー・トゥ・プレイで配信するつもりで考えていたんですよ。イメージ的には『Sky 星を紡ぐ子どもたち』のような。
――アクションやアドベンチャーの要素も入っていたということでしょうか。
人見
最初からアクションやアドベンチャー要素はありましたが、『がんばれ森川君2号』などを参考に、分割されたステージをクリアーしていくタイプのゲームだったのが現状との大きな違いです。ただ、AIを使ったシステム作りというのは森川さんしか経験したことがなかったので、開発はすごく難航してしまいました。
そうして試行錯誤しているうちに、オリジナルや、カジュアルなF2Pゲームの市場も厳しくなっていき……。そこで、思い切って売り切りタイトルとして企画し直すことにしたんです。
森川
その際に(Nintendo Switch版の発売を手掛ける)クラウディッドレパードエンタテインメントさんにも助けていただいたり、人見さんがゲームデザインに加わるなど、スタッフがまるっと入れ替わりました。けっきょく、最初から最後まで関わっていたのは私しかいません。もっとも、最初はふわっとした感じで関わり出したのですが(笑)。
人見
その後も、とてもひと言ではまとめられないくらい紆余曲折があって、いまの形になりました。ただ、ひとつ約束事はあって、“バトルゲームにしない”ということ。それだけは最後まで貫き通しました。
森川
あとは画一的な“機械”でなくひとつひとつがバラバラな“生き物”とどうやって関わっていくか。見守るのか、介入するのか。それらのバランス取りもたいへんでしたね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
――育成ものならむしろ、バトルがあったほうが成長の理由になりますよね。
人見
そうなんです。バトルなしでどうやって成長を実感させるかはとても苦労しました。
“AIゲームの元祖”森川氏はAI以上にイラスト描きで大忙しだった!?
――『はらぺこミーム』は、その世界観も魅力のひとつだと思いますが、これはどのようにして作り上げられていったのでしょうか。
森川
もともと、中心に世界樹があるという設定は僕が提案したものです。初めは、生き物は世界樹の中に住んでいたんですよ。高層ビルみたいなイメージですね。
人見
森川さんにはゲーム化されていない部分まで、さまざまな設定画を描いていただきました。ただ、世界樹があって、ミームがいて、最高のごちそうを目指す……という基本的な内容は当初から変わっていないのですが、それ以外のところはゲームの設定に合わせてけっこう描き直していただいています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
森川
最初は村も鍋も、絵本もなかったんですよ。設定をイラストに起こしてほしいと頼まれて「ハイハイ」と描いていたのですが、いつの間にか世界樹の外の世界を作るゲームになっていたり、鍋とかできていたり……。
人見
何度もすみませんでした(笑)。逆に、森川さんのイラストからシステムに落とし込んだ要素もあったりします。
森川
でも、木の中に閉じこもっているという設定を捨てたのはよかったかもしれません。おかげで設定に幅を持たせられるようになりましたし。あとはいつか、ゲームに入らなかったイラストも日の目を見てほしいですね。
――ミームのデザインはどのようにして生まれたのでしょうか? 何とも言えないちょっとおマヌケな表情がじつに愛らしいです。
森川
まず、ミームは集団でいるキャラクターだということは、最初から決めていました。そのうえで、それぞれがどれくらいの知性を持っているのかを設定するのが難しかったですね。“宴”をやったりするくらいですから、本能だけの生き物ではない。かと言って、サルほどの社会性はないだろうと。ある程度の知性を感じさせつつも、賢くはないという感じ。
あとは単体でキャラクターが立ってしまうようにはしたくなかったので、わざと没個性なデザインを心掛けました。ハデにして個性をつけると描くほうはラクなのですが、ゲームでは使いづらくなってしまうんです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
――没個性と言っても、見た目のバリエーションはかなり種類があるようですが、何種類くらい用意されているのでしょうか?
人見
素体の種類は10体ほどなのですが、あとはさまざまなパーツやら色やらの組み合わせでバリエーションを増やしています。それを数えると数千にはなると思います。
――そんなミームたちが住む拠点には、いくつかのオーバーテクノロジーで作られた施設も存在しているようですが……。
森川
世界観全体としては、古の文明というものが存在し、ミームたちはそれを再利用して暮らしています。そもそもミームたちは都市を作っていくような知性は持ち合わせていませんしね。
一方で、草木しかないような世界になると、そこに住むのは鳥とか爬虫類とか、もっと原始的な生物ばかりになってしまいます。ミームという生き物に合わせて、現在の世界を再構成していった感じです。
人見
森川さんには、ゲームの舞台となっている空間や時間軸以外にも、周辺領域やそこにいたるまでのミームたちの歴史も含めてイラストにしていただきました。そこでイメージを膨らませてシステムに活かしたり、システムからまたイラストに落とし込んでもらったりして、少しずつ煮詰めていきました。
森川
そもそもAIを使ったゲームを作ろうということで参加したはずなのに、俺はどうしてこんなに絵ばかり描かされているのか(笑)。
人見
膨大な設定画はNintendo Switchのパッケージ限定版に48ページのアートブックという形で収録しました。ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a79d59b191996ede84d98442fd4613cb0.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a5f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
AIが生み出す“生き物らしさ”
――ここからは、ゲーム内容について少し深くうかがいたいと思います。森川さんの代名詞としても知られていたAIは、本作ではどのように活用されているのでしょうか?
森川
最近は“AI”と言ったら皆“生成AI”のことになって、おもしろくないと思っているのですが(笑)、この作品では試行錯誤をくり返しながらモノを覚えさせるために使っています。方程式ができ上がっていて、必ず同じ答えしか出ないのではおもしろくないでしょう? AIだからこそ味わえるおもしろさを見せられるいい機会をもらったと思います。
人見
ミームたちは、最初はドングリさえも食べていい物かどうかもわかっていないですからね。実際に触れてみて価値を決めていくことになります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a50c7af4300bc73d1151904ab084cd802.PNG?x=767)
森川
それこそ生き物らしい振る舞いですよね。あとは初期値のいたずらで“性格”のようなものもそれぞれ違うので、同じことを教えても反応が少しずつ変わってくる。そこに個性が生まれるので、プレイヤーもより感情移入しやすくなると思います。
――収集した資材を入れて運ぶための“袋”を置くことで、そのまわりをミームが探索するようになりますが、3体連れて行っても皆バラバラに動いてしまったりしますね。
人見
AIは全員別に設定してありますから。そのあたりじつに生き物らしいと思います。
森川
袋を置くシステムも、じつは開発後期になって入れたものだったりします。最初は、プレイヤーは本当に“見ているだけ”で『ワンダープロジェクトJ2』のように注目点をプレイヤーが指すという形にしていました。
人見
あるとき、資材を入れる袋のシステムと合体できるのではないか、と発見しまして、それでいまの形になりました。この袋のように、ゲーム内で重要なシステムでも最近になって入れたものはけっこうあるんです。
森川
そのたびに絵を描いたりなんだりしていたので、そうとう働かされましたね(笑)。
激ムズ”と言われた体験版のバランスはどう変わる?
――発売も近づいてきていますが、実際これまでのユーザーの反応、評価はどうですか?
人見
世界観については、ポジティブに評価していただいている声が多いようです。あとは実際にプレイアブルを台北ゲームショウに出展したり、Steamで体験版を配信したりしました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a0b3e6157812098b352cdeefc6c06ce17.png?x=767)
――初のプレイアブルとなった台北ゲームショウでの評判はいかがでしたか?
人見
正直に言うと、とてもきびしいものでした。長時間遊んでおもしろさが出てくるゲームですから、短時間の試遊では魅力が伝わりにくかったと思います。それに、かなりゲーマー向けの作品になっているので、かわいいキャラクターが目当てで遊んでくれた人はけっこう戸惑っていたようです。
いちおうチュートリアルは入れていましたが、どうやって遊べばいいのかわからないと。それで、フィードバックを取り入れて作り直しました。
――その後、体験版も配信されましたが、編集部でもプレイしてみてかなり難しいバランスに感じました。とくに“メンタル値”の維持がたいへんで、すぐにミームが言うことを聞かなくなったり、施設を壊してしまったりするので、維持のための“おやつ”を用意するのに全体攻略の時間を取られてしまったり。
人見
ユーザーレビューやSNSでの反応を調べてみても、メンタル値に言及する声はありました。じつは、3つあるパラメーターのうち“まんぷく値”を高く維持しておくと、メンタル値も下がりにくくなっておやつを頻繁にあげなくてもよくなるんです。拠点では1日1回、ごちそうを作れるのですが、それをあげるとまんぷく値が回復します。
森川
このゲームはさまざまな要素がそれぞれつながっているので、意外なところに解決方法が転がっていたりするんですよ。
人見
それ以外にも、1日10分という制限時間や、ミームに寿命があるといった要素など、「難しい」と感じている意見が多かったですね。もともと製品版では3段階の難易度選択を入れるつもりで、体験版では真ん中の“ノーマル”に設定していました。
しかし、いきなりプレイするとかなり難しかったようで、それを受けて製品版では大幅にバランス調整を入れる予定です。具体的には、イージーで考えていたレベルをノーマルにし、さらにやさしいバランスの難易度を用意します。
――ここまでいい点悪い点をとても正直に語っていただきましたが、ほかに注目ポイントや、ユーザーへのメッセージがあればお願いします。
人見
探索や箱庭作りの要素もありますが、本作はミームの一生を見ていくゲームです。もっと愛着を持っていただけけるような要素も追加できたらと考えています。ミームたちのお墓を作れるとか。そもそも、最初はミームが死なないようにしようという声もあったんですよね。死ぬと悲しいので……。
森川
そこだけは断固反対しました。限りある命だから生じる愛着もありますからね。
人見
実際、思い入れは強まりました。
森川
僕自身は、久し振りにAIを使った育成ゲームを世に送り出せたので、まずは楽しんで、フィードバックをもらいたいと考えています。システム面もまだ拡張できる余地があるゲームなので、フィードバックをもらって成長させていきたいですね。よろしくお願いします。
『はらぺこミーム』関連リンク
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a79d59b191996ede84d98442fd4613cb0.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a5f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/39099/a0b3e6157812098b352cdeefc6c06ce17.png?x=767)