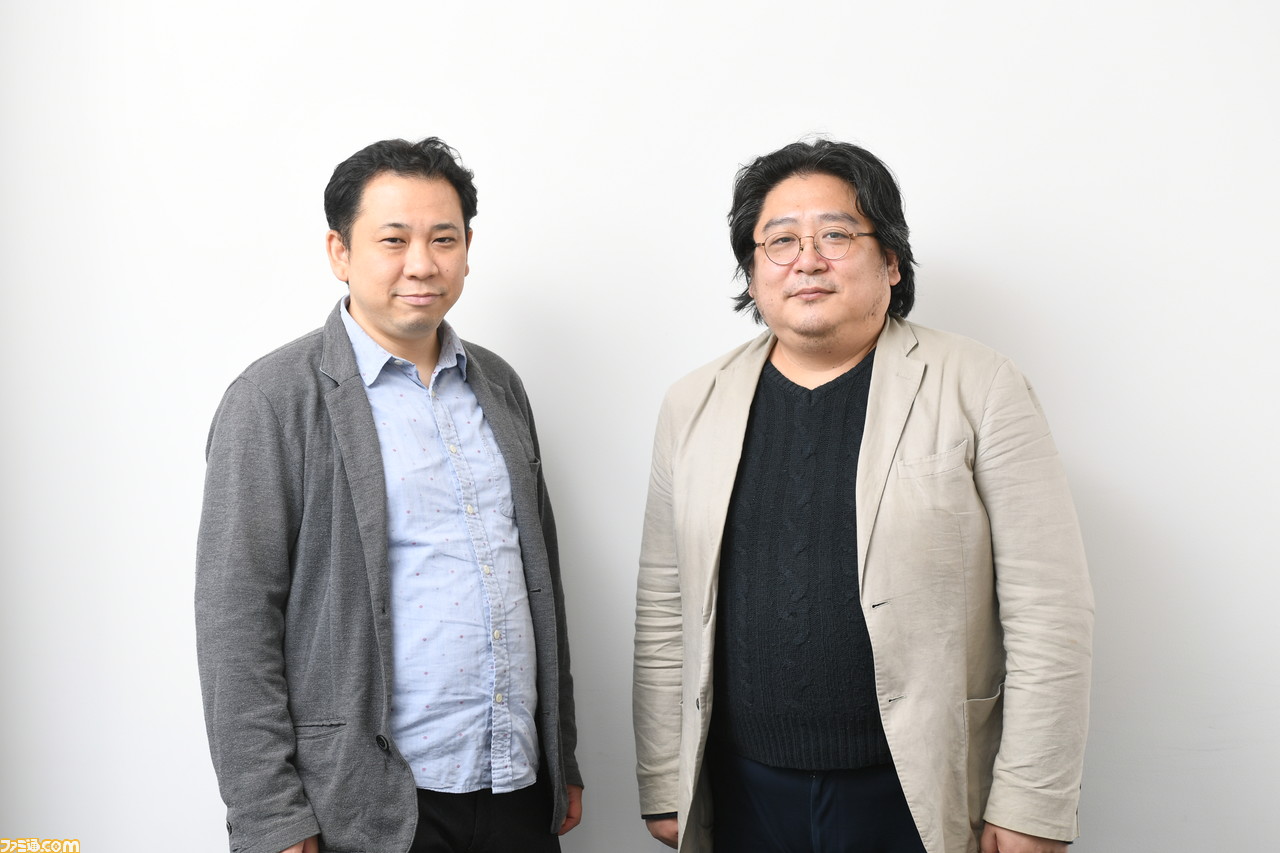2020年10月26日に日本で正式サービスを開始した『カートゥーン大戦争(英語タイトルは『CARTOON DUEL』)』をご存じだろうか? じつはこのゲーム、韓国のMUSTGAMESというデベロッパーとノックバックワークスがタッグを組んで全世界展開を始めている作品だ。
今回、ノックバックワークスのおふたりにインタビューを実施。ほかに例を見ないゲーム作りの方針や思いを聞いてきた。
秋山隆利氏(あきやまたかとし・写真右)
代表取締役社長。
代表作に『チェインクロニクル』や『黒い砂漠モバイル』をもち、ガチャシステムをゲーム市場で発案・展開。
松本恒彦(まつもとつねひこ・写真左)
取締役。
自身で法人を立ち上げ『酔わせてキャバ嬢』シリーズなど、ハイパーカジュアルゲームと呼ばれるジャンルで尖った作品を作り上げてきた。
ニアショアにオフショア、時代の先端を行く制作体制
――まずは、おふたりの役割をお伺いできますか?
秋山自分が会社の代表でプロデュースとか全体的な事業のことを行っていて、松本が役員として開発の全体を仕切っています。
――これまで業界ではどのような活動をおこなってきたのですか?
秋山自分はオンライゲームとかモバイルゲームのプロデュースを行ってきて、セガのモバイル部門の立ち上げも行ってきました。松本は自身で法人を立ち上げゲーム開発を行ってきて正式に我が社にジョインしてもらいました。
――これまで携わってきた作品を教えてください?
秋山セガ時代の『チェインクロニクル』とか、オンライゲームだと『SDガンダムカプセルファイター』とか、直近だと『黒い砂漠モバイル』になります。
松本自分は、『酔わせてキャバ嬢』というカジュアルゲームとかを、シリーズ通して開発させていただいておりました。
秋山松本はもともと鳥取でゲーム会社を立ち上げていたんです。地方でゲーム会社を作るということは、なかなかに稀有なことですよね。その中でも尖ったゲームを作っているおもしろい開発者だったので、前の会社のときにいっしょにゲームを作りたいなと話をさせてもらって、この会社につながったという流れです。
松本ジョインしたのは今年の早い段階だったのですが、いろいろなタイミングが合って、もともとのスタッフといっしょに合流しました。
――では、ノックバックワークス自体はどのような流れでできたのですか?
秋山北海道のブロックチェーンの会社に在籍していたときに、ゲーム事業の立ち上げをしたのですが、その会社がおもにセカンダリー運営(※)を行っていたこともあって、その延長線上で何か事業ができないかと考えるようになったんですね。もともとは自分の会社を興そうと考えていたこともあって、遠隔地を絡めた開発体制に可能性を感じてノックバックワークスを立ち上げました。
会社自体は東京、鳥取に事務所があり、あと韓国に支社を作るように動いているところです。設立は2018年で、現在3期目になりますね。2019年の7月に本格的に自分たちの専念したい事業をスタートして、いまに至っています。
※他社が開発・運用していたゲームを買い取って、運営する形態のこと。
――現在はどのような事業を行っているのですか?
秋山ノックバックワークスを立ち上げたいちばんの理由は、“優秀な会社といっしょになって、国をまたいですぐれたゲームを世界中のゲームユーザーに届けたい”というものです。そのための有効な会社としての仕組みが、いわゆる“ニアショア”と言われる業態です。前に所属していた北海道の会社では、いわゆる“ニアショア”と言われる業態で仕事をしていたこともあり、私たちは、ニアショア事業やオフショア事業に興味をもっていて、ニアショアやオフショアという手法で、いわゆる全世界に通じるゲーム作りをできないかということで拠点をたくさん持つような形を取ろうとしています。
――ニアショアにオフショアですか……?
秋山ニアショアというのは、東京から見た場合のニアな場所、近い 拠点という意味になります。オフショアは海外ですね。つまり、地方、海外に拠点などをもち、遠隔の多拠点で業務を行うというものになります。メリットとしては、人件費の単価が安くなるというものもありますし、ニアショアだと日本語が通じるのでコミュニケーションがとりやすい。オフショアはより単価の面が出る場合もありますが、逆に日本語でのコミュニケーションが取りづらくなる側面もあります。ただ、僕ら韓国には通訳者を常時用意していて、それでコミュニケーションが取れますし、社内にも韓国、中国を含めてバラエティーに富んだ人材がいますので、コミュニケーションが取りやすい体制ではあります。
――いま、テレワークでの業務が増えてきていますが、その最先端のような感じですね。
秋山結果的にそうなってきたという感じですね。もちろん人材とか人件費とか有効な面があってのものになります。実際に技術的なお話をさせていただくと、たとえばプログラミングは、比較的韓国や中国のほうが進んでいるんですよ。日本だとUnityに寄りすぎてしまっていて、多様性があまりないんです。それもあり、海外のエンジニアを使ってモノ作りをするほうが、いいものが作りやすいという側面はあります。
逆にグラフィックスになると、技術レベルと安さが中心になってくるので、アジアやニアショアの拠点を使って安く作るという選択になります。プランニングはむしろ日本のほうが得意なので、日本のほうで担当したりします。我が社では各国の得意なことを活かしながらモノ作りをするという体制で行っています。それが、新型コロナウイルスの影響もあり、わりとふつうにもなってきたということは言えるかもしれません。
――ちなみに、オフショアでは韓国以外に考えている国はあるのですか?
秋山中国やヨーロッパにも拠点を置きたいなと考えているのですが、まず解決しないといけないのはグラフィックスで、安くしていいものが作れる体制にしていく必要があります。そういう意味では、中国やアジア圏の拠点を考えています。
――やり取りする国が増えるとたいへんそうですね。
秋山そうですね。それでその前段に、自社にその国の人に入ってもらって、いっしょに文化を理解してもらい、現地のオフィスに赴任してもらうということをしていたりします。現在私たちは韓国のゲームを中心にスタートを切ったのですが、韓国で事業をスムーズに進めていけたのは、当社に韓国出身の優秀なスタッフが多かったという事情があります。オフショアに関しては、現地出身の優秀な人材の確保が必須となりますね。
ゲームを再利用する“ゲームリノベーション”という方法論
――設立から2年とのことですが、振り返ってみていかがですか?
秋山とてもたいへんでした(笑)。ノリと勢いでやっているところもあって、案件を取りながら会社を維持して、というのをくり返してきた感じです。その中間点として『黒い砂漠』のモバイル版のサポートをさせていただきまして、それが会社としてはターニングポイントになりました。
そこから自分たちがもともとやろうとしていた“LICENSE AD NETWORK(ライセンス アドネットワーク)”をいう事業を、立ち上げることにつながり、それを足場に自分たちの方向性を見定めたのが昨年の2019年になります。
そこからいま、ゲームリノベーションという形で、日本国内、全世界含めていろいろなゲームタイトルを集めて、それを運営したり、リノベーションとして修正や再加工、新しいゲームに作り直ししたりしています。そのリノベーション事業を進める方向付けが、ここに来てできてきたところですね。
――ゲームリノベーションというのは聞き慣れないですが、リノベーションのイメージ通りゲームを作り直すというものですか?
秋山そうですね。ゲームを作り直したり、再利用したりするということです。「少し手入れをしたら流行りそう」だとか、「グラフィックスを変えれば違うゲームとしてリリースできそう」というゲームを、ベースエンジンから調達して、その開発会社と我々がいっしょにパブリッシャーとして世の中に展開するというモデルの事業となります。
商品は当たり外れがあるにしても、たとえばラーメン屋だとおいしくても立地条件が悪かったり、具材が悪かったりしたら売れないですよね。必ずしもうまいからといって売れるというわけでもない。それと同じで、プロモーションやバランシング、仕組みづくりがうまくいっていないことで売れていないゲームは世の中にたくさんあって、そういったタイトルを発掘して、商品として最適化していく方法が、ひとつの新しいパブリッシングモデルなのではないかという発想ですね。
――ゲームリノベーションの事業は、基本的には海外タイトル中心になるのですか?
松本視野としては、海外も日本も含んでいます。その第一弾が、先日日本でも配信を開始した『カートゥーン大戦争』ですね。
『カートゥーン大戦争』は、韓国のMUSTGAMESという会社が開発したタイトルになります。もともとは『Cartoon Defense』というタワーディフェンスゲームで、プロモーション的にうまくいっていなかったんです。ゲーム的にとてもおもしろいのですが、僕らからすると、レベルデザイン的に少しミスをしていると感じられる部分もあった。それを僕らのほうでアドバイスをして、MUSTGAMESのほうで修正を施したものが、『カートゥーン大戦争』(『CARTOON DUEL』)となります。
――もともとの『Cartoon Defense』は、筋はよかったけど……という感じだったのですね。
秋山ゲーム自体はすごく新しいものだったんですよ。タワーディフェンスゲームというのは、基本的には、一方から敵がやってきて、それを迎撃するというゲームが多いと思うのですが、『Cartoon Defense』は上下左右から襲ってくるという遊びかたが新しい要素でした。基本的にタッチしておけば遊べるようになっていたので、その部分は売りとして新しい体験ではないかと判断しました。忙しいんだけど、隙間時間でちょっと見ながら遊ぶ……みたいなプレイスタイルに合うものになっていたので、だったらそのバランスや見せかた、露出の課題を解決できれば、十分に多くのユーザーに届けることができる可能性があると思ったんです。
MUSTGAMESとは共感できるところも多かったので、「だったら、いっしょにやりましょうか」ということになりました。
――『カートゥーン大戦争』ではどのような展開を予定しているのですか?
秋山いま、絶賛展開中でして、今後欧州を中心に露出展開していこうかなと思っています。11月から12月にかけてプロモーションをかけようとしています。
――日本というよりは、世界向けということですか?
秋山そうですね。基本的にカートゥーンは欧米地域での人気が高いので、そちらに向けてしっかりと届けていきたいと考えています。じつは、『カートゥーン大戦争』のもととなる『Cartoon Defense』は、韓国ではそれなりのダウンロード数は稼げていたらしいんですね。聞いているところだとシリーズ累計で500万ダウンロードとのことです。ただ、ほかの地域だとぜんぜんだめだったようで、『カートゥーン大戦争』は、いかにワールドワイドで訴求させていくかが課題となります。
――『Cartoon Defense』として、日本でも配信されていたのですか?
秋山そうですね。『カートゥーン大戦争』は、もともとあったいくつかの機能をオミット(除外)したり、新しい機能を新設したりして、新しいタイトルとして出し直した形になります。前はほとんど気づいてもらえていなかったんですよ。でもゲーム性は悪くなかったので……。全世界でヒットすれば、日本にも訴求できるはずなので、まず欧米展開に軸をおいていっしょにやっていきましょうというのが柱になっています。
――欧州向けの施策なども用意しているのですか?
秋山欧米の人たちは、どちらかというと回線が強い環境ではないので、大容量のゲームは嫌う傾向が高いようです。ですので、北米・欧州は、日本に比べるとカジュアルゲームに人気やニーズが寄っているんですね。そのため、カジュアルな範囲で、そんなにお金を使わないでも遊べて、ポイントを使いたいときにいわゆる間接課金でガッツリ遊ぶことができる、そういう課金バランスに作り直しています。
続くタイトルとおもしろさの原石を見つけて進めるリノベーション
――そのほかに進めているタイトルは、どういったものがありますか?
秋山この後は、11月半ばに『ドミノシティー』というタイトルを予定しています。同作は、韓国のGoogleが開催した、INDIE GAMES FESTIVAL 2020 KOREAで表彰されたタイトルとなります。
松本INDIE GAMES FESTIVAL 2020 KOREAという、毎年すぐれたAndroidアプリを表彰するイベントで、トップ20に入っているタイトルになります。ただ、なかなかうまくいかない要素があって、彼ら自身も困っていたところに我々がお声かけして、それでいっしょにやらないかということで話が進んだタイトルとなります。
秋山このゲームの場合は、ゲームの核となっている要素が少しブレてしまっていたんですね。それをきちんと定めてあげて、その上でどういうふうにドミノとして楽しめるものにするかということでデザインをし直して、いま共同で開発をしているところです。ミッドカジュアル向けとして、もう少し濃厚なゲームに発展できそうなので、アドモデルと、コンシューマーゲームっぽいもののふたつの方向性でできないか、模索しているところです。
――大幅に手を入れる感じになりそうですね。
秋山そうですね。ものによっては作り直すものも当然あります。
――そういった意味では、内部だとなかなかできないようなことを、スパッと判断できることが、このゲームリノベーションの強みのひとつと言えそうですね。
秋山開発に深く関わっていると、うまくいかなくなると方向性を見失うということも往々にしてあるようです。逆に当社はプロデュース会社として、解決策はわかるというのが、強みかと思います。ただ、私たちも内部にエンジニアを大量に抱えているわけでもなく、作る技術としてはそこまで高いものを持っているわけでもありません。逆にそこは、開発会社のほうが高いエンジニア力を持っていますので、お互いのニーズが合致する形になります。
つまり、企業の編成部分の機能が言ってみれば私たちで、考えかたをちょっと俯瞰してみるわけです。で、開発部門が開発会社さん。私たちがコンサルして事業の立て直しをして、売りにいくという。そういう役割分担の事業モデルですね。
――目利きがカギとなりそうですね。
秋山目利きとしての判断は、私と松本で担っています。その点に関しては、ある程度自分の能力として自信を持っています。もともとオンラインゲームのプロデューサーをずっと務めていて、複数のヒット作を手掛けてきました。
プロデューサーとしてはもちろん、いわゆる分析するスキルもあるとの自負はあります。タイトルのメカニクスを分解して、売れる要素を判断したり改善しないといけない仕組みをあぶり出したり……。もともとオンラインゲームを生業としてやってきたので、すぐに組み立てられるということはあります。その能力を買われて、セガのモバイル部門立ち上げにも参画したという経験もあり、いまはそれを自分たちの会社でいちから行っている感じですね。
――むしろ、そういうスキルがあるからこそ、ゲームリノベーションという発想にもつながるんですかね。
松本そうですね。日本の大手パブリッシャーが海外から持ってくるタイトルは、すでに売れていたり、KPIの数字がいいものが多いと思うのですが、私たちは売れている売れていないではなくて、おもしろいか、おもしろくないかを見て、やるかやらないかを判断しているんです。
――ある意味で、往年の野村克也監督の再生工場みたいな……。
秋山まあ、そんな感じになりますかね(笑)。ゲーム作りというものは、作っているとだんだんビジネス的な都合が入ってきて、ゲームが壊れていくことが往々にしてあるんですね。これは例ですが、とあるゲームでは、すごくいいコンセプトで、とても新しい発想だったのに、上層部からの“ガチャを入れたい”とのひと言でゲームコンセプトが壊れてしまったんですね。それは、仕様変更だから仕方ないという見方もできるのですが、俯瞰して見ると、ガチャにより何がおもしろい商品か、わからなくなってしまったんですね。
――上からのひと言で、ゲームがおもしろくなくなってしまうこともあるんですね。
秋山けっきょくゲームって、“それをするとおもしろい”ということを追求するものですよね。ボールを投げることがおもしろさなら、いかにその行為にバリエーションを持たせて遊ばせるかが重要なのであって、たとえばその投げる行為にお金の要素を混ぜて楽しめますよと言われたら、遊べなくなってしまう。
とくに、アイテム課金モデルにおいては、ゲーム設計の中でありがちです。それで破綻してしまったものは世の中にたくさんあります。そういうのを目利きで見ていったときに、もとのゲームはすごくおもしろいのに、この仕組によって矛盾が出てしまっているということが、関係性からわかるんです。その仕組をはずしてあげると、ゲームとして成り立つんですよ。その上で、このゲームだったらこういうマネタイズを入れると、もっと売上が上がるというのは、仕組み上、同じ理屈でわかるので、そこも直してあげるわけです。
――むしろ、現場だと気づきづらいこともあるということですね。
秋山ある意味で、会社の仕組みでしょうか。
松本トップダウンで“こういうふうにしてほしい”と言われると、その方向性に寄らざるを得ないということはありますね。
秋山トップが、NGを出したものを、現場が反発とかできないですよね。とくに大手ほどその傾向が顕著で、「まあまあおもしろくていいんだけど、なぜこうなったのだろう……」というものが多い。そういうものをちょっと直してあげるだけでも、十分におもしろいゲームができるんです。そしてそれは、ゲームユーザーにとっても“おもしろいゲームを楽しめる”という意味において、意義のあることだと思っています。ユーザー視線に立っても、ゲームリノベーションは、価値があることなんです。
――ちなみに、好奇心から聞いてしまうのですが、ゲームリノベーションの過程で、開発会社といさかいが生じたり……ということはないのですか?
秋山とくにないです。議論が水かけ論にならないようにするために、どのような楽しさを追求するものなのかという柱を明確にしています。もちろん議論することはあって、相手が納得しなくて、つぎの打ち合わせのときに企画書をガッツリと出してきたり……ということもありますが、それは“楽しさを追求する”という過程での前向きなフィードバックなのであって、きちんとおもしろさの本質に焦点を当てていれば、そこから軸が外れることは絶対にないです。
――なるほど……。けっこう理詰めな感じですね。
秋山その通りです。たとえばバランス調整では、ターゲットとしている消費者がどれくらいの時間でどういう遊びかたをして、ゲームの中でどうやって消化していくか、そしてそれがどれくらいの時間で成り立つのか……ということを精査していきます。バランス設計というのは、そういう計算の積み重ねで全部成り立っていくんです。ゲームのバランス設計で失敗しているのは、この辺を全部感覚で作ってしまうからです。で、できあがってアプリをオープンした結果、1日で終わってしまう。
――感覚でやってはいけないということですね。
秋山そうですね。私は、オンラインゲーム自体50~60本ほど関わってきているので、いわゆる定量定性という数字はつねに頭にあるんですね。「こういうゲームなら、これぐらい遊ぶだろう」というのを、逆算していく感じになります。
現状動いているタイトルは26本。IPを活用した展開も
――現在、どれくらいのタイトルが動いているのですか?
秋山26本くらい保持しているタイトルがありまして、そのうち8ラインはすでに走っている感じです。
――26タイトルもあるのですか?
松本調達してきたタイトルが26本くらいですね。その中からいけそうなタイトルを選別して、開発に着手しているのが8タイトルとなります。それ以外は工数的に負荷が高く、とりあえず優先順位から外しているという感じです。
――とりあえず、8本が出すメドが立っているということですね。ちなみにものによるのでしょうが、ゲームリノベーションには、だいたいどれくらい時間がかかるものなのですか?
松本『カートゥーン大戦争』はだいたい約2ヵ月ぐらいです。
――そういう意味では、2ヵ月で生まれ変わるんですね。
秋山はい。企画が2週間くらいで開発1ヵ月くらい、それにテスト2週間という感じです。
――ちょっとした工夫で何とかなるんですかね。
秋山なる可能性はあります。
松本ただ、やはりもともとのゲームによります。大手術が必要なものもあれば、そのままでプロモーションだけしっかりとやれば、ヒットする可能性もあるタイトルもある。僕らがそれをいろんな角度から多角的に分析して、提案している感じです。
秋山ものによっては、ベースの仕組みだけを活用して、ほとんど原型を留めていない企画もあります。ただ、そういうのは当然のこと負荷が高くなります。
松本中には、「これを人気アニメのIP(知的財産)に寄せよう」という提案をすることもあります。それをするためには原資が必要なので、取りに行きましょうということにもなります。
秋山ゲームリノベーションの延長には、代理営業も当然入ってくるので、そこも含めて活動している感じですね。
――どのゲームとどのIPをマッチングさせるのかというのは、判断が難しくはないのですか?
秋山ライセンスものも長くやっているので、その辺もある程度は判断がつきます。ただ、IPの組み合わせと言っても、ゲームのベースの仕組みが成り立っていることが大前提で、その魅力を最大限活かせる道を考えたときの選択に、IPが存在するということです。IPありき……という話ではありません。そういうものに対しては、積極的にマッチングしていきますね。
――IPはやはり強いですか?
秋山そのゲームを最大限有効に表現できる手段としては、あると思います。
松本あとIPがプロモーションの一環としても使われことも強みではありますね。
――10月に『カートゥーン大戦争』、11月に『ドミノシティー』とリリースされて、今後どのくらいのスパンでタイトルはリリースされていくのでしょうか?
秋山松本には、「1ヵ月に1本は出していきたい」と無茶ぶりをしています(笑)。
松本(苦笑)。
秋山ただ少し死にそうな雰囲気ですので、もう少し緩やかになるかとは思います。
――そうすると、2021年では10~12本ぐらい出るといいなという感じですか。
秋山そうですね。一方で、“LICENSE AD NETWORK (ライセンスアドネットワーク)”というプロジェクトもありまして。
――ああ、さきほどおっしゃっていましたね。“LICENSE AD NETWORK”とは、どのようなものなのですか?
松本IPライセンサーさんにIPを提供していただいて、ゲーム会社に「それらのIPを使って、ゲームを作りませんか」という声掛けをしていて、それでゲームを提供するネットワークを“LICENSE AD NETWORK”と呼んでいます。カジュアルアプリを媒体とした、新たな広告モデルサービスのひとつとして、2020年秋に立ち上げさせていただきました。カジュアルアプリに相互送客させることで、アニメIPの持っているユーザーと、参加しているゲームユーザーを獲得していくことを狙いとしています。
秋山世の中には、言ってみれば忘れられたIPもあるのですが、IPには根強い人気があります。そんなIPを活用してたくさんの選択肢を提供したいというのが、展開できる仕組みになっています。
――ああ、“LICENSE AD NETWORK”も言ってみれば、IPのリノベーションと言えそうですね。
秋山いまって、選択肢があまりないですよね。ソーシャルゲームだったらキャラクターコレクションがあってガチャで遊ぶ。ハイエンドになるとオープンフィールドのゲームが主流になっていたりします。でも、かつてのファミコン時代って、「ちょっとおバカだけど、こんな変なモノをよく出していたよね」というゲームもけっこうあって、その選択肢の恩恵もあって、豊かなゲーム体験になっていたと思うんです。『たけしの挑戦状』なんて、その最たるものですよね。そういった選択肢が最近ないとすごく思っていて、それをいろいろいろな形で作っていけたらというのが、“LICENSE AD NETWORK”の根幹にあります。
松本中小の開発会社って、宣伝力が弱かったりしますよね。とにかくおもしろいものを突き詰めて作っていって、どうやって宣伝するのだろうと考える中で、手軽にIPが使えるとなると、たくさんの人に遊んでもらえる機会も増えます。そういうことができる取り組みとしても、“LICENSE AD NETWORK”は有用性があるのかなと思っています。
――つまり、ノックバックワークスは、ゲームリノベーションと“LICENSE AD NETWORK”を事業の2本柱として展開していくということですね?
秋山そうですね。
――ちなみにゲームリノベーションの対象プラットフォームは、スマホを考えているのですか? それとも家庭用ゲーム機での展開も今後はあり得る?
秋山いまお話をいただいているタイトルは、スマホからNintendo Switchまでけっこう幅広くあります、正直、家庭用ゲーム機向けは、選択肢としては考えています。ただ、投資規模がいささか多いので、実際に動かすとなると少し慎重になりますね。
松本さきほどお話したアニメIPとのマッチングを検討しているのが、まさに家庭用ゲーム機向けに展開しようかと考えているタイトルです。じつは3タイトルあります。予算規模を解決しないといけないですし、実現にはまだ少し時間はかかるかもしれません。さすがに1年くらいの規模にはなってくると思います。
――いずれにせよ、そのタイトルのおもしろさを最大限に活かすための最適な手を選択するということですね?
秋山そうですね。私たちは、ゲームタイトルを持て余しているメーカーの、ある意味で代理店的な立ち位置だと思っていて、編成機能としていろいろな営業から販売から企画まで、幅広く展開している会社という感じです。海外の会社の日本での展開をお手伝いするというわけではなくて、むしろそのゲームを使って全世界でどうしましょうか、というのをいっしょに考える会社ですね。
もちろん、国内開発会社さんからのお話も積極的にうかがっていますよ。
――お話をうかがうにつれ、あまり例を見ないおもしろい立ち位置の会社ですね。
秋山ある意味で、わけわからない会社でもあると思いますけど(笑)。好きなことをさせてもらっているとは思いますね。
いまの日本って、若い子がゲームを作りたいと思っても、お金の敷居がけっこう高いんです。海外とは違って、ゲームの投資にあまりポジティブではないんですね。銀行が、ゲームに投資をしてくれない。だから若い子に意欲があっても、なかなか独立できなくて、大手の外注となって終わるケースも多いんです。これをどうにかできないかということで思って作っている事業でもあります。新しいゲームの共同体みたいなものができるといいかなと思っています。
――最後に、今後の豊富をお願いします。
秋山世の中のおもしろいゲームを探してきて、ちゃんと評価されるように展開したいと思っています。ユーザーの皆さんには、そんな私たちの提供するタイトルに注目してほしいです。“ノックバックワークスの提供するゲームはとにかくおもしろい”と、思っていただけるようにがんばります。
松本原体験として、自分たちのゲームが埋もれていたという思いがあるので、中小の会社でいっしょになって、ゲームを盛り上げていける取り組みができればいいなと思っています。今後にご期待ください!