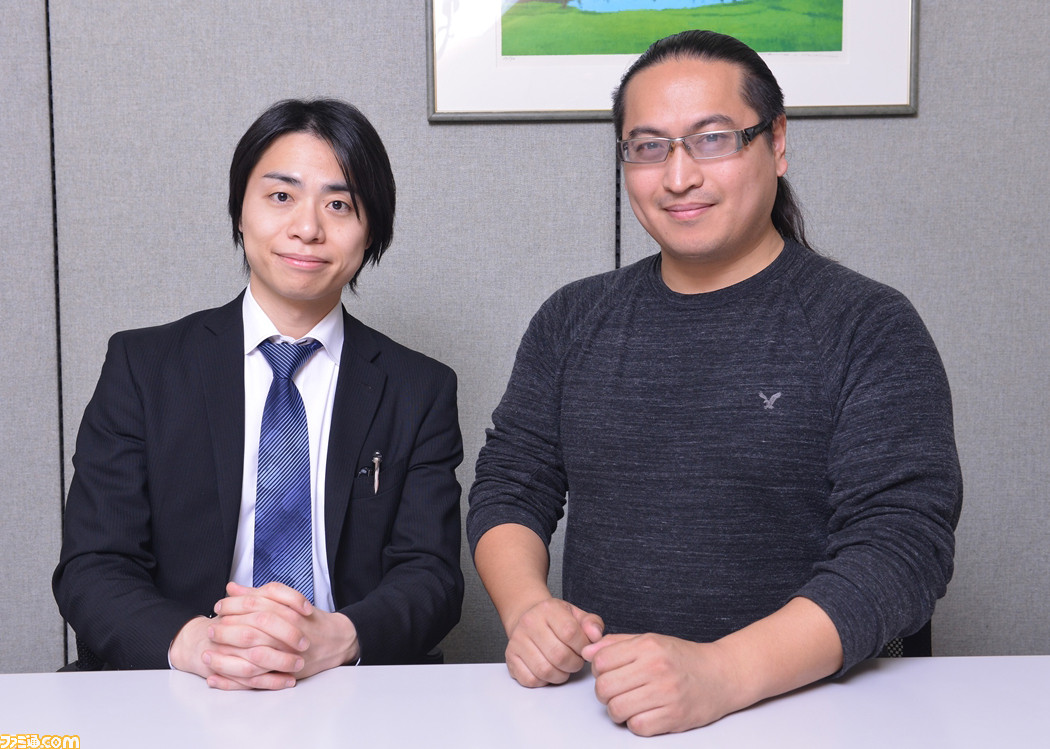プレイステーション VRやOculus RIFT、HTC Viveなどのデバイスが立て続けにリリースされた2016年を“VR元年”として、着実に認知度を高めてきたVR(仮想現実)。プレイステーション VRの好調なセールスはもちろんのことだが、市場には数多くの業務用VRデバイスや施設が出現。「休日の娯楽はVRで……」という状況も増えている。さらなる普及に向けて、まさに“追い風”といったところだ。
そんなVR業界にあって、関係者のあいだからひとつの懸案として口にされていたのが、いわゆる“13歳問題”。ご存じの通り、多くのVRデバイスでは対象年齢を13歳以上としており、そうでないデバイスについても、施設ごとに異なる年齢基準にて規制や運用をしているために、VRデバイスを幅広い層に訴求する……というときに、大きなネックとなってしまうのだ。
そんなときに、年明け早々気になるニュースが飛び込んできた。バンダイナムコエンターテインメント、ソニー・ミュージックエンタテインメント、イオンリテール、フタバ図書、ハシラス、電通、CAセガジョイポリス、アドアーズ、タイトー、カプコンなど、ロケーションベースVRの運営に関連する企業により構成される一般社団法人ロケーションベースVR協会が、VRコンテンツの利用年齢に関するガイドラインを制定。これは、13歳未満7歳以上の子どもに関し、自主規制として新たな年齢基準および遵守条件を設定した注目すべきガイドラインだと言える。
極めて興味深い内容だが、このガイドラインにはどのような根拠があり、いかなる趣旨のもとに策定されたのか。そちらに関しては、ロケーションベースVR協会の公式サイトにある “ガイドラインに関するQ&A”に極めて詳しく記載されているが、ファミ通ドットコムではロケーションベースVR協会の代表理事 安藤晃弘氏((株)ハシラス代表取締役)と理事・事務局長 三好慶氏(弁護士)にインタビューを実施。改めておふたりの口から、今回のガイドライン制定の経緯などをうかがってみた。
一般社団法人ロケーションベースVR協会
安藤晃弘氏
代表理事
(写真右・文中は安藤)
三好慶氏
理事・事務局長
(写真左・文中は三好)
“13歳問題”の対応に向けて……
――せっかくの機会なので、まずはロケーションベースVR協会の何たるか、から教えていただけないでしょうか。
三好 ロケーションベースVR協会とは、ホームユースVRではなく、ロケーションベースVR(ヘッド・マウント・ディスプレイによるバーチャル・リアリティ映像と、体感ハードウェア機器などを連動させ、よりリアルな体験を提供するバーチャル・リアリティ・コンテンツ)事業の運営に関連するメインプレイヤーを中心に構成されている一般社団法人となります。VRという幅広い業界においても、ある程度ロケーションベースVRに特化することによって、共通の問題意識を有する事業者が集まり、最大公約数とはならない新機軸を打ち出せるのではないか、という考えで設立されています。また、施設型VRであるがゆえに、ハイエンドの先端コンテンツが揃いやすいことから、“VR業界をリードし、業界の発展に貢献していければ”という考えも持っております。設立自体は、2017年5月8日と、比較的新しい団体ではありますが、ありがたいことに多くの賛同を得ることができ、現在では、会員数20社以上を数えるようになっています。また、会員各社以外にも、政府系法人の方や学者の方々にもオブザーバーとして参加していただいています。
――どういった経緯で設立することになったのですか?
安藤 私は、ハシラスというコンテンツ開発会社の代表取締役社長を務めていますが、当社は、没入型のHMD(ヘッド・マウント・ディスプレイ)を使用するVRに関しては、かなり初期の段階から、体感型のコンテンツ制作に携わってきました。そのため、初期のころに立ち上がったロケーションベースVR施設には、当社のコンテンツが入っているケースが多く、VR施設運営会社とのつながりができていました。そんな中で、“一度肩を並べて情報交換の機会を持てれば”ということで集まったのが、発足のきっかけになります。2017年4月7日のことですね。
――情報交換の場から、ロケーションベースVR協会はスタートしたんですね。
安藤 その通りです。2017年初めの時点においても、ホームユースVRが一気にコンシューマーに普及するという段階にはなく、現実的には、ロケーションベースVRが、ユーザーにとってのタッチポイントになっていました。VR業界は今後さらなる伸びが見込まれていますが、ユーザーの多くにとって、生まれて初めてVRに触れる機会がロケーションベースVRになりますので、“VR業界を私たちが牽引していく”という気持ちで、当協会を立ち上げました。
――そこで取り組むべき課題としてあったのが、いわゆる“13歳問題”だったのですね?
三好 はい。立ち上げ時に、ロケーションベースVR業界のさらなる発展のためにクリアーすべき“共通の課題”を挙げていきました。その際、オペレーションの負担軽減など、さまざまな意見がありましたが、もっとも早期に解決すべき課題として共通していたのが、いわゆる“13歳問題”、すなわち、13歳未満の子供のVRコンテンツの利用について、統一的かつ明確な利用基準がなく、施設ごとに異なる運用がなされてしまっているという問題でした。
――協会員のあいだでは、それはどのような感じで議論されていったのですか?
安藤 まず順番としましては、先ほどの話にもありましたように、統一的な利用年齢の基準がないということが問題であるということからスタートしました。そして、利用年齢の基準を作成する際には、VRについて子どもの視覚に影響が出た事例はないかということも調べていきました。そうしたところ、事例として報告されていたのは、3D眼鏡によって生じていた1980年代の1件のみであり、また、それに関しては、そもそも没入型のHMDによって生じたものではなく、立体映像生成の精度にも現在とは大きな差がありました。また、両眼立体視を行うHMDにおいて、問題が生じるというような実証は、現在に至るまで発表されていません。
三好 そういう意味では、本件はトランスサイエンス(科学に問うことはできるが、科学によってのみでは答えることのできない問題)的な問題でもあり、少なくとも公開文献の限度で検証した結果、現時点で医学的に完全な立証は行われていない、ということも分かりました。そこで、現時点で判明している医学的見地をもとに、もし新たな事例や医学的なエビデンス(証拠)が出てきた場合には速やかに対処するという方針で、一定の年齢基準を設けることとしました。
――では、ガイドライン策定に向けて、どのような感じで動かれていったのですか?
安藤 ガイドライン策定に向けては、3つの基礎資料を収集、確認していくことにしました。ひとつ目は“有識者からの意見聴取”。ふたつ目は、過去にどれだけ世界中で症例があるかの“事例”。そして、3つ目は、医学的見地から見ての目の発達に関する“エビデンス”です。この3つを基礎資料として確認しつつ、業界全体の動向なども集め、なおかつ協会会員である各社の知見も照らし合わせたうえで、「この基準でいいのか?」というのを策定していきました。
三好 医学的なエビデンスに関しても、医学部名誉教授の先生にご協力をいただき、医学文献や論文を頂戴したり、直接ご意見を伺ったりして慎重に検討いたしました。
安藤 そのように慎重に検討した結果として、対象年齢を7歳以上とするガイドラインを策定することになったのです。
三好 そのうえで、単に対象年齢を7歳以上とするだけではなく、保護者の同意や眼科的疾患がある場合の専門医への相談を条件とし、また、利用時間や休憩時間に関しても、VDT (Visual Display Terminals:ディスプレイ、キーボード等により構成される視覚表示端末装置のこと)作業における安全管理のためのガイドラインなども一部参考にしつつ、できるだけきびしい基準を設定することになりました。
――7歳という対象年齢の策定は、一定のエビデンスに基づいて策定されたということですね。
三好 はい。もちろん完全な立証は困難ですが、一定のエビデンスに基づいて策定されています。視覚というのは、その機能ごとに発達する年齢が異なってくるのですが、没入型HMDの使用に関連する立体視機能については、7歳までには基本的な発達は終了しているという文献が多数を占めています。
――なるほど。いずれにせよ、相当きびしめに設定したようですね。
三好 そうですね。ガイドラインを策定するに当たっては、本当にいろいろな意見が出ましたので、何度も議論を重ねたうえ、安全な基準となるように厳格な設定にしていきました。また、この基準は、教育目的での活用も想定していたため、そのような場面も想定して慎重に検討を行いました。VRの可能性は、決してゲームの分野に留まるものではありません。VRコンテンツは、教育分野においても、非常に大きな効果を有するものであると考えています。
安藤 VRとして“体験する”ことで、通常の学習に比べて非常にインプレッション強く学べるというのは、容易にご理解いただけるのではないかと思います。教育分野においてVR技術の活用が非常に期待されており、世界各国が教育を目的としたVRコンテンツの開発に踏み込んでいるにもかかわらず、日本はここで出遅れてしまっているというデータもあります。
――今回、ロケーションベースVR協会さんが明確なガイドラインを設けることは、VRデバイスメーカーにとっても大きな後押しになるかもしれないですね。
安藤 どうでしょう。その辺は急には変わらないのではないかと、私たちは考えています。HMDメーカーもさまざまな事情を折込んで、対象年齢を設定しているでしょうし。
三好 もちろん、HMDメーカーが当協会より厳格な基準を設定している場合には、当然にHMDメーカーの基準が優先することになります。当協会としては、基本的に“HMDメーカーの基準に準拠する”というスタンスです。あくまで、当協会の基準は、HMDメーカーが基準を設定していない場合、または、当協会よりも緩やかな基準のみ設定している場合に適用される自主規制になります。もっとも、現在ロケーションベースVRにおいてもっとも普及しているHMDであるHTC Viveについては、推奨年齢が撤廃されておりますので、本ガイドラインを適用し得る範囲は、当初の想定よりも大幅に増加するのではないかと考えています。
――ガイドラインの注意事項を拝見すると、細部に至るまでご配慮されたんだろうなあということが伝わります。
安藤 伝わったのでしたら嬉しいです。
三好 ガイドラインが完成するまでは、条文の細かい文言に至るまで、協会の会員各社にて議論を尽くして決めていきました。それこそ、“三人寄れば文殊の知恵”という言葉もありますが、会員各社の知見とネットワークを駆使して、ようやくリリースまでたどり着くことができました。
安藤 実際のところ、ロケーションベースVR協会を設立した直後に、すでに叩き台はできていたんです。でも、そこから叩きまくってですね(笑)。
――とくに盛んに議論が交わされたのは、どの部分だったのですか?
安藤 プレイ時間ですね。継続プレイ時間と休憩時間に関しては、会員各社において意見が分かれたところでしたが、業界の健全な発達を考え、安全性を高める方向へと議論が進んでいきました。
――開発者サイドから言えば、プレイ時間でゲーム性も変わってくる部分もありますからね。
安藤 そうですね。この議論も踏まえて思ったことは、これは生きたガイドラインになるべきで、発表して"これで終わり”としてはならないということです。これからも関連する情報を逐次集めて、業界の動向を見る中で、変更すべきところは変更していこうという方針でいます。
三好 本ガイドラインでは、利用時間と休憩時間に関しては、“連続20分のご利用に対し、10分から15分程度の休憩を取ってください”と明記しています。安全性を高める方向で議論が進んでいった結果、VDT作業における安全衛生のためのガイドラインなどと比較しても、きびしい基準になっているのではないかと思います。
安藤 もちろん、当協会は任意団体ですので、ガイドラインに関しては、“業界全体が守らなければなりません”という強制力まで持つものではありません。運営業者ご自身の任意の判断で、ご自身の責任で一部を変更のうえ使用することもあるでしょう。ただ、業界全体が準拠してくれるようになるとうれしいという思いはあります。
ゲーム以外の可能性としてのVR
――ガイドラインを発表されたあとの反響はどんな感じでしたか?
三好 関係各社から、好意的な反応や問い合わせをいただいています。また、HMDそれ自体の年齢基準についても、先日、会員であるクリーク・アンド・リバー社の関連会社が日本代理店を務めるHMDメーカー(アイデアレンズ社)製品に関し、日本における利用年齢基準を当協会の基準に準拠する、という内容のプレスリリースが発表されたりしています。
――店舗さんにおいても、新しいガイドラインに準拠する流れですか?
三好 当協会に加盟している会員は施設の運営事業者が多いですが、その一部では、早くもガイドラインへの準拠を開始したとの報告を受けています。
――ああ、そうなんですね。そもそもロケーションベースVR協会というのは、店舗側を中心に構成されている一般社団法人なのですね。
三好 当協会は、VRという幅広い業界において、とくにロケーションベースVRに関する共通の問題意識を有する事業者が集まり、これらを解決していくというのが設立の趣旨ですので、店舗側の皆様が中心的なメンバーとなっています。
安藤 私が代表取締役社長を務めるハシラスはコンテンツを制作する会社ですが、冒頭でお話ししたとおり、単純に店舗側の皆様とつながりがあって、VR業界の悩みや問題点などに気付ける立場におりました。私が行ったのはあくまでロケーションベースVR協会という団体作りであって、あとは、“13歳問題”という重要な課題があったために各社の力が結束されていったように思います。私は、今回のガイドライン発表は、各種の課題解決への取っ掛かりだと捉えていて、ロケーションベースVR協会は、ともに手を携えて業界自体を大きくしていける期待の場所だと思っています。
――加盟企業が連携して、VR業界を盛り上げていくべきだと?
安藤 はい。加盟企業が相互の意思疎通や情報交換を密に行うことによって、それぞれの活動をさらに加速していけるような場にしたいです。
――つまり、ロケーションベースVR協会はまだ設立されたばかりで、これからいろいろな課題を解決していって、VR業界の拡大に貢献していきたいということなのですね?
三好 そうです。今回は“13歳問題”に関するリリースとなりましたが、それ以外にも、オペレーション負担軽減の試みもありますし、安全性の共有や運営上の注意事項の策定なども、ワーキンググループを設置のうえ議論したりと、各種の課題解決に向けたさまざまな試みを行っています。実際のところ、グローバルマーケットにおける日本のVR業界の立ち位置は、現在、世界のリーディングポジションにありますので、さらに国際競争力を付けていくためにも、まずはロケーションベースVRに関する各種課題を解決し、その発展を後押しできればと思っています。加えて、最近、ロケーションベースVR協会の会合に参加された学者の方より、「VRを使うことで、子どものために有益な授業ができるはずなのに、現状だと依拠すべき基準が分からない」と、教育効果の観点からの問題提起をされるケースも出てきています。そういった意味では、当協会の活動が、エンターテインメントからエデュケーションに至るまで、VRの裾野が様々な分野まで広がっていくための一助になればと考えています。
――条件付きとはいえ、子供が使用する際の明確な基準ができることによって、教育用途での可能性がたしかに広がりそうですね。
安藤 はい。将来的に見て、VRが各分野に浸透していくことは間違いないでしょう。まず、コンシューマーの領域では、キラーコンテンツがリリースされたり、デバイスの低価格化が進むことによって、我々の生活の中にVRが徐々に入り始めています。それと並んでロケーションベースというのは、ハイエンドな没入体験ができる場として、存在感をずっと保ち続けるであろうと期待しています。ロケーションベースで実現できることは、家庭向けでできるものの10年後や20年後を先取りした先端的なものになります。これは、さまざまな事例があり過ぎて逆に紹介しきれないのですが、たとえば、メタバース(インターネット上の仮想現実)の世界。いわゆる『セカンドライフ』的な世界というのは、現状でも家庭用でもいくつかのツールを使うことで擬似的に体験はできますが、残念ながらその没入感は、“自分がそこにいる”ようなレベルにはなっておりません。しかし、ロケーションベースであれば、これを実現することも可能です。つまり、エンターテインメントに限らず、エデュケーションやコミュニケーションやソーシャルな交わりというものは、ロケーション発で盛り上がってくる可能性があると考えています。
――ハイエンドだからこそ、VRの可能性はロケーションベースでさらに広がるということでしょうか?
安藤 そうですね。そもそも論で立ち返ると、「VRって何だろう?」というと、次世代のテレビ、没入体験ができるテレビだと考えると分かりやすいかと思います。
――おお、なるほど。
安藤 つまり、テレビというのは何を映してもよいのです。娯楽を映してもいいですし、スリルがあるものを映してもいいですし、学ぶものを映してもいい。大切なのは、もっとも没入できるハイエンドな体験をいちばん最初に届けられるのが、ロケーションの場だということです。そういったロケーションベースVRの可能性を、私たちは今後も模索して行きたいと考えています。
■撮影/小森大輔