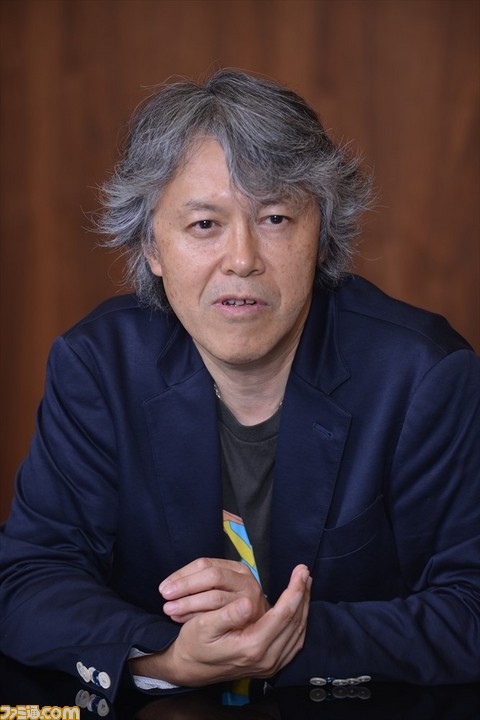先日、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)主催による、新たなる人材育成の取り組みとして、2018年より日本ゲーム大賞に“U18部門”が新設されることが発表された。“U18部門”とは、その名の通り18歳以下の応募者が開発したゲーム作品を審査し、優秀作を表彰するもので、「次世代のクリエイターを増やし、コンピュータエンターテインメント産業の振興と発展に寄与することを目的」としたもの。2017年11月12日には、そのキックオフシンポジウムとも言うべき、“集え! 創れ! 未来のゲームクリエイター ~日本ゲーム大賞 U18部門~”が開催され、エントリー受付が11月13日より開始された(作品受付は2018年3月1日~4月30日)。“U18部門”の設立にかける思いとは何なのか? ここでは、同部門設立を主導した、CESA技術委員会の松原健二氏と斎藤直宏氏にお話を聞いた。
右
松原健二氏(文中は松原)
セガゲームス 代表取締役社長 COO
左
斎藤直宏氏(文中は斎藤)
バンダイナムコスタジオ
10年、20年をかけての取り組みに
――そもそも、U18部門はどのような経緯で生まれたのですか?
松原 CESAにとってもゲーム業界における人材育成への取り組みは急務となっておりまして、昨年1月に人材育成部会をスタートさせました。ご存じの通り、日本ゲーム大賞には アマチュア部門があるわけですが、さらなる取り組みをどうするか……ということで議論を重ねた上に出てきた意見が、「小学生のころはゲームクリエイターってプロ野球選手やプロサッカー選手と同じくらい憧れの職業だったのが、中高大学生になるとだんだんそうでもなくなる」というものでした。たしかにその通りで、たとえば学生さんの就職人気企業とかを見ても、上位に来るのは金融関係や航空会社ばかりだったりします。
――現実的に見ても、なかなか就職を希望する対象にならないということですね。
松原 ゲーム業界を盛り上げていくためには、「ゲームを作りたい!」という思いでたくさんの人が入ってきてくれることが何よりも大切になります。そのためにどうすればいいのかということを考えたときに、若い世代にゲーム開発の楽しさを体験してもらって、職業を決める際の選択肢のひとつにしてもらえるようなステップを提供するのが大切だという判断に至ったんです。小中高生にゲーム開発のおもしろさを体験してもらって、「これは自分に向いているな、職業の選択肢のひとつに……」という道筋を作りたいと考えています。
――たしかに、野球にしてもサッカーにしても、子どものときに実際に体験して、自分で合う合わないを選択するということはあるかもしれませんね。
松原 そうなんです。これはあくまで感触なのですが、ゲームを作ったことがないために、職業として選択肢に入らないというのは、私たちのあいだでもよく議論されているところです。遊ぶ楽しさはわかっているけど、作る楽しさを学ぶ場があまりないという。野球だったら小、中、高校生とプレイして適正を見極めればいいわけですが、ゲーム開発にはそれがない。もちろん、クラブ活動などでゲームを作る機会がある方もいるかとは思うのですが。
――ゲーム開発者になるための道筋がないということですね。
松原 さらに言えば、みずから制作したゲームを発表して、ほかの人々と競い合う全国規模の大会のようなものもない。そうなると、「ゲームを作りたい」と思っていても、なかなかモチベーションが上がらなくなっていくわけです。それで、発表の場としてのU18部門を設立することにしました。
――U18部門のプロジェクト自体は、どのような感じで進められていったのですか?
斎藤 メンバーでいろいろな議論を重ねていったのですが、紆余曲折はありました。学生さんがどれくらい応募してくれるのか……という不安もありましたが、ほかのプログラムコンテストなどの実態も調べつつ可能性が見えてきたので、東京ゲームショウ2017で発表させていただきました。
――日本ゲーム大賞 アマチュア部門との兼ね合いが気になるところです。
斎藤 それも議題になりました。アマチュア部門の中のひとつの賞として、U18部門を作るほうがいいんじゃないかという議論もしました。やはり18歳以下という年齢制限を設けることによって、若い人たちにゲーム業界を目指すための経験を積んでいただくステップアップになると考え、独立させることにしました。
松原 もちろん、年齢制限はなくてもよかったのですが、“U18”と銘打つからこそ、そこを目指すという機運も盛り上がりますよね。とにかく、U18の世代に機会を作ってみたいと思ったんです。予選大会を実施するのも、U18部門ならではの取り組みと言えるでしょうね。
斎藤 アマチュア部門は応募していただいた作品を選考して賞を決めていくというプロセスなのですが、U18部門では、自分たちがどういうことを考えてゲームを作ったか、それをきちんとプレゼンテーションする場を設けることによって、ゲームそのものだけではなくて、制作途中の考えかたなどをアピールしていただきます。具体的には、まずは作品を応募して、審査を通過した作品は予選大会でプレゼンテーションをしてもらいます。そこで残った作品が、決勝大会に向けて自身の作品を改善していくことになります。肝心なのは、審査員であるプロのクリエイターからアドバイスをもらえるということです。もらったアドバイスを自分たちのゲームにうまいこと盛り込んでいって、決勝大会ではまた新しい勝負ができます。
松原 選考過程のプロセスが、アマチュア部門とは大きく異なる点です。おそらくU18世代にとっては、自分たちの考えたことを人前で発表するのも、初めての機会になる方が多くなるかと思います。私たちが考えているのは、“ゲームを作る力”はもちろんのこと、“どうやって表現するか”ということをアピールする力も身につけていただきたいということです。
斎藤 予選大会と決勝大会をわけ、プレゼンテーションの場を設定し、なおかつブラッシュアップの期間を設けるというのは、“U18部門”でこだわったポイントです。
松原 プロからもらったフィードバッグをどうやって取り入れてくるのかというのが、この賞の付加価値になりますね。
――そうすると、いまからあまり細かいことをうかがってもなんですが、両方の作品のクオリティーが甲乙つけがたかった場合、プレゼンテーションがうまかったほうを選ぶという判断があったりする場合もあり得ると?
松原 プレゼンテーションも重要な要素だと思っています。まだ正確な点数配分などは検討している段階ではありますけれども。
斎藤 プロの人たちもそうなのですが、実際にゲームを作るときはどういう想いでゲームを作るか、それをきちんと説明できないとなかなか世に出せません。プロの開発工程でも、開発の途中のステップで、いろいろなフィードバックをもらい、ブラッシュアップをします。U18部門の選考プロセスは、プロがゲームを開発するステップをそのままオープンにしていると見てもらえるといいかなと思います。
――ある意味で、CESAが思い描くクリエイターのしかるべき姿というのは、クリエティブな面を持ちながらも、ちゃんと自分でプレゼンテーションできる能力を身につけてほしいということなのですね?
松原 ある意味ではそうですね。ゲーム開発者には真面目でおとなしいといったイメージもあるかもしれませんが、プロとして仕事をしていく上では、「自分で考えていることをどのように表現して、他者とのコミュニケーションを取っていくか」というのが必須になります。これは、どの仕事でも当たり前に必要なことです。ましてや、おもしろさというのは、記号化するのがなかなかに難しい……。そういうところでコミュニケーションしないといけないとなると、表現力というのは、じつはすごく大事な要素です。何がおもしろいかというのはひとりよがりではなくて、「これはこうだからおもしろい」という説明をロジカルにしていかないといけない。おもしろいゲームを作るということを、どうやって人に伝えるのかということを考えたときに、プレゼンテーションするというのは大事な要素だということを伝えたいとは思っています。
――あと、募集年齢が小学生から高校生まで幅が広いというのにもちょっと驚きました。小学生と高校生を同列に並べて、「果たして評価し得るのだろうか?」というのはちょっと思ったりします。
松原 実際にはそうですよね。正直なところ、小学生と高校生を比べたときに、一般的に言えば知識や能力においても、高校生のほうが上であることは間違いありません。ただ、小学生の中にもプログラムに興味のある子はたくさんいます。そういう人たちに機会を提供してあげたいと思ったんです。あとは、2020年から小学生へのプログラミング教育が必須になるのですが、そのことも念頭にありました。プログラミングを学んだら、何かで応用したくなるのはごくごく当たり前のことですが、ビデオゲームはその応用先としては、適しているのではないかと。2020年から始まるプログラミング教育のアウトプットのひとつになれば……というのも、U18部門の対象年齢を小学生まで広げた理由のひとつとなります。
――なるほど。プログラミング教育が始まると、ゲーム開発に対する認識も変わってくるかもしれませんね。
松原 そうですよね。また、応募は1回きりという規定はないので、毎年応募していただいてもいいんじゃないかなと思っています。
――毎年どんどん成長していくさまが見えるのも楽しみですね。
松原 楽しみですよね。CESAの理事会でU18部門の会議をしているときに、たとえば、「ファミ通さんに取材してもらって記事に出てくるようになるには、何年くらいかかるのだろう?」という話になったんですよね。
――(笑)。
松原 ディレクターだとすると、30歳代にはなる。もうちょっと上になるかもしれません。そうすると、U18部門は10年くらい続けて、ようやく成果が見えてくるという足の長い話になるんです。
――それぐらい、U18部門には、10年、20年先をしっかりと見据えて取り組んでいこうということですね?
斎藤 人材育成というのは時間がかかりますからね。
ゲームを作るのは楽しいということに気づく機会を提供していきたい
――ちなみに、少し気になったのですが、受賞した方々に対するサポートなどはあるのですか? ゲームメーカーへの就職を希望する方に対する門戸を開くとか?
松原 さすがにそういったお約束はしていません。ただ、詳細はこれからの調整になるかと思いますが、受賞もしくは応募された方たちによるコミュニティが維持されるようサポートしていくことを考えたいと思っています。U18部門に挑戦して、18歳以上になったら、いよいよ日本ゲーム大賞 アマチュア部門に応募してもらって、U18部門に参加した仲間たちと切磋琢磨してもらいつつ、ゲーム開発者を目指してもらう……といった流れができればいいと思っています。
斎藤 中学生、高校生でゲームを作っている方って、けっこうまわりに同じ志をもった人が少ないというか、仲間がいない場合も多いようです。そういう子たちが、自分の地域を越えたところでネットワークができて、たとえばその年のU18部門で活躍した人たちが、翌年も会えるといったコミュニティができればいいなと期待しています。どう、コミュニティを構築していくのかは、これからの課題なのですが。
松原 いまの世の中だと、一端知り合いになれば、けっこうコミュニティってつながる傾向がありますので、それを後押しすることができればいいかなと思っています。その年度に応募した人たちがLINEグループを作るだけでも、コミュニティは広がっていくでしょうし。私たちがどうやってそれをサポートするかということをこれから考えていきたいです。
――最後に、U18部門への応募を考えている若者たちにメッセージをお願いします。
斎藤 とにかくモノ作りは楽しいです。モノを作って完成して、それを世に出す。そしていろいろなフィードバックがもらえる……。それを経験してほしいと思います。最近は受け身でいることが多いと思うので、自分で作って主体的に楽しむことを経験してほしい。それがゲームだったら、さらにとてもうれしいことなので、そういう子どもたちがたくさん増えて、未来のゲーム業界を後押ししてくれたら……と期待しています。
――子どもたちにとって、自分が作ったものに対して意見をもらうのは、これが初めての機会になるかもしれないですよね。
斎藤 そうですね。
――そこできびしいことを言われてショック受けたりすることもあるでしょうが、いろいろな気付きもあるでしょうし、とても有意義なことでしょうね。
斎藤 はい。競争なので、悔しいことはたくさんあると思います。やりたいことができなかったということもあるでしょうし、同じアイデアで競争相手のほうがもっとよくできているということもあるかもしれません。そういうことも含めて、もっとたくさん経験してほしいですね。
松原 ゲームは遊ぶと楽しいですが、作るのはもっと楽しいんだと気付く機会を作っていきたいです。それともうひとつ。このイベントは、周囲の人と“共感する”ことを味わってほしいです。いっしょに作品を提出して、いっしょに発表して、いっしょに表彰してもらう。感覚を共有するということが、自分のモチベーションになっていくのではないかと。自分が何かしらのアクションを起こして、形にして、それを人に見てもらってフィードバックをもらったときの喜びというのは、たぶん経験していない人からすると、舞い上がってしまうくらいの喜びだと思うんですよね。これは私自身の経験に照らしあわせてもそうなのですが、やはり若いときに何がいちばん自分の才能を伸ばしてくれるかというと、褒められるというのがものすごく重要な経験なんです。そして、たとえ「つぎはがんばろうよ」と言われたとしても、悔しいことがつぎへの糧になる。これはたとえ結果として将来ゲームクリエイターにならなくても、すごくいい経験になると思います。
――人生のいい糧になるような気はしますね。
松原 あと、U18部門では今後の取り組みとして、予選大会を全国複数の場所で開催することを検討します。地方在住の方がいきなり東京に来るのもたいへんかと思いますので。U18部門は、若い皆さんの将来を見据えて長いスパンで取り組んでいきますので、ご期待ください。