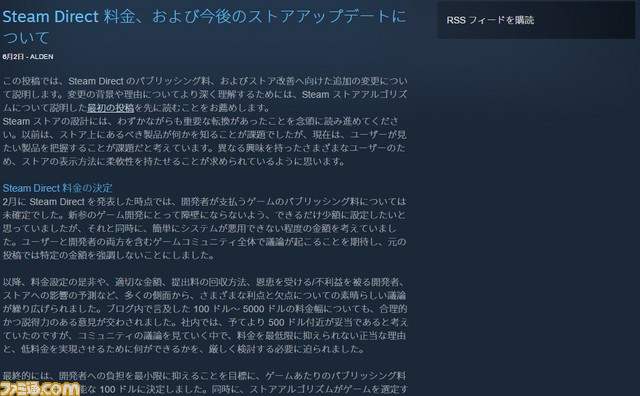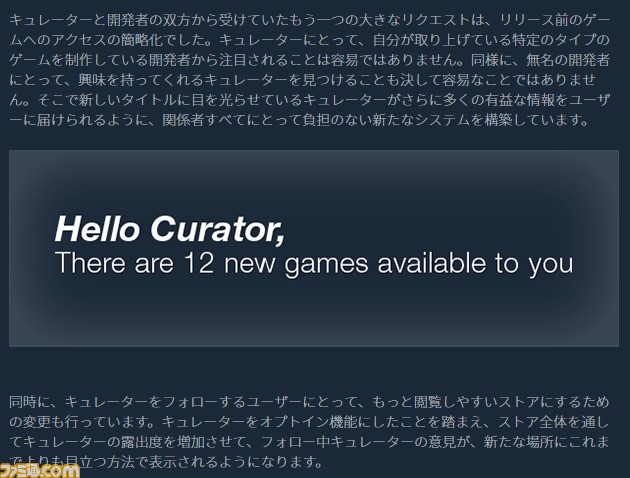より直接的なパブリッシングの解禁に向けて周辺機能も整備中
Valveが運営する、PCゲーム配信プラットフォーム“Steam”。その門戸をこれまでより多くの開発者に開く新たなパブリッシングプログラム“Steam Direct”の経費が、1タイトルごとに100ドルとなることが発表された。なおこの100ドルについては“配信後に回収可能”としており、一定のセールスをクリアーすれば返金されるものと見られている。
Steamでゲームを出すには、まず“Steamでの配信権を持つパブリッシャーと契約して出す”という方法、“Steamから配信権を得て開発者が直接パブリッシングする”といった方法が常道としてあるが、いずれも多少の伝手が必要だし、前者は古典的なデベロッパー―パブリッシャーモデルで、itch.ioなどで実現しているような直接パブリッシングではない。
これに対して対象を拡大する方法として導入されたのが、ユーザー投票を参考に配信権が与えられるSteam Greenlightだ。すでにGreenlightで配信権を得た多くのゲームがリリースされているが、Steam DirectはこのGreenlightに代わり、コミュニティによる承認フェーズもない、より直接的な配信方法を提供するものとなる。
しかし、本当に世界中からなんでもかんでもリリースできるようになってしまうと、ユーザーとゲームの適切な出会いは難しくなっていく。単に全体的な質の低下だけでなく、詐欺目的のゲームなんかもありえる。実際、Botで稼いだトレーディングカードを売りさばくのを目的に大して中身のないゲームを出すという手口もあったそうで、今回の発表に先んじてトレーディングカード入手の仕様が変更されている。
いずれにしても、すでに誰も追いきれないほど大量のゲームが出ているマーケットがこれ以上過密して窒息してしまうのも、開発者すら別にそれで遊んで欲しいわけではないゲームが並ぶのもSteamの本意ではないわけだ。そういった中で1ゲームあたり100ドルという経費は、もっとも直接的な障壁になりうる。Steam Directの発表時には“100ドルから5000ドル”という案を提示しフィードバックを受け付けており、Valve社内では500ドル程度が妥当という考えだったそうだが、結果的にその最低ラインを取るという形になった。
そして、Steamにおけるユーザーとゲームの出会いを向上させる各種施策も同時に実施される。ストアでオススメを表示するアルゴリズムの改善が施されるとともに、アルゴリズムが適切に動作しているかも可視化される予定で、キュレーター機能も強化される。
キュレーター機能は依然としてオプトイン型の機能(キュレーターをフォローした場合のみ、それがストア表示に影響する)に留まる一方、YouTubeなどの外部コンテンツを掲示できるようになったり、“今回のセールの注目タイトル”、“このゲームデザインの系譜”といった特定のテーマに沿った細かいリストが作成可能に。さらに発売前のゲームへのアクセスも容易になるという(具体的な内容は触れられていないが、スクリーンショットを見る限りでは、キュレーターに対して開発者が近日リリースのゲームをプレビューとして直接的に提供できるようだ)。
このように、Steam Directの解禁は、ストア表示のアルゴリズム、トレーディングカード機能の改善、キュレーター機能の強化など、さまざまな周辺機能の整備を経て行われる見込みだ。次回のアップデートでは、Greenlightの終了時期とSteam Directの投入時期について発表することが予告されている。