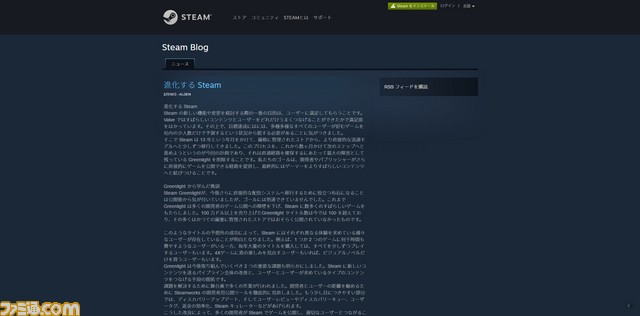より直接的でオープンな市場を目指す
Valveが公式ブログで、同社のPCゲーム配信プラットフォームSteamの新たな取り組みとして“Steam Direct”を発表した。
Steam Directは、Steamでの配信権を持たない開発者やスタジオが、所定の書類を提出し、タイトルごとに一定の金額(後述)を支払うことで、直接Steamでゲームを販売できるというシステム。2017年春からの稼働を予定している。
一方、これまではユーザーコミュニティでの投票によって配信権が与えられるSteam Greenlightが、配信権を持たない開発者がSteamで配信するための手段のひとつとして機能してきたが、こちらはDirectの投入にともなって廃止となる。
数の増大と質のバランスを取ろうとしてきたこれまでの歴史
これは、まさにSteamとともに発展してきたPC/インディーゲームブームによる、タイトルの爆発的な増加と密接に関係している。近年のSteamの取り組みは、その中で数と質のバランスをどう取るかに費やされてきたと言っても過言ではないだろう。
かつてのSteamでは、配信するにはValve側の承認プロセスを通る必要があり、実質的に質と数をコントロールする形となっていた。しかし、Steamでの配信を目指すタイトル数が増大していくと、それ自体はいいことなのだが、承認プロセスが追いつかない。かといって一気に全開放してしまうと、場合によっては全体的な質の低下を招き、アタリショックならぬ“Steamショック”となりかねない。
そこで導入されたのがSteam Greenlightで、これは配信に値するタイトルかどうかの判断をValveからゲーマーコミュニティに一部委ねることで、対象を増やそうというアイデア。実際に配信タイトル数もバリエーションも増え、該当記事では「100 万ドル以上を売り上げたGreenlight タイトル数は今では 100 を超えており、その多くはかつての厳重に管理されたストアではおそらく公開されていなかったものです」と述べられている。
しかしGreenlightは、Valveが最終的な目標とする「開発者やパブリッシャーがさらに直接的にゲームを公開できる経路を提供し、最終的にはゲーマーをよりすばらしいコンテンツへと結びつける」(同記事より)というレベルには至らず、さらに市場の成長はそれ以上のものだった。
以前も本誌で紹介したが、第三者機関のSteamspyによると、2016年1月から11月末にかけてのリリース本数だけでSteamオープン以来の約38%を占めるという。配信が決まったものだけでこの数字の増加なのであって、その外側の競争がさらに過熱しているのは想像に難くない。
よりオープンな市場であるitch.ioなどでまずリリースし、ファンなどを増やしてからパブリッシャーを見つけたり、クラウドファンディングを行ったりしつつ、Steamでのリリースを段階的に目指していくという手法がインディーゲームで増えてきているのも、こうした状況を反映していると思う。
そして数が増えれば、質のコントロールや、ゲーマー個人個人が適切なタイトルを見つけるのは徐々に難しくなっていく。この点についてValveは“ディスカバリーアップデート”をはじめ、キュレーターシステムの投入やレビューのテコ入れ、返金制度の整備など、あらゆる分野で対応を行ってきた。今回のSteam Directの発表は、(これで万全であるかはともかく)こうした前段階の準備を踏まえて、よりダイレクトでオープンな市場への変革を目指すものとなる。
38% of all Steam games were released in 2016 https://t.co/JiX2pt6JhB
— Steam Spy (@Steam_Spy)
2016-12-01 06:19:18
登録料はいったいいくらが適切なのか?
Steam Directの発表後、目下盛り上がっているのが、なんでもかんでも登録されないための障壁として機能する登録料の金額だ。Steam Greenlightでは最初に100ドル/1万円を支払えば、あとは複数タイトルにわたって有効だったが、Steam Directではタイトルごとに支払う必要があり、正式な額は検討中であるものの、現在出ている案では下は100ドルから上は5000ドルまで幅があるという。
これがまだたまたまSteamでの配信権を持っていないだけの中堅スタジオであったりすれば大きな問題にはならないかもしれないが、学生であることも多いインディーゲーム開発者にとってみれば、仮に1000ドルを超えるようなことがあれば、かなりの負担となるうえ、自作の質やアイデアの鋭さで切り抜けようにもGreenlightはもうなく、正規の承認ルートを目指すにも伝手がない、ということが起こりうる(このあたり、活発な議論からフィードバックを得るために、あえて話題を呼びそうな5000ドルという数字を出している気がしないでもない)。
ちなみに登録料は「後で取り戻すことができる」(英語原文ではrecoupable)とされているが、それが単に“まともに売れれば回収できる程度の金額を目指している”という話なのか、あるいは一定条件で返金があるようなことなのかは不明で、今後の正式発表を待ちたい。個人的には300ドル/3万円程度かそれ以下で、一定の金額または本数のセールス達成で返金される一時金としてならアリなんじゃないかと思うのだが。