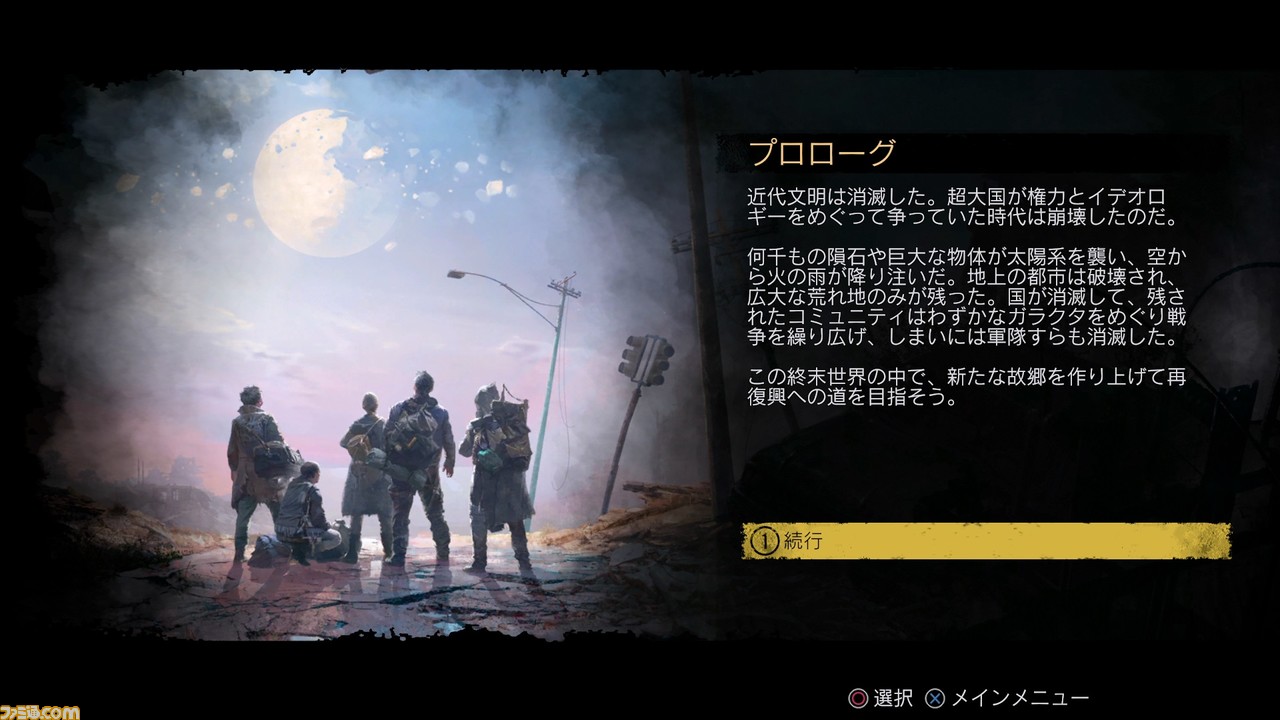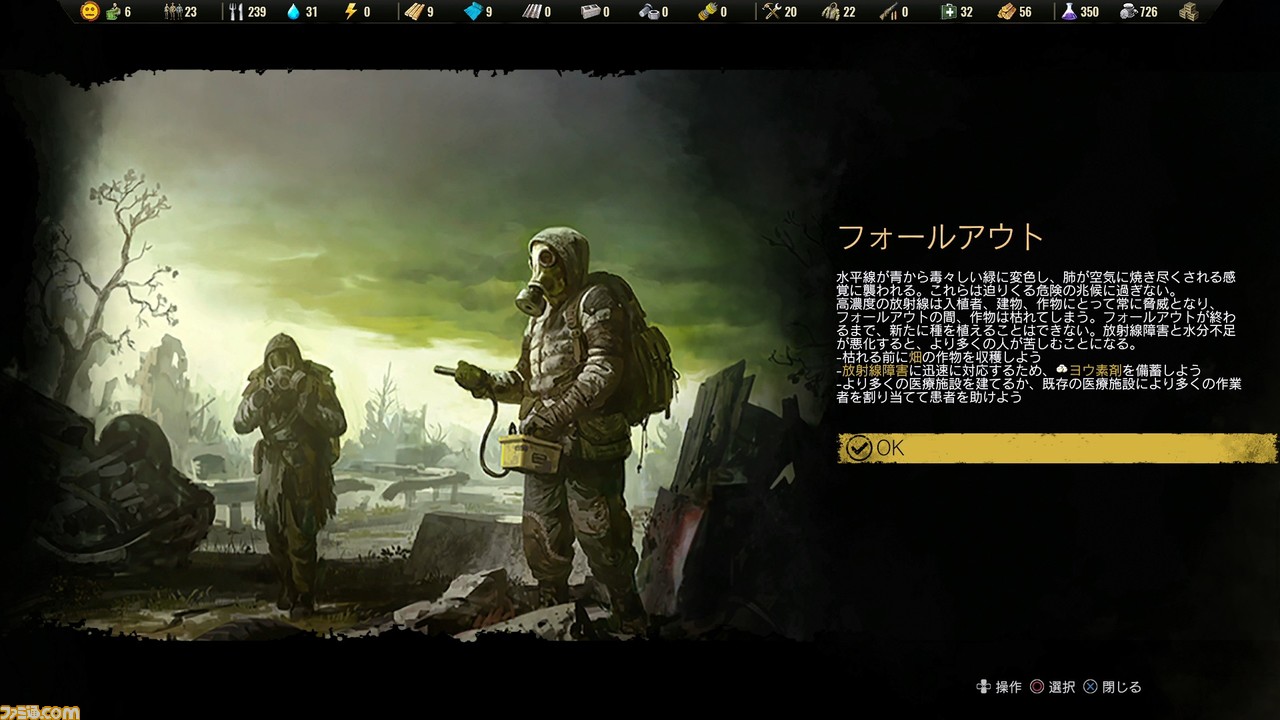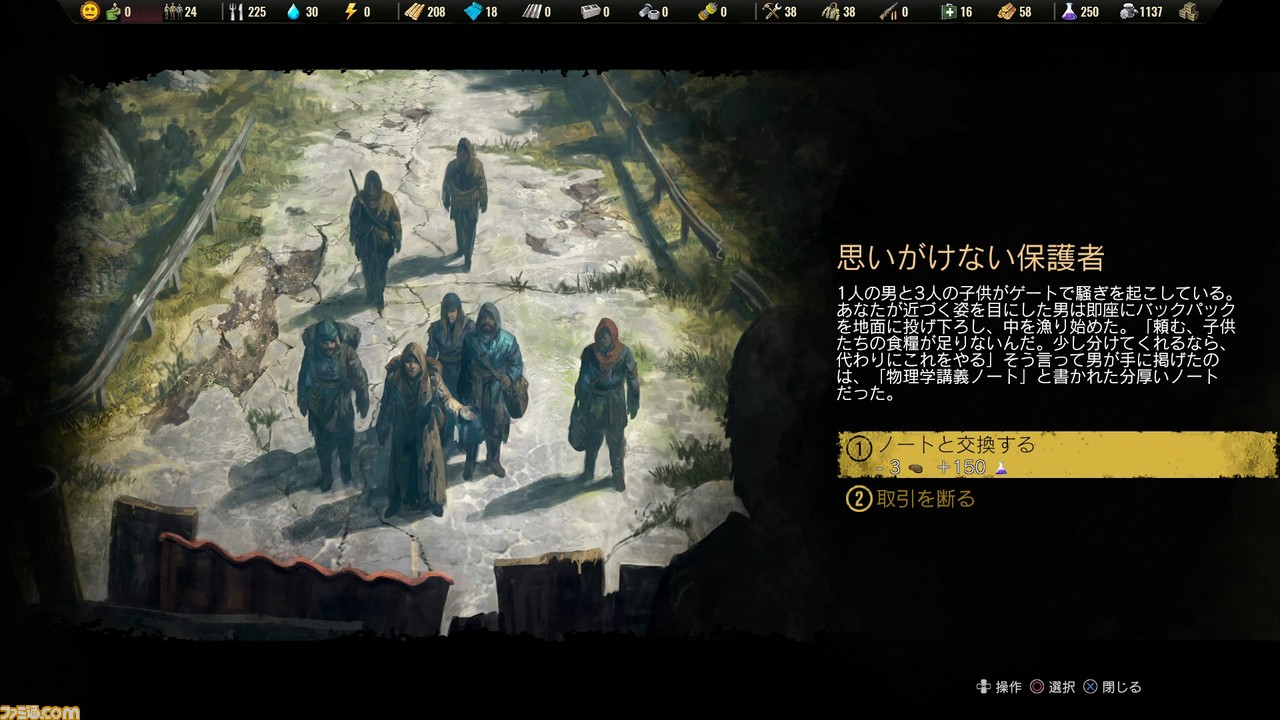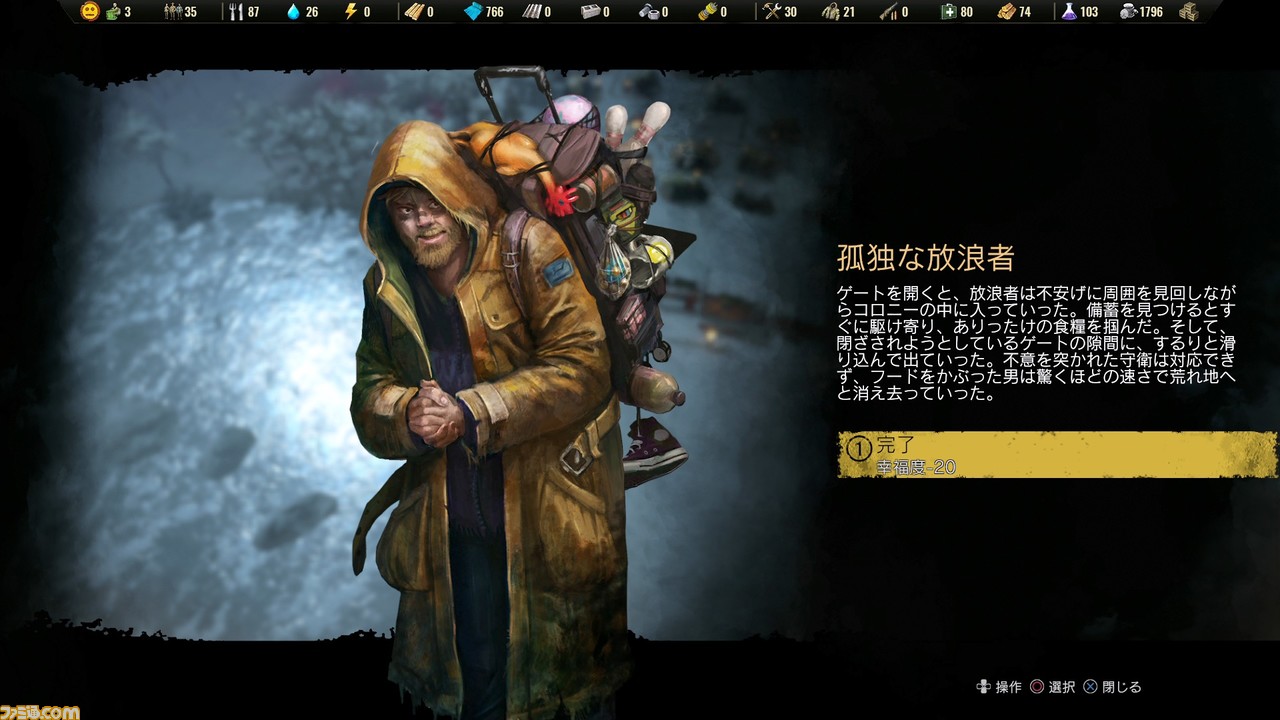セガから2022年7月28日(木)発売予定の、プレイステーション4、Nintendo Switch用ソフト『サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-』。
タイトルの通り、惑星規模の滅びを迎えた後の世界で生き残りを目指すサバイバルシミュレーションゲームだ。
ちなみに、筆者はシミュレーションゲームがけっこう好きだ。たいていのシミュレーションゲームでは、守りだけではなく、こちらから攻めていく必要も出てくるため、思考やリソースをふたつに割かないといけないのが難しいところである。
だが、サバイバルとなればひたすら生き延びればいいわけで、ということは守り一辺倒でオーケーなのでは。これはもう楽勝だろうと、プレイする前からIQ53万の脳で攻略を組み立て始めたのだが……。
災害とかいう相手が強すぎる。人間が立ち向かっていいレベルではない(※)。
※編注:それ、たいていの人が理解していると思います
長すぎる冬、放射能の嵐、そして本当に予兆なしで突然降って来る隕石。ただでさえカツカツなサバイバル生活を、スナック感覚で引っ掻き回してくる。安心できたと思ったのに直後にひっくり返される、パニック映画のような展開の連続だ。
今回はそんな災害にもみくちゃにされながらもなんとか生存戦略を追い求めた筆者の、先行プレイリポートをお届けする。順調な我々にドリフトで切り込んできたと思ったら富士急ハイランドのええじゃないか並みに感情をぐるぐるにする不幸不幸不幸の連続。希望の光りが見えたつぎの瞬間には悪党がのさばり何だこれどういうことだ。
のめり込むほどに激しくなる動機。うむ、これはいいトラブルだ。生き延びた先に待つドラマチックな展開や、序盤に向けてのワンポイントアドバイスも紹介していくので、ぜひご一読あれ。
操作とシステムは簡単。だが容赦はない
本作を始めると最初に触れることになり、以降もすべての基本となるのが、生存者たちのコロニーを作り上げていくシミュレーションパートだ。
時間経過によって生産や狩猟などが進行していくため、リアルタイムストラテジーの感覚に近いかもしれない。プレイヤーはさまざまな施設をコロニー内に建設し、そこに生存者たちを作業員として割り当てて、木や食料といった生活の糧を集めさせていくわけだ。
施設の配置自体はとてもシンプル。特定の建物を隣り合わせるとシナジーが起きるなどといった難しい要素はほとんどない。唯一気を付けるべきは、焼却炉などの暖房施設に有効効果範囲があることくらいだ。
材木や木の実、野生動物の肉などを集める収集施設については、設置後にその収集指定範囲を好きなように移動できるので、配置はわりと適当でも問題ない。
施設を配置すると、手が空いているコロニー内の生存者がそこに担当者として配属され、以降は自動で作業を進めてくれる。担当者の数は手動で増減することもでき、作業効率を変えられる。
このように、テントなどの居住施設と働く場所を用意しておけば、ほぼ全自動で生存者たちが生活のかたわらで食糧や燃料を集め、余裕分を備蓄してくれるわけだ。住民の満足度を示す“全体幸福度”や“福祉”、“快適さ”といったパラメーターも存在するが、住居を与えないなどといった特別なことをしない限りは、低くなることはあまりない。みんな、精神的にタフだな。
加えてチュートリアルをONにしておけば、つぎに建てるべき施設などを逐一教えてもらえる。滅亡惑星と銘打っているわりには、だいぶやさしい世界だなぁ……などと、ここまでの筆者は思っていた。
そこに突然やってきた、災害を迎えるまでは。
放射能の影響でばったばったと倒れていく生存者。それもそのはず、筆者はここまでの展開がわりとやさしかったため、病人やケガ人を治す“医療テント”をひとつしか建てていなかったのだ。当然ながら、薬となる“ヨウ素剤”の備蓄もない。
先述のとおり、各施設は生存者が労働力となって成り立っている。つまり生存者が倒れるということは、建設の手や生産の手が止まるということだ。そもそも畑や水をくみ上げる施設なども、災害中は停止してしまうので、資源は減る一方になる。
急いで医療テントを増設しようにも、建設できる人手どころか、その材料となる木やプラスチックゴミを集められる人手もない。結果、何人もの死者を出すことになってしまった。ああ……。
さらに、コロニーに死者を弔う“埋葬所”がないと死体は野ざらしにされ、そこから感染病が発生する。
当然のごとくこの世界を舐めていた筆者は埋葬所を建設しておらず、残された放射能汚染の被害者と感染症患者を限られた医療テントでは捌き切れず、結果的にたいへんな被害を被ることになった。おいおいおい地獄の具象化か?
それでも、まだ我がコロニーは滅んだわけではない。災害と同じく、ランダムで発生するコロニーへの来訪者のイベントによって、入植希望者が増えたり資源が手に入ったりと、プラスの出来事も起きるのだ。
ただし、来訪者は全員が善人ではない。こちらもプレイヤーの選択次第になるが、人災によって甚大な被害が出ることもある。
それでも順調に生存者の数が増え、居住テントも無駄にはならなくなったころ。またしても唐突な災害が訪れる。
いや、隕石って。それはもう、どう予測してどう防げばいいのか。
幸いにも落ちたのが居住区の一部だったので、インフラ関連に被害は出なかった。ランダムなタイミングで隕石が降ってくるとか、この世界は思った以上にとんでもない。
そうしてハプニングに対応しつつもコロニーの生活が安定してきたころに、またしても大きな災害らしきものがやってきた。
ちょっと寒くなる程度だから、フォールアウトほどではないだろう。そんな風に筆者は考え、焼却炉を増やして暖房の準備をする程度しかしなかった。
だが、実際に“冬嵐”が到来すると……。
ははぁ~ん。フォールアウトと同じく生産関連がほとんどストップするわけだね。だがまぁ、暖房のおかげで低体温症患者はあまり出ていないし、これだけ備蓄があればフォールアウト同様にしのげるはず……。
冬が長い。フォールアウトの比ではなく、生産停止期間が長すぎる。
これだけ長いと知っていれば、事前にもっと食料を溜め込んでおいたのだが、あいにく筆者が溜め込んでいたのは焼却炉用の薪くらいのものだった。
備蓄や準備はこれで十分だろうと思う筆者の予想を、災害はつねに上回ってくる。災害を前にした人間の無力感、そしてそれを何とか乗り越えたときの安堵感を、今回のプレイではこれでもかというほど味わえた。2回目以降の災害も初見ではないはずなのに、緊張感が薄れない。
スペシャリストといっしょに文明を取り戻せ
コロニーを何とか存続させてある程度発展させると、コロニーの外の世界“ワールドマップ”の探索が解放される。そこで活躍するのが、生存者の中でも特殊な能力を持つ“スペシャリスト”たちだ。
スペシャリストはふだんは生存者となんら変わらない人材だ。コロニー内で、建築や運搬、採集などの仕事を個別に任せることができる。
だが、ワールドマップの探索ができるのは彼らスペシャリストのみだ。ワールドマップにはさまざまな施設や資源の集積所、武装集団などの外敵が待ち受けており、“戦士”や“科学者”など、スペシャリストそれぞれが持つ能力によってそれらに対処できる。
スペシャリストたちは行動に費やせるポイントや敵からの攻撃、危険地帯での汚染などで減る体力が設定されており、移動や採集、戦闘などをポイントを消費して行なう。このポイントと体力は、コロニー内で時間が経過していくと自然回復する。
資源を集めるのは外世界でのスペシャリストの大事な役割だが、より重要となるのが“サイエンスポイント(SP)”の入手だ。
外世界の各地には文明の残骸が残されており、それらを探索するとSPが入手できる。このSPを消費することで、“テックツリー”にあるさまざまな新技術を入手できる。
畑や畜舎を作れるようになったり焼却炉や水道施設をバージョンアップできたりと、テックツリーの技術はどれも災害に対抗するために必須級のものばかりだ。これらをいかに早く入手できるかで、救える生存者の数は段違いになる。
さらにコロニーの発展と外世界の探索を進めていくと、メインストーリーが始動する。
この惑星を滅ぼした災害とは何だったのか、その再発にどう備えればいいのか。各地に残された施設をスペシャリストに調べさせていくことで、数多の謎を徐々に解明していくのだ。
これ以降はスペシャリストを派遣する探索でのメインストーリー進行と、そのあいだに生存者たちを守るためのコロニー運営という、ふたつのゲームモードを並行していくことになる。どちらもシステム面がわかりやすく、複雑に絡み合う要素はないので、それぞれ独立したゲームであるかのように遊びやすかった。
また、プレイしてみて気付いたことがある。災害に2回目以降に遭ったとき、初見ではなくなっているのに、緊張感が薄れることがなかったのだ。これは強く印象に残っている。
本作の基本システムはシンプルだと思う。単純明快だからこそ、食糧の数や生存者が倒れて減っていく様子が「ヤバい」という感覚にダイレクト接続。少し大げさかもしれないが、映画さながらの臨場感の源泉はここにあるのではないかと思う。
災害に翻弄されつつも、最後には災害に文字通り“立ち向かう”展開になるのがいかにもゲームや映画といった趣きで、プレイしていくと何としても生き延びたくなってくる。シミュレーションの煩わしい部分をほぼ省いているぶん、生き残ることに全力を尽くせるが、逆にいえば生き残れなかったらプレイヤーの力不足だったと明確にわかるシステムでもある。
攻略してやろうと息巻いていた筆者も、結果的には度重なる災害にだいぶ心を持っていかれた。我こそはと崩壊世界で生き延びる自信がある人には、この世界が滅びた真相について、ぜひその手で解き明かしてほしい。
プレイ序盤のワンポイントアドバイス
これまで触れてきたように、ちょっと序盤に手違いがあるだけでもコロニーが早期全滅を迎えかねない本作。システムは直感的だが、容赦のなさは従来の難しいシミュレーションゲームと同等かそれ以上だ。
そこで、最後は最序盤のコロニー運営におけるちょっとしたアドバイスをお届けする。人類再建のために役立ててほしい。
建物は密集しても問題なし
突如隕石が降ってきたりするこの世界だが、基本的には居住テントなどの施設は密集させておこう。密集した施設群に隕石が当たっても修理はすぐに完了するので、あまり問題がない。
それより重要なのは焼却炉の有効範囲。より少ない焼却炉と燃料の薪で冬を越すには、居住施設を密集させることがほぼ必須だ。
序盤はプラスチックゴミがほしいが……
ゲーム開始直後は、あらゆる施設を作るのに木材とプラスチックゴミが必要となる。ただし、最初の冬を迎える時期あたりになると、一時的に新たな施設はあまり作らなくなるため、“リサイクル施設”で集めるプラスチックゴミは余りがちだ。
資材の備蓄を確認し、プラスチックゴミが余り始めたようなら、それらを集めている人員を木材や食料の収集に割り当て直していこう。
これだけは先んじて作りたい施設
居住用のテントは人数分あれば十分として、序盤に最優先で作っておきたいのが医療テントだ。序盤における死者の発生は、医療テントがあればほぼ防げる。災害に備えて複数設置できればなおいい。
死亡事故が防げれば序盤には必要ないが、余裕が出たら郊外に埋葬所も作っておこう。感染症はかなり根強いので、放置された死体から感染者が出ることはなるべく避けたい。
建設しすぎると運搬の人手が足りなくなる
貯水設備や猟場など、災害に備えるためにはさまざまな施設を作りたくなるが、生存者の数には限りがある点には注意したい。各設備には担当者を割り振ることになるが、このとき担当が割り振られていない生存者が“運搬者”となり、建築中の施設への資源の運搬と、建築と修理を担当することになるからだ。
施設を増やして担当者を割り当てすぎて、運搬者がいなくなると、新たな施設の建築がストップしてしまう。設備を増やす際には、生存者の数と運搬者の数をしっかり確認しよう。
商品概要
- 商品名:サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星
- 対応機種:プレイステーション4、Nintendo Switch
- 発売日:2022年7月28日(木)発売予定
- 希望小売価格:パッケージ版・デジタル版:6578円[税込]
- ジャンル:サバイバルシミュレーション
- プレイ人数:1人
- 発売・販売:株式会社セガ
- CERO:C区分(15歳以上対象)