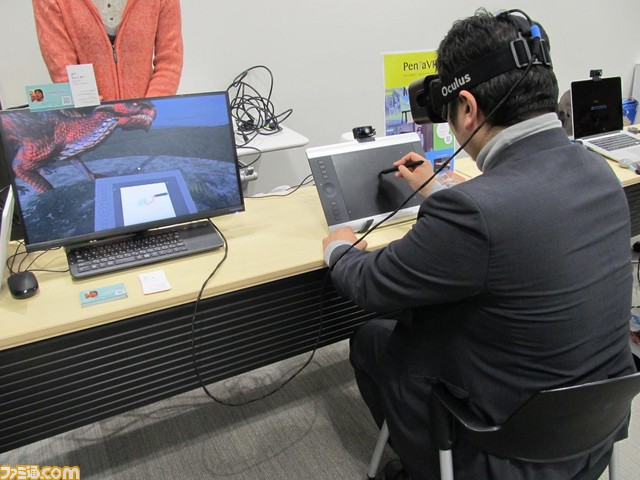VRは“2周目”を迎えている?
おなじみ黒川文雄氏による“黒川塾 (三十三) ”が、スクウェア・エニックス セミナールームにて2016年2月26日に開催された。
黒川塾とは、“すべてのエンターテインメントの原点を見つめ直し、来るべき未来へのエンターテインメントのあるべき姿をポジティブに考える”というテーマのもと、各界の著名人を招いてトークを行う会。今回のテーマは“バーチャルリアリティの未来へ3”となり、過去2回(21回、26回)に引き続き、バーチャルリアリティ(以下、VR)の未来と、その可能性をさら掘り下げる内容となった。以下より、そのトーク内容をお届けしよう。
※関連記事
・“黒川塾(二十一)”が開催 “本物”のブームがきているVR(バーチャルリアリティー)の未来をスペシャリストたちが熱く語る
・“黒川塾(二十六)”VRコンテンツを収益化するための方法とは? 藤山晃太郎氏や吉田修平氏による熱いトークをお届け
【登壇ゲスト】
吉田修平氏……ソニー・コンピュータエンタテインメント ワールドワイド・スタジオ プレジデント
藤井直敬氏……簡易型VRデバイスとして10万台以上を販売した『ハコスコ』の開発者
渡部晴人氏……個人でVR黎明期よりコンテンツを個人で開発し、現在は、gumi所属
ダリル・サーティン氏……AMD VRディレクター/VR諮問委員会チェアマン
※VRニュースサイト『ANORA』の編集長である広田稔氏は、インフルエンザのため欠席
VRコンテンツの市場をどう捉えるべきか
最初のトークテーマは“現在のVR事情がどのように変化しているか”。
藤井氏は、以前はVRが“世界初”ということで認知度を高めてきたが、いまは世界初ではなくなったという意味で“2周目”を迎えていると分析する。
昨今はVRを使ったイベントはあまり見られなくなり、もし開催してもニュースにならないほど、注目度が下降傾向にあるのだという。スポンサーもVRを利用したことによる効果を確認しにくくなっており、「試しにやってみるかな」ということはあっても、2度も3度も出資してくれていることはなくなってきているという現状があるそうだ。
VRにかける予算をどうするか、そもそもなぜVRにお金をかけるのか、という声は一般の方からも上がるようになっており、VRコンテンツのプロモーションは総じて辛い時期になっているのだという。そのため、効果とコストの兼ね合いを考慮してコンテンツを開発することが、これからは大切になってきているとのことだ。
渡部氏はVRの市場的なトレンドは下がってきている一方で、開発側の士気と、盛り上がりは存分にあると語った。
サーティン氏も渡部氏と同じく、ゲームを始めとしたコンテンツの開発者たちにとって、VRは熱狂的な盛り上がりを見せていると語る。自社(AMD)でも、ゲームだけでなく教育、メディカルなどすべてのVRコンテンツに目を向け、マーケット開拓に取り組んでいるそうだ。
ストリーミングや映画からでもVRのアプローチを
黒川氏からは、欧米ではアトラクションとしてVRを取り入る文化があることが告げられた。
吉田氏は日本に比べ、海外でのVR市場が盛り上がってきていることを指摘。企業サービスやスポーツ中継などでのストリーミングでVRを活用することが増えており、ベンチャー企業もより大きなコンテンツを狙いにきているのだそうだ。
サーティン氏によると、北米と欧米ではテーマパークのようなエンターテイメントにもVRでのアプローチをしており、多人数で楽しめるマルチプレイのVRの開発も盛んに行われているそうだ。
サーティン氏は、映画業界からは、360度映像を見渡せるだけでない、さらなるインタラクティブなコンテンツも盛り上がりをみせていると語った。
吉田氏によると、サンダンス映画祭にて、パノラマ映像やVRを使ったインディーズ映画が、数十作品も登場しているのだそうだ。ほかにもカンヌ、トロント、サウス・バイ・サウスウエストなどの映画祭でも、VRを取り組んだ映像作品が出品されてきているのだという。
サーティン氏は、VRのインタラクティブ性は没入感があるため、ビジネス的にはとても進めていきたいものであるが、技術的にはフルレンタリングするゲームと同じくらい難しいものであると語った。満足できるほどのインタラクティブ性を映画に加えられるのは、まだまだ先のことのようだ。
収益をあげるために“B to B to C”が必要か。
黒川氏は、スマートフォンに装着して簡易的にVRを楽しめるデバイス『ハコスコ』を開発した藤井氏に、“これから先に越えなければいけないことがあるか”を聞いた。
藤井氏は、スマートフォンを使ったVRコンテンツは“ただ1回見てみただけで終わっている”現状が少なからずあると指摘する。しかも、そのコンテンツから別のコンテンツに行くこともなく、ユーザーのアクションがそこで終わってしまうため、結果的に収益も上がりにくくなっているのだという。
そこで、藤井氏は、B to C(企業が個人ユーザーを相手とする事業)ではなく、B to B to C(ほかの企業のユーザー相手のビジネスをサポートするような事業)のビジネスモデルを遂行しないといけないと提案する。世界においても、こうしたビジネスモデルを考えている関係者は少ないのだという。