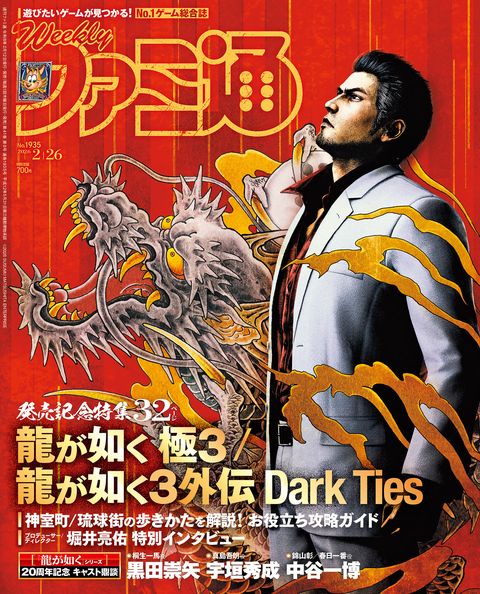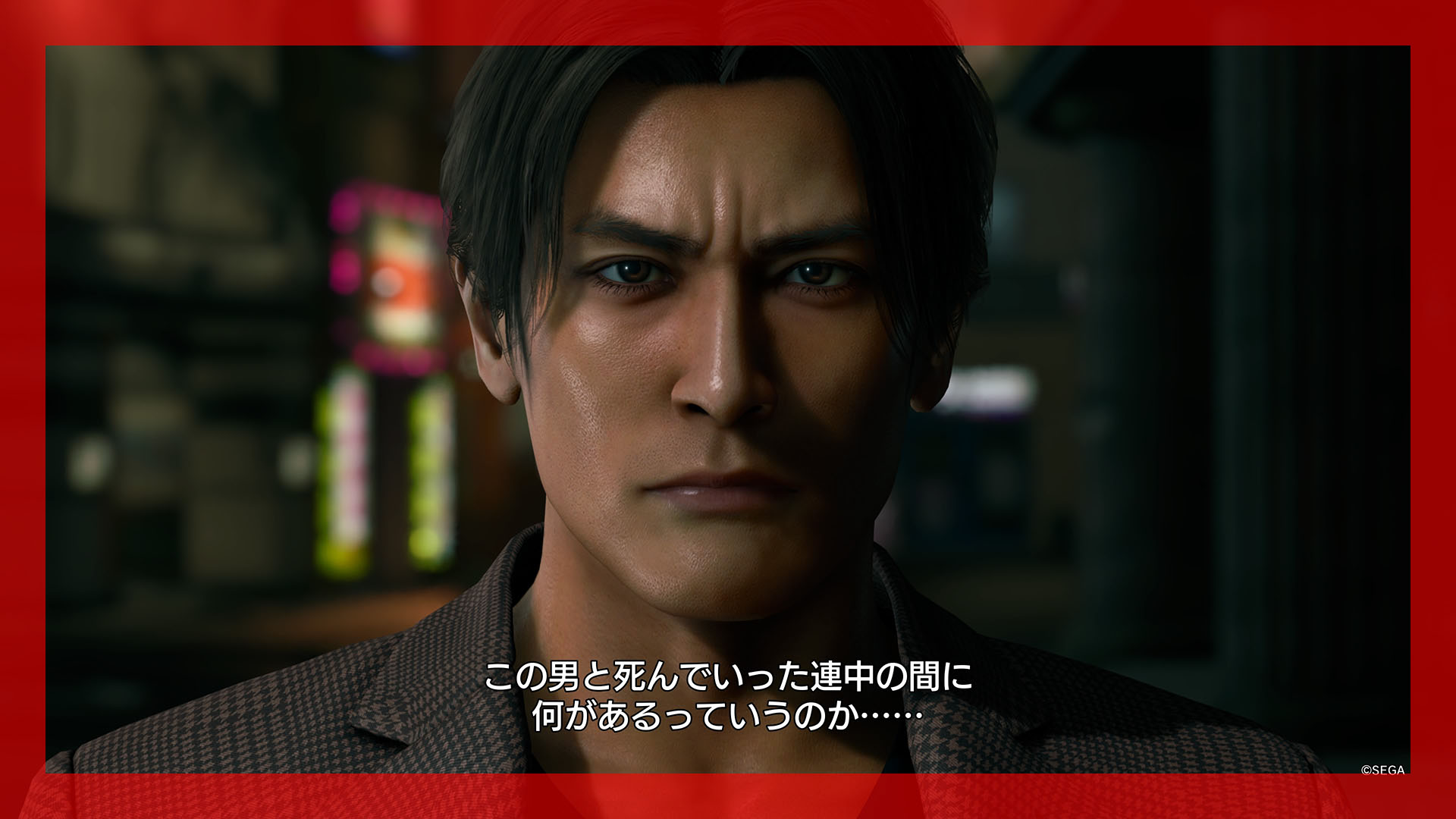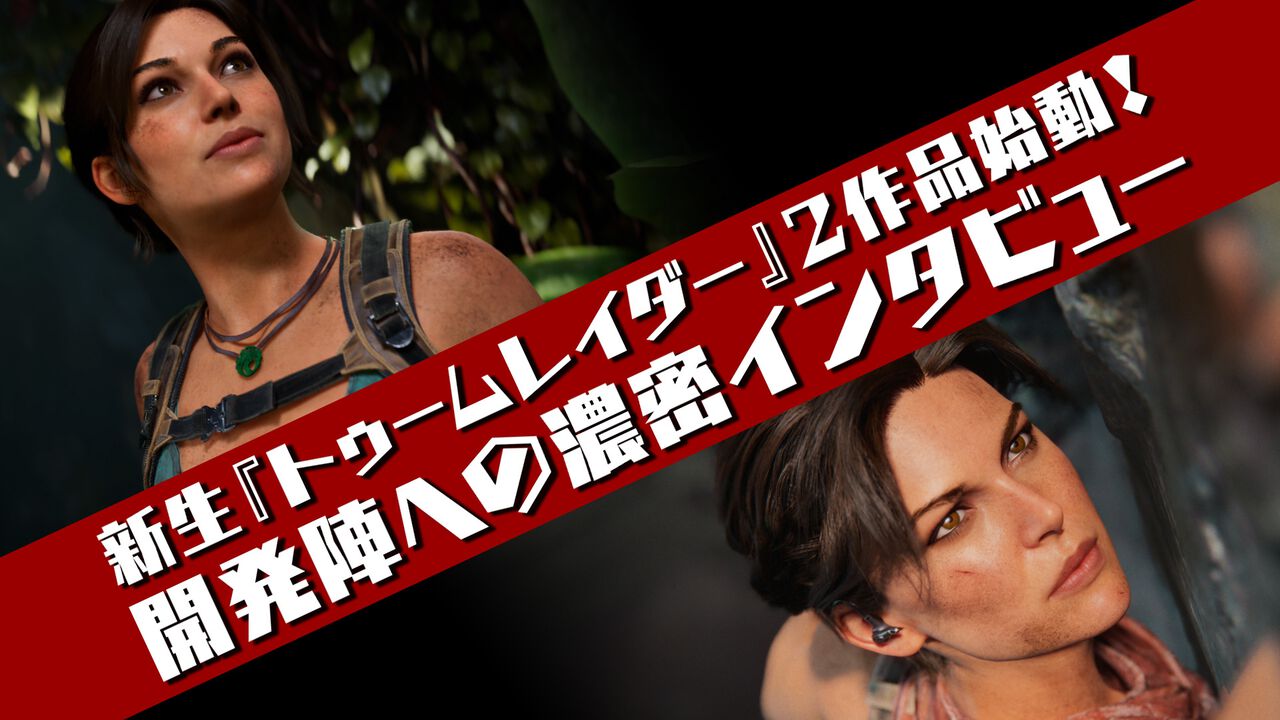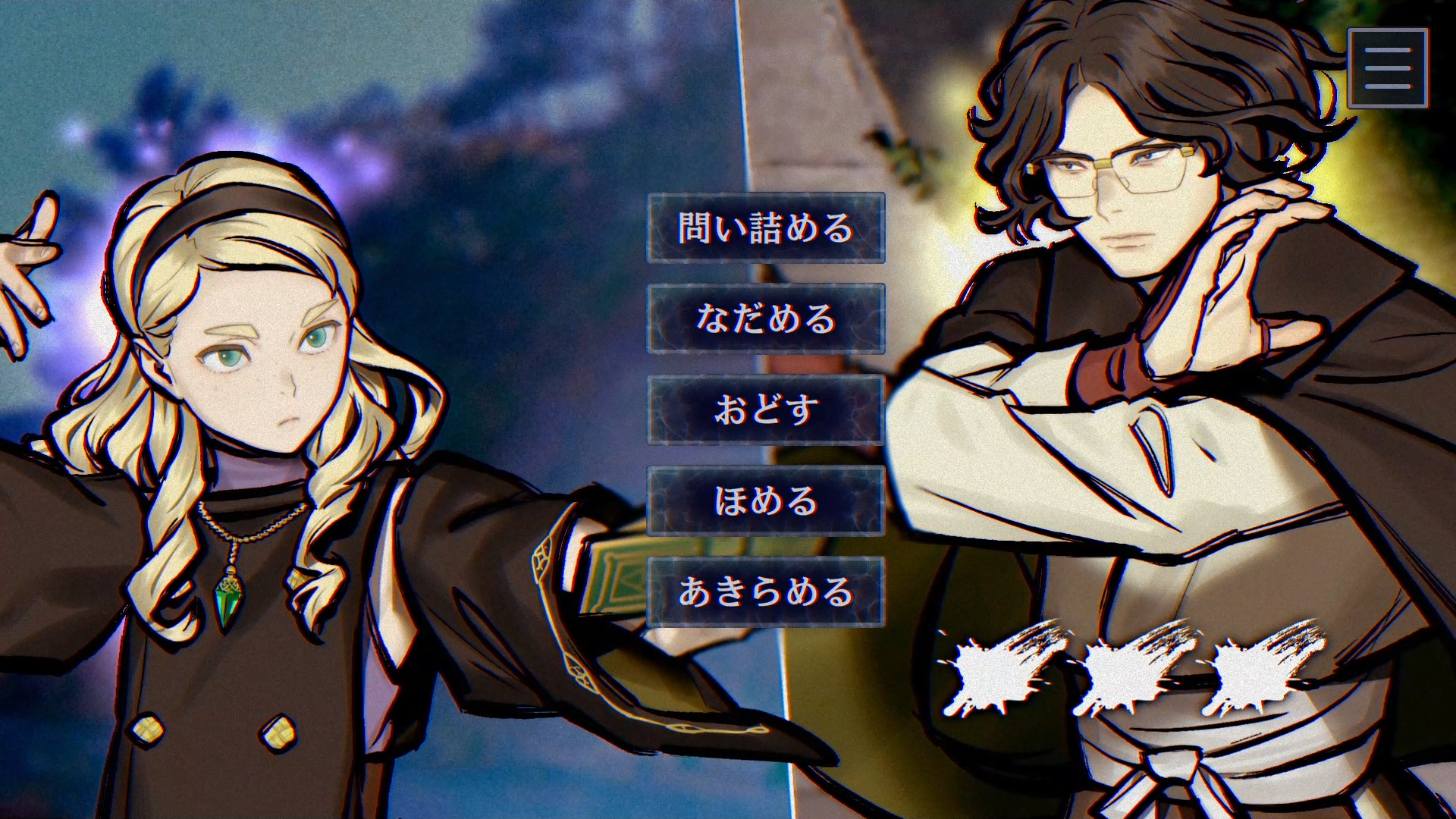2025年10月21日にマイクロソフト(Xbox Game Studios)より発売予定の『NINJA GAIDEN 4』。対応ハードはプレイステーション5(PS5)、Xbox Series X|S、PC(Steam)。Xbox Game Passにも対応する。
本作はコーエーテクモゲームスのアクションゲーム『NINJA GAIDEN』シリーズ最新作。前作から13年ぶりとなるナンバリングタイトルで、コーエーテクモゲームスのTeam NINJAと、アクションゲームで知られるプラチナゲームズの、共同開発タイトルとなっている。
発売に先駆けて、プラチナゲームズにて各国のメディアを招いた試遊会が開催。そのなかでメディア合同インタビューも実施された。本記事では、コーエーテクモゲームスとプラチナゲームズ両社のキーパーソンとなる、ふたりの開発陣へのインタビューをお届けしよう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a75937b721cd6740104353e9feac667fc.jpg?x=767)
平山正和 氏 (ひらやま まさかず )
ディレクター。コーエーテクモゲームス・Team NINJA所属。
中尾裕治 氏 (なかお ゆうじ )
プロデューサー兼ディレクター。プラチナゲームズ所属。
『NINJA GAIDEN』らしさを残しつつも、幅広い層に楽しんでもらえるような設計を目指した
――今回コーエーテクモゲームスのTeam NINJAと、プラチナゲームズの共同開発というところで、実際取り組んでみていかがでしたか? やりにくさなどもあったのでしょうか。
平山
お互いアクションゲームを制作している会社ですから、アクションに関する細かなこだわりかたや、考えかたの違いはありました。ただ、アクション性の高いゲームを作るうえで、より細かなやり取りができたと思います。何より、中尾さん自身が『NINJA GAIDEN』シリーズのファンでいてくれたことが大きかったです。
たとえば調整の話をひとつするにしても、Team NINJAが言語化できていないような、『NINJA GAIDEN』とはこうあるべきだ、リュウ・ハヤブサはこういうアクションができるからおもしろい、みたいなニュアンスを最初から持ってくださっていたので、他社さんではありながらも、うまく制作に取り組めたのかなと思います。もちろん、会社が違うとなると、文化のようなものが違う部分もあります。そこは真正面に向き合って、議論を重ねていきました。
中尾
ぶしつけながら、私もいちファンとしての目線があります。逆に私のほうから「いや、こうあるべきですよね?」みたいな提案をさせていただくこともありました(笑)。そこは正直に、意見を出していましたね。ただ『NINJA GAIDEN』を最高の作品として、皆さんに送り届けるという最終目標は、お互い同じです。作品をよりよくするための、いい意味でぶつかり合いができたと思っています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/ae63ea84ba5a2008dbcbea9bc279e05c8.jpg?x=767)
――開発初期にプラチナゲームズが制作したプロトタイプの印象と、そこから現在はどのように変化したのか教えてください。
平山
初期からプラチナゲームズらしいといいますか、ダイナミックなアクション、ケレン味のある部分は、開発初期段階からすでにありました。初期からTeam NINJAで制作しているだけではなかなか出てこないようなアイデアがけっこう入れ込まれていましたし、おもしろい融合ができるのではないか、という期待感がありました。そこから『NINJA GAIDEN』シリーズとしての手触りですとか、バトルの細かな部分などを我々が見ることで、いいところ取りじゃないですけれども、共同開発として作品を磨き上げられたと思っています。
“超忍”として自由自在にアクションがくり出せるゲームですから、その手触りや動作を中断(いわゆるキャンセル)できるタイミングなど、かなり細かくやり取りさせていただきました。過去作ではエッセンスと呼んでいた“血塊”ですとか、“滅却”や“絶技”などの既存のシステムも、新主人公のヤクモを中心とした新システムとして、どういう風に落とし込んでいくのかは、プロトタイプ版から磨きながら『NINJA GAIDEN』らしさを突き詰めていきました。
中尾
あと、初期から改善された点でいうと、ステージ周りの調整です。我々としては、ヤクモの扱う新システム“鵺の型”を軸に、どう活用して戦ってもらうのか考えていたのですが、アクションの制作に集中してしまうと、『NINJA GAIDE』らしさみたいな部分で、忘れてしまいがちな点がありました。たとえば敵が現れる頻度や、シチュエーションなどです。ちなみに、いい意味で「どんだけ来るんだ!?」と思うくらい敵がやってきます(笑)。
平山
『NINJA GAIDEN』シリーズは、もはや理不尽にすら感じる苛烈な状況でも、超忍ならではのスーパーアクションを駆使すればどうにか乗り切れるのも、重要なポイントです。ですので、敵の構成や難度などの部分で、ちょっと甘いのではと思う部分には、もう少しきびしくしましょう、敵を増やしましょう、みたいな部分も細かく意見していましたね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a0138e007a2e55f93112157ceacd714a2.jpg?x=767)
――既存の『NINJA GAIDEN』シリーズのアクションは、自由度は高いですがシステマチックな作りになっておらず、もちろん“絶技”を積極的に狙うなどの立ち回りはありますが、基本はプレイヤーに戦いかたを委ねるようなゲーム性でした。そこに、ジャスト裏風(回避)やジャストガードなどを織り交ぜて、従来の自由度の高い戦闘と、本作ならではのシステマチックな戦いかたができるようにしたのは、どう成立させていったのでしょうか。
中尾
作る順番として、まずTeam NINJAさんに制作したバージョンを見ていただくにあたり、私のほうで考えていたのは、『NINJA GAIDEN』のいい所・強みが現代化された手触りをお届けしたいと思っていました。システム的には、ある種同じものなのですが。
そのなかで、本作で追加されているジャスト裏風や弾き返しなどは、攻防の揺らぎ、攻守の切り換わりなどをより分かりやすくするために取り入れました。それを『NINJA GAIDEN』に入れ込むことで、アクションゲームとして磨き上げたかったんです。
そこはTeam NINJAさんもすごく賛成してくださって、その後に各システムの役割をどうするのかなどを、しっかりと明確にしていきました。ですので、さまざまな理屈をこねながらシステムを構築しています。それぞれの行動には、必ず何かしらの意味を持たせています。
平山
超忍に自分がなり切れるのは、『NINJA GAIDEN』らしい魅力です。ですので“このときには、この行動をしなければならない”みたいな作りではなく、自分が思った通りに動かせるべきです。ジャスト裏風や弾き返しなどもありますが、あくまでそれは選択肢のひとつにして、“滅却”の活用など、シリーズらしいバトルに集約しています。集約していますが、そこに至るまでの選択肢はプレイヤーの思った通りに動かせるようにしよう、という方針がありました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a7cad041ac0c269f516193092b41de5a9.jpg?x=767)
――とくにボス戦は、攻防のやり取りが明確になり、アクションゲームとしてメリハリが付いたように思います。旧作では、そこの攻防が窮屈になりがちと言いますか。そこも現代的な形にするうえで、整えた部分なのでしょうか。
平山
もちろん旧作ならではのボス戦の魅力もあると思いますが、本作は敵のガード不能攻撃に対して、鵺の型の攻撃を合わせると、カウンターとなる“崩撃”が発生します。また、鵺の型自体は敵のガードを崩すことができます。そういった部分は、メリハリが付いたひとつの要因だと思っています。
実際に実装されたときには、シリーズ作品らしいアクションではありながらも、新しいボス戦の攻防が体験できるなと感じました。とにかく敵の隙を突いて攻撃するのが旧作の基本でしたが、自分のほうから能動的に攻め込んで隙を作りだせるのは、本作の特徴になっていると思います。
中尾
ボス戦に限らず、先ほどのお話にもつながるのですが、今回の『NINJA GAIDEN』で私がしっかりと進化させたかった部分は、それぞれの仕組みやシステムの、記号性を大事にすることでした。やはり10年以上前のタイトルですので、そこは現代的に進化させたほうがよりおもしろくなると考えていました。そこから崩撃のシステムであったり、各ボスの行動パターンを考えていたりします。
ただ、そこをやりすぎてしまうと、やることがワンパターンになってしまって、つまらなくなってしまいます。いわゆる雑魚戦、ボス戦、そしてアクションシステムとしても、そこのバランス感をすごく意識して制作していました。
なぜ記号性を高めたかったのかというと、私はいち『NINJA GAIDEN』ファンとして、このおもしろさをもっと広いプレイヤー層に知ってほしかったんです。アクションゲームが苦手な方にも楽しんでもらいたいな、と思いつつも、でも「これキツくない?」みたいなところもあったりするような、そういった体験も楽しんでもらいたくて。『NINJA GAIDEN』らしさを残しつつも、幅広い層に楽しんでもらえるような設計を目指しました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/ad00f1e6c1298de26cbdae8c342171f7e.jpg?x=767)
――『仁王』シリーズなど、Team NINJAが手掛けられている昨今のボス戦などにも、通じる面があるのかなと感じました。難度は高いのですが、攻略の糸口を用意しているような。そういった部分で、幅広い層に楽しんでもらおうと狙っていたのでしょうか。
中尾
それもありますが、記号的なシステムがあり、攻略の糸口が見えていたほうが、攻略したときのプレイヤーの気持ちよさが上がると思っています。自分で考えて、自分でその回答を見出したという、達成感が味わえます。そういうところもアクションゲームは重要です。
超忍を自由に操作し、アクションゲームのなかでも最高峰をタイトルを目指すにあたり、そういったカタルシスを感じられる部分はすごく大事にしています。
――旧作では難しいなと感じていましたが、本作は多少難度が下がったのか、突破のしやすい面もあるなと感じました。そういった部分も、各アクションに回答を用意しているからなのでしょうか。
中尾
体験していただいたのがまだ序盤なので緩めにしてある、という側面はありつつも、本作は全体的なゲームスピードが早いです。戦闘スピードと、それによる攻守の切り替えがすごく早いことは、シリーズ作品の魅力だと思います。とはいえ、ただただ高速で攻撃され続けると、単純に理不尽です。
そこを解消するため、敵の数を調整したりですとか、敵の強さを段階的に上げたりしています。記号的に攻略法のある敵なども存在します。バランス感については『NINJA GAIDEN 4』としてよくなるように調整しています。
また、チャプター3以降には、より強力なボスが続々と登場します。たとえば『NINJA GAIDEN』シリーズらしい掴み攻撃を使ってくる敵ですとか。脅威度だけで言いますと、かつてない敵も現れるでしょう。そこの歯応えは、ぜひお楽しみにお待ちください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/aace26684f6b9c333312e6d4dd14faa8e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a83ca0f46f3c407454d4ae27a41e61a32.jpg?x=767)
――難度調整も含めて、遊びやすさがとても磨かれているなと感じました。旧作だったら、1ステージ目でやられてしまうことも人によってはあったかと思います。本作は、チュートリアルの部分が体力消費なしで戦えるようになっていて、ゲームに入り込みやすい印象でした。
平山
やさしくしようとは、あまり考えていませんでした。今回体験していただいたのが序盤ですので、難度も低く感じられたかもしれません。ただ、後半に行けば行くほど『NINJA GAIDEN』シリーズらしい歯応えのあるバトルが味わえると断言できます。
そのうえで、数十年ぶりの新作ということもありますし、昨今のアクションゲームの現代的に進化した部分は取り入れて、広い層に遊んでもらえるタイトルにしたいと考えていました。過去作にもありましたが、難易度設定にヒーローモードがあります。
ただ簡単に遊べるのではなく、オートガードなどで戦闘を補助してくれる難度になっています。オプション設定になっているので、ずっとそれをオンにしなくてはならないわけではなく、自分がうまくなったなと感じたら、たとえばオートガードをオフにしたりもできます。少しずつサポートオプションを外しながら、上の難度にチャレンジしていただけるような仕組みを用意しました。
また、本作はストーリーモードの難度を途中で変更することも可能です。ある程度慣れたら、ノーマルモードで遊んでみるといったプレイも可能です。段階を経て、超忍としてのステップアップを積んでいってほしいです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a3577dc1fafa79dc995dae0255e68055e.jpg?x=767)
中尾
序盤のチュートリアル的な導入部分は、とても意識して作りました。『NINJA GAIDEN』のよさがあるにしても、その前にゲームを楽しむ前提の部分を味わってほしくて。簡単にしよう、と思ったわけではなくて、このゲームのことを理解してもらえるような状態を作ることを意識していましたね。
――トレーニングモードや、技の解放なども含めて、学ぼうと思えば『NINJA GAIDEN』の仕組み・立ち回り・戦術をゲーム内でしっかり教えてくれるのは、シリーズ作品でも珍しいなと感じました。といった部分も『NINJA GAIDEN』のよさを知ってほしいから用意したのでしょうか?
中尾
テクニックを購入して解放し、それを練習して身につけていくのは、まさにそういった部分です。最終バージョンに向けて磨きあげた部分でもかなり力を入れた要素になります。『NINJA GAIDEN』はおもしろいのですが、そのおもしろさをしっかりと個人的に伝えたかったんです。
いろいろな人にその楽しさを知ってもらうにはどうしたらいいだろうと考えた結果、各種テクニックを丁寧に積み上げて知ってもらう仕組みにしました。すでにイロハを学んでいるプレイヤーにも、新しいシステムはどういうものなのか知ってもらう機会をたくさん用意しています。いままでの立ち回りにプラスした、楽しみかたの深みや、テクニックの組み合わせなども考えられるようにしました。
――過去作にあった、体力上限が削れる“壊死”が本作にはありませんが、採用は考えていたのでしょうか?
中尾
入れるべきか、相当悩みました。ただ私の解釈としては、“壊死”は理不尽なシステムというよりも、ジリジリと敵に追い詰められていく体験として、すごく重要だったと思います。一方で、現代化する面で言うと、ステージ全体の流れで戦うというよりも、バトルはバトルシーンごとに集中して戦ってほしい思いがありました。
といったなかで、ある程度体力をリセットできるタイミングを設けつつ、“壊死”が発生しないようにしました。もちろん、いろいろと制約はありますが、それぞれのバトルを全力で楽しんでもらえればと思います。
――自由ながらに、非常にメリハリの効いたアクションになっていますが、試行錯誤するうえで“『NINJA GAIDEN』らしさ”に悩んだポイントなどはありますか?
平山
一時期、“鵺の型”がものすごく強いバージョンがありました。重要なシステムだと思いますし、鍵になる要素ではありますが、やはり『NINJA GAIDEN』らしいバトルとしてはやりすぎていた部分もあったのかなと。そういった部分は、開発しながら調整していきました。入れてみて、完全に無くなったような要素はいまのところないのですが、どうシステムとして落とし込むのかは試行錯誤がありました。
中尾
鵺の型はすごく調整していて、原型がもはや無いレベルです。通常状態である鴉の型からスイッチできるのが鵺の型ですが、必殺技をくり出すようなシステムではなく、いつでも強い状態になれるシステムです。ですが、強すぎるとそれしか使わなくなりますよね。そして弱すぎると、いままで通りの戦いかたをすればいいことになってしまいます。そこのバランス感は、とても苦労しました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a9baae886a5b76259d6a9b0ac52a71c39.jpg?x=767)
――ロケットランチャー兵や、決死の覚悟で組みついてくる兵士など、敵キャラクターからもシリーズ作品らしさを感じました。そのあたりも、やはり入れ込みたかった部分なのでしょうか。
平山
シリーズファンの方々から「おっ」と思っていただけるようなアイデアは、プラチナゲームズさんからもいただきましたし、我々としても賛成でした。まさに、自爆する兵士などは「あぁ、あったあった!」と思っていただけるのかなと(笑)。今回も大ダメージになっているので、食らう前にはしっかりトドメを刺してあげてください。
――最高難度である“超忍”は、今回どれくらいの難度になるのでしょうか?
平山
ただ難しくなるだけのような難度上昇では、プレイヤーとしてもやはりおもしろくないと思いますし、アクション体験の変化も難易度変更では重要なポイントだと思っています。敵の配置はもちろんのこと、思考パターンも含めて変わる調整にしています。たとえば、ノーマル難度ではくり出してこなかった攻撃パターンを出してきたりですとか。そこはきっと、超忍の皆さんにも楽しんでいただけると思います。
――リュウ・ハヤブサは鵺の型ではなく、閃華という特殊な技を使います。具体的にはどのような性能なのでしょうか?
中尾
リュウ・ハヤブサが、ものすごく強い超忍であることを表現するために作ったのが閃華状態です。性能面だけで言うと、1対1に特化した性能になっています。ただ、技の種類によっては範囲攻撃を仕掛けられたりもして、万能なんですが扱うのはやや難しい性能になっています。
ヤクモはもっとカジュアルに鵺の型で戦えるようになっていて、リュウ・ハヤブサは使いこなすまでの道のりはやや高めです。そのぶん、使いこなすことができれば超強力な性能です。
平山
また、今回のバージョンのリュウ・ハヤブサは、火炎龍と暗極重波弾、2種類の忍法を使えます。今回は武器だけでなく、忍法もリアルタイムで使い分けながら戦えます。そこもリュウ・ハヤブサの進化ポイントのひとつで、敵が散っていたら火炎龍、通路などに敵がいたら貫通する暗極重波弾を撃つですとか、シチュエーションに合わせて忍法を使い分けられるようになりました。
――遊んでいて、“ニンジャらしさ”も強調されているように感じました。ステルスアクションが可能であったり、アスレチックアクションなども過去作以上に取り入れられていて。
中尾
忍んで隠密活動をするリアルな忍者というよりは、パワフルなニンジャ像があるのは『NINJA GAIDEN』のよさですよね。そこを意識しつつも、ヤクモのことは皆さん知らないので、フラットな状態で見ることになります。パワフルなイメージをヤクモからも感じてほしく、ニンジャらしさを強調している部分もあります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a49841316f44cb49043d8c696de4d1ed6.jpg?x=767)
――キャラクターデザインや物語、世界観などの部分で、中尾さんは『NINJA GAIDEN』らしさにこだわった部分はありますか?
中尾
『NINJA GAIDEN』はこういうものだよね、こうでありたい、といった着想はだいぶ入っています。ゲームのわかりやすさなど、システマチックなところは現代化を目指していますが、『NINJA GAIDEN』にも、もともとあったよさがあります。
たとえば世界観やキャラクターのトンデモ感、なんちゃって日本感ですとか。そういった部分はとても大事にしていて、そこはブレずにストレートに作っています。
――プラスして、ビジュアルなどからプラチナゲームズらしさが感じられる部分もありました。
中尾
細かな面でプラチナゲームズらしさを出そうとはしていませんでしたが、新しく取り入れたものはそう感じる部分もあるでしょう。たとえば新主人公のヤクモは、新しく超忍としてこれから成長していく存在です。我々としてもそこはオリジナリティを出しつつ、『NINJA GAIDEN』の世界に溶け込むようなデザインにしているつもりです。もしかしたら、そこで自然と我々らしさが出ているかもしれません。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a951152abce43c65c74b3d8d17a39cfab.jpg?x=767)
――とくに見た目は、やはりTeam NINJAとはまた違った魅力があるなと感じていました。そこは平山さんも、プラチナゲームズさんには好きにやってもらおうと考えていたのでしょうか。
平山
やはりプラチナゲームズさんじゃないと出ないアイデアはたくさんあります。バトルシステム面も、そしてアートスタイルの部分でもです。我々としてはアクションを通じて『NINJA GAIDEN』らしさを味わえることは、とても重視しています。また、リュウ・ハヤブサなどの過去シリーズのキャラクターも、イメージがズレないようにしっかりコミュニケーションを取っています。
ただ、新作ならではの新しさ・おもしろさの部分で、プラチナゲームズさんだからこそ出せる魅力は、積極的に取り入れています。せっかく2社の共同開発ですから、シナジーが生み出せると思ったポイントは、シリーズらしさが崩れない限りは取り入れるべきだと考えていました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a137f42f1e7da630f7216d77be0a38f12.jpg?x=767)
――平山さんは、見ていてプラチナゲームズらしいなと思った部分はありますか?
平山
たくさんありますが、たとえばチャプター1のステージである東京摩天楼の風景は、最初見たときとてもプラチナゲームズさんらしいなと思いました。そこはなんとなく、大阪の風景を感じさせるような。東京なんですけれども(笑)。※
※……プラチナゲームズは本社が大阪。
――往年のファンの方々に、まさにここが『NINJA GAIDEN』らしい部分だと、ぜひ注目してほしいポイントはありますか? たとえば、宝箱を蹴って開けるところですとか。
平山
あ、まさに宝箱を蹴る仕様って、じつは当初取り入れられてなかったんですよ。そこはぜひ蹴って開けてくださいと、プラチナゲームズさんにお願いしたポイントでした(笑)。といった話はありつつも、やはり新システムは取り入れながらも、『NINJA GAIDEN』らしいバトル体験を味わえることを目指して開発を続けてきました。そこはぜひ、プレイしていただけると感じ取ってもらえると思います。
中尾
これまで使用できたテクニックである、たとえば“着地絶技”、“絶技引導”なども使用できます。とくに“絶技”関連のシステムは『NINJA GAIDEN 2』からのものです。往年のファンの方々が本作を触ったときに、そういったテクニックをいい意味でそのまま活用できます。それ自体をそのまま味わうだけでも、『NINJA GAIDEN』シリーズらしさを懐かしんでいただけるのではないでしょうか。
――最後に、読者の方々へメッセージをお願いします。
平山
十数年ぶりに『NINJA GAIDEN』ナンバリングタイトルを皆さんにお届けできるのが、すごくうれしく思っています。新主人公のヤクモが登場しますが、しっかりと『NINJA GAIDE』らしさ、シリーズ作品らしい攻防をしっかり楽しめるキャラクターになっています。もちろん、リュウ・ハヤブサもプレイアブルキャラクターです。往年の超忍の方だけでなく、まだ遊んだことがないプレイヤーの方にも触っていただきたいと思っていますので、ぜひ今後の続報と、発売を楽しみにお待ちください。
中尾
インタビューのなかで、“『NINJA GAIDEN』らしさ”といったワードが多く出てきたと思います。期待されているファンの方々にとっても、ホットなワードかと思います。まさに、我々としても“『NINJA GAIDEN』が、『NINJA GAIDEN』である理由は何か”を、ものすごく深く考えて制作しました。ですが、十数年ぶりの新作というところで、より幅広い層に楽しんでいただけるのかも考えています。ただ間違いなく、『NINJA GAIDEN』の原体験、そして新しくなった体験を思う存分楽しめるタイトルになっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a75937b721cd6740104353e9feac667fc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/ae63ea84ba5a2008dbcbea9bc279e05c8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a0138e007a2e55f93112157ceacd714a2.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a7cad041ac0c269f516193092b41de5a9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/ad00f1e6c1298de26cbdae8c342171f7e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/aace26684f6b9c333312e6d4dd14faa8e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a83ca0f46f3c407454d4ae27a41e61a32.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a3577dc1fafa79dc995dae0255e68055e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a9baae886a5b76259d6a9b0ac52a71c39.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a49841316f44cb49043d8c696de4d1ed6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a951152abce43c65c74b3d8d17a39cfab.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49351/a137f42f1e7da630f7216d77be0a38f12.jpg?x=767)