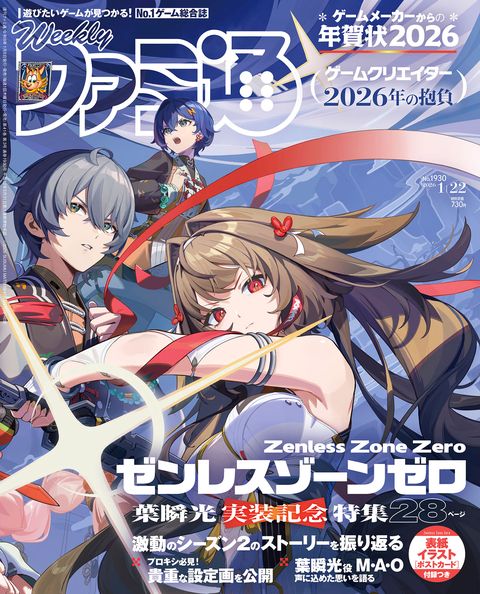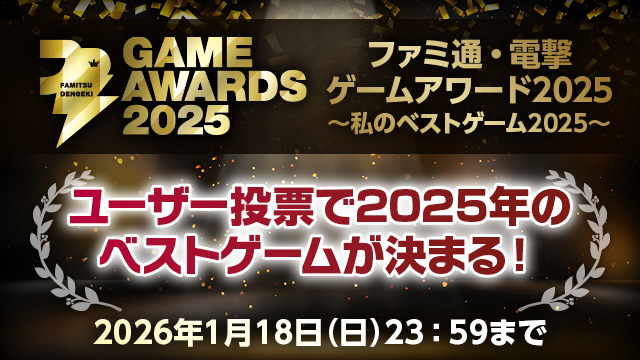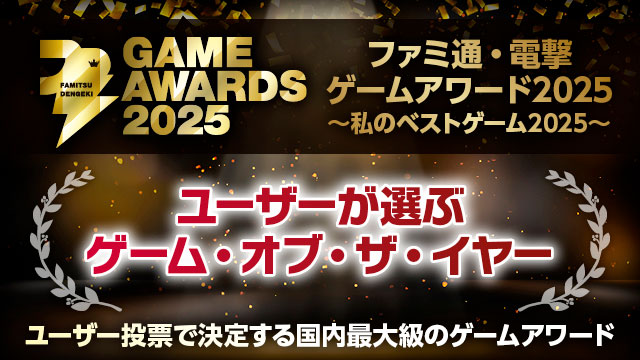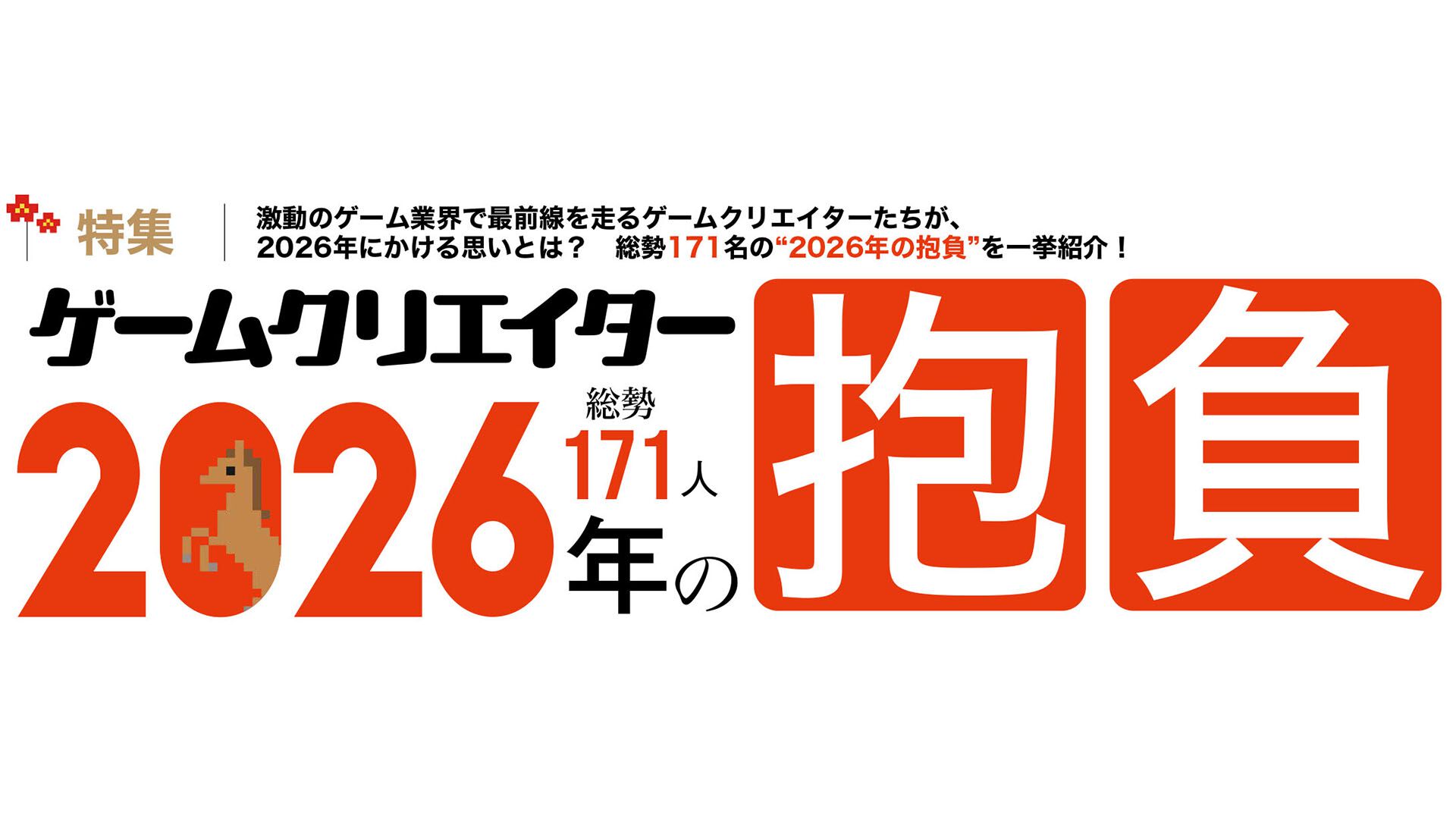本作はコーエーテクモゲームスのアクションゲーム『NINJA GAIDEN』シリーズ最新作。前作から13年ぶりとなるナンバリングタイトルで、コーエーテクモゲームスのTeam NINJAと、アクションゲームで知られるプラチナゲームズの、共同開発タイトルとなっている。
発売に先駆けて、プラチナゲームズにて各国のメディアを招いた試遊会が実施された。本記事では、開発中のバージョンを事前に体験した、先行プレイレビューをお届けしよう。なお、開発中のバージョンなので、細かな部分は製品版と異なる可能性がある。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a7cad041ac0c269f516193092b41de5a9.jpg?x=767)
- 序盤のステージ&ボス戦を体験
- 黒龍を巡る物語
- 無敵で進むチュートリアル
- 独特の『ニンジャガ』アクションが現代的に
- ジャスト系の新アクション
- 武器を変化させる、ヤクモの術
- 敷き詰められた『ニンジャガ』らしさ
- リュウ・ハヤブサ度満点!
- 発売が待ち遠しい!
序盤のステージ&ボス戦を体験
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a3e83f2b514dc79d2ac847fcf5030aad5.jpg?x=767)
筆者は『NINJA GAIDEN』シリーズの大ファンで、Team NINJAのアクションゲームが大好き。さらに、『ベヨネッタ』シリーズなど、プラチナゲームズが手掛けてきたアクションゲームも大好き。そんな2社の共同開発ということで、個人的には本当に夢のようなタイトルになったことに驚いた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a45bd96c28daa555bfc86f5e5099acb29.jpg?x=767)
ゲームプレイ映像などを見ると、プラチナゲームズらしいケレン味の利いたアクション要素がバリバリ含まれているので、『NINJA GAIDEN』シリーズらしさが感じられないかもしれない。遊んでみて個人的には、『NINJA GAIDEN』らしさを現代的に昇華しつつ、昨今のアクションゲームらしい文法に整えたタイトルだと感じた。
少なくともアクション面で言うと『NINJA GAIDEN』らしさは失われておらず、歯応えのある戦闘、自由自在に動き回れるアクション性の高さは健在どころか、シリーズ随一になるのではと、序盤のプレイを通しただけでも感じられた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/af49ddf06c2f66125586018fdb927e927.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a6648a8fd2aa57660638365c685d09b09.jpg?x=767)
黒龍を巡る物語
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a7cad041ac0c269f516193092b41de5a9.jpg?x=767)
物語の鍵を握るのは、シリーズ作品でもたびたび登場し、復活したり封印されたりした黒龍。ヤクモは任務をこなす中で、黒の巫女・セオリと出会う。ヤクモもセオリも黒龍に関わりがあり、セオリの提案でヤクモたちは“黒龍の封印を解く”という、大胆な作戦を進めていくことになる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a6069fdf4d719a0896906277209f5c0d5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a3ed003438ba685bd666644fdca505930.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a4b2f7ccb220410ecabaea5b6d1cfe23f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ae63ea84ba5a2008dbcbea9bc279e05c8.jpg?x=767)
ヤクモは無口なクール系といった感じで、クールながらに熱い闘志を宿すリュウ・ハヤブサよりも、かなりぶっきらぼうで冷静沈着な男。会話などから、隼の里が表仕事の忍者だとしたら、鴉の里は汚い裏仕事をこなす一族であることなどが語られていた。
キャラクターまわりはとてもプラチナゲームズの血が濃く、敵なども含めてシリーズ作品とはまた違った魅力に包まれている。体験した範囲では、物語の中でリュウ・ハヤブサの名が聞こえてくることもあったが、具体的に本筋にどう絡むのかはわからなかった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a0e5345b8f1a1f2b38a33b7b6c3166c45.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a9046490e6a4b9b0380fb18f6a6f9fd85.jpg?x=767)
敵となるのは黒龍の封印を護る組織・龍神党。白いアーマーなどに身を包み、さまざまな武装を使いこなす戦闘集団といった感じ。また、いわゆる妖怪的な“妖魔”も登場する。これまでもモンスターである魔神などが登場したが、大体同じような立場の敵だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/aaf6acadd301d2164e41d55924141bfdd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/aace26684f6b9c333312e6d4dd14faa8e.jpg?x=767)
ストーリーはカットシーンによってそれなりに長くしっかりと描かれているが、チャプター3まで遊んだ印象としては要所要所のみに挟まっている程度で、やはりアクションゲームらしくアクションを重視している印象を受けた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a9baae886a5b76259d6a9b0ac52a71c39.jpg?x=767)
無敵で進むチュートリアル
自由にアクションをこなせるうえで、横に操作説明がなんとなく出てくる程度に留められている。ときどき、重要なシステムだけウィンドウが挟まって解説してくれるようになっているので、チュートリアル過多な印象はなく、アクションの楽しさをゲームスタート時から楽しめるのは、時代に逆行しているかもしれないが、むしろ好印象だった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad00f1e6c1298de26cbdae8c342171f7e.jpg?x=767)
そして、『NINJA GAIDEN 2』シリーズのような感覚で、そのまま操作できることに驚いた(『NINJA GAIDEN 3』はまた違ったアクション形態になっている。本作は『NINJA GAIDEN 2』に近い)。もちろん新アクションやシステム、そもそも敵をロックオンできるようになっているなどの違いもあるのだが、感覚としてはリュウ・ハヤブサを動かしている、あの楽しさそのままなのだ。
とはいえ、システムは非常に多いので覚えることも多い。本作にはチュートリアルとは別に、トレーニングモードがステージ中からでも遊ぶことができるほか、同じく鴉の忍びであるタイランと道中出会えば、アクションの詳細なシステムを学びながら、実践訓練にも挑める。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a83ca0f46f3c407454d4ae27a41e61a32.jpg?x=767)
あとで練習できる場があるにせよ、シリーズ作品に初めて触れた人は、最初のステージ、何をすればいいのかわからずにこのチュートリアル期間に挑まなくてはならないだろう。ただし、最初はなんとヤクモの体力バーすら表示されず、ヤクモが倒れることはない。
このあたりの思い切ったイントロダクションは「とにかくいろいろ攻撃しまくって、気持ちいいアクションゲームを味わってくれ!」といったメッセージなのだなと、勝手に感じ取っていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a951152abce43c65c74b3d8d17a39cfab.jpg?x=767)
なお、体力まわりについてはシリーズ作品にあった、最大体力が削られる“壊死”がなくなったので、ステージ攻略をしながら徐々に追い詰められていくような難しさはなくなった。そのぶん、食らってしまうと敵の攻撃はしっかり手痛い印象を受けた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a137f42f1e7da630f7216d77be0a38f12.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a3577dc1fafa79dc995dae0255e68055e.jpg?x=767)
独特の『ニンジャガ』アクションが現代的に
シリーズファンとして驚いたのは、戦闘の攻防がシステムでしっかりと味付けされていて、プレイヤーが何を狙えばいいのか、どう攻略すればいいのかが、明確に可視化できるようになっていたことだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a49841316f44cb49043d8c696de4d1ed6.jpg?x=767)
これまでの『NINJA GAIDEN』シリーズもシステムはいろいろあるのだが、敵をどう倒せばいいのか、どう戦えば有利に立ち回れるのか、といったことが具体的にゲーム側から語られることはかなり少なく、ゲーム側から「さあ攻略してみろ!」と挑戦状を叩きつけられているようなタイトルだった。
もちろん、溜めることで超連撃を放つ“絶技”、『NINJA GAIDEN 2』以降ならば、部位欠損した敵を一撃で倒せるようになるフィニッシュアクション“滅却”を決める、など、ある程度ゲーム側から用意されたものもあるのだが、その攻防にセオリー的なものは少なかった印象を受ける。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a32c8d462716792e1fcad02a32b9ae6bc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ac871e871d61de3af9249066016cd6cb4.jpg?x=767)
『NINJA GAIDEN 4』はそこがグッとわかりやすくなっていて、戦いに大きなメリハリが付いた。システマチックに戦えるからこそ、カッコよさも倍増。いままでのような、なんとなくダメージを食らわないように立ち回る、何かの行動一辺倒になる、などのシーンはかなり減った。もちろん、プレイヤーの立ち回りによるところはあると思うが、“そうしないと突破しにくい”みたいなシーンが少ない印象だった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a701e2b130abb66d520a03029565961a9.jpg?x=767)
逆に言えば自由度が減ったように感じるかもしれないが、決してそうではない。『NINJA GAIDEN』シリーズでこれまでできた、独自の連携(いわゆるコンボ)は上級者向けのやり込み要素といった感じで、手裏剣などを交えてさまざまな連携をくり出せた。本作では、それも可能のままだ。
さらに、相手に飛び掛かる強力な技“飛燕”をとにかく使い続ける、みたいな『NINJA GAIDEN』シリーズらしい立ち回りも、そのまま可能だ。壁走り(無影脚)→飛燕→着地絶技みたいな黄金連携も健在。敵からドロップする回復できる血塊(旧作のエッセンスにあたる)を使った、絶技引導もある。といった感じで、『NINJA GAIDEN 2』ライクなアクションに、新要素を交えて現代アクションに整えたのが『NINJA GAIDEN 4』なのだと筆者は感じていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a7452eb0d980839668a14c49165b3ca34.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a0a3ef9851970545ceaae6fb6270b49c5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad5b8b12c093a92d98c47529f0ae279fc.jpg?x=767)
ジャスト系の新アクション
本作はそれに加えて、ジャストガード、ジャスト回避、そして弾き返しができるようになった。ガードは敵の攻撃を防ぐが「〇回まで連続でガードできる」といった性能になっており、ジャストガードならばその回数制限がない。また、ジャストガード後は即座に別の行動に移れる。
攻撃をくり出すとシャストガードからのジャストカウンターのような攻撃となり、相手の体勢が崩れたり、大ダメージを与えられるのが特徴。また、ジャスト回避も同じように、ジャストカウンター的な攻撃に以降できる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ac3a5c5bdda25e13936fdd8788574313c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a2fb39ebcdf7ad53671e1b10fae6d7d90.jpg?x=767)
いずれも移行できるタイミングはややシビアで、かつジャストカウンターが最適な行動というわけでもない。敵が怯んでいない状態で出してしまったら、そのままカウンター攻撃が潰されてしまう場合もある(ジャストガードや弾きでは発生しにくいが)。
このあたりの攻防が明確に付けられたことによって、スピーディーなアクションの最中、華麗なディフェンスアクションで敵をいなすことが可能になった。このあたりは、やはりプラチナゲームズらしい味付けだ。とはいえ、それだけを狙えばいい、みたいなゲームで済まないようになっているのが、本作は『NINJA GAIDEN』シリーズ作品なのだなと感じ取れた部分。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad68cc9117dabd78f49fba4605c388eb3.jpg?x=767)
そもそも、本作のゲームスピードはものすごく早く、攻撃・防御問わずとにかく動き続けて立ち回らないと、攻略するのが難しいようなゲームになっている。自由自在に動きながら、“超忍”として活躍することが攻略の秘訣であり、かつ本作の醍醐味になっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a36511e3da0953f29efc0dba089148f9f.jpg?x=767)
相手の部位を欠損させ、“滅却”に持ち込むのは、やはり基本の流れ。ちなみに残虐表現は、『NINJA GAIDEN 2 BLACK』くらいバンバン欠損する。個人的にはグロいとは感じなく、シリーズ屈指の血液量が画面を覆うので、いっそコミカルに感じていたくらい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/afdfd669eb38df817c4c6e97b6266dc6c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a55f061fadb167e939f56a3ad8c2fd088.jpg?x=767)
アクションゲームとしての難しさはあるが、オートでガードしたりしてくれる“ヒーローモード”は健在なので、苦手だけれども物語や世界観を追いたい、という人もご安心を。
武器を変化させる、ヤクモの術
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/abcd57b6a3e86a606f8a8ebff5b502487.jpg?x=767)
ヤクモのデフォルト装備は二刀の“鬼刃建御名方(きじんたけみなかた)”で、通常攻撃アクション(鴉の型)の攻撃では、シンプルで扱いやすいスピーディーな攻撃をくり出せる。リュウ・ハヤブサの龍剣と、だいたい同じようなイメージだ。
鵺の型は血楔ゲージがあるときに使える構えで、鵺の型中に攻撃をすると、二刀が1本の太刀に変化する。威力は高いが隙の大きく、ボタン長押しで威力を高められる武器になるのだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/adc4b249b4d1accb09291440f7efb21e6.jpg?x=767)
本作の武器は鵺の型により、1本で2種類の性能を持っているのが特徴。しかも、ゲージを使っているからと言って高性能かというとそうではなく、しっかり使いどころを見極めないと、扱うのは難しいのがおもしろいところ。
通常の立ち回りで使うこともできるが、ジャストカウンター時、鵺の型の技で返したり、通常攻撃から空中コンボに行き、途中から鵺の型に移行するなど、さまざまな使い道があった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a25df79483e6a2c2137649cf129f6c146.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ac1c3882f2316578f969711d37b87a1ab.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a9db492ed6c8f045751e098d18d575e62.jpg?x=767)
もうひとつ今回使用できたのは通常時は突進力に長けた剣“降魔夜刀穿(ごうまやとうせん)”。敵に突進するような攻撃が多く、相手との距離を詰めながら戦える。そして鵺の型は、巨大なドリルのような槍に変化する。ボタン長押しでドリルを回転させることができ、敵に継続攻撃を仕掛けられた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a44cb95fa586c4efcf83c130235cc865e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/abeca5f1666869894975346f2879735a0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a5be4b2df56155072d87ccdb0d10cd307.jpg?x=767)
そのため、カウンターとして崩撃を狙う場合は敵の行動を読んで使うと効果が高く、読み切ったときに大ダメージチャンスを狙えるような作りになっていると感じた。もちろん通常の敵などの場合は、見てから崩撃できることもあるのだが、ボス戦ではきっと強攻撃を出してくるだろうと、“読み”でくり出さないと当てにくいのだ。崩撃の仕様も含めて「これだけやっていればいい」みたいな攻略にならないような作りになっているのは、アクションゲームとして非常にやり応えがあった。
さらに新アクション“乱殺”が登場。これは切り札のようなもので、乱殺ゲージが最大まで溜まっているときに発動すると、乱殺状態となる。乱殺状態中、鵺の型で特定の攻撃を敵に当てると、どんな状態であろうとも一撃で倒せる“血殺”を発動できる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a55c84c1d9ee12445e4ffc90ebc2f4726.jpg?x=767)
切り札ではあるのだが、どれが血殺対応技なのかどうか把握しておく必要があるなど、これまた使い勝手に一癖あり。もっと簡単に、周囲の敵を血殺する“乱血殺”といった発動方法もあるので、初心者のうちは乱血殺のほうが使い勝手がよさそうだ。
なお、武器はアクション中に自由に切り替えることが可能だった。これまでの作品も戦闘中に武器変更はできたが、ポーズメニューなどを挟んでの変更だったため、武器を変更しながらの連携などは不可能だった。本作では攻撃後でも変更できるので、さらに連携の幅が生まれるだろう。しかも、武器スロットは4つ存在していた。もしかしたら、4つの武器を自在に変更しながら戦えるのかも。
遊べた範囲の限りでは、ヤクモはリュウ・ハヤブサなどのような忍法攻撃を持ってない。忍法は、これまでのシリーズ作品でいわゆるボムのような扱いで、危なくなったら使える緊急回避手段、または特定の攻略に使う要素だった。その役割が、本作では乱殺にあたるのだろう。ちなみに遠距離武器は試遊では手裏剣のみだったが、ほかにもあるのかは不明。
敷き詰められた『ニンジャガ』らしさ
相手を投げ飛ばし、運がよければ首を刈りとれる“首切り投げ”ももちろん健在で、しかも本作では敵に投げ付けて敵を巻き込んだり、首切り投げから自分で追撃を狙うなど、連携パーツの1個としても使えるようになっていた。
壁走り(無影脚)を使いながら、落とし穴を回避するような移動アクションもそのまま。連続壁ジャンプで高所を昇る“飛鳥返し”は、あまりにも早すぎて笑ってしまった。むしろ進化していて、本作は素早い身のこなしで移動する、まさにニンジャのようなシーンもより多くフィーチャーされていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a070f303223a07a57349724950cbb2883.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/af3a8b0d3b346a09d20da695ee34dfc21.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a40495d4b50a16f1396cc1706fbac82b1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a98728397cf726faad4f403acc874ffc9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/adf678bd7a1d30238e9f92dfb9f5c76e0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad9c1733ca97d350c41813ae4d2300040.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a91de30ac80ef96ab5f51db6a8e4ec2de.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/af59b092f7f9c4027fee4f5367ad66577.jpg?x=767)
“忍ぶ”という部分のニンジャらしさも一応あり、見つかっていないときに敵の背後へ回る、または空中から飛び掛かる場合、敵を暗殺できる。ステージの場所によっては、見つからずにステルスキルで突破もできるだろう。飛び掛かり攻撃は、『NINJA GAIDEN 3』の“ムササビダイブ”を彷彿とさせる。とはいえ一応ある、というくらい。敵に見つかってもヤクモが「倒せば問題ない」みたいなことを言い出したときには、「そうだよね!!」と思った。これぞニンジャ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ab7c6dd240ccdf6ae68cb9d4030132cdc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a9fb9f4946d5e37c40f4a3e9c27053b97.jpg?x=767)
ちなみに、これまでのシリーズ作品はフィールドがやや窮屈というか、段差があっても基本的には登れない場合が多かった。本作は見える場所は大体登ることが可能になっていて、より立体感のある探索が可能に。通常ならば行かないような場所に行くと、チャレンジ系のミッションが隠されていることも。“最大体力をいくら減らすか賭けて戦う”という、かなり尖ったコンテンツになっていたので、やり込みがいもあるだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/adcc246537392572e6e5222360a3c2105.jpg?x=767)
また、敵からもシリーズ作品らしさが強く感じられ、たとえば遠くからミサイルランチャーを撃ってくる敵など、これまでも厄介だったなと思い出すような敵も少なくない。敵の部位欠損が発動したあと、自爆覚悟で掴み攻撃を放ってくる敵の姿は、ファンならばニヤリとする要素だろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/adf3aac186bf50b05d86cf5e92638624e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a73ea18841d066c8a679c3e2260f8f517.jpg?x=767)
なお、今回は各種技が最初から解放されていたが、実際にはポイントを消費して解放していく仕組み。先輩の忍びであるタイランから学ぶことできた。ちなみにアイテムは、特信機 八咫烏という端末を通して購入する。端末では“忍務”というサブミッションを受注することができ、ステージ内で達成するとお金を稼ぐこともできた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a4117b680cee164e16baa2ea81bff1c2a.jpg?x=767)
リュウ・ハヤブサ度満点!
チャレンジでは、リュウ・ハヤブサも使用することができた。メディア向けの試遊では、初披露とのこと。ハヤブサは基本的には『NINJA GAIDEN 2』と同じような性能で、試遊では龍剣を使用することができた。ほかの武器が使用できるのかは不明。過去作のハヤブサと比べると、本作のハヤブサは見た目がかなりマッシブな印象(ヤクモが線の細い、やや小柄のキャラクターというのもあるかもしれないが)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a3e6fd5e0cf4c25f59919af8b72e548ab.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a7f425575143b4f233a24b166d47128ec.jpg?x=767)
ヤクモは基本的に戦闘中もあまり掛け声を強く発さないのだが、ハヤブサはやはり気合十分。「トァーッ!」と戦場を駆け巡るさまは、シリーズおなじみの心地よいやかましさ(褒め言葉です)がある。リュウ・ハヤブサの声の担当はもちろん、堀 秀行氏。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/af046c9fdddc60e7e149fcfd14760d0b1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a4ba80f26ea77495edc79888103a5d7c4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ab8ef5626428635ccb7006fb4d04ba7ee.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a77ab483f537515862ff2a542a2845192.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/add257dafea8dd6d79a62c3ba5a7caa1c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a0e00e4253d884b0eab67074c59d50829.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ae6886890c6984dc1aafe0dcd21967bcb.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad45dbc0ee8fab02b1af3cacc4b0cd1c7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a35192cf132876a54500816ed209a76f0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a679b500e6058662b8596f9c13ed5f443.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/ad1e0d1a98c19f95eecb21fd361bc5277.jpg?x=767)
このへんの細かな“リュウ・ハヤブサらしさ”みたいなところはとても大事に作られているなと、さまざまな場所から感じられた。もしかしたらこれまでのレイチェルや紅葉などといった、ややオマケ的なプレイアブルキャラクター、といった立ち位置なのかもしれないが、それでもリュウ・ハヤブサの雄姿がしっかりと、プラチナゲームズらしい味付けで味わえるのは非常にうれしい。ちなみにショップの特信機 八咫烏も、ハヤブサ操作の場合はおなじみのムラマサショップに変化。「ヘイラッシャイ!」と聞きなれた声で、ムラマサが出迎えてくれた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a1098aef4b28c091713ed27a9c1cd1c07.jpg?x=767)
発売が待ち遠しい!
もともとのシリーズ作品に慣れていた、というのもあるだろうが、そのへんが整えられていたおかげでメディア試遊会内で“超忍”難度のボス2体を、今回倒すことができた。限られた試遊時間でやるべきではなかったかな、と途中は正直思っていたのだが(難しかったので)、超忍難度に挑んだからこそ近接戦の攻防をしっかりと理解することができた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a8687de5e3c641d0b6406552ee8816a21.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a6ece0ea3e5eea2403e70d8be7733fb4a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/aa98b92e0e13d9ee579496ffe70d05163.jpg?x=767)
安心してほしいのは通常難度ならば“死にゲー”のような作りには全体的になっていない。ボス戦で多少倒れてしまうことはあるかもしれないが、基本は超忍らしい爽快バトルを楽しめるアクションゲームとなっている。少なくとも、体験した序盤の範囲は。
プレイヤーを倒しにくる挑戦的な部分はありつつも、遊びやすさや爽快感を重視していることはゲームの多くの部分から伝わってくる。たとえば、ゲームオーバーになり続けると回復アイテムなどを補給してくれる。わざわざ先輩忍者のタイランがくれるのもうれしい。
また、トレーニングモードは、初心者にも上級者にもうれしい要素。コマンドリストを眺めながら、さまざまな技をくり出せる。ちなみに、各技の部位欠損確率が低いのか、高いのかといった細かな部分も書かれていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a7e1caa488b4f8a67b180ce8f79c882fc.jpg?x=767)
世界観などは『NINJA GAIDEN』かと言われると、ややコミックテイストでスタイリッシュな作りになっているのは、やはりプラチナゲームズが開発しているゲームだなと思うところは少なくない。シリーズ作品の、というかリュウ・ハヤブサ自身の魅力なのだと思うが、マジメにやってるけどちょっと笑えるみたいな雰囲気もさほど感じられなかったりもするので、そういった面ではシリーズファンには物足りなさがあるかも。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a75937b721cd6740104353e9feac667fc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a0138e007a2e55f93112157ceacd714a2.jpg?x=767)
ゲーム部分は、アクションゲームとしてバッチリ。体験できたのはおそらくゲーム全体の最序盤であり、成長要素部分の感覚など体験できなかった要素もあるのだが、ステージ攻略を通してアクションゲームとしては、しっかりと『NINJA GAIDEN』らしさを感じ取ることができた。それでいて、カメラワークなどの理不尽な要素も少なく、しっかりと遊びやすくなっている。カメラは戦いやすいように引き気味なのはプレイヤーとしては気にならなかったが、スクリーンショットやプレイ映像ではこじんまりとした印象を受けるかも。
体験した範囲では、とくに敵の数が多くて楽しかった。敵兵士だけでも、これでもかというほど押し寄せてくるので、うまく操作できる人ほど“超忍”の力を堪能できるはずだ。おそらくチャプターが進むと、きっとさらに難しくなっていくはず。なんか強い犬は出てくるだろうか、爆破弓で狙撃されないだろうか、ボスは理不尽な投げを連発するのだろうか、爆発する手裏剣を付着しまくる敵は出てくるだろうか……。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/49348/a18ac083c982b3dd6a719fab1a1ed38ed.jpg?x=767)