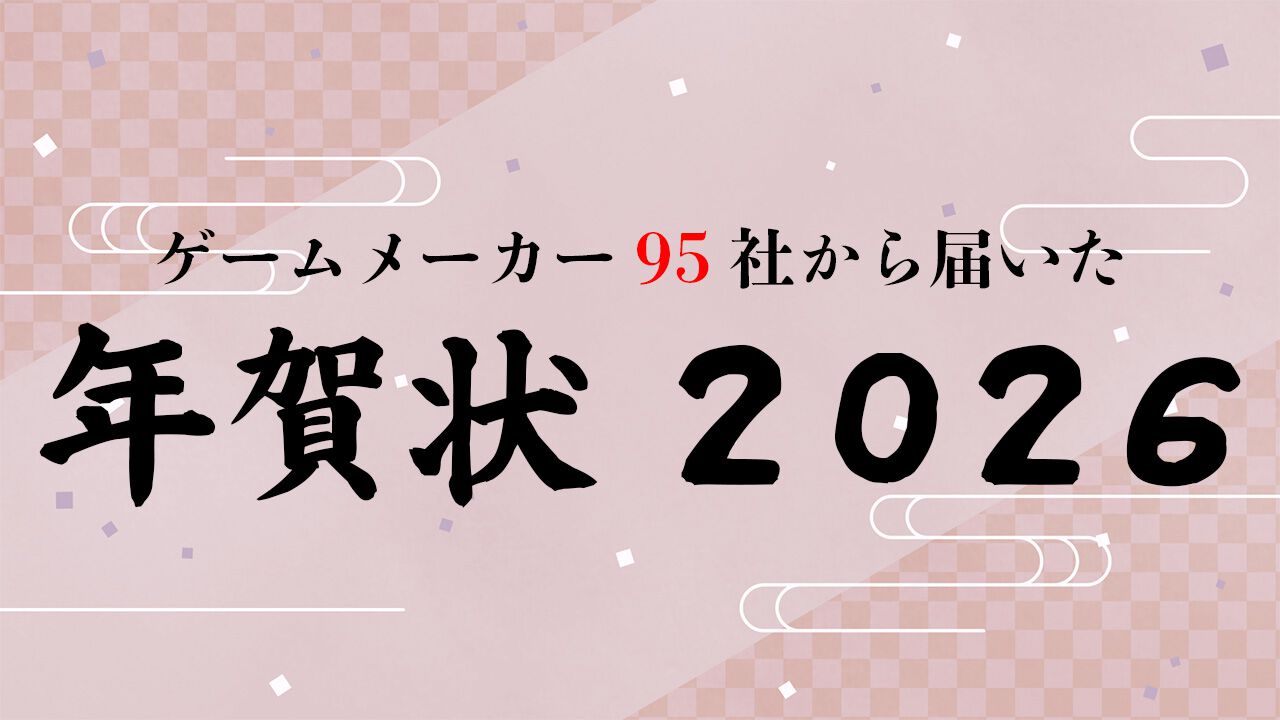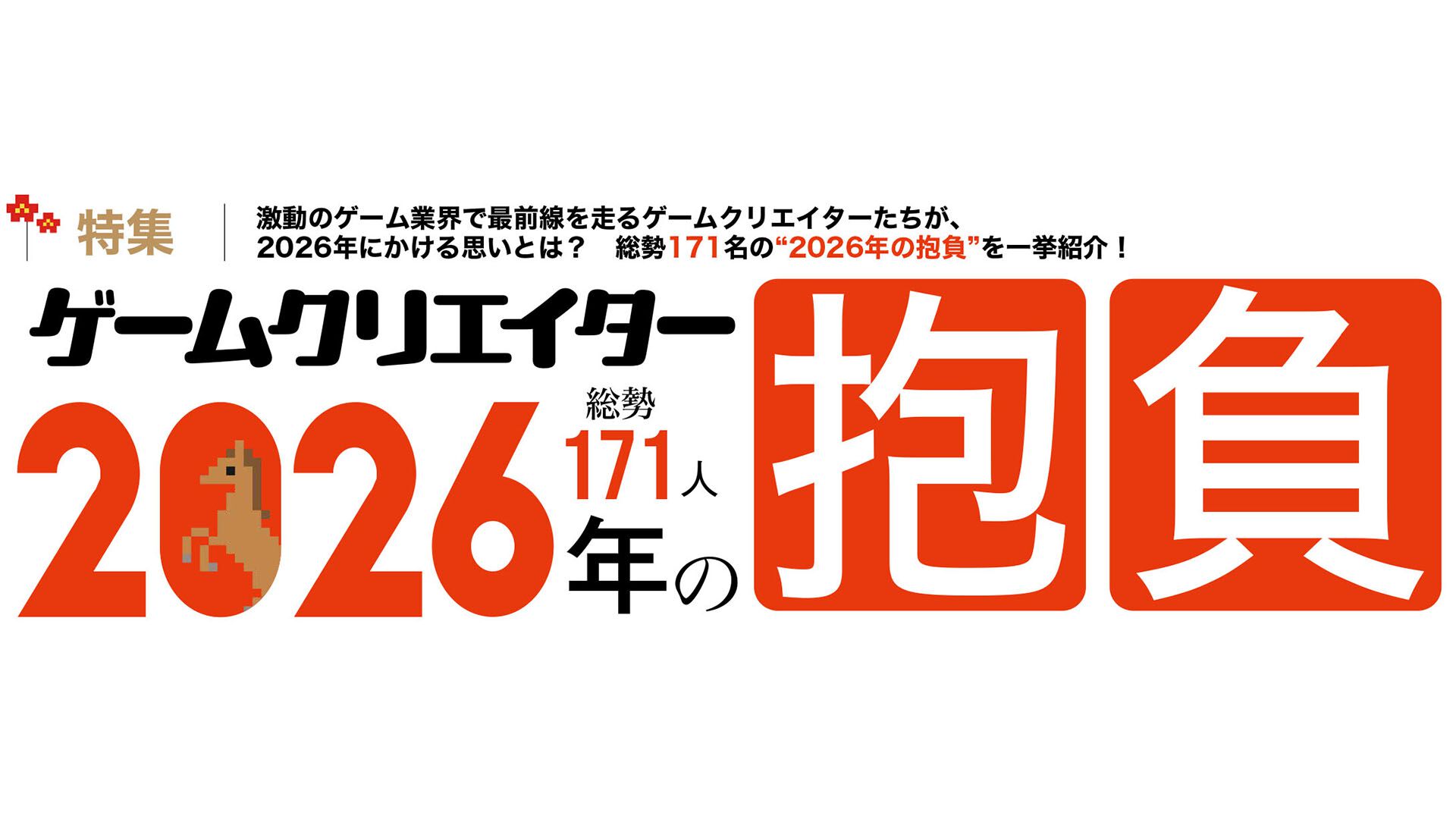ストーリーノートのアドベンチャーゲーム専門ブランド“Lorebard”(ロア・バード)の第1弾タイトルとして、2025年7月18日から体験版が配信となったSteamタイトル『Pain Pain Go Away!』(ペイン ペイン ゴー アウェイ!)。
タイピングゲームとアドベンチャーゲームが融合した、これまでにない“心療タイピング型アドベンチャーゲーム”となっており、7月18日~20日まで京都で開催される“BitSummit the 13th(ビットサミット13) Summer of Yokai”においてもプレイアブル出展されている。
そんな本作のプロデューサー兼ディレクターを務めるのは、ストーリーノート代表の藤澤仁氏。これまで“第四境界”のARG(※)などにおいて“既存のメディアに収まらない物語体験”を追求してきた氏が、コンピューターゲームの物語体験の原点とも言えるアドベンチャーゲームでやろうとしていることは何なのか。開発チーフを務める虎渡由姫氏とともに、その制作意図をうかがった。
※:ARG……“Alternate Reality Game(代替現実ゲーム)”の略称。SNSや動画サイトなどを活用し、日常世界をゲームの一部に取り込んで現実と仮想を交差させる、体験型のエンターテインメント。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
藤澤仁 氏(ふじさわ じん)
ストーリーノート代表。「ドラゴンクエスト」シリーズのシナリオに携わり、『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』でディレクターを、『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』(Ver.1)ではディレクターとメインシナリオライターを務める。2018年にスクウェア・エニックスを退社後、ストーリーノートを設立。ARG(代替現実ゲーム)『Project:;COLD』シリーズの総監督のほか、 “第四境界”総監督としてARG『かがみの特殊少年更生施設』『人の財布』『人の給与明細』などを手掛ける。文中は藤澤。
虎渡由姫 氏(とらと ゆき)
ストーリーノート所属のシナリオライター。『Pain Pain Go Away!』ではプロジェクトのチーフとして、シナリオやプランニングだけでなく、BGMなども担当している。文中は虎渡。
「もうディレクターはやらない」からアドベンチャーゲームを作りはじめるまでに起こったこと
―― まずは、物語を制作する集団としてスタートしたストーリーノートが、今回“Lorebard”というブランドを立ち上げて『Pain Pain Go Away!』というゲームを作ることになったきっかけからお聞かせください。
藤澤
そうですね……。ストーリーノートの原点からの話になるんですが、僕が前職で「ドラゴンクエスト」シリーズにディレクターとして3本関わった後、「もうゲームのディレクターはやめよう」と思ったことが発端になります。全体のディレクションよりも「残りの人生は、自分が楽しいと思うこと、自分が得意なことに集中したい」と考え、そのために生まれたのがストーリーノートという会社でした。
ストーリーノートでは、世の中にあるゲーム、マンガ、映画のような、誰もが知っているメディアだけではなく、物語の表現手法、表現場所について自分たちなりの発明がしたい、という想いからさまざまな実験を繰り返していて、“第四境界”のARGなどもそのひとつの成果だと思っています。
――たしかに、ここ数年の藤澤さんの試みは、既存のメディアでの展開とは大きく異なるものでした。
藤澤
一方でインディーゲームシーンの熱気も感じていて、そんな中で「アドベンチャーゲームって、まだまだできることが残されているジャンルだな」という想いと、「コンピューターゲームの黎明期を知る自分だからこそ、いま作っておきたいアドベンチャーゲームがある」という、ふたつの想いが生じました。
――黎明期というと、ファミコンよりもさらに前の時代ですね。
藤澤
はい。ファミコンが出る前、マイコンと呼ばれていたPCでゲームを遊んでいた時代の話です。当時はコントローラーもなく、キーボードを使ってプレイするのが普通でした。『ミステリーハウス』や『サラダの国のトマト姫』など、“言葉を探して入力する”アドベンチャーゲームがまず主流となり、その後コントローラーでコマンドを選ぶゲームや、ポインティング・デバイスで遊ぶポイント&クリック型のアドベンチャーが生まれて……といった流れですね。
そんなマイコン時代から40年ほど経って、いまふたたびPCでゲームを遊ぶ人が増えています。そんな状況ならば、いまアドベンチャーゲームを作るということは、新しい物語への挑戦としてあり得るんじゃないかと。そして、自分がもう一度ゲーム開発に携わってみる意味があるのかもしれない、と思えたんです。
――ある意味、1周回ってアドベンチャーゲームがふたたび新たな挑戦になった、という感じですね。
藤澤
はい。そんな経緯を経て、“誰もプレイしたことがない独特なアドベンチャーゲームを、社内で毎年1本ずつ作る”という目標を掲げて立ち上げたのが、Lorebardというブランドです。そして『Pain Pain Go Away!』は、その第1弾タイトルとなります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/ad9b6f4554ead74cebd62effb6a671a52.png?x=767)
――本作の開発にあたり、虎渡さんはどの段階で合流されたのでしょうか。
藤澤
シナリオを本格的に固めていく段階で虎渡に入ってもらって、あれよあれよという間にプロジェクトのチーフになりましたね(笑)。肩書き上は僕がプロデューサー兼ディレクターとして全体総括していますが、実際のクリエイティブは虎渡がチーフとして責任を持って見てくれています。
――虎渡さんは本作において、具体的にどういった範囲を担当されているのでしょう?
虎渡
シナリオやプランニングのほか、BGMやSE(効果音)も担当しています。アニメーション演出に関わるSEはイチから作り、実装まで行っています。音が鳴るタイミングなどもこだわり、自分で調整しています。
――ご自身で音楽も作られているとは! もともと音楽を学んでいたのですか?
虎渡
幼いころにピアノを習っていて、趣味で音楽を作るためにDTMの機材は持っていましたが、本格的に作曲を学んでいたわけではありませんでした。今回、ゲーム開発をするにあたって思い切って「音楽も作りたい」とお願いして、初めてチャレンジしました。
――シナリオと、演出面を考慮した音の部分を、両方ひとりで手掛けるからこそ生まれる相乗効果はありそうです。実際にそうやって作られた名作はインディーゲームではいくつもありますし。
藤澤
そういった意味では、まさにインディーゲームらしい体制で作っていますね。絵も外注ではなく、可能なかぎり社内の人間で作っています。その理由としては、効率重視というより、“そういう気概を持つメンバーが力を合わせて作っているプロジェクト”にしたかったからです。
――実際に何人くらいで本作を開発しているのですか?
藤澤
社内の人間は僕を除くと3人、それに社外のエンジニアやパートで手伝ってくれているメンバーを数名加えた少人数チームで作っています。
過去に「ドラゴンクエスト」シリーズでは200人規模で作っていましたが、「これだけの人数がいればゲームって作れるよね」という最小単位に近い規模でやっている感じですね。
――以前とはまったく異なる規模感のプロジェクトを動かしてみて、いかがですか?
藤澤
いや、ゲーム作り自体に大きな違いはないですよ。むしろ、細部まで目が行き届く規模で作れるのは楽しいですね。
キーボードを介することで感情が流れ込んでくる、独特のゲームプレイ
――『Pain Pain Go Away!』をタイピングが軸となるゲームにしたのは、やはりマイコン時代のゲームにあった“自分で言葉を入力する”という要素を物語に落とし込みたかった、という意図があるのでしょうか?
藤澤
それもありますが、着想のヒントはもっと身近なところにありました。ストーリーノートでは、入社した新入社員全員に、まずはタイピングの練習からしてもらうんです。
――いきなりタイピングの練習ですか?
藤澤
ええ。シナリオライターとして、タイピング速度は基礎スキルなので。具体的には、ブラウザでプレイできる『寿司打』というタイピングゲームがあるのですが、「これの1万円コースをクリアできるくらいにはなるように」と伝えています。そしてその様子を眺めているうちに、「タイピングの要素を使って、アドベンチャーゲームを作れるかもな」と思ったんです。タイピングで入力する言葉で物語を紡ぐ……それが最初の着想でした。
先ほども言った通り、僕たちは「物語を“どこ”で語れるか?」ということ、つまり“まだ誰も物語を語ってない場所”をずっと探しています。最近だと“第四境界”の『READY TO STORY』は“ビール×物語”というアイデアでしたが、同じような感じで「タイピングゲーム×アドベンチャーゲームはあり得るんじゃないか」と考えたわけです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
――体験版をプレイしてみると、選択肢型のアドベンチャーゲームとも、ストーリー性がないタイピングゲームにチャレンジするのとも、また違った感覚になるのが印象的でした。
藤澤
そうですね。まさにそこが本作の特徴で、以前“東京ゲームダンジョン”というイベントに、誰もこのゲームを知らない状態で試験的に出展してみたのですが、大勢が列を作って遊んでくれたんです。
ああいった試遊時間の限られたイベントだと、アドベンチャーゲームってとっつきづらいと思うんですよ。短時間で物語を堪能するのは難しいことだと思うので。なのであまり盛り上がるイメージはなかったのですが、行列になるほど遊んでもらえたのは、やっぱりタイピングのようなアクション性があってこそだろうなと思いましたね。
“アクションアドベンチャーゲーム”……というと違うゲームジャンルを想像しちゃいますが、“アクション性のあるアドベンチャーゲームが持っている可能性”は、そのとき感じました。
――ちなみに虎渡さんが参加したときには、もうタイピング×アドベンチャーというテーマはすでにあり、それをどのような物語にするかを具体的に考えていった形でしょうか。
虎渡
そうですね。お話を読むアドベンチャーパートと、タイピングで物語が進むカウンセリングモード・ダイブモードが分かれている構造は決まっていました。「タイピングで物語が進む部分って、どうシナリオを書けばいいんだろう?」とすごく悩んだのを覚えています。
――でも、実際に体験版をプレイすると、すごく腹落ちするものがありました。タイピングですと能動的に言葉を打ち込むことになるため、辛い言葉を打つときはプレイヤーも辛い気持ちになると言いますか……。キャラクターとコミュニケーションをするうえで、プレイ中は“キーボードを介することで流れ込んでくる感情”のようなものがあったように感じます。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a9675c1ff34145d7b1a68d3ddb6c0e555.png?x=767)
藤澤
そうですね。女の子の頭の中を駆け巡っている無数のトラウマを打ち消していくって、実際にやってみるとなかなか生々しさを感じる体験ですよね。
――タイピングについては、PCでキーボードを使い慣れている人と、そうではない人の差が大きいかと思いますが、そのあたりは難易度のバランスを考えるうえでどのくらい意識していますか?
藤澤
体験版では、EASY/NORMAL/HARDの三段階の難易度を用意しています。難易度によってワードの流れる速度だけでなく、ライフの数や出てくるワード数も変わります。最終的な製品版では、今日初めてキーボードを触る人でもそこそこ遊べるくらいの難易度も用意したいと思っています。
――その一方で、タイピングってとんでもないスピードの猛者もいますよね。
藤澤
じつはボス戦のクライマックスで、複数ターンかけて入力するかなり長い “ファイナルワード”があるのですが、東京ゲームダンジョンでプレイしてくれた50人くらいのうち、その長いワードを1ターンで入力し切った猛者が二人いましたね。完全に初見の状態で、です。
――1ターンでの入力はそれだけ難しいのですね。
藤澤
“ファイナルワード”はほかのワードと違い、1回でもミスタッチするとやり直しになるので、緊張感が高いんです。なのでどうしてもタイピングスピードが落ちるんですが、それでも1発で成功できてしまう人が、ごく稀にいて。
なので、「これはメチャクチャすごいことなんだ」というのが周囲にも一目でわかるように、特別な演出を入れることにしました。
シナリオからアニメーション演出の“音ハメ”まで、すべて自分たちの判断で試行錯誤
――つぎに物語についてもお聞きします。心理療法をストーリーの軸にしたのは、どのような理由からでしょう?
藤澤
“心の中にあるトラウマをひとつずつ消していく”感覚が心理療法に近いのではないかと感じたので、そこはあまり悩まずにいまの形になりました。
――タイピングの結果などで、ある程度ストーリーが分岐するような作りなのでしょうか?
藤澤
そういうシーンもありますし、エンディングもマルチになっています。変わったプレイをすることでしか見られない結末もあるので、いろいろと試してみてほしいですね。
――ほかの物語媒体と違って、さまざまなif(もしも)の物語を用意できるマルチエンディングは、アドベンチャーゲームの魅力のひとつだと感じます。
藤澤
そうですね。いまのインディーゲームは“実況ありき”なところがありますから、ひとつしか結末がないと、それを実況で見た後は体験価値が減ってしまいます。なので、自分がプレイしたときには、また違うエンディングにたどり着けるという要素は、現代のアドベンチャーゲームとして必須要素と思っています。
――虎渡さんはとくにストーリー面で苦労されている点はありますか?
虎渡
メインストーリーは、体験版をプレイしていただいてもわかる通り、ちょっとシリアスな空気感になっています。ですがマルチエンディングの部分はかなりおもしろい内容になっているものもあります。ほかのチームメンバーにシナリオを担当してもらったこともあり、「どこまではっちゃけたエンディングにしていいのか?」という本編とのバランスには、ちょっと苦労しました(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
――シナリオのほかに、音楽や効果音もご自身で手掛けるにあたって、具体的にこだわった部分をお聞かせください。
虎渡
カウンセリング機器 “P2GA”の起動演出は、アニメーションにあわせて「ガシャン、ガシャン」といった音が気持ちよく鳴るように、ひとつひとつ細かく調整しています。“映像と音がしっかりハマると気持ちがいい”というのはゲームのいろいろな場面で大事にしているポイントです。
またSEについては、素材をお借りすることもあるのですが、自分のイメージと合わないときは音楽制作ソフトを使って楽器をひとつひとつ試して、納得する音を追求しています。
あとは、ダイブモードの曲を何パターンか作っていくうちに、「この曲はラスボス戦に使えそう」と感じて割り振ったものがあります。それは注目してほしい楽曲になったかもしれません。
――そういった“自分の判断で試行錯誤している感覚”は、インディーゲーム開発ならではの体験とかもしれませんね。
藤澤
実際に作っていくうちにどんどんうまくなっていくので、僕から見ても目を見張るものがありました。
虎渡
趣味としての作曲は自分が好きなものを作って満足したら終わりなので、“ゲームに合わせて作る”のはぜんぜん違うなと感じています。藤澤さんも「音楽のことはわからない」と言いながらいろいろアドバイスしてくださるので、ありがたいですね。
“かほちゃん”は「かわいい(確信)」、というかむしろヒロイン
――ビジュアルですごく気になった点があるのですが……カウンセリングのとき頭に被せる“P2GA”は、なぜカニの形をしているのですか?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a5f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
藤澤
あれは……、最初はカニじゃなくてメンダコだったんですよ。意外性があって好きだったんですが、某アニメでメンダコが出てくることがわかって。真似したみたいになるのもなぁ……と(笑)。
――たしかに、某アニメにそういうシーンはありますね(笑)。
藤澤
そこで二転三転して、最終的に食パンかカニの二択になったんですが、「まあカニかな……」みたいなノリでカニになりました。
――すごい二択ですね(笑)。頭に被るのが食パンだったら、ゲームの印象がだいぶ変わっていた気がします。
藤澤
なので、フフカがP2GAをかぶったときに「ベチョッてする」というセリフがあるのは、メンダコ時代の名残ですね。
――ちなみにこのカニ型機械の名前“P2GA”の由来にもなっていますが、『Pain Pain Go Away!』というタイトルはどんなコンセプトで決まったのでしょう? 日本語にすると「痛いの痛いの飛んでいけ!」だとは思うのですが。
虎渡
これは、カニ型のカウンセリング機器に“P2GA”と名付けたのが先なんです。「Pain Pain Go Awayを略してP2GA」という案が通って、そのあとゲームのタイトルを決める話し合いのときに……。
藤澤
「タイトルも『Pain Pain Go Away!』がいいんじゃない?」となりました。
――ビジュアルといえば、本作の雰囲気やキャラクターは基本的にかわいらしいですが、ボス戦などでは一転して強烈なビジュアルとなっていて、かなり印象的です。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
体験版で登場するボスキャラクター(自粛あり)。
藤澤
“かほちゃん”のことですね。そこはやっぱり“二面性があるゲーム”にしたいという思いがありました。表向きはファンシーでパステルカラーな世界だとしても、「心の中まではそうではないはず」というギャップを表現しようというのが当初からの狙いでした。
ちなみに、“かほちゃん”はボスの中ではかわいいほうです。
虎渡
かわいいですよね。
藤澤
僕らは“かほちゃんはヒロインだ”と思っている節があって、東京ゲームダンジョンで試遊してくださった方に、かほちゃんのアクリルスタンドをプレゼントしていたんですが、「怖いからいらないです」と、二人から断られました(苦笑)。
――(笑)。
藤澤
じつは、今日も持ってきているんです。
――あぁ、これは……。なんだか名前が入っているのが絶妙に威圧感を倍増させていますね。
藤澤
かわいくないですか? “ビットサミット13”で試遊していただいた方にも配ろうと思っているので、共感してくださる方はぜひ受け取ってください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
これが問題の“かほちゃん”のアクリルスタンド。こちらも実際のビジュアルは自粛させていただく。
ふたりが大きな影響を受けたアドベンチャーゲームとは?
――本作は自分でタイピングすることで、より“言葉の力”を感じられる作品になっていますが、おふたりはどんなときに“言葉の力”を感じられますか?
虎渡
言葉の力……そうですね。いまはSNSがとても普及していて、知らない人ともテキストで気軽にやりとりできる時代です。でもそれって直接会話するよりも、言葉そのものの刺々しさを強く感じやすいと思うんです。
ですから言葉を扱う側は、より繊細さが必要とされている時代だと思います。ただその反面、うれしい言葉や心に響く言葉がいろいろな人に届くといった、プラスの力もあると思っています。たとえば、社内チャットで藤澤さんが褒めてくれたときなどは、ブックマークしてあとで読み返したりしています(笑)。
――ポジティブな言葉をパワーに変えていると。
虎渡
モチベーションにしていますね。言葉って怖い一面もありますが、パワーになる一面も確実にあるので、それを信じて丁寧に扱わなきゃいけないな、と思っています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
――言葉自体は昔からそこまで変わっていないのに、それが広まりやすくなりすぎた結果、マイナスのパワーもプラスのパワーも大きくなっている気がしますね。藤澤さんは言葉の力に関して、どのように考えられていますか?
藤澤
僕はコントローラーでゲームを遊ぶことが一般化したころから、言葉が“紡ぐもの”ではなくて“選ぶもの”になって、自分の感情の乗りかたが希薄になってしまったような感覚があります。そんな時代だからこそ、 “書いたり入力したりしながら、その意味を自分の中で解釈する”ことを特別な体験として感じてほしいと思います。Lorebardは、まさにそういうことをするために立ち上げたブランドです。
――Lorebardがやろうとしていることは、昔からあるアドベンチャーゲームという枠組みに、これまでと異なる新しいものを入れていくチャレンジだと思いますが、それは今後作っていく作品でも同様でしょうか。
藤澤
そうですね。必ず“言葉の入力”にこだわるわけではありませんが、どれくらい世の中に新しい発明を届けられるかというところに価値を置いて、モノづくりをしていくつもりです。そして、「アドベンチャーゲームってこんな表現の仕方もあるのか」とハッとさせることが一番の目標ですね。
――ちなみに、これまで刺激や大きな影響を受けたアドベンチャーゲームがありましたら教えてください。
虎渡
私は最近の作品ですと『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』(※)をすごく夢中になって遊びました。難しいゲームは苦手なのですがシンプルにお話のおもしろさに引き込まれ、続きが知りたくて毎日夜更かしして楽しみました。
『Pain Pain Go Away!』を作るときも、「どうすればあんなにおもしろく、魅力的なアドベンチャーパートを作れるのか?」というのは参考にさせていただきました。
※パラノマサイト FILE23 本所七不思議……2023年3月9日にスクウェア・エニックスから発売されたミステリーアドベンチャー。物語の魅力と完成度の高さが話題となり、日本ゲーム大賞2023で“優秀賞”を受賞。ファミ通・電撃ゲームアワード2023では、“シナリオ部門”、“アドベンチャー部門”、“ルーキー部門”の3部門で最優秀賞に輝いた。――藤澤さんはいかがですか?
藤澤
アドベンチャーゲームは、マイコン時代は人気ジャンルでした。僕は中学生のころ、電波新聞社の『マイコンBASICマガジン』(※)で山下章さんが連載していた“チャレンジ! アドベンチャーゲーム”を夢中で読んでいたような少年だったので、このジャンルへの想いには、まずそういった原体験があります。
そして、アドベンチャーゲームの歴史を変えたタイトルのひとつだと思っているのが、師匠である堀井雄二さんの『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』(※)です。なにがエポックメイキングだったかというと、アドベンチャーゲームにおける“日本語入力”から“コマンド選択式”への転換点だったことでした。
※マイコンBASICマガジン……電波新聞社が1982年~2003年にわたって刊行していたパソコン雑誌。読者投稿によるオリジナルのプログラムや、パソコンゲームの攻略記事などが掲載されていた。
※北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ……堀井雄二氏がシナリオを手掛けた、1984年発売のアドベンチャーゲーム。堀井氏が手掛けたアドベンチャーゲームとしては、1983年の『ポートピア連続殺人事件』、1985年の『軽井沢誘拐案内』も有名。――たしかに、その前年の『ポートピア連続殺人事件』は、日本語を入力するシステムでした。
藤澤
堀井さんのことは本当に尊敬していますが、僕は『オホーツクに消ゆ』については、アドベンチャーゲーム好きとしてちょっと物足りなさを感じていました。自分の脳内にある言葉を探り当てて入力するという楽しみかたが、コマンド選択式のゲームではなくなっていたからです。コマンド選択式がプレイヤーの間口を広げる発明だったのと同時に、ゲームとして日本語入力の方向性が途絶えたのはもったいないとも感じていました。
そんな背景があった中で、近年いちばん衝撃を受けたアドベンチャーゲームは『Her Story』でした。
――インディーゲームとして、かなり話題になった作品ですね。
藤澤
はい。『Her Story』は形こそ昔とは違いますが、ひさびさに見る“言葉探し”のアドベンチャーゲームだったんです。初めて見たとき、「あぁ、こういうゲームを自分は作りたかったんだ」と感じました。そして「自分で言葉を入力するゲームを作れる時代が、もう一度来たのかもしれない」と思ったのです。
なので、“第四境界”として手掛けた『かがみの特殊少年更生施設』も検索ワードを探す遊びだったし、Lorebardに先駆けてストーリーノートが企画・脚本を担当した『ソフィアは嘘と引き換えに』というゲームも、“言葉を入力することでサジェストされる選択肢を選んでいく”ゲームです。これらの作品も “Her Storyライク”だと思っているので、『Her Story』がなければ、「自分でアドベンチャーゲームを作ってみよう」とは思わなかったかもしれません。
“ビットサミット13”では1ターンでのクリアーにチャレンジしつつ、ティッシュやアクスタをもらおう!
――今回“ビットサミット13”に出展するにあたって、会場での注目ポイントなどを教えてください。
藤澤
イベント会場で遊ぶときって、なかなか「物語をじっくり読もう」という気分にはなれないと思います。なので今回は、タイピングによって少女をカウンセリングする感覚、そしてそれによって物語を進めていく感覚がどんなものなのか、そこに注目してもらえたらと思います。物語の全容はぜひ製品版で、じっくり楽しんでもらえたらうれしいですね。
あと、このバージョンから、“ファイナルワード”を1ターンで入力したときの専用演出が実装されているはずなので、どれくらいのプレイヤーさんがそれを見せてくれるか楽しみです。このあたりは実況映えも気にして取り入れた要素です。スーパープレイで周囲がワッと盛り上がるような場面って、アドベンチャーゲームにはないじゃないですか。そんな新しい感覚にも注目してほしいですね。腕自慢の方は、ぜひ挑んでみてください。
虎渡
海外からのお客さんも大勢いらっしゃることを見越して、今回の試遊バージョンから英語にも対応しています。日本語版・英語版ともにタイピングの難易度も3段階で変えられるので、ぜひ幅広いゲームファンの方に楽しんでいただきたいですね。
藤澤
タイピングゲームは世界中にありますが、多言語で遊べるものは、じつはあまりないんです。ただ、キーボード前提のゲームである以上、幅広いゲームハードで楽しんでもらうことは難しい。だから、「世界中のPCでゲームプレイができるように対応言語を増やす」という方針を取っています。製品版では、日本語と英語のほかに中国語と韓国語も加え、4言語になる予定です。希望が多ければ対応言語はもっと増やしたいと考えています。
なお、会場で試遊していただいた方には、かほちゃんとフフカのアクリルスタンドをランダムで配ろうと思っています。ほかにもティッシュを配ろうと思っていまして。こんなデザインなんですけれど……。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
――これはまた……なんというか(笑)。
藤澤
4000個くらい用意しているので、ほしい方はぜひブース(IP1-26)まで遊びに来てください。
――ふだん前面に出ているパステルカラーとは大きく異なる、グロテスクさを連想させる赤黒いデザインが目を引きますね……。なにげに“かほちゃん”も出ちゃってますし。
藤澤
ティッシュになったのにはちょっと文脈があって。“第四境界”のストーリーノートが作ったティッシュということで気にしてもらえたらいいなと。かほちゃんたちのアクリルスタンドともども、ぜひ受け取ってください!
目指すは『Outer Wilds』を世に出したあのパブリッシャー。未発表タイトルも準備中
――最後に、これからSteamでの体験版や“ビットサミット13”会場での試遊、そしていずれリリースされる製品版で『Pain Pain Go Away!』をプレイする人に向けて、メッセージをお願いします。
虎渡
ゲーム制作にここまで深く携わるのは今回が初めてなので、『Pain Pain Go Away!』は我が子のような大切な作品です。シナリオやBGMはもちろん、ADVパートを動かすスクリプトなど細かい部分まで調整し、たくさん愛情をかけました。まずは体験版や“ビットサミット13”の会場で一度触れてみていただけたらうれしいです。
製品版については、最後までプレイしていただければきっと驚いていただけるような展開が待っていますので、ぜひ多くの方にエンディングまでプレイしていただきたいです。よろしくお願いします。
――続いて藤澤さんには、Lorebardの今後の展望もうかがえればと思います。
藤澤
Lorebardブランドは、僕が2年前に「極めてオリジナリティの高いアドベンチャーゲームを毎年出せる会社にしたい」とブログにうっかり書いてしまったことが始まりです(笑)。ただ、実際にそんなことを目指している会社はほかにないと思っていたので、それが本当に可能なものなのか、正直に言えば不安もありました。
ですが、あとになって、自分たちがやろうとしていることを実現していたゲームパブリッシャーがあったと気付いたんです。それは、Annapurna Interactive(アンナプルナ・インタラクティブ)です。あのパブリッシャーは“ストーリードリブンのゲームを作る”という旗印のもとに、『Gorogoa』や『Outer Wilds』など、世界を驚かせる傑作をつぎつぎと生み出し続けていました。その事実に勇気をもらえたんです。
おこがましいかもしれませんが、僕らは彼らの魂みたいなものを、自分たちなりのやり方で引き継いでいきたいという気持ちがあります。「まだこういうアドベンチャーゲームって世の中にないよね」と思える作品を、今後もLorebardブランドとして作り続けていきたいと思っています。
まずは前身という形で『ソフィアは嘘と引き換えに』が発売され、ブランド第1作目が『Pain Pain Go Away!』も体験版が始まりました。さらに続く企画として、すでにふたつのタイトルが走り始めています。未発表の2タイトルも「そんなのってある!?」と思ってもらえるアドベンチャーゲームになっていますので、そちらの展開も含めて、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/ad9b6f4554ead74cebd62effb6a671a52.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a9675c1ff34145d7b1a68d3ddb6c0e555.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a5f3b980f0213c331c10559468a556d31.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47465/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
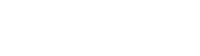





![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)