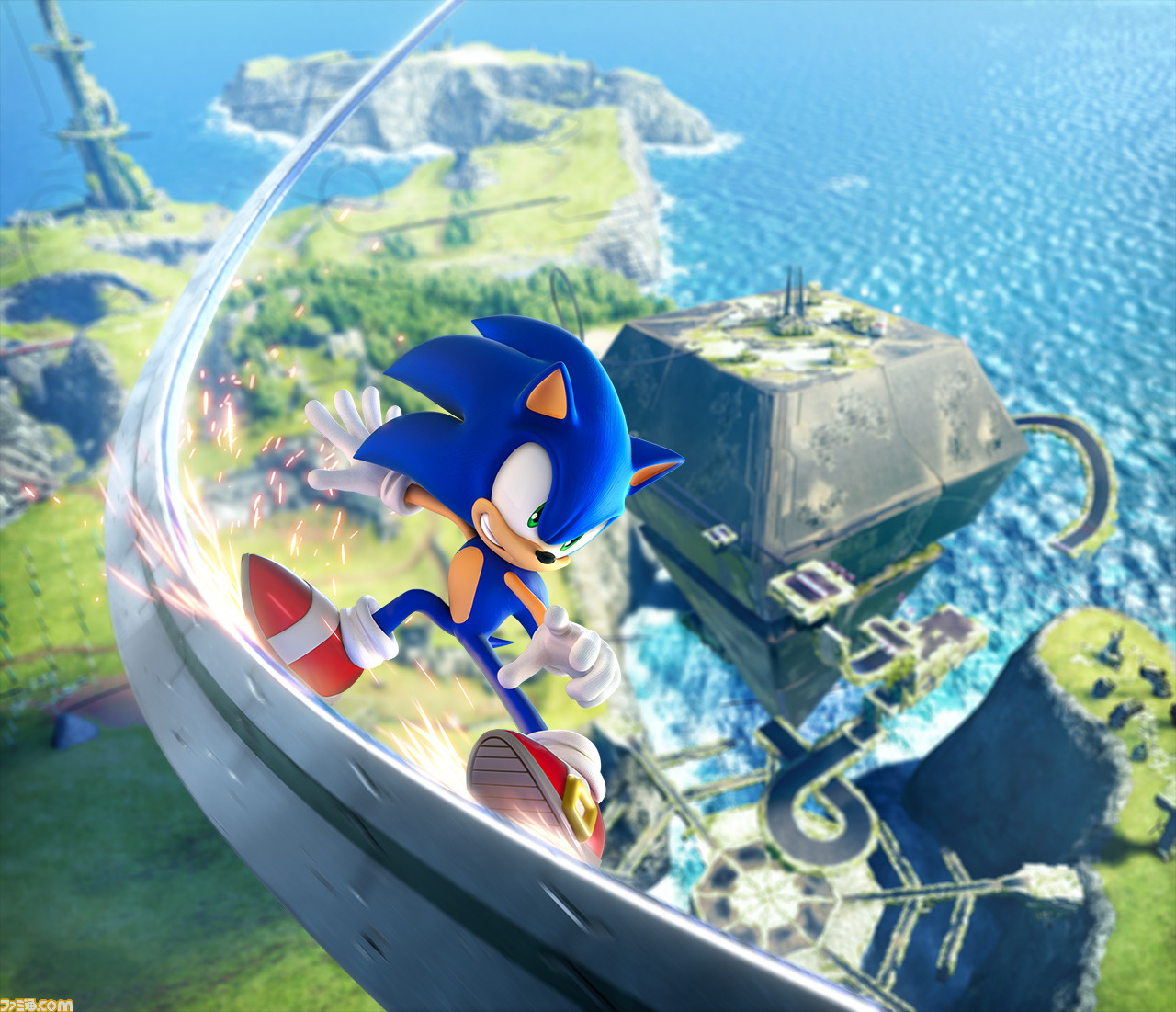セガより、2022年11月8日発売予定のNintendo Switch、プレイステーション5/4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam)用ソフト『ソニックフロンティア』。
2022年9月15日~9月18日まで千葉県・幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2022(TGS2022)にて、『ソニック』シリーズプロデューサーの飯塚隆氏と『ソニックフロンティア』ディレクターの岸本守央氏にインタビューを実施。本作の開発の経緯や魅力などを聞いた。
飯塚隆氏(いいづかたかし)
『ソニック』シリーズプロデューサー
岸本守央氏(きしもともりお)
『ソニックフロンティア』ディレクター
3Dソニックの新たな進化のために生まれた、次世代のソニックゲーム
――まずは、本作がどういったコンセプトのもと開発がスタートしたのか教えてください。
飯塚ソニックチームとしては、2017年に『ソニックフォース』をリリースしたのですが、同作を作り終えた後、つぎのソニックゲームを作ろうとなったときに、これまでのシリーズのように、スタートとゴールがあるリニアなソニックゲームをこのまま作り続けていいのか、疑問が生まれました。
さらに、3Dのソニックゲームは1998年に『ソニックアドベンチャー』が発売されてから24年ほど経っていますが、今後10年、20年と戦っていくために新たな進化がこのタイミングで必要なのではないかと考えました。
じつは『ソニックフォース』の後、リニアなタイプのソニックゲームの企画もあったのですが、それを見送りにして、次世代のソニックゲームを作ろうということで、『ソニックフロンティア』の開発がスタートしました。
岸本ちなみに、本作には裏コンセプトも存在していまして。それは、「もう一度、世界のトップレベルで戦う、輝くソニックチームになろう!」ということです。
メガドライブで発売された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズは、圧倒的なスピードのアクションで当時のアクションゲームの概念を覆して、世界に輝きました。これを僕たちは、第1世代と呼んでいます。
第2世代は、3Dソニックの『ソニックアドベンチャー』シリーズです。ループやスパイラルのアクションなど、2Dだからこそ表現できたものを、ホーミングアタックの発明のもと立体空間でも実現し、さらにソニックは輝きました。
これまでのソニックチームは、言わば第2世代のソニックの流れの延長線上にありました。ただ「このままではいけない。もう一度世界のトップレベルで戦うソニックチームになるためには進化が必要だ」ということで、オープンゾーンを軸に開発を行うことになりました。
3、4ヵ月に1回のハイペースで行われるプレイテストで、ソニックらしさを追求
――ソニックチームの皆さんの情熱も多大に含まれているのですね。そんな表、裏のコンセプトがありつつ生まれた『ソニックフロンティア』には、いまお話にもあった、オープンゾーンと呼ばれる広大なマップが存在しますが、このオープンゾーンを実装するまでに、いくつか実験みたいなものはされたのですか?
飯塚たくさんやりました。2017年に開発がスタートしてから5年ほど経ちますが、その期間のうちの約半分は作っては壊しをくり返す、試行錯誤の時間に費やしていましたね。
――なかなか次世代のソニック像が見出せなかった?
飯塚いまの『ソニックフロンティア』のイメージ自体は、最初から持っていました。ただオープンゾーンという、これまでにない360度自由に動ける環境の中で、なかなかソニックらしさを出すことができなかったんです。やはり、スタートとゴールがあるルートが存在するからこそ、ループやジャンプといったソニックらしいアクションが生まれたわけで。
今回は、そんなルートがないオープンな環境ですので、どのようにソニックのレベルデザインをすればいいのか、悩みました。
――そんな試行錯誤の中で、何が突破口となったのでしょうか?
岸本プレイテストをくり返している中で、光を見出すことができました。従来のソニックゲームでは、プレイテストは2回やるのがつねでしたが、本作では3、4ヵ月に1回のペースで、北米でプレイテストを行っています。そこでテスターの子どもたちに本作をプレイしてもらってその感想を聞き、そのフィードバックを受けてさらに開発、プレイテストをくり返していました。
そうした日々の中で、オープンゾーン、我々は“遊べるワールドマップ”という呼びかたをしているのですが、これをいちばん最初に実装したときは、だだっ広いフィールドの中にリニアなステージが点在しているという状況になっていました。フィールドにはフォトリアルな風景を用意して、ステージに移動するまでを楽しんでもらおうと思ったのですが、空間は草原ばかりスカスカなので、移動が退屈という意見がテスターから出ました。
そのときに、“移動するのがおもしろい”というのが“ソニックらしさ”であり、ソニックらしいオープンゾーンを作る必要があるという考えが生まれたんです。
――ソニックらしいオープンゾーンを実装する必要があると認識できたことで、本作の開発の方向性も明確に決まったと。プレイテストを何度も行っていたということですが、その中で、ソニックチームの考えるソニックらしさと、ユーザーさんが思うソニックらしさにギャップなどはありましたか?
飯塚プレイテストでは、「本作はソニックらしいか」ということは必ず確認するようにしていました。大方、我々の考えるソニックらしさと、テスター、ひいてはお客さんの考えるソニックらしさは合っていたと思います。ただ、「ソニックらしくない」と評価されたこともありました。
それは、フィールドの中にプラットフォームアクションがまったくなかったときで、テスターからも「ソニックらしさが足りない」という意見をかなりいただきました。それらの意見を参考にしながら、本作ではバトルやフィールドの探索など、すべてにおいてソニックらしさを最重要視して作っています。
――そうした新しい魅力はもちろん、電脳空間など、過去のシリーズのエッセンスも取り入れられていると思いますが、本作が発表された当初は、あまりそういった点は露出されていませんでしたよね?
飯塚そうですね。企画のコンセプトが遊べるワールドマップということで、電脳空間を用いたアクションステージは大前提で作っていましたが、最初のティザートレーラーでは舞台となる島のみお見せして、電脳空間はお見せしませんでした。そのときは、オープンワールドっぽいソニックゲームを喜んでいただける声も多かったのですが、一方で「ソニックのゲームが変わってしまった」という声もありました。
そんな反応もある中で、第2弾で発表したトレーラーで電脳空間をお披露目したときには、「ちゃんとソニックらしいゲームを作ってくれているんだ」との声もいただけたようで。
これらの反応を通じて、新規のファンと従来のファンとではフックとなるポイントが違うと感じましたが、本作ではその両方の意見を大切にしています。
『ソニックフロンティア』TOKYO GAME SHOW トレーラー
――若い世代だと、オープンワールドに、古くからのファンは電脳空間に魅力を感じる方が多いように思われますが、その両方の層も満足できるように制作されていると。
岸本そうですね。今回のプレイテストでは、ソニックファンのほかに、ソニックへの想いが強すぎないニュートラルな層にプレイしてもらっています。そうして、双方の意見を聞き、すべての方に響くゲーム作りを目指しました。
フィールドは最高速のソニックで走り回っても飽きないぐらい広い。バトルは多彩なアクションを駆使して戦うのが魅力
―――なるほど。ところで、フィールドの広さはどれくらいなのですか?
岸本本作では、ソニックのレベルが上がるとソニックの速度も上昇するのですが、最高速で全力で島を走り回っても飽きないぐらい広いです。
――レベルは1~99までありますが、最高速はどれくらいの速さですか?
岸本ゲーム内にはスピードメーターがありまして、最初は20%ぐらいを示すものが、最大では振り切るようになります。最高速を出すためにはレベルを上げる必要がありますが、一方で、最初からソニックの非日常的なスピード感を感じたい人のために、レベルアップをしなくても最高速が出せる秘密のテクニックが隠されています。ぜひプレイを通じて見つけていただけたらと思います。
――わかりました。ちなみに、ファストトラベルのような機能はありますか?
岸本もちろん、存在します。ただこの機能は、当初は入れる予定はありませんでした。というのも、とにかくソニックは速いので、ファストトラベルは使う必要がないんじゃないかなと考えたんです。でも、テスターの子たちから意見をもらい、ときには役立つかと思い、入れています。
――確かに、ソニックの速さは、ファストトラベルにも勝りそうです(笑)。ここで、バトルについてもお聞きかせください。本作では敵によっていろんな倒しかたがあると思いますが、力押しだけにしなかった理由は?
岸本当初はHPが多く、たくさんのコンボ攻撃が必要な敵も存在していました。でも、そうした力押しが必要なアクションはソニックらしくないということで、敵ごとに多彩なアクションを駆使して攻略する方針に変えています。
飯塚我々が作っているのはファイティングゲームではなく、アクションゲームです。アクションゲームでは、ボスの行動を見極めてアクションを行っていく攻略の要素が魅力ですので、それを味わっていただけるように作っています。
――攻略しがいのある敵がたくさん登場するのですね。ちなみに、さきほど試遊ブースを覗いてきたのですが、長蛇の列ができていました。これは、想定どおりといった感じですか?
飯塚いえ、完全に想定外です。まだ信じられないぐらい。胸がドキドキするほどでした。海外のゲームイベントではこういった光景はよく目にするのですが、東京ゲームショウの場合はまた別です。ソニックに列ができていなかったらどうしようかと、少しナーバスな気持ちにもなっていました。
ですが、一般デイはもちろん、ビジネスデイ初日から多くの人が並んでくださっていて、たいへんうれしかったです。岸本とふたりで「本当によかったね」と笑い合いました。
ソニックファンはもちろん、初めてソニックゲームに触れる人にも配慮したゲーム内容
――それだけ多くのゲームファンから期待を受けるのは、うれしいことですよね。そういった、本作を楽しみにしている方々に、もっとも注目してほしい遊びどころがありましたら教えてください。
飯塚私はゲームを遊ぶとき、ひとつひとつしっかりと攻略していかないと気が済まないタイプなんです。たとえばRPGですと、村の端から端まで探索してからつぎに行くような遊びかたをしています。ですが『ソニックフロンティア』では、そういった遊びかたではなく、自由気ままにプレイしていただきたいと思っています。
――本作でいちからすべて攻略しようとすると、時間もかなりかかりそうです。
飯塚そうですね。端からすべて攻略しようとするのではなく、自由にこの島を歩いて、気になるものがあればアクセスしてみる。そうすると、知らない場所にたどり着いて、冒険が広がっていく。島を自由に探索して気になるものにアプローチすることで、どんどんゲームが進行するようになっていますので、走るのが得意なら島を駆け回ったり、バトルが得意なら敵とガンガン戦闘したりと、皆さん好みの遊びかたで楽しんでいただきたいです。
――そういったスタイルにしたのも、ソニックらしさを追求した結果なのですか?
飯塚いえ、オープンゾーンというゲームシステムゆえですね。いままでのソニックでは、一面をクリアーしたら二面へ、二面をクリアーできなかったら先へ進めないというアーケードスタイルでした。今作では、オープンゾーンを採用し、好きなものから遊んでもゲームは進行する、自由度の高いゲームプレイを目指したので、このようなスタイルになっています。
――岸本さんはいかがですか?
岸本私は10年以上ソニックのメインストリームタイトルのディレクターを担当しているので、ソニックファンに応えるゲームを作るのには自信があります。
ただ、今作ではソニックファンではない方にも遊んでいただきたかった。そのために、いろいろな工夫をしているので、そこは注目してほしいです。
――それはどういったところですか?
岸本わかりやすいところですと、ストーリー展開があります。従来のステージクリアー型のゲームですと、勧善懲悪なお話が採用されることが多いですが、本作では、物哀しさのあるシリアスなストーリーが展開されます。
また、ゲームがスタートした直後に、難易度が選べます。そして、ふたつの操作タイプも用意しています。ひとつは、従来のソニックゲームのような、疾走感を強く感じられる“ハイスピードスタイル”。もうひとつは、ソニックゲームに慣れていない、王道なアクションゲームで育ってきた方たちのための“アクションスタイル”です。
これらさまざまな要素を用意して、ソニックらしさはありつつも、ソニックを知らない方も楽しめるようなポイントを作っているので、ぜひ手に取って遊んでほしいです。
――ソニックの映画などを通じて、ソニックのファンになった方も手に取りやすいかもしれませんね。
飯塚まさに、そこを狙っています。この5年間でソニックを取り巻く環境が劇的に変わっているんです。映画のほかに、この冬にはNetflixでアニメもスタートしますし。ゲーム以外のメディアから入ってくるお客さんがすごく増えている。そういった方たちのために、間口の広いゲームを心掛けています。
――ちなみに、物哀しいストーリーというのは、ソニックらしさとは異なると思うのですが、そこはあえてそうしたのですか?
岸本そうですね。ターゲット層を上げるという意図のもと、シリアスな物語にしています。少年よりは、青年以上の方に刺さる、グッとくるストーリーを狙っています。ほかのアクションゲームと差別化をするという意味でも、そのような物語となっています。
飯塚やはり、ソニックらしさ100%の作品だと、ソニックファンしか遊んでくれないんですよね。あえてソニックらしくない要素を入れないと、ソニックファン以外のお客さんが興味を示さない。そういった意味で、フォトリアルなグラフィックやシリアスなストーリーなどで、通常のソニックタイトルとはコンセプトを変えています。
――“ソニックらしさ”と“らしくなさ”のバランスを大切にされているとのことですが、海外に向けて、あるいは日本に向けて、といった、特定の地域をターゲットにしたゲームにはなっていない?
岸本基本的には、どの地域の方も楽しめるように作っています。ただ、これまでのソニックゲームは、欧米では大変多くの方に支持していただけていましたが、日本の方には海外ほどではないようにも感じています。
しかしそれは、まだまだ伸びしろがあることだとも思うんです。ですので、日本のゲームファンに響くような仕掛けも存在しています。たとえば、日本の方々といえば、マンガやアニメ、特撮作品などに慣れ親しまれていると思いますので、今回はシリアスで奥深い、考察しがいのある世界観をご用意しています。
飯塚本作では、すでにお気づきかもしれませんが、日本やアジアと、アメリカやヨーロッパとで、キービジュアルが異なっています。そうして、どちらのゲームファンにも響くようなプロモーションも行っているんです。
欧米ですと、ソニックといえばアクションのキャラクターなので、アクション性がビジュアルからも伝わるような画となっています。逆に日本やアジア向けのものは、もっとしっとりとした、ストーリー性が感じられる画にしています。
“ONE OK ROCK”の歌う『Vandalize』は、物悲しいメロディーの中に、ソニックの疾走感を感じさせる、アップテンポな楽曲
――双方のファンに寄り添ったプロモーションになっているのですね。ところで本作のエンディングテーマにはONE OK ROCKの楽曲が選ばれていますが、起用の経緯も伺えればと思います。
飯塚最重要視したのは、「『ソニックフロンティア』の世界観に合ったアーティストさんであり、楽曲であること」でした。「どんな著名なアーティストでも、ゲームに合わないなら選ばない」くらいの考えだったのですが、ONE OK ROCKさんのエンディングテーマ『Vandalize』は、日本はもちろん、欧米のファンからもソニックらしいと感じてもらえる楽曲になっていたんです。それならばぜひ! ということで、ONE OK ROCKさんに決めました。
一方、テーマソングはソニックシリーズの音楽を担当している大谷智哉がいままで通り担当しました。これまでのソニックタイトルでは、とにかく明るくて楽しい、ハッピーな気持ちになれる、勢いのあるテーマソングを作ってきましたが、今回はシリアスなストーリーや舞台に合わせて、物悲しいメロディーで入って、ところどころ盛り上がっていくという曲になっています。
ソニックフロンティア』エンディングテーマ ONE OK ROCK「Vandalize」PV(Short Ver.)
――それでは最後に、本作を楽しみにしているゲームファンにメッセージをお願いします。
岸本本作は、ソニックファンの皆さんにとっては、次世代のソニックゲームとして楽しめものになっているので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。一方、これまでソニックゲームに触れてこなかったユーザーの方々には、最先端のおもしろさを味わっていただけると思いますので、ぜひお手に取ってプレイしていただけら幸いです。
飯塚我々ソニックチームが5年の歳月をかけて築き上げた次世代のソニックタイトル『ソニックフロンティア』が、11月8日にいよいよ発売となります。バトルや謎解きのほか、通常のソニックではなかったようなアプローチも満載ですので、ソニックゲームを遊んだことのない方にもぜひ遊んでいただきたいですし、本作を通じてソニックを好きになってくれたらうれしいです。