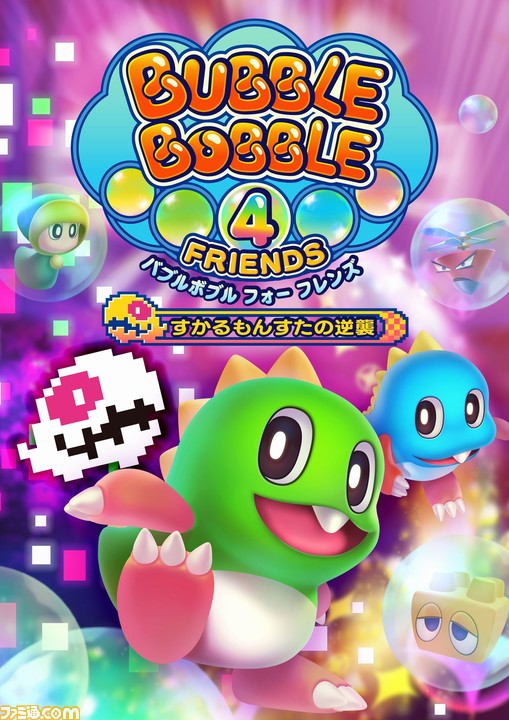2020年11月19日、タイトーからプレイステーション4版『バブルボブル 4 フレンズ すかるもんすたの逆襲』が発売日を迎え、同日にはNintendo Switch版『バブルボブル 4 フレンズ』も無料大型アップデートが行われた。それを記念して、本作のサウンド担当のおふたりと、戸崎ディレクターを交えての鼎談を行った。
石川勝久氏(タイトー ZUNTATA)
『バブルボブル 4 フレンズ』サウンドディレクター・効果音クリエイター
瓜田幸治氏
『バブルボブル 4 フレンズ』音楽担当
戸崎剛志氏(タイトー)
『バブルボブル 4 フレンズ』ディレクター
「いわゆるチップチューンサウンドにはしたくなかった」
――まずは、皆様それぞれ、本作の制作にはどのような形で携わっていたのか教えてください。
戸崎ディレクターとして開発現場を束ねていました。また、ゲーム全般のデザインとレベルデザインを少々、あとは雑用を担当していました(笑)。
石川サウンドディレクターと効果音をやらせていただきました。
瓜田音楽を担当させていただきました。
――瓜田さんは元ZUNTATAですよね?
瓜田はい。現在はフリーでお仕事させていただいています。
――発売日も迎え、サウンドチームの作業はもう落ち着いていますか?
石川じつはサウンドの作業は、半年以上前に終わっているんですよ。
瓜田コロナ自粛の前ですよね。
――ということは、Nintendo Switch版の『バブルボブル 4 フレンズ』が発売してすぐ?
石川そうですね。『バブルボブル 4 フレンズ』が出るころには、『すかるもんすたの逆襲』のプロジェクトが動き始めていまして、すぐ瓜田さんに連絡しました。サウンドがかなり先行していたわけです。
――今回はサウンドのインタビューということで、本作のサウンドの特徴をお聞かせください。
石川『バブルボブル 4 フレンズ』のサウンドは、初代『バブルボブル』のよさを活かしつつ拡張していくことをコンセプトとしています。
具体的に言うと、オリジナル版のサウンドをフィーチャーしつつも、レトロゲームな感じを強調したいわけではないので、いわゆるチップチューン(※)サウンドにはしないでおこうと、今回瓜田さんにお願いしました。
※チップチューン……昔の家庭用ゲーム機などに内蔵されていたような、制限のある音源チップや音源仕様で制作される音楽のこと。
チップチューンのような制限を設けずにFM音源を使って自由に曲作りをしてもらうというのも、今回のコンセプトのひとつです。そもそも、『バブルボブル 4 フレンズ』というゲーム自体が、新システムを前面に出した作品ではなく、オリジナルの『バブルボブル』のいいところを拡張した作りなので、サウンドもそれに倣う形です。
――ゲームに合わせたサウンド作り……まさにゲーム音楽ですね。
石川そんなコンセプトですが、瓜田さんにはメインテーマについて、ある注文をしました。
瓜田オリジナル版メインテーマのアイデンティティーでもある、ベルの音色ですね。
石川そうなんです。メロディー部分をこのベルを使ってこその『バブルボブル』だと。それだけは守ってほしいと、瓜田さんにオファーしたわけです。
瓜田オリジナル版が稼動していた当時を思い返しても、騒がしいゲームセンター内であのベルの音色とメロディーは耳に届いてきて、記憶に残っているんですよね。しかも、くり返し聴いても飽きない。
石川少しマニアックな話になってきますが、オリジナル版はFM音源チップに、初期ロットでは2オペレーターのYM3526(※)、以降はYM3812(※)を使用していました。
※YM3526、YM3812……いずれも日本楽器製造(現:ヤマハ)が開発したFM音源チップ
瓜田3526から3812へ載せ換えたんですよね。
石川じつは基板そのものには4オペのYM2203も載っているのですが、なぜか曲ではほとんど使われていないという(笑)。それはともかくとして、今回瓜田さんと相談して決めたのは、OPZ(YM2414)のサウンドを使うということです。
瓜田そうですね。OPZ II(YM2424)も含めOPZ系中心です。今回はどちらかというとOPZ IIがメインです。個人的にもいちばん思い入れがある4オペレーターのFM音源チップです。
石川本作はオリジナルよりもかなり見た目もリッチになってきているため、オリジナルと同じ2オペレーターのFM音源でやるのはさすがにチープな印象が出てしまうと思いました。そこで多用することになったのが、OPZ系と呼ばれる後期FM音源チップです。
瓜田皆さんが80年代中盤から90年代中盤にかけてゲームセンターでよく耳にしていた、OPM系(YM2151)などのほぼ後方互換にあたるチップですね。ヤマハのシンセサイザーが好きな方はご存じかと思います。
オリジナル版の1986年当時、YM3526からYM3812に載せ換えたがあったのと同じく、OPM/OPN系が主音源として基板に搭載され続けた世界線上で、もしもヤマハがタイトーにOPZ系を提供してくれてたら……。そんな世界線にある『バブルボブル』の続編はこんな音になったんじゃないか……という僕の妄想やロマンを『4 フレンズ』に詰め込みました。
当時のローファイではないハイレイトなPCMの使用(あまり前面には出ないようにしていますが)やエフェクトも含めたミックスの処理などによりサウンド全体としては現代的ではありますが、それがあたかも90年代に存在したアーケードゲーム作品のサウンドとして聞こえてくる様な感覚があると思います。
――ああ、確かにゲーセンで聴こえてきそうですね。
石川リズムやコーラスはPCMで、ほかの楽器音は基本的にOPZのサウンドで。今回、いちばんお話ししたかったのが、この部分です。
――チップチューンは目指さない、昔OPL(YM3526、YM3812)でやっていたベルの音を使いたかった、今回はOPZをフィーチャーしている、ということですね。
瓜田マニアックな話なので、どこまで読者の方に届いているのかわかりませんが(苦笑)、僕たちふたりのあいだでは共通のコンセプトでした。
ちなみに僕は当時のゲームセンターで『バブルボブル』にハマったクチなので、ZUNTATAに在籍していたときに前作『バブルメモリーズ』(※)の開発を羨望の眼差しでチラ見しつつ、いつか続編を担当できる日を心待ちにしていたのですが結局夢叶わず(苦笑)。
※『バブルメモリーズ』……『バブルボブル』シリーズのナンバリング3作目にあたるタイトル。1996年稼動。
石川でも、『パズルボブル3』は担当していたよね。
※『パズルボブル3』……泡を発射して色を揃えるパズルゲームの3作目。こちらも1996年稼動。
アーケードゲームを意識した曲作り
――それから四半世紀近くが経過したいま、長年の念願かなってナンバリング作品の楽曲を担当することになったと。石川さんから瓜田さんへのオファーは、すぐ決まったことなのでしょうか?
石川瓜田さんとはZUNTATA在籍時代からの長い付き合いで、FM音源に精通していることは知っていました。タイトーの前はマイクロキャビンで『サークIII』や『幻影都市』などで、FM音源での音作りをしていましたし。
さらにゲーム音楽以外でも、楽器メーカーのサウンドデザイナーとして活躍した経験もあるため、シンセに非常に詳しいんです。
あと、瓜田さんが作るメロディーがすごくいい。『バトルギア』(※)や『パズルボブル3』などもそうでしたが、メロディー部分がハッキリとした、いわばゲームミュージックマインドのある曲を作ってくれるんです。
※『バトルギア』……タイトーの大型化筐体のレースゲーム。1999年稼動。
瓜田ありがとうございます。
石川そして、ここまでにお話したコンセプトを長々と説明しなくても、瓜田さんならわかってくれると思って(笑)。
――(笑)。ところで、ディレクターからサウンドに対して注文はあったのですか?
戸崎とくに曲風をこうしてほしい、というのはなかったですね。石川さんに設定をお伝えし、あとはお任せと言った感じです。私よりも『バブルボブル』を熟知されていますので、事細かく指示はしませんでした。
ゲーム音楽ですから、「ここはこのくらいの尺で」というくらいでしょうか。あと、イントロを入れるとか。
瓜田『バブルボブル 4 フレンズ』の曲は全エリア必ずイントロ付きで始まるんですよね。ここでほぼ楽曲のテンポが決まるので、そこは気を付けました。
――サウンドチームから上がってきた曲を聴いたときの印象はいかがでしたか?
戸崎『バブルボブル』らしさや、舞台となる子ども部屋に合った、かわいらしい曲だと思いました。“ベッドミュージアム”や“てんじょうギャラクシー”など、エリアごとにテーマが決まっているので、それぞれの曲がイメージにピッタリ一致している感じで。
石川そうなんですよ。単にいい曲、というのではなく、ちゃんとゲームに合っているものに仕上げてくれる。“てんじょうギャラクシー”の曲も、しっかり宇宙っぽさが出ているんですよね。
――確かに! “てんじょうギャラクシー”は後半のエリアなので、曲の盛り上がりもいい感じにマッチしていますね。本作は家庭用ゲームだけど、曲の盛り上げかたがアーケードゲームっぽいというか。ゲーセンの筐体でプレイしたくなりました。
瓜田アーケードらしさに関しては、僕自身に染みついている部分があるのかもしれません。エリア1はメインテーマのアレンジで強調して、エリア2は少し落ち着かせて、エリア3~4で徐々にテンションを高めていく。そして最終エリアではエモいのが来るように。
石川個人的には、ベッドミュージアムのイントロがお気に入り。おもちゃっぽさがあって。
瓜田あそこには、カシオから1985年に発売された、SK-1というサンプリングキーボードの音を使いました。これも『バブルボブル』同様に発売当時から個人的にとても思い入れがあり、付き合いの長い楽器です。本作におけるサウンドの要のひとつですね。
――細かいところにこだわりがあるのですね。
瓜田じつは、各ステージの曲には、歴代のタイトーのゲームミュージックの曲へのオマージュも、ほんの少しずつ隠れているんです。
石川そうなの? 気づかなかった。
瓜田言われないとわからないレベルですが、たとえば“てんじょうギャラクシー”の曲は『レイフォース』(※)を意識していたり、“ベッドミュージアム”では小倉さん(※)がよく使うベースラインに近づけています。
※『レイフォース』……“ロックオンレーザー”が斬新な、タイトーの縦スクロールシューティング。1994年稼動。
※小倉さん……元ZUNTATAのOGR氏。現:小倉久佳音画制作所。
石川『ダライアス』の『CAPTAIN NEO』でも使っていたベースラインか。確かに言われてみれば!
瓜田細かくしすぎて誰にも伝わらないレベルですが(笑)。
――ちなみに、本作でとくにお気に入りの曲はどれでしょうか?
石川どらんくキャッスルの曲は全人類に聴いていただきたいです。とてもとてもエモい曲になっていますので!
戸崎この曲は、開発チームでもかなり好評でしたね。
瓜田ありがとうございます。アーケードゲームの終盤ステージというイメージで作りました。
――確かに、クライマックスで盛り上がっている感じがすごいですね。
瓜田ZUNTATAに在籍していた時代から、「自分が『バブルボブル』の曲を作るなら、最終面はこんな感じにしたい」と思っていたのを実現できました。
この曲を通して、ゲームセンターで『バブルボブル』を遊んで楽しかった当時の思い出やオリジナル含めシリーズへのリスペクト、そして新たに生まれた続編の喜びを皆さんと共有できたらな……という想いを込めました。ぜひ皆さん聴いてみてください。
新モード“みらいアーケード”の曲はチップチューンに
――みらいアーケード(すかるもんすたの逆襲)は、本編とはまた違うテイストの曲に聴こえます。こちらはどんなコンセプトで作成されたのでしょうか?
石川いままでお話しした内容を翻すようですが、すかるもんすたの逆襲の音楽に関しては、完全にチップチューンを目指しています。
――こちらは素直にチップチューンなのですね。
石川タイトルがドット絵になっていたり、すかるもんすたもドット絵のまま出てきたりと、レトロゲームテイストなので、チップチューンが合うかと。ということで、今回はOPL縛りです。
瓜田とはいえ、『バブルボブル 4 フレンズ』の世界に含まれるコンテンツですので、本編の質感からは大きく乖離しないようにはしました。YM3812に沿う挙動をOPZ IIで……“挙動制限”というべきでしょうか。こういった制限を自分に課して作っていきました。
――こちらはこちらで縛りがあるので、苦労も多そうですね。
瓜田当初、音そのものをサンプリングしてしまったほうがよいのではとも思ったのですが、Y8950(※)搭載機で直接弾いてそのまま収録してしまった曲もあります。
ただ、いま持てる限りの技術を使って音源を全力で音を鳴らしすぎてしまうと、なんとも不思議な違和感が出てしまうので、その“さじ加減”でとても苦労しました。
※Y8950……1986年に発売されたFM音源ユニット“MSX-AUDIO”に使われていたFM音源チップ。
石川全力でやるとリッチになりすぎてしまうんですよね。今回のアレンジに関してはチップチューンぽく聴かせたかったので、少し不自由な感じも出してもらいました。本編の曲がリッチなので、差をつけたかったという狙いもあります。
瓜田現代なら音色を切り換えなくてもいいところを、がんばって切り換えている風を演出したりと、まわりくどい苦労はありました。内なるさまざまなジレンマとの戦いです(笑)。
――“みらいアーケード”は本編の表ステージをクリアー後に遊べるモードですよね。プレイヤーの耳が本編の曲に染まってきたあたりで、“すかるもんすたの逆襲”のチップチューンな感じを楽しめるわけですね。
戸崎そうですね。プレイに慣れて腕が上がってきたところで“すかるもんすたの逆襲”の曲を聴くと、プレイヤーは新たな難しさを予感できると思います。
効果音にも石川氏のこだわりが!
――効果音についてもお聞きします。本作の効果音は作品にあった心地よさのようなものが感じられます。こちらも何か工夫が?
石川最初はオリジナル版のSEをメインで使う案もあったんですよ。でも、最終的にはオリジナル版の音は1割くらいしか使っておらず、9割は新たに作っています。ただ、音自体はFM音源やPSGで作り、オリジナルのテイストに近づけました。
『バブルシンフォニー』や『バブルメモリーズ』のときも僕が効果音を作ったのですが、音源がエンソニック(※)だったというのもあり、実音に近い音をたくさん使っていたんですよ。
※エンソニック……アメリカの楽器メーカー。当時のF3システム基板(タイトーのマザーボード)にはこちらのサウンドチップが搭載されていた。
――今回はシンプルな効果音でいこうと。
瓜田さすが石川さんというか、本作は音の“立ち具合”がいいですね。「ゲームの音って、こういうのが絶対に気持ちいいよね」というベストポイントを突きまくっている感じです。
本作を遊びながら、「じつは昔こういうアーケードゲームが実際にあって、いま自分が遊んでいるのはそれの復刻版なのではないか?」とすら思わせられました。
石川ただ、苦労したところもありました。オリジナル版は、キャラクターがアクションするときのドット絵のアニメーションは一定なため効果音を合わせやすいですが、本作は3Dで描写されているのにともない、動きもなめらかです。そのため、ジャンプや着地などの効果音を違和感なく調整するのが難しかったです。
――現代だからこその苦労があるわけですね。オリジナル版になかった要素といえば、キャラクターの音声(?)などもありますね。
石川最初、プロジェクト内では「音声は入れなくてもいいんじゃないか?」という意見もありまして、悩みました。ただ、動きが豊かなボスができてくると、何もしゃべらないのも寂しいかなと。
それと、『パズルボブル2』や『バブルシンフォニー』以降のタイトルでは、キャラクターがけっこうしゃべっているんですよね。今回もバブルンの「ぱよんぱ~!」といった声などは、過去作品を踏襲していますね。
ただ、新たなボスキャラクターなどは、性別の設定がなかったりするので、どんな声にするか、いろいろと迷いました(苦笑)。
瓜田戸崎さんはどう感じられました?
戸崎性別が曖昧なキャラクターは、見た目も中性的なものが多いので、上がってきた音声を聴いても違和感はありませんでした。ちなみに、音声と言っても日本語や英語をしゃべっているわけではないんですよね。
石川言葉がないからこそ、個性付けが難しかったですね。力強い音声や、なよなよした感じの音声など、そのキャラクターの特徴を強めに出していました。
――そういえば当時、『パズルボブル2』で音声がついたときのインパクトがすごかったのを思い出しました。
戸崎そのときは、ちょっとドキドキしましたね。こいつらしゃべるんだ、って。
石川何気に、当時は声優さんを使っていなくて、タイトー社員とZUNTATAメンバーが総出だったんですよね。僕もやったし、小倉さんもやっていました。
戸崎石川さんは“もんすた”でしたっけ?
石川やってた気がする。
――小倉さんもやっていたというのは驚きです。最後に、ひと言ずつメッセージをお願いします。
戸崎シリーズ初めてプレイする方も、昔『バブルボブル』に触れられた方も楽しめるように、遊びやすさと懐かしさの両面のバランスを念入りに調整しました。
また、最大4人のマルチプレイでは助け合いのおもしろさもありますので、お友だちやご家族といっしょにワイワイ遊んでいただければ幸いです。
瓜田ひとりの『バブルボブル』ファンとしてシリーズに関われたことが光栄です。また、本編と“すかるもんすたの逆襲”の音楽を通して、このシリーズへの愛情とオリジナルへのリスペクトを僕なりにではありますが出すことができて、とても幸せでした。
ゲームセンターの扉を開けたときに聞こえてきたあのベルのメロディー、テレビの前で握りしめたコントローラーの感覚……それぞれの思い出とともに、この新たに生まれた続編を、ちょっとした時間にでもゆる~くふわふわと遊んでいただければうれしいです。
石川『バブルボブル 4 フレンズ』は、オリジナル版の『バブルボブル』も収録していますので、操作感と併せて、サウンドの違いを比較するつもりで両タイトルをプレイすると、新たなおもしろさが感じられると思います。
さらに、“すかるもんすたの逆襲”では、どちらとも違う、ちょっとひねったFMサウンドになっています。それぞれのサウンドの違いがわかるようになったら、皆さんは立派な『バブルボブル』マニアです!