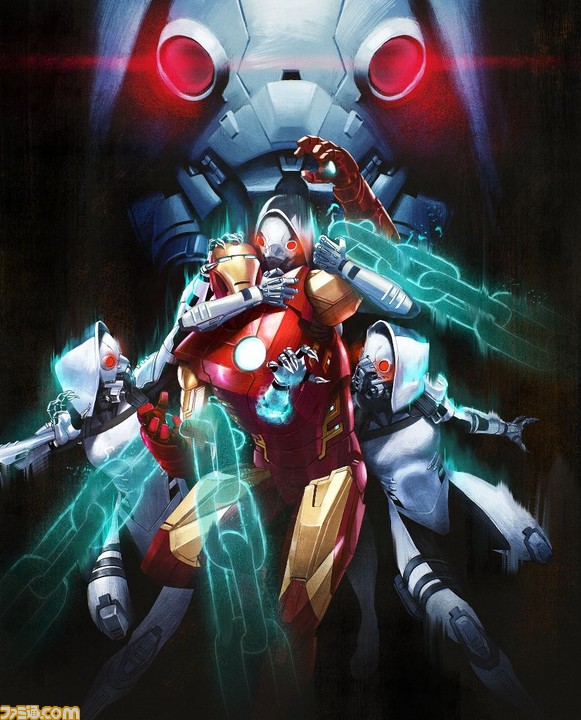2020年7月3日にソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)から発売されたプレイステーション4(プレイステーション VR専用)向けのソフト、『マーベルアイアンマン VR』。
編集部では本作の開発で陣頭指揮を執った“カモフラージュ(Camouflaj)”社のディレクター、ライアン・ペイトン(Ryan Payton)氏にインタビューを行う機会を得た。
ライアン氏がどのような想いを持って、本作を作っていったか。多くのプレイヤーが驚愕した“アイアンマン”になれるというVR体験は、いかにして生まれたのか。そのすべてがわかるテキストとなっている。
Ryan Payton(ライアン・ペイトン)氏
Camouflajディレクター。コジマプロダクションで『メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』に携わった後、Camouflajを創業。ほかに手掛けた作品は『Halo 4』、『Republique』など。自身のKickstarterでの創業経験をもとに『シェンムーIII』へのアドバイスも行った。
遊びの要素とチュートリアルのバランスが難しかった
――まずは、アイアンマンをPS VRでゲーム化することになった経緯を教えてください。
ライアン2016年にマーベルから我々に連絡があり、ヒーローのひとりをモチーフとした大規模で革新的なVR専用ゲームを開発することについて持ち掛けられました。これは秘密にしていたことなのですが、当時はほかのプロジェクトで忙しかったため、私は最初「No」と答えたのです。
――そうだったのですか!?
ライアンはい。ですが、その後にチームメンバーとマーベルの申し出について話し合う機会があり、すぐに大きな間違いを犯したと気づきました。なぜなら彼らに「もしも、マーベルがアイアンマンを題材としたVRゲームの開発を許可してくれるのであれば、それはまさに我々にとってのドリームプロジェクトになる」と諭されたからです。
――オファーの時点では、どのヒーローになるかは決まっていなかったのですね。
ライアンそうです。言われてみれば、アイアンマンはVRと組み合わせるのに最適なヒーローのひとりでした。PS VRのヘッドセットはアイアンマンの3次元ヘッドアップディスプレイ(HUD)を、PS Moveモーションコントローラはアイアンマンのリパルサーレイやパンチを再現することができます。また、もっとも重要なアイアンマンのスラスター(推進装置。ここではリパルサー・ジェットを指す)も、PS Moveのトリガーを使うことでまったく同じように機能してくれますから。
――実際に遊んでみると、見事に再現されていました。それはプレイヤーの評価を見ても明らかです。では、考えを改めてからすぐに開発がスタートしたのですか?
ライアンいいえ。チームミーティングのあと、すぐに私はロサンゼルスに飛び、マーベル・ゲームズ(Marvel Games)のヘッドであるジェイ・オン(Jay Ong)氏に「アイアンマンを主役とした大掛かりなVR専用ゲームを開発させてほしい」とお願いしました。ですが、今度は彼が「No」という番でした。アイアンマンという、世界でもっとも人気のあるヒーローをフィーチャーした巨大プロジェクトを一手に引き受けるには、我々のスタジオが十分な大きさではない、と。
――うまくいかないものですね。
ライアンしかし、私たちはあきらめませんでした。チームメンバーが、すばらしいクオリティーのプロトタイプやオリジナルのストーリー案、映像を作ってくれたのです。ありがたいことに、それを披露した会議の最後にジェイ氏は私の手を握り、「すばらしいだけでなく、プレイヤーの心に響くようなゲームを作るべく、徹底的に追求するように」と言ってくれました。私は彼に「もちろんそうする」と約束しました。その後の経緯はご存じの通りです。
――ちなみに、当初のスタジオの規模感はどの程度だったのでしょうか?
ライアン2016年の8月に最初のプロトタイプを完成させたのですが、そのときのCamouflajには約30人の従業員がいました。ところが、約4年の開発期間を経て、ゲームの核となる部分の開発が落ち着いたときに周りを見渡してみると、Camouflajの規模が倍以上になっているときに気づきました。「ほかのVRタイトルと比べても大規模なゲームを作る」という私たちの野望を考えれば増員は当然なのですが、ここまでチームが大きくなったことに深い感慨を覚えますね。
――開発時、世界的なヒーローであるアイアンマンをゲームにするというプレッシャーは感じていましたか?
ライアンCamouflajの最初のゲームは『RÉPUBLIQUE』という、当初はスマートフォン向けとして作られたゲームでした。30人規模のスタジオの最初のプロジェクトとしては野心的でしたね。そんな経緯もあってか、多くの人は私たちが小規模のインディーズであり続けたいのだと勘違いしていました。しかし実際はまったく逆で、2011年にこの会社を設立したとき、私はCamouflajを世界レベルの独立系AAAデベロッパーのひとつにするという目標を持っていたのです。
ライアンですので、アイアンマンを主役にした大作VRゲームを開発する機会が訪れたとき、プレッシャーを感じるというよりも、私のAAA級の同僚たちが手掛けるべきサイズのプロジェクトであると感じました。
――なるほど。
ライアン本作の発売にあたって、SIEと協力できたことをうれしく思っています。PS VR専用タイトルとして開発することはチームが当初から望んでいたことでしたし、PSブランド、そしてPS VRの多くのユーザーと本作を結びつけることは自然な流れだと感じました。
――ところで、VRゲームの最大の魅力は没入感だと思いますが、本作でそれを損なわないように工夫した点はありますか?
ライアンアイアンマンとしてVRで飛んだり、武器を使ったりすることは、ほとんどの人にとってゲームで初めて触れる体験ですから、慣れるまでに少し時間がかかることが多いでしょう。それはまるで、映画『アイアンマン』の1作目でトニー・スタークが初めて空を飛ぶシーンのようなもので。
――コミカルないいシーンですよね(笑)。
ライアン一方で、いかにしてプレイヤーに負担をかけずに、新しいメカニクスを素早く学んでもらうかという部分はチームにとって大きなチャレンジになりました。プレイヤーからしてみれば、PS VRを装着してすぐに、アイアンマンのアーマーで飛んだり、リパルサーレイを撃つ体験をしたいこともわかっていましたから。
――確かに、操作が難し過ぎても困ります。
ライアンですから、ゲームの最初の1時間においての、遊びの要素とチュートリアルの絶妙なバランスを取るのが非常に難しかったです。このバランス取りがうまくいったことで、8時間から10時間程度のゲームプレイを通じて、多くの新機能を少しずつ導入していくという、つぎのチャレンジに向けての準備ができました。本作は新しい敵や環境、追加のゲームメカニックやアクション、アーマーのカスタマイズ方法などを少しずつ導入していく形をとっています。そういった手法も、プレイヤーの皆さんの負担にならないよう注意しつつ、ゲームを進めるごとに新しいエキサイティングなアイアンマンの楽しみかたを提供できるように工夫した結果なのです。
――システム面でもうひとつ伺いたいのですが、本作はよくあるフライトシューティングではなく、サンドボックス的なフィールドを飛び回れる自由度の高い作品になっています。こうしたシステムを採用した理由はどこにあるのでしょう?
ライアン本作の醍醐味は、プレイヤーが自由に飛べる開放的な環境の中で、アイアンマンになって空を飛んでいるようなスリリングな感覚を味わえることです。これは、最初のプロトタイプを作ったときから実現できると確信していました。ただ、“非常に高速な飛行をする体験”をVRでは快適にプレイできないのではないかという心配はありました。しかし、トニー・スターク本人と同じように、私たちはその後に何年もかけてフライトコントロールを完璧なものにするために、微調整と修正を重ねたのです。ファンの皆様の反応を見るかぎり、快適にプレイしてくださっているようで、喜ばしく思っています。
――爽快感はもちろんありますし、VR作品のなかでは比較的酔いにくいという評もあるようですから、その調整はうまくいていると感じます。
ライアン当初予想していなかった困難があったとすれば、「本作がレールの敷かれたタイプの作品ではないことを、しっかりと皆さんに伝えなければならない」ということでした。そんな想いもあって、アイアンマンとして空を飛ぶスリルを皆さんにいち早く体験していただくべく、2020年5月に無料体験版を公開しました。この体験版のおかげで、本作のスピード感や開放感、そしてそんなアイアンマン体験が快適できることを人々に説明する必要はなくなりましたね(笑)。
“マーベルらしさ”を最大限感じられるようにしたかった
――本作は、細部の作り込みもかなりのもので、マーベル愛に溢れていると感じます。相当な労力がかかったと思うのですが、なぜそこまでやりきれたのでしょう?
ライアン飛行や戦闘、立体的なHUDなど、アイアンマンならではのゲーム性についてはたくさんお話ししてきましたが、じつは開発で非常に多くの時間を費やしたのは、トニー・スタークとしてプレイする際のストーリー部分です。マーベル作品のすばらしいところのひとつとして、多くの人々が共感できる私的なストーリーが、全体の物語と対になっていることが挙げられます。そして、トニー・スタークが魅力的なキャラクターである理由のひとつは、そこにあると考えていました。傲慢で天才的な発明家であり、億万長者であるにも関わらず、私たちと同じ内面的な問題を抱えている。だからこそ、信じられないほど親近感が湧くのです。
――確かにそうですね。
ライアンそのため、アイアンマンのアーマーを身にまとうだけでなく、トニー・スタークの身になって……とくに物語の中で彼が直面するであろう困難において、PS VRの力を活用してプレイヤーがトニーの気持ちを感じることができるようにする工夫が重要だと考えました。
――徹底的にトニーになりきらせるために、細部まで作り込んだわけですね。
ライアンそのために、大規模なアクションミッションの合間に、プレイヤーがトニー・スタークになりきれるインタラクティブな映像を用意しました。これにより、プレイヤーはトニーとして彼の邸宅や、巨大なS.H.I.E.L.Dのヘリキャリアなど、マーベル作品でおなじみの舞台を探索したり、さまざまなアイテムに触れたり、つぎのミッションを決める前にひと息つくことができるようになっています。
――そういった部分は、アイアンマンのファンにも好評です。
ライアンまた、チームは『バイオハザード7 レジデント イービル』をVRでプレイしたときのキャラクターの没入感に非常に刺激を受けており、ペッパー・ポッツやフライデー、ニック・フューリーなどのキャラクターとプレイヤーが直接対話するストーリーの重要な場面を数多く用意しました。これだけのトニー・スタークになりきれる瞬間を細かなディテールで描ききったチームの力をとても誇りに思いますし、そのおかげでプレイヤーの皆さんは本作の世界に入り、自分自身がトニー・スタークなんだと信じられるようなものに仕上がっていると思います。
――見事に仕上がっています! 続いては、本作の物語やそれを生み出すまでの苦労など、言える範囲で教えてください。
ライアン本作では、Camouflajのリードライターであるブレンダン・マーフィー(Brendan Murphy)によって執筆されたオリジナルのストーリーが展開します。彼はマーベル・ゲームズのビル・ローズマン(Bill Rosemann)氏から多くのすばらしいアドバイスを受け、『アイアンマン』のクラシックなストーリーにひねりを加えて、「トニー・スターク自身が自分の最大の敵である」という物語を作ることになりました。また、ブレンダンはこの作品がVRゲームであることを踏まえ、ほかのメディアでは実現不可能なストーリーを考えてくれました。そして開発の後半には、マーベルのベテランライターであるクリストス・ゲイジ(Christos Gage)氏が参加し、本作の脚本がマーベルの世界により忠実なものとなるよう、マーベル流のジョークやコミック版の要素を散りばめてくれたのです。
――いい協力関係ですね。
ライアンまた、本作はコミック版や映画版とは直接リンクしない、オリジナルのストーリーです。アイアンマンは世界中で圧倒的な人気を誇るキャラクターであり、彼の生い立ちのストーリーについては数え切れないほどの人々が知るところです。そこで、マーベルは私たちにトニー・スタークがアイアンマンとしてのキャリアを歩み始めてから数年後の物語を描くよう勧めてくれました。これはすばらしいアドバイスだったと思っています。
――確かにそうですね。加えて、ヴィランがアイアンマンの宿敵であるゴーストだというところも、ファンからすればアツい部分です。
ライアン私たちは「トニー自身が最大の敵である」というストーリー……つまり、トニーが武器商人だったころに作って売った凶悪な武器の数々を、敵として戦う物語を描きたいと思っていました。しかし、メインのヴィランを誰にするのか……という問題は解決せずにいたのです。そこでマーベルのビル・ローズマン氏や彼の同僚たちに「トニーの古い武器をハッキングで復活させ、それらを使ってトニーを攻撃しそうなヴィランは誰だろう?」と聞きました。「トニーが過去に犯した罪を受けて、トニーに“取り憑く”としたら誰だろうか?」と。すると、彼らは顔を見合わせた後、声を揃えて「ゴーストだ!」と言ったんです。まるでコメディードラマのようでしたね(笑)。
――その光景が目に浮かぶようです(笑)。
ライアンそこからマーベルと協力しながらゴーストに独自のひねりを加え、コミック版では男性であったゴーストを女性として描き、彼女の自己破壊的な性格を強調しました。私自身も過去の過ちを忘れることに苦労した経験があるので、ゴーストの物語を通してこの普遍的なテーマを探求できたことを、とてもうれしく思っています。また、プレイヤーの皆さんの心に響くことを願っています。
――オリジナルでありながら、原作のテイストは大切にしているのですね。
ライアンその通りです。このプロジェクトの目標のひとつは、本作を通じて“マーベルらしさ”を最大限感じられるようにすることでした。開発初年度に、私たちのチームは何百ものコミック版『アイアンマン』を読んで、触発されたアイデアを作品に入れる方法を議論しました。ですから、筋金入りのファンだけが気付けるような楽しいイースターエッグ(隠し要素)も多数仕掛けてあります(笑)。
――楽しみです! すべてに気付けるかどうかはわかりませんが……。
ライアンまた、プレイヤーをトニー・スタークの一人称視点に立たせながらも、賢く、おもしろく、皮肉屋であるトニーの個性をプレイヤーに“見せる”ことも重要なミッションでした。ブレンダンと私は約1ヵ月間、「どうすればプレイヤーがトニー・スタークになるだけでなく、彼を見ることができるか」を考えました。ゲームを最後まで遊んでいただければ、この問題を解決するためのブレンダンのスマートなアイデアを見られると思います!
――期待しています。続いて伺いたいのは、本作ならではのアイアンマンのデザインについてです。本作のアーマーはマーベル作品のアートを数多く手掛けているアディ・グラノフ(Adi Granov)氏によるオリジナルデザインの“インパルスアーマー”ですが、これはどのような経緯で制作されたのでしょう?
ライアンプロジェクトの立ち上げ当初から、本作には専用のアーマーが必要であるとチームの誰もが感じていました。しかし、インパルスアーマーを作るのは予想以上に大変な作業でした。開発の初年度は、私や私の同僚たちはかなり独創性の強いものを求めていたと言っても過言ではないでしょう。そのため、マーベルの承認がなかなか得られなかったのです。紆余曲折あって、マーベルは「アディ氏に私たちのデザインを見てもらうのはどうか」と提案してくれました。これはすばらしいアイデアでしたね! 結果的にゲーム内のほかの多くの要素についてもアディ氏と密接に協力することになりました。
――それはとても頼もしいですね。
ライアンええ! そうしてアディ氏の協力を仰ぎながら開発が進行するつれ、Camouflajは「マーベルがいかにしてすぐれた作品を作っているのか」という要素を取り込めたと思います。それにより、マーベルの承認時間は徐々に短縮され、彼らの信頼を得ていると感じることができました。いまでは、完全に共生関係にあると感じています。それは、トニー・スタークとアイアンマンのアーマーのように(笑)。 また、マーベルのおかげでCamouflajがはるかに強固なスタジオに成長したとも思っています。
――そうだったのですか。ここまでいろいろなお話を伺ってきましたが、ライアンさんは相当なマーベルファンだと感じるのですが……?
ライアン1990年代にアメリカで育った私は、多くの友人たちと同様、アメリカンコミックスに夢中になっていました。しかし、私が興味を持っていたのは、ほんのひと握りの「存在が現実に根ざしていると感じられるようなコミックヒーローたち」だけでした。そして偶然にも、私が読んで関心を持っていた数少ないコミックシリーズのひとつに『アイアンマン』があったのです。
――なるほど。確かに『アイアンマン』は、荒唐無稽な物語ではなく、リアル寄りですからね。
ライアンそうです。そしてトニー・スタークはスーパーヒーローというだけでなく、魅力的で複雑なキャラクターですしね。だからこそ、開発が始まって以来、マーベルやSIEとともに大規模で革新的なアイアンマンのゲームを開発するという、信じられないような機会にワクワクし続けてきました。14歳の自分からしてみたら、いまの自分がこんな仕事をしているなんて絶対に信じないと思います(笑)。
――自身が好きな作品に関われたなんて、夢がありますね! では、最後に『マーベルアイアンマン VR』を楽しみにしていた日本のファンにメッセージをお願いします。
ライアンご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は『メタルギア ソリッド 4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』という作品でゲーム開発者の道を歩み始めました。そんな世界的なチームの仕事を経験したことでインスピレーションを受け、みずからCamouflajという独立したゲームスタジオを立ち上げて、かつての同僚たちとともに取り組んでいた作品に匹敵するクオリティーの作品を開発すべく努力しています。
そういった経緯もあり、私は日本のプレイヤーの皆さんをつねに意識していました。じつは、日本語版の声優はマーベル映画の日本版の声を担当している方が大勢参加してくださっています。私は本作を日本語でプレイするのが大好きなのですが、SIEのスタッフによるすばらしいローカライゼーションには感嘆するばかりです。私たちが一生懸命開発したこのゲームを、日本の皆さんにも手に取っていただけるとうれしいです。私が愛してやまない日本という国において、バーチャルリアリティーというコンテンツのさらなる発展に『マーベルアイアンマン VR』が貢献することを願っています。