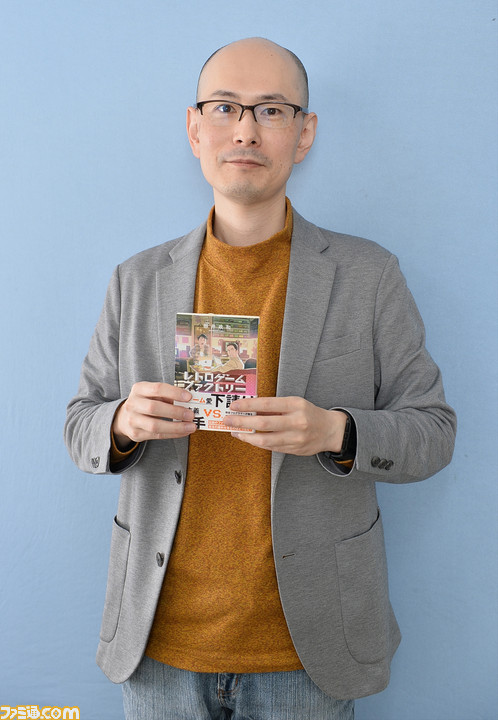まさにテレビゲーム版『下町ロケット』との声も
2018年10月に発売された『レトロゲームファクトリー』(新潮文庫nex)は、過去のゲームの復刻移植を専門とするゲーム開発会社が、権利的にいわくつきのファミコンゲームの復活プロジェクトに携わった顛末を描いた一般小説です。
小規模受託開発会社の悲喜こもごもとともに、1本のレトロゲームを巡る数十年におよぶ人間ドラマが描かれ、物語終盤では、長年テレビゲームとともに生活してきた筆者のようなゲーマーの心を揺さぶる展開が待ち受けています。
作者の柳井政和(やない まさかず)氏は、2016年に小説家デビューしたばかりの新鋭であるとともに、“めもりーくりーなー”などのPC用フリーソフトを多数開発し、プログラミング技術書の執筆も手掛けるベテランの現役プログラマー……という風変わりな経歴の持ち主。そんな柳井氏がなぜテレビゲームをテーマにした小説を執筆することになったのか興味が湧いた筆者は、ご本人に直接訊ねることにしました。
柳井政和氏
ソフトウェア開発合同会社クロノス・クラウンの代表社員として精力的に活動する。ゲームメーカー在籍時には広報を担当し、各種メディア対応を行った経験も。
『レトロゲームファクトリー』
新潮文庫nex刊
表紙イラストを担当したのは、映画『ペンギン・ハイウェイ』のキャラクターデザインを手掛けた新井陽次郎氏。スタジオジブリ出身の注目のアニメーターだ。「ゲーム好きの方はもちろん、そうではない方も楽しめるお仕事小説なので、新井さんのお力を借りて幅広い読者にささるものを目指しました」(担当編集)とのこと。
出版社から与えられたテーマは「レトロゲームで人情もの」
──まずはテレビゲーム、しかも“レトロゲーム”というマイナーな分野をテーマにした小説を書くことになった経緯を教えてください。
柳井新潮社さんから新作執筆のお話をいただいたときに、いくつか企画を出しました。そこで出したのが“同人・インディーゲーム”をテーマにしたものです。
──よりコアな分野を(笑)。
柳井私自身、昔から同人ゲームを作っていて、今年2月にはSteamでもリリースしています。そういう方面の話はどうかと提案したら、さすがにそれはニッチ過ぎるという話になって、「たとえばレトロゲームはどうでしょうか?」と編集部から振られました。自分が作っているゲームのルーツはそこだし、それならば書いてみたい……と決まりました。
──単にレトロゲームを扱うのではなく、“レトロゲームの移植復刻”を専門に手掛けるメーカーの活動を中心に描かれている点が新鮮でした。
柳井私の友人に、“自転車創業”というゲーム開発会社の代表がいるのですが(※かざみみかぜ。氏)、彼の会社が手掛けたレトロゲーム移植の話がおもしろく、自分も興味がある分野だったので、いろいろ聞いているうちにストーリーの原型が固まっていきました。
──とくに印象に残ったエピソードは?
柳井思った以上に権利を取得するのが大変だった、という話です。古いソフトだと会社がすでになかったりとか、ほかの会社に権利が移っていたりとか、結構あるみたいで。
──権利関係はあらかじめクリアーしてから作っているわけではない、と。
柳井移植を趣味にしているプログラマーさんがいて、「せっかく作ったんだから権利を取らないと」と、動き回るそうなんです。それ順番逆じゃないかなって思うのですが(笑)。
──小説の冒頭であった“特定タイトルの権利を個人が買い取っている”というケースも、実際結構あるのでしょうか。
柳井ほとんどないと思います。レトロゲーム移植のエピソードをドラマにするためには、それを“人”に紐づける必要があるんです。
──そこは小説ならではの飛躍なんですね。本作のプロットはどのように固めていったのでしょうか。
柳井“レトロゲームで人情ものを”という大前提ありきでおこなった、編集さんとの打ち合わせの段階で、結末までの大まかな流れは会話のキャッチボールの中でまとまっていきました。作中に登場するゲームやプログラムの具体的な仕様の話は説明しても伝わらないだろうから「先に小説書きますので」という話をしました。
──読者の年齢層は想定していましたか?
柳井「自分と同じくらいの世代を想定して書きました。ファミコンを当時遊んでいる人は、当然ターゲットです。ただそれだけだと幅が狭いので、補足説明を入れつつ、共感できる要素も入れつつ、世代を限定しないようには注意しています。
──“人情もの”であることあえて強調した理由は?
新潮社担当編集 柳井さんのプロットを読み、これはゲーム業界のあるあるネタや雑学を知れる面白さだけではない、幅広い世代にとって魅力的な小説になると感じました。自分の好きなものを仕事に選んだ主人公たちが、それぞれ葛藤を抱え、過去を振り返りながら人生や家族に向き合う過程、そのノスタルジックな心の動きを大事に書き進めていただきたいと思いました。
──お仕事、人情といったキーワードがあるとはいえ、一般小説でテレビゲームを題材にした作品を出版するというのは、なかなかのチャレンジだったのではと思います。
柳井任天堂さんから“ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ”が出たりとか、ここ数年でレトロゲームのブームが来ていたのが大きいと思います。
独立系ゲーム開発会社の“実体験”が満載!?
──本作を読み終えての個人的な感想としては、“世に出ているすべてのテレビゲームには、それに関わった人たちの人生が刻まれている”ということが、肯定的かつちょっと切ない形で描かれていることに、グッときました。本作の主要キャラたちが一様に、一生懸命なのにどこか不器用でもうひとつうまくいっていない感じがするのは、当初のコンセプトありき、ということでしょうか。
柳井それは僕側のテイストじゃないですかね。いままでに書いた小説の感想でも「ちょっと欠けた人、踏み外した人を書いているね」って、よく言われます。自分でもそういうタイプの人が好みなんだろうなぁと思います。
──やや失礼な指摘かもしれませんが、柳井さんも経歴を拝見する限り、“そちら側”のような気が。
柳井ある意味、自分も踏み外していますね(笑)。自分ひとりで会社を立ち上げて好きなものを作ってやってきているというあたりが。
──ゲーム会社勤務を経てから独立とのことですが、会社勤めは性に合わなかった、ということでしょうか。
柳井「そんなにゲームを作りたかったら、どこかから資金を引っぱってきて作れ」って社長から言われたんですけど、「それって自分で会社を作ってやるのといっしょなのでは」と思って、会社を辞めて数ヵ月後に起業しました。実家が商売をやっていたこともあって、何かやるなら自分で会社を作るんだろうなというイメージはありました。設立当時はボードゲームを作っていました。ちょうど2002年くらいのころですね。
──ちょうどカプコンが『カタン』(ドイツ製のボードゲーム『カタンの開拓者たち』の日本版)をリリースしていたあたりですね。
柳井それなりに盛り上がってはいましたが、いまよりも規模は小さかったので、1年ほどやって「これは食えるほどじゃないな」と(笑)。そんなときに、知人に誘われた業界飲み会に参加したのが縁で、当時流行していたiモード(ドコモの携帯電話IP接続サービス)用のシミュレーションRPGやリアルタイムストラテジーの開発・リリースを、数年間続けることになりました。
──作品中でも描写がありましたが、業界飲み会は重要ですね(笑)。その後はスマートフォンアプリの開発に?
柳井スマートフォンにはうまく移行できませんでした。一応作ってはいましたが、自分ひとりでやるにはお金も広報の手間もかかるし、iモードのときより面倒くさいなと感じていました。
──柳井さんのそうした会社代表としての経験も、今回の作品に反映されているのでしょうか?
柳井そうですね。灰江田(『レトロゲームファクトリー』の主人公・灰江田直樹)の会社には、先ほどお話した自転車創業さんや、自分の会社のイメージを何割か入れていますね。
──作品の中では、ゲーム開発現場を巡るえげつない出来事が描かれていますが、これらの中には実際にあったことも……?
柳井冒頭の白野(灰江田と行動をともにする若手プログラマー・白野高義)のエピソードは、私が会社を作ったばかりのときに食らったことを元にしています。
──マジですか!? 道理で尋常ならざるリアリティーが。
柳井読者の感想の中にも「嫌な汗が出た」というコメントがあって、その人も経験あるのかなと思いました(笑)。本作に登場するグリムギルドは架空の大手メーカーですが、以前勤めていた会社の社長が話していた“元・大手企業社員”としての体験談を、大いに参考にしています。
──……ここはあまり踏み込まないほうがよさそうですね (笑)。登場人物たちは、実在の人物がモデルになっていたりするのでしょうか。
柳井そこはお話に合わせて混ぜたり肉付けしているので、誰か特定の人物がいるわけではありません。
──とはいえ、レトロゲームへの思い入れが強い灰江田は、柳井さんご本人の成分が強く入っているのではないかと思いますが……ご自身のファミコンの経験は?
柳井小学校に上がったころにちょうどファミコンが出た、どストライク世代です。当時はシューティングゲームが全盛でしたから、『スターフォース』とか『スターソルジャー』はみんなで家に集まって遊んでいました。あとは『ファミスタ(プロ野球ファミリースタジアム)』とか『ハイパーオリンピック』ですね。大学生時代も、友人と「どのファミコンゲームがどうだったか」みたいな話をしながら夜を過ごしていました。日本各地から集まった同世代の共通の話題が、ファミコンだったんです。
──やはり“レトロゲーム”は特別な存在なんですね。
柳井いま作っている同人ゲームもファミコンのころを思い出しながら作っているので。そう考えると地続きであるなとすごく思います。
──“レトロゲームに興味がある天才肌のプログラマー”白野も相当キャラクターが立っていますが、やはり特定のモデルはいない?
柳井そうですね……ただ、IT系のプログラムの世界だと、いまの若い人の能力って、本当にすごいですからね。うちらの世代が時間をかけて調べていたことがネットで即わかるから、成長もすごく早いんです。レトロゲーム趣味に関しては、若い層がふつうに生活していてこっちに入ってくるっていうのはかなりレアケースなので、そこには何かファンタジー要素が必要だなとは思っていました。
プログラマーが小説家デビューするまでの10年間
──そもそも最初に小説を書くことになったきっかけは?
柳井iモード用ゲーム作っていたときに、1作目をリリースして半年経ってからお金が入ってくるようになったのですが、まわりの人が誰も知らないんです。
──でも、遊んでいるユーザーは大勢いたんですよね。
柳井ドコモの携帯電話を持っている人たちは遊んでいても、外からは流れてこないので、もうちょっと人の見えるところの仕事がしたいと思いました。それから、漫画を描くか小説を書くかで1ヵ月悩みました。
──贅沢な二択!
柳井私は気が短いので、漫画でまかり間違って売れてしまったら連載で10年くらい同じことをしないといけなくなるのはいやだなと思いました。小説なら1冊書くのにせいぜい数ヵ月から1年くらいだろうということで、小説を選びました。
──売れてしまったときのことまで考えていたんですね(笑)。
柳井そこから小説家デビューするまでに10年以上かかったので、「結局10年かかるじゃないか」となったのですが(笑)。
──その10年間はどうやって生活してきたのでしょうか。
柳井技術書を出版したり、動画のプログラミング講座を作ったりと、一度完成させたら自動的にお金が入る感じのことをなるべくやって、できた時間で小説を書いていました。
──それだけを聞くと優雅ですね。もちろん、昔から小説を書きたいという下地があってのことですよね?
柳井ストーリーを作るのが好きでした。中学生のころからテーブルトークRPGを始めて、大学時代もRPG研究会に入っていてずっとやっていたことで、ノウハウが培われたと思います。
──デビュー作『裏切りのプログラム ハッカー探偵 鹿敷堂桂馬』(2016年)は文藝春秋社ですよね。
柳井松本清張賞の最終候補作を改題してデビューしました。
──デビューしてからの周囲の反応はいかがでしたか?
柳井家族も含めて「え、書いていたの?」って人が多かったですね。実際、作品を毎回読んでくれる大学時代の先輩など、ごく一部の人にしか伝えていなかったので。
──先輩というのは作家さんですか?
柳井いえ、オールジャンルの“読む専”です。チェックしてもらって「ココはダメだね」とか指摘を受けるのですが、最初のころはページ単位で×をつけられていました。
──それで鍛えられたんですね。でもずっとその調子だと「書く側の気持ちもわからないくせに!」ってなりませんでした?
柳井なるべくそういう意識が芽生えないよう、すごく年上の先輩に頼んでいました。「これは送らないほうがいいよ」と言われて没にしたものもありましたね。
──先ほどから伺っていると用意周到というか、計画段階から抜かりがありませんね。その方針で10年以上書き続けてきたことが、何よりすごいです。
柳井かなりきつかったですけどね。某出版社のコンテストで最終候補に残って、「◎時に結果報告の連絡をするから待機していてください」と言われたので待っていたら、「落ちました」の電話だけで終わり。何のアドバイスもいただけず……なんてこともありましたね。
“フリーミアム精神”が支える、新たな小説家のカタチ
──柳井さんがゲームの造詣が深い作家さんということは、これまでの話でよくわかりました。たとえば、小説にゲーム的な構造を意識的に盛り混んでいたりするのでしょうか?
柳井内容はそうでもありませんが、プログラム的な書きかたは意識しています。
──というと?
柳井小説推敲の補助ソフト“Novel Supporter”を自作して使っています。小説って、文章の末尾が連続していたり、同じ単語が何度も出てきたら読みにくいとか、いろいろルールがあるじゃないですか。それを画面で可視化するプログラムを作っています。それでチェックして、ここは読みにくいはずという箇所を修正してリーダビリティをなるべく上げるようにしています。
──まさにプログラマーだからこその作法ですね! それはひょっとしたら市販できるのでは……。
柳井すでに無料で公開しています。ネット小説を書いている人には、好評のようです。別途、キャラクター設定や相関関係をブラウザ上で管理する用のソフトも作っているので、それもそのうち公開したいと思っています。
──無から小説を生成するのではなく、小説を書くときにこれがあると便利……というソフトの立ち位置は、ある意味『RPGツクール』シリーズなどのコンストラクションソフトに近いですね。
柳井そういう方向性です。自分の中でプロットのテンプレートはすでに用意しているので、入力項目を埋めていくと、だいたいの話の流れができるようにしています。
──なぜそんなすごいソフトを無料公開するのでしょうか。
柳井最初に公開した“めもりーくりーなー”(PCのメモリ領域を定期的に解放し、快適な動作を維持する常駐ソフト。2001年公開)が無料だったから、ほかのものも……っていう感じですね(笑)。
──そんな理由!?
柳井「無料公開したものの有償版を作ってくれ」という話が、わりとくるんです。“めもりーくりーなー”も後にパッケージ版を作ったし(※2003年発売の“めもりーくりーなーPRO2”など)、『マンガでわかるJavaScript』というマンガも無料で公開していたら、出版社さんから話が来て書籍化(2010年)されたり……私の場合、無料で始めてもビジネスが後で着いてくるって感じです。
──そうして得た利益が会社の運営資金、引いては作家活動を支える糧になり……まさに柳井さんならではのライフスタイルだと思います。現在、小説家としての活動は柳井さんの中で大きな位置を占めているのでしょうか?
柳井もっと書きたいですね。がんばって売れて年に何本か書かせてもらえる状態にならなきゃなって思います。どんどんお仕事募集中です。
──今度はこれを書いてみたい、というテーマは。
柳井すでにいろいろ書いてはいます。ジャンルは幅広くしていかないと生き残れなさそうですしね。いまは何が受けるかなっていうのを自分の引き出しからひとつずつ出して探している状態です。今回の『レトロゲームファクトリー』が受けてくれるのが、一番いいですね。
──読んだ上での印象としても、この話はまだ先にも続きそうな気がしました。そういう構想はあるのでしょうか?
柳井いろいろ設定はキャラクターシートに書いているので、それを膨らませたいという思いはあります。
──まだ書かれていない部分もあると。
柳井続編の構想は毎回あるのですが、売れないことには(笑)。
──ではこの機会に、本作をまだ読んでいない方にアピールしていただければと。
柳井ゲームの話をどっぷり書きつつ、人情話を織り交ぜつつ、“いろいろな趣味を肯定したい”という、私が好きなテーマを込めています。そして、好きなことを仕事にした人の“不器用な本気”を見つめました。何よりゲームの技術も分かるガチ世代の人間が書いた小説はなかなかないと思うので、ぜひ楽しんでください!