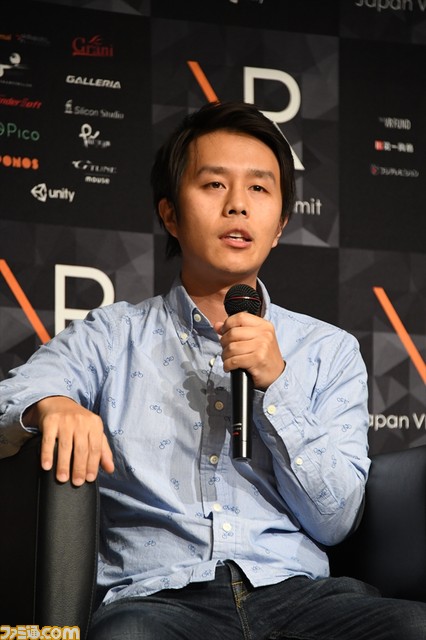医療や建築、ジャーナリズム……AR・VR活用の未来
グリーと一般社団法人VRコンソーシアムは、本日2016年11月16日に大型VRカンファレンス“Japan VR Summit 2”を開催。多数行われたセッションのなかから、セッション4“VR/ARはゲーム/エンタメから各産業へ花開く”をリポートする。
同セッションには、今年大きな話題となったスマートフォンゲーム『ポケモンGO』でディレクターを務める野村達雄氏(Niantic Inc.)のほか、VRゲームのほか360度動画を企画・制作・配信する360Channelを展開するコロプラ 代表取締役社長の馬場功淳氏、VRコンテンツ開発をUnityエンジンからサポートするユニティ・テクノロジーズ・ジャパン日本担当ディレクターの大前広樹氏、そしてLittle Star Media, Inc.よりファウンダー・CEOにして、360度動画のVRネットワークなどを提供するTony Mugavero氏が登壇。現在はゲームを始めとするエンタメを中心に躍進を遂げるVR、ARだが、エンタメ以外(ノンエンタメ)分野における活用の可能性が語られた。
『ポケモンGO』のバリューは“人を外に連れ出す”こと
まずは登壇者が自己紹介を交え、ノンエンタメ分野でのAR・VR活用の事例を紹介。大前氏が所属するユニティはおもにゲームエンジンの提供・開発を行っているが、VRコンテンツ開発においても多くの顧客を抱えている。ゲームはもちろん、医療や建築、教育など、ユーザーの1/4ほどはゲーム以外の分野でUnityを活用しているとのことだ。同氏が例として挙げたのは医療分野での活用。手術をVR化する取り組みがすでに行われているようで、手術室にVRヘッドセットを持ちこみ、患者の身体のなかを3Dでビジュアル化したデータを取り込むことで手術のデモンストレーションができるという(大前氏「つまんで引っ張ることもできます」)。
360度動画の配信を手掛けるMugavero氏が例として挙げたのはジャーナリズムでのVR活用。テレビ番組のように編集され、ナレーションがついた映像よりも、実際の現場を360度動画で収録するほうが当然臨場感が生まれる。また教育エンターテインメント(Education+Entertainment=Edutainment)においても360度動画は有用で、あらゆる動物や植物を360度動画で観ることで、楽しみながら学ぶことができるのだ。なお360度動画の活用に関しては馬場氏も「体験系は相性がいいです」と有用性を語っており、すでにANAの機体工場見学などのコンテンツを360Channelにて配信中だ。
一方、『ポケモンGO』などAR技術を活用したゲームタイトルを手掛ける野村氏が所属するNiantic Inc.は、会社として“人を外に連れ出す”とのミッションを持ち、ARを“Adventure on foot(自分で歩いて冒険しよう)”と再定義。『ポケモンGO』やその大もととなる『Ingress(イングレス)』も、あくまでこの目的のための手段として開発された。もちろんそのバリューも“人を外に連れ出す”ことにあり、たとえば自閉症の子どもが『ポケモンGO』をきっかけに外に出かけ、ほかのプレイヤーとコミュニケーションを取るようになったという例もある。『ポケモンGO』では現在、東北地方の沿岸部でラプラスが発生しやすくなるイベントが実施されているが、こういった“人を呼ぶ”ための地域振興的な取り組みにも積極的だ。野村氏は加えて、「ARは拡張現実の略称だが、マーカーがあってカメラがあって……という“AR”とは違う。『ポケモンGO』をプレイすることで知り合いが増えたり、あまり行かないところへ行ったり、新しい発見をしたり……といった意味で現実を拡張している側面がある。カメラはトリックでしかなく、あくまで一部。ゲーム外にある皆さんにとっての現実が、いかに拡張されるかが重要」と語った。
ARの活用というテーマでは、野村氏が「ARは裾野が広く、広義では例えばスマートフォンのマップのナビゲーション。GPSでトラッキングするマップのナビゲーションは、ひとつのARと言える」と解説。『ポケモンGO』の登場により、スマートフォンでもそれなりのAR体験を提供できるという“気づき”が生まれ、今後はさまざまなコンテンツが増えるだろうと予測した。
一方、100%精確に“世界を同定させる”という意味でのARは技術的に不可能であるがゆえ、ARの未来にはネガティブであるという馬場氏は、「『ポケモンGO』のすごいところは、なんとなくやっているところ。完全に一致していなくてもおもしろいところに妙がある。こういったゲームは広がっていくのではないかと思っています」と分析。これに対して野村氏も「100%の精度でやると不可能だということがわかる。技術的にはパーフェクトにはなりえないですが、進化の途中でさまざまな説得力のあるアプリが出ると思います」と補足した。
またMugavero氏によると、360度動画では旅やジャーナリズム、スポーツ、音楽に人気が集まっているというが、従来の動画との違いはナラティブ(物語)性。従来の動画ではどのシーンに照明を当てるのか、どう物語を語るのか……といった演出が重要になるが、360度動画ではまったく違う考えかたが要される。この点音楽やジャーナリズムはナラティブなコンテンツである必要がなく、360度動画の体験そのものがコンテンツになるとのこと。「嵐の後に撮った映像はそれだけでエキサイティング。完璧に照明を当てる必要もない。映像はナラティブから“いま何が起きているのか”に移行しており、例えばコスタリカのビーチに45分座るコンテンツに物語はいらない」(Mugavero氏)
登壇者が期待を寄せるVR・AR活用の未来
セッションの終盤の“VR・ARと相性のいい分野”というテーマでは、登壇者それぞれが今後の展望を披露。「とくに建築や製造の方で、VRに興味のない方にお目にかかったことがない」と語る大前氏は、プロダクトに関わる産業に注目。VR空間でプロトタイプを制作することによるコスト削減に注目が集まっているとのことで、「いちばん大きな例はNASA。火星に機械を持っていく前に、動作を検証する環境としてVRが活用できる」(大前氏)。このほかNASAでは学者が火星などの研究をする際のテレプレゼンス(遠隔臨場感、遠隔存在感)にもVR技術の応用が期待されており、宇宙飛行士と視界を共有し、分業できるソフトを制作するなどの取り組みが行われているようだ。
Mugavero氏は今後期待できる分野にアナリティクス(分析)を挙げた。例えば野球チームの試合をVRで観戦するというシーンでは、観戦者がスタジアムのどの広告を見ているか、どのように試合を見ているかをトラッキングすることができる。鼓動や目の動きなどをデータ化することにより、人間の行動が分析できるが、これは広告業界に大きな意味をなすと予測した。
「ARの未来は明るい」と語る野村氏は、「応用できる分野は無現にあり、むしろ応用できない分野は何だろうと思うくらい」と熱弁。すでに家具を実際の部屋に配置してシミュレーションできる家具メーカーのスマホアプリなども登場しており、「未来の話ではありますが、医療でも手術の瞬間に何が起きているのか、血圧の数値はどうなっているかといった情報が、視界のなかに入る未来はそう遠くないと思っています」と、さまざまな分野での活用に期待を寄せた。
続けて馬場氏は「VRと相性がいいのはコミュニケーション。やはり、人とやるゲームは評判がいい。人と人が会って話をする行為には、本能に訴えかける何かがあり、VRではそれを大量に発生させることができる」と知見を披露。「例えばSkypeで話しているよりも、VR空間で会話をしているほうがより話している感じがしますよね。コミュニケーションのある分野はVRと相性がいいと思います」と展望を述べ、セッションを締めくくった。