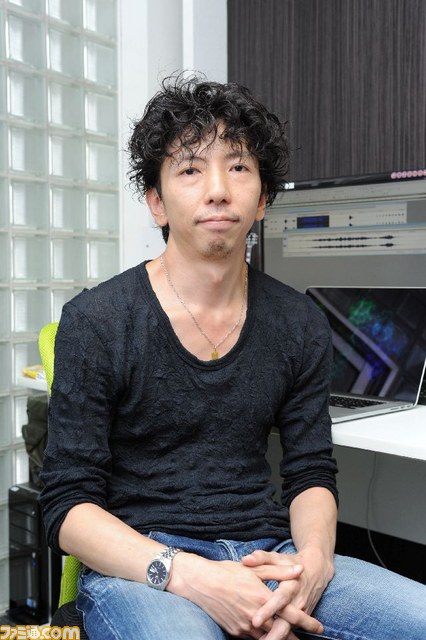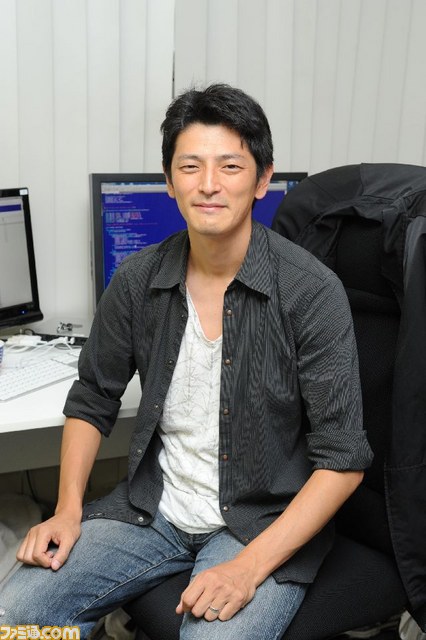“ファミキャリ!会社探訪”第5回はネイロ!
ファミ通ドットコムにオープンした、ゲーム業界専門の求人情報サービス“ファミキャリ!”。ゲーム業界での転職を目指す人たちに向けた“ファミキャリ!”が、ゲームメーカーを訪問し、実際にお話をうかがうこのコーナー。第5回となる今回はネイロ!
セガ在籍時代に『シェンムー』のメインプログラマとして活躍した、代表取締役社長の平井武史氏。その後、キューエンタテインメントでCTO(最高技術責任者)を務めた後、2009年にネイロを設立。4年目を迎えた今年、ついに自社パブリッシングタイトルを世に放つ! 今回は、その平井社長と若きネイロの屋台骨を支える各セクションのリーダーにお話を伺った。
ネイロは“五感で楽しむエンターテインメントを作る企業体”
代表取締役社長 プロデューサー
--最初に、プロフィールから教えてください。
平井武史氏(以下、平井) 僕がゲーム業界に入った1991年というのは、ゲームはありましたが、まだインターネットもありませんでした。ただ、「これからの世の中は、単方向のノンインタラクティブの時代ではなく、双方向インタラクティブが要求される時代だ」と感じていました。ゲームなら、国境を越えて遊んでもらうこともできるし、ユーザーそれぞれが楽しい思いや体験ができるという、新しいメディアになるのではないかと思い、ゲームというメディアに非常に興味を持ちました。ゲーム会社は1社しか訪問してしませんでしたが、会社訪問をして帰ってきたらもう内定が出ていて、そのままそこに入りました。
--それが、アイレム(現アイレムソフトウェアエンジニアリング)さんですね。
平井 そうです。その後転職して、セガで10年間。『シェンムー』 では、メインプログラムを担当しました。そのセガが、ファーストパーティからパブリッシャーになり、既存のタイトルやシリーズを重要視するスタンスに変わっていきました。自分はメディアとして新しいものを提供するということに重きを置いていたので、セガを退職して、2003年にボードメンバーとしてキューエンタテインメントに参加しました。約7年コンシューマ開発、オンライン開発の立ち上げ業務をまっとうしました。僕が考えるゲームとは、インタラクティブであり、おもしろいものであり、売り上げが立つものではない。日本という国で時代が要求してきているものと相反することになりますが、そういう本来のゲームの遊びを大切にするものを創造し続けていきたいと考えて、2010年に“ネイロ”という、五感を大切にするプロダクト制作を心がける企業体を目指して起業しました。
--かなり前から起業を考えていたわけですか?
平井 ゲームを自分の判断で作りたいという考えはありましたが、こんなに遅咲きで会社を作るとは思っていませんでした(注:平井氏は42歳)。でもこのタイミングで「やりたい」と思ってしまったので、仕方ないですね(笑)。そうして、プレイステーション Vitaで『orgarhythm(オルガリズム)』(発売元:アクワイア)を開発させていただき、いまはアエリア(株式会社アエリア)さんと協業で、スマートフォン向けオンラインRPG『Klee(クレー:開発コードネーム)』を開発しています。そして、iOS/Android向けの初パブリッシングタイトルも予定しています。これまでは受託モデルでしたが、4期目に入ってようやくパブリッシングステージに突入していきます。
--とても順調ですね。
平井 目安として、35人くらいの企業体を作りたくて、ようやく自分が思っているような会社規模になってきたと思います。ひとりで面倒を見られる大きさというのは、やはり30人くらいだと思います。
--社名の由来は?
平井 名刺の裏に書いてあるのですが、“音を彩る”と書いて“ネイロ”と読みます。起業した2010年当時、携帯ゲーム機やケータイでゲームをしている方が増え、そこで気づいたのが、ヘッドホンをしていない方がたくさんいるということでした。“音”は五感の中でリアクションをつかさどっていて、その大切な部分が重要視されていないゲームが増えているのだと思いました。「五感で楽しむエンターテインメントを作る企業体にします」という宣言のようなものですね。たとえば、スマートフォンはタッチデバイスですから、ボタンを押したというリアクションがないですよね。指で画面も隠れてしまう。ゲームでいう大切なインタラクティブのリアクションは、音で付ける必要がありますが、その部分にこだわりがない開発をよく見かけます。“ネイロ”は、その根幹の部分を大切にするスタジオであり続けます。
“一歩先”を行くゲームデザインを求めて
--業務内容はどういったものですか?
平井 たとえば、「この企画なら、国内外のどのパブリッシャーと組むことができるか」といった、ビジネスリサーチや事業計画といったビジネスモデルのプランニング、ゲームの企画から開発の全工程までです。サウンドも外注ではなく、自分たちで作ることができるので、企画・提案からアート、サウンド、プログラム、ディレクション、そしてパブリッシングの支援までできる会社というのは、ベンチャーとしては珍しいと思っています。たくさんのクリエイターやディベロッパーとコラボしてきましたが、そういった仕事によって“トレンド”や“そのときの開発のスタンダード”がわかることがあります。いまのスタッフにもそういう体験をさせてあげたいので、自分たちだけで開発するのではなく、協業モデルで仕事ができる体制というのも、いまの企業体に合っていると思います。オリジナルタイトルは、なかなか制作が読みづらく、ビジネスする上でハードルが高いのですが、せっかく起業したので、会社の規模が大きくないいまこそ、たくさんトライしたいと思っています。
--スタッフは経験者が多いのですか?
平井 新卒採用もしているので、何人かは新卒からのスタッフです。大きな会社ではないので、実践的な仕事を教えながら、モノをつくる体制を作っていきます。
--社内の雰囲気はどんな感じですか?
平井 直接話ができる環境を大事にしていて、パーテーションもなく、机と机が近い状態です。Skypeなどでも業務のやり取りをしていますが、人と人が話をしてモノを作るのが大事だと思っています。僕は「トライ&エラーした回数だけ、いいゲームができる」と思っているので、話しやすい空間づくりも大切にしています。放っておくと、「あれ、本当に仕事の話かな?」と思うこともありますけどね(笑)。年齢層も幅広いですね。僕より年上もいますし、いちばん若いのは新卒で22歳がいます。また、全体の4分の1が女性で、サウンド、プログラム、企画、アートと各セクションに1名以上はいますね。女性スタッフだけで何かを作るのもおもしろいのでは、と思っています。
--他社にない、魅力や強みはどこですか?
平井 まだまだスモールカンパニーですが、オールインワンの開発がしっかりできるというのが強みです。開発セクションはあっても、それぞれにリーダークラスの仕事ができるスタッフがいる会社は少ないと思います。ですから、モノづくりをする全工程を勉強できるのではないかと思いますね。さらに、ワールドワイドに目を向けて開発しているので、新しいものを作りたい人には魅力を感じていただけるのではないかと思います。開発しているプラットフォームも、コンシューマもあればスマートフォンもあり、また業務用も開発しています。
--会社を設立してよかった点は?
平井 まだ僕は“旅の途中”なので、最終的によかったのかどうかは、これからだと思いますが、人との出会いに関しては、とても感謝しています。自分が描いてきた“ネイロ”最初の3年間の事業計画は、結果的にはその通りに進んできています。同時に、『orgarhythm(オルガリズム)』という、僕らが目指してきた音楽とストラテジーが融合したような、新しいタイトルを世の中に出すことができたことは、非常に感慨深いです。
--“旅の終着”のイメージはあるのですか?
平井 継続してやっていきたいことはあります。お客様の笑顔が何よりもうれしいので、ずっと期待して作品を待っていただけるようなスタジオであるように、継続していきたいです。“ネイロ”だったら、ほかと違うことをやってくれるかもしれない、と期待してもらえるようなスタジオに、早くなりたいと思っています。
--今後のビジョンについて教えてください。
平井 ゲームデザインをいま一度見直すタイミングなのかなと思っています。いままでUIをさんざん研究して、ゲームというデバイスと内容も考えられてきたのが、ユーザー自身のライフサイクルというものまで意識して作るような、新しいデザインを要求されていると確信しています。“半歩先”というあいまいな少し先や、“二歩先”という未来でもなく、確実に来る“一歩先”くらいのゲームデザインを目指して提案していきたいですね。そうして、つねに時代の先取りができる企業体を目指していきたいと思っています。よくことわざとして使われますが、「昨日の非常識は今日の常識」というところを大切にして、ものづくりに活かしていきたいと考えています。
--“CEDEC 2013”で講演されましたが、いかがでしたか?
平井 “In-Game Cinematics(IGC)”というタイトルでパネルディスカッションをさせていただきました。(※リポート記事はコチラ)“In-Game Cinematic”という言葉を聞いたことがある人は、まだ多くないと思いますが、「ゲームの中に“シネマ”が存在する」という意味です。分かりやすく説明すると、たとえばアクションゲームをプレイしていて、ある場所でカットシーンが入ることで、ゲームの操作が中断され、そのシーンが終わるとゲームが再開される……まぁ、こういったことをなくそうという考えかたですね。カットシーンとゲームシーンを完全に融合させようというのが基本的な考えかたです。1999年に発売した『シェンムー』では、“QTE(クイック・タイム・イベント)”というシステムを採用して、シネマの中にインターフェースを入れて作りました。シネマをボーっと見るのではなく、前のめりになって見ることができるように作ったものです。
--日本では、現在の“QTE”の評判はよくないですよね。
平井 そうですね。“QTE”ばかりのタイトルがあったり、“やらされている感”が強いためですが、つぎの段階へと進化を始めている段階だと思います。余談ですが、『シェンムー』の制作発表会もパシフィコ横浜だったんですよ。ちょうど14年と半年前の1998年の12月20日。そのときにはライブでメインテーマの演奏もあったんですが、今回のCEDECでそのテーマが流れている中、自分が『シェンムー』について語っていることは、とても感慨深かったです。
--それでは、最後にメッセージをお願いします。
平井 未経験者でも、ゲーム業界に興味があれば採用されるチャンスはあります。未経験だからといってあきらめずに、自分に何ができるのか、何が得意なのかをしっかりとイメージしてトライしてください。「未経験だけどこんなことができます」というものがあれば、採用検討できると思うので尻込みする必要はないですよ。ゲームが好きで、作りたいと思っていただけるのであれば、トライしていただきたい。むしろ、歓迎ですね。
転職という点では、環境や人が変わっても、モノを作るワークフローは、基本的にどこの会社でも同じだと思います。大切なのは、遊んでもらう人のイメージがしっかりできていて、自分がまず自分自身のファンで、モノづくりが大切にできるかどうか。ゲームを作る目線、遊ぶ目線をしっかりと持つ。それはどのセクションでも同じです。スマートフォン、現行機、新世代機、さまざまなプラットフォームがある中で、何かひとつのスキルを極めたり、強みを持つというのも大事なことです。結局はゲームが好きで、ゲームで遊んでいるかどうかということが大事だと思います。ゲーム以外でも趣味を持ってほしいですね。いろいろなものをインプットしている人のほうが、アウトプットもいい。インプットしたさまざまなものを、エンタメとしてアウトプットすることに意識を持つことが大切かなぁと思います。“ネイロ”は、遊びを大切にする人材といっしょにものを作っていきたい。
僕は水中写真の撮影が趣味なんです。よく「いまはそんなことをしている時期じゃないですよね?」と注意されますが(笑)、僕にとっては、アウトプットするためのインプットとして必要なんですよ。趣味の延長上で作っているモノのほうが、“熱”は伝わりやすいです。“好きこそものの上手なれ”とはうまいことを言ったものだなぁ、と思いますね(笑)。
ここからは、サウンド、企画、アート、プログラムという、ネイロの根幹を支える各部署のメインスタッフからのコメントを紹介しよう。
一木 裕樹/開発部 サウンドディレクター
“音”に関わるすべてのことを統括しています。僕は、平井が以前在籍していたキューエンタテインメントにフリーランスで参加していたのですが、ネイロを立ち上げるにあたって声をかけてもらいました。
ゲーム会社のサウンド部門は、1本ヒット作が出ると、その特色というか、ヒットしたタイトルに似たものばかりになるのですが、弊社はよくも悪くも未成熟な部分があるので、いろいろなタイプの音作りができます、そういう意味では、いろいろな経験をさせてもらっていると思っています。サウンドティレクターという立場から言わせていただくと、社内にサウンドチームを持っているメーカーは、最近はひと握りの大手メーカーだけになっています。
会社のサウンドチームに所属して、ガッツリと開発に携わることができるというのは、未経験の方にはとても勉強になると思います。ゲームだけにかかわらず、いろいろな分野に対しての音作りを、今後も広げていきたいと思います。
濱田 修一郎/企画戦略室 プロデューサー
社内の企画チームのチーフとして、スタッフの管理や自分のプロジェクトのプロジェクトマネージャーやディレクターをしています。ネイロには、PS Vita『orgarhythm(オルガリズム)』の制作に、別の会社から出向という形で関わっていて、いろいろと意気投合した部分もあって、合流しました。
弊社のスタッフは、いい意味で個性が強いメンバーが集まっています。単純な作業をこなしていくだけではなくて、作品の先にある“商品”を意識したモノ作りができるような会社ですし、それができるメンバーが揃っています。
昨今、ソーシャルゲームを始め、ゲームというジャンルも幅広くなってきたと思います。弊社はモノ作りにこだわり、ひとつひとつの作品に対して、もっとオリジナリティーを持った、個人個人がクリエイティビティを発揮した作品を作っていきたいと考えています。そういったことがことがしたいと感じた方がいらしたら、どんどん応募していただければと思います。
渡邉 悠太/開発部 グラフィックデザインディレクター
デザイン業務のディレクションを担当しています。具体的な業務としては、そのゲームの企画や世界観に合ったキャラクターや背景、デザインを作っています。
ネイロに入る前は、別の会社でおもに音楽ゲームのグラフィックデザイナーとして働いていました。たまたま、ネイロといっしょに仕事をする機会があり、そのときに平井から声をかけていただいて、この人といっしょだったら楽しいモノが作れるなと感じて、ネイロに入りました。
会社によって、いろいろな条件があると思いますが、自分が継続して追求できること、自分が成長できる仕事ができると思える職場を選んでほしいと思います。
竹島 覚/開発部 プログラムディレクター
プログラムディレクターとして、プログラムセクションの統括をしています。とはいえ、まだ人数が少ないので、プログラムそのものを書くこともありますが、おもにシステム管理が守備範囲です。
平井とは古い付き合いで、セガに新人で入ったとき、彼は『シェンムー』のメインプログラマでした。その後も何度か仕事をする機会があったのですが、「またいっしょに仕事がしたいな」と思い、ネイロができた1ヵ月後に合流しました。
自分はいろいろな部署を転々としてきたのですが、「そのときにやりたいと強く感じたことをやる」という考えでやってきました。そのためには環境も変わるかもしれないし、異動した先では周囲に認めてもらわないといけません。ずっと同じ仕事を続けるより、ハードルが高いかもしれません。やりたいことを探している段階だとしても、いろいろと勉強しておかないと、いざというときにたいへんになるのではと感じています。
ネイロってどんな会社?
アイレムソフトウェアエンジニアリング、セガ、そしてキューエンタテインメントで活躍した、ゲームクリエイターの平井武史氏が、2010年に起業したネイロ。この9月で、設立して4年目に突入した。この社名の由来は、「アウトプットする作品の先端となる音まで彩りたい」という平井氏の思いから、“音を彩る”=“ネイロ”。
アクワイアから発売中の、プレイステーション Vita用ソフト『orgarhythm(オルガリズム)』の開発を手がけているネイロ。家庭用機、スマートフォン、さらには業務用タイトルと活躍の場を広げ、間もなく自社によるパブリッシングタイトルも予定している。
<会社概要>
ネイロ株式会社
●代表取締役社長:平井武史 ●設立年月日:2010年9月1日 ●従業員数:36名(2013年8月現在) ●事業内容:家庭用・業務用ゲーム開発事業、サウンド制作事業、デジタルコンバージェンス事業