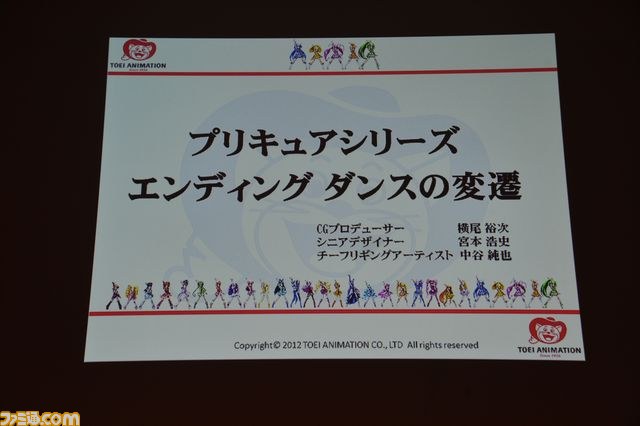数あるセッションの中でも、屈指の人気
2012年8月20日~22日まで、パシフィコ横浜にて開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC2012”。会期最終日に行われた、東映アニメーションのスタッフによるセッション“プリキュアシリーズ エンディング ダンスの変遷”のリポートをお届けしよう。
『プリキュア』シリーズは、子ども、なかでも女児をメインターゲットとした人気コンテンツだが、子ども向け作品とは思えぬハイクオリティーなアニメーションや、魅力的なキャラ造型などが、大人のアニメファンからも注目を集めることが少なくない。とくに、『フレッシュプリキュア!』の番組エンディングから始まったフルCGで描かれるダンスは、カラフルな色彩やキャラの魅力が存分に発揮された仕上がりで、アニメに興味がない人でも思わず惹きつけられてしまう。何を隠そう、記者もそのひとりだ。友人の家へ遊びに行ったとき、友人の1歳半になる娘が観ていた『スイートプリキュア』(たぶん)のエンディングを目にして、「な、なんてスイートでキュートなんじゃい!」と激しく心を揺さぶられたのである。まあ、記者の話はどうでもいい。それにしたってスゴイのだ。陳腐な表現だが、キャラが生きているようなのだ。ちなみに、記者は恥ずかしながらキャラクターの名前をひとりも知らない。しかし、あのCGアニメーションは『プリキュア』を知っている知らない以前に、ひとつのエンターテインメント作品とし……まあ、記者の感想はどうでもいい。とにかく、この鼻息の荒さから、『プリキュア』シリーズのエンディングがどれだけスゴイか、ということは1ミリくらい伝わったと思う。誤解がないように一応言っておくが、興奮しているのは記者だけではない。本セッションは入場規制がかかるほどの盛況ぶりで、記者が取材した数あるセッションの中でも、屈指の人気となっていたのである。
話が少し脱線したが、ようやくここからが本題だ。今回のセッションでは講演名にもある通り、この大注目のエンディングがいかにして生まれ、進化してきたかが語られた。最初に話をしたのは、東映アニメーションのデジタル映像部でCGプロデューサーを務める横尾裕次氏。同氏からは、エンディングダンスの生まれた経緯などが語られた。
2009年に『フレッシュプリキュア!』をスタートするに当たって、東映アニメーションでは、子どもや女の子が好きなものに関するアンケートを実施した。そこで、ダンスという答えが集まり、エンディングにその要素を取り入れることになったのが、エンディングダンスのそもそものきっかけ。しかし、細かな動きが多いダンスを作画で表現するのはハードルが高いと判断し、3DCGで表現することに。こうして、東映アニメーションのCG部門とも言えるデジタル映像部に、仕事がまわってきたというわけだ。
ダンスシーンを手掛けるにあたっては、ふたつのルールが設けられた。ひとつは、子どもたちに向けた作りにすること。結果的に多くの人から注目を集めることになった『プリキュア』のエンディングダンスだが、同作はあくまで子ども向けの作品だ。大人目線でのクオリティーよりも、子ども目線のクオリティーを優先するのは当然の話である。具体的には、夜のシーンを減らす、また振り付けにも子どもへの配慮が行われることになった。もうひとつのルールは、覚えやすい演出。ただ観るだけでなく、子どもにダンスを覚えてもらい、いっしょに踊ってもらうという目的が、エンディングダンスにはあった。そのため、制作に当たってはつねに体全体が画面に見えていなければいけない、というきびしいチェックが行われることに。ちなみに、全体が見える画というのは要するに引きの構図しかできないということだ。そうなると見た目が単調になってしまう……という問題が生まれるわけだが、それは『スマイルプリキュア』で取り入れた、背景スクリーンに映すという仕掛けで解決したとのこと。
『プリキュア』シリーズのエンディングダンスは、デジタル映像部がアニメ本編とは独立して手掛けてきたが、制作体制は初期と現在では若干違う。初めてエンディングダンスを取り入れた『フレッシュプリキュア!』の前期では、監督を立てて提供されたコンテを元に映像を作っていたが、同2期目からはそれらがなくなり、デジタル映像部主導で進めることになったという。これにより、現場のスタッフがさまざまな提案を行える環境が整い、可能性はさらに広がっていった。
横尾氏らは『フレッシュプリキュア!』から始まり、4年間のあいだに『ハートキャッチプリキュア!』、『スイートプリキュア♪』、『スマイルプリキュア!』の各前後期、合計8つのエンディングダンスをこれまでに手掛けてきたが、それらの仕事はデジタル映像部の技術力向上にもひと役かったそうだ。理由のひとつは、90秒というエンディングの尺。90秒は約30カットで構成されており、これが多くもなく少なくもないちょうどいい塩梅で、何か新しいことに挑戦するのには最適だったという。また、前後期で年に2回制作するタイミングあるというのも、アイデアを実践する機会として恵まれている。現在では、エンディングダンスをやりたがるスタッフも多いそうで、アイデアも自然と集まってくる状況。今後もさらなる発展が望めそうだ。
チーフリギングアーティストの中谷純也氏からは、エンディングダンスの具体的な制作ノウハウが語られた。講演名にある“エンディング ダンスの変遷”だが、中谷氏の話を聞く限り、これは“揺れ物の変遷”とも言い換えられそうだ。
3DCGアニメーションを制作する際、動きに説得力を持たせる手段のひとつとして、髪の毛先やアクセサリーといった“揺れ物”をキャラクターに合わせて動かす、というものがある。最初期の『フレッシュプリキュア!』でも“揺れ物”は動いているわけだが、それらはなんとすべて手作業で付けられているもの。これは莫大な手間だ。そこで、『ハートキャッチプリキュア!』の前期からはある程度は自動化したが、まだ一部は手作業に頼っている状況だった。『スイートプリキュア!』からは、フェイシャル(表情)以外すべての揺れ物が計算で表現できるようになったが、髪の毛先が過敏に反応してしまうという問題が発生。毛先だけは手作業で修正した。そして、最新作『スマイルプリキュア!』でついに揺れ物の表現はほぼ完成となる。対象物の動きをフレーム単位で遅らせるディレイなどの要素が加わり、より柔らかで自然な揺れ物が、全自動で描けるようになったのだ。
また、キャラクターの動きを付けるモーションキャプチャーも、作品ごとに進化している。当初モーションキャプチャーは外部のスタジオに頼っていたが、途中から自社での収録に切り替え、コスト計算やスケジュール調整の融通が効くようになって、研究する余地が増えた。その中で一貫して行なわれているのが、指先の細かな動きのキャプチャー。結論から言えば、この件に関してはまだ満足のいく結果は出ていないとのことだが、撮影距離を縮める、センサーを付ける位置を工夫してみるなどの試行錯誤をくり返す中で、徐々にノウハウは蓄積されている。また、「今後何か新しい技術、よりより方法が発表されれば積極的に取り入れていきたい」(中谷)とスタッフのモチベーションも高いようだ。
講演の最後では。シニアデザイナーの宮本浩史氏による、Mayaを使ったキャラアニメーション制作の実演も行われた。『プリキュア』シリーズの3DCGはモデルがアニメキャラクターという点において、リアル系のソレとは大きく異なる点がひとつある。表情や部位の見えかたに嘘があったほうが望ましいのだ。より適切に表現すればアニメ的な見せかたを意識する必要がある、ということ。たとえば、前髪が長いキャラの顔を横から見た場合、リアルに状況を表現するならば顔ほとんどが前髪に覆われてしまうのが正しい。しかし、アニメのキャラクターにおいては、前髪の形も顔も両方が見えたほうが、表現としては正解だ。そこで、『プリキュア』シリーズのアニメーションツールには、体の動きだけでなく腕の太さや、前髪の角度、口の歪みなどを調整し、アニメーターがキャラのモデリングに近い操作を行える機能を実装。よりアニメ的な表現を、簡単に作れる環境が揃っているのだ。
楽しさが弾ける『プリキュア』シリーズのエンディングダンス。しかし、その舞台裏では制作者たちのたゆまない努力が……と、“らしい”まとめかたをしようと思ったが、今回の登壇者からは、いい意味で努力の雰囲気が感じられなかった。もちろん作業は困難の連続だろう。しかし、「何かひとつ目標を立てて、クリアーしていくことができる」という横尾氏の言葉が象徴するように、どこかゲーム感覚、いやここはダンスの振り付けを学ぶ感覚とか言ったほうがいいかもしれない。とにかく、どこか楽しげなのだ。技術研究やノウハウの積み重ねはもちろん、こういった現場の雰囲気も、『プリキュア』シリーズエンディングダンスの楽しさを生み出すのにひと役買っているのかもしれない。