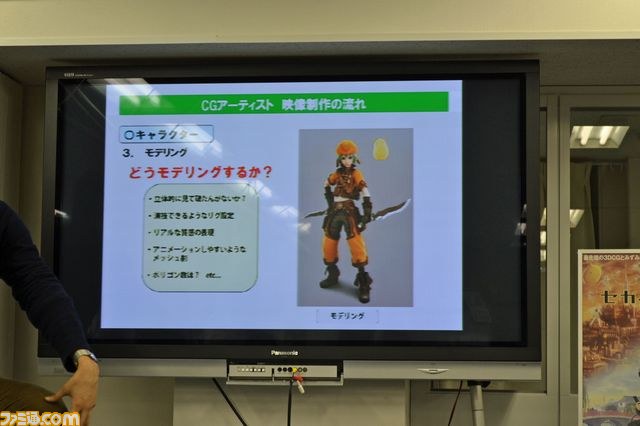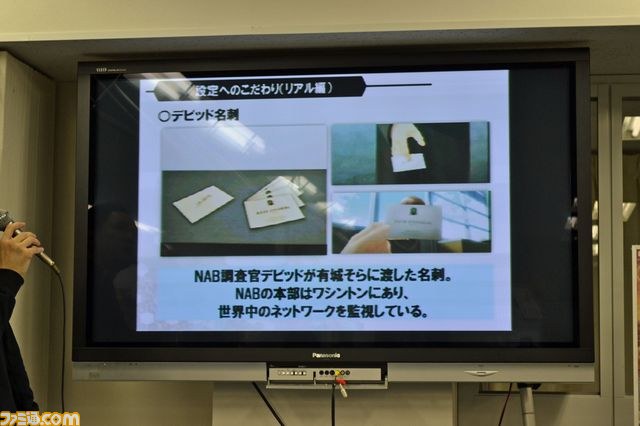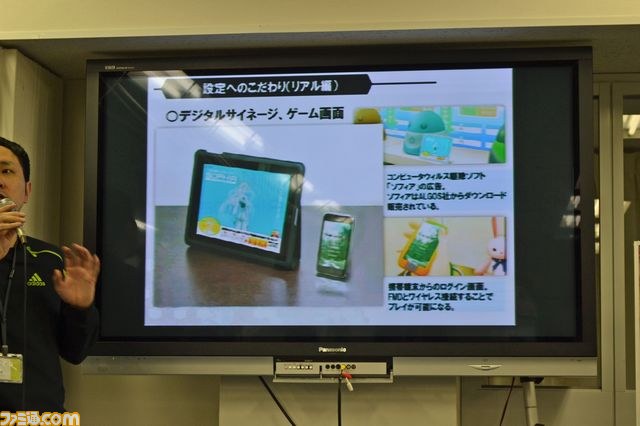日野晃博氏、原田勝弘氏も絶賛した物語はいかにして作られたのか
ゲーム『.hack(ドットハック)』シリーズや『NARUTO-ナルト- ナルティメット』シリーズ、『Solatorobo(ソラトロボ) ~それからCODAへ~』などの開発で知られるサイバーコネクトツーがアニメーション制作を担当した劇場用3Dアニメーション『ドットハック セカイの向こうに』。2012年1月21日の全国公開(テアトル新宿、シネ・リーブル池袋ほか)に先駆けて、監督を務めるサイバーコネクトツー代表取締役社長の松山洋氏による特別講義が、2012年1月11日に代々木アニメーション学院東京本部校アニメ・マンガ館にて開催された。
『ドットハック セカイの向こうに』は、現実世界と“THE WORLD(ザ・ワールド)”と呼ばれるオンラインゲームの世界を並行して描くメディアミックス作品『.hack(ドットハック)』シリーズの最新作にして、初の劇場長編作。最先端のフル3DCGで、現実の世界とゲームの世界を創り出す意欲作となっている。今回の講演では松山氏に加えて、映画のためにサイバーコネクトツーで結成された制作チーム“sai -サイ-”でプロジェクトリーダーを務める二塚万佳氏も登壇し、映画完成までの具体的な流れなどを代々木アニメーション学院の学生たちに紹介した。
最初に松山氏が語ったのは、劇場映画で『.hack(ドットハック)』シリーズを制作するうえでのスタンスについて。同氏いわく、ゲーム版ではゲーム世界と現実世界の割合を9:1で描いているのに対し、映画では現実世界を6割、ゲーム世界を4割で描いているそうで、ゲームと現実の比率が逆転している。その理由は、映画はゲームと比べてより幅広い層が気軽に楽しめるメディアである、という同氏の考えに拠るもの。言い換えれば『ドットハック セカイの向こうに』は、誰でも楽しめるというコンセプトを掲げており、そのために、観客と地続きである現実世界に比重を増やしたというわけだ。ゲーム版と異なる点はほかにもある。ゲーム開発ではハードのスペックに制限があるため、映像表現にはどうしても制約が生まれてしまう。しかし、映像の世界ではその制約がゲームと比べれば幅が広い。そこで松山氏は、制作に当たってはスタッフに「映像の力で思う存分やったれ、好きなことができるぞ!」と呼びかけたそうだ。
『NARUTO-ナルト- ナルティメット』シリーズのリアルタイムで描かれるマンガ的表現に代表されるように、映像表現に強いこだわりを持つサイバーコネクトツー。松山氏のスタッフに対する呼び掛けからもわかる通り、今回の映画制作においても映像へのこだわりは遺憾なく発揮されたが、それに加えて力を入れたのが脚本だと言う。松山氏を始めとする制作チームでは、脚本家の伊藤和典氏から提出された初校をもとに、スタッフ全員でブラッシュアップを行った。シーンのつながりに不自然な点はないか? 物語としての見どころはしっかりとあるか? などをしっかりと確認し、そのうえでブレインストーミングのように意見を出し会い、じつに7回もの書き直しを行ったそうだ。また、脚本を具体的に映画の場面として落とし込む絵コンテについても第6稿まで作成。ゲーム制作の現場では“デバッグ”というプレイ中に起こる不具合などを洗い出す作業工程があるが、『ドットハック セカイの向こうに』ではシナリオ制作においてデバッグを行ったというわけだ。その出来については、松山氏いわく、試写で観たレベルファイブの日野晃博氏、バンダイナムコゲームスの原田勝弘氏という著名クリエイターが揃って「人間の心理描写やドラマ部分が丁寧に描かれている。“松山洋の新たなチャンネル”だ」と絶賛したほど好評な模様。松山氏自身も「今回は違うチャンネルです。自然な仕草、心理描写など、見ている人にどう感じてもらいたいかを考え抜いて作った」と講義の中で語っており、従来までのサイバーコネクトツー作品とはひと味違った世界を、『ドットハック セカイの向こうに』で見ることができるだろう。
映像表現については、キャラクターのモデリングから背景、アニメーションまですべての面においてハイクオリティーを目指したのは言うまでもない。しかし本作は“フル3D”ということで、苦労もその分多かったと二塚氏は語る。たとえば、立体視では右目と左目用の画像を用意しなければいけなので、制作の作業量は単純計算で倍。加えて、立体視にズレがないかの確認や、左目用と右目用で片方だけに映っている物はないか……といった確認の手間も増大する。しかし、二塚氏らは決して妥協することなく1フレーム単位でチェックを実施。松山氏も納得のクオリティーに仕上げたという。
以上のように映像と脚本ともに細部まで作り込まれた『ドットハック セカイの向こうに』だが、サイバーコネクトツー独自の取り組みも、もちろん複数盛り込まれている。まずは『.hack(ドットハック)』シリーズとしてのつながりだ。映画の時代設定は2024年で、これは2011年に発売された『.hack//Quantum』シリーズの2年後。『.hack//Quantum』の中で起きた事件は、映画で起きる事件にも関連しているという。さらに、今後展開が予定されているゲームプロジェクトでは2025年が舞台になる予定で、そこで描かれる事件は映画とも関連している。「ゲームを遊びたい人は映画をおさえておいたほうがいい」(松山)ということだ。映像表現については、立体視の使いかたをシーンによって差別化している。具体的には現実世界では立体深度が緩められており、ゲームの世界では立体深度を強めてより奥行きのある映像を表現。『.hack(ドットハック)』という現実世界とゲーム世界を並行して描くというコンテンツ力を活かした取り組みと言えるだろう。そのほか、“サイバーコネクトツーらしさ”として松山氏が挙げたのが、スタッフの“○○ごっこ”だ。たとえば劇中で人々が“THE WORLD(ザ・ワールド)”を遊ぶ際に使用する“FMD(フェイス・マウント・ディスプレイ)”を、スタッフが実寸で再現。ただ外見だけを作るのではなく、劇中では語られないパッケージに記された商品情報が書かれており、さらにその内容は2024年という時代設定から予測されるもの(リサイクルマークや注意書きを近未来的に変えるなど)になっていたという。つまり、映画の世界にいる商品開発者“ごっこ”をしていたのだ。もちろん、“THE WORLD(ザ・ワールド)”についてもスタッフが映画内のゲーム開発者“ごっこ”で作り込み、“THE WORLD FORCE:ERA”という最新バージョンを用意。そういった“○○ごっこ”を重ねることで、世界設定に説得力を持たせたのだ。
世界設定の説得力という点ではほかに、徹底したロケハンも実施した。『ドットハック セカイの向こうに』の現実世界は福岡県の柳川と天神がおもなロケーションとなっており、制作陣はそれらの地域にあるさまざまな店舗へ出向き、実名での使用許可を得た。大型のビルはもちろんのこと、バスや電車と言った公共交通機関、さらには老舗の明太子屋、学校で使用している机のサイズ、登場人物が持つバッグや靴まで、リアルに再現されている。土地勘がある人ならば、映画を観る際にはぜひ注目しておきたいポイントだろう。
講義の最後では事前に学生から寄せられた質問に答える質疑応答も実施。その中では松山氏のモノ作りに対する熱い思いもうかがうことができた。フル3Dの劇場映画に挑戦した理由を問う質問には、「いま3D立体視の映画はたくさんあるが、3Dの演出がしっかりと行われているものは少ないと思う」と率直な意見を述べたうえで、「3Dアニメーションのひとつの指針になれるものを作りたかった」と回答。加えて、できあがった作品は3D立体視作品として「超観やすい、気持ちがいい」ので、2Dバージョンの上映は行われないと説明した。また、さまざまな分野でモノ作りをするうえで気をつけることについて問われると、分野ごとのクリエイターの意見を尊重しつつ「ひとつの作品としておもしろいものにしたうえで、ほかのメディアから入ってきた人がニヤリとできる内容にする」という点だけは外さない、松山氏の流儀を紹介。『ドットハック セカイの向こうに』ももちろんその流儀にのっとったもので、「映画を観る前に、ゲームの『.hack(ドットハック)』シリーズを知っておく必要はないです」と断言。「ゲームを遊んだことがない女の子が観ても、おもしろいと思ってもらえる作品を目指しました。ただし、シリーズをすべて遊んでいる人ならニヤリとできる要素は入っています」と万人が楽しめる作品に仕上がったことをアピールした。