●必要なときに必要なデータを配信し、柔軟に更新や追加に対応
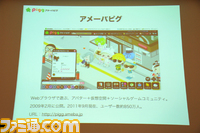 |
2011年9月6日〜8日の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜・国際会議センターにて、ゲーム開発者の技術交流などを目的としたCEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス) 2011が開催されている。
サイバーエージェントが運営するWebサービス“アメーバピグ”がどのように運営され、どのように作られているのかを、同社のインタラクションデザイナーである浦野大輔氏、技術担当執行役員の名村卓氏が紹介するセッション“アメーバピグの作り方〜Flashで作るマルチプレイソーシャルゲーム〜”。この記事では、その模様をお届けする。
 |
まず、クライアントの立場として浦野氏が登壇。“アバター+仮想空間+ゲーム”、“会員数850万人”、“基本無料”、“課金アイテムとしてアバターのアイテムやモーション、家具などを販売”といったアメーバピグの概要を説明した。加えて、ガーデニングをテーマにしたAmeba上のソーシャルゲーム『ピグライフ』についても触れ、「『ピグライフ』はアメーバピグと連動した農園生産型ソーシャルゲームとして200万人が利用しています」と同社のサービスがいずれも好調であることを語った。そのほか「アメーバピグはアバターのアイテムのデザインが肝なので、在籍する100名のスタッフのうち、デザイナーが7名、イラストレーターが30名」と、スタッフの構成についても明かした。
続いて技術面の話に。アメーバピグの特徴として「20代〜30代の女性利用者が多い」と浦野氏。おもな利用者がライトな女性ということで、アメーバピグを手掛ける際に“ブラウザで遊べる”、“低スペックのマシンでも動く”が必須条件だったと語った。さらにアメーバピグは、仮想空間で多人数のユーザーのアバターがコミュニケーションを取るサービスということで、多人数キャラの同時通信表示が可能で、かつ毎日のようにコンテンツを追加し、プログラムを更新できる技術が必須だったと言う。そこでアメーバピグはFlash Playerをプラグインソフトとして利用しているとした。
アメーバピグ内のアプリケーションの構成については、「必要なときに必要なコンテンツを配信するため、プログラム(機能別にモジュール化されたフラッシュ)とコンテンツ(アバターアイテムなど)を分けている」と浦野氏。毎日のように配信されるコンテンツは、現在15000もあるそうで、これらをサーバー上にすべてアップしていると負荷がかかっています。そこで、ユーザーがアメーバピグを起動、ログインしたときに必要なプログラムやコンテンツをその都度サーバーからダウンロードするという仕組みを設けていると説明した。
また、前述のとおり、アメーバピグにおいて、アバターアイテムは重要な要素。そのアイテムだが、「実際にデザインしてサーバー上に登録するまでの過程をイラストレーターが一貫して行っている」と浦野氏。そのため、イラストレーターでも簡単に登録できるように独自の社内ツールを用意しているという。さらに社内ツールではないが、アメーバピグでは毎日“おでかけエリア”が追加されているが、そのマップエディタの編集権限をゲームマスターが持っていて、ログイン中同様の感覚でマップをリアルタイムに編集できる機能も設備しているそうで、運用を効率化する社内ツールの重要性を語っていた。
●つねにコンテンツを更新できる運用のしやすさと品質を維持
 |
浦野氏に代わって登壇した名村氏は、サーバー側から見たアメーバピグの裏側について語った。アメーバピグは多人数が同時通信できることが重要だということは、浦野氏の話にもあったとおり。したがって、技術的な面でも「10000人だろうが10万人だろうが、多人数が同時に接続して遊んでも大丈夫なデータベースが必要」(名村)と、アメーバピグ立ち上げ当初は独自に作った分散データベースを使っていたとのこと。また、「Amebaとは独立したシステムで、完全にソーシャルゲームとして立ち上げている」とし、さらに「Amebaは比較的安定した守りの技術を使っているが、『ピグライフ』はいろいろと新しい技術に挑戦している」と、サーバー側ならではの情報を明かした。
ほかにも、SNSやソーシャルゲームについて「マーケティング分析が大事」だと名村氏。同社ではユーザーがサービス内でどのような行動を取ったのかログ情報を収集しているそうで、『ピグライフ』だけでも1日あたり数億行(このユーザーが誰かと会った、この作物を手に入れたなどのログ)にも上るという。やはりサービス業として、ユーザーの反応は逐一把握しておく必要があるのだ。
最後に名村氏は、ソーシャルサービスにとって大切なことをつぎのように示した。
「リリースすることではなく、リリースしたものを改善し続けること。拡大し続けるユーザーとシステムに耐えうる拡張性と柔軟性を持ち、つねにコンテンツを更新できる運用のしやすさと品質を維持することが大切だ」(名村)
