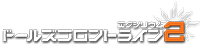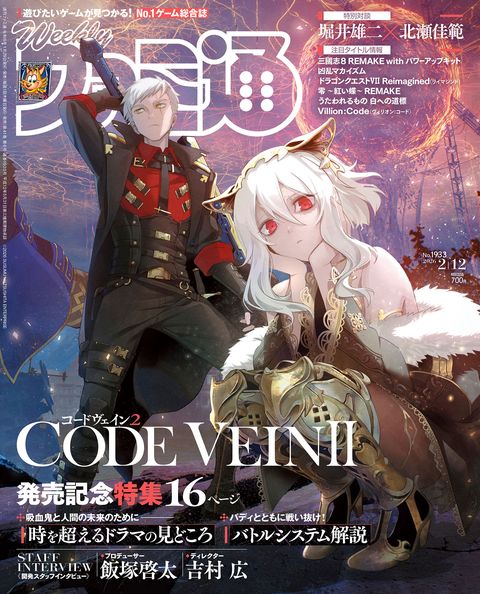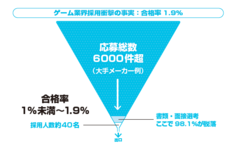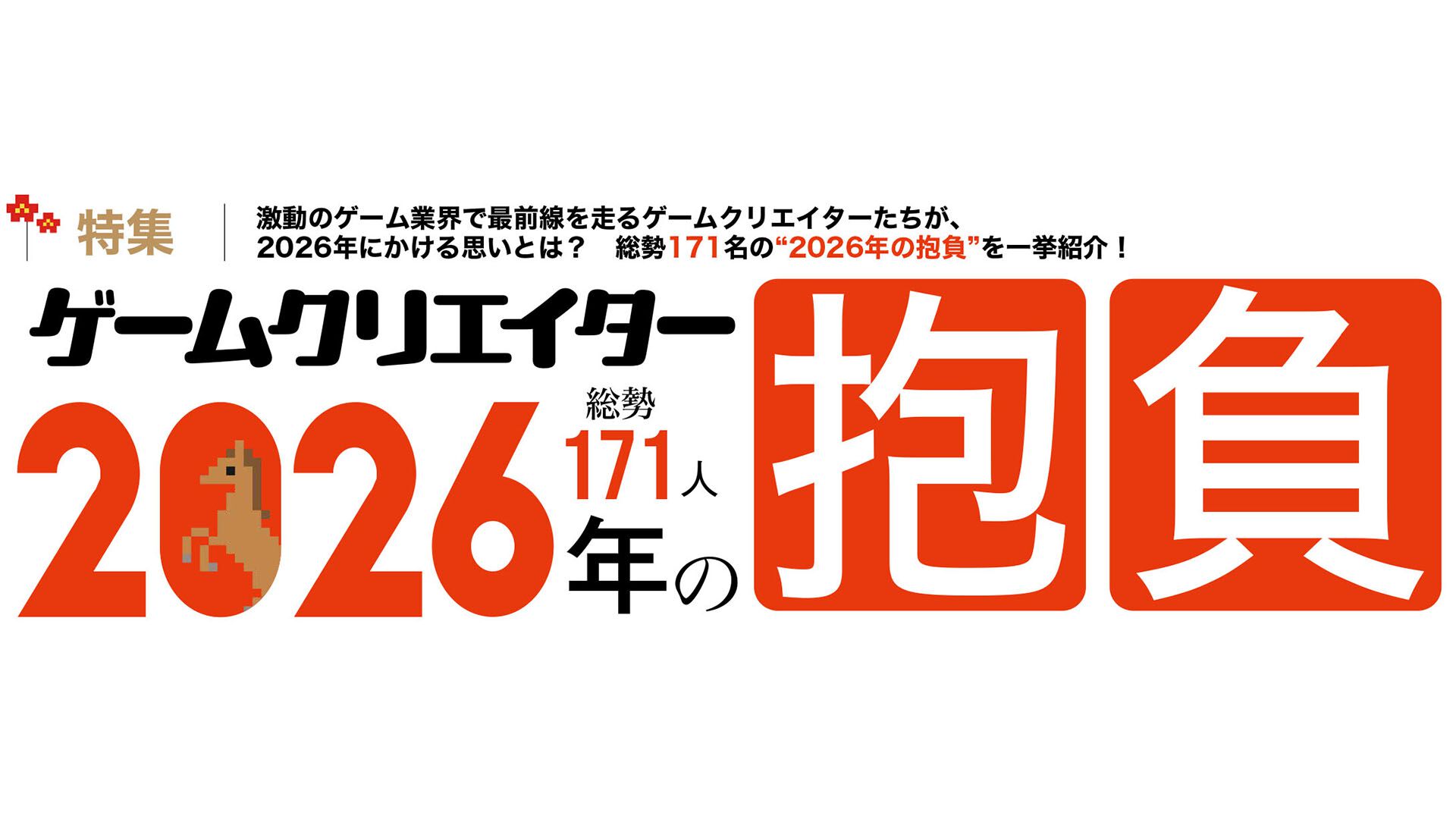最初に書いておく。この記事は広告である。それを差し引いても『アーケロン』(Arkheron)の体験会が最高だった。シンプルに、楽しかった。
このゲームをひと言で表すなら、大人数で遊ぶMOBA風バトロワアクションである。仲間と意思疎通を図りながら戦略を立てて戦う対人ゲーム。ボイスチャットをしながら、あるいはオフラインで仲間と横に並んで遊ぶと、とてつもなくおもしろくなる。
2025年8月某日に行われた先行体験会は、そんな最高の環境で『アーケロン』をプレイできる場だった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4e47cf3c61c47808f9c45b0d1a01fd0d.jpg?x=767)
この記事は『アーケロン』の提供でお送りします。
『アーケロン』の対応プラットフォームはプレイステーション5(PS5)、Xbox Series X|S、PC(Steam)で、9月20~9月22日と9月26日~9月28日にプレイテストが実施される。この記事を読んでテンションを上げたうえで体験してほしい。
レジェ掘りの感動をチームで共有。装備集めのおもしろさを極端に高めたバトルロワイヤル
このたび実施された体験会はメディアとストリーマーを招いた合同イベント。「どうせなら1位を取っちゃいましょう」と、他メディアさんのこの強気の発言に全力で乗っかることに。
『アーケロン』は最大45人でのプレイが可能。3人1組でパーティを組み、15組が同時に同じマップへと降り立ち、最後の1組になるまで戦い続ける。勝ち残るには自分たち以外の14組=42人をぶっ潰さなければならならない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a28220cff15e52b1a02bc230ebbfa8b26.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a0048dabc39d36787bfa0dc6031ad4e82.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a99a68e5d6d384ebb60d1dbf9f2c253dc.jpg?x=767)
会場には名だたるストリーマー陣がずらり。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/af207e0f825122792d94e6c53d5cdfcb3.jpg?x=767)
日韓合同でのイベントであったため、海の向こうでは韓国の有名ストリーマーも参加していた。MOBA界隈では超有名なあのAmbitionとKuroもいたというのだから驚き。
ゲームの序盤をざっくり言えば“レベルアップのないハクスラ&トレハン系ゲーム”がいちばん近いように感じる。
敵チームとの直接対決には確実に勝てるようにしたいので、我々のチームはスタートからキャラ強化に専念することが多かった。レベルアップという概念がない本作では、強い装備を集めること=キャラ強化。フィールドのさまざまな場所にあるチェスト(宝箱)を開けたり大型の敵を倒すことで装備を入手しながら、敵チームとの戦いに備えて動く。
ランダム要素のある収集品を拾う。レアなやつが出たら強いのでうれしい。シンプルに言えばそんな感じだ。いわゆるバトロワ系におけるファームの動き。PvPにおいてはかなり地味な作業なのだが、ここに『アーケロン』ならではの楽しさがあった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a508ae044cbdea325b8ac9681a0dc9e20.jpg?x=767)
『アーケロン』は装備の枠が4個(画面中央下側)。武器が2個とアミュレット、クラウンと呼ばれる装飾品が2個。いまは武器として弓だけを装備している状態だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a87f13fbe978fafa054e5b2e144efc0ae.jpg?x=767)
全部埋まっているとこんな感じ。左側にあるアミュレットとクラウンは、一時的な強化や敵を妨害するようなスキルを持つものがあり、任意での発動が可能。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac9132d4a82c26a8048a9e25341a398de.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a1a06e32798a63c61142b27027747e8ee.jpg?x=767)
たとえば、このクラウンを使うと、スキルによって無敵化しながら移動可能。使用後はクールダウンが挟まるため、連続使用はできない。
基本的には等級の高い武器を求めて……いわゆる“レジェ掘り(レジェンダリー集め)”に近い作業で、強い装備が手に入ったときの喜びをチーム全体で共有できるのがうれしいのだ。「こっちにいいモン入ってる箱ありましたよ!」という報告ひとつでチームが沸くのだから、必然的に探索にも熱が入るし、モチベーションも高くなる。
レジェ掘りの結果を我がことのように喜んでくれる人がいる。それだけでこんなにもファーム作業が楽しくなるとは。これは間違いなく『アーケロン』ならではのおもしろさだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ad9d87ade0176184beadfb9f06f304a85.jpg?x=767)
黄色い箱にはいいものが入っている。これを見つけるだけでチーム全体の士気が上がる。
そしてこの装備集めにおいて、もっとも重要になるのが“エターナル”。アイテム収集が重要なゲームにおけるレジェンダリーとかエピックとかユニークとか、そういう等級の超強い装備だと思ってほしい。
エターナルとは『アーケロン』の世界における英雄たちが扱った武具のこと。「男の子ってこういうの好きでしょ?」と言わんばかりである(大好きです)。シンプルに性能が高いだけじゃなく、装備することでその英雄たちにまつわる特殊効果も発揮する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/af0ef5b1afa5a2c72e866941ee3f0351b.jpg?x=767)
先ほど開けた宝箱には“カリヴ・フォージファイア・クラウン”が入っていた。これもエターナルと呼ばれる装備のひとつ。
エターナルはそれぞれ、その装備を扱った英雄の名前を冠している。たとえば上記の画像に登場している“カリヴ・フォージファイア・クラウン”は、“カリヴ”と呼ばれる英雄の装備だ。
同じ英雄の名前を冠する装備……この例で言えば、カリヴの名前がついた装備をふたつ集めると、固有のセットボーナスが発動する。このボーナスが強力なので、基本的にはこのボーナスを集めるために、チーム全体で協力しながら探索を進めていくのである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/aa47713c50029a306cdadc5e5cee2aee5.jpg?x=767)
『アーケロン』における英雄たち。カリヴは左から3番目のランタンを持った赤いやつ。見た目がゴツくてかなり好き。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/acf67ebd2c37a8fdf791bafe5b992a584.jpg?x=767)
エターナルは同名の装備を入手すると性能が強化される。ほしいエターナルをどれだけ集められるかが勝敗に直結するわけだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a6ef40e3b8a8dd9f4e35c8f6fa23e3e0c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4364dd357d07d716cceb60c9baf83d86.jpg?x=767)
「自分はこのエターナル集めます!」、「なら自分はこっちを!」と報告をしながらゲームを進めるのがね、なんかすごい楽しいんですよ。
伝説の英雄たちの武具を身に着けて戦う。これだけでもグッと来るのに、その先もあるのだからすばらしい。同じ英雄の名前を持つ装備をすべて(武器ふたつ、装飾品ふたつ)集めると、なんとその英雄へと変身できるのだ。ピリオドの向こう側である。
派手なエフェクトとともに体力が全回復し、超強力な固有スキルを使用可能。扱える武器がひとつ増えるようなものなので、当然ながら非常に強い。チームメンバーが装備を揃えた際は全員がお祭り騒ぎだった。
日本三大祭は京都の祇園祭、大阪の天神祭、東京の神田祭と言われるが、ここに4つ目が誕生した。『アーケロン』のエターナル祭りである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/acfe23ca169598e5276fcdb26b72088d2.jpg?x=767)
筆者はあとひとつで“ラヴァ”のエターナルが集まるという状況。「ラヴァの装備! ラヴァの装備ない!?」とチームメイトと探し回り、ついに箱からドロップした瞬間、みんなが雄たけびを上げた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a8a53594165fcd9ae8afae81460f3444f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ab672228e7c8566efd9e23726f7df2a9d.jpg?x=767)
装備することで変身可能に。このときのボイスチャットを確認したら全員変なテンションになっていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4f01d7747ae6c2f9f1dfa5b4cea36747_am8x9O4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a9c6d6414dbb3948074c55c936b321e69.jpg?x=767)
ラヴァは遠距離攻撃に特化したアタッカー。固有スキルでは自身の周囲にダメージ判定を持つカラスを展開可能。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a545a80aa0876c1ad1fb2041fb8019fe4.jpg?x=767)
カラスは敵に飛ばすこともできる。自衛にも火力の補強にも使える便利なスキル。
だが、ちょっと待ってほしい。同種のエターナルを全身に装備して、英雄へと変身することだけが最適解とは限らないのだ。その理由は、同じ種類のエターナルをふたつ装備すると発動するセットボーナスにある。
セットボーナスは2つ装備することで発動し、全身には4つのアイテムを装備可能。つまり、異なる英雄のエターナルをふたつずつ装備すれば2種類のセットボーナスを発動できるわけだ。
変身を狙うと同じ種類の英雄装備を集めることになるため、発動するセットボーナスは1種類のみ。2種類のセットボーナスで強化して汎用性を高めたほうがいい場面もあるため、“ただ同じ英雄の装備を揃えればいい”というわけじゃないのが『アーケロン』の深いところでもある。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a9fdddca8e9c2e5486c382ebfe4db3f73.jpg?x=767)
エターナルを集めて変身すると装備枠の交換はできなくなる。ほかのセットボーナスが欲しくてもどうにもならない。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a99ff31e4e71649a519d8235ed78b3acf.jpg?x=767)
終盤まで残ったパーティーの中には、2種類のセットボーナスを意識して装備を組んでいる人も多かった。
このゲームにおいて、キャラクターの基本性能に差は一切ない。全プレイヤーが“エコー”と呼ばれるプレーンな性能のキャラを使用し、道中の装備からビルドを組んでいくわけだ。
遠距離攻撃ができる武器を持てば遠距離担当になるし、近距離攻撃かつブリンク系(瞬間移動=短距離のワープ)ができる武器を持てばスピードタイプのキャラクターになる。最初に選んだキャラクターの性能にあった装備を探す……のではなく、その場そのときに引いた装備から、パーティ内での立ち回りを考えることになる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a39f1d1d955cfea401160882402dd8cd3.jpg?x=767)
バトロワには“ファーム”と呼ばれる戦闘準備の段階がある。そこにしっかりと楽しさを用意されているのが印象的だった。
「あー、いま後衛やれる人いないですね。自分そういう武器出たらやりますよ」
「じゃあ自分はもっと固めにして前衛張れるようにしますね。コレとコレが出たら声かけてもらえるとうれしいです!」
みたいな会話をしながらパーティを組み上げていくのが非常に楽しい。運の要素が強いものの、ただの運ゲーに終わらず、連携と意思疎通で戦略へと昇華させていく感覚がたまらないのだ。
バトロワ系のゲームらしいチームゲームの楽しさをしっかり保ちながら、ハクスラ&トレハンのランダム性をきれいにマッチさせている。そこが『アーケロン』をやっていていちばん魅力的に感じた部分だ。
運だけがよくても勝てるわけじゃない。戦闘では連携と個人の実力が試される
……で、「大口叩いてたお前らは1位取れたのか」という話。たいへん残念ながら1位は取れずじまい。かなり惜しいところまではいったのだが、さすがにそううまくはいかなかった。
というのも、筆者たちのチームはわりと探索メインで動いていたこともあり、いざ戦闘になったときに、しっかりと勝ち切れなかったのだ。積極的にアクションを仕掛け、しっかりと敵を倒したチームが勝つ。この辺りはちゃんと“うまいヤツが勝ち残る”ようになっているということなので、ゲームとしてはとても健全に思える(めちゃくちゃ悔しくはあるものの)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a90e21d40285b5921ec9137259f0e4a5d.jpg?x=767)
いちばん勝ちまくっていたのは、とあるMOBAタイトルでプロ選手だったAmbition氏とKuro氏がいたチーム。かたや元世界王者、かたや世界の最前線を戦っていた選手であり、「勝てるわけねーだろ!」というメンツである。
戦闘することのメリットは、なによりも倒した敵の物資を奪えることにある。敵を倒すとその時点で装備していたアイテムが全部ドロップ。これまでの探索で得たものを全部奪えるわけだ。だからこそ、“戦闘に勝てるヤツが強い”のである。この辺りは、バトロワ系によくある不文律だと思ってほしい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a85655b07efd4e6eb09e42bcefbb5b6de.jpg?x=767)
激戦の後にはそこら中にエターナルの装備が散らばる。戦利品を選んでいるときの気持ちよさたるや。
ちなみに、逃げ続けて一度も戦うことなく勝ち残れるなんて都合のいい話はない。必ず戦闘が起こるタイミングが用意されている。
バトロワ系ゲームでは、徐々に安全圏が小さくなって接敵回数が増えて……というのが定番だが、本作ではちょっと違う。ざっくり言うならばラウンド制で、1ラウンドごとにマップが切り替わる。つぎのマップへ行くにはフィールド上にある“ビーコン”のもとへ行かなくてはならず、そこで各チームが鉢合わせるようになっているわけだ。
ひとつのビーコンで移動できるのは1チームのみ。同じビーコンを利用しようと2チームが鉢合わせた場合は、その場で戦闘が勃発する。マップ自体は塔をモチーフにしており、勝者のみがつぎの階層へと移動できるのである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ae7049ccde9e6c239e1379ea734802444.jpg?x=767)
鉢合わせた別のメディアチームと覇を競い合っている図。進軍をかけた戦いにおいて、慈悲は不要である。
そうしてラウンドごとにだんだんビーコンの数が少なくなっていき、最後には2チームが残される。その2チームは塔の最上階に招待され、生き残りをかけた最終戦を行う。勝ち残ったほうが、見事そのマッチの勝者となる。
ビーコン自体は数が決められているものの、1ラウンド目は比較的数が多く、かぶることは少ない。2ラウンド目、3ラウンド目と進むにつれてどんどん減り、生き残りをかけた戦いは熾烈になっていく。時には3、4チームでひとつのビーコンを争うことすらある。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/adc7b5c0154b98c5ba7e2cf465865f0f9.jpg?x=767)
我々メディアチームと日本ストリーマーチーム、韓国ストリーマーチームによる三つ巴の戦い。激戦になるとボイスチャットでのやり取りにもどんどん熱が入り、非常に楽しい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac8dda5e6f0ff1775f00464c90772fe7a.jpg?x=767)
「右から回ります! 挟み撃ちに!」、「了解!」みたいな一瞬のやり取り。この即興での連携が決まったときは本当に気持ちいい。
後半にいくにつれどんどん戦いが激しくなっていく構造のおかげで、プレイするうえでのおもしろさが担保されているのは言わずもがな、観戦時のわかりやすい盛り上がりポイントでもある。前半がピークで後半は消化試合なんていうのはどうにも試合として映えないが、『アーケロン』はその辺りもしっかりコントロールできているように思う。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a158b7098b9670c57ea15351ab9ef6ae0.jpg?x=767)
最終戦まで残るチームはエターナルを大量に集めて強化していることが多いため、後半は大規模なスキルがぶつかり合うことになる。
と、ここまで戦闘が起こるメカニズム的な、システム面の解説になってしまったが、操作難度についても簡単に記しておこう。個人的な感覚にはなるが、『アーケロン』の操作にそこまでの複雑さは感じない。キャラクターはキーボードのWASDで操作して、マウスの方向に武器の攻撃が飛ぶ……という基本的なことさえ理解していれば、大してハードルは高くない。
なので重要なのは武器の知識。そしてエターナル装備の特殊な行動をどのタイミングで使うかという判断力だ。もちろん細かく動いて敵の攻撃を避けるのも重要ではあるが、個人的な印象ではやはり判断力と知識量が物をいうゲームだと感じた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac29f3ce1919245faf10885c12bdadcba.jpg?x=767)
ほかのプレイヤーのスキル発動タイミングを見て「うまい!」と感じることが多かった。
『アーケロン』から感じる、“競技的”な盛り上がり。
体験会は約5~6時間ほど。終わった後もチームメイトと「まだやりたりない」「なんとかしてあと3時間ぐらい延長できないか」と、熱く感想を語り合ってしまうぐらいのおもしろさだった。プレイするほどに“いま、何をするべきか”が明確になっていき、いろいろな戦術を試したくなってしまう。それが本作の持つ深みだ。試合を重ねるたびにうまくなっていく実感が蓄積されていき、これが思いのほか心地いい。
……ただ、やはりプレイヤーとしての成長具合は名だたるストリーマー陣のほうがよっぽど上で、試合を重ねるたびに手も足も出なくなっていったのだが。まあ、ちゃんとゲームがうまい人が勝つのはゲームデザインとしてとても健全であり、競技性が担保されている証だろう。悔しいがそういうことにしておこう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a32b854a82d66893d95fc823dc18af488.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a98b06ed74257a42667a1de5a8f4d27fa.jpg?x=767)
日本勢で勝ち残ったのはSHAKA氏、らいじん氏、ふらんしすこ氏によるチーム。非常に素晴らしいプレイングで最終戦を勝ち切った際、会場からは大きな拍手が巻き起こった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a46c35aa00fbaa5230324bee2e3f8d5eb.jpg?x=767)
とはいえ、やっぱり勝ちきれなかったのは悔しい! とりあえず当分は、「おれ、AmbitionとKuroといっしょにゲームしたんだよね」というのを誇りにして生きていこうと思う。
競技性がしっかりとしていることは、だ。チャットやボイスチャットでの綿密なコミュニケーションが求められるということでもある。戦闘時の立ち回りは仲間の動きからある程度は把握できるが、装備の受け渡しは無言では難しい。今回ご一緒させていただいた他メディアの方はこういった対戦ゲーム慣れした楽しい方々であったため、たいへん快適だったが、いわゆる野良(ソロでのプレイ)でゲームをした際、同じぐらい楽しめるかどうかは断言しがたい。意思疎通さえスムーズなら、このうえなく楽しいゲーム体験ができるのは確かなのだが。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a53cd9531e975bf35f0904f73599a25ca.jpg?x=767)
すばらしいゲーム体験だった。同席した各メディアの皆様に、改めて感謝を述べたい。
最後は冒頭にも書いたひと言で結ぼう。『アーケロン』のプレイは間違いなく最高だった。この熱狂を手軽に体験できるときが待ち遠しい。
手軽に体験できるとき。直近で言えばプレイテストである。9月20日~9月22日と9月26日~9月28日に実施予定なので、公式X(Twitter)での詳細発表を楽しみに待っていただきたい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a609d593bc8f525cdcd9e96ee19d499ff.jpg?x=767)
なお、今回の体験会はマウスコンピューターが協賛。ゲーミングPCブランド“G TUNE”のハイスペックゲーミングPC総数11台の端末支援を受けていた。PC版はスペックの高いモデルで遊ぶに越したことはないので、参考までに使用PCを紹介しておく。
G TUNE FZ-I7G70
G TUNE FZ-I7G7T
G TUNE FZ-I9G80
G TUNE FG-A7A70
G TUNE FG-A7A7X
G TUNE FG-A7G70
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4e47cf3c61c47808f9c45b0d1a01fd0d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a28220cff15e52b1a02bc230ebbfa8b26.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a0048dabc39d36787bfa0dc6031ad4e82.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a99a68e5d6d384ebb60d1dbf9f2c253dc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/af207e0f825122792d94e6c53d5cdfcb3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a508ae044cbdea325b8ac9681a0dc9e20.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a87f13fbe978fafa054e5b2e144efc0ae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac9132d4a82c26a8048a9e25341a398de.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a1a06e32798a63c61142b27027747e8ee.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ad9d87ade0176184beadfb9f06f304a85.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/af0ef5b1afa5a2c72e866941ee3f0351b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/aa47713c50029a306cdadc5e5cee2aee5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/acf67ebd2c37a8fdf791bafe5b992a584.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a6ef40e3b8a8dd9f4e35c8f6fa23e3e0c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4364dd357d07d716cceb60c9baf83d86.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/acfe23ca169598e5276fcdb26b72088d2.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a8a53594165fcd9ae8afae81460f3444f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ab672228e7c8566efd9e23726f7df2a9d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a4f01d7747ae6c2f9f1dfa5b4cea36747_am8x9O4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a9c6d6414dbb3948074c55c936b321e69.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a545a80aa0876c1ad1fb2041fb8019fe4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a9fdddca8e9c2e5486c382ebfe4db3f73.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a99ff31e4e71649a519d8235ed78b3acf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a39f1d1d955cfea401160882402dd8cd3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a90e21d40285b5921ec9137259f0e4a5d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a85655b07efd4e6eb09e42bcefbb5b6de.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ae7049ccde9e6c239e1379ea734802444.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/adc7b5c0154b98c5ba7e2cf465865f0f9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac8dda5e6f0ff1775f00464c90772fe7a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a158b7098b9670c57ea15351ab9ef6ae0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/ac29f3ce1919245faf10885c12bdadcba.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a32b854a82d66893d95fc823dc18af488.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a98b06ed74257a42667a1de5a8f4d27fa.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a46c35aa00fbaa5230324bee2e3f8d5eb.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a53cd9531e975bf35f0904f73599a25ca.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/52435/a609d593bc8f525cdcd9e96ee19d499ff.jpg?x=767)