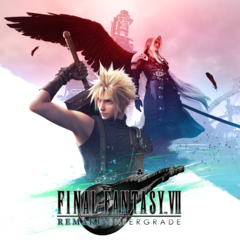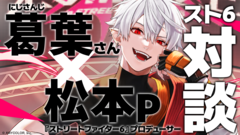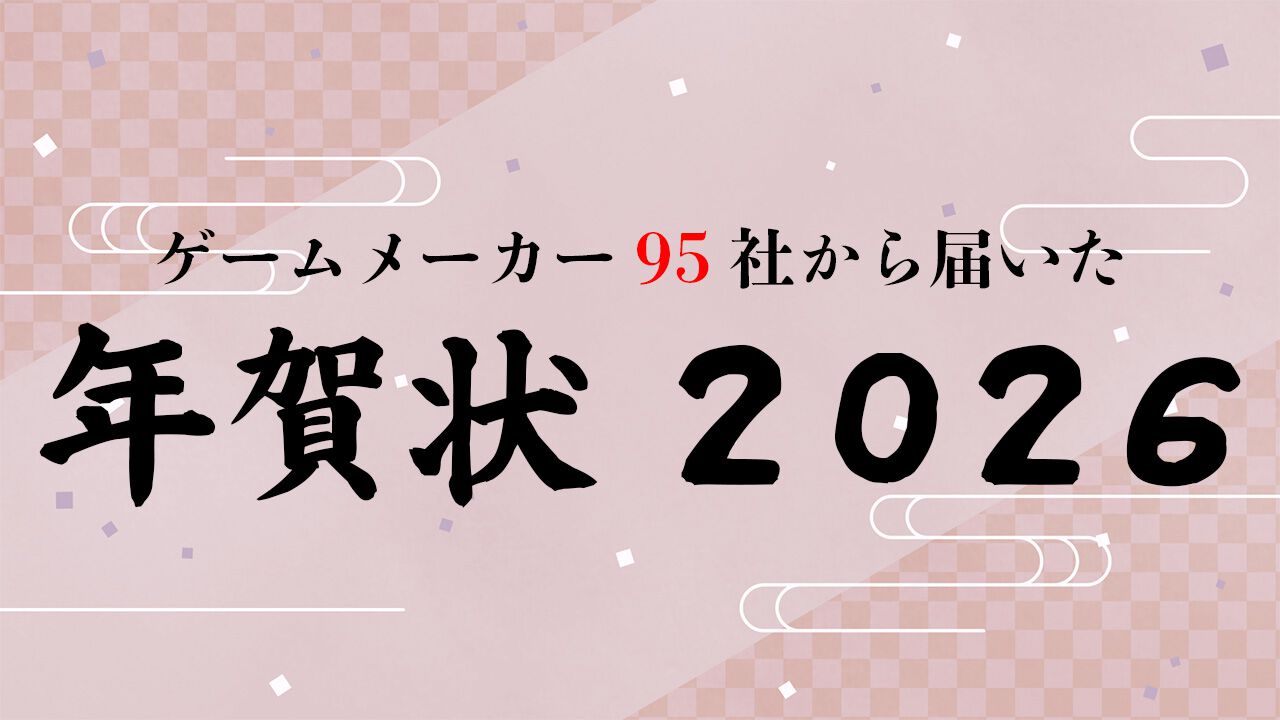本稿では、ゲームの概要に加え、南北アメリカ限定で開催されたアルファテスト版をプレイした独占インプレッション、そしてBungieが現在直面している課題について詳述する。
なお、リリース時の対応機種はプレイステーション5(PS5)、Xbox Series X|S、PCとなっている。
惑星タウ・セティIVを舞台にしたランナーの生存戦略とゲーム概要
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/ac270eb7dd0e8b6b2e46e7b8efb3a1362_Z8msZlo.jpg?x=767)
エクストラクションシューターというジャンルは、『Escape From Tarkov』(エスケープ フロム タルコフ)のようなコアゲーマー向きか、カジュアルに寄せたタイトルのふたつの傾向に分かれる。『Marathon』には『Apex Legends』を彷彿とさせる3人1チーム制やキャラクター固有のスキル、死亡後のリスポーンといったバトルロイヤル的な要素も取り入れられており、カジュアルなプレイヤー層をターゲットにしていると見られる。
最大で6チーム、合計18人のプレイヤーが同一マップにスポーンし、各マッチは25分以内の制限時間で展開する。このジャンル特有の仕様として、死亡時には獲得した戦利品を含む装備の大部分を失うという高いリスクが存在し、これが毎回のプレイに強い緊張感を与える。
『Destiny』の系譜を継ぐランナーシステムとヒーローシューター的アビリティシナジー
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a365827bfb4dc6a8eedae87269a810331_hzKxqCN.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a0b4a218c4aac2671e59121f32cc06691.jpg?x=767)
ウォーロックがどこに行ったのかは考えてはいけない。製品版のローンチ時には、さらにふたりのランナーが追加される見込みなので、多分そこにウォーロックの系譜があると期待しよう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a47c43e370d1b44bb893980f7bdadf2b6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a90c61a8453cba8a9f8c2ca0c137fbade.jpg?x=767)
探索と戦闘、そして脱出をくり返すコアゲームプレイ
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a29ba3d9f6738f576196988adf7833924.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/af432d6390991b2aade984a17f3775ea1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a7d1b89a0a4d80e35bafad8fb43da4eac.jpg?x=767)
ただし、簡単な任務をソロでこなす際には、あえて軽装で挑む方が効率的な場面も存在する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/ad535d91f3baaaf490250e7110550fb56.jpg?x=767)
Bungie印の卓越したガンプレイと武器カスタマイズ
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/ae1b26ea6dfb5d4679e0953ffab925bf7.jpg?x=767)
まず称賛すべきは、Bungieの真骨頂とも言える銃撃戦のクオリティだ。銃声、リコイル、着弾感、各武器の個性など、射撃に関するあらゆる要素が心地よく調整されており、撃つこと自体の爽快感は特筆に値する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/af0fb1a147ed9f7707b21a2793057b4e4.jpg?x=767)
筆者は2点バーストの“Twin Tap”という武器を好んで使用していたが、遠近両用で高い性能を発揮し、非常に頼りになる存在だった。それだけに、失った際の喪失感もまた大きかった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a89c65c425cc91b5e83de4c75b47bcdde.jpg?x=767)
強烈なアートディレクションと独特すぎるUI/UX
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a68a2062e1b50dc0dff1bb6ef05ad7825.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a71525d4da520cc6367ed4c9abd106925.jpg?x=767)
一方で、屋外のフィールドでは画質設定による変化があまり感じられなかった。これがデフォルトでフィールドのグラフィック負荷が抑えられている設計なのか、あるいはアルファ版特有のレンダリングの問題なのかは現時点では判断できない。
コンソール展開の意義とチート対策への高まる期待
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a2199897fdf188470b1c7541baf8f51e0.jpg?x=767)
エクストラクションシューターに限らず、PCで展開される多くの対戦型シューターは、依然としてチート行為という深刻な問題に直面している。Bungieは『Marathon』のアンチチートシステムとして、『Destiny 2』でも採用している“BattleEye”を採用しているものの、現状ではいかなる対策も不正行為を完全には防ぎきれないのが実情だ。一度のデスで多くを失うエクストラクションシューターにおいて、チーターによって倒されることほど不条理な体験はないだろう。
開発側は『Marathon』を基本プレイ無料ではなく有料タイトルとすることで、チーターの参入障壁を上げようとしているが、これだけで問題が解決するとは考えにくい。有料タイトルであってもチーターの存在は後を絶たないからだ。
しかし、ここでコンソール版の存在が大きな利点となる。コンソールはPC環境と比較してチート行為が格段に少ない傾向にある。さらに有料タイトルとなれば、不正プレイヤーの参入はより困難になるだろう。Bungieがプレイステーションファミリーの一員であることを考慮すれば、PlayStation Plus会員向けの割引や特典などを提供することで、コンソール版の優位性をさらに高めることができるのではないだろうか。
ソロプレイにおける障壁とチームの重要性
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a8c8e5faefd4f441a9708c7b0928c322b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/aacda8230577dc76386c5e7d7ec143c9b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a7da00498bcc8b6510d3b4777f1610e60.jpg?x=767)
ジャンルにおける新規性と“平凡さ”というジレンマ
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a1b40c8dd4ecd53311c64fef4dd8f9e63.jpg?x=767)
ところが、根幹となるゲームプレイはほかのエクストラクションシューターと大差なく、率直に言えば、際立ったビジュアル以外の新規性や独自性に乏しい印象を受けた。たしかに射撃の感触は素晴らしいが、エクストラクションシューターは絶えず銃撃戦が発生するタイプのゲームではない。また、前述の通りアートデザインは個性的だが万人にアピールするものでもない。こうした中で有料タイトルとして展開し、どのようにしてプレイヤーを継続的に惹きつけ、コミュニティを維持していくのか、疑問が残る。
開発体制を揺るがすアセット無断流用問題と懸念される影響
筆者が再三言及してきた『Marathon』の際立った特徴であるアートデザイン面において、残念ながらBungieの元デザイナーによる、別のデザイナーAntireal氏の作品の無断流用が発覚した。具体的には、Antireal氏が2017年に制作したポスターの一部が、そのままゲーム内アセットとして実装されていたのだ。
the Marathon alpha released recently and its environments are covered with assets lifted from poster designs i made in 2017.@Bungie @josephacross pic.twitter.com/0Csbo48Jgb
— N² (@4nt1r34l) May 15, 2025
Antireal氏がXで告発すると、Bungieは迅速に事実確認を行い、元デザイナーが無断流用した事実、そして社内の誰もがその事実に気づかぬまま実装に至ったことを認めた。後日、予定されていた公式配信において、アートディレクターのJoseph Cross氏がこの件について公に謝罪。Antireal氏本人にも個別に謝罪が行われ、現在両者間で協議が進められているとのことだ。
We immediately investigated a concern regarding unauthorized use of artist decals in Marathon and confirmed that a former Bungie artist included these in a texture sheet that was ultimately used in-game.
— MarathonDevTeam (@MarathonDevTeam) May 16, 2025
ここで補足しておきたいのは、『Marathon』全体のアートスタイル自体はAntireal氏個人の創作物というわけではなく、1990年代から続くデザイン潮流を汲むものであるという点だ。Cross氏自身も10年以上前に、類似のテイストを持つ作品を発表している。したがって、『Marathon』のすべてが無断流用であるかのような誤解は避けるべきであり、問題はあくまで一部アセットの盗用である点に留意されたい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/42744/a365827bfb4dc6a8eedae87269a810331.jpg?x=767)
発売前からこれほどネガティブな評価を受け、問題となった部分の修正作業も不可避となった今、果たして『Marathon』は当初の予定通り2025年9月24日に無事リリースされるのだろうか。また、仮にリリースされたとして、この一件がプレイヤーの心象に与える影響を考慮すると、多くのユーザーを長期間惹きつけられるのか、依然として大きな不安が残るので問題の解決に期待したい。




![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)