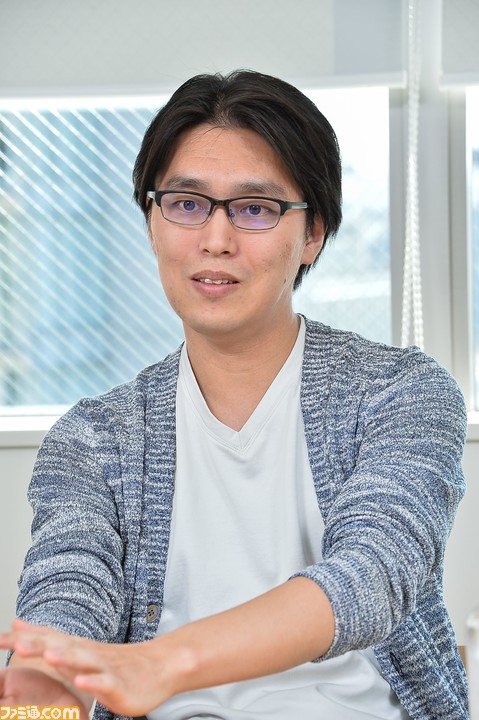“ファミキャリ!会社探訪”第84回はヒストリア!
ファミ通ドットコム内にある、ゲーム業界専門の求人サイト“ファミキャリ!”。その“ファミキャリ!”が、ゲーム業界の最前線で活躍している、各ゲームメーカーの経営陣やクリエイターの方々からお話をうかがうこのコーナー。今回は、ヒストリアを訪問した。
2013年に設立されたヒストリアは、アンリアルエンジンでのゲーム開発にこだわったデベロッパー。最近では、アーケードゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』やプレイステーション4用ソフト『Caligula Ovedose/カリギュラ オーバードーズ』などの開発を手掛けている。今回は、同社を起業した佐々木瞬氏を始め、アート部門の黒澤徹太郎氏、エンジニアの馬場俊行氏に話を聞いた。
佐々木 瞬(ささき しゅん)
(株)ヒストリア
代表取締役
プロデューサー / ディレクター
黒澤 徹太郎(くろさわ てつたろう)
(株)ヒストリア
アートディレクター / テクニカルアーティスト
馬場 俊行(ばば としゆき)
(株)ヒストリア
エンジニア / レベルデザイナー
アンリアルエンジンでの開発1本で起業
――まずは皆さんがどういった経緯でゲーム業界を目指し、業界に入られたのかを教えてください。
佐々木私は学生時代からゲームが好きで、とくに中高生のころはよくゲームを遊んでいました。それでゲームを作ったり、シナリオを作ったりする仕事がしたいと思っていて、ゲームの専門学校に入って企画科で勉強をしました。
――最初からゲーム業界を目指されていたんですね。
佐々木そうですね。高校2年生のときから専門学校の見学会などにも行っていました。専門学校では、最初はシナリオに興味があったのですが、授業の課題でゲームを作ったときに、ゲームを作ること自体がとても楽しいと感じたんです。
新卒のころは2D系のゲームを作っていたのですが、家庭用ゲームの主流が3Dになりつつあるときだったのと、技術的にも興味があったので3D系の会社に転職しました。それまでは企画職だったのですが、そこでなぜかエンジニアになったんですよ(笑)。そのままプログラムのリーダーなどを経験して、その後2013年に独立してヒストリアを立ち上げました。
――企画からエンジニアになられたのは、佐々木さんの希望だったのですか?
佐々木単純にスタッフが少なかったのです(笑)。プログラム自体は学生時代に趣味で少し触っていたので、いろいろと教えてもらいながらやっていました。ただ、それがすごく楽しくなっていったんです。
独立し、起業を考えたのが、ちょうどアンリアルエンジン4が出るタイミングで、アンリアルエンジン自体が非常に魅力的だったというのが大きいのですが、会社を立ち上げるなら特徴を持ちたいと思っていたので、アンリアルエンジン一本で作っていくことに決めました。
――ヒストリアさんの設立が2013年ですが、当時はまだエンジンとしてはユニティを使う会社が多い印象でしたね。
佐々木そうですね。当時はアンリアルエンジンを開発したエピックゲームズさんの日本支部、エピックゲームズジャパンさんにも3人ぐらいしか人がいないときだったんですけど、そのころから連絡は取っていて、「アンリアルエンジン一本で行きます」というお話はしていました。
アンリアルエンジンを盛り上げるというようなことも手伝わせていただいて、会社も次第に大きくなっていった、という感じですね。
――御社のホームページでは、トップに“アンリアルエンジン専門のゲームデベロッパー”と出てきますよね。
佐々木それも弊社の特徴的な部分かなと思います。
――黒澤さんがゲーム業界を目指した経緯を教えてください。
黒澤僕も昔からゲームが好きだったのですが、美術系の大学に行くために勉強をしていたこともあって、あまりゲームをせずに美術にどっぷりという時期もありました。大学を卒業したくらいのタイミングで、3Dソフトがおもしろいと思って触ってみたりしていて、せっかく3Dソフトが使えるようになったのだから仕事にしようかな、と地元で3D系の仕事をしていました。
その後、時間ができたのでまたゲームを遊ぶようになったのですが、3Dを使ったゲームの表現の進化に感銘を受け、映像からゲーム業界に移ってきたという感じです。
――ちょうどポリゴンが出てきて、ゲームの映像表現が大きく変わってきたころだったんですね。
黒澤そうですね。映像とゲームは、交互に技術の進歩で追い越し合っているという部分があるのですが、当時はちょうどスカルプトやノーマルマップがゲームに使えるようになったばかりで、映像の技術をゲーム業界に持っていくというようなかたちで、タイミングよく別業種に入ることができました。
――黒澤さんはヒストリア入社以前からアンリアルエンジンを触っていたのですか?
黒澤趣味でもCGを触るのが好きなんですけど、アンリアルエンジン4が発表されたタイミングから注目していて、ひとりでゲームを作れないかなと考えていたら、ヒストリアでちょうど“UE4ぷちコン”(※)をやっていたので、作ってみて応募したんです。
※UE4ぷちコン:ヒストリアが主催する、アンリアルエンジンの学習を目的とした一般参加型のゲームを中心とした作品制作コンテスト。参加者は約1ヵ月の短期間でテーマに沿った作品を制作して投稿する。
――UE4ぷちコンをきっかけに入社を?
黒澤そうですね。ぷちコンで触ったことをきっかけにアンリアルエンジンを使って仕事をしたいなと思い始めていて、ちょうど佐々木と共通の知り合いもいたので、会社見学に来て、そのまま入社を決めました。
――なるほど。馬場さんはいかがですか?
馬場僕もゲームは小学生のころから大好きで、高校の進学先を考えたときにも、将来ゲーム作りを仕事にしたいと思っていたんです。そこからはゲームを作るために情報系の工業高校に入って、プログラムを勉強していました。
――そのままゲーム業界に進まれたのですか?
馬場いえ、一度自分で勉強をしながらゲームを作りたいと思って、最初はまったく違う業界に就職して、休日に趣味でゲームを作っていました。そして、もっとちゃんとしたゲームを作りたいと思うようになって、ゲームの作りかたを教えてくれる専門学校があることを知ったので、それをきっかけに上京。専門学校を出てからゲーム会社に入社しました。
その会社ではアンリアルエンジン3を使っていました。先ほども話に出ていたように、当時はアンリアルエンジン3を使っている会社がそんなに多くなったので、そこで佐々木ともつながりができてきました。
――それでヒストリアさんに転職を?
馬場ヒストリアに入る前に、前の会社を辞めてから一定期間あり、そのあいだは趣味でゲームを作っていました。しばらくして貯金もなくなってきたので、そろそろ就職しないとな、と(笑)。
佐々木クレイジーだなぁ(笑)。
馬場そのときに前の会社の社長から、佐々木が会社を立ち上げて人を集めているという紹介があり、会社説明会に行って、そのまま入社することになりました。
――おふたりはヒストリア入社後はどのような業務をされているのでしょうか?
黒澤以前の会社では、キャラクターやキャラクターアニメーションの管理と実務が多かったのですが、最近はアンリアルエンジンの特性もあって、もう少し根本的な部分でマテリアルや質感表現をいじっています。わりとエンジニア寄り、テクニカルアーティストという感じの業務が増えていますね。タイトルによってはアートディレクターを務めていて、足りないアートの部分をどうするか決めたり、コンセプトアートを描いたりといった仕事を中心に行っています。
馬場僕はプログラマーとしてプログラム全般をやっていて、業務としてはリードプログラマーになることが多いです。以前は出向で別の会社に行って、レベルデザインのチーム内でプログラム、仕組みを作る仕事をしていたので、そこで学んだレベルデザインのワークフローなどを持ち帰って、社内でレベルデザインをしたり、その監修をすることもあります。最近では若い子の教育や研修も増えてきているので、そういった部分も業務としては出てきていますね。
――ヒストリアの業務形態について教えてください。
佐々木起業してから6年半ほど経ちましたが、いまでは1タイトルを丸ごとパブリッシャーさんからまかせていただくことが多いです。企画からプログラム、グラフィック、UIなどの制作機能は持っていて、コアな部分は自社で作って、サウンドやそのほかの部分はパートナー企業さんといっしょに作っています。家庭用ゲームとアーケード、VRの3つを軸にして、丸請けの仕事を中心に行っています。
最初は数枚の企画書がクライアントさんから来ることが多いです。それを見てからディスカッションに入って、その段階で予算感はすでにあるので、「こういうプロトタイプを作ってみますか?」とこちらから仕様の提案をしていきます。このタイミングで簡単な、グレーボックスと呼ばれるものを出したりして、ゲームデザインや企画面を詰めていきます。弊社の場合、プロトタイプの段階で、このパートはあの会社さんが強いから、そこといっしょにやりたいね、みたいに巻き込んでいくことが多いです。
黒澤会社の方針的にグラフィックの量産部分をすべて抱えるようなスタイルではなく、まかせられるものは他社さんにお願いするようにしているので、協業になる部分はグラフィックがいちばん多いと思います。
アートが得意な会社さんなら、最初からその部分をおまかせしていっしょに作っていきます。エフェクトが扱える人間は社内にもいますが、ずっとエフェクトだけやるわけにもいかないので、そういうときはエフェクトに強い会社さんなどに最初から入ってもらったりしています。
――協力する会社はクライアントではなくヒストリア側で決めるのですか?
佐々木弊社が主導で決めています。本制作の量産段階に入ってから入ってもらうより、プロトタイプの段階でリーダー的な人にひとり入っていただくという流れが理想的なので、弊社ではそういう座組にすることが多いです。協力会社のアサインが済んだら、あとはプロトタイプを作って、本制作に進んでいきます。量産計画のなかで足りていない部分を、ここはこの会社さんにお願いしましょう、みたいなことを進めつつ。
――制作されるゲーム、ジャンルの幅も広いですよね。
佐々木そうですね。アーケード用ゲーム『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』はネットワーク対戦アクション、『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』はRPG、VRタイトルの『Airtone』はリズムゲームと、いろいろなものを作っています。
開発規模はやはり小中規模で、いわゆるAAAタイトルの方向にはいかず、基本的に1チームが大きくても社内で20~30人。小さいチームは各役職にひとりの3人構成などになっていて、それで1タイトルを作る規模でやっているのがひとつの特徴であり、方針ですね。
――起業して6年以上となると、佐々木さんの立場は徐々に経営面にシフトし、現場からは遠ざかっていくような印象がありますが、実際はどういった感じですか?
佐々木完全に現場から外れることはないと思います。ゲーム作りをメイン事業としているので、やはり現場知識のアップデートは必要ですし、そこを理解しているからこそできる経営、リクルートがあると思います。
弊社はイベント運営なども行っているのですが、それも現場の感覚がわかっているからできることが多いので、制作現場から抜けることはしばらく考えていません。ただ、現状ではまだ自分がやりすぎている部分が多いかな、という思いはあります。
『ジョジョの奇妙な冒険』のような大きなIP(知的財産)をまかせていただけるようになって、現在進行形で会社が成長しているところです。社員たち個々人の成長もすごく実感しているので、順々にステップを踏んで権限を渡していければと考えています。いまの状態で「すべてまかせた!」とやるとムチャぶりになってしまうので、順々と。
――他社さんとの協業タイトルであれば、それはなおさらですよね。
佐々木外部の方との関係なども含めて、難度が高いですからね。ただ、いまはこういうタイトルをやってみたいといった挑戦ができるようになってきたので、そこでほかの人が育っていき、プロジェクトをひとつずつ渡していけるように努力しています。
――設立10年目に向けて、そういったことも徐々に進められていると。
佐々木今回の記事の趣旨とは少しずれるかもしれませんが、非ゲームの部門も立ち上げています。そして、その先にはゲームのパブリッシングにも手を出したいと考えています。新規事業の確立にもう少し自分のリソースを割いていく必要があると感じています。まだまだ成長期が続く予定です。
アンリアルエンジンが社内の共通言語に
――御社を語るうえで欠かせないアンリアルエンジンですが、そもそもどうしてそこまでアンリアルエンジンにこだわっているのでしょうか?
佐々木やはり、まずアンリアルエンジンが非常によくできているところです。開発者にとって本当に魅力的なツールで、自分もエンジニアになりたてのころはとくに、どちらかというとアンリアルエンジンを使うことで学ばせてもらっているところがたくさんありました。ある意味、ひとつの“正解”なんですよね。洗練されていて、教科書でもあるというか。アンリアルエンジンはソースコードが公開されており、このような一流のコードを見ることができる機会もなかなかないので、そういうことも含めて魅力的です。
――エンジンとして純粋に魅力的なんですね。
佐々木それと、ひとつのツールに社内のみんなが精通していて、高いレベルで社内の技術交流が行えることも大きな理由です。たとえば、社内で別々のゲームエンジンをチームごとに使っていた場合、まず用語や前提知識のすり合わせが必要になります。
統一することでそのすり合わせが必要なく、もっと深い技術の話ができるのです。広報スタッフも、このあいだ本を1冊勉強しきったので、用語が通じるのです。
――それぐらい突き詰めて使うに足るエンジンだと。
佐々木そこは間違いないです。我々はシステムを作りたいわけではなく、ゲームを作る会社です。エンジンを深いレベルで理解している人たちがいれば、プロトタイプがすばやく作れ、試行錯誤にコストを割けます。また、完成間際の作品を詰めるところも、少ない時間で問題を解決していくことが可能です。このように、他社さんと比べて制作の期間やクオリティーに差が出るだろうという思想のもとにやっていて、実際その通りになってきていると思っています。
黒澤グラフィックから見ての魅力もあります。前の会社では、エンジンというほどではなく自社ライブラリのようなものを使っていたのですが、やっぱり新しい表現を使って何かを作りたいとなると、まずエンジニアに相談してそれを可能にしてもらうところから始まるんですよ。でも、アンリアルエンジンで再現された最新の新しい表現がWEB上で多く公開されているので、そういうものを自分で見て、軽く試してみて、そのうえで提案ができます。話が早いというか、世の中の潮流とそのままリンクできるんですよね。
佐々木何かの表現を見るときに、ほかのアンリアルタイトルのこの部分はどうやっているんだろう、というのを解析して試したりもしやすいよね。
黒澤そうですね。雰囲気から解析することもあれば、記事にされていてある程度わかることもありますから。あとは、アンリアルエンジンの場合はマーケットプレイスなどでハイクオリティーなアセットが販売されているので、そこを見て参考にすることもできます。
馬場似たような話になりますが、社内で技術が停滞しないことが魅力ですね。社内エンジンや社内ライブラリは“秘伝のタレ”のようなところがあるというか、独自進化してしまい、ほかと違うことをしようとすると、それはそれで苦労が出てくるんですよ。
アンリアルエンジンは情報のアップデートがしやすいですし、拡張もしやすいんです。うちはほかの会社よりもアップデートの頻度が高いほうで、新しいバージョンが出たらすぐに対応するので、そのあたりも魅力というか特徴だと思います。
――エピックゲームズさんとのやり取りなどはあったりするのですか?
佐々木しょっちゅうあります。技術サポートを受けている案件がほとんどですし、“アンリアルフェス”(※)というイベントでは、一時期我々が実行委員に入っていた過去もあります。まだエピックゲームズジャパンさんの人数が少ないときに、なぜか私たちがブース担当としてミドルウェア企業さんに「ブースを出しませんか」という話をしていたこともありました(笑)。
※アンリアルフェス:エピックゲームズが主催するオフィシャルのアンリアルエンジンの大型勉強会。
――先ほど“UE4ぷちコン”のお話が出ましたが、そもそもどういった経緯で開催することになったのでしょうか?
佐々木会社を立ち上げる前から、イベントや交流が好きなことから業界イベントを主催していたので、きっかけとしてはそれですね。アンリアルエンジン専門のデベロッパー会社を立ち上げたので、関連したイベントをやりたいな、と。当時はまだアンリアルエンジンがあまり世に広まっていなくて、一般の人がやっと触れるようになった時期でした。アンリアルエンジンって“お高い”イメージがありましたよね?
――“高級品”みたいな。
佐々木それで、もっと気軽に触れるよ、触ろうよ、みたいなイベントをしたらおもしろいなと思って、エピックゲームズさんに企画を持っていったのが最初です。実際に開催したらかなり多くの方から応募していただきました。“ぷちコン”がきっかけでゲーム業界に入りました、という人も出てきました。
自分のなかで、業界人口を増やしていくことをひとつのテーマとして持っていて、“ぷちコン”ではそれもできているのかなと思います。弊社としてもそこから採用につながることもあるので、いろいろいい感じに進んでいて、楽しくやっています。
――応募作品のレベルはいかがですか? 参考になったり、それとも、もっとここをこうすれば、といった印象が多いでしょうか?
佐々木そういった視点というよりは、純粋に楽しんでいます。このネタがきたか、みたいな(笑)。
黒澤仕事とは違いますからね。応募作品は、どちらかというと一発ネタみたいなものが多いです。もちろん、そうではない作品もありますけどね。
――業界を盛り上げる取り組みとしては非常にいいですよね。応募数は年々増加しているのでしょうか?
佐々木平均してみると伸びているとは思います。春と秋のタイミングで開催していて、春がだいたい70通、秋が100通ぐらいの感じです。
常連さんもいます。今回で13回目ですが、皆勤賞の人もいますよ。すごいと思いますし、ありがたいですね。でもじつは、基本的に半分くらいが初めてだったりします。アンリアルエンジンを広げていくという意味でもそのあたりのバランスはいいかなと思っています。
――将来的にこんなイベントになったらいいな、というイメージはありますか?
佐々木現在、ゲームを作ること自体のハードルがすごく下がってきています。プログラミング教育が始まったこともありますし、『マインクラフト』や『フォートナイト』のクリエイティブモードのように、自分で作ることが一般ユーザーの楽しみにもなってきているので、そこからコンテンツを作る楽しみに広げていきたいですね。アンリアルエンジンでのものづくり、コンテンツ作りが、仕事としてだけでなく趣味としても広がって、みんなにとって身近なものになるといいなと思います。
アンリアルエンジンは、プログラムに触れてきていない人にとっても、いいツールだと思います。ぷちコンはもともとアンリアルエンジンを触るきっかけを作るコンテストだったので、そういう意味でも気軽に触ってみてほしいですね。たとえばサンプルをダウンロードしていじってみたり、本で勉強しても、実際に自分で作品を作ってみないと、なかなか理解が進みません。それを経験するためにも触ってほしい、という思いでやっているコンテストなので、2日、3日で作ったものでもいいので応募してほしいです。
パブリッシングを視野にさらなる成長を
――起業から6年以上が経って、成長期にあるというお話もありましたが、起業当時に持っていた将来像といまを比べてみて、いかがでしょうか?
佐々木思ったより大きくなったな、という感覚はあります。目標としていたのは、ゲームエンジンの力を使っておもしろいゲームをおもしろく作るということだったので、そこは変わらずですね。
弊社は3つの価値を掲げていて、ひとつはイノベーション……革新的なもの作ること。つぎにシナジー……異なる人が合わさるからできること。そしてカラー……ひとりひとりの色を出してものづくりをしていくことです。これは、その通りになってきていると思います。
――イノベーションとシナジーに関しては、外側から見てもその通りに思えます。
佐々木革新性については、VRではかなり実績が出せていると思います。シナジーという点では先ほどもお話しした、アンリアルエンジン一本にすることでの高レベルな技術交流の実現、プロジェクトをまたいだ機能の流入、そしてその人たちが話し合うことによって生まれるゲームデザインなど、提案型で動けているところはいいかなと思います。
カラー、色を出していくという部分は、これも提案を積極的に出すスタッフが多いので、実現できているかなと。ただ、ここはもっとプロジェクトをたくさん出していって、ひとりひとりのディレクションのカラーが出てくるといいなとは思っています。ここについては、会社がつぎのステップに行くことでさらに発揮できる場所なので、いまから楽しみです。
――これからの展望のようなものはありますか?
佐々木会社が成長して大きくなっていって、デベロッパーとしてふつうに考えると、つぎに目指すのはAAAタイトルのように開発規模を大きくしていくことだと思いますが、弊社ではそれをやりたくないと考えているんです。
――と言いますと?
佐々木あまり開発規模を大きくし過ぎてしまうと、ひとりひとりの色を出すという部分が難しくなってきます。プロジェクトの要職に就く人が多いほうが、個々人の色が出せるし、楽しいじゃないですか。もちろん苦しみもありますけど(笑)。イチからものを作る力というのは、大きなプロジェクトでドーンと出すよりも、みんながある程度の規模で試せる場があるほうがいいと思っています。
――業界全体でタイトルの大型化が進んできて、ディレクターとしての経験を積むこと自体が難しくなってきていることも問題視されていますからね。
佐々木自分もディレクションをしてきて、今回はこれを試してみたい、つぎはこう踏み込んでみたいという挑戦と、安定して成果が出せる部分をバランスを見て入れているのですが、その感覚はある程度ディレクターとしての場数を踏まないと成長しないと思うんです。となると、やっぱり規模を大きくしていくよりは、いまの規模でタイトルを横に広げていって、そこを回せる人を増やしていくことが、目指すところに近いのかなと思っています。
――そのための展開なども見据えているのですか?
佐々木ゲーム事業でいえば、パブリッシングに挑戦してみたいですね。いまはほとんどの案件でクライアントが一般ユーザーとのコミュニケーションを取ってくれていますが、今後は自分たちで直にコミュニケーションを取ることもやっていければと思っています。
ゲームをおもしろくすることはいままでの蓄積もあり、今後もそこは成長していきます。しかし、やはり市場との対話というところに踏み込みたいなと思ったんです。商業でゲームを作っていくのであれば、我々が目指すつぎのステップはそこかな、と。
将来的にパブリッシングを事業として回していくには、コンスタントにタイトルを出せるようにならないといけないと考えています。売る担当者がついて、そこも何度も売る経験をして試していって、会社として成長していく、経験を積んでいくというプロセスが必要だと思います。
――家庭用ゲームの制作期間が長期化していくなかで、短い期間で試行をくり返せるとすれば、それもひとつの武器になりそうですね。
佐々木今後も自社タイトルだけでなく、他社さんメインのタイトルも作っていくことになると思うので、それを両立させるためにはどうしていけばいいのか、というのも課題です。自社パブリッシングは期間を自分たちで調整できてしまうので、そのぶん社内で作るのは難度が上がります。ですので、どういった感覚値でものづくりをしていかないといけないのか、というところも含めていまは整えているところですね。
――会社の規模としては、どのようになっていくイメージですか?
佐々木人数は増えていくと思います。50人くらいの規模でやっていきたいなと思っていたところはあるのですが、いままでのゲーム制作事業に加えて、最近正式にチームを発足したエンタープライズ事業、そして将来的にパブリッシング事業を整えるとなると、トータルではもう少しいくんじゃないかと思います。
よいかたちでクライアントの方々に期待していただいていることもあって、その期待に応えるため、またその先にあるやりたいことをやっていくためには、いま以上に人は必要になりますからね。
――パブリッシングまで視野に入れられているのであれば、成長の結果として会社が大きくなることはいいことだと思います。
佐々木そうですね。ただ、一気に制作陣を増やしていったり、100人を目指すことはありません。各プロジェクトがきちんと回せるようになり、それがいいクオリティーで安定してユーザーに届けられるようになる。そうして横に増えていくぶんにはいいかな、と考えています。
――社内の雰囲気はどうですか?
黒澤基本的に、コミュニケーションができる人が多いのは特徴のひとつだと思っています。アンリアルエンジン一本に統一しているから話が通じやすいというのもありますが、採用時にもコミュニケーション能力は重視しているので話しやすい人が多いです。僕の場合、エンジニアさんやプランナーさんと話すことも多いのですが、同職種に限らず他職種とも話しやすいので、そこは非常に助かっています。
あとは、週1でセクションをまたいだ技術交流会のようなものがあって、そこでアート、エンジニア、プランナーがそれぞれにドキュメントを貯めることもしています。
馬場本当にコミュニケーションは取りやすく、社内が明るいですね。プログラマーはプロジェクトが違うとあまり話をしないことが多いと思うんですよ。でも弊社の場合は、エンジンが統一されているので、別のプロジェクトで何か問題があったときの情報共有や対応の共有もすぐにできるんですよね。自分も相談をしますし、相談を受けることもあります。そういうのもあって、社内的に話しやすい雰囲気ですね。
とにかく情報共有が大事という考えが全体的にあって、あえてミーティングを行って積極的に情報を共有する場を設けることで、ふだんから情報を交換するのが当たり前という雰囲気があります。
佐々木情報共有という意味では、ブログもかなり大きいです。基本的に外に向けた発信なのですが、社内の技術共有にもなっています。アンリアルエンジンを使っている方にお会いすると、「ブログ見ています」と言ってくださるので、業界内では“ぷちコン”よりも知名度があるかもしれませんね。
――福利厚生はいかがですか?
馬場個人的にいいなと思っているのは、デリランチです。月に1回、みんなでお昼ご飯をいっしょに食べる制度です。いまは新型コロナウィルスの影響で自粛していますが、お昼にワイワイしゃべりながらご飯を食べるのはけっこう好きです。
黒澤技術系に関しては、会社がかなり負担してくれていて、たとえば大阪で開かれる勉強会に行くときには、宿泊費も全額出ます。基本的に勉強の目的であれば、会社が全額負担してくれます。
また、CEDECやアンリアルフェスといったイベントには、社内の全員が出席しています。全員が出ている会社はあまりないと思います。加えて、技術書などはいくらでも買えたりするので、そういった勉強面でのサポートはかなり手厚いですね。
――求人まわりのお話を伺いたいと思います。先ほども少しお話にありましたが、どのような人がヒストリアさんに合っていると思いますか?
黒澤やはり自主的にコミュニケーションが取れるかどうかはかなり重視しています。アートに関して言えば、現在は細分化が進んでいますが、そういった枠にあまりこだわらず新しい領域を広げていける人には、そのための環境も整っているので、向いているかなと思います。
また、よく勘違いされるのですが、入社前にアンリアルエンジンを触ったことがなくても入ることはできます。入った後はもちろん触ることになりますけどね(笑)。
佐々木どんな職種でも、アンリアルエンジンは未経験でも大丈夫ですね。入ってから使えるようになってもらえればいいので。
馬場プログラマーも、アンリアルエンジンは触れなくても大丈夫です。C++さえしっかりできれば問題ありません。あとは、情報の共有、発信が弊社の特徴であり、そこに重きを置いているので、情報に対して受け身ではなく発信する側に立てる人がいいかなと思います。
アンリアルエンジンはどんどん新しくなっていくので、それに追いつき追い越せというか、それぐらい最新の情報をつねに追っていないと取り残されてしまいますから。
佐々木エンジンのうわべだけを使うのではなく、場合によっては改造もするので、内側まで理解してほしいです。「アンリアルエンジンが対応していないのでこの機能はできません」というのはプライドとしてもイヤだなと思いますし。
馬場アンリアルエンジンも完全ではないので、こういう機能が欲しいというときに別のプラグインを引っぱってきて、それをアンリアルエンジンで動かせるようにすることもときには必要になります。そういった柔軟な対応ができる人がいいと思います。
――エンジンに使われるのではなく、使いこなすということですね。
佐々木ゲームをよりおもしろくすることに興味がある人、ユーザーに対してどういうものを提供するか、という観点でものづくりができる人に来てもらえたらとてもうれしいです。
先ほども触れた通り、AAAではない、AAにもいかないぐらいの小中規模でものを作っているので、ひとりひとりがユーザーの方をどう意識しているかが如実に出ます。裁量を残す作りかたをしているので、そこを意識して楽しめる人はマッチすると思います。
ものによっては、タイトル全体ではなく、自分のパートがタイトルに組み込まれたときにどう見えるかや、どういうふうに遊んでもらうものかといった観点です。そういう意味で作品をよくすることに夢を持っている方は弊社にも合っていると思います。
――最後に転職を考えている方に向けたアドバイスがあればお願いします。
馬場アドバイスとしては、ひとつゲームを作るにしても、具体的な目標や目的を持って取り組むことが大事だと思います。たとえば、ゲーム会社に入ることは目的ではなく手段ですよね。そこを間違えないようにするのが大事だと思います。
黒澤僕がゲーム業界に入ったころは、仕事以外ではリアルタイム系グラフィックには触りようがなかったのですが、いまは家でも簡単に試せるようになりました。まずはやってみようぜ、と。
佐々木弊社のアピールになってしまいますが、今回の取材でも成長がひとつのキーワードになっています。会社も人もすごく成長していて、これからも成長する余地はまだまだあると感じています。
コンセプトからものごとを詰め込みたい、あるいは技術的な面を作り込んでいきたい人、その両方に合っている会社だと思うのですが、やはりコンセプトを試す場が多いというのは大きいと思いますし、いま意識している部分です。いまは、そういったコンセプト作りでの中心となる人物を募集しているので、そこに興味がある人、夢がある人はマッチしていると思います。
ヒストリアってどんな会社?
ゲームやデジタルコンテンツの企画、開発、販売を手掛ける同社。特徴的なのは、アンリアルエンジンでの開発にこだわっていることだ。人生観を変えるほど心に刺さる作品と体験作りを目指し、家庭用、アーケード、VRの3つを軸に、パートナー企業と協業しながら開発全般を丸ごと請け負っている。最近では、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』や『Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ』など、さまざまなタイトルの開発・開発協力を担当。また、アンリアルエンジンの学習を目的に一般参加型ゲームコンテスト“UE4ぷちコン”を2014年より開催し、その回数はすでに14回を数える。
●代表取締役:佐々木 瞬
●設立年月日:2013年10月31日
●従業員数:56名(2020年4月現在 ※プロジェクト契約者・外部スタッフ含む)
●事業内容:コンピュータゲームの企画・開発・販売、デジタルコンテンツの企画・開発・販売、イベントの企画・運営、Unreal Engineの導入や運用に関するコンサルティング