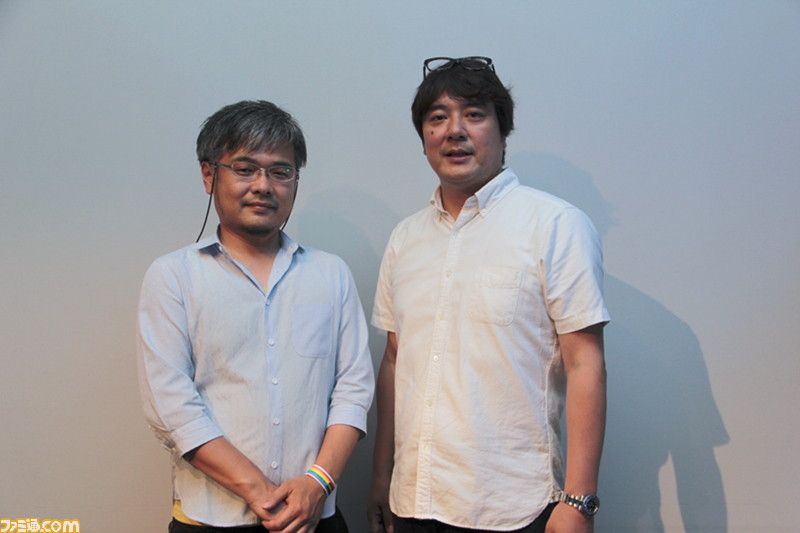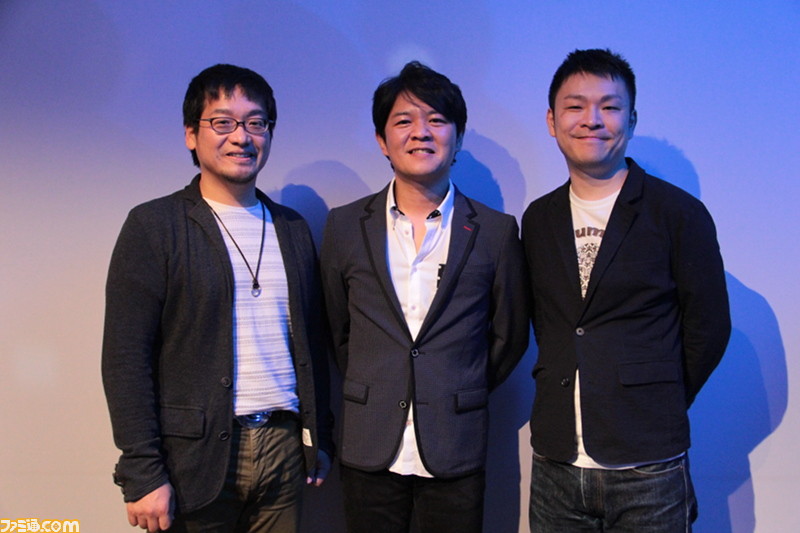受賞直後の喜びのコメントをお届け
2018年5月24日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開催したプレイステーション 4開発者向けのイベント“PlayStation Developer Conference”の一環として行われた、ゲーム開発者による投票で選ばれた作品を表彰する“PlayStation Developers Choice Awards 2018”。表彰を受けた6部門のタイトルの登壇者による喜びのコメントと、囲み取材の模様をお届けしよう。
ベストビジュアルアーツ
『ドラゴンボール ファイターズ』
(バンダイナムコエンターテインメント)
バンダイナムコエンターテインメント プロデューサー 広木朋子氏(写真右)
アークシステムワークス ディレクター/テクニカルアーティスト 本村純也氏(写真左)
<壇上コメント>
本村 この度は、このような素晴らしい賞をいただきまして、非常に感激しております。スタッフのみんなを代表して、お礼を申し上げたいです。ありがとうございました。正直身に余る光栄と言いますか、素晴らしいビジュアルのタイトルが今年もすごくたくさん出たなかで、本作を選んでいただけたということで、非常に感謝しております。セルシェーディングのビジュアルを得意としている弊社と、『ドラゴンボール』のIPのマッチングのよさというところ、そこを結び付けていただいた、バンダイナムコエンターテインメント様のおかげというところもあるのかなと思っております。あとは、開発に尽力してくれたスタッフのひとりひとりに改めてお礼をいいたいです。
広木 この度は、このような素晴らしい賞をいただきまして、本当にありがとうございます。とくに今回、“Developers Choice”という、ゲームを見る目が非常にきびしい方も多いのではないかと思われる中で、本作を選んでいただいたのが非常にうれしいです。本村さんからもお話がありましたが、このような賞をいただけたのも、世界中で愛される『ドラゴンボール』というコンテンツを、われわれは勝手に“超ハイエンドアニメ表現”と呼んでいるのですが、この表現で描いてくださった、アークシステムワークスさんの技術力と、それを最高のパフォーマンスで出していただいた、プレイステーション4というハードのおかげかなと考えております。『ドラゴンボール ファイターズ』はまだこれからです。主人公の孫悟空が、最初は地球人かと思いきや、超サイヤ人、超サイヤ人2、さらにいまでは超サイヤ人ゴッド超サイヤ人というすごい進化をしているところを見習って、『ドラゴンボール ファイターズ』自体も進化していきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
<囲み取材コメント>
――今回、“超ハイエンドアニメ表現”が評価されたと思いますが、いかがでしょうか?
広木 おっしゃるとおり、本作では、まさに“まるでアニメを自分で動かしているかのような表現”というところをどうしても実現したかったんですね。ファンの方からも、「アニメ表現を最大限に活かしたゲームを出してほしい」という要望がものすごく多かったんです。そこを本当に最大限表現してくださったのはアークシステムワークスさんの技術力で、今回の狙い通りの評価をいただけたのはすごくうれしいです。
本村 最高の題材をご用意いただいたバンダイナムコエンターテインメント様のおかげかなと思っております。
――プレイステーション4という開発環境についてはいかがでしょうか?
本村 今回、最高3vs3ということで、キャラクターが同時に6体画面に登場します。さらに、格闘ゲームなので60fpsをつねに保持しなければならない。「それはなかなかきびしいかな」というのが最初の見通しだったのですが、プレイステーション4のパワーのおかげで、比較的スムーズに開発が進められました。それは、SIEさんのおかげかなと思います。
――Awardの受賞作のなかで唯一の格闘ゲームですが、そのあたりはいかがでしょう?
広木 格闘ゲームというと、敷居が高く見えてしまいがちなジャンルですが、今回『ドラゴンボール』という題材を合わせたことで、「格闘ゲームをもっと幅広い層に遊んでいただきたい」という思いがありました。そのため、グラフィックには非常に力を入れなければならなかったんです。というのは、「難しそうかもしれないけれども、おもしろそうだ」と思っていただくには、グラフィックの力がすごく重要だったんですね。そこをアークシステムワークスさんと何度も何度もすり合わせをして作っていった結果、こうしてグラフィックを評価していただいたというのは、格闘ゲームでこの賞をいただいたことに繋がっているのかと思います。
本村 もちろん、いろんなゲームでグラフィックはポイントになりますが、格闘ゲームはまた違った意味でグラフィックが重要です。遊んでいる人が楽しいのはもちろん、見ている方たちも楽しめるというところが、いま格闘ゲームがesportsなどで盛り上がっているひとつの要因だと考えていまして、今回そこをすごく意識して、「見ているだけでも楽しめる」という点、「何が画面で起こっているのか、どういう駆け引きが起きているのか、どっちが勝ちそうで負けそうでハラハラするのか」というところをグラフィックを通じて表現することに注力し、意識して作っています。そこを評価していただいたことをうれしいと思っています。
――受賞したからこそ思い出す、一番大変だったことなどはありますか?
広木 (本村氏と)同じことを思い出しているのかと思いますが、開発中に一番詰まったというか、何度もすり合わせたのが、じつはグラフィックの部分でした。『ドラゴンボール』は非常に歴史の長いタイトルなので、そのまま表現すると、いまにしてみると“一昔前の表現”ということになりがちなところがあって、一時期はかなりあっさりしたグラフィックになっていた時期もありました。それを『ドラゴンボール』のファンの方々が抱いているイメージを変えずに、「でも新しい表現にするにはどうしたらいいんだろう?」と、何度も何度もすごく悩んで……。イメージボードを作ったりしました。
本村 ものすごくたくさん、いろんなパターンを絵で用意して、ああでもないこうでもないと、アメコミみたいなものすごい黒い影が入ったものや、逆にもっとふわっとした陰影のものとか、いろんなものを試しました。その中で『ドラゴンボール』のイメージを崩さずに、かつユーザーさんにアピール力のあるものをということで、いろいろな要素を鑑みて絞り込んでいった結果が、いまの表現になっています。そのやりとりは、かなり心を削って取り組みました。
広木 ひとつの絵を用意して、草ひとつ取っても「この色じゃない」とか、2~3人のスタッフで何度も検討したのは、いまではいい思い出ですね。
ベストオーディオ
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』
(スクウェア・エニックス)
スクウェア・エニックス
プロデューサー 岡本北斗氏(写真左)
ディレクター 内川毅氏(写真右)
※岡本氏は囲み取材にのみ同席
<壇上コメント>
内川 本日は、このような名誉ある賞をいただけて、本当に光栄に思っております。どうもありがとうございました。『ドラゴンクエストXI』は、『過ぎ去りし時を求めて』というサブタイトルの通り、これまでの『ドラゴンクエスト』の思い出を振り返るといったこともコンセプトにしてゲーム作りをしてまいりました。音楽に関しても、そのテーマに基づいて、すぎやま(こういち)先生に作っていただいた新曲だけでなく、昔の懐かしい音楽をお客様にお届けしたいということで、過去の曲をシーンに合わせて選んでまいりました。シリーズは30年以上続いていますが、その思い出の部分が皆さんの琴線に触れて、このような賞をいただけたのではないかと思っております。本当にありがとうございました。
<囲み取材コメント>
――サウンドトラックなどの人気はありますが、ゲームのオーディオが評価される機会はあまりないように思いますが、いかがでしょうか?
岡本 『ドラゴンクエストXI』は、サブタイトルの『過ぎ去りし時を求めて』ということもあり、新たなお客様と、いままでの30年間支えてくださったシリーズファン、すべてのお客様にもう一度王道の『ドラゴンクエスト』を届けよう、ということもテーマとしてありました。そこで、過去の名曲や新曲を含め、“新しくも懐かしい”と感じられるものにするというコンセプトを立てました。ゲームをプレイしていただいたときに、「ああ、あのときに聞いたあの曲だ」とか、「あの曲が今回はこうなっているんだ」とすごくわくわくしていただけた、というのが、ベストオーディオを受賞させていただけたひとつの要因かなと思っています。
内川 今回は過去作の曲を使うというのが『過ぎ去りし時を求めて』というテーマにがっちり符合したので、それをウリのひとつとしたかったんです。そこで、すぎやま先生とお話させていただいて、曲を使わせていただきました。
岡本 “序曲”も『ドラゴンクエストI』のフレーズを入れよう、というのは最初から決まっていたよね。
内川 最初に曲を発注する際に、テーマを直球で伝えたかったので、すぎやま先生にそんなオーダーをさせていただきました。曲で言うと、岡本はプロデューサーでありながら、すぎやま先生と密に仕事をしていて、すぎやま先生とのやりとりを岡本が一手に引き受けてくれていた部分があります。ですので、すぎやま先生については彼に聞くのが一番ですね(一同笑)。
――すぎやま先生とのやりとりで思い出に残っているエピソードなどありましたら。
岡本 今回は、『ドラゴンクエストXI』としては、新しい物語なんですけれども、どこかで懐かしさもなければいけないということもあって、「もしかしたらあの曲のあのフレーズなんじゃない?」という、過去作の曲のフレーズが散りばめられていて、シナリオの演出上でもそういう要素を入れていたりします。そういう意味では、一番印象的なのはエンディングです。堀井さんから「終わりかたをこうしたい」というオーダーがあって、それをどうするかすごく考えて、今回のエンディング曲の構想をすぎやま先生に提案させていただきました。ほかには、ある場面で新曲を作っていただいたのですが、曲をいただいたあとで演出や映像ができてきたときに、「これって、過去作のあのシチュエーションを思わせるから、シナリオテキスト自体にも変更を加え、あの曲を使おう」って過去作の曲を使ったことがありました。
内川 すぎやま先生には新曲をお願いしていたのですが、夜中に岡本と、できてきた映像に曲をあててみて……。
岡本 Premier(動画編集ソフト)でイベントシーンとプレイアブルシーンを動画に撮って1本の映像にして、ひとつひとつトラックに音楽をあててみて、「どう?」と検討をくり返していたんです。そこにお願いした新曲をあてていたんですが……。
内川 そのシーンを見て、「この曲を使ってみたらどう?」と岡本に話してみたんです。
岡本 「えー!」って言いながら、試しにはめてみたら「はまった!」と。
内川 ふたりとも鳥肌が立っていました。後日すぎやま先生にも、堀井さんにも確認していただいたんですが、堀井さんも「確かに!」と。テーマも合っているし、キャラクターの立ち位置もシナリオ的に曲に合っているということで……。
岡本 僕が後日すぎやま先生へ謝罪に行きました。せっかく新曲を作っていただいたのに申し訳ありません、と。
ベストVR
『V!勇者のくせになまいきだR』
(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)
ソニー・インタラクティブエンタテインメント JAPANスタジオ 『勇者のくせになまいきだ。』シリーズプロデューサー 山本正美氏(写真右)
アクワイア 『勇者のくせになまいきだ。』シリーズディレクター 大橋晴行氏(写真左)
<壇上コメント>
山本 すみません、身内が主催しているこういった場で(賞を)いただくという、申し訳ない気持ちもありつつ、すごく自信をもって作ったゲームなので、本当にありがたい賞だと思っております。『勇者のくせになまいきだ。』というシリーズは、2006年に初代が出てから、1年ごとにプレイステーション・ポータブルで3作まで発売させていただいています。その後、プレイステーション Vitaでパズルゲームとしてスピンオフ作品を出し、そこからかなり間が開いて、今年の2月に『勇者のくせにこなまいきだDASH!』というスマートフォンのスピンオフコンテンツもサービスインさせていただいています。これまで10年ぐらいこのIPを育ててきているんですけれども、こういった賞とは本当に無縁で、無冠の名をほしいままにしてきました(笑)。今回、このような賞をいただいて、本当にありがたく思っております。
僕らも、アクワイアのスタッフのみんなも、VRのコンテンツを作るのが初めてだったのですが、体験性や没入感が大事なVRのコンテンツのなかで、僕らが得意としている“ゲームのルールのおもしろさ”というものをしっかりコンテンツの中に取り込みたい、ということで、独特の立ち位置を作れたんだとしたら、非常にうれしいです。タイトルが売れたら当然うれしいですし、メディアの方に評価されたらうれしいですし、ユーザーの方に選んでいただけたらうれしいのですが、開発者のみなさんにこのような賞を授けていただいたということは、僕らにとって非常に誇りになります。今後、まだまだおもしろいゲームを作っていくうえで、この誇りは、1980年代をほうふつとする(会場内に設置された)ミラーボールのように輝いていくことでしょう。この誇りを糧に、新しいおもしろいゲームを作っていきたいです。本当にありがとうございました。
大橋 『勇なま』シリーズでは、2作目、3作目、そして今回のVR版でディレクションを務めております。昨年、シリーズ10周年という節目のタイミングで『V!勇者のくせになまいきだR』をリリースさせていただくことができましたけれども、今回、ゲーム開発者の皆様からこのようなよい評価をいただくことができまして、本当に10周年にふさわしい、記念すべきタイトルになったと思います。開発陣を代表いたしまして、お礼申し上げます。
<囲み取材コメント>
――今回、同業者の方々から“ベストVR”の評価があったわけですが、個人的にどこが評価されたとお考えですか?
山本 もともとのゲームが一風変わったシステムのゲームだったので、さらに個性を出すために何を乗せるかというときに、ちょっとメタ的なネタをいっぱい入れ込んだのがゲーム的な特徴だったんですね。ネタの出元として、ゲームやアニメ、映画やマンガからインスパイアされていろいろ仕込ませていただいたのですが、ふと思えば、今日、会場にいらっしゃる人たちがまさに作ってこられたものを、僕たちはある種お借りしているわけです。それで、こういう栄誉ある賞をいただけたというのは、皆さんに感謝しかないという気持ちでいっぱいですね。
大橋 コンテンツとしては、魔王やムスメといっしょにボードゲームを遊ぶ、という体験が目新しかったのかな? そこが評価されたのかなと思いますね。
''――“ゲームのルールのおもしろさ”を大事にされたということが、VRタイトルの中で目新しかったということでしょうか?
山本 そうですね。海の中に潜るとか、現実の中であることをVRで代替するということは、コンテンツとしては優れたものが出揃っている中で、僕らはVRゲーミング自体をもう1回ネタにするというか、「VR空間の中にもう1回おもしろいゲームを入れ込んだらどうなるのか?」というところが、結果的に評価されたポイントなのかなと、いままさに感じているところです。
大橋 友だちがいない、寂しいプレイヤーを癒すコンテンツとして……。
山本 そんな言いかたあります?(笑) 隣にムスメがいて、向こうに魔王がいるっていう、彼らの部屋に入っていく、でも彼らからは絶対出てきてくれないという切なさみたいなものも、エンディングではしっかり演出できたかなと思っているので。そういう意味では、ちょっと立ち位置の違うVRコンテンツとして、いいポジションを取れたのかなと、改めて感じさせていただきました。
――VRコンテンツは長時間遊ぶと疲れやすいという話もあると思うのですが、そういう意味で、今回評価されたポイントの中に、『V!勇者のくせになまいきだR』は没頭してけっこう長時間遊べてしまうタイトルだったということもあるのかな? と思ったんですが。
山本 ステージはかなり用意しようという話は最初からしていて、1回にできるプレイ時間は15分ぐらいだろうと、大橋さんがディレクションして詰めていってくれましたのですが……。
大橋 最初は1ステージ20分ぐらい遊べるボリューム感にしようと思っていたんですが、いざやってみたらちょっと疲れる。そこで、5分~10分で終わる構成にしようということで作ってみたんですけれども……。
山本 案外みんな疲れない(笑)。
大橋 そうなんです。ぶっ続けで遊んでくださる方も多くて。「楽しい!」って……。
山本 データとかを見てみると、けっこうすぐクリアーされちゃっているんですよね。もうちょっと休憩しながらやろうよって。
大橋 すぐ疲れるだろうから、だいたい1週間ぐらい楽しんでいただくぐらいの想定で作ったんですけれども。あっという間に……。
山本 飢餓感がすごかった(笑)。
大橋 その背景にあるのがやっぱり「おもしろかった」っていうところと、「酔わない」っていう声と。そういったポジティブな理由でこういう結果なのは納得はできるんですけれども。
山本 その仕組みはできたので、後は予算さえあればボリュームは増やせます。1発目としては、新しいVRコンテンツとしての立ち位置は得られたかなと思いますね。
――これまでにない開発だったと思うのですが、一番大変だったことを挙げるとすればどこでしょうか?
大橋 何だろうなあ……。技術的なところで言うと描画回りですかね。魔王やムスメをきちんと描画するためにも、フィールド上の魔物をどれぐらい表示するか、描画できるか。
山本 あのごちゃごちゃ感がゲームとしての持ち味だったので、そこを損なわずに。
大橋 両立させなければいけないというのがちょっと大変でしたね。ゲームボードとそれ以外のところの描画をきっちりやる、しかもゲームボードはなまじビオトープをテーマにしているものですから、生き物もそれなりの数を出したいし……どこを間引いていくか、という取捨選択が大変でした。
山本 あとはVRコンテンツを開発するときには、どなたも苦労するポイントなんですけれども、ゲーム側にカメラの主導権がない。とくに今回、「ルールをおもしろくしたVRゲームを作ろう」ということで、でもルールを覚えてもらわないといけない。そのため、チュートリアルをどう作ろうかという点で苦労しました。最終的には看板がボーンボーンと出る感じになったんですけれども。あれはもっとやりようがあるんだろうなと思います。
大橋 アトラクション型ですと、ちょっと体験していただければわりとルールはわかってもらえると思うんですが、ゲームのルールを学んでもらうのは大変でしたね。
山本 シチュエーションでわかっていただく、ということができないゲームだったので、いきなり椅子に座っていて、「そこで何するの?」というところは序盤の導入としては苦労したところですね。
ベストテクノロジー
『アサシン クリード オリジンズ』
(ユービーアイソフト)
ユービーアイソフト リリース マネージメント マネージャー 岸田定幸氏
<壇上コメント>
岸田 本日はこのような素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。ご投票いただきましたみなさまと、SIEのみなさまに感謝申し上げます。ありがとうございました。本日は、開発を主導していたモントリオールスタジオのスタッフが来られませんでしたので、代わりにプロデューサーのジュリアン・ラピリエールからビデオメッセージをもらってまいりました。そちらをご覧いただければと思います。
[ビデオメッセージ]
ジュリアン 『アサシン クリード オリジンズ』がベストテクノロジー賞をいただき、大変光栄に思います。『アサシン クリード オリジンズ』は古代エジプトを再現しました。これはとてつもなく大きな世界です。私たちはすべてのAIをキャラクターごとに書き分けることを決断しました。ゲーム内のNPCたちをクエストで使用するだけではなく、キャラクターたちそれぞれに予定や目的など、日常の生活を与えたので、オープンワールドをさらに真実味のあるものにするための数多くの技術への投資が必要でした。
またナビゲーションの考案に多くの時間を割きました。新たな『アサシン クリード』では、プレイヤーが走ったり登ったりしているあいだに流動的なナビゲーションを体験してほしいと思っていました。そのため、コードとアニメーションを基本的に流動的な動きとして一体化したナビゲーションシステムを作りました。そしてそれは、プレイヤーにとって非常に柔軟性のある体験となりました。
これ以外にも『アサシン クリード オリジンズ』のために開発した技術としては、自動的にゲームのフィールドを生成するものがあります。木々、太陽、砂漠などすべての風景はまず自動で生成され、その後アーティストが手を加えました。これにより、生産コストを抑えながら巨大な世界を生成することができるようになりました。最後に、もう一度受賞できたことに感謝します。今回はそちらにうかがうことはできませんが、この受賞はわれわれにとって大変な名誉です。本当にありがとうございました。
<囲み取材コメント>
――ベストテクノロジー受賞おめでとうございます。同業者から評価されるということをどのようにお考えですか?
岸田 ほかの開発の方から認めていただいたということで、非常にうれしく思っております。開発もつねにチャレンジを続けて、新しいものを導入しようとしているので、それが評価されて大変光栄です。
――日本の開発者による投票ということで、どこを一番評価されたとお考えですか?
岸田 ジュリアンも言っていたのですが、アニメーションの流れをスムーズにすることを前作よりもだいぶ強化しているところやNPCをより生活感を出したりしているところでしょうか。実際に生活をしているような形で表現できたというのが大きかったのではないかなと思っています。
――6部門タイトルが発表されましたが、海外産タイトルとしては唯一の受賞ですね。
岸田 いろいろ有名タイトルがある中で、海外タイトルで『アサシン クリード オリジンズ』が唯一選ばれたということで、かなりうれしいです。なぜ『アサシン クリード オリジンズ』だけなのかというところはちょっとわかりませんが……。古代エジプトというテーマが、みなさんお好きなのかな。
――受賞されたことによって、またユーザーさんに注目されると思いますが、まだ遊ばれていない方に本作の魅力などをお伝えいただけますか?
岸田 本作は古代エジプトをテーマにしています。学校の歴史の授業で習うのは2~3ページだと思うのですが、古代エジプトには魅力的なことがいっぱいあります。それをゲームの中でいろいろ見つけていただければと思います。
ベストゲームデザイン
『モンスターハンター:ワールド』
(カプコン)
カプコン
常務執行役員 CS第二開発統括 兼 MO開発統括 プロデューサー 辻本良三氏(写真中央)
ディレクター 徳田優也氏(写真右)
エグゼクティブディレクター/アートディレクター 藤岡要氏(写真左)
<壇上コメント>
徳田 本日は素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。『モンスターハンター:ワールド』は、世界の方、日本の方、すべての方に楽しんでもらえるタイトルにしようということで、シリーズタイトルでありながら、ゲームデザインにかなり手を入れました。その部分に対して同業者の皆様が投票していただいて、このような素晴らしい賞をいただけたことは、本当にうれしいですし、励みになります。ありがとうございました。
藤岡 今日はこのような賞をいただきまして、ありがとうございます。今回はとくにアートディレクションを担当させていただきました。ゲームは没入感が大切だとずっと思っていて、ゲームデザインとグラフィックの部分はいっしょになってゲームデザインがよりユーザーに伝わる、ということを今回意識して作りました。没入感を出すためのグラフィックがゲームデザインを後押しできたのではないかと思って、こういった賞をいただけたのは本当にうれしく思っております。ありがとうございました。
辻本 今回、『モンスターハンター:ワールド』がこのような賞をいただきまして、本当にうれしく思っております。シリーズも10年以上続いてきまして、『モンスターハンター:ワールド』を作るにあたって、僕たちの課題でもある、“これからの『モンスターハンター』の土台を作る”というテーマを掲げたうえで、何を崩して、崩してはいけないところはどこなのか、というところを『モンスターハンター』を作ってきた経験のもと、チームのみんなで話し合って、“さらにチャレンジする”ということで、このゲームを作ってまいりました。10年以上続くシリーズのタイトルで“ゲームデザイン”という賞をいただいたことを、すごくうれしく思っております。これを励みに、これからもがんばっていきたいと思っております。ありがとうございます。
ゲーム・オブ・ザ・イヤー
『モンスターハンター:ワールド』
(カプコン)
<壇上コメント>
徳田 最高の賞をいただきましてありがとうございます。『モンスターハンター:ワールド』は僕にとってもチームにとっても本当に大きな挑戦で、チャレンジの連続でした。今日も、何人かチームメンバーが講演してくれましたけれども、みんなが本当に心血を注いでがんばってチャレンジしてくれた結果、このような賞もいただけまして、チームのみんなとこの賞を共有できることが本当にうれしいです。本日はありがとうございました。
藤岡 このような賞をいただきまして、本当にありがとうございます。『モンスターハンター:ワールド』を作ろうと思ったときに、「グローバルで勝負したい」ということもあって、日本のゲーム業界がもっと盛り上がるといいな、という意気込みでチームメンバー一丸となってがんばってきました。いい形でグローバルにもちゃんと名前を残せたかなと思っておりますので、これからまだまだこの業界が盛り上がるよう、僕たちもがんばっていきたいと思います。本当にありがとうございました。
辻本 この度はこんなに素晴らしい賞をいただきまして、誠にありがとうございます。また、投票してくださったみなさま、本当にありがとうございます。『モンスターハンター:ワールド』は、最新技術を使って、最高の『モンスターハンター』を作って、ワールドワイドで通用するようなゲームを作るというテーマを掲げました。その“最新技術を使って”というところですが、それを実現させていただけるプレイステーション4、SIEのみなさまにすごくご協力いただきました。そのご協力がなかったら、僕たちもここまで満足のいくものができなかったと思っております。
今日は“Developer Conference”ということで、こういう場だから言わせていただきたいことがあります。本当に大規模なプロジェクトになりまして、チームもすごく大きくなりました。ここにいるふたりのディレクター並びに社内のスタッフ、そして外部の協力会社のみなさま、本当にありがとうございました。みなさまのおかげでこのゲームが完成されました。そしてこのような評価をいただけたこと、本当にうれしく思います。ありがとうございます。
<囲み取材コメント>
''――おめでとうございます。ベストゲームデザインの受賞コメントで、『モンスターハンター:ワールド』は今後の『モンハン』を作る上で大きな立ち位置になる作品で、「どこを崩してどこを崩してはいけない」ということを話し合われたというお話がありました。『モンハン』で一番崩してはいけないところはどこだったんでしょうか?
辻本 今日のカンファレンスでもお話したのですが、世界一のマルチハンティングアクションを作る、ということで、『モンスターハンター』がより初心に戻ったときに、『モンスターハンター:ワールド』は何をしなければならないか、何を継続させて、何を変えなければならないか、ということをみんなすごく考えてくれたんです。それが土台になる部分になります。そこに対してはみんなの意識がすごく強くて。これから先のことを考えて、ある意味、もっともっと初心に戻ったわけです。フォーカステストをたくさんやって、意見をすごく取り入れられたのは、その意識がみんな高かったからですね。ひとつひとつの意見に対して、いま、これを言われたときに、“これはどういうことなのか?”ということをひとつひとつ分析してやっていったわけですね。そういった意味では、崩す崩さないというのは都度都度決めていった部分が多いです。トライアル&エラーをして、「これをやろう」、「これはやめよう」ということを、いっぱいやったのが、本作だったと思います。
藤岡 マルチプレイでコミュニケーションが取れるアクションゲームって、ほかにはあまりないジャンルで、『モンスターハンター』はけっこう早くからそれに取り組んできました。アクションゲーム面と、マルチプレイでコミュニケーションを取りながら遊ぶという面が大事だと思っています。そこを崩さない内容をちゃんと考えていったというところはあります。
徳田 素材を集めて装備を作る、という部分は「海外ではウケない」と言われてきたのですが、僕たちはそうではないと考えていました。そこに至るまでの難しい部分やわかりにくい部分をそぎ落とすけれども、根本的な“採集して自分の武器を強化していく楽しさ”はより進化させていくべきだと思ったんです。そういったジャッジをひとつひとつ重ねていった結果だと思います。
――『モンスターハンター:ワールド』で日本だけではなく、世界的に見ても相当の飛躍があったと思うんですが、その理由をいまどのように分析されていますか?
辻本 正直、一言では言えないと思うのですが、『モンスターハンター:ワールド』は、“ぽっと出しました”というわけではないんですよね。いままでも各地域のコミュニティーをすごく活性化していって、各地域で「このゲームが好き」って言ってくれる方がいっぱいいてくれて、とても応援してくれたんです。『モンスターハンター:ワールド』が世に出たとき、いままで応援してくれた人たちが、新たに入ってきてくれたプレイヤーを助けてくれたんですね。「このゲームをもっとプレイしてほしい」とか、「もっと助けてあげたい」とか……。海外では自分たちのプレイを配信して、「このゲームはこうやって遊ぶんだ」といったことをとてもやってくれた。そういったコアなベースが確立していて、『モンスターハンター:ワールド』を出すことができた。据え置き機の要望が海外では強かった、という部分もありますし、Co-opプレイもより注目されてきて、みなさんの意識も高くなってきたところでリリースできたということもある。すべてはタイミングというものがあるのかなと思っています。そういうところがマッチしたのかなと。
藤岡 シリーズは、これまでも海外でも展開してきたので、徐々に『モンスターハンター』というワードを認知してきてくれたというのは明らかでした。これまでは、そこから「遊ぼう!」というところまでなかなか到達しなかったのですが、それが今回、「とにかく手に取ってみよう」と興味を示してくれたというのは、大きくひとつ、何かを越せたものがあると思っています。そこから、辻本が先ほど言っていたコミュニティーや熱心に応援してくれたユーザーさんが発信しているものを見て、それが後押しをしてくれたということをすごく感じています。
徳田 据え置き機なので、「グラフィックレベルでも、AAAタイトルに劣らないようなものを」というのは強く考えていました。足切りラインのようなものがあると思っていて、見た目もそうですし、10分ぐらい遊んだ段階で、どんなものかをある程度分かってもらわなければならない。そういう意味では、ベータテストではいい評価をいただけて、段階的に広まっていったという気がしています。
――今回の受賞を機に、まだ遊んでいない方にアピールなどありましたら。
辻本 “PlayStation Developer Conference”では、僕たちのチームメンバーがこのゲームに対してどういう意識や気持ちで作ったのか、ということを説明させていただきました。僕らがいまからやっていかなければならないのは、アップデートというこれから作る作業はもちろんあるんですけれども、一方で、作ったものをどう理解していただいて、興味を持っていただいて、触っていただけるか、というところが、いま一番大事になっているのかなと思います。そういった意味でも、“PlayStation Developer Conference”でお話をすることで興味を持ってくださって、「ちょっと触ってみよう」と思ってくださる方がいてくださればうれしいですし、そういう場に参加させていただいてすごく幸せです。
藤岡 今後も、どんどん大会やイベントを展開していきますので、まだプレイされていない方で興味がある方が、「ちょっとやってみようかな」と思っていただければうれしいです。いまのタイミングで始められても、初心者の方々でも遊びやすくなるような配信施策などもやっていますので、これを機に遊んでもらえるとうれしいです。
徳田 コミュニティーメンバーがサポートをする意識をものすごくもってくれているので、下位のクエストでも救難信号を上げたらけっこう入ってきてくれます。助けてくれる人たちがいますので、いまからでも遅くはありません。みなさん入ってきていただければなと思います。
辻本 僕たちも助けにいくよね。
徳田 行きますよ!