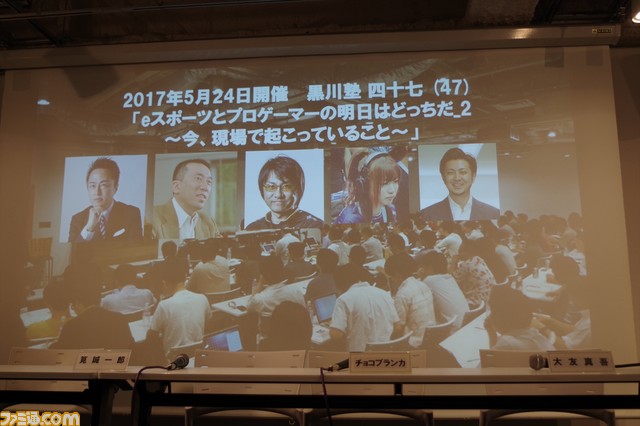日本と海外のeスポーツの温度差
2017年5月24日、黒川文雄氏が主催するトークイベント“エンタテインメントの未来を考える会”(黒川塾)の第47回が、都内のデジタルハリウッド大学大学院 駿河台キャンパスにて開催された。その模様をリポートする。
今回のテーマは、“eスポーツとプロゲーマーの明日はどっちだ_2 ~今、現場で起こっていること~”。本セッションは、2017年1月13日に開催された“黒川塾(四十四)”のテーマ、“eスポーツとプロゲーマーの明日はどっちだ!?”のいわば続編にあたる。セッションでは、前回浮き彫りになった課題にフォーカスし、実際のeスポーツチームの育成や運営の現状や、未来への展望などが熱く語られた。
冒頭でまず、主催の黒川氏があいさつを述べたのち、さっそくゲストの登壇に。今回のゲスト陣は、ゲーミングチームDeToNator代表 江尻勝さん、日本eスポーツ協会事務局長 筧誠一郎氏、CyberZ執行役員 RAGEプロデューサ 大友真吾氏、米国EchoFox所属の日本初女性プロゲーマー チョコブランカさんの4名だ。
各自が席に着き、簡単な自己紹介が行われたのち、いよいよセッションがスタート。黒川氏がまずは江尻さんとチョコブランカさんに、海外と日本のeスポーツの温度差や、国内のeスポーツについて感じている点などを尋ねた。
江尻さん率いるDeToNatorは、実際に海外に選手を送る活動をすでに始めているが、これからの課題は選手にかかってくると言う。
「興行として成り立つには人を集めなければいけませんが、選手目当てで何万人も集まるかと言えば、まだ力不足ですし、危機感を持ってます。いかに魅力的な選手が見たいか、応援しに行きたいかというサイクルが必要。そのためのイベントを開いていただきたいし、自分らも努力しないといけないと思います」と、スタープレイヤー不在の状況を語った。併せて、オフライン大会については、「告知が行き届かず集客が悪いと、よいタイトルでも、盛り上がっていないと見られてしまうんですよ。悪い点はどんどん、改善していってほしいですね」と、運営側への不満をこぼした。
また、海外企業と契約しているチョコブランカさんは、海外の知人に「日本のeスポーツは遅れているよね」と言われたエピソードを紹介。続けて、「日本はまだまだですが、日本に合ったやりかたがあるのではないかと思います。それで盛り上がってくれれば……」と語り、独自路線もアリなのではと主張した。
日本独自と言えば、AVEXとのコラボを展開するなど、まさに日本ならではの大会を展開しているのがRAGE。プロデューサーの大友氏はふたりの発言を受けて、「自分も同じような課題を抱えています」とコメント。盛り上げるヒントを探るべく、海外のeスポーツ大会や格闘技イベントなどを見て、ショー要素に注目しているそうだ。
「観戦するそもそもの文化が違う気もします。そこも演出や企画で工夫して、よりファンが応援しやすい空間作りをするとか、試行錯誤する中で、日本ならではという部分が見えつつあるのかなという気がしています」(大友氏)。
選手を育成していく難しさ
続いて黒川氏が話を振ったのは筧氏。江尻さんが語った運営への不満なども例に出し、運営側の現状を尋ねた。
筧氏は「足りないところだらけで、選手を含めてみなさんに不自由をおかけしていることは重々感じています。お金がない中で、それでもマンパワーでなんとかがんばっています」と内情を説明。RAGEとAVEXの協力なども参考に、「今後はそういう部分も学んで実践していきたいですね」と語った。
「選手ありきで、選手が輝くイベントをみんなで盛り上げていって、Jリーグのカズさんやラモスさんみたいな選手が出るようにしなければならない。協会としても、選手を支援できるようなシステムを充実させたいです」と筧氏。いずれは育成という部分にも力をいれていきたいとのことだ。
育成という面では、チョコブランカさんが若い選手の育成企画を展開しているという。その目的についてチョコブランカさんは、「ただプロゲーマーを養成したいのではなく、こうしたプロジェクトがあれば回りも活気づくのでは、という狙いもあります。さきほど日本と海外の違いの話が出ましたが、海外の選手はお金目的、日本の選手は名誉目的と単純には言い切れませんが、ゲームに求めるものがちょっと違う気はします。そこも考えなければいけないと思っています」と語る。育成企画については、「森に木を植えている」ようなイメージだそうだ。
育成というテーマの流れに乗り、ここで黒川氏が、実際にチームを率いて選手を育てている江尻さんに、「現状をどう感じているのですか?」と質問を投げかけた。江尻さんが強く感じているのは、日本と海外の“母数の違い”だという。
「プレイヤーの母数が圧倒的に多い海外は、まさに弱肉強食の世界。日本で多少ゲームがうまく、たまたまチームに入ったようなぽっと出の選手は、ほとんど通用しないでしょう」と江尻さんは明言する。チーム加入=プロ選手=お金をもらえる、という甘い認識を持った若い選手が増えることを危惧する。
「プロとしての価値があってこそのプロ。またお金にしても、なぜいただけるかの意味をしっかり理解しなければなりません。主役は選手ですが、スターダムに立たせるために、どれだけ教育できるかは重要です」(江尻さん)。
さらに江尻さんが強調したのが、裏方さんへのリスペクトだ。かつてヘアメイクだった江尻さんは、幾多の有名アーチストが、裏方さんをとても大事にするシーンを見てきたという。
「なぜ自分たちが、この晴れ舞台で戦えているのか。そういう気持ちは理解したほうがいいです。海外のトップ選手たちは、そのあたりもすばらしいんですよね。そこを自分たちに置き換えたとき、ちょっと不安だなと感じますね」と語った。
続けて江尻さんは、青山学院大学のマラソンチームを例に出し、“自発的に考えて動く”ことの重要性を指摘する。現在DeToNatorのメンバーは台湾で活動しているが、とくに相談がない限り、あえてアドバイスは送らないそうだ。
「自発的に考えて、モチベーションを高めて行動できる選手は、めったにいません。僕がこれまでで“この人”、と思うのは、もう選手ではないのですが、『カウンターストライク』で活躍したnoppoくん。彼はダントツで、自分で動き、自分で考え、それでいまの地位がある。そういう子はいまは出ていないし、noppoくんに憧れる子もいない。みんな、周囲の環境に依存しているんですよね。真剣に危機感を持ってやらないと、ここまで盛り上がってきたシーンがゼロになる可能性もあると思っています。そこはオールジャパンで、戦っていかなければならないと感じています」(江尻さん)。
(※2017/5/25 19:50 名前の誤りを修正しました)
危機感が不足している状況については、チョコブランカさんも同様の意見だ。
「いまの子たちを見てると、すぐに結果や答えをほしがっている気がします。育成企画でも、すぐ答えは与えないような指導で、考える力をつけてほしいのですが、生徒からしてみると、あまり教えてもらえないというように映るみたいです。でも、自分で考える力をつけないと、プロになったとしても戦っていけないと思うんですよね」(チョコブランカさん)。
大会やイベント運営のありかた
黒川氏は続いて大友氏に、チームや選手について思うところはないか、運営側としての意見を求めた。さまざまなトッププレイヤーを見てきた大友氏だが、大友氏いわく、ゲームのジャンルによっても印象が違い、歴史の古い格闘ゲームのプレイヤーなどはおしなべてマナーのいい大人で、歴史の浅いゲームについては、若い年相応に精神的に未熟な人もいたそうだ。
「こんなことまでTwitterに上げるんだ、とか、困惑することも多かったです(笑)。RAGE発足当時はそういうこともありましたが、大会を重ねると、見られる側としてどこかでスイッチが入るんでしょうね。対応も大人になってきます。そういうふうに自覚を持たせていく部分は、引き続き強化していきたいです」(大友氏)。
また協会代表としての立場から、選手をサポートする部分について、筧氏はサッカーや野球の例を挙げて説明した。心得や注意点などに関し、プロ1年目の新人選手を集めてセミナーを開くようなことが、eスポーツにおいてもしかるべきだという。協会としての正規なプログラムではないが、学校の特別授業で講習を開いたりする活動を続けているそうだ。
筧氏の発言に加えて、江尻さんは「恵まれた環境にいることを、選手たちにはもっと感じてほしいですね」とコメント。Wカップで優勝した女子サッカーのメンバーでさえ、国内でのリーグ戦ではアピールのビラ配りをするような状況を例に挙げ、「ほかのスポーツも見習って、現実を見てプロ意識を高めないと状況は変わらない。ゲームに対して真剣に向き合う面でも、海外のトップレベルと比べるとまだまだ弱いですよね」とのことだ。
日本ならではの大会運営や選手育成という点に関しては、大友氏は、中央にステージがあり周囲を観客が囲む海外スタイルをひとつの目標と挙げつつも、「ドリームハックのような、見る以外にお祭り要素を楽しめるものが、いまの日本のeスポーツに合うのかな、と考えています」と語る。その背景には、ただ試合をするだけでは、配信で事足りてしまうという状況もある。
「あの選手をじかに見たいと、会場に人が集まる時代を作っていくとともに、実況では味わえない体験を用意できれば、裾野は広がっていくのかなと思います」(大友氏)。
バトル観戦以外の楽しみという部分では、チョコブランカさんはコミュニティーイベントを展開しているそうで、『ストリートファイターV』をテーマとした、“東京オフラインパーティー”を定期的に開催しているという。
「大会とせず、あえてパーティーと呼ぶのは、初級者から上級者まで楽しめるものにしたかったからです。最近では遠方からの参加者も増えてきました。コミュニティーが元気になれば、その上も元気になっていく。そんな流れを作っていければいいなと思います」と語る。手軽に利用できるイベントスペース“スタジオスカイ”を運営するなど、最近では運営する側のサポートにも力を入れているようだ。
続いての発言は江尻さん。コミュニティーという点について、「我々も同じように、ゲームをプレイしなくても興味を持ってもらうといいますか、見る人を育てなければいけないと思っています」と語った。江尻さんは、地方イベントに選手を派遣するなど、コミュニティー作りの活動を積極的に行っているという。
この活動については筧氏も、「地方を回っていて、量販店のゲームPCコーナーを見ると、いたるところでDeToNatorさんの名前を見ますよ。これからDeToNatorさんが来ます! とか、地方に本当によく行ってますよね」と、感心していた。
eスポーツを取り巻く環境の変化
セッションも終盤となり、ここで黒川氏が最後にふたつのテーマを提示。まずひとつ目は、“国内のパブリッシャーの協力”という点についてだ。eスポーツの大会でタイトルが取り上げられるとしても、メーカーにとっては言わば、“旧作”。「積極的に協力してくれるの?」という疑問を黒川氏が投げかけた。
RAGEを展開する大友氏は、「個人的な印象としては、とくにスマホアプリなどは、発売タイトルに関して事前にご相談をいただくことが増えてきました。ですので、非常に協力的な印象を受けています」とコメント。また嬉しかったエピソードとして挙げたのは、“玄武杯”、“朱雀杯”といった、小規模の『ストリートファイターV』をテーマとした大会だ。
「カプコン様に、賞品としてオリジナルコスチュームを提供いただいたことが、すごく嬉しかったですね。そうした形でご協力いただく機会が、これからも増えるといいと思ってます」(大友氏)。
同様に筧氏も、「最近はメーカーがeスポーツにきちんと向き合い始めてくれている」という印象を持っているという。一例として以下の話を紹介した。
「あなたの会社のこのタイトルで大会を開きたい、とアピールし続けていたタイトルがあるんです。それが、いまになってそのメーカーの方から、あのとき断らなければよかった、と言われたんです。つまり、競技シーンやコミュニティー作りに、もっと協力すればよかったというニュアンスなんですね。そういう意味では、メーカーの姿勢も、昨年から今年にかけて、わりとガラッと変わってきた気がします」(筧氏)。
ふたつ目、ラストとなるテーマは、“選手のセカンドキャリア”。これには各ゲストが、セッションの締めという意味も含め、順番に意見を語った。リポートの締めくくりとして、以下にコメントをまとめて紹介する。
大友氏
CyberZとして配信プラットフォームを持っていますので、一線を退いたあとのハコというか、受け口としていろいろなものを提供できるような存在でありたいと思っています。とくに、一線を退いて配信者として活動している人が、いまはすごく増えてきているように感じます。いままではユーチューバーというか、おもしろくしゃべれる人が人気でしたが、最近ではゲームプレイだけで視聴を集める方も多くなってきているので、ゲームストリーマーみたいな職種も今後は増えてくるのではないでしょうか。あとは、実況者のマーケットが少ないことを課題に思っています。詳しく解説できる人は大勢いますが、スポーツアナウンサーのように盛り上げて実況できる人はまだ少ないですよね。そういったプロの育成についても、なにか貢献はしていきたいと思っています。
チョコブランカさん
私たち夫婦自身のセカンドキャリアとして、起業したような部分はあります。それで今年は、コーチの募集などもしたんですね。チーム戦ですと、海外でもコーチがいるのは当たり前なのですが、格闘ゲームでもそういうことができればと思いまして。いろいろ新しいことに挑戦して、それが誰かのセカンドキャリアになればいいなと思います。まだ手探りですが、これからいろいろ作っていければと思っています。
筧氏
eスポーツリーグが発展すれば、ひとつの産業として回っていき、解説、指導者、裏方スタッフなど、雇用が成立していきます。そのための活動を、僕らがやらなきゃいけないということですね。そうした中から強い人が出てきて、海外に挑戦するというストーリーが、いちばんいいだろうなと思っています。もうひとつは、いわゆるユース世代についてです。僕の若いころ、サッカーのうまい知人がいたのですが、ユース時代に同じポジションに柱谷選手がいて、サッカーをあきらめて別の道に選んだということがありました。だから切磋琢磨する中で、自分の選ぶべき道は何かと考えることは、通過点として整備していかなければと思います。学校のeスポーツ科を卒業するような人もこれから出てきますが、プロ選手になる人にもならない人にも、就職できる道を少しずつでも用意できるようになればいいなと思っています。
江尻さん
うちのチームでも、選手のセカンドキャリアとして、パートナーさまに面倒を見てもらうことが多いです。自分の会社にも入れてます。僕も選手には厳しいほうなのですが、やはり生きていくうえで、現役を退いてからのほうが長いんですね。だからそこに真剣に向き合い、覚悟を持ってやるなら、サポートしたいんですよ。「チームに入ったら将来どう面倒を見てくれるんですか?」と聞いてくるような子も以前はいました。ちょっと待てよ、と。セカンドキャリアを勝ち取れるのは、がんばった者が、求められて行くんですよ。ウチに来た以上、なんとかしようとはもちろん思いますが、選手自身がコミットしなければ、話は成立ないということです。これは何年たっても変わらない状況だと思います。