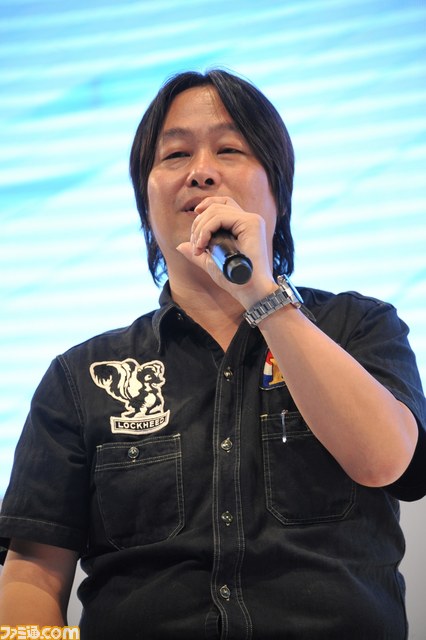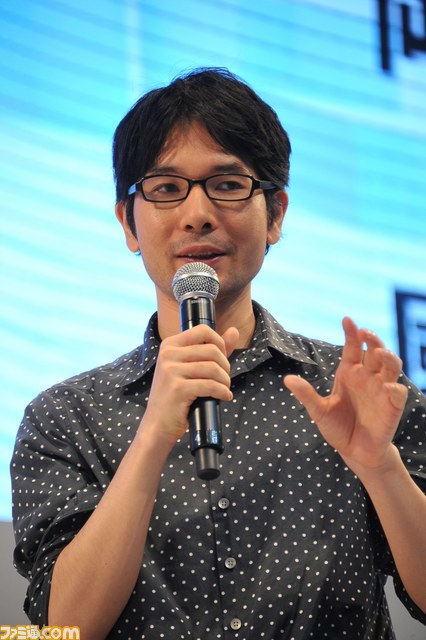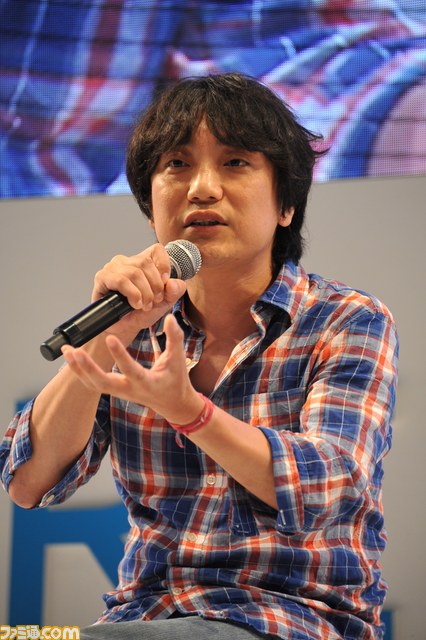ソーシャルゲームは日常に入り込んだエンターテインメント
2012年9月20日~23日、千葉県・幕張メッセにて東京ゲームショウ 2012が開催。開催2日目には、グリーブースにて“ビジネスセッション”として、“ゲーミフィケーションの盛り上がりにみるゲームの力”と題されたパネルディスカッションが行われた。ゲーミフィケーションとは、課題の解決や顧客の獲得などを、ゲームデザインの手法を用いて行う取り組みのこと。近年アメリカを中心に大きな注目を集めており、オバマ大統領がアメリカ大統領選挙の資金集めの際に展開した“マイバラクオバマ・ドットコム”でもおなじみだ。
トークセッションは、グリーの澤田典宏氏をモデレーター役に、日本におけるゲーミフィケーション研究の第一人者である国際大学GLOCOM 客員研究員 井上明人氏、エンタースフィア 代表取締役 岡本基氏、gumi 代表取締役社長 國光宏尚氏の3名が参加。ゲーミフィケーションの可能性について語り合った。
まずテーマとして取り上げられたのが“過去からの変動の可視化”。つまり、自分の達成した成果をいかに目に見える形でわかりやすく表現するかということで、たとえば、レベル1からレベル2に上がったといったことなどはその一例に当たる。何かを「達成した」とユーザーに思わせるには、“可視化”をしてわかりやすく表現する必要があるというわけだ。岡本氏が例示した、コンシューマーゲームにおける“スコアリング”や“コレクション”は、そんな可視化の適例と言えるだろう。いまやほとんどのソーシャルゲームに標準的に採用されている、ログインボーナスも“可視化”の一例。井上氏によると、仕事の効率を上げるためにもこの“可視化”は行われており、社内でプロジェクト管理にゲーム要素を取り入れている企業もあるそうだ。「このタスクをこなしたらバッチをプレゼントする」といった取り組みを行なっているのだ。
おつぎのお題は“場の文脈付け”。“場の文脈付け”というと少々難解かもしれないが、具体例を出すとわかりやすいかもしれない。要は、“悪者がお姫さまをさらった”というストーリーを聞いたときに、何も言われずとも“救出に向かう”という意識が働くコンテクスト(文脈)のことだ。岡本氏によると、“文脈付け”ということでは、ストーリーのほかに“直感性”があるとのこと。たとえば、敵キャラクターのデザインを見ると、「こいつはこうすれば倒せるな」と何も説明されずとも倒しかたがわかるケースが多い。「ストーリーで語るところもあれば、見た目で語るところもある」と岡本氏。
さらに“文脈付け”の応用として國光氏が挙げたのが、企業イメージの付けかた。エンターテインメント企業にとって会社のファンを作るというのは大きな武器になるが、じつはそれがなかなかに難しい。ところがごく一部で、ファンの獲得に成功している企業も存在する。たとえば、よしもとや宝塚などがそれに該当する。それは、「●●とはこういうものだ」という決まったひとつの価値を提供し続けているからだと國光氏は言う。つまり企業の“文脈付け”だ。壮大なワンパターンでイメージを刷り込むというのだ。gumiではそれを応用して、『任侠道』や『騎士道』などの『道』シリーズや、『幻獣姫』や『青春姫』などの『姫』シリーズをリリースすることで、パッケージ感をつけているという。これはCDのレーベル戦略に近いとのことだ。『海賊道』では、ユーザーの「海賊になりたかった」という子どものころの(中二病的な)夢を叶えてくれる。「今度は俺の中のどんな中二病的な心をくすぐってくれるんだろう」と期待されることをgumiでは意識しているのだという。
3つめのテーマは“達成すべき大きな目標をレイヤー化させていく”。ほとんどのゲームはチュートリアルから始めて徐々に複雑な操作を覚えていくようになる。まずは達成しやすいところに目標を設定して、徐々に難易度を上げていくことになる。そんな、“レイヤー化”について、ソーシャルゲームのクリエイターたちはどう考えているのか。まず岡本氏がわかりやすい例として挙げたのが、Xbox 360の“実績”。ご存じの通り“実績”は、ゲームのやり込み具合を可視化したもので、ゲームをプレイしていくと、徐々に実績が解除されることになる。実績解除は、ゲーム開発者からのやり込みに対する“贈りモノ”といった意味合いもあり、「ゲームでは少しずつ褒めてあげるのが重要です」と岡本氏。そして“褒める”ということに関して岡本氏が、コンシューマーゲームとソーシャルゲームとの興味深い違いを例示してくれた。「コンシューマーゲームでは、よかったら褒めるし、悪かったらダメとはっきりできるが、フリー トゥー プレイのソーシャルゲームは、容易にやめられる分、すごく褒めるか、褒めるしかない」(岡本氏)というのだ。たしかにコンシューマーのアクションゲームなどでは、最初は失敗しまくっていても、徐々に上達してきて達成感を味わえる。いわばダメなことがモチベーションになってやる気を掻き立てるのだ。ところが、ソーシャルゲームは一端挫折すると、そのままで終わってしまうことが多い。これはなぜか?
この問いに対して岡本氏は、「家庭用ゲーム機は子どもの文化だったのではないか」と推察する。子どもは勝負に負けるのが悔しいので、何とかがんばってクリアーしようと思って鍛錬を続けるが、大人は時間も限られているので、何か嫌なことがあると、ほかのものに興味を移してしまうというのだ。これに呼応する形で國光氏が、「子どもは日々の生活の中でストレスを感じることが少ないので、ゲームの中でストレスがあっても問題ありませんが、大人は日常生活がストレスに満ちあふれているので、ゲームの中でまで苦しめられたくないのかもしれませんね」と発言し、パネリストの賛同を得ていた。「いずれにせよ、一般社会ではあまり褒められることがない分、頻繁に褒められるのがゲームのいいところだというのは言えるかもしれません」と澤田氏。
さらに、“褒められる”ということに関して言えば、「ソーシャルゲームの限りなく大きな価値のうちのひとつではないか」と國光氏も続ける。たとえば、映画にしてもコンシューマーゲームにしても、あるいはテレビにしても、いずれも気合を入れなければ体験することはできない。いわば、休みの日にしか楽しめないエンターテインメントだ。ところがソーシャルゲームは、日常生活の中で気軽に遊べる。通勤時間で楽しんだり、就寝前のちょっとした時間に遊べる。「ランチタイムで魔王を倒しにいけるのがソーシャルゲーム」(國光氏)なのだ。映画やコンシューマーゲームはふつうの人の日常に影響を与えることはできなかった。だから“余暇”と言われてきたわけだが、ソーシャルゲームは日常に入り込んできており、たとえ日常があまりおもしろくなくても、彩りを与えてくれる存在になり得るというのだ。
それに対して井上氏も、「ゲーミフィケーションというのは、人々の日常にゲームを持ち込めるということです」と、國光氏の意見に全面的に賛同する。コンシューマーゲーム機は、電源を付けないとゲームを遊べないが、iPhoneだと四六時中ゲームを遊ぶことができる。これは、「日常そのものをハードにできるのと同じ」(井上氏)だと言う。ソーシャルゲームとゲーミフィケーションはその点で非常に似ており、「“日常”をプラットフォームにした初めてのゲームがソーシャルゲーム」という井上氏の意見には、うなづかされるものがある。
最後に、このセッションのまとめとして、澤田氏はふたつのポイントを挙げてくれた。ひとつめは、“ゲーム製作者の可能性”。こらは、ゲームを開発するということには娯楽面だけではなくゲーミフィケーションなども含め、幅の広いゲーム作りが可能であるということ。そしてふたつめが“知識の共有によるよりおもしろいゲーム作り”。こちらは、クリエイターどうしが意見交換をする場はなかなか持てないが、できるだけ交流を深めてよりよいゲーム作りに役立てましょう、という来場者へのメッセージとなった。
たしかに、日本ではまだまだ浸透しているとは言い難いゲーミフィケーションだが、「5年後、10年後には、いまのソーシャルゲームに対するのと同様のスタンスを持って取り組まれているのではないか」という井上氏のコメントが説得力を持つような、刺激に富んだトークセッションとなった。極めて相性がいいと思われるソーシャルゲームとゲーミフィケーション。今後、ソーシャルゲームにとって、ゲーミフィケーションがどのような役割を果すことになるのか、興味は尽きない。