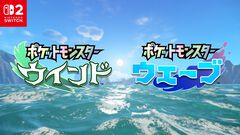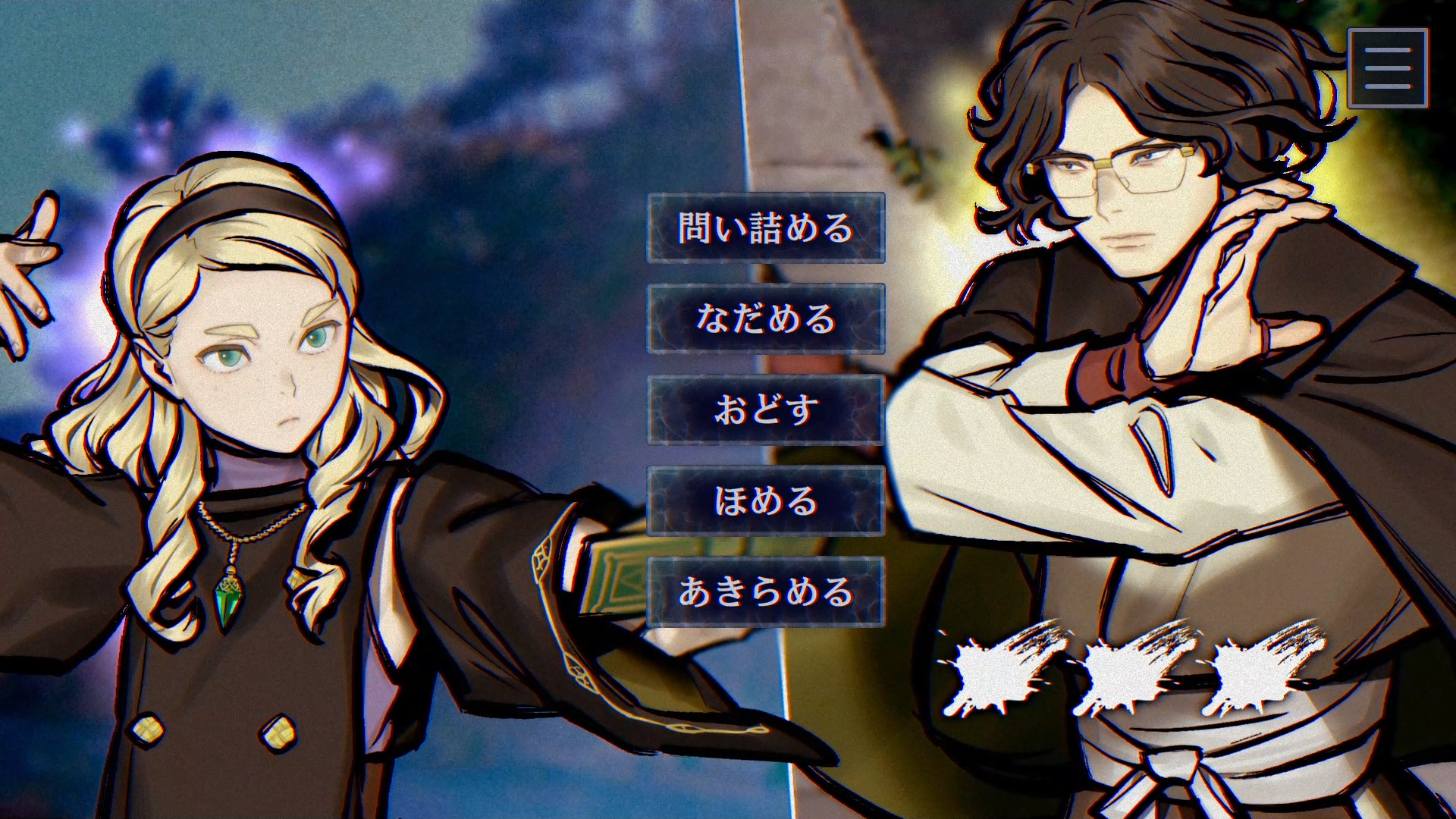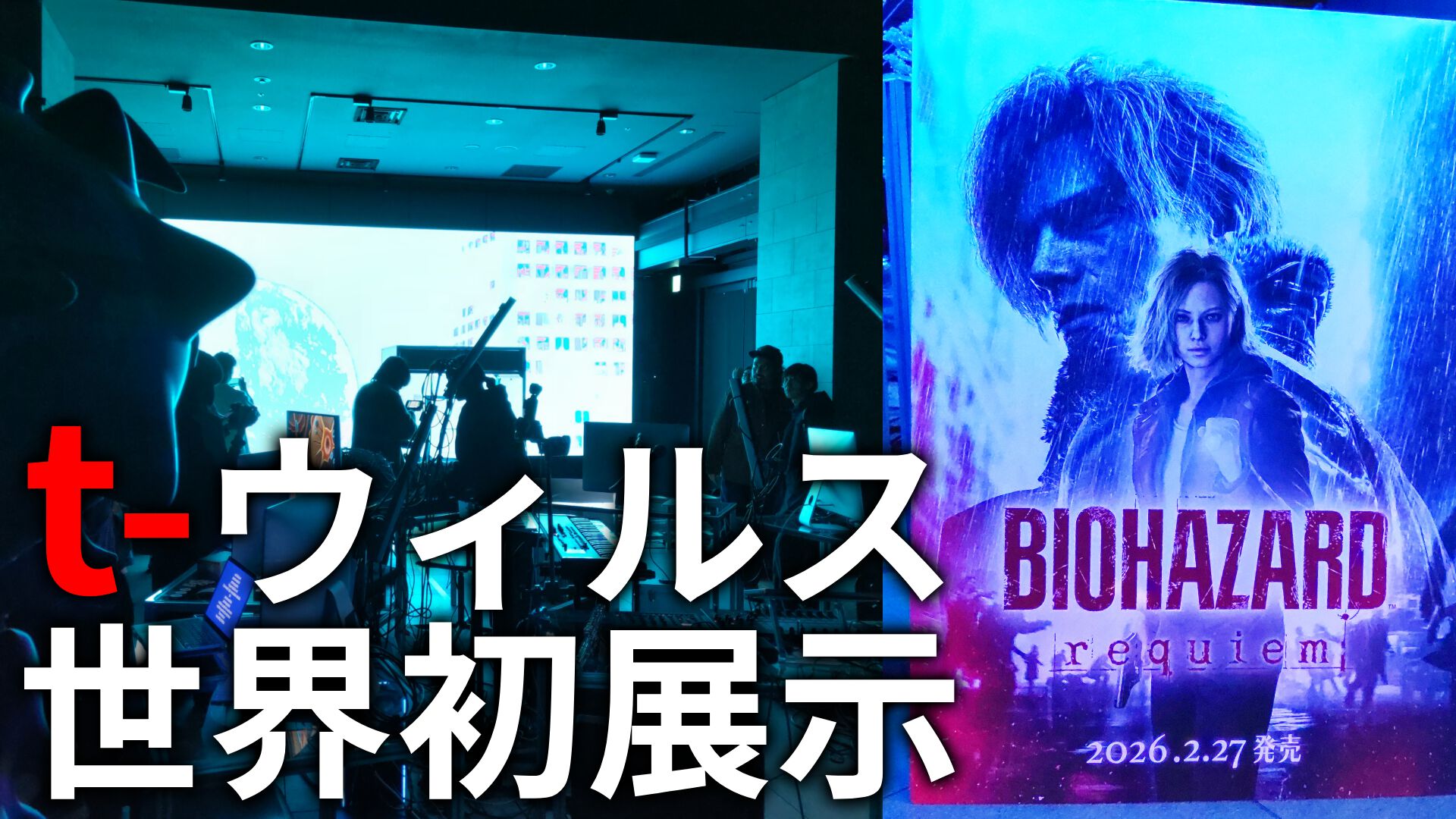スクウェア・エニックスのオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)のパッチ7.xシリーズにおいて、現在展開中のレイドコンテンツ“至天の座アルカディア”シリーズ。その中でもパッチ7.2で追加された第2弾“クルーザー級”はいかにして制作されたのか。各層を担当した開発者へのインタビューをお届けする。
前編の記事では“至天の座アルカディア”の全体像や各層のコンセプトなどを聞いたが、後編では各層を深掘り。ギミックの制作秘話やこだわりなどをうかがった。ぜひ前編と合わせてチェックしてほしい。
※本記事内の内容については、とくに前置きがない限りは零式について言及したものになります。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
横澤剛志 氏(よこざわ つよし)
アシスタントディレクター。“至天の座アルカディア:クルーザー級”では監督者としてコンテンツ全体を監修。文中は横澤。
吉橋和登 氏(よしはし かずと)
バトルコンテンツデザイナー。至天の座アルカディア:クルーザー級1(以下、1層)を担当。文中は吉橋。
森田畝生 氏(もりた せな)
バトルコンテンツデザイナー。至天の座アルカディア:クルーザー級2(以下、2層)を担当。文中は森田。
岩附知宏 氏(いわつき ともひろ)
バトルコンテンツデザイナー。至天の座アルカディア:クルーザー級3(以下、3層)を担当。文中は岩附。
秦成志朗 氏(はた せいしろう)
バトルコンテンツデザイナー。至天の座アルカディア:クルーザー級4(以下、4層)を担当。文中は秦。
1層は本当にダンスを踊っていたかのような体験を目指して
――インタビューの後編では、各層の深堀りをしていきたいと思います。まず1層ですが、ボスのダンシング・グリーンはダンサーという設定で、バトルステージもダンスフロアになっているなど、ビジュアル、サウンドともにすごく印象的でした。制作のうえでとくに意識されたポイントなどはありますか?
吉橋
ダンスとひと口に言っても年代によってさまざまですが、今回は1970~1980年代のアメリカのディスコをテーマにして、あらゆる音、ビジュアル、ゲーム体験を作り込もうと意識しました。そうした中で、アルカディアがあるソリューション・ナインは近未来を感じさせるSFチックなビジュアルをしているため、それと似た方向性にならないようにしています。クラブではなく、ディスコを好んでいるという設定ですね。
――バトル中に流れる楽曲も、往年の1970~1980年代のディスコミュージックを意識したものになっていますよね。このあたりもサウンドチームにオーダーした形でしょうか。
吉橋
はい。ボス自身も踊るバトルにしたかったので、いまのようなハイテンポなダンスミュージックではなく、当時のディスコでかかっていたソウル・ミュージック風にしてほしいというオーダーをしました。
――nポイント&ポーズという技のエフェクトも、スペクトラムアナライザー風というか、グラフィックイコライザー風というか。
吉橋
そうですね。当時の音楽やビジュアルにマッチするように、ボスが出してくるエフェクトをイコライザーのような表現にしたり、音符を浮かせたりしています。僕自身は当時のディスコ文化を知りませんから、まずは自分で調べて資料を作りながら知識を蓄えて、それを エフェクトチームに共有して、「こういう方向性でいきたい」と伝えて作っていただきました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
――nポイント&ポーズの話題を続けるのですが、nの値に合わせてSEが変化したり、技のタイミングもBGMとシンクロしていて、ものすごく凝っているなと。
吉橋
1層を作っていく中で、そこがいちばん苦労したポイントです。じつは、ずっと前から「BGMとSE、バトルが密接に連動したバトルを作りたい」という思いがあったんです。そしてその方向性が、今回の1層のテーマとすごくマッチしていたため、この機会に実現させようと思ってチャレンジをしてみました。
ただ、『FFXIV』はクライアントとサーバーで通信をしながら遊ぶゲームですから、どうしてもタイムラグが出るため、音のタイミングを揃えるのがすごく難しいのです。そのため、早い段階でプログラマーとサウンド担当の方、そして祖堅さん(サウンドディレクター・コンポーザーの祖堅正慶氏)にも入っていただいて、何度も打ち合わせをさせてもらいました。そして細かいすり合わせをしながら、なんとかいまの形にできたという感じです。
――サウンドを担当された方のリアクションはいかがでしたか?
吉橋
じつは、今日のインタビューのためにサウンド担当の方からもメッセージをいただきまして、その方いわく、数年おきに必ず、バトルコンテンツデザイナーから「音ゲーのようなバトルをやりたい」という要望が来るらしいんです。もちろん、実現すれば音楽や効果音にフォーカスしたおもしろいコンテンツになるとは思うのですが、先ほどもお話しした通り、オンラインゲームで音の同期の問題を解決することが難しく、「どうやって実現させるか……」と頭を抱える日々だったそうです。
そこで今回は、バトルコンテンツデザイナーやプログラマー、モーション、エフェクトを作るアーティスト、そしてサウンド班など、各セクションが連動して、「ここでボスがこういう動きをして、このタイミングで通信をして、この瞬間に音を鳴らす」といったタイムラインを1フレーム単位で作り、それを調整していくというやりかたを試してみました。
流れとしては、開発環境を使って仮の素材でテストをして、「この方向性ならうまくいきそうだな」という部分を手探りで作っていき、本番の素材の作成に入るという形ですね。ここまでテストをするケースは、ほかのコンテンツでは前例がないかもしれません。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
――少し脱線するのですが、ダンシング・グリーンはプレイヤーがうまくギミックをこなせると「パーフェクトだ! 最高にイケてたぜッ!」とほめてくれますよね。なんだ、いいヤツじゃん、と思いました。
吉橋
ダンシング・グリーンはとにかく陽気で、「相手を打ち負かしてやろう」ではなく、その場にいる観客も含めて全員がダンスでハッピーになればそれでいい、と考えるようなキャラクターだろうとイメージしていました。これは零式限定の演出なのですが、最後に「またダンスフロアで会おうぜッ!」というセリフもあったりしますから。
――時間切れ間際のセリフですね。
吉橋
そういうキャラクターなので、うまくギミックをこなせばほめてくれるし、客が盛り下がったら「おいおい、ガッカリだぜ」と言ってくるなど、「彼ならこんなことを言いそうだな」と妄想しながら作っていきました。
――戦う相手ではあるのですが、基本的に憎めないキャラクターですよね。そんな彼とのバトルではアフロヘアー姿のカエルも登場するのですが、これはどういった経緯で生まれたキャラクターなのでしょうか?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
吉橋
バックダンサーを登場させて、ダンスフロア上でボスといっしょにダンス攻撃をさせたり、お立ち台に並んで大技のギミックをくり出したりということは、企画の初期段階からやりたいと思っていました。
なお、ダンシング・グリーンが取り込む魔物の魂はトードで、バックダンサーたちはそれと同じ眷属ということは決まっていましたので、そこからアーティストが発想していったという流れですね。アーティストに渡していた参考資料の中に、アフロヘアーのダンサーの写真もいくつかあったと思います。
――ムーンウォークや『サタデー・ナイト・フィーバー』(※)のようなポーズも印象的でした。
※:ディスコを舞台にした1977年のアメリカ映画。主演ジョン・トラボルタによる片腕を上げた決めポーズが有名で、ダンシング・グリーンのポーズにもオマージュされている。吉橋
あの年代をテーマにしているなら、これは入れるしかないなと(笑)。
――先ほど、ダンシング・グリーンはトードの魂を取り込んだという話がありましたが、これはどういった経緯でトードになったのでしょうか?
吉橋
魔物のチョイスにあたっては、まず『FF』の世界にいる代表的な魔物をリストアップし、その中から今回のテーマに合った“踊れそうな魔物”をピックアップしていきました。ダンシング・グリーンは、魔物の魂を取り入れる前も踊りを得意とするキャラクターなので、「彼の踊りをよりスゴいものにする魔物はなんだろう?」と。
選定中にはクモやタコなど、“手足をいっぱい増やして、ふつうの人体ではできない踊りを表現する”といった案もありました。最終的にはトードに決定したのですが、理由はシンプルで、身体能力を人間のときから底上げするだけでなく、カエルには歌う(輪唱)というイメージもあります。今回のバトルのテーマのひとつには“バトルとサウンドの調和”があったので、その点からもトードがぴったりだろうと。
すでにウサギのような耳があるヴィエラとトードの融合ということで、アーティストにはけっこう苦労をかけてしまったかもしれませんが……(苦笑)。
――最後に難度についてお聞きします。過去のインタビューで1層を担当していた方が、「1層は最初に挑む層なので、ある程度難度を抑えなくてはいけないが、だからといって簡単にこなされないようにしたい」とおっしゃっていたのが記憶に残っているのですが、今回、難度付けをするにあたって苦労されたポイントなどはありますか?
吉橋
ギミックを考えるにあたって、ダンシング・グリーンが明るい性格を演じていることから、「脳トレ系や、ひねった攻撃はあまりしてこないだろう」とは考えました。さらにダンスが主軸のため、全体的にフィジカル系(※)のギミックが中心になり、得意な人にとってはそれほど難しくない1層になるだろうと思って作っていました。
※フィジカル系……反射神経やキャラクターコントロールの器用さなど、身体能力が問われるものという意味として使われる。吉橋
また、自分としては「1層だからといってなめられてはいけない」という考えはまったくありませんでした。自分の中では、とにかく戦い終わった後に「まるで本当にダンスを踊っていたかのような体験だった」と感じられるようにできれば、今回の1層は成功だろうと。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
――横澤さんが最初にお話しされていた、“結果的にコンテンツの難度が多少落ちてしまったとしても 、おもしろさを追求する”という考えですね(前編参照)。
吉橋
といっても、じつは零式の大技の“レッツダンス!”は、調整中はもっと難しかったんです。とても1層クラスの難度ではなかったので、かなりマイルドにしていまの形になったという経緯があります。
――お立ち台にいるバックダンサーたちが手で示す方向に合わせて、フィールド半面攻撃が連続でくり出されるという技ですよね?
吉橋
そうです。当初は、1回目から前後左右4方向のパターンがあり、いまよりももっとテンポが早く、かつそれを避けながらふたりペアを作って音響爆弾αとβを処理していく、というものでした。
――それは……1層ではやりたくないですね(笑)。
横澤
テストプレイでやってみたら、「さすがにちょっと……」という感じでした(笑)。ダンスをさせたいというコンセプトがあるなら、もっとそれがプレイヤーにストレートに伝わるものにしたほうがいいだろうということで、いまの形に落ち着いています。
――それでは、1層の締めくくりとして横澤さんに総括いただけますか。
横澤
すごく苦労して作ったという話でしたが、本当に狙った通りのものが体現できていて、吉橋のしっかりした部分が余すことなく出たコンテンツになったなと思います。彼を1層担当に任命して本当によかったなと感じました。
徹底的に作り込んだウェーブ戦を目指した零式2層
――2層のバトルは、砂漠、河、溶岩と、フィールドがつぎつぎと変わっていくのが印象的でした。これは開発当初から決まっていたのでしょうか?
森田
初期の企画書に書かれていた原案には、ほかにも“ファンタジー樹海”に変化したり、昼から夜に時間経過して流星群が降ってきたりと、さまざまな要素が書かれていました。そこからブラッシュアップしていった結果、いまの形に落ち着いた感じですね。
――ファンタジー樹海ではどんなことが起こる想定だったのでしょうか?
横澤
ファンタジー樹海については、“キノコが生えてきて胞子を撒き散らす”といったイメージはあったものの、砂漠のサボテンが爆発するのと本質的には変わらないね、ということで、より変化を出せそうな河のフィールドを採用した形です。
――変化するフィールドの数は決めていたのでしょうか?
横澤
戦闘時間の制約から、せいぜいふたつくらいまでだろうと考えていました。さらに砂漠では流砂が発生して、河ではマグマが流れるといったように、バトル中にボスが“アレンジ”を使ってフィールドに変化を加えるという要素も主軸に据えていましたから、その点でも数は最初から決めていましたね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
――2層はボスがスプレーガンで描いた絵が具現化されてからギミックが発動するという、時間差攻撃のような形になっていますが、いわゆるタイムラインを意識されたのでしょうか?
森田
いえ、ボスが絵を描いてそれが具現化されるという、演出的な側面が強いです。2層では、絵が具現化される場所をチャネリングライン(線)で示していますが、当初はいろいろなものが具現化される想定で、線がフィールドのあちこちに飛び交っていたんです。これでは視認性が悪いということで、いまのようなシンプルな形に着地させました。
――なるほど。なぜタイムラインの話を持ち出したかと言いますと、全体的に近接物理DPSが攻撃しやすいように配慮されていると感じたからです。
森田
それは意識しました。たとえば、矢が飛んでくるギミックでは、ステージ中央付近のどこかが必ず安全地帯になるようにしています。
――いわゆるバースト(※)タイミングも意識されたのでしょうか?
※バースト……与ダメージを上昇させるバフの多くが120秒周期であることから、使用するタイミングを全員で揃えて攻撃を最大化させること。森田
意識しています。ただ、2層では砂漠フェーズでサボテンの爆発を避けながらだったり、河フェーズで雷を避けながらだったりと、そこまで気持ちよく攻撃できなかったかもしれません。ギミックやタイムラインの都合上、どうしても今回のような形になることはあります。
――そして零式2層と言えば、多くのパーティが苦戦したであろう、いわゆる雑魚フェーズも印象に残っています。このフェーズのコンセプトからお聞かせください。
森田
コンセプトはずばり“ウェーブ戦(※)をやる”ということでした。『FFXIV』における雑魚フェーズは、バトル中にボスが画面外に消えて増援が出現し、すべて処理するとつぎの増援が出現する、といった流れが多かったと思います。しかし、今回の2層はそうでなく、戦っている最中につぎからつぎへと増援が出現します。そのうえで、倒す優先順位を誤ると致命的な全体攻撃を食らうなど、先々の展開も考えてもらうところにフォーカスしました。言ってしまえば、“大迷宮バハムート:邂逅編4”の再来というイメージですね。
※ウェーブ戦……その名のごとく、波(ウェーブ)のように敵がつぎつぎと押し寄せてくること。第1波、第2波といった具合に、グループ単位で出現することが一般的。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
――レイドではひさびさのウェーブ戦でしょうか。
横澤
形式的なウェーブ戦としては、“機工城アレキサンダー:起動編2”以来になります。
――2層の雑魚フェーズは、DPSのアクションローテーションをはじめ、タンクの誘導、防御バフまわし、ヒーラーのヒールワークなど、あらゆる面で最適化が要求された印象です。開発側としてはどのようなことを意識されましたか?
森田
雑魚フェーズでは、どのロールにも役割を持たせたいという狙いがありました。たとえば、レンジのジョブがフェザーサークルを誘導して、メレーがジャバウォックにスタンを入れる、などですね。ロールごとの負荷に関しては、何度もテストプレイを行って、「どこまでならいけるか」というギリギリを攻めていった感じです。
――にしても、タンクへの攻撃はキツすぎませんか?(笑)
森田
じつは、タンクへの攻撃はいまよりももっとキツかったんです。上げては下げてを何度も何度もくり返して、詰めていきました。
秦
テストプレイのときは、自分と岩附がタンクを担当していたのですが、何度もの調整を試して、しっかりと手ごたえを感じていただけるラインを探っていきました。 もちろん、最初はたいへんかもしれませんが、トライをくり返すごとに慣れていきますし、プレイヤーの皆さんならきっと大丈夫だと思っていました。とはいえ、僕らもコツをつかめるまでは、ヤーンを抱えながら「もうバフがありません!」とひーひー言っていたのは間違いないです(笑)。
――そうして、ギリギリまで難度を追い込んだ雑魚フェーズによって、2層が攻略のストッパーになりました。近年では珍しいことだと思いますが、開発チーム内ではどのように受け止めていましたか?
横澤
今回の2層の雑魚フェーズはタンクが敵をどう誘導するかがすごく重要ですので、その考えかたが浸透し、動きが洗練されていけば、おのずとクリアーするパーティも増えてくるだろうと思っていました。ですので、そこまで不安は感じていませんでした。
――なるほど。雑魚フェーズが話題になったのは、その難度だけでなく、ムーやヤーン、いただきキャットといった『FFIX』由来の敵が登場したという点もありました。
森田
はい。『FFIX』の敵を登場させるにあたり、原作のエッセンスを出したいなと思っていました。たとえば、ムーは原作では原石をねだってきて、原石を渡すと「ありがとう」と言ってAP(※)を10くれるんです。それを『FFXIV』のバトル内で再現するために、ボスのシュガーライオットの“原石あげる”に連動して、ムーが“原石ありがとう”という超痛い全体攻撃を放つ、といったようにしています。
※AP……アビリティポイント。『FFIX』において、アクションアビリティやサポートアビリティを習得する際に必要になる。森田
いただきキャットも、原作では無視すると隕石を落としてくるので、『FFXIV』でも時間内に倒せなかったらメテオを降らせてくる……といったように、それぞれエッセンスを盛り込んだ形ですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
横澤
森田に引き継いだ段階で、すでに『FFIX』に登場する精霊たちを使うというのは決めていたので、そこから広げてくれた感じですね。ちなみに、精霊を選んだのは自分でした。手ごたえのあるバトルのなかに、かわいいモンスターが入ることで中和剤になればいいなと……。
――中和は……されていないかもしれません(笑)。 といっても、ヤーンはファンアートがSNSに溢れるくらい、話題になっていましたよね。
横澤
良くも悪くも注目されましたね。
――そういえば、インタビューの前編でタンク強攻撃について“大喜利”というキーワードが出ていましたけれど、その詳細を教えていただけますか。
横澤
タンクへの強攻撃を単純な大ダメージにするだけでなく、ほかにも要素を加えることを、我々は“タンク大喜利”と呼んでいるんです。言ってしまえば、タンク強攻撃にバリエーションを持たせるイメージですね。
森田
今回の2層でも「タンク強攻撃は大喜利をしてほしい」というオーダーが出ていたので、ボスが青いインクを放つのか、赤いインクを放つのかを確認して、それぞれのタンクが近づく・離れるを判断するといったものにしています。
――ギミックとしてはすごくシンプルですが、判断を誤ると甚大な被害が出るんですよね(笑)。
森田
テストプレイでもよく秦さんが叫んでいました(笑)。
秦
くり返しプレイしていると「あれ? どっちだっけ!?」という状況に陥りますね。
――ちなみに、開発当初から大きく変わったギミックはありますか?
森田
2層に関してはスムーズに進行していて、すべて調整の範囲です。強いて挙げるなら、砂漠フェーズでのサボテンの爆発を避ける際、全員が北側に集合して反復横跳びをするように動いて避けるやり方が多いと思いますが、あれはできないようになっていました。
――サボテンがもっと不規則に出現していた?
森田
そうですね。出現ロジックがいまとは違って偏った配置になることもあり、横移動だけでは避けきれませんでした。また、現在はサボテンの爆発を避け切った後に“熱蓄積”のデバフによる爆発が発生しますが、当初はデバフの秒数がバラバラかつ全員に付与されていて、残りの秒数が迫っている人だけ離れて、そこでサボテンの爆発を避けないといけない作りになっていました。
――サボテンの爆発を避けながらデバフ処理ということは、デバフなしの人たちがある程度固まっていないとジャマになってしまいそうなのに、サボテンの出現ロジックは変則的であると。たしかに、きびしそうです。
森田
あとは、雑魚フェーズ中にボスが“どっすんババロア”という技をくり出していたのですが、それもボツになりました。
――どんな技だったのですか?
森田
いわゆる“タケノコ”ギミックです。雑魚を処理するためにわちゃわちゃとみんなが動きまわっている中、それぞれの足もとにドカンと。ですから、雑魚フェーズでもっとも凶悪なのはボスだったんです。どっすんババロアのキャストを見逃さないように、フォーカスターゲットは必須レベルでした。テストプレイ中は「ババロア! ババロア!」とみんなで叫んでいましたね(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
――避け忘れ、他者の巻き込み、もう考えたくないですね……(笑)。それでは、最後に横澤さんに2層の総括もお願いします。
横澤
2層は、じつは僕がベースのアイデアを8割くらい出していました。同じウェーブ戦である“大迷宮バハムート:邂逅編4”も自分が作っていて、当時を知っている人間だったのも大きいです。企画をしたのはひさびさでしたが、楽しんでやれたと思います。
――2層は横澤さんの意向が色濃いわけですね。
横澤
全体の監督という立場であるものの、自分のアイデアがもっとも色濃く反映されている層なのは間違いないです。2層はプレイヤーによって賛否はあるかと思いますが、印象に残る層にすることができたと思います。
――従来の2層より歯応えがあったものの、立ち回りの工夫次第で突破できる絶妙な難度だったと感じました。
森田
あ! そういえば2層には小ネタも仕込んでいます。連続頭割り攻撃“プリンパーティー”の際に、5%の確率で“プリンの形をしたインク”が落ちてくるという隠し要素を用意しています。
――河フェーズで“積乱雲”のギミックが終わった後の頭割り攻撃ですよね?
森田
はい。基本は球状のインクが落ちてくるのですが、プリンの形をしたインクが5%の確率で落ちてきます。ここはアーティストさんといっしょになって、楽しみながら作りましたので、今後2層に挑戦する際はぜひ注目してもらえるとうれしいです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
通常の頭割り攻撃“プリンパーティー”はこちら。球体に目が描かれている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
こちらは同じパーティのフレンドが撮影した写真(どうやら見た目がプリンになるかはプレイヤーごとに違う模様)。確かにプリンが混ざっている。
3層は2回のステージ転換でトリッキーなバトルに
――3層ではブルートボンバーが複数の魔物の魂を取り込んで、ブルートアボミネーターとなって戦うというストーリーが展開しますが、複数の魔物の魂を取り込むというのは企画当初から決まっていたのでしょうか。
岩附
そうですね。シナリオチームから「複数の魂を組み合わせてほしい」というオーダーがありました。
――取り込む魔物の魂は岩附さんが選ばれたのでしょうか?
岩附
はい。どの魔物の魂を取り込むかは、自分で選ばせていただきました。どの魔物の魂を使い、どんな能力を掛け合わせたら新しいことができそうか、という観点で魔物をリストアップしています。
なお、もともとのキャラクターがブルートボンバーですし、闇市のような場所で魔物の魂を買い漁るというシナリオの流れもあって、プライドの高いブルートボンバーならプリンやトードといった魔物の魂は買わないだろうと考えました。結果、『FF』シリーズの中でもある程度“格がある魔物”をピックアップして、ギミックへの活かしやすさも考えて最終的に選んだのが、カトブレパス、サイクロプス、ベラドンナの3体でした。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
――複数の魔物の魂を取り込むとはいえ、ベースはブルートボンバーではあるので、オリジナルの彼らしさを残すことも意識しましたか?
岩附
もちろん意識しましたが、「前回のライトヘビー級3がこうだったから、今回はこうしなきゃいけない」というような“枷”としては考えていませんでした。とりあえず、自由にバトルの構想を考えた後に、ブルートボンバーらしさを出せるエッセンスを加えたというイメージです。
たとえば、アイビーラリアットはブルートボンバーらしさを出すために取り入れた要素ですが、前回と同じではおもしろ味に欠けるので、見栄えを変えるなど、新規性を出しています。といっても、あまり擦りすぎても白けてしまうので、「本能はブルートボンバーなんだ」とうっすら感じられる程度のニュアンスがちょうどいいのかなと考えました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
――オリジナルのブルートボンバー(ライトヘビー級3)を作られたのは秦さんですが、今回のブルートアボミネーターはいかがですか?
秦
ラリアットや連続全体攻撃といったブルートボンバーらしさもしっかり残っていて、とてもよかったですね。なお個人的には、シナリオについて「こんなことになってしまうなんて……!」というショックが大きいです。
――ネタバレになるので詳細は伏せますが、たしかにそうですよね……。さて、3層では3つのフィールドを移動して戦うのが大きな特徴ですが、これはどのようにして考えられたのでしょうか?
岩附
フィールドを変えて戦うことは草案段階から検討していて、せっかくなら形状が違うフィールドで戦ったほうがおもしろいバトルになるだろうと思っていました。そういった狙いもあって、最初は正方形のオーソドックスなバトルフィールドから始まって、つぎに長方形のフィールドでトリッキーなバトルを展開させることにしました。
ただ、最後の地底フィールドに関しては、零式のギミックを作るうえでリソースの制約もありましたので、取り回しを考慮して最初のフィールドと同じ正方形にしています。
――長方形のフィールドでは、ボスがビルからビルへと移動するなど、ユニークなギミックが多いですよね。その中でも零式でとくに印象に残っているのが、8方向に広がる茨を捨てていく“ソーンデスマッチ・ビルディング”です。このギミックにはいくつかの解法が生み出されていますが、開発チームはどういった攻略法を想定されていましたか?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
岩附
いま3層のパーティ募集で主流になっている処理法が、開発想定の解法に近いですね。ビルからの茨につながれる遠隔ジョブのシードの捨てる位置は想定と多少違いますが、それ以外の近接やヒーラーの動きはまったくいっしょなので、ほぼ想定していた形かなと思います。
――ソーンデスマッチ・ビルディングは3層前半の壁となっていた印象で、歴戦の猛者によってつぎつぎとやりやすい方法が編み出されていくのが印象的でした。
岩附
今回の3層は直観的なギミックが多く、イチからロジックを考えるようなものはほぼなかったので、全体のギミックを見るまでそれほど時間はかからないだろうと思っていました。最終的にボスのHPを削り切るまでの火力を詰めるほうに時間を要するだろうとは考えていましたが、おおむね想定していた通りという印象です。
――あと、3層で難所だと感じたのは、最後のフィールドでくり出される“ストーンウェポン:ツイン”からのブロウシードです。シードを捨てる位置に対して、ストーンウェポンの安全地帯がもっとも遠いパターンになってしまった場合、スプリントを使って移動してもギリギリで、かなりきわどい調整だと感じました。
岩附
開発想定の解法に比べると、プレイヤーの皆さんのあいだで主流となっている解法では“シードを捨てる位置が1ブロック外側”のため、そう感じるのかもしれません。主流の解法は、正方形に配置されたフィールドマーカーを目印にシードを捨てるため判断しやすいという利点はあります。
――なるほど。フィールドマーカーの都合で遠くなっているということですね。確かに、ボスに対して後列のシードは安全地帯を潰しさえしなければ、もう少しルーズに捨てても問題ないんですよね。
岩附
ちなみに、その“ストーンウェポン:ツイン”からのシード捨てのギミックは、いまはタンク・ヒーラーの4人、DPSの4人という区分けで予兆マーカーが付き、シードを捨てにいくようになっていますが、あれは当初もっと複雑だったんです。
――どんな感じだったのですか?
岩附
まず、予兆マーカーはメンバーの中からランダムでふたりに付くという形でした。そのふたりはボスが1回目のストーンウェポンの攻撃をくり出す前にシードを捨て、その最中に続いて別のふたりに予兆マーカーが付きます。そのシードはラリアットをかわしながら捨てて……といった感じでした。対象者がランダムなうえ、シードを捨てるタイミングもいまより多く、なかなかたいへんなギミックだったのです。ただ、そこにたどり着くまで10分ほど戦ってきて、最終盤に待ちかまえているギミックとしてこの難度は適切なのか、という意見も多かったので、現在はよい難度に落ち着いたかなと思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
――その仕様でやってみたい、という猛者もいそうですね(笑)。では、横澤さんに3層の総括をお願いします。
横澤
クルーザー級の中でもっともトリッキーなことをやったのが3層だと思っていて、場面転換が2回もあったり、ボスが壁に張り付いて移動したりと、パッと見たときの驚きをわかりやすく提供できた層になったと思います。今回のレイドのコンセプトである、“新しくておもしろいことを追求しよう”というテーマが反映されていますね。1層、2層と担当しながらステップアップしてきている岩附のいいところが出た層です。
ちょっと余談になるのですが、開発が終盤に差し掛かったBGMが入るか入らないかというタイミングで、「吉田が歌で参加させられているらしい」という噂を聞いたんです。チーム内でも「メインボーカルだったらどうする?」と、ざわついていました(笑)。どうやら、サウンドの祖堅に言われてデスボイスシャウトで参加させられたとのことです。
4層のフィールドの狭さは明確な意図がある
――インタビュー前編で各層のコンセプトをうかがった際、4層はスピード感やテンポを重視したとのことでしたが、改めて意識されたポイントをお聞かせください。
秦
先にお話しさせていただいたように、今回の4層は“令和のタイタン”をテーマにしていて、素早い判断が必要な攻撃をつぎつぎと畳み掛けていくバトルを意識しました。それに加えて、受けるダメージもギリギリに調整していて、しっかりと軽減アクションを合わせて、仲間と連携しながらボスの猛攻をしのぐ、といったバランスにしています。
あくまで個人的な好みなのですが、大量のデバフが付いてそれに応じた動きをするというギミックはあまり作りません。今回の4層前半に関してはデバフを極力使わないように意識しました。
――4層のハウリングブレードは、光剣による攻撃のほかにも、ビットやフェンリル(群狼)など、いろいろな要素が複合的に組み合わさっていますが、どのようにしてギミックを組み立てていったのでしょうか?
秦
メインのコンセプトとして“剣技による連続攻撃”というものがあったので、まず考えたのは剣を使ったギミックです。“群狼剣”や“幻狼招来”などの剣技をメインで作っていき、そこからビットの攻撃を追加していきました。また、ビットではできないような、たとえば連続シェアダメージや巨大な塔を出現させるなどのギミックは、風と土のフェンリルを使ったという感じです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
――零式の群狼剣はボスに近づいて対処する“薙”と、離れて対処する“廻”がありますが、とくに“廻”のときのタンクの立ち位置がシビアだった印象です。
秦
今回の4層は、フィールドマーカーを8方向に設置している人が多いのですが、開発チームによる調整の際は、6方向にだけ設置してテストプレイを行っていました。なぜ6方向かというと、“群狼剣:廻”はフィールドを6分割したうちのいずれかにボスが飛んでいくので、フィールドマーカーを6ヵ所に置いておけば、タンクの立ち位置の目安にできるからです。その形であれば、もう少し楽になるかもしれません。それでも立ち位置がシビアになっているのは事実ですね……。
――そのさじ加減は難しいですよね。マージンを取りすぎると難度を担保できないというか。
秦
“薙”と“廻”は対極にある技で、共通の安全地帯などで対処されたりするのは絶対に避けたいと思っていました。それもあっていまの攻撃範囲に設定してあります。
――群狼剣に関連して、3回目の群狼剣ではフェンリルの直線範囲攻撃が追加されますが、うっかり食らってしまう攻撃の筆頭でした。
秦
あれはちゃんとした理由づけもありまして、ノーマル難度でもそうなのですが、履行技の後にボスにバフがついているんですよ。その状態で群狼剣をくり出すと、フェンリルの攻撃が追加で発動するという仕組みです。
これも調整中の段階で履行技の後に何か変化がほしいなと思い、“ボスの剣技に対してフェンリルが追加攻撃でサポートする強化状態”になっているという形にしました。
――シンプルな直線範囲なのですが、当たっちゃうんですよね……。
秦
調整中も「頭がくるよ! 頭がくるよ!」と連呼していましたね(笑)。攻撃としては大したことはないのですが、全体のテンポが早いため、ついつい抜け落ちてしまうのかもしれません。
あと、スピード感という意味では、4層は意図的にフィールドを小さくしています。これはコンセプトとして、ボスが連続剣の際に高速で移動するという演出にしたかったからなのですが、通常のレイドのフィールドサイズでは近接ジョブが攻撃しづらくなり、プレイ体験としても窮屈さを感じさせる可能性がありました。工夫すればロスなく攻撃し続けられる、といった作りにするためにも、フィールドを小さくしたという意図があります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
――群狼剣は、ボスの動きに合わせて近接ジョブがビュンビュンと移動していたのが印象的でしたが、確かにロスなく攻撃できるギリギリのフィールドサイズになっていますね。
秦
ボスのターゲットサークルの大きさで、このぐらいのフィールドの大きさならGCD(※)間に移動しながら攻撃できるよね、というところを予測して作っていきました。
※GCD……グローバルクールダウンの略。アクションを使った際に発生する、つぎのアクションを実行できるまでの共通の待ち時間のこと。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
――その狭いフィールドでもうひとつ印象的だったギミックが “千年の風化”です。DPSの位置を半固定化する解法も生み出されていますが、これは想定されていましたか?
秦
はい、想定していました。本当はフェンリルの回転方向と、予兆マーカーがついたロールだけ確認して、マーカーがついたロールは直線攻撃を追いかけるように動き、最初にマーカーがつかなかったロールは90度ずれた場所で処理、という解法を考えていました。
ですが、攻撃範囲の都合もあって、予兆マーカーがつく順番に関係なく、ほぼほぼ固定の位置で円範囲攻撃を捨てられるなと気づいてはいました。
横澤
調整段階では、僕たちも円範囲攻撃を捨てる位置を固定にしていたよね。
秦
完全に固定化させていましたね。ちなみに、あそこは細かい間隔でボスからのノックバックが2回あるのですが、「2回ともノックバック無効化アクションでしのげる形にはしない」という意図のもと、間隔を調整しています。
――ギミックに関する話が続くのですが、巨大な塔を出現させてから“斬空剣”で塔を倒壊させるギミックについて、これはノーマル難度のほうが難しくないですか?(笑)
秦
このギミックは零式ではやりたくないだろうというところで、いまの形になっています。ギミックとしてはアトラクション的な位置付けで、わちゃわちゃさせる側面が大きいので、零式では仕組みがわかってしまえば容易に対応できるという方向性にしました。あそこで詰まってしまうのは、プレイ体験としても気持ちよくないかなと。
――そして、最初のフィールドで最大の山場となる“幻狼招来”ですが、こちらについてもお聞かせください。
秦
おっしゃる通り、前半の難所として作っています。早いテンポでいくつもの細かい判断をさせたいという思惑があって、それを突き詰めていったのがあのギミックですね。
現在は4回のなぎ払い攻撃を避けつつ、ロール単位の円範囲攻撃とシェアダメージという複合ギミックになっていますが、開発当初はさらにビットの攻撃も加わっていたんです。これはさすがに難度が高すぎました(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
――思いとどまっていただいてよかったです(笑)。さて、この難所をくぐり抜けるとフィールドが転換して後半に入るわけですが、今回の零式4層は後半にチェックポイントがない、“通し”の作りになっていました。このあたりの構成は、どのようにして決めているのでしょうか?
秦
プレイヤーの皆さんのフィードバックはもちろん考慮するのですが、コンテンツ作りに着手するタイミング的に、前回のレイドの意見を反映させるのは難しいのです。ですので、そのバトルの難度付けの一環として考えることが多いですね。
――それでは、今回はなぜチェックポイントがなかったのでしょうか?
秦
じつは、もともとは後半にチェックポイントを置く想定だったのですが、後半の地形が特殊なこともあり、後半だけ独立させた形で難度を調整することが難しかったというのが実情です。結果、いまの形になったのですが、全体の難度のバランスはよくなったかなと思います。
――後半の浮島を転移しながら戦うという展開は、どういった発想から生まれたのでしょうか?
秦
後半を作るにあたり、前半のバトルからガラッと印象を変えないとインパクトがないだろうと思っていたので、どのようなものを作るかはすごく悩みました。そんなときに、自分が担当した“希望の園エデン:再生編1”や“万魔殿パンデモニウム:辺獄編2”などの特殊なフィールドを思い出して、今回の4層はその方向性に振ろうと決めました。
まず再生編1の“暗黒天空”のような、1マスに乗れる人数が限られているという遊びをとっかかりに考え始め 、そこから発展して最終的にあの浮島に行き着いた感じです。ですので、4層後半は先にあの地形を完成させたうえでギミックを考えていきました。
――ボスを取り囲むようなフィールドは8人用のレイドでは初めてで、すごくユニークだなと感じました。ギミックもフィールドと密接に関連していましたし、浮島を移動する転移装置の時間制限もうまく機能していて。
秦
途中で転移装置に対して7秒のクールタイムが設けられるのですが、じつはあの移動制限はずっとつきまとう想定だったんです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
――その場合、敵の攻撃の順番をしっかり把握していないと、移動がギリギリになる場面もありそうですね。
秦
実際、調整中はそうなっていました。これはプレイ体験としては窮屈になりすぎていたので、結果的にいまの形に調整しています。
――後半のギミックについておうかがいしますが、“廻天動地“ではつぎにくる範囲攻撃を隣の浮島の予兆を見て確認していた人も多いと思います。じつは、どの範囲攻撃がくるかはボスの向きで決まっていて、ボスだけ見ていれば避けられるんですよね。このことについて、坂口さん(坂口博信氏。『FF』の生みの親であり、『FFXIV』プレイヤーとしても知られる)がXにポストされていて、目から鱗でした(笑)。
秦
廻天動地は、発想的にはボスが向いている方向で5つの浮島にくり出される範囲攻撃が決まっていて、ボスの向きや回転方向を考えて避けるというのが原点でした。
ちなみに、いまは島ひとつぶんボスが回転するものしかありませんが、開発当初はひとつ飛ばしで回転するフェーズもあったんです。つまり、ふたつ先の浮島の範囲攻撃を見極めないといけないという作りになっていました。実際にやってみたら、難しすぎました(苦笑)。
――そして、時間切れ直前のギミックですが、ひとつずつ浮島が壊され、追い詰められていく演出もよかったと思います。
秦
おそらく、タンクでプレイされた方は、受け止め攻撃を無敵アクションで受けるのがすごく気持ちよかったのではないかなと思っています。今回の浮島フィールドを考えたときから、この演出は入れようと思っていました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
――それでは、横澤さんに4層の総括をお願いします。
横澤
秦が話した通り、前半と後半で印象がガラリと変わるバトルになっていますよね。前半は“令和のタイタン”という話がありましたが、本当に一歩間違うとすごく難しくなったり、逆に簡単になったりと、振幅が大きいバトルだったと思います。最終的にちょうどいい難度バランスに着地できたので、そこはしっかりと秦が実力を見せてくれました。
後半もいままでにないバトルに挑戦して、ユニークなコンテンツに仕上がっていると思います。ここも、秦がこれまでの経験を活かしながら、実力を発揮してくれた部分ですね。
今後も新たな体験と記憶に残るコンテンツを目指して
――ここまで各層を掘り下げてお話をうかがってきましたが、改めて横澤さんにクルーザー級全体を総括いただければと思います。
横澤
いままでとはまた違った方向性を意識して、しっかりとコンセプト通りのものが提供できたと思います。プレイヤーの方々の反応も見ているのですが、ポジティブな意見も多く、手応えを感じています。
――なおレイドにおいては、ギミックによってどうしても「近接ジョブが攻撃しづらい」、「遠隔魔法ジョブが詠唱しづらい」というシチュエーションが出てくるかと思います。その点についてクルーザー級では、どのように調整されましたか?
横澤
パッチ7.0のライトヘビー級からの変化としては、ボスのターゲットサークルの大きさも含め、多少ギミック中に近接ジョブが攻撃しづらくなるシーンがあるだろうというのは予想しており、そのぶん近接ジョブの火力を上げるという対応を行いました。そのうえで、コンテンツ側としても工夫しだいで攻撃し続けられる作りを意識したので、「どうやっても攻撃できない」という理不尽感は抑えながらも、レイドとしてのユニーク性は出せたかなと思います。
――7.xシリーズ全体で感じることとしては、フィジカル系のギミックが多い印象なのですが、これはシーズンごとに変わっていくのでしょうか? それとも「7.xシリーズ全体としてフィジカル系に寄せる」というコンセプトがあったりするのでしょうか?
横澤
そういうわけではないのですが、今回の7.2のクルーザー級に関しては明確に方向性の違いを感じていただけるように、開発初期の段階で「デバフ系のギミックはなるべく使わないようにしよう」という指示を出して、かなり意識しました。ですが、基本は制限を課さないようにしています。今後のコンテンツに関しては、プレイヤーの方々の反応を見ながら、つぎの担当者がやりたい、おもしろそうだと判断すれば、デバフを使ったギミックも取り入れると思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
――では最後に、レイドを楽しみにしているプレイヤーの方々に向けて、それぞれメッセージをお願いします。
吉橋
レイドに限らず、IDやクエストバトル、討伐・討滅戦など、あらゆるコンテンツを通して、記憶に残るものを企画することを意識しています。思い返すと「あのバトルはユニークだったな」とか、「おもしろいボスキャラクターだったな」とか、そう思っていただけるような、そして新しさや驚きを感じられるものを作れたらいいなと思っています。
森田
プレイヤーの皆さんそれぞれに、好みやプレイスタイルの違いがある中で、全員に楽しんでいただけるバトルコンテンツを作るのは簡単ではありません。 ただそのうえで、ひとりでも多くの方に楽しんでいただけるよう、今後もがんばってコンテンツを作っていきたいと思っています。つぎのレイドにもどうぞご期待ください!
岩附
コンテンツを作るゲームデザイナーとして、“味のするコンテンツ”を残していきたいですね。もちろん、より多くの方が楽しめるようにすることは大前提ですが、独自の魅力がある、記憶に残るようなコンテンツを作っていきたいと思っています。
秦
今回のクルーザー級は、初めての4層ということもあって、かなりプレッシャーを感じていました。改めて振り返ると、反省すべき点もあるのですが、印象に残るバトルコンテンツになったのではないかと思っています。皆さんのコメントやSNS、フォーラムでの反応もたくさん拝見していまして、励みになります。今後もよりよいコンテンツを作っていきたいです。
横澤
レイドに限らず、『黄金のレガシー』のコンテンツ全体で、従来とは違うおもしろさをしっかりと出していこうと思っています。プレイヤーの方々の期待に応えられるよう、チーム一丸となってかんばりますので、引き続き『FFXIV』をよろしくお願いします。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a135007e7085979a7d5b41ce54c0e54d7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/afac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/ae4bde0eb46b8f32ef4b4207f5344b4d4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a86c3cbc8cde622a8c725d89a88bdcb96.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a1058abae0dc372f4432cbea7fa123512.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aae566253288191ce5d879e51dae1d8c3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a62bf1edb36141f114521ec4bb4175579.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aedab7ba7e203cd7576d1200465194ea8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/adb3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a85b6f89b41cae26786ac72365fff771b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a64b8299d1597b8a5c7b9cb9c88642f6c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aa269962fe1424e1ca3e68c328b9fed61.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/ae89666feb714ab9c3946f28f00c5d8c4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aca538c343179bf0fbdfab6cd10469afd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a030d7e8e966169ab4c7f67c291c333f4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a134ce63057f068a219a0df338fb0b723.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/a648b9906a614a4bb30c20591243c65ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/47282/aadaf0ad2e085c835a82b2f021fe236ae.jpg?x=767)