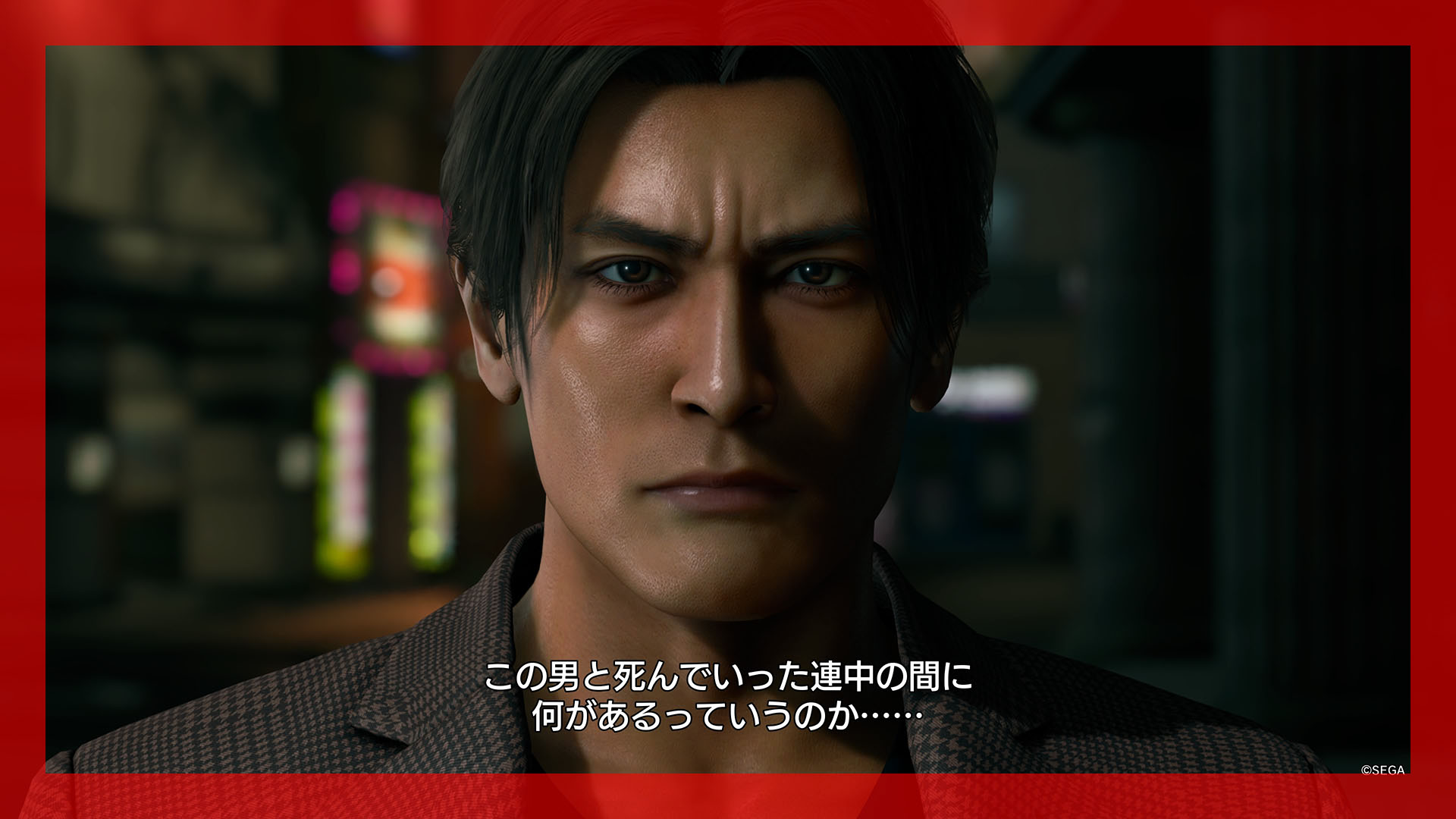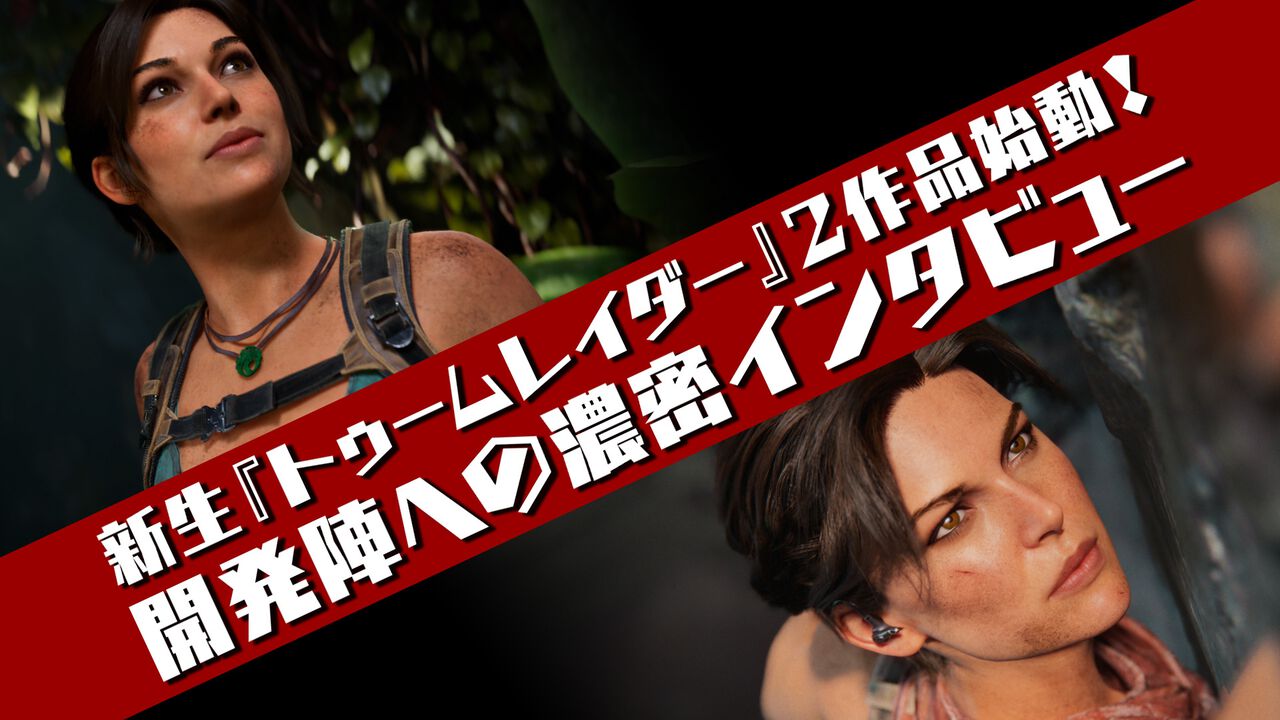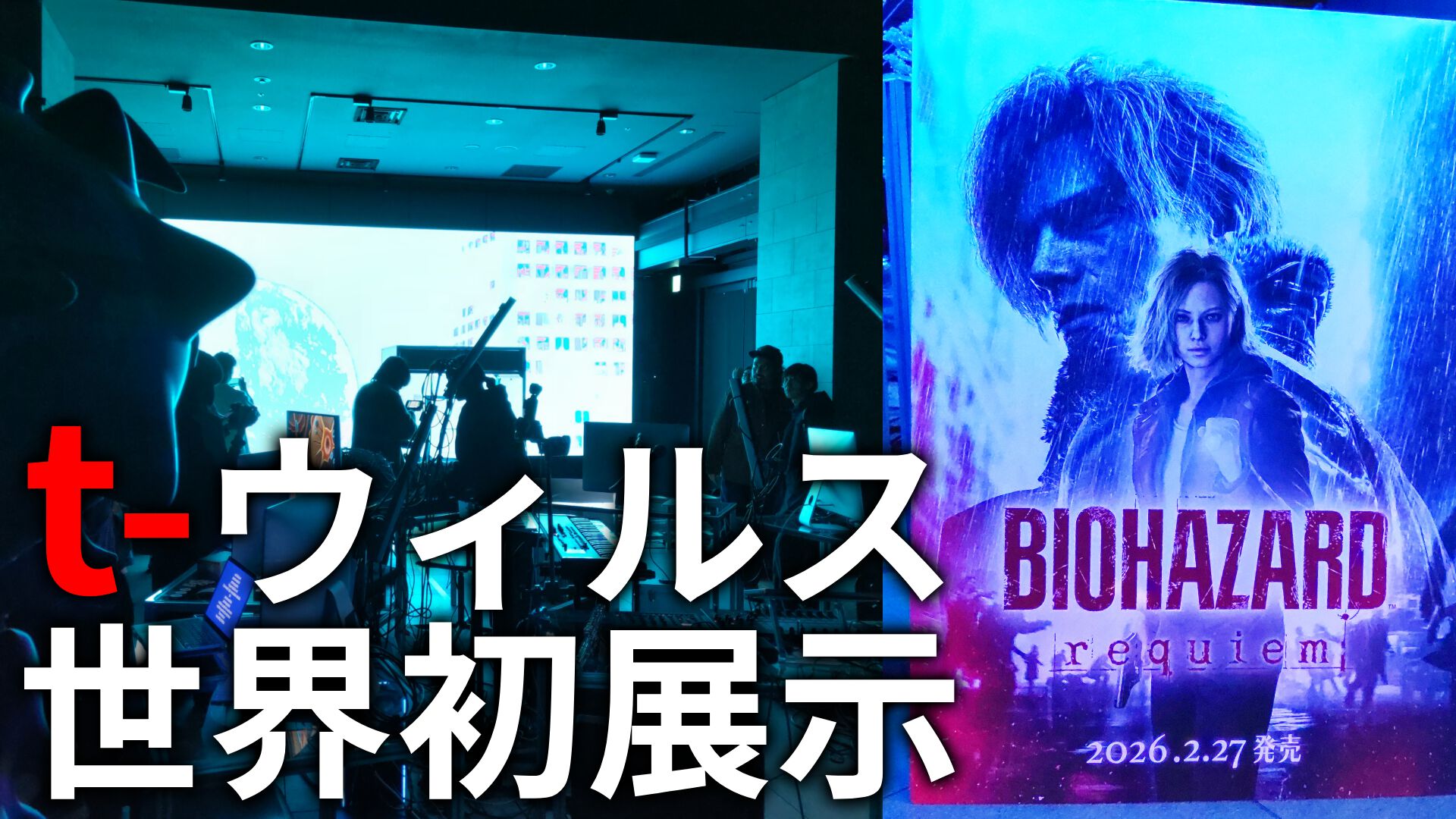THQ Noricの『REANIMAL』は、前夜に行われたオープニングイベントの“gamescom Opening Night Live(ONL)2024”にて発表されて、注目を集めたタイトルのひとつ。『リトルナイトメア』シリーズを開発していたスウェーデンのTarsier Studios(ターシア スタジオ)による新作ホラーアドベンチャーだ。どのような経緯で本作が生まれたのか、ナラティブディレクターのDavid Mervik(デイビッド・メルヴィック)氏に聞いた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/aed6869f01d267ca15246f4a4142ec797.jpg?x=767)
David Mervik氏(デイビッド・メルヴィック)
Tarsier Studios ナラティブディレクター
『REANIMAL』というタイトルは1年以上かけてつけた。そこに込めた思いをあれこれ考えてみてほしい。
――開発状況はいかがですか?
――本作開発の経緯を教えてください。
子どもと不気味な世界というのは、魅惑的なコントラストになります。さらに新しいことに取り組んでいきたいということで、協力プレイモードも入れることにしました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/8709b309b70bb43135064e745b0f0a7d.jpg?x=767)
子どもを主人公にしたいと思ったのは、子どもたちをこういった怖い環境に放り込むと、大人よりもより無防備でプレイヤーもより感情移入しやすいからです。彼らの行く末が心の底から気になる、という状態になる。本作と『リトルナイトメア』とのあいだに似た部分があることを感じる人もいるかもしれませんが、リアリティーの構築の仕方はまったく違ったものになっています。
怖いモンスターが出てくるというのは踏襲していますが、『REANIMAL』のほうがより地に足のついたリアリティーのある世界観になっているということは言えると思います。
――本作でとくに取り入れた新しい要素を教えてください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/a40b018db74c4e941189d31da5cf34c6e.jpg?x=767)
ただ、作品のソウルをよく表現しつつ、商標登録されていない言葉を見つけるというのが、すごく難しくて、1年以上の時間を費やして、私たちは言葉を探しました。けっきょく、“REANIMAL”という造語を作りにいたりました。
じつは、“REANIMAL”というのは、1回却下しようと思っていました。ただ、いろいろと考えた末に、やはり“REANIMAL”がいいのではないかという結論に落ち着きました。シンプルな言葉で口から発したときに気持ちがいいということもありますし、覚えやすい。“リアニメーション”(※)という言葉を少し連想させるということもあります。
私は小説を読むのが好きなのですが、いつも「作者はどうしてこのタイトルを付けたんだろう?」ということを読みながら考えるのが大好きで、本作では、そういう体験をしてほしいと思っています。
たとえば、“アニマ”という言葉があります。“魂”という意味なのですが、“REANIMAL”にはそういった言葉が含まれていたりとか……。タイトルの中のパーツパーツが、何かしらのゲームの大切な要素を表現するものであるということですね。
――“アニマル”が大きなカギを握ることは間違いなさそうですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/af17bb779c9408e9c8ed78c61c9321382.jpg?x=767)
本作の物語の構造としては、キャラクターたちは何が起きたのか理由がわかっています。でも、プレイヤーはわかっていないという状況です。主人公たちは何が起きたのか知っているので、そのことについて会話を交わしたりするのですが、詳細なディテールが明かされることはない状態で会話が進行していくので、プレイヤーはふたりの会話を聞きながら「いったい何があったのだろう?」ということを自分で考えていくんですね。そして、この世界でモンスターと闘いながら、抜け出していくのです。このストーリーの作りかたは『リトルナイトメア』シリーズを踏襲していますね。
――なぜ、キャラクターたちがわかっていて、プレイヤーがわかっていないというシチュエーションにしているのですか?
何か断片的な情報を提供して、「その背後には本当は何があるんだろう?」と気にさせることによって、どんどんストーリーに引き込まれていく。内容が忘れられなくなっていく……ということを目指しています。
『リトルナイトメア』シリーズに関しても、ストーリーが進むごとにいろいろと考えて、「これはどういうことなのか?」「ああ、こういうことだったのか」ということを楽しんでいただけたのではないかと思っています。
ひとつ言えるのは、すべてがわかってしまったらのめり込めなくなってしまうということです。「これは何なのだろう?」という、興味を惹かれる要素がなくなってしまうと物語の推進力が弱くなってしまう。これは、ストーリーテリングの手法としても有効だと思っています。実際に私たちが生きている世界の中で、日々暮らしていてすべてをみんなが見せるわけではないですよね。
――まあ、そうですね。
人間は本能的にミステリが好きなのだと思います。謎を解くという。ミステリ小説やテレビドラマは人気がありますよね。
――本作では協力プレイも楽しめるとのことですね。
私たちが目指す恐怖の方向性というのがあります。ひとり孤独に恐怖するのではなくて、友だちといっしょに身を寄せ合いながら、恐怖するというシチュエーションです。「怖いね」と言いながらホラー映画を観るような感じを目指しています。だからこそ、協力プレイでは画面分割にしないで、ふたりが同じフレームの中で、いっしょにプレイすることにしているのです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/add9f0231fbdd9cafa6cb2218bf445df4.jpg?x=767)
実際のところ、私たちは何年か前にまったく同じ境遇に立ったことがあります。『リトルビッグプラネット』をメディアモリキューさんから引き継いで、タイトルを進化させて『リトルビッグプラネット PlayStation Vita』(2012年)を作ったんですね。その状況は何となく理解できます。
私たちは私たちで、『リトルナイトメア』の世界から進んで、さらなる怖い世界が始まろうとしています。ファンの方たちにとっても、『リトルナイトメア3』と『REANIMAL』という、怖い世界観のゲームが出てきたことは、非常に喜ばしいことなのではないでしょうか。私たちもすごくワクワクしています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/15410/a2071f820466f4ce6926ff2dbd24570d2.jpg?x=767)