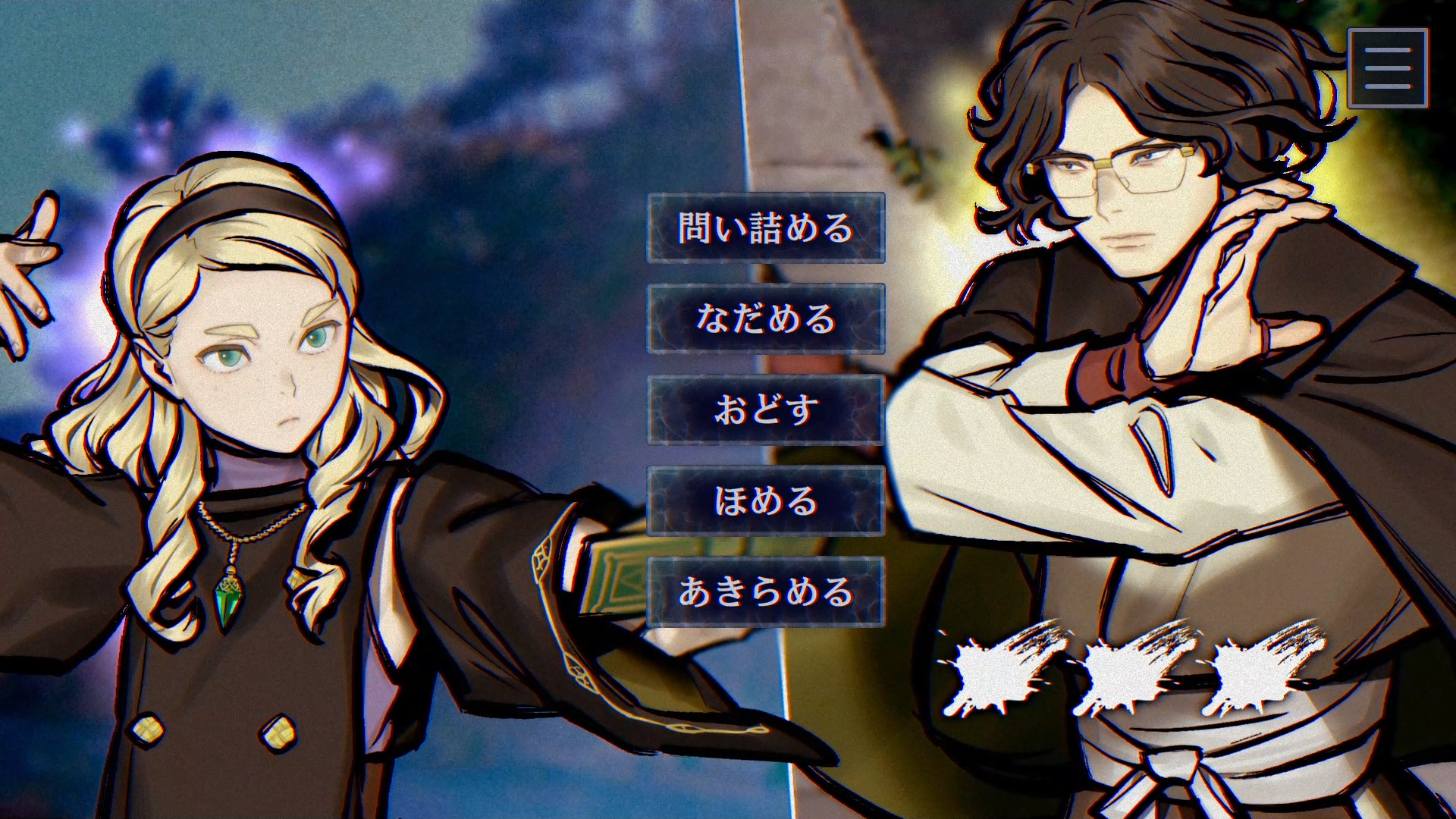2025年7月7日に25周年を迎えた、スクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジーIX』(以下、『FFIX』)。本作は、2000年7月7日にプレイステーション用ソフトとして発売。“命”をテーマにキャラクターたちが懸命に生きるさまが描かれ、25年が経ったいまでも多くのファンから支持される一作となっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/aaa6a0af77239b3c757a651ee1766fbae.jpg?x=767)
週刊ファミ通2025年7月24日発売号(2025年8月7日号 No.1908)では、そんな『FFIX』25周年を記念した18ページの特集を掲載。特集内では、『FFIX』の開発に携わったクリエイターからイベントデザイン 青木和彦氏、キャラクターデザイン 板鼻利幸氏、作曲 植松伸夫氏の3名にインタビューを行った。
今回、ファミ通.comでは御三方のインタビューをWebで再掲載。一部のインタビューでは増補改訂版となっているので、週刊ファミ通本誌を読んだ方もチェックしてほしい。
なお、週刊ファミ通の特集内では『FFIX』のイベントやグッズ情報をまとめて掲載。すでにイベントなどは終了してしまっているが、『FFIX』25周年を記念して新たに制作されたキービジュアルが表紙を飾った特集もあるので、こちらもどうぞ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a94318516d0ef8c1133ea33d328d174aa.jpg?x=767)
「ゲームは、手で触ってどう感じるかがすべてなんです」
『FFIX』25周年クリエイターインタビューで今回登場するのは、イベントデザインを担当した青木和彦氏。『FFIX』の物語がどのように作り込まれていったのかを語ってもらった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a310f70d6357c405fe3645a399679bc9d.jpg?x=767)
青木和彦氏(あおきかずひこ)
『半熟英雄』や複数の『FF』作品、『チョコボの不思議なダンジョン』シリーズなど、数々の作品を手掛けたクリエイター。2025年6月にスクウェア・エニックスを退社し、フリーランスとなった。(文中は青木)
スタッフが気持ちを汲み取り合う『FFIX』の開発現場
――『FFIX』が25周年を迎え、新しいグッズやイベントが展開され、ファンからは喜びの声が上がっています。まずは、こういった反響を聞いての感想を教えてください。
青木
本当にありがたいと思っています。作り手としては、10年先、20年先も語ってもらえるようなものを作りたいと思っていますので。こういったインタビューのお話があることも含めて、25年経ったいまもこういう風に作品のことを思っていただけるのはうれしいですし、「やっぱりそういうものを作らないといけないよな」と再認識できました。改めて、身が引き締まる思いですね。
――『FFIX』において、青木さんはイベントデザイン担当だったとのことですが、具体的にはどのような業務を担当されていたのでしょうか。
青木
イベントチームのリーダーとして、プロット作成などに関わっていました。ある程度作業の流れができたら、各イベントの担当者にプロットを渡して、その先はほぼ任せていましたね。物語の流れや、核となるメッセージは各スタッフが十分に理解しているので、そこにどんな色付けをしていくかは各担当に任せていました。僕は上がってきたものをチェックして、わかりづらい部分を直していくという作業をしていました。
――イベント制作に関わるスタッフの統括を担当されていたんですね。
青木
それと、開発の後半は、データの容量をエクセルでチェックするのが日課になっていました。『FFIX』はディスク4枚組だったんですけど、ちょっとムービーが入るだけで容量が足りなくなるので、どこでお話を区切るか、溢れた場合はどこかのマップを削れば調整できるかなどを計算する必要があったんです。それとディスク4では、「どこかのマップに入ると、ディスクの入れ換えが発生する」ということが起こらないようにしたかったので、ダンジョンの入り口を塞いじゃったりして、何とかして無理やり1枚に収めました。
――ここにムービーが入ったら盛り上がるけど、もう容量がないから無理……といった判断をされていたと。
青木
ムービーや曲は本当に容量を食うんですよ。ですので、ムービーの秒数は先に確定してもらっていました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ac43e1367b4671012999ad226fc6712ff.jpg?x=767)
――4枚組にすることは開発当初から決まっていたのですか?
青木
そうですね。4枚にしようというよりは、4枚にしないと想定している内容が入りきらないんじゃないか、という感じでした。
――いっそ5枚以上にするという選択肢もあったのでしょうか?
青木
けっきょくは、最後のディスクにさまざまなデータを収めないといけないので、4枚よりも増やすことは難しかったと思います。ディスクを収納するケースも、当時、最大4枚くらいまでにしか対応していなかったと思いますしね。
――本作の基本的なストーリーの流れは、青木さんが中心となって作られたのでしょうか。
青木
坂口さん(坂口博信氏。『FFIX』プロデューサー)が大もとのプロットを書いて、そこに僕やマップ関係のスタッフがストーリーを入れていったという形ですね。ジタンとガーネットの出会いのような骨子の部分は坂口さんが考えていました。キャラクターの名前も坂口さんが考えていましたが、名字はイベント担当が付けたりしています。
――最初から、坂口さんがフルネームで考えていたわけではないんですね。
青木
名字は開発の最後のほうまで調整していましたね。いまだと、ボイス収録などの関係で名字も最初に決めておく必要がありますが、当時はけっこうフレキシブルだったんですよ。
――近年のゲーム制作の現場では、後からキャラクターの名字を変えるのは難しそうです。
青木
近年とは違う点と言うと、当時、イベントはマップと関わってくる部分が多いので、マップ班のメンバーとはよく話をしていたんですけど、バトル班とはほぼ会話をしていなかったんです。僕が関わってきた『FF』ではだいたいいつもそうでした。
――なんと、イベント班とバトル班が連携することはなかったんですか?
青木
バトル班は勝手にバトルを作るし、イベント班は勝手にお話を作るし、という形でした。プロットはすでに各スタッフに共有されているので、「ストーリーはこういう流れで進むんだ」ということはバトル班もわかっているんですよね。たとえばビビが黒魔道士を相手に戦うバトルでは、勝ったときにビビは勝利ポーズを取りません。あれはイベント班から頼んだわけではなく、バトル班が気持ちを汲んで、ビビならここでポーズは取らないだろう、という判断をしています。そういう風に作ってくれるので、そのあたりの話はまったくしませんでした。
――このボスにはこういうバックボーンがあるから、バトルはこういう見せかたにしてほしい……というようなリクエストもしないのですね。
青木
した記憶はないですね。基本的に向こう側で汲み取ってくれるので。アートは各スタッフに共有されているので、ボスの容姿などもお互いに理解していますからね。本当にそんなやりかたでした。いまはもっと密に連携しないとダメだと思いますけど。
――そのやりかたですと、意図が伝わらなかったときに想定外のものができてしまいそうですが……。
青木
これはいまでもあまり変わらないんですけど、当時の作りかたとしては、まずデータを全部バンって入れて、とりあえず遊んでみるんです。そうすると最初は、本当におもしろくないんですよ(笑)。そこから3ヵ月とか半年かけて、寝る間を惜しんで「ああしようこうしよう」と手を加えていっておもしろくなる。やっぱり、ゲームは手で触ってどう感じるかがすべてなんですよね。だからまずは(ゲームを)触れるようにして、そこから揉んでいく。違うなと思うところは直していく。そういう作りかたをしていました。
――当時、イベント班には何名のメンバーが所属していたのですか?
青木
メンバーは8人くらいですかね。基本的にはマップ単位で担当が分かれていて、アレクサンドリアはこのスタッフ、トレノならこのスタッフ、といった感じでした。キャラクターが自分や仲間のことをどう呼ぶかという一覧表を作って共有して、あとはそれぞれのマップの担当が話を作っていましたね。それで週に1回くらい、イベント班全員に僕の部屋に集まってもらって、誰がどんなイベントを作ったかを共有して、全員で流れを把握しながら作っていました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a8714b5787db51f3f779eb44099c116ae.jpg?x=767)
――『FFIX』は原点回帰がテーマになっていましたが、青木さんは原点回帰というテーマをどのように受け止めていたのでしょうか。
青木
やっぱり、クリスタルですかね。『FF』には、いくつかクリスタルが登場していない作品もあるんですけど、僕の中では『FF』と言えばクリスタルありきだなと思いました。だから登場させたのですが、ただ、ユーザーさんからは「クリスタルって最後にちょこっと出てくるだけじゃん」と言われてしまって……これは、ちょっと失敗してしまった部分ですね。僕の頭の中では、最初にクリスタルがあって、テラのクリスタルが古くなってきたところから物語が始まっているんですよ。だから、僕としてはクリスタルは最初から登場しているものなんですけど、ゲーム上ではそうではないんですよね。発売してから、「もっと序盤で匂わせておけばよかったな」と思いました。
――『FFIX』では初代『FF』の四天王が登場するなど、過去作品をオマージュしている要素も多くありますよね。こちらについては、青木さんがとくに「『FF』らしい」と思ったものを入れたということでしょうか。
青木
最初に自分がプロットを手掛けた段階で、「過去作のこの要素を使おう」というのは大まかに決めていました。そのうえで、データとして実際に入れられるかどうかを検討して、「ここはいける」、「ここはやめよう」と判断していましたね。あんまり強くこだわることはせずに、使えなかったらそれでいいか、くらいのつもりではいました。
日本にいてもハワイにいても忙しさは変わらない!?
――青木さんは、『FFIX』の前に『チョコボの不思議なダンジョン2』(1998年発売)のディレクターを務めていますが、どういった流れで『FFIX』の開発に参加されたのでしょうか。
青木
当時、『チョコボの不思議なダンジョン』1作目の開発が終わったらそのまま『FFIX』のチームに加わる予定で、ハワイに行くという話も事前に坂口さんとしていたんですよ。でも『チョコボの不思議なダンジョン』が思ったより売れたのか、急きょ続編を作ることになったんです。
――それは、すでにハワイへと移られた後ですか?
青木
そうですね。だから、まずはハワイで『チョコボの不思議なダンジョン2』を作って、そこから『FFIX』に合流したんです。合流時、ストーリーのプロットは存在してはいたんですが、調整すべきところがあって、少し手を加えました。
――そもそも、ハワイに開発スタジオを作ると聞いたとき、どう思われましたか?
青木
スクウェアでは、年に一度の社員旅行でいろいろなところに行っていたんですけど、20代のころに坂口さんといっしょにハワイに行って、「ここに会社ができたらいいよね」みたいなことを言っていたんですよ。それから10年くらい経って、本当に会社ができたので、それはもう「行きますよ」と。そんな感じです。
――本当に実現したのがすごいですね。坂口さんの中では、かなり昔から構想があったのかもしれないですね。
青木
あったんじゃないかなと思いますね。坂口さん、ハワイ大好きでしたから(笑)。僕もハワイで時間を過ごすのがすごく好きだったので、「ハワイに会社ができるんだ!」と喜んで行きました。
――ハワイにはどのくらい滞在されたのですか?
青木
3年くらいですかね。ハワイでは、おじいさんが外でゆったり座って煙草を吸っていたりしていて、僕らの中で流れている時間と、ここに住んでいる人の時間は、速さが違うんだなというのを目の当たりにしました。向こうに行ってすぐのころは、出社は午後からだったので、午前中は何人かで早朝ゴルフに出て、ハーフを回ってから会社に行こう、みたいなのんびりした生活をしていました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/af4140ecc56fd92cb1c9ecd7d4f776711.jpg?x=767)
――ハワイならではのゆったり感がありますね。
青木
でも開発中盤以降は、僕がデータをまとめてメインプログラマーに渡すという作業があったんですけど、渡すのが午前3時くらいで、そのデータをプログラマーがディスクに焼き終わるのが朝7時くらいでした。だから僕は3時に帰って寝て、7時になったらまた出社してディスクのチェックをして、今度は日本にいるデバッガー用にデータをアップして、みたいなことをしていました。けっきょく、日本にいてもハワイにいてもやることは同じじゃん、という結論になりました(笑)。
――それほどのデータをサーバにアップして日本に届けるのは、当時はかなりたいへんだったのでは?
青木
当時はまだ、電話回線を使っていたと思います。テレビ会議をするときも電話回線を3本使ってやっていましたね。こっち側でアロハタワーのほうに夕日が見えているころ、日本はちょうどお昼くらいの時差でした。こっちで朝7時にデータを送ると、日本時間の12時くらいにQAさんのもとに焼いたディスクが行き渡るというような、ギリギリの時間で動いていた気がします。
――『FFIX』が開発されていたのは25年以上前ですから、当時としてはかなり時代を先取りした動きかたですよね。複数の国で開発するというのは。
青木
そうですね。そういえば、ハワイ時代の後半に、PS2のテスト機材のようなものを送るから、『FFIX』がPS2でも動くかどうかチェックしてくれという話があったんです。でも当時、PS2のCPUが高性能すぎて軍事転用できてしまう可能性があるということで、輸出が制限されてしまう出来事があって。なかなか現場に届かなかったんですよね。あれはたいへんでした。
マスターアップ直前まで内容を調整するこだわり
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ae9a40fbb60adcb410a03341658dbbd85.jpg?x=767)
――5年前に『ファイナルファンタジー』ポータルサイトに掲載されたインタビューで、青木さんが植松さんにおすすめ楽曲を聞いたところ、植松さんが『独りじゃない』を聞かせてくれて、それでストーリーを思い付いた……というお話をされていました。あの曲はゲーム終盤で流れますが、曲が出来てからイベントを作っていたのですか?
青木
ストーリーに合わせて作ってもらう曲もあるんですけど、それ以外に植松さんがフリーで作ってくれる曲もあるんですよ。植松さんのところに行ったときに「何かオススメの曲はないか?」と聞かせてもらったのが、『独りじゃない』だったんです。ちょうどプロットであの曲に似合うシーンがあったから、担当者にも曲を聞いてもらって、曲の雰囲気に合わせてイベントを作ってもらいました。
――じゃあ、植松さんがあの曲を作らなければ、ファンからの人気も高いあのイベントシーンも、ああいった内容にはなっていなかったかもしれない。
青木
ちょっと毛色が違っていたかもしれないですね。本当にイメージにぴったりだったので、曲をもとにしてイベントの内容を広げてもらいました。そこに合わせてバトル班も演出を作ってくれて、いいシーンになったなと思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ae6e0ebf237450c421f92a33873dea83b.jpg?x=767)
――同じく、5年前のインタビューにて、マスターアップ直前でゲネロ、ゼネロ、ベネロの3人が生まれたというエピソードを拝見しました。マスターアップのタイミングでキャラクターが増えるなんて、いまでは考えにくいですが……。
青木
いまだとボイス収録やローカライズがありますからね。でも当時は、日本版が終わってから海外版に着手するという流れだったんですよ。だからけっこう好きにやっていましたね。開発後半に、まだ手を加えたいなっていう部分が100個くらいあったとして、時間や容量の都合もある中で「40~50%くらい入ればいいかな」くらいの感覚を持っていました。それはまわりの人間も同じで、みんなが必死にいろんなものを拡張して、いいものに仕上げていきたいという連鎖反応があって。そうやって各スタッフが要素を入れ込んでいくので、マスターアップしてから「こんなにキャラクター増えたんだな」と思ったりする感じですね。
――ほかにも、後から追加されたイベントがあるのでしょうか。
青木
プロットにはなかったけど後から入れたものは、いくつかありました。たとえば、ブランクの兄貴が石化した後に迎えにいく場面も、最初はなかったんですよ。でも、あれは「作っておかないとね」ということで追加したんです。最後に、ガーランドが独白のようにしゃべる場面もそうですね。『FFIX』は本当の悪人がいないつもりで作っていたので、最後にガーランドの心境も出したいなと思って。本当にギリギリのタイミングだったんですけど、担当者に「ごめん」って言いながらメッセージを渡しました。セリフをいいタイミングで止めたり、少し間を空けてガーッと流したりする演出はその担当者が勝手にうまく入れ込んでくれて。これでガーランドの心情も伝わるようになったかな、と。
――ゲーム終盤のそういった演出まで、マスターアップ直前で追加しているというのはすごいですね。
青木
足りない部分や伝わりにくい部分は、最後の最後までなるべく手直しするようにしていました。いまだと、メッセージを1文字変えるだけでもたいへんですからね。“ジタンに”を“ジタンにも”に変えるだけでも、ボイスの撮り直しとかローカライズの修正とかでタスク量が一気に増えてしまいますから。そういう手間を考慮せずに変えていけたのは、当時の強みだったなと思います。いまの時代でも同じような作りかたができないわけではないんですけど、ひとつの修正で生まれる影響がものすごく大きくなっているので、コストもそのぶんかかってしまうんですよね。
――時代が進んでゲーム開発がしやすくなった部分がある一方で、融通が利かなくなった部分もあるのだなと感じます。『FFIX』はジタンやクジャ、ビビなどの生き様を通して生命というテーマを描かれていると思いますが、彼らの生きかたや結末は、最初のころから固まっていたのでしょうか。
青木
大枠は決まっていましたけど、エンディングにあるビビの独白部分なんかは、ギリギリまで修正していました。7、8回書き直してもらったと記憶しているんですけど、もしかするともっと多かったかもしれません。一度、ダメ出しが多すぎたせいか、ビビじゃなくてクジャの独白に変わっていたりして(笑)。「いや、ビビでやってよ」と。そんな感じで担当者が何度もがんばってくれたおかげで、最終的にはいい形にすることができました。
――主題歌『Melodies Of Life』の歌詞は、本作のストーリーとも密接にかかわる内容になっています。この歌詞はディレクターの伊藤裕之さんが書かれていますが(※シオミ名義で作詞)、伊藤さんとストーリーやエンディングについて話し合うことはあったのですか?
青木
そこについては話し合ったことはないですね。作詞に関しては、(伊藤氏が)自分でプレイして、見て感じたものを歌詞として落とし込んでいったんじゃないかなと思います。伊藤くんと、“ここほれ!チョコボ”とかのミニゲームに関して話をしたのは覚えているんですけど、ストーリーに関して話した記憶はないですね。
――お話をうかがっていると、当時のスタッフの皆さんは、綿密な情報共有をしていく現在のスタイルとは違って、本当に以心伝心で動いていたのですね。
青木
やっぱり、“触って感じるものがすべて”という感覚だったんだと思います。もちろん、最初は頭の中で考えて作っていくんですけど、最終的には触り心地がどうか、ですからね。
――ちなみに、やりこみ要素のひとつであるエクスカリバー2は、ゲーム開始から12時間以内にラストダンジョンで土のカオス・リッチを倒す必要がありました。かなりシビアな時間設定でしたが、あのあたりはどのように決めていたのでしょうか。
青木
そこに関しては、僕はあまり関わっていないんですよ。たぶん伊藤くんと担当者が話し合って決めたんじゃないかと思います。僕は「こんなの入ったんだ」くらいの感覚でしたね。たぶん伊藤くんがひとりで「制限時間はもうちょっと短くしよう、いや長くしよう」とか決めたんじゃないでしょうか(笑)。
ビビとクワンの前日譚を描く『FF』絵本第2弾が発売
――ここからは、25周年を記念して発売されたオリジナル絵本『ファイナルファンタジーIXえほん ビビとおじいちゃんと旅立ちの日に』についてお話をうかがいたいと思います。『FFIX』のキャラクターデザイナーである板鼻利幸さんと青木さんが絵本を制作するのは、2021年に発売された『ファイナルファンタジーえほん チョコボと空飛ぶ船』に続き2作目となりますが、そもそも、前回の絵本の企画はどのように始まったのでしょうか。
青木
最初は、「何か『FF』の本を作りたいよね」みたいな話から始まったんです。板鼻くんから「話を書いてほしい」と言われて、僕も板鼻くんもチョコボに関わっていたので、チョコボの話にしようと。じゃあ舞台はどうしようかな、と考えたときに、初代『FF』のワールドマップを見まして。あの世界って、砂漠に飛空艇が埋まっていたり、魔法と縁が深い村があったりして、ゲーム本編よりも前の時代を感じさせる要素があるじゃないですか。だから、それをお話にしてみようかなと思ったんです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ab8c7ad0038d9cc06a44e0a87516ddf01.jpg?x=767)
――ゲームの開発と絵本作りでは、どのような部分が違いましたか?
青木
ゲームの場合は、ストーリーの導線はわかりやすいか、謎解きの難易度は適切か、演出は、バトルは……みたいな部分を、手で触りながら確かめられるじゃないですか。「HPはこれくらいでいいし、ダメージもいい感じだ」と。でも絵本を作るときって、この部分は大丈夫、みたいな手応えがわからないんですよね。ゲームみたいに要素を分解してチェックできない。だから五里霧中というか、わからないまま作っていました。
――第1弾のときは板鼻さんとどんなやり取りをされていたんですか?
青木
「こんな感じのお話を作りたい」、「ここにはこういう演出を入れたい」という大まかなラフを投げましたね。そこに対して向こうから返ってきたものを見て、「ここはこうしよう」と何度か往復しながら作っていました。文章をどこまで直せば正解なのかもわからなくて、本当に手探りでした。
――第1弾の絵本では、『FF』の戦闘画面を思わせるような、キャラクターの横顔が並んでいる演出もありましたが、あれは青木さんの発案ですか?
青木
そうですね。あんな感じでアングルを横にしてほしいとか、そんな話をしながら作ってもらっていました。
――初代『FF』にあったジョブが登場したり、『FFIII』のジンが出てきたりと、シリーズ作品の要素が登場していたのも印象的でしたが、これも青木さんのご提案だったのでしょうか。
青木
そうですね。ボスに関しては『FFIII』から出すぞと決めていたわけではなくて、ボスとして出すには歴代の敵キャラクターのうち誰がいいか、と考えたうえでピックアップした感じでした。ザコモンスターについては、初代『FF』でそのフィールドに出てくるモンスターからピックアップしています
――そんな第1弾の発売から約4年が経ち、今回第2弾として『FFIX』の絵本が発売されました。
青木
『FFIX』の25周年に合わせて絵本を出そう、というお話になったのですが、最初はどうしようかなと思ったんですよ。ゲームって、作っているときは自分たちのものなんですよ。だから開発中に「こういう風にしよう」と思ったらそういう風に作っていくんですが、一度世に出たらもう自分たちのものではなくなるという認識なんです。『FFIX』は、皆さんがプレイして、自分の中にそれぞれの『FFIX』を持っているわけじゃないですか。ひとりひとりが自分の正解を持っているなかで、その既成事実を変えるのはタブーだと思ったんですよね。だからどういう内容にするかは悩みました。でも、『FFIX』の絵本だったらやっぱりビビがメインだろうな、というのは最初から考えていました。
――では、ビビを登場させることは決めつつも、どんな話にするか悩んだと。
青木
最初は、ゲーム本編の時間の中で、ビビが落ち込んだときにどうやって立ち直っていくか……という話を考えていたんです。でも編集の方や板鼻くんから、「『FFIX』を知らない人もいるし、子どもが読むものだし、暗いお話じゃないほうがいいんじゃないですか」と言われたんですよね。それで、人と関わるのがすごく苦手なビビとクワンがふたりで暮らしていた短い時間にスポットを当てよう、と考えました。その中で、「人生は楽しいよ」ということを伝えられれば、小さいお子さんから『FFIX』を遊んだことがある方まで、幅広く楽しんでいただけるんじゃないか、ということでいまのお話になっていったんです。
――開発当時、クワンとビビについての設定は深く考えてあったんですか?
青木
ぜんぜん(笑)。クワンのバックボーンとしては、人を導くことに失敗してひとりで暮らしていて、自分が掲げる理想もうまく叶えられない、そういう状況にいたというのはゲーム中でも描かれていましたので、そこでビビと出会って……というところを膨らませていきました。
――絵本の中には、クワンがビビに名前を与えるシーンがあります。
青木
ゲームでもビビが名前を聞かれるシーンがあるんですけど、その問いに答えることで仲間との信頼感みたいなものが生まれていったと思うんですよね。そういう風に、名を聞かれて答える名前があるということは、クワンがビビの将来を考えて名前を与えたということじゃないかと思うんです。「自分を高めてくれるような相手に出会ってほしい、そのときには名乗る名前があったほうがいいし、名前が生きた証になっていつまでも残る」って。そういうところでクワンの師匠っぽい感じが出したい、ビビに名前を贈って旅に出させることがクワンの一番の使命だ、と思って書かせていただきました。
――ビビという名前の由来も、この絵本の中で明かされました。
青木
そこも最初は悩んだ部分でした。“VIVI”だから、黒魔道士6型の6号にするか、でも黒魔道士の初期バージョンだしなあ……とか考えながら。ゲームの中で、身長が伸びなくて悩んでいるビビの描写があったので、6フィート6インチという数字だったら、師匠が「これくらい大きくなってくれ」と願ってもおかしくない身長の値だなと思ったんです。ちなみに、VIVIを逆さまにしたらIVIVで、4フィート4インチだと130センチくらいで、ちょうどいまのビビと同じくらいなんですよね。だから「いまはIVIVだけど将来的にはVIVIに」という由来にしておけばしっくりくるかな、と。
――ビビの名前の由来について、坂口さんにも相談されたんですか?
青木
こういう由来にしましたよ、という話はちゃんとしました。後で「知らなかったよ」と言われるのもマズいので(笑)。「おもしろいね!」と返ってきました(笑)。
――まさか25年越しに前日譚が出るとは思っていなかったので、今回ビビの絵本が発売されてうれしいです。『FFIX』は、発売後に時間が経ってからファンの熱気が高まっていったという印象があるのですが、青木さんは当時、ファンの声をどう受け取っていましたか?
青木
基本的にどの作品もそうなんですけど、開発が終わるとすぐに「つぎは何を作ろう」というほうに集中しちゃうので、作り終えた作品のことはなかなか意識しないんですよね。昔、『クロノ・トリガー』を作ったときも、発売日の夜中に社長から電話がかかってきて、「ここで詰まってるんだけど、どうしたらいいの?」って聞かれたんですけど、もうつぎの作品に取り掛かっていたから忘れちゃってて。調べてから折り返したりしました。
――確かに、ユーザーがゲームを遊ぶころには、もうつぎの企画に向けて動いているわけですからね。
青木
見返すと、失敗したこととか、「こうすればよかったな」という負の沈殿物が貯まっていってしまうので……。でも『FFIX』はインタビューなどで見直す機会を多くいただいていて、そこで改めて「こんなに愛してもらっているんだな」と再認識しています。
――今回の絵本は、ユーザーにとっても『FFIX』への思い入れを再確認するものになると思います。絵本を最後まで読むと、もう一度ゲームを最初からプレイしたくなると思います。
青木
先ほど、一度発売されたゲームで既成事実を変えるのはタブーだと言ったんですけど、じつは今回の絵本で、変更している部分があるんです。”おしばいのチケット”の入手方法ですね。攻略本では“トレノで手に入れた”ということになっているんですけど、やっぱり“おじいちゃんが旅立つビビのために用意してあげる”ほうが筋が通るなと思ったんです。ですので、ここに関しては少し歴史を変えてしまいました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a937cf5f8888a40a5bbec567192ee2351.jpg?x=767)
ものを作る楽しさを一度知ったら止められない
――今回の絵本は青木さんにとっての2作目の絵本となりますが、第3弾への意欲などはありますか?
青木
僕は受け身な立場なので、お話があれば、という感じですかね。でも絵本作りって、ゲーム開発とはまた違っていておもしろいですよね。ゲームの場合は200人、300人で作るのもあって、いろいろなことを手配しないと先に進めないじゃないですか。でも絵本の場合は、短いスパンで少人数で意見を交換しながら作れるので、スピーディーにものづくりができるのは楽しいですね。
――では、絵本に限らず、小説の執筆などにも興味はありますか?
青木
そうですね……本格的にストーリー作りを、というのはハードルが高いなとも感じています。僕はゲームを作るとき、システムとかのほうから考え始めるんですよね。こういう遊びかたはこれまでなかったとか、おもしろそうだっていうところからスタートして、それを遊ぶうえで没頭できるような世界を作るんです。ストーリーについては作りたい人がいれば作ってもらって、いなければ自分が作るか、くらいのスタンスで。それで、ゲームであれば、手で触ればシステムの手応えやゲームの世界に浸れる感覚がわかるし、7~8割の人に気に入ってもらえるかなと思えるんですけど……ストーリーのみとなると、評価は好きと嫌いに半々に分かれるイメージがあるんです。好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌いだろう、って。
――ゲームと違って、“手で触ればわかる”という感覚がないと。
青木
とくに絵本は文字数も少ないし、絵も止め絵ですから、そこから想像を膨らませてもらえるようにしないといけない、というのはなかなかたいへんですね。
――青木さんは長年スクウェア・エニックスでゲームを作ってこられましたが、6月末に退社されたとうかがいました。今後、どういった活動を予定されていますか?
青木
ちょうど今日(※本インタビューは7月1日に実施)、区役所に行って国民健康保険に加入する手続きをしてきました(笑)。ゲームを作るのってけっこうパワーがいるので、年齢もあってフルタイムでやるのはちょっと難しいかなと思いまして、いったん休養させていただこうかなと思っています。でも、ものを作る楽しさは一度知ってしまうとなかなか止められないので、何かあれば創作活動は続けていきたいですね。ひとまず、いまはノープランです。
――今回の絵本がスクウェア・エニックス在籍時としては最後のお仕事になりますよね。板鼻さんとしても感慨深いものがあったのではないでしょうか。
青木
どうでしょうね。そう感じてくれていたら、つぎの仕事もくれるとうれしいです(笑)。
――(笑)。では最後に、『FFIX』をいまなお愛するファンの皆さんへのメッセージをお願いします。
青木
先ほども少しお話ししましたが、今回の絵本のメインキャラクターであるビビとクワンは人と関わるのが苦手ですが、ふたりは「それでも人生は楽しい」ときっと思えたお話になっています。ぜひ皆さんで楽しんでいただければと思います。『FFIX』本編は、命と、その命を使って生きることを描いていたんですよね。ひとりひとりの、「生きているぞ」という積極的な部分が出れば、お話として成立するだろうと考えていました。今回は、その“生きる”という部分に加えて、“人生を楽しむ”とか、“落ち込んだときにどう這い上がるか”といった、落ち込んでも立ち上がれる土台となる部分を二人の生活の中に描ければと思って書きましたので、よろしくお願いします。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ac953f0988ec2a2fb174ad5755f239ac8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a38b1e9c8b1a5defab6bc695fc6300c9d.JPG?x=767)
商品情報
ファイナルファンタジーIXえほん ビビとおじいちゃんと旅立ちの日に
2025年7月2日発売/1320円[税込]
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a32a7606c61713c62eace979de1e89e44.jpg?x=767)
『FFIX』のオリジナル絵本。『FFIX』のメインキャラクター・ビビと、彼の育ての親であるクワンおじいちゃんのふしぎな生活が、穏やかな文章とやさしい絵で綴られる。本作のストーリーは青木氏が手掛け、絵は『FFIX』のキャラクターデザイナーのひとりである板鼻利幸氏が担当。両氏がコンビで絵本を手掛けるのは、2021年に発売された『ファイナルファンタジーえほん チョコボと空飛ぶ船』以来となる。前作に続き本作も、『FF』ファンはもちろん、『FF』を知らない人でも楽しめる一作となっている。
『ファイナルファンタジーIX』20周年&25周年記念インタビュー一覧
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/aaa6a0af77239b3c757a651ee1766fbae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a94318516d0ef8c1133ea33d328d174aa.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a310f70d6357c405fe3645a399679bc9d.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ac43e1367b4671012999ad226fc6712ff.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a8714b5787db51f3f779eb44099c116ae.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/af4140ecc56fd92cb1c9ecd7d4f776711.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ae9a40fbb60adcb410a03341658dbbd85.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ae6e0ebf237450c421f92a33873dea83b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ab8c7ad0038d9cc06a44e0a87516ddf01.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a937cf5f8888a40a5bbec567192ee2351.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/ac953f0988ec2a2fb174ad5755f239ac8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/61817/a32a7606c61713c62eace979de1e89e44.jpg?x=767)