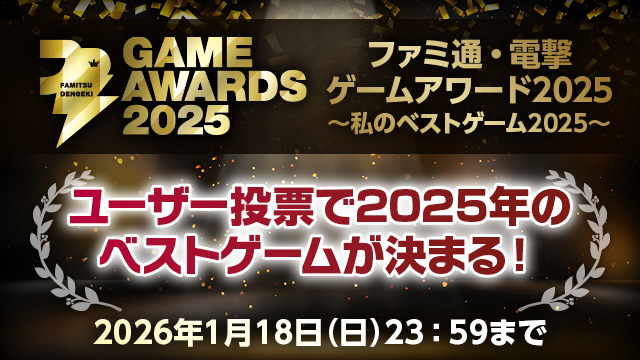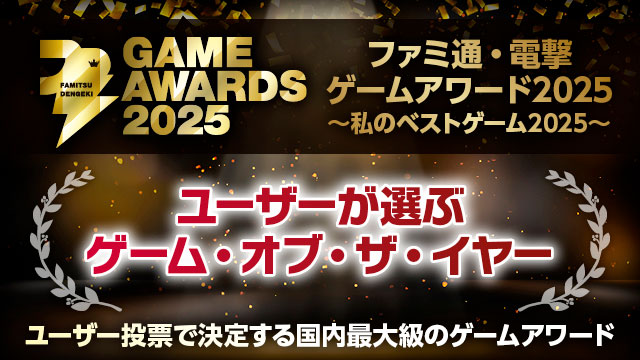2025年11月17日、ユニバーサル ミュージックのパートナーシップビジネス部門VMGと、ゲーム音楽制作会社・ノイジークロークによる共同企画“Game Music & Artists”の始動が発表された。 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 』や『 428~封鎖された渋谷で~ 』などの数々のゲーム楽曲を手掛けてきた坂本英城氏を筆頭に、ゲーム音楽のスペシャリストが揃うゲーム音楽制作会社。
井口昌弥氏(いのくち まさや)
ユニバーサル ミュージック合同会社 BE-U/VMG マネージングディレクター。The Black Eyed Peas(ブラック・アイド・ピーズ)やLady Gaga(レディー・ガガ)など洋楽アーティストのディレクターを歴任。現在は、株式会社BMSGとの共同レーベル“BE-U”と、アーティストや音楽レーベルをグローバルでサポートするサービス“VMG”のマネージングディレクターを務める。(文中は井口)
坂本英城氏(さかもと ひでき)
株式会社ノイジークローク 代表取締役社長。『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』メインテーマ「命の灯火」や『文豪とアルケミスト』、『428~封鎖された渋谷で~』など、数々のタイトルの作曲を歴任。オーケストラコンサートの開催や自社バンド“TEKARU”、“騒然のカワズ”としてのライブ出演、音楽出版社・ココカラ株式会社の運営など、ゲーム音楽関連の活動を精力的に行う。(文中は坂本)
ゲーム音楽×アーティストで音楽きっかけのゲームのヒット創出も ーー今回の新サービス“Game Music & Artists”とは、どのようなものなのでしょうか? 併せて、サービスを作ることになったきっかけをお聞かせください。
井口
端的に言うと、ゲーム音楽とアーティストの距離を近くしたいというサービスになります。もちろんゲーム音楽に関しては、その世界のプロフェッショナルの方がいらっしゃって、ゲームに最適化した音楽を非常に高いレベルで作られています。ただ、アニメなどのほかのコンテンツと比べると、ゲームとアーティストの音楽というのが意外と近いようで遠い感覚がありまして。
坂本
アーティストを使った主題歌が一部の大作ゲームに限られていたり、アニメ業界と比べて音楽業界との距離があまり近くないというのは、ゲーム業界が抱える課題が影響していると思います。たとえば音楽アーティストの方に主題歌のみを依頼するだけでも、まずレーベルにご連絡するのが適切なのか事務所にご連絡するのが適切なのかすぐにはわからないなど、ややハードルが高く感じられてアクションが難しいと思うんです。このあたりの知見を溜める機会がアニメ業界に比べて少なかったのではないかと思っています。と同時にその連絡を受け取った音楽業界側も人的リソース不足だったり、ゲーム業界とのノウハウが足りなかったりして、オファーをスムーズに検討に載せられる体制が整っていないといった課題がおありになるということがユニバーサル ミュージックさんとのお話でわかりました。これらの課題を解消すべく、明確な依頼窓口を作りたいと思ったのが今回のきっかけですね。 ーー数々のゲーム音楽を担当され、主題歌なども手掛けられた坂本さんでも、そういった音楽業界との距離を感じられるんですね。
坂本
これでも最近はだいぶ近づいたほうなんです。音楽業界の方からは「そんなことない」というご意見があるのかもしれませんが、約10~20年以上前はゲームの主題歌などをお願いしても、上から目線とまでは言いませんが、必死にお願いをしてようやく実現するといったような雰囲気があったんですよね。でも、それは当然とも言えるんです。そのころのメジャーアーティストの方々はゲームを遊んでこなかった世代の方が多く、子どもを中心としたエンターテインメントと思われていた。それはアーティストだけでなく、ミュージシャンや作曲家も含めて、そういう風潮がありました。 ーーいちユーザーとして見ると、以前はアニメやゲームの主題歌はアニソンアーティストや声優などの専門ジャンルの方々が多く担当していたころがあり、それがメジャーなアーティストがアニメやゲームの主題歌を担当する時代が来て、でも当時はアニメやゲームの中身と関係ない曲や歌詞になることが一般的で。それがここ10年くらい、とくに昨今はメジャーなアーティストの方々が担当する主題歌も、作品に寄り添った内容になるのが当たり前になってきたように感じます。その流れはゲームにも来ているように感じていますが、それはおふたりも感じるものなのでしょうか?
坂本
それはもう本当にそうですね。
井口
それは僕もとても感じるところです。僕はいま45歳で、僕の子どもの時代だとゲームは男の子がメインで遊んでいたんですよね。しかし、年代が進むに連れてだんだんと年齢も性別も関係なくなり、ゲームに親しんでいる世代が増えていって。またそれは日本だけでなく、海外もそうなんです。我々ユニバーサル ミュージックは海外アーティストを多く抱えていますが、海外のアーティストがDJをやるときに自分のセットリストの中でアニメやゲームの音楽を特別なものではなく、よくあるものとして入れ込むようになってきています。アニメやゲームの音楽がニッチなものでなく、自然な形でメインストリームになっているのが、いま起きている現象だと思います。 ーーなるほど。こういった流れもあって、ユニバーサル ミュージックとしては、このタイミングでゲーム音楽に力を入れていこうという流れになったんでしょうか?
井口
はい。もちろんビジネス視点がまったくない、ということを言うつもりはありません。ただ、それ以上にとてもおもしろい時代になってきている実感があって。それこそ、先日はアトラスさんの『 ペルソナ3 リロード 』の曲 『It’s Going Down Now』 が、ビルボードの“Global Japan Songs Excl. Japan”(日本を除く全世界の日本楽曲)で1位を取るほどバズっていたりと、そういったゲーム音楽の事例がいくつも出てきているんです。 ーーアトラスサウンドチームは、Spotifyの“海外でもっとも再生された国内アーティスト”ランキングで、YOASOBI、Adoに続いて3位に入っていましたね。 画像はアトラス公式サイトより引用。
井口
こういったことが日本以外のあちこちで起こっている。僕らからすると、「これはゲーム音楽だ」とか「これはアーティストの楽曲だ」とか、そういった区別はしていないので、世界の多くの方に聞かれている音楽だと、とても実感するんですね。
坂本
井口さんのお話を聞いていて、いま本当に泣きそうになりました。ありがとうございます。
井口
いやいやいや、でも実際にグラミー賞(編注:世界的な音楽のアワード)にゲーム音楽部門ができたりと、もっと誇るべき作品であり文化になっているので、どうにかしたいんですよね。 ーーとても熱いお話ですね……! 坂本さんはゲーム音楽の制作だけに留まらず、コンサートを開いたり、ゲーム音楽の権利関係について管理する会社を作ったりと、精力的に活動されてきましたが、ゲーム音楽の地位向上も考えていらっしゃったわけですよね?
坂本
そうですね。ゲーム業界において音楽は過小評価されてきた歴史があると思っていて、その要因のひとつは、ゲーム音楽はその多くがメーカー所属の会社員で作っていたことから、音楽アーティストと比較すると「誰がこの音楽を作っているのか」というゲーム業界内外からの関心が薄かったから、だと思っています。でもその後ゲームファンのあいだでゲーム音楽の人気が高まっていって、いろいろと成功事例が出たりと地位向上の機会はあったんですが、音楽業界との距離という点ではなかなか縮まらず。 一方、アニメのほうは、たとえば『君の名は。』でRADWIMPSの野田洋次郎さんが劇伴(編注:ドラマやアニメなどの作品中で流れる楽曲、BGMのこと。劇中伴奏音楽の略)を含めて担当されたり、最近では『チェーンソーマン』や『【推しの子】』の主題歌が世界的なヒットになったり、『ONE PIECE FILM RED』では数々の有名アーティストの楽曲をAdoさんが歌って映画自体が大きなヒットになったりと、さまざまな成功例が出ているわけです。
VIDEO
VIDEO
坂本
ゲーム業界にいる身として「こういった成功例をゲームで実現できないんだろうか」とずっと考えていて。音楽業界と深く寄り添う道を模索していたんですが、弊社の力だけではなかなかそれを実現できなかったので、今回のユニバーサル ミュージックさんとのタッグはとてもありがたく、私がずっとやりたかったことのひとつが実現しそうだということで、期待でワクワクしています。
アニメと違って、ゲームが音楽業界と距離がある理由 ーーアニメで実現していたものがゲームでできていなかった要因としては、たとえばアニメとゲームで主題歌の発注のタイミングや制作体制の違いが大きいのでしょうか?
井口
ビジネス構造的に見ると、アニメも最初から私たちのようなレコード会社と近かったわけではないと思います。間違いなく映像業界と音楽業界の権利の考えかたは違っていて、私たちにとっては楽曲がもっとも大事なコンテンツですが、映像業界からすればアニメや映像の一部という位置付けだったと思うんです。それが、先駆者の方々の努力で突破口を開かれたことで、いまはアニメにアーティストの主題歌が入ることが自然な流れになっている。
坂本
補足すると、そのほかにもいろいろな理由があります。まずゲーム側の発想として、主題歌をアーティストに依頼しようという考え自体があまりないように感じるんです。ゲームメーカーのスタッフやサウンドチームが作るのが当たり前だったので、音楽業界に声をかけるという発想自体がなかったり、冒頭にお話したように具体的にどう行動すればいいのかわからなかったりする。
ゲーム音楽家の人気をもっと上げるきっかけにも ーーこのサービスを利用することで生まれる効果やメリットを教えてください。
井口
いままでも散発的にアーティストが主題歌を担当したり、ゲーム内にアーティストがアバター的に登場することはあったものの、トータルでゲームのストーリーや世界観に関わるというものは稀だったと思います。それを企画段階からお話いただくことで、アーティストがもっと深くテーマに関係した主題歌や挿入歌を作ったりできるようになります。
坂本
そうですね。ゲームの中にアーティストが登場することも、これまでよりスムーズに実現できるようになると思います。ほかにもたくさんの可能性を感じていて、たとえばゲーム内容に沿った音楽イベントを作り、リスナーとオーディエンスの行動によって楽曲やライブ構成が変わって、それが将来的にゲーム側にフィードバックされるようなことだって可能でしょうし、『 フォートナイト 』のようにゲーム内にアーティストが登場して限定ライブをやったりすることも考えられます。 ーーユーザーのゲーム体験という点ではどのような変化が期待できますか?
坂本
自分が好きなアーティストが劇中曲をも担当することで、ふだんの歌ものとは違うアーティストの魅力を再発見できたり、アーティストの個性を活かした楽曲がゲーム作品全体の統一感を増幅し、より深いゲーム体感ができたりすることが考えられます。主題歌のアレンジ曲がゲーム内でだけで聴けるとしたら、それも聴いてみたいというファン心理もはたらくかもしれません。
井口
ユーザーさんからしても、ゲームを作っている音楽家の方にもっと興味を持つきっかけになるかもしれません。たとえば『 ドラゴンクエスト 』には明確にすぎやまこういちさんという作曲家の存在があって、それはゲームをあまり遊ばない人にも名前が知れ渡っていますよね。 坂本
最近はゲームの規模が大きくなって、ひとりの作曲家だけで1本のゲームの音楽をすべて担当することができなくなってきていて、10人以上で作ることもあります。そうすると、その中の代表の方の名前だけが大きく出ることになったりして、遊ぶ側からはいま聞いているこの曲が誰の作ったものなのかわかりにくくなっていくんですよね。そこに著名アーティストの名前があったり、このサービスによってゲーム音楽作曲家という職業が高くブランディングされるようになれば、より注目されやすくなると思いますし、アーティストのライブなどでその音楽が使われることで、またゲームを思い出してもらえるという相乗効果も期待できます。
井口
ゲーム業界にいる作曲家の方でアーティストに楽曲提供されたことがある方はいますが、それほど多くないですよね。音楽制作の現場で「今回は誰といっしょにやろう」となったときに、現在の音楽業界ではよほどでない限りゲーム音楽作曲家の名前は挙がってこないんです。でも本来は一般的な有名作曲家の方と同じようなレベルでゲーム音楽作曲家の名前が挙がってもいいはずなんですよね。
大手もインディーも。まずは成功事例を作る ーーこのサービスのターゲットはどういった会社やクリエイターを想定されていますか?
井口
正直、規模などで制限するつもりはありません。そもそも「こういう窓口がある」ということをお伝えしたいので、サウンドチームをお持ちで音楽制作に力を入れている大手の会社から、いま盛り上がっているインディーゲームまで、ありとあらゆるところにお話に行きたいと思っています。
坂本
前述の 『ONE PIECE FILM RED』 のAdoさんを始め、いろいろなアニメの成功例を見て、ゲーム業界の方々も指をくわえて見ているわけではないと思います。『 ファイナルファンタジーXVI 』(FF16)で米津玄師さんが楽曲を担当したような動きもありますが、これがアニメのように当たり前になっていないのは、さきほど挙げたような理由があるからではないかと思っているんです。 VIDEO
VIDEO
需要自体はあると思いますが、動き出しかたがわからない。そういう意味では、コラボレーションの効果や魅力を感じているゲームメーカーがまず最初のターゲットだと考えています。それでいくつか前例を作ってから、そのほかのメーカーさんにも「音楽にはこんなに大きな力があるんですよ」とアピールしていくのがわかりやすく伝わる切り口になると思います。
井口
音楽業界側から見ても同じことを思っています。以前はアニメのタイアップというと、ドラマや映画、CMよりも優先度が低かったんです。それがいまは「アニメのタイアップがとにかく欲しい」というアーティストがとても増えてきた。これはもちろんアーティストがアニメ・ゲームに自然に触れてきた世代になったというのもありますが、グローバルな成功例が出てきたからでもあります。アーティストにとっても、ビジネス的にもブランディング的にもいい効果が出る事例が増えているんです。 ーーなるほど。もしこのサービスでアーティストといっしょにゲーム音楽を作る、といったことになったときは、ノイジークロークがサポートされるのでしょうか?
坂本
はい。弊社はゲーム専門のサウンド制作会社として長年のノウハウがあります。まずアーティストの楽曲をゲーム用にアレンジするということになれば、ゲームのプレイを邪魔しないアレンジのしかたがあるのでそれをお手伝いしますし、ゲームそのものへの実装作業などを弊社側で引き受けるということもあると思います。 ーーああ、なるほど。
坂本
そういった理解が深まった、いま始まるべくして始まるサービスだと思います。
他社との連携、そしてフェス。広がっていく可能性 ーー現在、すでに動いているプロジェクトはありますか?
井口
まったくもってこれからです。むしろ旗印を立てることが重要かなと思っているので、ノイジークロークさんと私たちがいっしょにやらせていただくということを打ち出したうえで、各社にお話に行く、もしくはご相談をいただくほうがいいと考え、今回の発表になりました。 ーー今後このサービスが広がった場合、ほかのレコード会社との連携や、ユニバーサル ミュージック以外のアーティストが参加する可能性はありますか?
井口
個人的には十分あると思います。ユニバーサル ミュージックとしては、弊社がごいっしょしているすばらしいアーティストが世界中にたくさんいますので、まずはそこにお声がけいただくだけでもできることはたくさんあると思います。アニメと音楽業界を先駆者の方々がつないだように、私たちとノイジークロークさんでビジネススキームが作ることにより、むしろ、さまざまなアーティストさんにご参加いただけるほうが広がると思っています。
坂本
そうですね。まずはゲーム業界と音楽業界の考えやスケジュールの理解を深めていけば、もっとチャンスは広がると思います。 ーー今後サービスが軌道に乗った場合、さらなる拡充や夢、野望などはありますか?
井口
もっと先のお話ですが、ゲームミュージックの大型フェスはぜひやりたいですね。これは国内だけでなく、世界でも待っているユーザーさんがたくさんいると思うんです。私の知る限り、最近でゲーム音楽のフェス形式のライブはありませんし、現役のゲーム音楽の作曲家の方々にもご参加いただくことで、皆さんをよりアーティストとして認知される、人気を上げるお手伝いもできたらいいと思います。 ーー以前はフェス形式のものや、メーカー横断のオーケストラなどもありましたが、最近は確かに減ってきていますよね。
坂本
弊社も横断のオーケストラをやっていたんですが、やはりゲーム業界は音楽の権利がとてもクローズで許可取りも難しいので、だんだんタイトル単独のものが主流になってきてしまっているように思います。でも、ユニバーサル ミュージックさんといっしょに動くことで、主題歌を担当されたアーティストさんがそのまま出ていただくこともできるようになって、また時代が変わるかもしれません。 ーーそれはいちゲーム音楽好きとしても期待しています!
井口
あとは、かつてアルファレコードという会社が、“G.M.O. RECORDS”というゲーム音楽専門レーベルをやっていまして、ゲームメーカー横断でサウンドトラックや、ゲーム音楽のCDなどを出していたんですが、こういう取り組みをいまの時代に合わせた形でできたらおもしろいかもしれません。
坂本
懐かしいですね。サイトロンレーベルなどもありました。当時は各メーカーが自社で音楽配信をする仕組みがなく、アルファレコードさんにお任せすることで実現していったものだと思います。そのあと紆余曲折あり、各社が自社でやるようになったんだと思いますが、音楽業界との協力という意味では、いまの時代だからこそ各メーカーに響くものがあるかもしれません。ゲーム音楽専門レーベルとフェスを絡めるのもおもしろそうですね。 ーー夢が広がりますね。では最後に、この記事を読むゲーム業界関係者やゲームファンへメッセージをお願いします。
井口
ゲーム音楽の世界と音楽業界をより近くしていきたいと本当に思っています。それぞれの業界の仕組みやありかたには重なる部分も新しい部分もありますが、音楽業界側からすると、ゲームは全世界に展開されているコンテンツ産業です。そこから学ばせていただきながら、一方で弊社が持つグローバルなアーティストやネットワークを通じてお手伝いできることもあるのではないかと思います。
坂本
熱量が非常に高いアーティストの皆さんと協力して、音楽の力でゲームの体験がいかに刺激的でおもしろくなるかということを世界に示していきたいと思います。シンプルですが、それが私たちの思いです。 ーーちなみに、このサービスを知ったアーティストの方々のほうからアプローチするといったこともアリなんでしょうか?
井口
それはもちろん。本当にゲーム好きなアーティストは多いので、アーティストのほうで興味がある方も気軽に手を挙げてほしいですね。 ーー大きなうねりになることを期待しています。本日はありがとうございました。
Game Music & Artistsサービス概要 サービス内容:ゲーム音楽に関するクリエイター/アーティストのキャスティングを含む企画・制作・実装からマーケティングサポート サービス開始時期:2025年11月10日より開始 ![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/54458/a5888e56fe08e466709cec034daf9f441.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/54458/51f97765083e196d67fd59e05b3b869b1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/54458/a2371170f9db048bb622abfc912328f3e.png?x=767)








![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)