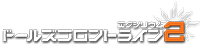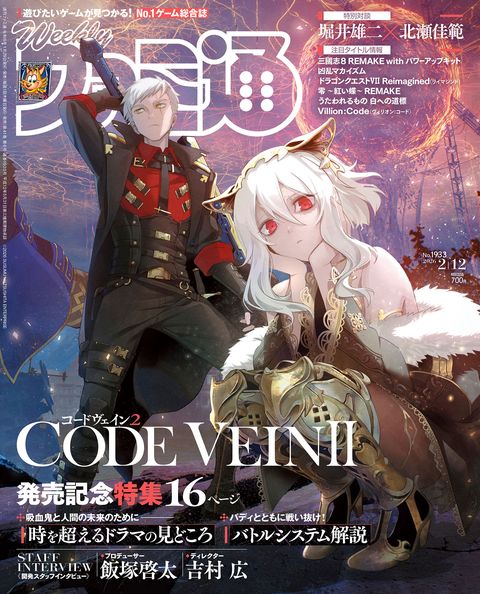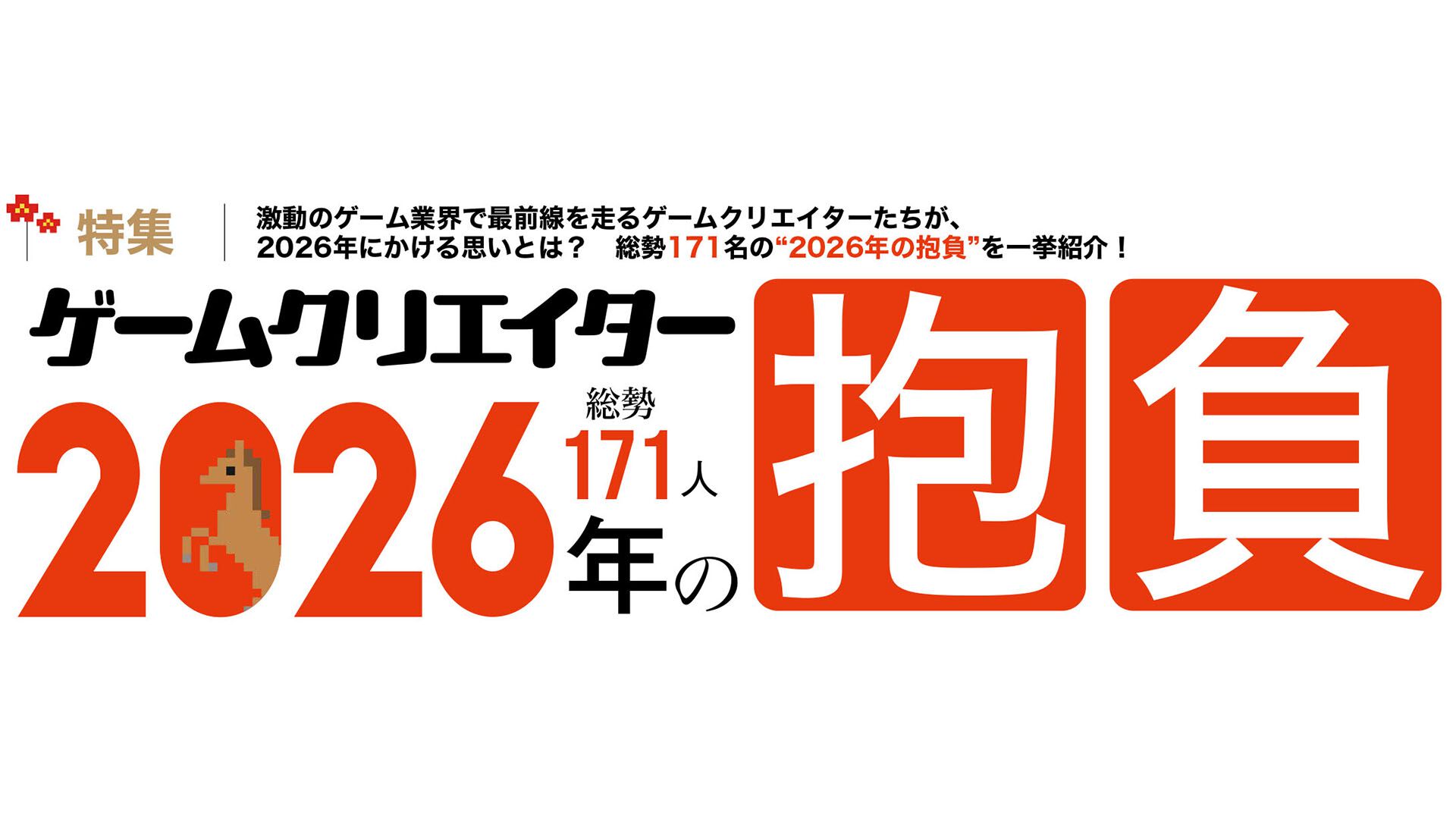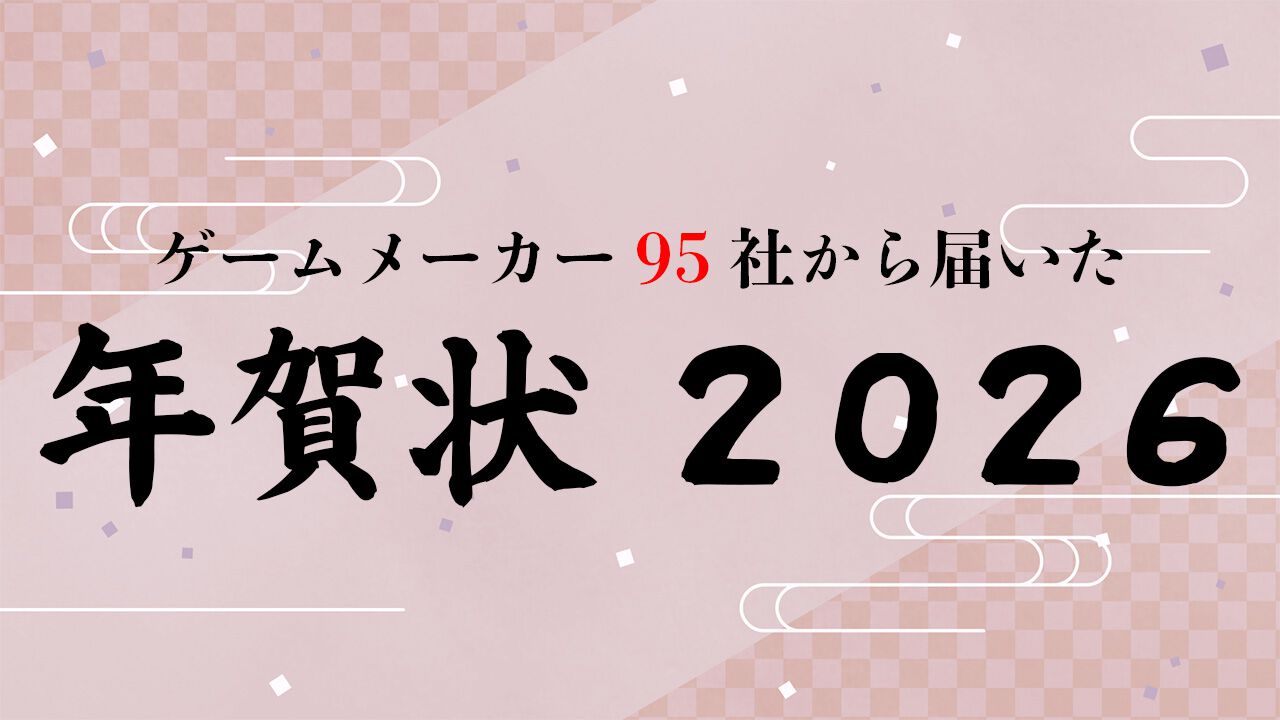孤児の姉と弟が、闇の秘密が隠された故郷の島を舞台に、行方不明の友だちを助けだして逃げ出していくホラーアドベンチャー『REANIMAL(リアニマル)』。
『リトルナイトメア』と『リトルナイトメア2』を手掛けた開発会社による最新作ということもあり注目度も高い同作だが、東京ゲームショウ2025に合わせて開発元のTarsier Studios(ターシアスタジオ)のクリエイターのおふたりが昨年に続き今年も来日。ファミ通.comのインタビューに応えてくれた。
2026年第1四半期に発売予定となる『REANIMAL(リアニマル)』だが、現時点での進捗や手応えなどを聞いた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ab92dcfd4a261724a5ae97e81742fc526.jpg?x=767)
デイビッド・メルヴィック氏(写真右)
Tarsier Studios ナラティブ・ディレクター
アンドレアス・ジョンソン氏(写真左)
Tarsier Studios アソシエイト・プロデューサー
ひとりはもちろん、ふたりで遊ぶとより楽しめる
――『REANIMAL』が2026年第一四半期に発売されますが、現在の進捗状況を教えてください。
デイビッド
とても忙しくしています。私たちはゲームをもっとよくしたいと思う気持ちが強いので、まだまだリリースしたくないという気持ちがつねにあります。完成に非常に近いところまで来ていますが、最後の調整が重要なので、そこに注力しています。
――開発状況はどれくらいなのですか?
アンドレアス
現在80%はバグの修正、20%は仕上げに時間を費やしているのですが、これは最後の段階にあることを意味しています。ゲームはすでに完成していると言えます。
――仕上げとはどのようなことを?
アンドレアス
アニメーション、敵との遭遇、カメラを調整してプレイヤーにどこへ行って何をすべきかをよりよく理解してもらうためのシーンにおける明確さなどの最終的な調整です。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac003f159ee19ec90988c08ac5130d1a6.jpg?x=767)
――現状の出来具合への手応えはいかがでしょうか?
アンドレアス
8月に行われたgamescomで、隣どうしに座っていただいたプレスの方々に協力プレイで本作を遊んでいただきました。社外の人たちに触っていただくのは初めてで、ひとりではなくふたりでプレイしていただくというのは、私たちの賭けでした。ふたりがいっしょにプレイして、その反応をリアルタイムで見ることができ、大きな手応えを感じました。
デイビッド
お互いを知らないプレスの方たちは、最初は恥ずかしそうにしていましたが、ともに恐ろしい体験をしながら声を出して励まし合い、成功を喜び合っていたのが印象的でした。彼らに何かクールなものを提供しているんだなあということを実感しました。
――プレスの方々は感情を大いに喚起されたのですね。何が要因だったのでしょうか。
アンドレアス
昨年もお話ししたかと思いますが、『REANIMAL』では、ホラー映画をふたりでいっしょに観るときに起きるような、ふたりで恐ろしい体験を共有してほしいと思って作っています。
デイビッド
ひとりでは孤独感がありますが、ふたりなら叫んだり共感したりできますからね。
アンドレアス
ふたりでいると何かが起きるのです。緊張感、雰囲気、恐怖感が高まる中、ふたりでプレイするところにマジックが生まれるのだと思います。
――恐怖感を与えることだけではなく、そのような共感は隠しテーマとしてあるのですか?
デイビッド
両方重要なテーマだと思います。プレイヤーがキャラクターに共感を抱いてくれることに対しても大切だと考えています。プレイヤーが共感したときにキャラクターたちとのつながりが生まれ、恐怖がより強いインパクトを与えるのです。共感はとても重要です。
キャラクターたちとのつながりがなく、彼らが生き延びようとしている世界への関心がなければ、恐怖はただのノイズとムーブメントに過ぎず、何の意味もありません。このふたつがともにあることは非常に重要なのです。
また、このふたつのバランスを取ることも重要です。プレイヤーがストレスを感じ始めるように少し休憩を与えます。プレイヤーはストーリーの何かが見つからないかと世界を見回しているうちに間もなく何か酷いことが起きるのではないか……という感覚に陥ります。そこで感情が解放されて、全員が叫ぶのです。
アンドレアス
シングルプレイヤーでプレイしていてもプレイヤーはキャラクターとのつながりを持てるようにしなくてはいけません。その点はデイビッドと同じ意見です。
協力プレイでの体験は、少なくとも最初はひとつの付加価値として考えていました。プレイヤーがふたりでいっしょに笑ってしまって怖さが少しなくなったら、それはいいのか悪いのかどちらでしょう? gamescomで見たのは、彼らはひとりがジャンプに失敗して死んだり、何かをミスしたりすると笑っていましたが、それは体験に付随してのものでした。その後にやり直して怖さを味わったのです。ゲーム体験に追加されるひとつの価値のレイヤーなのだと思います。
デイビッド
私の好きな効果的なホラーの緊張感の盛り上げかたの例は、最初の怖さを感じるところまでつねに長い時間がかかっています。『エイリアン』、『シャイニング』、またはデイビッド・リンチの『ツイン・ピークス』はそのよい例です。
観客はキャラクターたちを知り、彼らに関心を寄せることで彼らに何かが起きるのではないかと心配します。一方『プロメテウス』は間違った方向に行ってしまいました。観客は誰にも関心を寄せず、誰のこともよく知らなかったので心配もしませんでした。成功例を分析してみることは大事です。
皆さんには好きなやりかたでプレイしてほしいですが、私たちはふたりで座っていっしょにプレイすることをお勧めします。ひとりでプレイしたい場合はもちろんAIコンパニオンが動いて人間のプレイヤーが探索して進んでいけるようにサポートします。シングルでもふたりでも楽しめますし、オンラインでもシェアカメラは同じなので、同じように体験できます。
――本作で緊張感を高めるためにどのような工夫を凝らしているのですか?
デイビッド
自分たちでとにかく何度もプレイしてみることです。そのうちにこれは何かの骨組みかもしれないと思うことが見つかります。そこからほかの人たちにプレイしてもらって反応を観察し、あちこち調整し、時間を長くしたり短くしたりして反復し続けます。時には何かを取り除いたり別の場所に移したりします。そのゲームのプレイ体験が明確になったら、そこにはもう触れずに進めます。言ってみれば、シェフが味見をしながら作るようなものですね。
アンドレアス
背景で起きていること、そしてオーディオやサウンドエフェクトの組み合わせです。画面で表現しているものが、どんな建物でどんな環境の中にいるのかによって、より緊張感を感じます。環境がどのように変わるか、オーディオの雰囲気が変わるかも影響します。また、デイビッドが言ったように時間も重要です。どれだけ長くプレイヤーをあるエリアや部屋にいられるようにするのか。長過ぎるとつまらなくなり、短過ぎても緊張感の高まりが不足します。これらすべての組み合わせで作っていきます。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac779d742847be8fe17b5a633bf66b85f.jpg?x=767)
――ストーリーは、どのような位置付けになるのですか?
デイビッド
ストーリーがすべてのコアになります。声を使った長いカットシーンがあると安心感が生まれます。通常、シネマティックではみんながしゃべり、どのように感じたらよいのかを示唆します。
私たちのアプローチはそうではなく、これらのキャラクターがお互いをよく知っていて、なぜこのように反応するのかについて興味をそそるため、非常に短いミニマリスト・スタイルのシネマティックを使います。彼らに何が起きてつぎには何が起きるのかを事細かく説明することはしません。つまり、すべてを知るという安心感を与えないということです。
情報は小さな塊として少しずつ出します。このバランスを取るのが非常に難しいですね。情報が少な過ぎるとプレイヤーはわからないことだらけで迷ってしまいますが、多過ぎてもうまくいきません。コアストーリーは非常にシンプルです。この子どもたちに何が起きたのか、そしてなぜここにいるのかを感じ取ってもらうことです。
――キャラクターは姉と弟ということですが、なぜこの組み合わせにしたのですか?
デイビッド
私たちのストーリーの中では、姉という存在が重要でした。私には姉も妹もいまして、昔よく姉に面倒を見てもらった記憶がありますが、これはこのふたりのキャラクターについて語る際にとてもよい関係性だと思いました。
――いろいろな組み合わせを試した結果……というよりは、デイビッドさんの個人的な経験が影響したようですね。
デイビッド
そうですね。それはつねに優先します。自分自身がストーリーの要素につながることができれば、より簡単に書くことができますし……。私には兄もいて、彼も姉と同様私に正しい方向に進むべくうながす役割を担っていました。しかし本作のキャラクターで姉と弟というダイナミックを考えたとき、姉がいることがとても特別なものに思えたのです。
――『REANIMAL』の“The Boy”は、ある意味でデイビッドさんが色濃く投影されている?
デイビッド
いえいえ(笑)。そうでないことを祈ります。プレイヤーの皆さんが一度プレイすれば私がモデルになっているとは思わないでしょう(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a03c1b6993dd6cfb1ecc2a9a135e7d95b.jpg?x=767)
物事の核心部分をつかむようなゲームを
――Tarsier Studiosが『リトルナイトメア』シリーズを手掛けたスタジオということで、比較されることも多いかと思いますが、『リトルナイトメア』をあえて踏襲した部分と、逆に新しくした点を教えてください。
デイビッド
つねにストーリーのコアとの感情的なつながりが中心にあると思います。どんなに恐ろしいことが起きても人々はストーリーのコアの肝心な部分につながりを感じます。すべてを取り去っても何か原始的なものが残り、共鳴できるのです。私にとっては、これがつねにもっとも重要な部分で、そこから構築していくことができます。
ただ、同じことをくり返したくはありませんし、つねに進化する方法を考えています。とはいえ、同じIPの中では難しい。『リトルナイトメア2』は『リトルナイトメア』に非常に近いものである必要がありました。そこから離れて本作の新しい世界を作ったので、『リトルナイトメア』で達成したことを再現したいとは思いませんでした。
『リトルナイトメア』はそれ自体非常に取り扱いが難しいからです。本作で私たちは違った感じの何か新しいものを作り出す機会を得ました。よりエッジの効いたもの、もう少し年上の子どもたち、よりダークなストーリーはどうか。ストーリーのコアと作りたい世界が決まれば、そこからは自然に構築されていきます。つねにこれまでの経験を生かし、特定の方法で物事を説明しますし、ある特定のゲームプレイを生み出したいと思います。しかし、それ以外は、コアの周囲に構築していくのであまり考えませんし、過去に何をしたかは考えずにこのゲームには何が必要かを考えます。
アンドレアス
もちろんこれまで作ってきたタイトルで得た経験は使いますし、前にやったことがあるのでいろいろな方法は知っています。しかし、当社には、長年培われてきた根本的な思想があり、それは物事の核心部分をつかむという考えかただと思います。そのゲーム、あるいは作品のために信じている何かです。
そしてミニマリズムは、量より質という考えかたに通じます。最終的にゲームの質が残るようにどんどんいろいろなものをカットしていき、あとはプレイヤーに解釈、想像してもらうのです。人間の想像力は非常にパワフルなので、すべては語らずにプレイヤーに任せる。このゲームで費やす1分、1時間が質の高いものであってほしいと思います。本作は100時間のゲームではなく、6~8時間のゲームですが、その時間は長く記憶に残ると思います。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac779d742847be8fe17b5a633bf66b85f.jpg?x=767)
デイビッド
理由はわからないのですが、私たちはつねにキャラクターの顔を隠します。
アンドレアス
ひとつにはプレイヤーが顔のないキャラクターとのつながりを感じられるからだと思います。また顔を隠すことで緊張感が高まります。
デイビッド
数年前に『Statik』というVRゲームを作ったときはキャラクターの顔はピクセル化されていましたが、それはストーリーの一部でした。つねに顔を隠す方法を考えていて、今回はバケツをかぶっています。人間のようなものにはつながりを感じないのに対して、顔を隠しているものにはなぜ顔を隠しているのか好奇心をそそられ、何が起きているのか知りたいと思うというのは不思議です。
※【関連記事】両手をふさいだ謎の機械を操作する実験に巻き込まれる、ちょっとPortal感ある脱出系VRゲーム『Statik』【Day of the Devs】
アンドレアス
『リトルナイトメア』から『REANIMAL』に何を持ち込んだかという点ですが、それは先ほどの根本的な思想だと思います。私たちを本作へと導いたのは特定のメカニックや要素ではなく、根本的な考えかたなのです。
新しいゲームをスタートする際は、つねにいくつかの柱を立てます。本作では、“いっしょに怖がること”が中心となる柱でした。そこからすべてのシステムなどが進化していきます。カメラシステムはシングルプレイヤーでもオンラインでもローカルでもつねに同じで変わることはありません。しかし、メカニックやプレイヤーのインタラクションを見ると、それは“いっしょに怖がること”という柱が中心となっています。
デイビッド
つねにそのやりかたで進めてきましたし、柱はすべての決断において私たちを導く光となります。
――本作では、柱はいくつあるのですか?
アンドレアス
“いっしょに怖がること”という中心となる柱と、その下にサブの柱が3つあります。
本作では、最初から中心となる柱を持って新しいゲームを作り、すべてはそこから始まっています。『リトルナイトメア3』でも協力プレイがあるようですが、どのように導入されたかを見ると既存の柱に追加されていて、ゲームの柱ではありません。一方、本作はすべてが柱から始まっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a62863f2c6ad4687f884092cccb6da609.jpg?x=767)
――本作の開発中でとくに苦労したのはどんな点ですか? また、それはどのように乗り越えたのですか?
デイビッド
このプロジェクトではさまざまな困難が押し寄せてきました。まず新型コロナウイルスです。新しい形でコミュニケーションを取らなくてはならず、開発の一部が非常に難しくなりました。ふつうは社内でいっしょにゲームを作るわけですから、それが突然孤立してパソコンを通じてしかつながれなくなりました。
――それはどのくらい続いたのですか?
アンドレアス
私が覚えているのは、『リトルナイトメア2』の最後のころで、バグ修正をするだけだったので家でもできました。しかし新しいものを作るのはたいへんでした。新しいIP、新しい世界を作り出すのは、うまくいくものを見つけなくてはならないので、つねにたいへんです。ゲームに入れていいものとそうでないものの境目を見つけなくてはならず、時間がかかります。がんばって作ったものが排除されることもあります。
デイビッド
それは避けたいことですが、ゲームがよくならなければ意味がありません。
アンドレアス
Embracer Groupが難しい状況になったことからも影響を受けましたが、幸いにもそれほど大きなものではありませんでしたので、作りたいゲームを作り続けることができました。
デイビッド
ゲームの名前を見つけるのも本当にたいへんでした。気に入ったものはすでに使われていて、新しいワードを作らなくてはなりませんでした。『REANIMAL』は存在しないワードですが、それ以外につけようがありませんでした。ゲームタイトルはゲームの魂とつながっていないといけないので、時間がかかりました。好きな名前にたどり着いたのは幸いでしたが、1年かかりました。プロジェクトの最初にコードネームを一時的につけて、それはそのときのスタイルには合致していたのですが、3年経ってもまだその名前しかなく、急いでなんとかしなければならなかったのです。
――そのコードネームはなんだったのですか?
アンドレアス
『Everholm』という名前でした。当時は適当につけたコードネームで、実際のゲームタイトルにならないとはわかっていました。ある場所に閉じ込められるという意味で、“Forever Home(永遠に家にいる)”のジョークですね。
――最初から島という設定だったのですか?
アンドレアス
いまは群島のようなところになっているので、孤島にいるとは感じませんが、当初は孤島のようなところでした。
デイビッド
ちなみに、以前私たちはつねに衛星の名前をコードネームに使っていました。フォボス、ヘルセなどですが、あまりおもしろくないということで、もう少し関連性のある名前にしようということになったのです。まあ、衛星の名前には詳しくなりました(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/af4c6174986ad2877e8f21ed7bbb5c873.jpg?x=767)
――昨年インタビューさせてもらったときに、『REANIMAL』というタイトルの意味をうかがって教えていただけませんでしたが、2026年第1四半期に発売日を控えて、いまならお話いただけますか?
デイビッド
いまも話せません。ただ、「ジャジャーン、こういう意味だったのだ!」というようなものではありません。このゲームのもうひとつの側面として、子どもたちと動物たちの深い結びつきがあります。このゲームの動物たちは破壊されダメージを受けています。子どもたちはそうではありませんが、孤児である彼らに深く根付いているものがパラレルとして一方で可視化され、他方で内面化されるようにしたいと思いました。
子どもたちと動物たちは互いに共鳴し合うものです。それをこの世界で、相対的な状態で見ることに何か正しいと感じられるものがありました。とはいえ、ゲームの最後のシーンを見て、これが『REANIMAL』という名前の理由かと納得するようなものではありません。プレイヤーの皆さんにはそれぞれの結論を導き出してもらうのがフェアだと思います。
――すべてのプレイヤーが同じ結論にたどり着くと思いますか?
デイビッド
経験から言って皆さんそれぞれ違う意見を持たれると思います。私たちが作ったこれまでのタイトルについても、いろいろな解釈が飛び交っていますし。
――最後に、本作を待ち望んでいるファンにメッセージをお願いします。
アンドレアス
まずはトレーラーを見ていただけたらと思います。気になったらプレイしてみてください。気に入ってくださるとうれしいですし、ぜひふたりでプレイしてほしいです。
デイビッド
皆さんに本作をプレイしていただける日が待ち遠しいです。ここまで来るのに長くかかりましたので、私たちが作ってきたものをファンの皆さんに楽しんでいただきたいと思います。2026年初めの発売日まで、もう少しお待ちください。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a631cce70b7575f399feafc985489616f.jpg?x=767)
お茶目なポーズを取ってくださったおふたり。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ab92dcfd4a261724a5ae97e81742fc526.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac003f159ee19ec90988c08ac5130d1a6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac779d742847be8fe17b5a633bf66b85f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a03c1b6993dd6cfb1ecc2a9a135e7d95b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/ac779d742847be8fe17b5a633bf66b85f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a62863f2c6ad4687f884092cccb6da609.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/af4c6174986ad2877e8f21ed7bbb5c873.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55823/a631cce70b7575f399feafc985489616f.jpg?x=767)