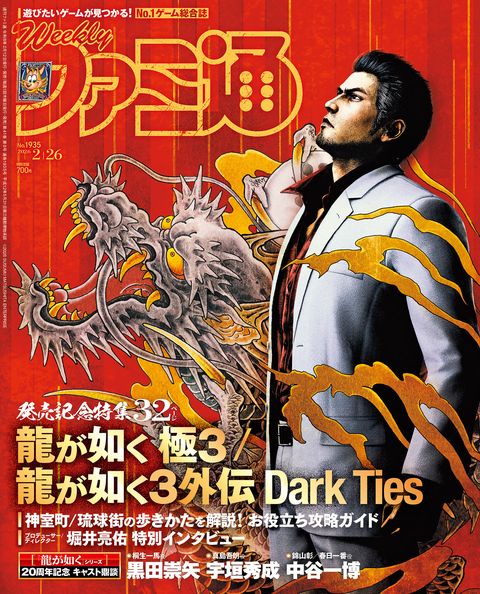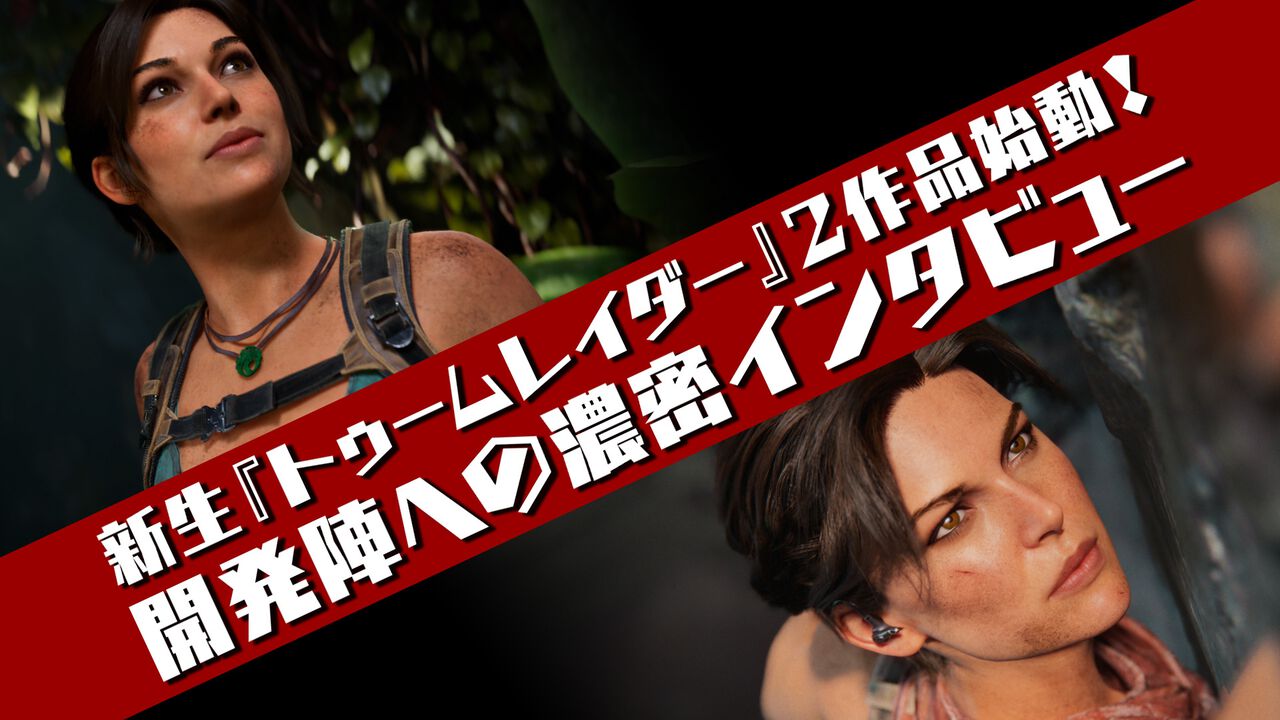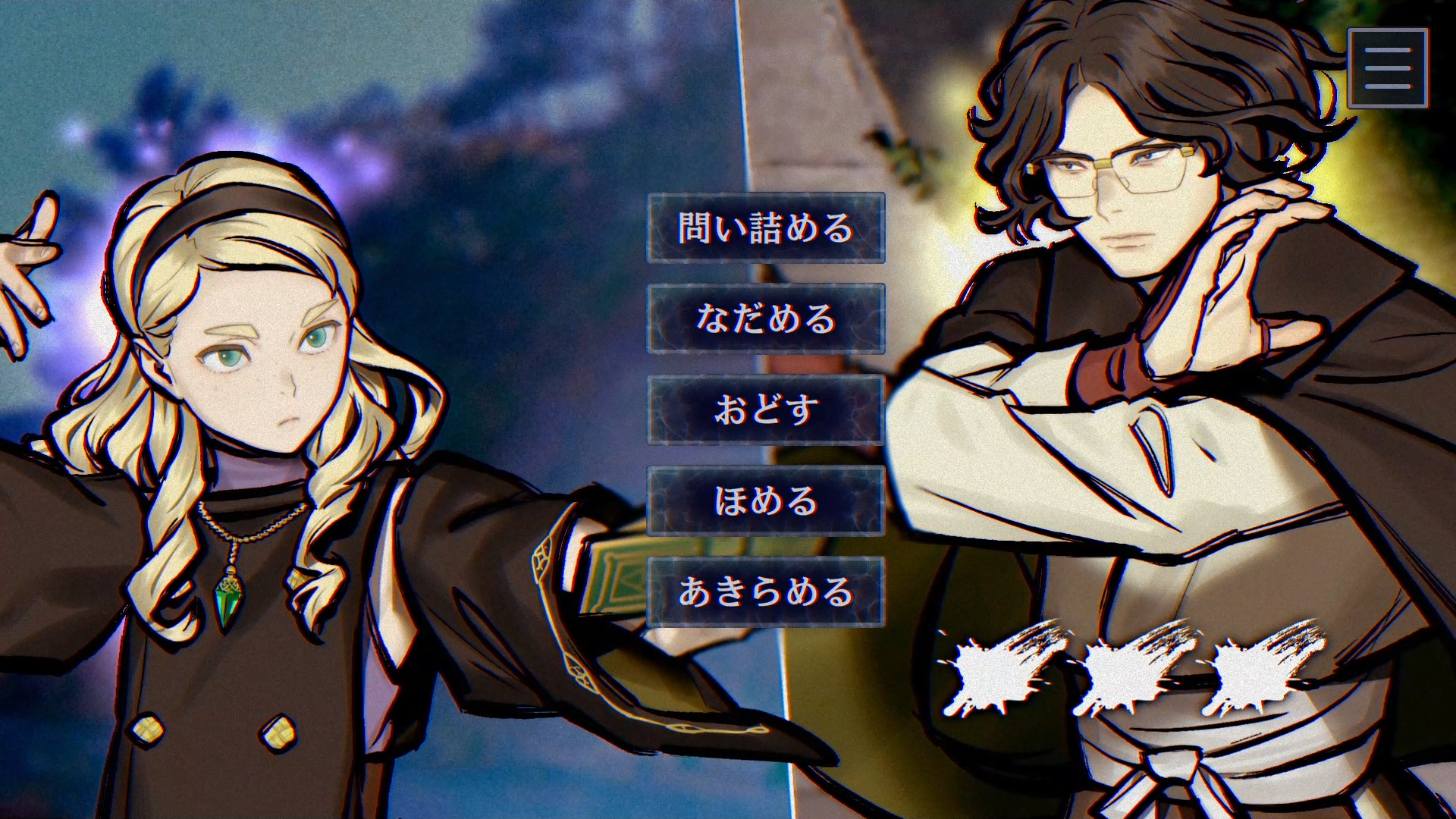氏からそう発言されたとき、ここは必ず太字で使おう……と、筆者は思った。
かわいい小さなロボット“アストロ”を操作して仲間のボットを救出していくアクションゲーム『アストロ』シリーズ。最新作『ASTROBOT(アストロボット)』が2024年9月6日に発売となる。
プレイステーション5にプリインストールされていた『アストロプレイルーム』(ASTRO's Playroom)の正統進化といった内容の最新作で、前作同様のきもちいいジャンプアクションが楽しめる内容となっている。
本稿ではTeam ASOBIのクリエイティブディレクター、ニコラ・デュセ氏へのインタビューをお届けする。
誰でも遊んで楽しい爽快感のあるアクションゲームとはどのように作られるのか? 無機物のロボットをかわいく描く方法とはどこにあるのか? さまざまに直撃した。
また、ファミ通.comでは本作の試遊プレビュー記事も掲載。こちらもぜひチェックしてほしい。
――あっ、そうか、『アストロボット』を制作しているTeam ASOBIは東京のスタジオですものね。
――あっ、あっ、そうか。どうしよう。
――わかりました。通訳さんお願いします……。
3年の開発期間を掛けて、より大きな作品に
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/a4778f0f410f70f93aea629a05a7e3415.jpg?x=767)
――短いデモながらさまざまな遊びが詰め込まれていて満足感のある仕上がりでした。前作からの正統進化で、さらにボリュームも増えていそうで期待が持てます。開発経緯というのは?
『アストロプレイルーム』には3つの柱があり、ひとつ目はデュアルセンスのテクノロジーを存分に感じてもらえるゲームにすること、ふたつ目がプレイステーションの歴史を楽しんでもらえるものにすること、みっつ目がジャンプアクションゲームとしてクオリティーの高いものを世に出すことです。
――本作のコンセプトにもつながっていますね。
この進化はプレイヤーの方々からの反応によるものでもあります。前作はとても革新的で操作性もよく、非常にクオリティーの高いゲームとして認めていただたので、3年を費やして開発を進め、大きなゲームとして発表できました。
――『アストロプレイルーム』はPS5のプリインストールソフトということで、多くの感想が届いたのではないかなと思うのですが、どのような反響がありましたか?
うれしかった反響で言うと、前作『アストロプレイルーム』は25年のプレイステーションの歴史をカバーした世代の架け橋になるゲームでした。
――さまざまなプレイステーション作品のキャラクターの格好をしたボットが登場したり、ゲームのワンシーンを再現したりしていましたね。
親御さんに対して「このキャラクターは何?」と質問したときに、親御さんが「あなたたちくらいの年のときに、このキャラクターの出てくるゲームを遊んだんだよ」と答えるようなやり取りが生まれたり、子どもたちにとって興味を掻き立てられるようなものになっていたようです。
こういった反応はあまり予測しておらず、非常に新鮮でした。本作でもそういった世代の懸け橋になる要素を盛り込めるよう考えて制作しています。
――『パラッパラッパー』のパラッパや『ゴッド・オブ・ウォー』のクレイトスなど、本作にもたくさんのキャラクターがカメオ出演するようですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/ab88df0caaffd5ea022941edc89749170.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/a39df6859a531f1b511d38f5c4d04df67.jpg?x=767)
――前作ではガチャガチャで歴代のハードウェアが出てくる要素がありましたが、今回もそういった要素はありますか?
まだ詳しくはお話できないんですが、マザーシップになっているプレイステーション5がバラバラになってしまい、それを組み立てなおす要素があったりと、前回とは形は違いますが、ハードウェアに関する要素がまったく出てこないわけではありません。
――『アストロボット』は3Dアクションゲームとして非常にクオリティーの高いものになっています。参考にしたり影響を受けたタイトルはありますか? 箱庭でのジャンプアクションや、ボス戦で攻撃方法を模索する楽しさ、新たに、ステージをハイピードで移動する要素など、名作アクションゲームのエッセンスを感じました。
ただ、「インスピレーションを受けるのはいいけれど、コピーペーストはしない」ということをチームに掲げて開発に取り組んでいました。さまざまな影響は受けつつも、それを革新的に再発明するということです。
プレイステーションを通してオリジナルな体験にできるよう考え制作しました。なので、遊んでいて懐かしさを感じたとしても、それが新しい体験としても感じていただけたなら成功だと思います。
また、本作では操作性について“いかにシンプルに楽しくプレイできるか”を再考しています。『アストロボット』はひとつのスティックとふたつのボタンでプレイできるようになっていて、カメラを自ら動かすことも可能なんですが、基本的には自動でプレイヤーをフォローするようになっています。
これまでのゲームの歴史の中で、操作が非常に複雑になった瞬間もあれば、逆にシンプルに戻ってきている最近のトレンドもあります。いまのモダンなゲームの楽しみかたというのはどういうものなのか、“シンプルに楽しむ”とはどいうことなのか――と、考えた結果でもあります。
アストロくんのかわいいの秘密
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/a16565872c04456e57163919256a8b820.jpg?x=767)
――そんなアストロくんのデザインはどのようにして決まったのでしょうか?
時間の制限もあったので、キャラクターのデザインはシンプルにする必要がありました。最初のデザインは小さなロボットに筒状の手が伸びたようなもので、どこか『ボンバーマン』を思い起こさせるような非常にシンプルなシルエットでした。
ただ、そのシンプルなシルエットにハイテクな要素を加えたいという思いがあり、LEDを付けることになりました。プレイステーション・ヒストリーということを考えると、LEDは、プレイステーション2からブルーのLEDが使われていたのでそれを要素として取り入れました。
――ああ! 当時、たしか実用化されて間もない青色発光ダイオードがプレイステーション2の電源ボタンに配置されていて、未来的なデザインのひとつの特徴になっていましたね。
結果として子どもたちが絵に描きやすいといういい要素もたらしてくれました。いくつか微調整はしてきていますが、基本的にそのデザインを踏襲してきています。
もうひとつ付け加えたいのが、おしりです。おしりの形がおむつをしているようなぷくっとした感じで、歩きかたもぎこちない。まさに歩き始めた赤ん坊を思い起こさせるようなスタイルになっていることで親愛の情が湧き、キャラクターとして、思わず触りたくなるようなかわいらしさを兼ね備えるようなものになりました。
――なるほど、おしりがポイントなんですね。
そのあとゲームはジャンプアクションに進化していったので、よちよち歩きという要素はあまり必要がなくなり、キャラクターも自信をもって走ったりするようになりましたが、フォルムとしては頭が大きくてお腹が丸くて、という基本的な形は踏襲されています。
――作品ごとにデザインも調整されて、細かく変わっていますよね?
ただ、全体的なシルエットを大きく変えたくありませんでした。もうひとつは、背中にアタッチメントが付いていたり『アストロ』シリーズのキャラクターは“おもちゃ”のような印象を持たせたいと思っていて、CGで描かれたゲームのキャラクターではありますが、たとえばアタッチメントはリアルに取り外しが想像できるような作りにしています。
そして、もちろんプレイステーションが進化するに従って、グラフィックのクオリティーも上がっているので、表面の質感などディテールは変化しています。
――かわいいデザインというのは、日本人にとっては受け入れやすいものだと思いますが、そのようなデザインを世界に向けて送り出す際に、どのような工夫をされていますか?
ユニバーサルで受け入れられるデザインにするために、チームの中でかわいいとは何なのか、何がおもしろいのかというディスカッションを重ねました。
コンセプトアートの時点では日本のかわいさやユーモアのセンスが盛り込まれています。それをドイツ人のアートディレクターがプロダクトデザインとして起こしていくにあたって、先ほどお話したようにリアルに着脱できるようなアタッチメントのメカニズムといったものが生まれました。
非常にいいコラボレーションになっていたと思います。
クリアーまでは15時間ほど。開発状況は90%超
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/aeff87dd15d72b7fe54cd6428d8572e5d.jpg?x=767)
ゲームのボリュームに関して、まずは全体の構成を説明しますと、ゲームには全部で6つのギャラクシーがあります。
――試遊ではTENTACLE SYSTEM(テンタクルシステム/触手星系)の一部がプレイできましたね。
メインの部分をいったんクリアーするまではおおよそ12~15時間くらいを想定しています。すべての要素をやり込んでいくと、さらに3時間ほどプラスされるのではないかなと思います。
それぞれの惑星には、大体ふたつのレベルとひとつのチャレンジがあり、テーマ的にもゲームプレイの面でもバラエティに富んだものになっています。メカニクスはとにかくバラエティに富んでいるので、ひとつのメカニクスにつき大体2回ほど使って、どんどん新しいものが登場する形になっています。
12~15時間くらいのプレイ時間の中で、フレッシュな体験をたくさんしていけただけます。
――最後に開発状況についてお聞きします。もうマスターアップはされているんでしょうか?
――パーセンテージで言うと?
――個人的にも楽しみにしています。
――なりました! 前作の『アストロプレイルーム』も、本作『アストロボット』も遊んでいて気持ちいいものになっていました。
――こちらこそ、ぜひ!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/a2684b8665b2369bd454120996da688ea.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7939/ac647653f19b2538d0ac1297ac53ce9fb.jpg?x=767)