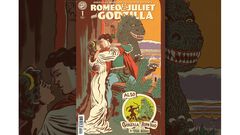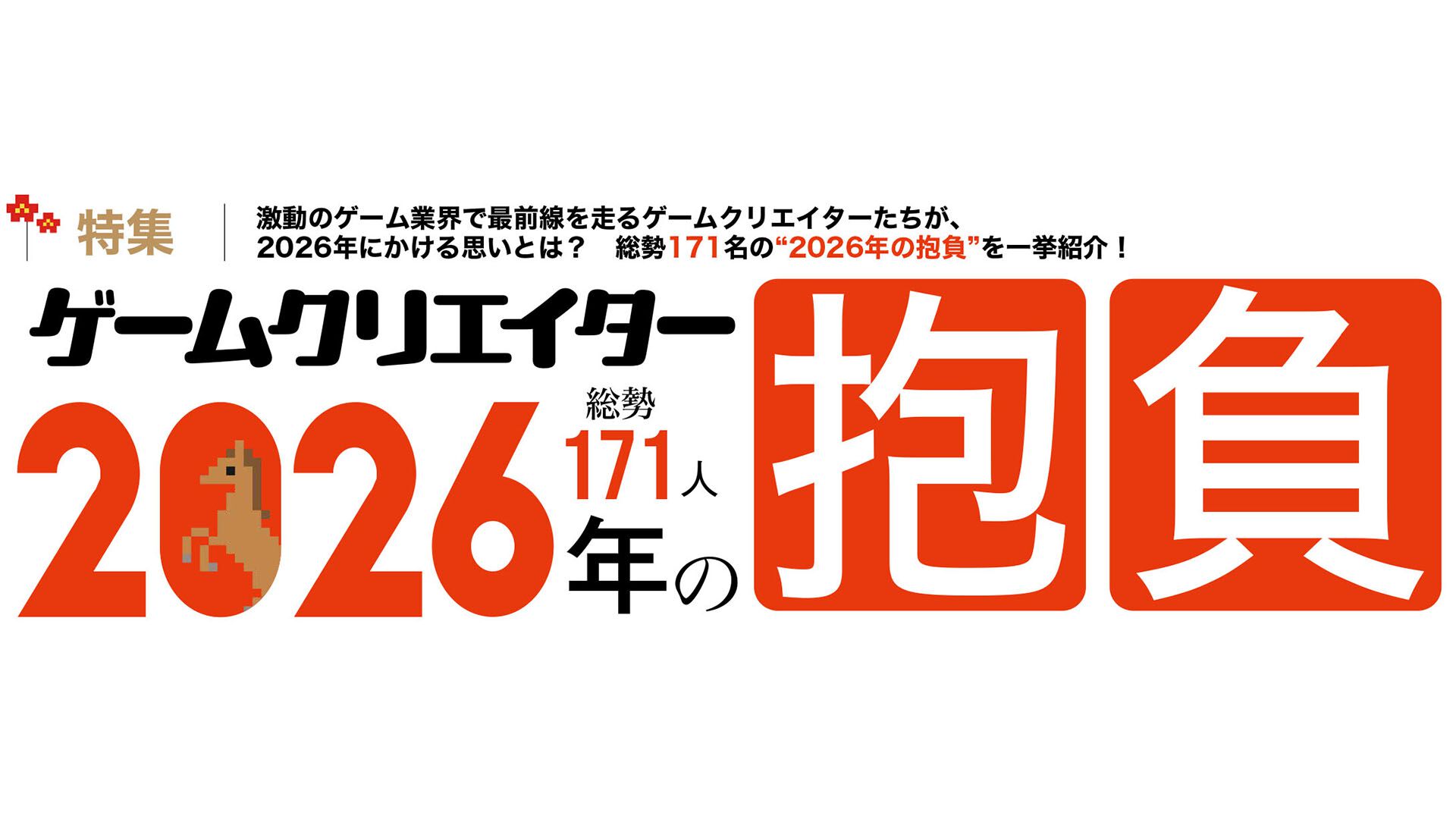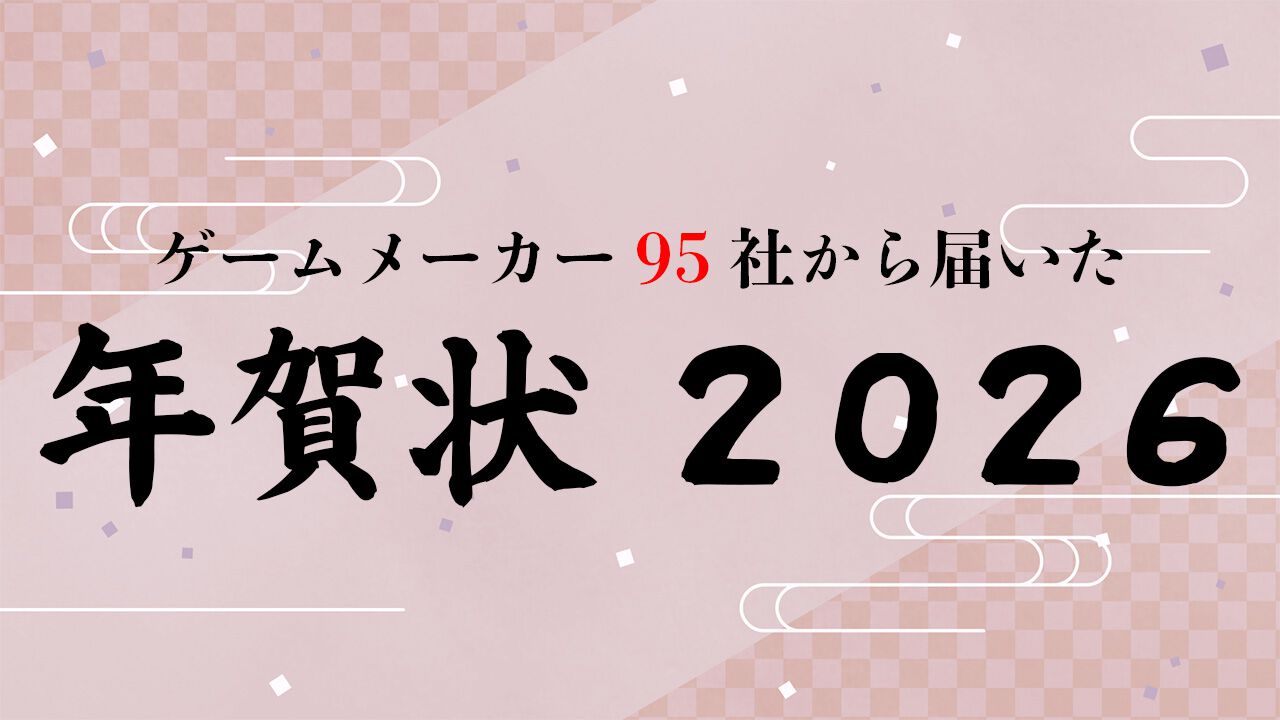本作は、『PixelJunk Eden』や『Eden Obscura』など、独特な作品で知られるマルチメディアアーティストBaiyon氏による最新作。ポイントクラウドという技術をベースに、“撃つ”ことで抽象化している散らばった世界を具体化して創造していくという新感覚の三人称探索型アクションゲームだ。
“破壊なくして創造はない”という刺激的なテーマを掲げた一作でもある。本作はどのような思いで作られたのか、キュー・ゲームスのクリエイティブディレクターであり、本作の企画、アート、サウンド、シナリオなどを務めたBaiyon氏に聞いてみた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/a53ec67081dac04a387d3b44ddda6ee68.jpg?x=767)
Baiyon氏
キュー・ゲームス クリエイティブディレクター。『Dreams of Another』では企画、アート、サウンド、シナリオなどを担当。
人間の不完全や自己矛盾を表現できるのではないかと思った
そこに私が個人的に長年持っていた“破壊と想像”というテーマを重ね合わせたときに、アイデアが降りてきました。具体的には、まず最初は大量の半透明の大きな円によって満たされた、全体がぼんやりと抽象化された夢の世界があり、その大きな円を銃で撃つと破壊され、細かく飛び散ります。そして、それらが小さくなり不透明度を増して同じ場所に戻ってくる。
このプロセスを複数回くり返すことで、物体が徐々に具体化し、形を成して目の前に出現するのです。すると道ができて進めるようになったり、ドアが出現して話ができたりするようになるイメージです。
こうして撃っている(破壊している)けれど、同時に創造している感覚を体験できるかもしれない、というところからプロジェクトは始まりました。ゲーム内ではそれを“抽象化したものを具体化する”と呼んでいます。
――別に破壊に対するアンチテーゼというわけではないのですね。
ゲームが好きな方々は、FPSやTPSなどをプレイしている、もしくは少なくとも知っていると思うので、ゲームの中で銃がどういう役割を持ち、撃ったらどういうことが起こるかということを知っていますよね。撃ったら当然人が死んだりするわけです。それが逆になったらどうなるか?
そういう意味では、ゲームというメディアにおけるひとつの実験ですね。一種の社会実験みたいな。ユーザーさんも巻き込んで、「みんなでいっしょに考えてみませんか?」という。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/a837a34be095cb80571a2c0c86e567f75.jpg?x=767)
その二面性が、“破壊なくして創造はない”というテーマなのだと思います。そして、銃で撃つとモノが作られるという一種の逆転現象が内在することによって、人間の不完全さとか、自己矛盾みたいなものを表現できるのではないかと思っていました。
――撃つことで構築するというのは不思議な感覚ですよね。
とはいえ、ゲームとしてのフレームはしっかり残っているので、別にコンセプトとか複雑な何かを必ずしも理解して進める必要はありません。ゲーム初心者の方でも、プレイできる難易度のゲームになっています。僕の中ではビデオゲームというフレームと構造を残して、ほかをちょっと違うものや、別の角度に入れ替えた(ズラした)感じです。
――“違うもの”ですか? ほかにどのようなものを?
――夢の中だから、主人公はパジャマだし、裸足ですね。
最近のRPGって、群衆にしてもすごい数を出せますよね。街を歩いていたら、しゃべっている声が聞こえてきて、「今日はいい天気だね」とか「この街はなになにで有名らしいよ」といった、いわゆるガヤが聞こえてくる。つまり、NPCはおもに設定や場所の説得力の補強のために使われているんです。もちろん現実にはない場所がどこかには存在していると思ってもらえることはすばらしいとは思うんですが、それだけだと個人的にはちょっとつまらないなあ……という感じなんです。
――(笑)。
たとえば、これを街灯に置き換えてみてください。街灯は固定されていて動けないですよね。その街灯が「俺はここで一生明かりを照らし続ける存在なのだろうか」、「その人生って果たしてどういう意味があるのだろうか」と言った瞬間に、モノからそれが発されることで、それを抽象化して取り込み、自分(人間)の人生にもう1回置き換え直すことで、プレイした人が何かの記憶を思い出したり、どこかの何かに接続する瞬間みたいなのが、もっと作れるだろうなというふうには考えていたんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/a537294b13d09c47cd72537c5c0c89ba7.jpg?x=767)
本当の意味でゲームという定義に初めて本気で挑戦した
『PixelJunk Eden』もそうです。白い紙の上に絵の具を置いた瞬間の興奮とか、楽器で1音目を大きな音で奏でたときの感動とか、メロディーやベースラインにリズムが入った瞬間に立ち現れるグルーブ感みたいなものとか、めちゃくちゃ気持ちよくて楽しいんですよね。“疑似的にでも、何かを作っている気持ちになってもらえる”というのは、ずっとテーマとして持っていて、『Dreams of Another』も風変わりに見えるかもしれませんが、けっこうストレートにやっているつもりではあります。
――これまでのBaiyonさんのゲームと比較すると、若干ゲーム寄りになったとは言える?
そんな僕にとって、ゲームで得たインスピレーションを直接ゲームに返すというのは初めての試みだったんですよ。
――そうなのですね。
とくに構造体のフレームの部分の捉えかたですよね。少し例をお話しすると、たとえば以前に自分自身の遊びかたの実験としてFPSやTPSをプレイしていたときに、僕はクラシック音楽を流して遊んだりしていたんですね。そうすると、撃ち殺した相手に対して「家族いたのかな」とか、ぶっ壊したマンションで、「もしかしたら誰かが家族団らんでご飯を食べていたのかもしれないな」とか、敵という一括りで捉えていたものが、解きほぐされて個々のパーソナリティがすごく気になるようになってきたんです。
僕は音楽を作っていますから、「この効果いいな」って思ったんです。この、完全にコンテキストを変えてしまえる音楽によって、場の意味とか、体験した人がフォーカスする視点さえも少しずらすことができるという効果をそこに発見したんです。
そして、もうひとつ大きかったのが、ピアノソナタみたいな少し悲しい音楽が流れている状況で、ゲーム内で敵を銃で倒して、その映像を見たときに、なぜか逆の“生”をしみじみ感じたんです。
――そうなのですか。
人の一生みたいなものも、少しそういうふうに思うようになってきていて、それはすごく大きな気付きだったなと思います。
少しくだらないたとえなのですが、みんなによく寒い冬にお風呂に入ったときに「なんて言う?」って聞くんですけど、大体みんな「温かい」と言うと答えるんですよね。それはそうですよね。でも僕は違っていて、「ああ、寒かった」と言うんです。別に気をてらっているわけではなく、ただ昔から自然にそう言っていたことに、ふと人に質問したことで気が付いたんです。
――あら。
結果として同じことを言っているんです。文脈で言うと、“寒い”と“温かい”という言葉が同じことを指しているんですよね。そういうのっておもしろいなって思うんです。そういうものを一旦抽象化して、ゲームにどうやって落とし込むかということを、誰かほかに挑戦している人がいるのかわからないですけど、僕は『Dreams of Another』でやりたかったんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/a4835a787632369844f176376291643c0.jpg?x=767)
人生は最悪だけど美しい
――本作はアートがすごく印象的で、BitSummit Awardsで“ビジュアルデザイン最優秀賞”を受賞していますが、アートも最初にアイデアが落ちてきたときからこのテイストで行こうと思っていたのですか?
前例なんか当然まったくありませんので、そこをどうやって表現していくかという試行錯誤があり、最適化などもめちゃくちゃたいへんでした。チームはものすごくがんばってくれてました。ほんとにもう感謝です。
――独特のビジュアルですよね。『Dreams of Another』はポイントクラウドから発想したとのことですが、ポイントクラウドを触っているときに、「これは自分の作品にこういうふうに生かせるな」と思ったのですか?
――そもそも“破壊と創造”は、Baiyonさんの大きなテーマなのですね。
――“昼と夜”とか、“男と女”とか?
――少しわかるような気がします。
少し話がずれるかもしれませんが、以前公開したトレーラーの冒頭に、僕が自分ですごく気に入っているセリフを入れたんですね。
「人間は覚えておきたい事と忘れたいことを選べるわけじゃないから…僕もいつかこの事も完全に忘れちゃうんだろうね。」というセリフです。
これはもう本当に正直な気持ちで、だから人生は最悪だけど美しいっていう感じがしているんですよ。選べない。なんと儚いことかと思うんですよね。それだけでもう、何か滲んでくるものが自分の中にあるんです。
――素敵な人とのひとときは覚えていたいですけど……。
また、そもそも覚えているという感覚自体が幻想だという考えかたもあります。思い出すからこそ思い出になるわけですが、人間の特性上思い出す度にそれらは少しずつ変容していきます。ふと思い出すことの連続を我々は覚えているとか、記憶とか呼んでいるにすぎないのかもしれません。そしてそれをくり返すことで思い出は美化されたりもするし、より嫌な記憶として残ることもあるでしょう。
ちなみに、本作は何かに挑戦して失敗していたり、苦い経験がある人にとくに体験してほしいと思っているんです。それは勧善懲悪のようなプラス、マイナスの話ではなくて、いろいろな体験をした人に対していろいろと想起させるような一種の装置みたいなものを作りたいという思いが、僕にやっぱりあったからです。そういう意味で、奇妙な言いかたですが、いろんな角度から人間の多様性みたいなのものを称えたいという思いがすごく強いですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/aa83a51aa35026cba6a7bb2e3ae3a361a.jpg?x=767)
人間は白か黒かではない、グレーゾーンをつねにさまよっている
僕としてはいちばん気にしていたのは、1回破壊されて創造されるという、相反するものが同時に起きているということの、意識の納得と気持ちよさです。脳に腑に落ちて、体感的にも腑に落ちてくるみたいなものはどうやったらできるのだろうと、チームとはすごい模索しました。
調整はすごく苦労しましたし、何度も試行錯誤をくり返して、現状のものにたどり着くまでが本当にたいへんでした。
――そのニュアンスを言葉にするのは難しそうですね。
僕たちはゲーム会社なので、いろいろな積み重ねがあります。一方で、僕はゲーム業界で仕事をさせていただいて長くなりますが、少しまた視点が違うようで、そんな視点をフルに活用して、スタッフとはさまざまな角度からディスカッションしました。
――主人公の“パジャマの男”には、明確な設定があったりするのですか?
――記憶ですか?
――映画でもそういうのありますね。
――主人公に対して明確なキャラクター付けはしていない?
――そうなんですか。
――ストーリーがあるのですか? 意外ですね。
――そうなのですね。ストーリーがあるということは、それに即したテーマというか、訴えたいメッセージもありそうですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/ab9688f77ac9aa4cc0f04c4a9e8590b12.jpg?x=767)
少なくとも、勧善懲悪のストーリーには興味ないです。人間は白か黒かではない、グレーゾーンをつねにさまよっています。マンガやアニメでも、正しいと信じていていたものがつぎの日にいきなり反転してしまってぜんぜん違う世界が来るみたいな内容のものがけっこうありますよね。
いま、僕たちって立ち止まって考える時間もないくらいにすごいストレスの中で生きているんだなと感じます。すごいスピードで過ぎていく現実を前に、「自分って一体何なのか」って考えることに意味なんかあるのだろうかと思っている人もいるかもしれない。
本質的な質問ほど、抽象的で、即効力がなく価値がないように感じられてしまうような風潮を感じます。だから、その現実世界から少し離れて、自分と対話してもらえるような、柔らかくてぼんやりとした夢の中の“秘密の心の隠れ家”みたいなものを作りたかったんです。
ポイントクラウドという技術に関しても、“破壊なくして創造はない”というテーマがある前提で取り入れ、ストーリーとも響きあうように設計しました。つまり、もちろんビジュアルのよさはありますが、見た目だけが理由で使いたかったわけではありません。
僕がポイントクラウドにものすごく興味を持った理由はいくつかあるのですが……たとえば久しぶりに会った知人がいたとします。ある程度の期間が空けば、体の多くの細胞は入れ替わっているんですよ。つまり、肉体的には別人とも言える。でも、「お久しぶり」とか言ってお互いに認識し合えるんですよね。もちろん、脳の神経細胞の大部分はほとんど入れ替わらないので、認識できるのはそこに記憶が残っているからですが、先ほども触れたように、その記憶は思い出す度に少しずつ変容していきます。だから、それでもなんだか不思議に感じるんです。よく考えると、そもそも自分自身の細胞も入れ替わっているのに“自分”だと思えること自体も、不思議ですよね。
ポイントクラウドって、そういう一種の不思議さと儚さみたいなものを孕んでいると思うんです。それは何かと言うと、オブジェクトの一部を構成していたポイントクラウドがパーンっと弾けたら何物でもなくなりますよね。そして空間をしばらくさまよった後に、ほかの構成物の一部になることで違うものになる。つまり、何物でもなくて何物でもあるという、さっき言った対になる矛盾したものが同時に存在するわけです。なんかそこが自分の中ですごく大きくて。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/a96f35bcd3f51241078e53f11a7c81ec4.jpg?x=767)
それは、生物的とか細胞的な方向性からロジカルに説明することも可能ですが、感情でも受け入れられますよね。「それはそうだよね。明日になれば思うことって変わるよね」みたいな。その曖昧さとかいい加減さみたいなものが、なにか人間らしいなといったことも思います。
ちょっと哲学的な話になってしまいますが……。ジャック・デリダみたいな、差延とか脱構築とかに関わってくる話だと思うのですが、そういうことを考えるのが、やっぱり好きなんですよね……。
あと、今回もうひとつ大きなテーマがありました。“自由とは何か?”ですね。
先行公開したトレーラーでも、“彷徨う軍人”のセリフ「人間というのはなぜ、これほどに自由という感覚に囚われてしまうんだろう」を入れたのですが、人間って、自由であるということにすごくこだわりがあるような気がするんです。正直、自由って何なのか僕にはわからないのですが、僕はたぶんすごく大事にしています。
人それぞれだと思うのですが、人は自由という状態にとらわれる。そして、さきほどの対の話に戻るのですが、僕の自由とあなたの自由っていつかは衝突する。しますよね。自由という本質を研ぎ澄ましていけば、いつかは衝突するのが必然です。個の自由は絶対にぶつかる。それはどういう意味なのかな、その先をちょっと知りたいなと思いながら、ストーリーを書いたりしていました。
★★★★★
その後も、Baiyon氏の興味深いお話は尽きることがなかったのだが、今回はこのあたりで幕とさせていただく。Baiyon氏が頭の中で思い描いていることをしかと共有することは、いち記者として荷に余ることであるが、とにもかくにも最新作の『Dreams of Another』をプレイして、Baiyon氏のビジョンに触れてみてはいかがだろうか。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/57892/aabd9108165beb6d6700cfdb1cac92373.jpg?x=767)
『Dreams of Another』製品情報
- 発売日:2025年10月10日発売
- 対応プラットフォーム:プレイステーション5、プレイステーション VR2、PC
- ジャンル:アクション・アドベンチャー
- 発売元:キュー・ゲームス
- 価格:各3960円[税込]
- 対象年齢:IARC 3歳以上対象
- 備考:ダウンロード専売 『Dreams of Another + PixelJunk Eden 2 スペシャルバンドル』は各4620円[税込]





![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)