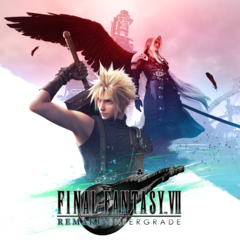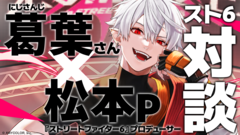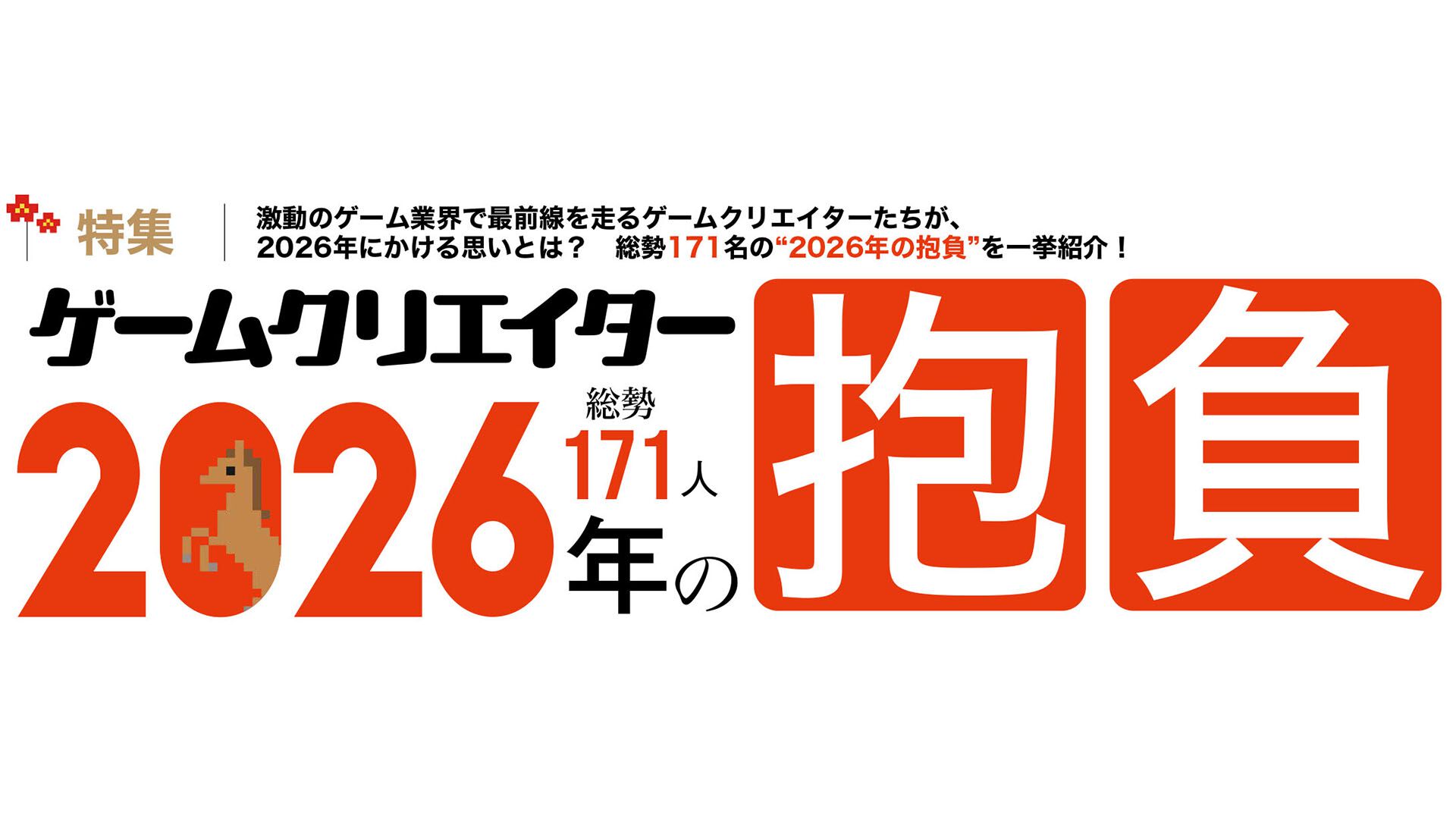◆ “撃てば壊れる”というゲーム的文法に疑問を投げかける
従来のシューティングゲームでは、ゲーム中で銃を構えるキャラクターが登場すれば、プレイヤーは無意識に引き金を引いて何かを破壊するゲームだと認識するはずだ。それに対し、『Dreams of Another』におけるプレイヤーの目的は、銃による“破壊”ではなく“創造”と、従来のシューティングゲームの文法とは対極にある。
銃を携えたプレイヤーは、“夢の世界”を舞台としたゲーム世界をさまよいながら探索することになるが、プレイヤーが銃を撃つと、オブジェクトが壊れるのではなく、散らばった抽象的な点が集合しながら新しいオブジェクトを形成していく。すなわち“創造”である。Q-Gamesでは、本作に対して “破壊なくして創造はない”という哲学的なテーマを掲げ、“新感覚の三人称探索型アクションゲーム”と銘打つ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55788/a8f1a1bae5d3ed5004523ad8ff08d48fc.jpg?x=767)
「“銃を構えるキャラクターの登場=何かを破壊するゲーム”という前提に疑問を投げかけることで、プレイヤーに夢の世界における新発見を体験させたい、というのが根源にありました。破壊ではない銃撃行為に、プレイヤーは“なんなんだ、これは?”、“どんな意味がある?”といった疑問を繰り返す。こうした、プレイヤーから生まれるとりとめのない疑問こそがこのゲームの本質なのです」
筆者の疑問に対して、Baiyon氏は即答した。
言うはたやすいが、それを具現化するのは、そう簡単なものではなかったようだ。手触りはあくまでシューティングアクションでありながら、“撃ったら(何かが)作られる”という体験は、既存のゲーム的文脈に該当する単語すら存在しない。言語化もままならない感覚を、ゲームとしてゼロから構築し直す必要があり、具現化までに多くの時間を要すことになったという。
もともとこうした逆転的な発想の源には、Baiyon氏が物事を常識とは異なる側面から見つめるという独自の感性があった。自身がシューティングゲームをプレイする際、ただ普通にプレイするのではなく、クラシック音楽をBGMに流しながら遊ぶ、というユニークな試みを行っていたことも、“シューティング=破壊”への疑問に至るきっかけになったという。
「悲しいピアノ曲をBGMにFPSを遊ぶと、倒した相手の人生や背景に思いを馳せてしまいます」
と、当時のプレイ体験をBaiyon氏は述懐する。暴力的なシーンでさえも、視点や文脈を変えることで、全く別の感情が立ち上がってくる――そんな“コンテクストのずらし”こそが、新たな感情体験を生み出すという発見につながったのだ。
◆ポイントクラウドとの出会いがビジョンを現実へと顕現させた
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55788/a3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd.jpg?x=767)
ポイントクラウドとは、3D空間内にオブジェクトなどを描画する際、粒子の集合体としてそれらを表現するテクノロジーである。ネット上などにあるポイントクラウド技術のデモ映像では、粒子が収束し、特定の形が生成される様子がよく見られるが、Baiyon氏は、そこに逆再生と再収束というアイデアを持ち込んだ。逆再生のアイデアでは、破壊によって粒子が離散し、ぼんやりとした輪郭を保ちながら細かくなって空間全体へ広がっていく。そして再収束によって、それらの飛び散って細かくなった粒子が再びまとまり、特定のオブジェクトが創造されていく。
この一連の流れを思い描き、その構造を従来のTPS的ゲームプレイへと接続させた。これにより、モノや人が粒子群の浮遊した状態から再構築(創造)され、コミュニケーションが可能となるという状態と、プレイヤーの“撃つ”という行為がアイデアとして一体となったとき、ゲームのコンセプトが明確になったと、Baiyon氏は大きな手応えを感じたという。この段階でようやく“破壊なくして創造はない”という本作の核心的なテーマがゲームというインタラクティブな枠組みの中で、具体的な設計図として可視化されたのである。
ただ、このビジョンをチームと共有する際にも、前例がなかっただけに、試行錯誤の連続だったという。最終的にその意図が形となり、表現としても最適化されたことは、「感謝しかない」とBaiyon氏は開発チームへの想いを口にした。
◆なぜパジャマの男なのか?――語られない物語と、語る“モノ”たち
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55788/af99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7.jpg?x=767)
人間にとどまらず、あらゆる“モノ”と言葉を交わしながら物語を進めていくのも『Dreams of Another』の世界観を特徴づける要素だ。これに関しては、「夢という舞台設定のおかげで、モノと話せる不思議な状況にも違和感なく入っていける。“モノ”から発せられる言葉を通じて、人間社会の疑問が不思議な視点で浮かび上がる瞬間を作りたかった」とBaiyon氏は語る。
これもまたゲームとしての面白さを想定するうえでの、Baiyon氏による逆転的視点が色濃く反映されている。通常のRPGでは、様々なNPCが場所や状況を説明して説得力を補強する役割として何気ない会話を交わしていることが多いが、Baiyon氏の関心はそこにはない。だが、例えば、一生、同じ場所にたたずむだけの存在であるはずの街灯が会話をしたらどうだろう。
「おれは一生、この場所で光をともし続けるだけなのか?」
「その人生って果たしてどういう意味があるのだろうか?」
そう、語りかけたら…? これが“モノ”から発された言葉であるからこそ、プレイヤーはそれを抽象化して自分の人生へと再接続できるのではないか――そう、Baiyon氏は考えていたという。
物語の詳細について取材で明かされることがなかったが、一見、謎に見える世界や設定にもすべて答えは用意されている。
「彼らがこの世界にいるのはどういう意味なのか」
「(このゲームにおける)銃とは何を象徴する存在なのか」
こうした疑問に、プレイヤーがゲームを通して向き合うことで「遊んだ人が体験の中で自分なりの解釈をしてほしい」とBaiyon氏は期待を込める。
◆相反するものが同居するBaiyon氏のクリエイティブ哲学
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/55788/a2de40e0d504f583cda7465979f958a98.jpg?x=767)
氏が感銘を受けている思想のひとつに、生物学者・福岡伸一氏が唱える “動的平衡”がある。これは、生命を固定された構造物としてではなく “常に分解と合成を繰り返しながら自己を維持する流れ”として捉える概念だ。さらにこの考え方は、フランスの哲学者ジャック・デリダが構想する「あるものの意味や存在は、常に他のものとの関係や差異によって成り立っており、固定的・絶対的なものではない」という思想にも通じているとBaiyon氏は述べる。
そうした “相反するものが並列的に実存することの本質”を捉えようとするビジョンが、『Dreams of Another』においては “破壊なくして創造はない”というテーマに結び付いている。それは、間違いなく、Baiyon氏がこれまでの活動の中に蓄積してきライフワークの延長上にある。
そして、本作がライフワークの一環として生まれた背景には、クリエイティブ・ディレクターとして日々ゲームクリエイターと接してきた経験や、Baiyon氏自身が愛してやまない“ゲーム”というミディアム(mesium=手段・方法・媒体・メディア)との真摯な向き合いと不可分にある。氏はかつて、音楽やアートとゲームの融合を試みてきたが、本作に関しては「ゲームが大好きだからこそ、ゲームの文脈を借りて新しい解釈を提示したかった」と取材で答えている。
『Dreams of Another』はあくまでもゲームという形式ではあるが、それに対する深い信頼と愛情、そしてその表現に対するリスペクトが作品の土台にある。同時に、本作はその “ゲーム”という形式のなかで、“生と死”、“善と悪”といった対極にある概念を並列的に提示し、プレイヤーの内面を強く揺さぶってくる。
例えば “創造するためには何かを犠牲にしなければならない”という構造が物語全体に散りばめられており、なかでも冒頭で強烈な印象を残すのが、プレイヤーが誰かと会話をするために、まず相手を銃撃してその存在をこの現実に創り出さねばならないという仕掛けだ。
「本来なら暴力であるはずの行為がコミュニケーションの入り口の手段になるという逆説なんです。でも、コミュニケーションって、意図せず結果として人を傷つけてしまうこともありますよね?」とBaiyon氏は言う。本作のあらゆる設計は矛盾をプレイヤーにつきつける。だが、こういった仕掛けの数々が、プレイヤーに「人間は白か黒かではなく、常にグレーなゾーンをさまよっている」というBaiyon氏のメッセージを実感させるのだ。このようなきわめてパーソナルな体験を“アート”と呼ばずして、何と呼べばいいのか?
勧善懲悪的なストーリーテリングに安住することなく、現代に生きる我々が日常的に抱えるグレーな感情や葛藤に向き合わせてくれるという点において、本作はプレイヤーになんらかの意味もたらすはずだ。このゲームにはプレイすることで生み出されるアート表現が確かに“実存”している。
『Dreams of Another』は2025年10月10日にプレイステーション5、プレイステーション VR2、Steamの各プラットフォームで発売された。この体験が “ゲーム”なのか “アート”なのか――その答えを、是非、自身のプレイ体験で検証してみてほしい。
中村彰憲(なかむらあきのり)
立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザー。 おもな著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』。