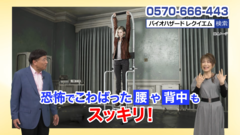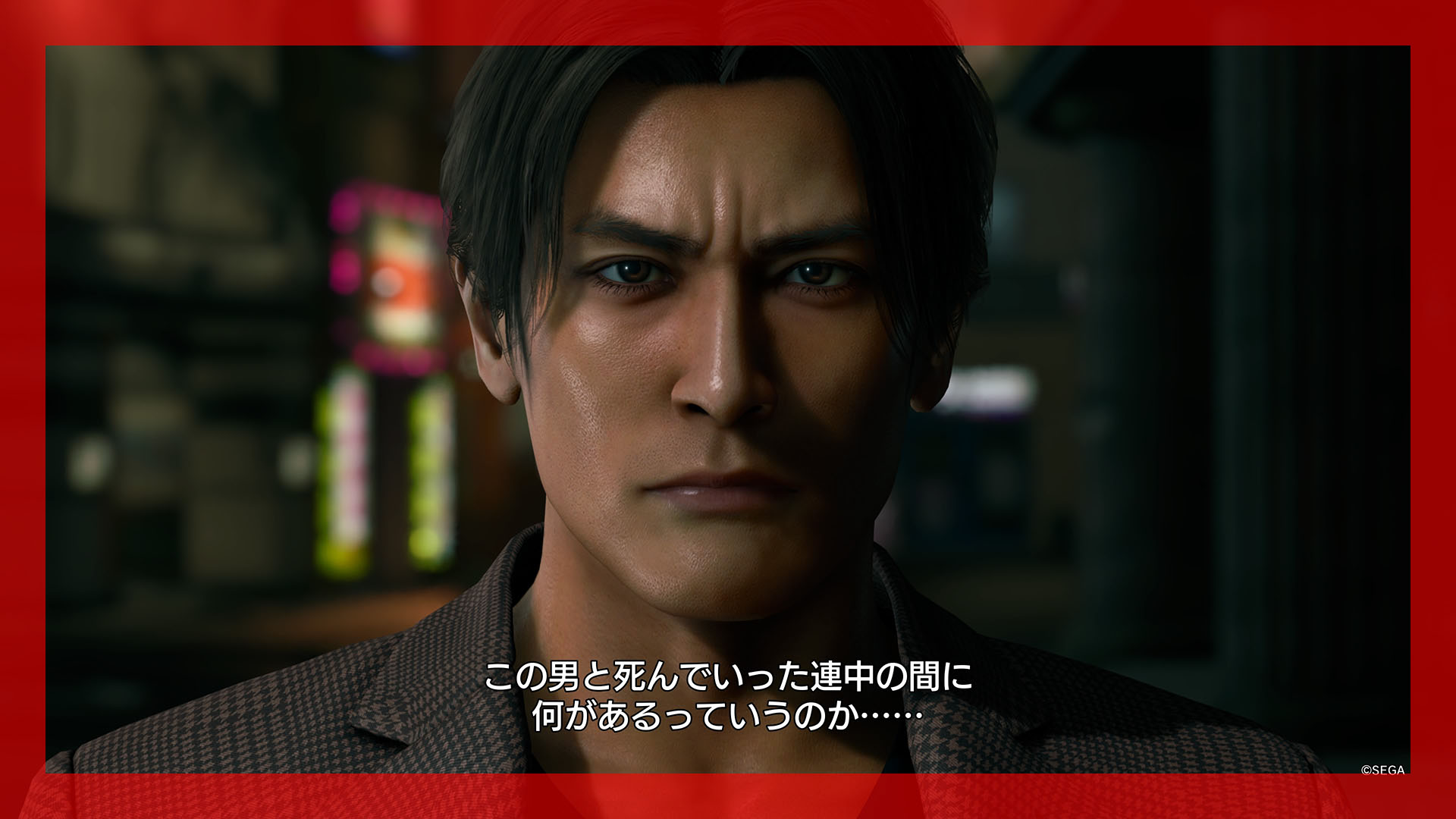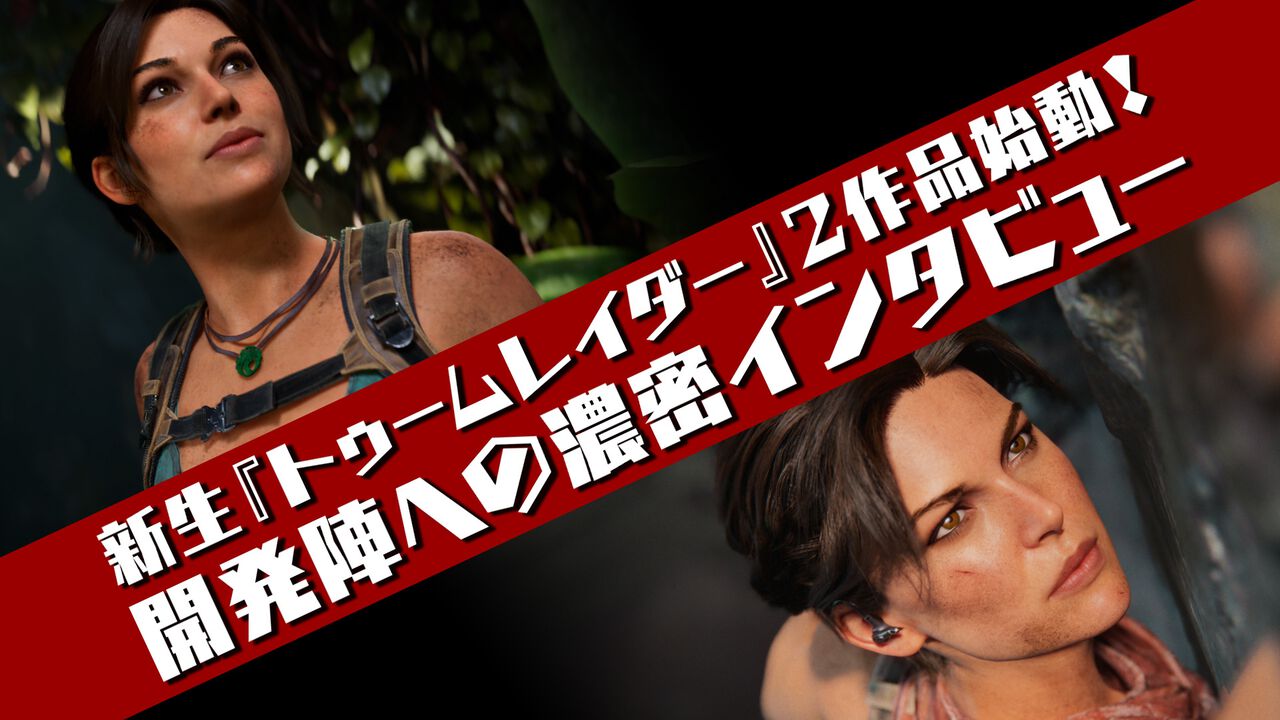いまから25年前の1999年12月29日、セガ・エンタープライゼス(当時)から1本のソフトが発売された。『シェンムー 一章 横須賀』という名のゲームは、ジャンル“FREE”を称する自由度の高さで、作り込まれた日本の街を探索し物語を進めていく。
父の死の謎を追うという本筋がありながらも、街にはガチャガチャやゲームセンターなどの寄り道要素、『バーチャファイター』のバトルシステムを活かした戦闘も搭載されており、町の住民にはすべて異なる姓名と行動パターンが設定され、そのすべてがフルボイスでしゃべるなど、異常なまでの設定の練り込み、あまりに先進的なつくりが注目を浴びた。当然のことながら制作費は膨れ上がり、総製作費70億円という数字は当時“もっとも高額な製作費がかかったゲーム”とギネスブックにも登録された。
『シェンムー』とは何か。『シェンムー 一章 横須賀』がどのようなゲームだったか、どんな文脈を背負っていたか、詳しくはファミ通.com関連記事をチェックしてほしい。
完成されたゲームから想像されるように、その開発現場はじつに壮絶なものだったと、25年経ったいまでも漏れ伝わって来る。その実態はどうだったのか? のちに“伝説”と語られる作品はいかに作られたのか? 1990年代のセガAM2研とはどのようなものだったのか?
AM2研で『シェンムー』開発に携わった当時の開発者7名に、都内某所の居酒屋へ集まってもらった。久しぶりの再会だからか開始当初は硬かった空気も、杯を重ねるにつれて和みディープかつレアな話に進行していく。載せられる話はなるべくそのままに、載せられない話はなるべく載せられるように編集した。“伝説のゲーム”と語られる『シェンムー』開発現場の伝説的エピソード、じっくりとご覧あれ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/abb91a98e9e575757490b36a2b6388d60.jpg?x=767) ※本記事では『シェンムー 一章 横須賀』を『一章』または『I』、『シェンムーII』を『II』と表記する場合があります
※本記事では『シェンムー 一章 横須賀』を『一章』または『I』、『シェンムーII』を『II』と表記する場合がありますセガ 笠原英伍 氏(かさはら えいご)
『シェンムー 一章 横須賀』、『シェンムーII』プランニングディレクター。『What's シェンムー』、サポートソフト『シェンムーパスポート』の制作も担当。プレイステーション4版『シェンムー I&II』ではローカライズプロデューサーを務める。『一章』発売時は30歳。現在はセガ 第2事業部でクリエイティブディレクターを務める。
和田誠 氏(わだ まこと)
『シェンムー 一章 横須賀』プログラマー、『シェンムーII』メインプログラマー。『シェンムー』開発をきっかけにセガに入社し、その後2024年までセガ勤務。発売時は36歳。
平井武史 氏(ひらい たけし)
『シェンムー 一章 横須賀』メインプログラマー。開発後独立、開発会社ネイロを立ち上げる。M&Aで2年前に譲渡し、現在はフリー。発売時は28歳。
ファンコーポレーション 岡安啓司 氏(おかやす けいじ)
『シェンムー 一章 横須賀』、『シェンムーII』サブディレクター。また、『シェンムーIII』開発にもサブディレクターとして携わる。発売時は31歳。
CRI・ミドルウェア 黒岡聡亨 氏(くろおか としゆき)
『シェンムー 一章 横須賀』プログラマー。芭月家、地下室まわりのイベントを担当。
トイディア 松田崇志氏(まつだ たかし)
『シェンムー 一章 横須賀』、『シェンムーII』CGデザイナー。住人キャラクターやビジュアル部分を制作。
宮脇謙史 氏(みやわき けんじ)
グラフィックデザイナー。『シェンムー』デザイナー、シリーズキャラクターデザイン、ユーザーインターフェイス設計などを担当。近年ではゲームのアートディレクターを行いながらテレビアニメのプロップデザインも制作。
25年ぶりに集う『シェンムー』を作り上げた精鋭たち
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9ba96b4801ef7ee4fbd5b6c1dca1aaba.jpg?x=767)
――皆さん、久しぶりに会う方もいるのですか?
笠原
たまに会うメンバーもいれば、久しぶりという人もいますかね。
松田
僕は当時、本当に会社入りたてのペーペーデザイナーでしたので、僕からは岡安さんや笠原さん、和田さんは覚えていても、皆さん僕のことは覚えていらっしゃらないと思います。
黒岡
僕も同じで、入りたてのプログラマーでした。
松田
新卒やハタチそこそこのスタッフにもばんばん仕事が回ってくる現場でしたね。
――本企画は、発売25周年ということで、いまでも語り草になっている、『シェンムー』開発現場のアレコレを当時の方に語っていただこうという企画でして。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a7ff0e638cbaca73da5f854d82cee5adc.jpg?x=767)
一同 ……。
――なんで静かになっちゃうんですか!(笑)
岡安
いや(笑)、やっぱりいろいろな思い出がありますから、どこから話したものかと。
平井
苦しい思いもありましたし。
宮脇
僕はとくに苦しい思い出はないですけどね。
笠原
君は特殊なんだよ!(笑)
松田
みんな会社に泊まっていましたよね。
笠原
もう時効だと思うのですが、僕が覚えているのは、当時和田のタイムカードを見たら、同じ職場で働いている僕でもびっくりするくらいの勤務時間で、ほとんど家に帰れていなかったんですよ。
松田
そう! 和田さんは本当にいつもデスクにいましたよね?
和田
(にこにこ笑っている)。
――まずは皆さんが当時どのような立場で『シェンムー』に関わっていたのかと、いま何をやっているのか教えてください。
岡安
ファンコーポレーション副社長の岡安です。当時はアシスタントディレクターとして、裕さん(鈴木裕氏。『シェンムー』シリーズディレクター)の思い描くことを実現する責任者といった立場でした。また、スタッフたちからの相談役でもありました。
笠原
唯一、いまもセガの人間の笠原です。『シェンムー』では2作ともに、プランニングディレクターを担当しました。要はプランナー、企画マンです。湯川元専務を探す『What's シェンムー ~湯川(元)専務を探せ~』(※)や、サポートソフト『シェンムーパスポート』(※)の制作を担当しましたね。2018年に移植された、『シェンムー I&II』ではローカライズプロデューサーを務めました。
※1『What’sシェンムー』……『シェンムー 一章 横須賀』の体験版ディスク(非売品)。ドブ板の街のどこかにいる湯川英一氏を探すという内容。ドリームキャストの広告塔を担った湯川元専務が本人役で声の出演。モーションキャプチャーはさすがに別人が行ったと思われる。
※2『シェンムーパスポート』……『シェンムー 一章 横須賀』のオンライン要素を楽しめるインターネット接続ソフト。セーブデータに記録された進行度合いに応じてストーリーのヒントが見られたり、ゲームセンターのハイスコアランキングを登録して全国のプレイヤーと競い合ったりできた。100万ポリゴンでハイグラフィックに作られたキャラクターや特典画像を閲覧するといったオフライン要素もあり。平井
ネイロ創業者でexCEOの平井です。当時はメインプログラマーを担当していました。『一章』のソースとなるおびただしい数のプログラムファイルがあるのですが、その約4分の3、つまり75%は僕が書きました。だから、『シェンムー』は僕が作ったと言ってもいいと思うんですよ!(笑)
――おお。
岡安
うるさいよ(笑)。自慢から入るんじゃないよ。
――続いて、ほとんど帰らなかったという和田さん、お願いします。
和田
当時、私はセガの社員ではなく業務委託でプログラマーとして『シェンムー』に関わりました。途中参加だったんですよ。その後、セガに入ることになりまして、そこから2024年7月までセガの社員でした。現在は退職して別の会社に在籍しています。考えてみればセガに入ったのは『シェンムー』が切っ掛けということになりますね。
宮脇
『シェンムー』にはデザイナーとして関わりました。基本はキャラクターデザインを担当し、あとはUI(ユーザーインターフェイス)系のデザインですとか、2Dグラフィックまわりをおもに担当していました。
――芭月涼やシェンファを始めとした、キャラクター設定画を描かれていたのが宮脇さんなのですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/addc4f72e86589a99337e4ec6c737fc47.jpg?x=767)
週刊ファミ通1998年12月25日号。莎花やレン、鳥隼の設定画がページを飾る。ドリームキャストの最大注目作“プロジェクトバークレイ”を追う連載企画が、発売の1年以上前から掲載されていたのだ。
松田
続きまして、トイディア代表取締役CEOの松田です。『シェンムー』は新卒でセガに入社したばかりのときに関わったタイトルで、今回のメンバーでいちばん下っ端でした。でも、本来は『シェンムー』の開発チームではなかったのですが、やはり途中でヘルプで呼ばれ、そのままチームでお手伝いすることになりました。おもに3Dのキャラクターモデルを担当していました。
黒岡
僕も松田さんと同じくらいの年齢で、派遣社員の形でプログラマーとして『シェンムー』に関わっていました。『一章』では芭月涼に関するイベントまわりをおもに担当していました。具体的に言うと、芭月家まわりと地下室あたりですね。
――そんな、年齢も職種もバラエティー豊かな皆さんに集まっていただいたところで、思い出をいろいろ伺っていきます。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a7226a177be9d417f7028ff4ac53b2d5f.jpg?x=767)
平井
強く思い出に残っていることはたくさんあるのですが、僕はプロジェクトが始まってから半年後にチームへ合流しました。プログラマーが約15名のところに、ほかのスタッフも含めて約15名が参加し、約30名のプログラマーとなりました。
もともと『シェンムー』の開発チームは第2ソフトウェア研究開発部・通称“AM2研”と呼ばれた、アーケードゲームの開発を担当していた部署です。ですから『デイトナUSA』ですとか、『バーチャファイター』など、名作ばかりを産んでいたチームではありますが、プログラマーたちは多人数での製作経験があまりなく、連携を取るのが苦手でした。
そこからプログラマーたちを引っ張るリードプログラマーを決めようという話になりまして、チーム内で誰に任命するのか“総選挙”が始まったんですよ。あれって、岡安さんが言い出したんだと思ってますが、違いますか?
岡安
そう、まとめ役を決めるのは総選挙式がいいだろうと。
平井
で、スタッフたちがみんなひとり名前を書いて投票していったら、僕がリードプログラマーに選ばれたんです。あくる日に岡安さんから呼び出されて「お前がリードプログラマーだから」と。
岡安
そこは覚えてないんだけど(笑)。
平井
あんまり僕に興味がないんでしょう(笑)。
――平井さんが選ばれたのは、やはりプログラマーとして優秀で腕が立つ、という理由でしょうか?
平井
僕は家庭用ゲームの開発経験が長かったですし、セガハードの環境にも慣れていて。開発当初はドリームキャストで発売する『シェンムー』ではなく、セガサターンで発売予定の“バーチャファイターRPG アキラの章”から始まっていたので、サターンのプログラムも得意だったんです。
また、システムエンジニアでもあったので、開発環境を整えたり、描画やプログラムの最適化・高速化も得意でした。だから選ばれたんだろうな、と自分では思っています。もちろん、僕よりすご腕のプログラマーは多くいましたが、中でも幅広い分野をカバーできるのが僕だったのかなと。
岡安
もうわかりますよね。「僕はすごいですよ」アピールがすごいでしょう?(笑)。ならば選ばれて当然だろうと。
平井
いやいや、投票のときはそんなアピールしてないですから!(苦笑)。
岡安
ようは、リーダー気質だったんですよね。ちなみに平井と笠原は、もともとセガの関西開発から“お手伝い”の名目で東京にやってきて、結果的に『シェンムー』チームに入りました。
笠原
“シェンムー狩り”に遭ったんですよ(※)。
――あっ、噂の……。
松田
“シェンムー狩り”、いい言葉ですよね(笑)。
※シェンムー狩り……『シェンムー 一章 横須賀』開発スタッフを集めるため、セガ内外からあらゆる人材が招集された。その強引さ、規模の大きさからいつしか“シェンムー狩り”と呼ばれるようになったという。笠原
これが俗に言う“シェンムー狩り”です(笑)。『シェンムー』のためにほかのチームやら会社からスタッフがどんどんと、なかば強制的に集められていきました。
平井
「半年で終わるから」って聞かされて東京に来てみたら、ぜんぜん終わんなかった。
笠原
僕も平井も、半年って言われて入ったのに、もちろん半年では終わらなくて。
平井
僕たちは関西のセガに入る前、アイレムに在籍していました。アイレム時代は1年に1本はゲームをリリースしていたのですが、セガに入ってから縁や運もなく、3年ほどゲームをリリースできずに過ごしていたんです。ですから「半年でゲームが出せるなら、それは関わりたい!」と、わざわざ関西から東京に行ったんです。で、そこから4年掛かりました。
岡安
もともといたプログラマーたちの中には、チームを引っ張れるような人間があまりいなかったんです。平井は気質的にも上に立ってまとめてくれそうだなとは思っていて、選挙で選ばれたというのは、現場スタッフも平井 のことをそう見ていたのかなと。
細かい部分は覚えていないのですが、本来であれば裕さんが「メインのプログラマーはお前」って決めてからプロジェクトがスタートしているはずなんです。ですが決まっていなかったということは、おそらく困っていたのかなと思います。
――イベントを制作していたという黒岡さんはいかがでしたか?
黒岡
イベントを作るにあたり、物語やテキスト、グラフィックなど、あらゆる素材をまとめて構築していくのですが、毎週のように内容が変わっていったのがたいへんでした。また、会議用のプロトタイプのようなものがあったのですが、あれを企画の方々がイベントに声を当てていたのが印象的でした。会議室でそのままアフレコしていたんです。
あと、これは没になった要素なのですが、僕は福さん(登場人物のひとり・福原正幸)の1日の行動パターンを作ったことがあります。その中のパターンに、“トイレに入って用を足す”といったパターンがありました。ですが、最終的には「トイレをしている最中にドアを開けたら気まずい」と(笑)。イベント自体がなくなった記憶があります。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9a859bf779cc1a142000ea3dbdf5dfd9.jpg?x=767)
左が福さん。
――では松田さんは?
松田
『シェンムー』は当時としても、あまりにも登場人物が多いです。ですから、キャラクターデザイナーの方々が描いても描いても、街のおじさんとかおばちゃんとか、あまりにもデザインしきれないという話になりまして。途中から、3Dモデル班はデザイン画なしで、直接キャラクターを作っていましたね。
もともとのデザイン、絵があって、それを3Dモデルにするのかなと思ってたんですけど、入ったばかりの自分がデザインまでやらせてもらえるなんて「なんて自由でいい会社なんだ」と感激していました。
みんな自分でデザインしたものをモデリングしていたのですが、そのうち同僚スタッフたちを元にキャラクター化するのが流行りまして。いかに『シェンムー』っぽいデザインで、同僚に似せられるのか競っていたのをいまでも覚えています。
――実際にスタッフに似せたキャラクターはゲームに入っているので?
松田
たくさんいます。僕も出演していますね。全身タトゥーの入った男として、『シェンムーII』に登場します。
笠原
気がついたら作られてるんですよね(笑)。
平井
僕も『一章』にいるなあ(笑)。
黒岡
中華料理屋に僕がいるらしいです。後で知りましたね。
松田
モデル班が暴走気味に「これでいいなら、どんどん作っちゃうぞ」と、スタッフたちをどんどん3Dモデル化したので、かなり登場しているんです。僕は涼のやられ役のひとりだったので、自分がぶっ飛ばされているのを見て笑っていました(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9156feef718f6780a4556e218c441ec5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a3e3bbe134c4b6e11446281d76550f7b5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a05fd0e805476516948a712b8a8c1bb3f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a949cde8a20faa473af9ac99186d7aeef.jpg?x=767)
街にはひとりとして同じ顔の住民はいない。スタッフの顔をしたモブキャラクターがいるかも?
――当時若手だった黒岡さんや松田さんは、開発現場をどう見ていましたか?
黒岡
会議のときは僕たちが交代制でゲーム操作を担当したりしていたのですが、毎回のように主要のスタッフ陣が疲れきっていたのを覚えています。会議であーだこーだと皆さんが議論を交わし、僕は会議自体に参加するわけではないのですが、自分の担当時間が終わるとチームに戻り「また仕様が変わるのかな」と、みんなでボヤいていましたね。
松田
僕としては、人生史上いちばん人間密度の高い開発現場でした。あらゆる会社の方々が『シェンムー』を完成させるために動いていて、1週間単位で違う人が出入りするので、人間密度がものすごいんですよ。
オフィスのデスクもいまみたいに140センチとかなくて、隣と肩がくっつくくらいの密度感。もうギッチリと詰められていて。また、当時は喫煙所にいかなくても喫煙できるような時代で、物量、人間密度、オフィスのギッシリ感、そして1990年代ですから、タバコの煙。あの密度感、あの空間はいまでも強烈に覚えています。忘れられない光景です。
一応喫煙所は外にあったんですけど、ぜんぜん中でも吸っていましたね、当時は。
笠原
裕さんが吸ってたからね。だからみんな吸っていました。で、途中で裕さんが禁煙したらみんな吸えなくなりました(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a024d5ae83c40fe708327987e8858bded.jpg?x=767)
――ではメインキャラクターなどをデザインされた、宮脇さんはどうでしょうか。
宮脇
僕はゲーム畑の人間ではなく、もともとマンガ家を目指していたけれども、それだけでは食べていけないので本屋でアルバイトをしていたくらいの人間なんです。そんなとき知り合いから「ゲームの企画会議で出たアイデアを、即興で絵にしてほしい」といった、バイトのような仕事を受けまして。
それで参加したところ、裕さんが「この人をメインキャラクターデザイナーにする」と言い出し、いきなり僕は『シェンムー』に関わることになったんです。突然ゲーム会社との仕事、しかも大手のセガでデザインを担当することになったんですから、驚きましたよね。
ただ、いきなりゲームの開発に関わることになり、わからないことばかりだったので、とにかくまわりの人にいろいろと聞きながら四苦八苦していたのを覚えています。
――当時、プレッシャーなどはありましたか?
宮脇
僕よりうまい絵が描ける人なんて、いくらでもいたんですよ。その中でメインキャラクターをデザインしていたので、プレッシャーは強かったですね。また、いきなり入って来た謎のデザイナーだったので、周囲からも「誰なんだコイツは?」と思われていたと思います。
平井
裕さんが、彼の作風をものすごく気に入っていたんですよね。何かあれば「宮脇を呼べ」と言うくらい、宮脇さんの絵を頼りにしていたと思います。
岡安
宮脇は理不尽な目にもあってないし、とても順調に仕事をしていたと思います。おそらく唯一、誰ともモメてない人間なんじゃないでしょうか。世わたりがとてもうまいなと(笑)。
宮脇
たしかに、誰かとモメたような記憶はないですね。
――なんだかモメる前提の空気を感じるのですが……?
笠原
開発現場は戦場ですからね(笑)。
平井
モメてる場なんて何回見たかわからないくらい見ました(笑)。毎週木曜、金曜日は絶対に戦いが起きていました。とくに、最後の1年は。
――木曜日には何があったのでしょうか?
岡安
それが僕の強烈な思い出になりますね。毎週木曜日は、制作したものを1個にまとめて全体会議をする日でした。夜から会議が始まり、終わるのは深夜2時~3時くらいで、もちろんみんな家には帰れません。で、そのあと各部署が「ここをこうしてください」と修正指示を振り分けて1日が終わるわけです。
いまだに覚えているのが、にいつものように深夜3時くらいに会議が終わって、裕さんがいったん寝たときの話です。そのあと僕たちは各部署への指示をまとめ、自分たちもいったん寝ることにしました。翌朝、起きた裕さんから開口一番に聞かれたんです。「できたか?」って。
「できてないです」って言うと「なんで?」と(苦笑)。「いや寝てたからです」と言うしかないんですけど。純粋に裕さんは僕たちが寝る時間のことを考慮してなかったようで(笑)。
――なるほど(笑)。徹夜ばかりだったようですが、仕事が終わって飲みに行く、みたいなことはありましたか?
笠原
ありましたが、大勢で行くというよりは、一部のスタッフたちが少人数で個別に行くような感じでした。辛いことしかないので、わかり合ってるメンバーだけで“傷を舐め合う”ために飲みに行くんです(笑)。ちなみに女性スタッフもいて、そのおかげか仲が深まってカップルが誕生したり、“シェンムー婚”もけっこうありましたよ。
――へー! おめでたい。
宮脇
当時社内用のBBSに、パッと見るとただのゴミに見える1ドットの表示があって、そこを押すとなぜかプログラマーが仕込んだ、そいつの彼女自慢が書いてあるという事件がありましたね。
――1990年代っぽい逸話だ(笑)。
平井
あと、麻雀もよく行きましたよね。
笠原
行ったね。夜中まで仕事して、朝まで雀荘で麻雀して、そのあと出社して……みたいな。
平井
いまだから言えますが、僕はもう就業時間内にほかのスタッフから質問などが飛んでこないように、終電まで雀荘に行って、終電になったら会社に行って朝まで仕事していました(笑)。それをチーム内にあった“BBS(電子掲示板)”に書き込んだら、岡安さんに怒られたのを覚えています。
岡安
平井は奥さん向けの言いわけに、僕を使っていたこともあったよね。岡安さんに誘われたので仕方なく、みたいな。でも実際は雀荘に行っていて。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a0b8e3df37b6375b6e90a08f5dd4662ce.jpg?x=767)
『シェンムー 一章 横須賀』に登場する雀荘。リアルな取材の成果が反映されている?
平井
そうでしたね(笑)。開発の後半は、月に2回くらいしか家に帰ってなかったと思います。あえてやっていましたが、会社で寝るか、麻雀をするかの2択でした。まあ会社まで歩いて10分の家だったのですが、それでも帰る時間がもったいなくて。
――10分なのに。
岡安
寝てたか麻雀してたかどっちかでしたね。
平井
ちゃんと仕事はしてました(笑)。
岡安
帰りたくない理由がほかにあったとか!?
平井
そんなことはないです(笑)。ただ本当にあったこともあって、岡安さんから「飲みに行かない?」、「麻雀しない?」と言われるのは、何か大きい仕事をお願いされるときだけでした。いまから仕事が増えるんだな、と思って岡安さんと飲みに行ったりしていましたね。
岡安
いまでは考えられませんが当時は徹夜が当たり前でしたね。終電前に帰る人は、むしろ睨まれるような。ええもう、超絶ブラックです(笑)。もちろん、社員じゃないスタッフもいたので、ちゃんと帰っている人もいましたが。
とはいえ、もともとゲーム開発の現場がそんな感じでしたから……『シェンムー』のせいでさらにひどくなったかもしれないですけど(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/adc765ec1487bf89aaf02ee7d84f50ac6.JPG?x=767)
過酷だった開発現場
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/ad38c6f43953342d6c1f722b444cddc5e.jpg?x=767)
平井
夜の10時から会議始めちゃダメですよね。仮眠室もありましたけどね。とはいえじつは前の会社も似たようなものでして、「いっしょだなあ」と思っていました。そういう時代でしたね。ただ、シェンムー開発時はもっとすごい重圧を感じていましたが。僕はタイムカードが月で●●時間になっていたのを覚えていますね。
笠原
勤務時間と言えば和田ですよ。さっきの話ですけど、タイムカードを見ると、1ヵ月ほとんど家に帰っていない。しかも、タイムカード誤魔化したり、ズルするような人間じゃないんです。勤務時間の記録が1ヵ月で▲▲時間くらいになってて。
――ガハハ(笑うしかない)。ひと月って24時間×約30日として720時間くらいしかないはずなんですけど。
平井
和田さんは「ヌシ」って呼ばれてました。それくらい働いてましたし、開発現場に必ずいました。業務委託社員なのに!(笑)。
笠原
いつ行ってもいるんですよ。
――なぜそれほどまでに、和田さんは働いていたのでしょうか……!?
和田
僕は業務委託社員で、もともとは別会社でさまざまな開発を行っていたんですが、業務委託を受けてシェンムー開発に参加しました。その委託された業務内容というのが「『シェンムー』をリリースすること」でした。リリースしないと自分の責任は果たせないと思っていたので、それに従ったまでです。
まあ単純に言えば、2ヵ月間家に帰らなかっただけですよ(笑)。
とくに開発終盤は約2ヵ月間デバッグしなくてはならなくて、24時間体制のデバッグ業務がありました。そのデバッグ中にゲームが止まってしまって、チェックするスタッフが何もできないまま朝を迎えてしまったことが何回かあって。なぜならば、プログラマーがいないのでバグが起きても直せる人がいないんです。
「だってプログラマーがいないから、デバッグができないんですよ」と言われてしまったら、それ以降は僕が24時間見るしかなく、僕がほぼ24時間働いていたんです。
――いつ寝ていたんですか!?
平井
確かに。和田さんいつ寝ていたんだろう……。
和田
シンプルに、寝てなかったんじゃないですかね。
笠原
寝てたよ。朝の5時から5時15分まで。
平井
アッハッハッハ。でも本当に、そのくらい寝てなかったイメージですね。「寝るわ」って言ったらまたすぐいて、「あれもう起きてきたの」ってなったような。
和田
寝るって言っても、机の下に段ボールが敷いてあって、そこで横になるだけです。
――わ、ワァ……。
松田
みんな段ボール敷いていましたよね(笑)。
和田
24時間体制で3交代式でデバッグしていたのですが、それに合わせてプログラマーも3交代にする必要がありました。ちなみに、当初は2交代でやろうという話になりましたが、全員潰れたのでやめました。
宮脇
2交代は無理ですよ(笑)。
和田
で、3交代と言っても簡単なプログラムのバグなら、誰でも直せるんですよ。トリッキーなバグがあったら、平井くんか僕しか直せないんです。ハードウェアの知識が必要なとあるツールがあって、それを扱えるのが僕か平井くんしか本当にいなくて。どちらかが絶対に残る必要があったので、僕はずっと開発現場に居ただけです。
笠原
そして、3交代の朝5時交代の時間があって、その交代のタイミング15分くらいは報告が上がらないので、その瞬間だけ和田は寝てたんですよ。
平井
開発期間4年のうち、最後の1年に和田さんが入ってきたのですが、もう本当に仕事がグッと楽になりました。楽になったと言っても、仕事量や労働時間はまったく減っていません。ほかの仕事にも手が回せるようになったので、気分がとても楽でした。
宮脇
僕がいたアートチームって、作ってしまえば作業から手が離れるので、開発としては早めの段階で終わるんです。そのあと、デバッグを担当することになり、僕もデバッグチームのリーダーみたいなこともやっていたのですが、そのときよく和田さんたちにバグの報告をしていました。ただ、バグの量が本当にものすごいんです。
和田
1日300個バグが出て、1日バグを300個潰さなければいけない、みたいな量でしたね。
宮脇
ですから最終的に「もうデバッグの報告を持ってこないで」と言われましたね(笑)。探せば探すほど出てきて、本当にキリがなくて。
平井
ダメじゃないですか(笑)。
和田
とはいえたとえばバグ300個があるとしても、大半はイベント関連のバグだったので、そこはイベント班が潰して、僕らは致命的なバグを直していました。
宮脇
どうでもいいバグも多くて、横須賀港にいたお姉さんが180度足を開いて海の上を高速飛行していくバグとか、涼の胴体にボタンUIの表示が出ちゃって全身特撮スーツのスーパーヒーローみたいになっている涼とか、笑えるバグもありました。タトゥー屋で「強そうなのにしてくれよ」と言っている米兵がいるところに、ヒーローみたいな見た目の涼が現れて、「うわあ~」ってチンピラたちが恐怖して逃げていった(笑)。それはイベント進行通りのセリフなのですが、バグった涼の状況と合わさって妙におかしかったですね。
和田
これはバグといいますか、報告として「居酒屋になぜか湯川(元)専務がいる」といったバグが上がってきたんですね。いやいや、そんな仕様で作ってないから、いるわけないじゃんと思うわけです。こちらとしては。
――まあ、作ってないものは出ないですよね。理論的に言って。
和田
それでチェックしたら本当にいるんですよ、湯川(元)専務。プログラマーがこっそり仕込んでいた!
――ガハハ。それはバグというかむしろヒューマンエラーですね(笑)。
平井
イベント班はねえ、本当に勝手なことばっかりやってた(笑)。
和田
バグはできる限り潰したんですけど……。
平井
開発終盤になって、本当にこれ以上遊んでいるヒマはないという話になって、和田が戒厳令を出したんですよ。マジで本当にこれ以上、そういうのやめろよって。
和田
あと、製品版には載ってないんですけど、涼が裕さんの見た目になっちゃうというバグがどこからか映像が流出したんですよね。
松田
ありましたねえ!
和田
あれはめっちゃおもしろかった(笑)。
松田
業務時間外でみんなノリノリで作ってたんですよ、そういうお遊びデータみたいなものを。
――セガっていい会社ですねえ(笑)。そういったものは別としても、バグが大量にあったのはゲームの規模があまりにも大きかったのが原因だったのでしょうか?
平井
プログラムとしては、バグの少ない環境ではあったと思います。バグが起きないように、最初から気を付けてプログラムを組んではいたのですが。
笠原
動いていたのが奇跡だと思うよ。事前に考えていたものより、継ぎ足し継ぎ足しで要素がどんどん増えていったのが原因だと思います。
岡安
デバッグって、ふつうはバグが起きたら、それを直して、正常な動作にするのが一般的かと思います。ですが裕さんの場合は、バグを直すついでに「もっとこうしたい」と、そこに追加アイデアを積み重ねていくんです。
平井
また、当時BバグCバグと呼んでいた、通常ならば「できれば直したいけど、軽度なバグだから後回し」みたいな些細なバグもあるのですが、『シェンムー』の場合はすべてが同一のバグ扱いだったと言いますか、裕さん的には「こうしよう」が実現できてないものは、重要なバグだったんですよね。
岡安
僕たちが「もうデバッグ作業だけに集中しましょうよ!」って、アイデアを出さないように止めないといけなかったです。とことん突き詰める、それが裕さんのいいところでもあるのですが。
笠原
平井がいなかったらできてないと思いますよ。
平井
僕も和田さんがいなかったらできなかったと思います。
笠原
奇跡なんですよ。ふたりがいなかったら『シェンムー』はできていないと思います。
平井
1999年12月末に発売でしたけど、1ヵ月前の11月でバグ10000個くらい残ってましたよね?
和田
最後、『一章』は1ヵ月ほど発売延期となったのはそれですね。さすがに潰し切れませんでした。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/aec30f6ed50a7283a3d137f421028919b.jpg?x=767)
開発現場は大ピンチの連続!
――和田さんの伝説をお聞きしたところで、笠原さんの思い出を教えてください。
笠原
AM2研はいままで家庭用ゲームを作ったことがなく、じつは企画チームがいなかったんです。いままで全部感覚でゲームを作っているといいますか、プログラマーが組み込んだら裕さんがチェックをして、「ここはもっとこうしよう」と都度修正し、叩き上げて作っていったんです。
でも、『シェンムー』はRPGですから、企画や仕様書がない状態で作れるワケがないんです。ですが、プロジェクトがスタートしてから1年くらいは企画担当がいませんでした。(シェンムー狩りにあって)『シェンムー』チームに合流したとき、僕は企画ではなく事務的な仕事をしていましたね。
その横で岡安さんには「企画担当が絶対に必要ですよ!」とは何度も言っていて、途中で、「いるよな」という流れにようやくなって、ようやく企画セクションができました。
岡安
そこ、あまり記憶ないんだよなあ。
笠原
いや、岡安さんは「企画なんていなくてもできるだろ!」って言ってましたよ(笑)。
松田
言いそう(笑)。
平井
言ってそう(笑)。
――それはAM2研イズムなんですか。
岡安
イズムですね。
笠原
『バーチャファイター』とか、『バーチャレーシング』なら「このコーナーはもう少し曲げよう」、「ここはアクセルを踏む気持ちのいいストレートにしよう」など、アーケードゲームの開発は、感覚で調整していたわけですが、RPGは物語を展開しながらゲームを進めるのが基本ですから、何を作るのか企画していかないとダメなんですよ。
これこれこうで、こういうモノを説明するために、企画が必要です! って紙に書いて説明して「必要だね」って納得してもらっていったんです。そこから、プランニングディレクターとして関わるようになったのを覚えています。
平井
僕は4年間一度も仕様書もらったことないですけどね。
――出た! 仕様書のない開発現場!(※)。
笠原
いや、書いてた! 書いてたよ!
平井
僕のプログラムには仕様書はいっさいなかったですね。こういう仕組みでプログラムしてほしい、みたいなものはなく、全部自分でどうすればいいのか考えていました。
笠原
システムの仕様は書いてなかったね(笑)。
和田
見たことなかったね。
笠原
シナリオやシチュエーション、遊びの部分を考えて渡していましたね。1イベントの概要みたいなものです。
※仕様書……ゲームに限らずプログラムの作成時には、いわばその設計図となる仕様書が必要となる。しかし往年のゲーム開発現場には仕様書のない現場もちょくちょくあったとかなかったとか。とはいえ開発規模が大きくなればなるほどその必要性は増すはずで、仕様書なく『シェンムー』をプログラミングしなければならなかった平井氏の苦労は推して知るべしである。アイデアを実現させるために
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a1bc0f9034ce9daa8ae80b054421b049a.jpg?x=767)
――なんだか、聞いていると「それでよく作れましたね!?」と思えてくるのですが……。
岡安
めちゃくちゃなんですよ、めちゃくちゃ。
――(笑)。
岡安
もうちょっとマシな言いかたがあるかな……破天荒! 破天荒な作りかたをしていたのは間違いないです。
キャラクターも、涼などの基本となるメインキャラクターたちは宮脇と裕さんが考えて作り上げていったものですが、ほかのキャラクターはイチから現場スタッフレベルで作った人たちばかりです。それも人物設定から考えるのではなく、ビジュアル先行でガンガンキャラクターを作っていました。裕さんがそれらを見て、その人物を登場させるのか否か決めていきました。
平井
場当たり的というかドロナワ式というか。とにかくアーケードゲームの開発ばかりでしたから、ああいう、家庭用ゲーム機向け大型タイトルの開発経験がみんな不足していたんですよね。最初に全体の大枠を作って、こういう設定がいるよね、じゃあこういう素材が必要だね……という、外堀から埋めていく計画的なやりかたではないプロジェクトでした。
――走りながら作り上げていく、マラソン方式とでも言うような。
岡安
キャラクターの裕さんチェック時は、おじいさんやおばあさんみたいなシワのあるキャラクターのほうが、顔の情報量が濃いおかげか、それが裕さんの合格ラインを超えやすかったんです。ですから、老人キャラクターばかりになっていたりして(笑)。
松田
キャラクターによく「横須賀の街に住んでいる息吹を感じない」ってダメ出しされましたね(笑)。逆にいいときは、「イエスだね」と言ってもらえました。
宮脇
一般的なキャラクターデザインじゃ、裕さんにはハマらないんですよ。個性的か、超個性的なデザインじゃないと「コレいいね!」とならなくて。ですから、一時期は個性的なキャラクターしかいなかったです。
岡安
裕さんに合格を貰わないと仕事にならないですから、合格をもらうためにみんな個性的なキャラクターばかり作り始めちゃってたいへんでした。
笠原
背景であるフィールドも、汚い街並みとかじゃないとオーケーがもらえないんですよ。綺麗な背景ではダメで、ゴミが落ちていたり、壁が汚れたりしていないといけなくて。ですから『シェンムー』の街並は、基本汚れています。
――ブロック塀の黒ずみかたとかすごくいいですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a2712082f21ce7849c6323b5f7aee3c7a.jpg?x=767)
見てくれよ壁のこのクラック(ひび)!
松田
グラフィック的な話をすると、シワがあったり壁が汚れていたりしたほうが、1枚の絵から伝わる情報がもちろん増えますよね。たとえば、きれいなシワのない女の子の顔よりも、しわくちゃのおばあちゃんの顔のほうが“シワがある”とわかりますから。綺麗な女の子の顔が、つい物足りなく感じてしまっていたのかと思います。
だからおっしゃるとおり、老人ばかりが自然と増えていき……。
岡安
それであるとき裕さんに言われたんです。「なんか登場人物が老人ばかりじゃないか?」と。
平井
選んだのは裕さんなのに(笑)。ちなみにプログラマーとしては、キャラクターの容姿が全員違ったりするのも、とても苦労したポイントでした。
――あの独特なテクスチャがいいですよね。
平井
ゲーム内に同じものがほとんどないので、流用せずに個別に描画しないといけなくて、メモリを圧迫するんですよ。しわひとつ取っても。
雪や雨を、時間や天候をプログラムで調整する“マジックウェザー”というシステムがあったのですが、それもどんどん表示させる雪を増やす指示が飛んでいて。雪が表示されればされるほど、処理が重くなるんですね。「これ以上増やしたら重くなりすぎますよ!」と言っても「だったらお前が早くすればいいだろう」と(笑)。
雨も単に雨粒が降るのではなく、地面に落ちたら水しぶきが飛ぶような表現が取り入れられたりして、それも処理が重くて。もう開発の後半はとにかく、ゲームの処理を軽くする高速化の作業ばかりやっていたように思います。
岡安
ですから、過程は破天荒ではありますが、目標としては裕さんのアイデアをとにかくみんなで実現させる、独特の開発スタイルだったんです。天気と言えば、ビックリしたのは「横須賀の当時の天気を再現しよう」と言ったときでしたね。
笠原
あれをただランダムで雨が降ったり雪が降ったりするんじゃなくて、当時の現実の気象データを取り寄せて、ゲームに取り入れたんですよ。
岡安
笠原が俺に聞きにきたんですよ。「裕さんが1987年の実際の横須賀の天気を入れたいって言ってるんだけど、どこに聞けばいいんでしょう?」って。知らないよ!(笑)
笠原
あと、電話番号も、わざわざ横須賀市の電話番号を使おうといったアイデアもありましたね。横須賀に住んでいないと取得できないので、セガ社員の横須賀に住んでいるスタッフを探し、AM2研ではない別部署の人にお願いして、実際に横須賀の電話番号をいくつかゲットできました。
――実際の電話番号を取得してどうしようと?
笠原
実際にその番号は、ゲーム内に登場します。現実に、その番号へ電話を掛けると呼び出し音は鳴るんですが、結果的には何も起きません。構想としては電話を掛けたら何かしらつながるという企画があったんですよ。
――リカちゃんでんわみたいな(笑)。
笠原
そうそう、貴章の合言葉を伝えると、現在はもうない“ダイヤルQ2”みたいなことをやれたらと考えていました。
平井
電話で思い出しましたが、黒電話のコードの処理がものすごく難しかったですね。
あれわかりますかね。ただのコードじゃなくて、丸まっててそれが伸び縮みする。
――ああ、バネみたいになってますもんね。
平井
あのクルンクルンしたコードが伸び縮みするのを描画する処理が本当にたいへんで、ものすごい時間を掛けて作ったのですが、実際にゲーム内に表示される時間は……ほんの一瞬!(笑)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/b4b572ef0fb0adbc303c3a2ada32b91a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/ad008dd08315b2fa36bd7df6f803ece50.jpg?x=767)
芭月家の黒電話。動画で見るとコードが自然ないい動きをしている。
岡安
自慢してたよね、当時(笑)。
平井
本当に物理的にも正確な動きをするプログラムなんですよ! 残念でしたが『シェンムーII』になって、涼とレンが手錠でつながれてしまうシーンでは、手錠の鎖の部分にそのプログラムが使われています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4fb14ef374284531c35eba42579ea592.jpg?x=767)
『シェンムーII』
岡安
いまとなっては当時の気象データや電話番号、電話線のコードの表現なども含めて、再現した意味は果たしてあったのだろうかとは思ってしまいますが……。
――いやいや、『シェンムー』ファンとしては、ゲームの本筋に関係ないところにやたらエネルギーを懸けているのがいいんですよ。たとえば居間にこたつがある、そのうえにミカンが乗っている、ひとつ手に持つ、それを回して見ることができる。これってゲームの本筋にはぜんぜん必要ないと思うんです。でも、それができるから『シェンムー』はほかのゲームとは異なるし、そのユニークさが最大の魅力だと思うんですよ。
岡安
我々としては「そこにエネルギーを使うなら、ひとつクエスト増やすほうがいいんじゃないか」とも考えていました(苦笑)。そういった“こだわり”がファンを生んでいったんだなというのは、後になってから感じましたね。
和田
モノをつかめるシステムは、僕が作りましたね。当初は「モノを持てるようにしてほしい」と言うので、それはつかむモーションを作ればいいだけだろうと返したのですが、そうではなくて「何でもつかめるシステムがほしい」という話で。
――つかめますよね。いいですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a886358b0c76b3c22302a1eebda4371f7.jpg?x=767)
和田
だからつまり、指それぞれを人間のように動かせるようにしたらいいんだと、自分の手を見ながらプログラムしました。最初は「まあつかんでるように見えればいいんだろう」と、汎用的なプログラムにしたのですが、あるとき湯呑みをつかんでその中を覗いた裕さんから「湯呑みのなかに指が入ってる(食い込んでる)」と言われて。
――あら。
和田
そんなの「見なきゃいいじゃん!」って。
――がははは。まあ、ゲーム進行としては別に、湯呑みを持ってその中を見られることは必須ではないですもんね。
和田
だからもう、本当にアイテムそれぞれに合わせて持っているように見えるシステムにしなくてはなりませんでした。「角度変えなきゃいいじゃん! 傾けて湯呑みの中を見る必要ないじゃん!」とは思いながら(笑)。
平井
和田さんはそういう細かいことを、全部やってくれたんですよ。
――これは僕の考えなのですが、ゲーム(づくり)においてはシンプルに効率的であることが必ずしも正解ではないんじゃないかなって思うんです。なんかヘンなところにやたら力入ってるなとか、これって無駄かもしれないけどちょっとおもしろいな、コスパ悪いかもしれないけど制作者がこだわってるんだみたいなポイント、余地、システム上の“遊び”こそが魅力になるというか。それってある種エンターテインメントの本質でもあって。だって、娯楽ですから、オフィスソフトを作ったり使ったりするのとはやっぱり違うと思うんですよ。
岡安
そう言ってもらえると当時の開発者たちも報われる……かな?(笑)
シェンムーツクール的なプログラム
――ほかにはプログラムで、とくに難しかった部分はありますか?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/c022a38c6740f8aa840eac0880612fbaf.jpg?x=767)
平井
ゲームセンターYouのゲームインゲームはけっこうたいへんでしたね。『スペースハリアー』とか『ハングオン』がゲームの中で遊べて。本編のデータをいったん置いておいてこれらを遊んで、プレイ後にはいろいろな内部データがぐちゃぐちゃになって戻ってくるんですよ。それをあたかも何もなかったかのように調整しながらまた本編のプレイを再開するというのは、じつはなかなかたいへんな処理でした。
――なるほど。
黒岡
ちょっとおもしろいところで言うと、ガチャガチャあるじゃないですか。あの中でソニックが出てくるんですけど、ソニックだけやたらポリゴン数が多く作られていて、開発中はソニックが当たるとフリーズしてしまうという事件がありました。セガの看板であるソニックだからちゃんと作ろうとして50万ポリゴンくらいで作っていて、めちゃくちゃデータが重くなってしまっていた時期があったと(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9376f3e00dfa26a0f591af56d6003f61.jpg?x=767)
おっ、これは……。
平井
あと難しかったのは、ゲームの制作がどうこうより、人間関係を減らすプログラムを作ることでした。プログラマーは最終的に僕を入れて、88人で作りました。88人もいるとなると、コミュニケーションがたいへんになります。コミュニケーションなしでプログラムできるようにならないと、僕の仕事がいっさい進まなくなると思ったんです。
実際、僕が合流してからの半年間は、そのプログラムを作った人に「どういう仕様なんですか」と聞かないとプログラムに手を付けられなかったんですよ。それをなくすために、プログラムの基本を共通化したんです。「なんでもできる」というのがプログラムというものは自由なことが特徴ですが、その自由を消したんです。「なんでもできる」ということを一回なくして、「なんでもできない」にしたんです。そのうえで「なんでもできる」という環境を構築しました。
――禅問答みたいになってきた。
平井
わかりやすく言うと、レゴブロックのような。見るとどういうブロックで作ったかわかりますよね。そういうブロックパーツを作って、「このコマンドを使わないとプログラムできませんよ」みたいな基礎を設定し、みんながブロックを積み上げるだけでイベントやシーンなどを作れるようにしました。「このレゴブロックを使って、好きにプログラムを組んでいいですよ」というふうにしたんです。それを僕が全部管理してデバッグするので、というふうにやりました。
――はああ。自由度が高いフリープログラムだと本当に収集がつかなくなるので、そこを、共通ルール、共通規格があるなかで最大限の自由度を持って開発できるようにしたというか。
平井
みんな好きにプログラムをして、いいものは残ってダメなものは自然と消えていきました。
僕を除いた87人をひとつにする仕組みを作ったおかげでコミュニケーションも必要なくなりましたし、オープンワールドの先駆け的なRPGが実現できたんじゃないでしょうか。
――いわゆるエンジン部分ということですかね?
平井
エンジンでありながらも、最終形を見越して作ったコミュニケーションレスのシステムということですね。
岡安
なんか平井、ぜんぜんグチを言わないで「俺はすごかった!」という自慢をしているよな?
――アッハッハ。
平井
だって……だって、すごいの作りましたもん!(笑) グチの多さは岡安さんと笠原さんにかないませんよ。ふたりがプログラマーが働きやすいように、守ってくれていたからだと思います。
――岡安さんと笠原さんが防波堤だったのですね。
平井
ふたりが守ってくれたことで、作る時間をきちんと確保してくれて、皆さんのおかげで……僕が作りました。
――(笑)。
岡安
オイ(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/aae2275490ecd4141bbea2e6d5dd0acb3_4YRPjI8.JPG?x=767)
平井
そして和田さんもすごいです。和田さんがいたから、僕も動けていたと思うので。
岡安
入ってすぐに、しかも社員じゃないのに、その場を仕切る立場になっていたよね?
平井
完全にナンバー2でしたね。4年目の最後の1年に入って、1ヵ月でチームの細かいところを仕切って、11ヵ月でゲームが完成したんですから、和田さんがいなかったら『シェンムー』完成は無理でしたよ。
和田
それはもう、業務委託で、「完成させてくれ」と言われて契約しているので、終わらせるのが僕の仕事でしたから。
――2ヵ月帰らずに3倍くらいの稼働で働いていたのですから、いたのは1年とはいえ実質3年くらい働いてたっていうことですよね。
松田
あっはっは。そういうことですよね。
和田
ちなみに当時、自分は自分の会社で、別タイトルのゲーム開発もしていました。『シェンムー』がそこまで忙しくない時期は、セガから帰宅中に自分の会社に戻って、その別タイトルを開発し、そこから帰宅してました。
松田
もっと働いてた。
黒岡
超人。
和田
そういうのが当たり前だったので、僕としては正直、『シェンムー』はそこまでたいへんだったりしんどかったとは思ってないんですよ。
平井
いやしんどかったよ、めちゃくちゃしんどかったですよ!
一同 (爆笑)。
止まらない鈴木裕氏とのエピソード
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4421bdb81fbf12e9bc1eba276e1c2c00.jpg?x=767)
――すでにいくつか挙げられていますが、裕さんとの開発で、記憶に残っているエピソードはありますか?
岡安
なんだっけな、なんか口ぐせみたいのもあったんですよ。
和田
それ言いましょうか。
岡安
はい。
和田
「OKとは言ったが、GOとは言ってない!」でしょう(笑)。
一同 ああああ~~!
笠原
あったあった(拍手)。
平井
ありましたね、みんな食らっていました。
笠原
何かを作るとなったとき、裕さんに「こういうのでいいですか」とプレゼンし、確認して「OK」と言われたので作って。完成して見せたら「何を作ってるんだ、何でそんなもの作ったんだ」と、NGが出されるわけです。
平井
当然、「先週見せて裕さんがOKって言ったじゃないですか」って反論するんですけど。
笠原
そうしたら裕さんが「OKとは言ったが、GOとは言ってない!」と。
――がっはっはっは。
平井
あれから毎週、「裕さん、OKですか?」、「OKだ」、「そのOKは、GOですか!?」、「GOだよ」と、2段階の認証をするようになりましたよね(笑)。
笠原
何なんだこの会話、と思いつつね(笑)。
平井
あれは名言だったなあ。
黒岡
懐かしい(笑)。みなさん心が折られてガクっとしていたのを覚えています。
――皆さんにとってよくあった話なのでしょうか……!?
平井
僕はほかの人が言われているのを見ただけですが、実際にありました。
笠原
だいたいの人は言われたことがあったと思います。
岡安
まあ言ってしまうと、裕さんがOKを出したことを忘れていて、恥ずかしくて誤魔化しただけなんだと思います。
笠原
あと強烈に残っているのは、“逗子マリーナ合宿”ですかね。
岡安
あったね(笑)。
笠原
裕さんの家が当時逗子にあったので、毎週企画会議のように逗子マリーナという場所に集まって合宿していたんですよ。裕さんが多彩な業界の人たちを招待して話し合ったり議論したり、毎週のように最終的にはワインを飲んで交流したりと、これまた破天荒な会でしたね。
――今回、鈴木裕さんからの25周年コメントもいただいています。それがちょうど、逗子マリーナ合宿の思い出の話ですので、ここで発表させていただきます。
鈴木裕氏 25周年コメント
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a86a01576be85b6f0169b517804d28334.jpg?x=767)
印象に残っているのは、やはり毎週週末におこなっていた、逗子マリーナ合宿ミーティングです。異業種の幅広い考えかたを取り入れるために毎週末、1泊缶詰ミ-ティングを決行しました。映画監督や小説家、作曲家や映画、映像関連の人たちなど、多種多様な人たちを集めて交流を図り、まったく新しいゲームの姿を探そうとしていました。
言語も感覚も違う人たちをまとめるのに、まずは逗子マリーナに1泊して、食事や温泉のあと『シェンムー』の概要を話し、懇親を深めることから始めました。初めはみんなも警戒してあまり話してくれず、とうとう夜9時過ぎには酒を出して話しやすくするという、まさに裸の付き合いからのチーム作りでした。
夜弱い人は早めに寝てしまったり、午前3時を過ぎても白熱した議論をしている人もいました。酒が入ったほうが良い意見が出る人は「飲んでもいい」というルールを作ったので、このルールは絶大なる効果を発揮しました。
『シェンムー』に携わったすべての方に感謝いたします。とくにウィークエンド逗子マリーナミーティングの準備を、毎週欠かさず行ってくれた企画の面々には苦労を掛けました(笑)。
――とのことでした。
岡安
笠原、泣いていいぞ。
笠原
どういう感情の涙なのか(笑)。
合宿にはたくさんの人数が参加しますから、ワインやおつまみがなければ買いに走って、体調の悪い人がいれば薬を買いに行ったときもあります。逗子に住んだことはないのに、逗子のどこに何の店があるのかだいたい把握してましたね(笑)。クリスマスから大晦日まで5日連続合宿もありました。会議が終わった大晦日に、宮脇と「俺たちは(逗子で)何をやっているんだろうね」と、大黒埠頭でドンブリメシを食べたのを思い出します。
宮脇
(笑)。
岡安
逗子合宿は本当におもしろいエピソードがたくさんあって、シナリオをみんなで考えていたときのことです。もう明け方なのですが、ヘロヘロで、かつベロベロで。そのときは涼のピンチをどう解決するのか、という展開を考えていたのですが、裕さんが「そうだ、この人物が助けに来てくれる展開はどうだ!」と言ったんですね。
一瞬、みんな「おお」となったのですが、よく考えてみると、その日の前半の会議で、夜7時ごろにその登場人物は死んでしまうことが決まっていたんですよ。「裕さん、そいつもう死んでますよ」と(笑)。
――苦労話は自然と出てくると思いますが、明るく楽しいエピソードはあったりしますか……?
平井
まあ、裕さんも「いつか笑い話にできるよ」と言っていたので、いまそうなっているのかなと……(笑)。
岡安
辛い話はいま思い返すと笑い話になりますね。
笠原
あれを乗り越えられたから、どんなことも基本耐えられるようになりましたし。
平井
これもまたそういう笑い話に近いのですが、パシフィコ横浜で1998年に開催した『シェンムー』の発表会も思い出深いです。
――大々的にやったやつですよね。
平井
『シェンムー』というタイトルや主人公が涼であること、声優陣なども発表されました。ただ、そこで流された映像はすべて中国が舞台でした。ですが『一章』の舞台は、横須賀ですよね。
あの発表時、日本の舞台はまったく作ってなかったんですよ(笑)。もとが“バーチャファイターRPG アキラの章”なので、アキラが主人公であれば中国でも問題なかったのですが、発表後に「日本人の芭月 涼が主人公なら、日本からスタートしないとダメじゃないか?」という話になり、1年で横須賀を作り上げたんです。
――そう思うとすごいですよね。実質1年でわーっと作り上げたわけですか。
岡安
懐かしいなあ。当時としては珍しくフルボイス対応にもこだわっていました。音声データも膨大になるので、ディスクが何枚組になるか試算したんですよ。
そしたら裕さんが「岡安、全部入れるとディスク16枚組になるらしいんだけど、16枚ってゲームとしてありかな?」って聞かれて(笑)。「絶対に無理です!」と答えた覚えがあります。
平井
サターン版の開発もかなり長くやっていましたね。2年半か3年くらいはサターン版を模索していたんじゃなかったかな。孟村とか作ってね。もちろんスペックがかなりきびしくて、その後ドリームキャストで作るということになりましたが、音声データも軽量化のために、かなり音質を下げていますよね。それでもディスク容量が足りなくて、4枚組のうちゲームディスク3枚になりましたが。
ディスクの話で思い出すのは、当時ドリームキャストに使われていたのはGD-ROMでしたが、あれって読み込みのために少し回したら、一回止めて、つぎに読み込むまで一定時間止めてください、というレギュレーションがソフト開発者には課せられていたんですね。だけど『シェンムー』だけは例外で、“インフィニット”って言ってずっと円盤回し続けていたんですよ。その方がシークがほとんどいらなくて読み込みが早くなるんです。
街なかで人物の読み込みとかをずっとするので、ほかの会社には許していないインフィニットで、回し続けていました。だから『シェンムー』を遊んだらハードへのダメージはほかのゲームを遊ぶより強かったかもしれません。
『シェンムー』を遊ぶときは、GD-ROMがずーっと回っていました……最高速で……。
――(笑)。
岡安
ちなみにみんな『シェンムー』は発売後に最後まで遊んだの? 俺は逗子でも、デバッグで散々やったからもういいかなって。
平井
僕はやりましたよ、時間切れのゲームオーバーになるまでやりました(※)。
※時間切れ……『シェンムー 一章 横須賀』では、エンディングまで進めずに1988年4月15日まで遊ぶとゲームオーバーとなる。岡安
それは仕事でやったんじゃないの。
平井
仕事でもやったんですけど、製品版でも一応やりました。ふつうにクリアーするぶんにはできるのはわかっていたので、イレギュラーなゲームオーバーも製品版でできるかなと。開発中はデバッグモードがあったので時間がすごく早く進められるんですけど、製品版はそれがないからたいへんでしたよ。
岡安
1日1時間だからね。
和田
ちなみにいまはわかりませんが、当時の裕さんって、本当にマジメに真剣にゲーム作りに臨んでいる方で、冗談は通じないタイプの方だったんですよ。
――へーっ。
和田
ですから、プログラマーがふざけて入れたりする要素は、絶対に許しませんし、本気で怒られました。
当時チームには3Dの“揺れもの”ができる人プログラマーが僕しかいなくて。髪や衣装が揺れる動き、たとえばシェンファの三つ編みの動きみたいなものを作りました。
そもそも僕が合流したときって当初、女性キャラクターの鳥隼を担当していたんですよ。彼女が本格的に登場したのは『シェンムーIII』からですが。まあ鳥隼はもとからセクシーな女性で、デザイナーチームにもセクシー好きの担当がいて、鳥隼や秀英の胸に「骨(※)入れっから、あとはよろしく!」と、ようは“乳揺れ”のプログラムを要求されたんですね。
※骨……ボーン。ポリゴンを作る際の動かせる部分。 それで仕込んでいたら裕さんにバレて、とんでもない大目玉を食らって。「このゲームはそういうゲームじゃないんだ!」と激怒されちゃって。『シェンムー』では一律“乳揺れ”は禁止になりました。
松田
そんな話ありましたね(笑)。
笠原
怒られたと言えば、いまだから言える話なんですが、四神獣が『シェンムー』には出てきます。それの名前を決めなくてはならない会議が長時間続いたんです。そこでシナリオライターのひとりが、一般的な四神獣の名前、朱雀、白虎、玄武、青龍を提案したんです。裕さんは「この名前、すごくいいね!」と、これをたいへん気に入っていたんですね。私は「ほかのゲームに出ているのでヤバイですよ」ってシナリオライターに伝えたのですが……。
その後、いい命名ができたと上機嫌の裕さんが飲みに行くというので私も同行することになったのですが、そこで悲劇が起きました。裕さんが店の子に四神獣のことを話し出したんです。「この名前すごいだろ、青龍とか朱雀とか、いま作っているゲームのボスの名前なんだよ」って自慢し始めて。するとその子から「その名前知ってる、『ペルソナ』で見た!」って言われて(笑)。
そうしたら裕さんはすぐに帰り支度を始め、入店10分でお店を出てタクシーに乗せられ帰らされました……翌朝、裕さんの部屋に呼ばれ、やはりというか私が怒られまして、名前案も却下され、けっきょく命名し直しとなりました。「やっぱり、こうなるやん……」って。貧乏くじを引く役割ではありましたね(笑)。
速攻で羽田図書館へ行って四神獣について調べまくりました。そこでわかったのが、青龍や朱雀にはさらに古い名前があったんです。それが蒼龍、鳥隼といった四神獣の旧名で、それでOKをもらい、何とかかんとか切り抜けたのをよく覚えています。
――転んでもただでは起きないというか、災い転じて福となすということで!(笑)
開発者たちの岐路となった『シェンムー』
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4053d78e3e03064ed90e22bea6eefb95.jpg?x=767)
岡安
『シェンムー』開発に関わって人生が変わったという人は多かったと思うんですよ。
――多くのスタッフが関わる本作でしたが、その人の出入りの多さを皆さんどう見ていたのでしょうか。
岡安
いやもうとにかく人材を入れろ、とにかく人海戦術で、といった手法だったので、正直できるスタッフもいれば、まったく役に立たないスタッフもいました。
笠原
プログラマーとして入ってきたのに、プログラマーじゃないんですよ。プログラムを組んだことがない人まで入っていたので、もう本当にメチャクチャでした。その“人をさらってくる”仕事をする人もいたんですよね。そういう人はスタッフを入れることがノルマですから、人を連れてきたらそれで自分の仕事は終了するんですよ。
――あああ。人事採用も含めたすべてのシステムが未整備で、個々の仕事をこなすことがトータルの成果につながらないという状況……。
松田
それで現場はたいへんになるんですよね。
岡安
松田は「『シェンムー』のチームに入れ」、ってシェンムー狩りにあったとき最初どう思った?
松田
いやもう、チームに入るか否かの決定権もなかったですよ。有無を言わさなかったですね。新卒で入って初めての夏休みの前だったのをよく覚えています。
『シェンムー』チームに入る前は、あーAM2研の仕事ってハードだな、さすがだな、と思っていて、よし、1回夏休みでリフレッシュだ! と考えていたら上司に呼び出されました。当時の上司から「松田ァ、『シェンムー』ってゲームがあってな、人手が足りない。松田ァ、お前の力が役に立つときが来た。デザイナーとして成長したいだろ?(渋い声真似で)」と言われまして。「はい!」と答えた瞬間、僕の夏休みはなくなりました。
一同 (笑)。
笠原
声真似が若干似てるなあ(笑)。
松田
そこからは即『シェンムー』開発メンバーでしたね。いまでは2~3週間で作るキャラモデル作業を、3日くらいで作る過酷な現場でした。上司の言う通りデザイナーとしての成長にはつながったと思います(笑)。
和田
ちょうどそのころ、プログラマーも追加で入ったりして、どんどんスタッフが増えてきましたね。
岡安
また、『スーパーモンキーボール』などの名越さん(名越稔洋氏。元セガで、現名越スタジオ代表取締役)は当時、アミューズメントヴィジョンって開発子会社にいて、そこからもスタッフが合流したりしていましたね。
――へえ。
岡安
そうして人を山程集めて作った開発も、終盤になって終わらせなければならなくなっていきます。でも裕さんは、「もっとよくできる!」とこだわるタイプなので、どんどんアイデアを出すのですけど、「何もしないでください!」と僕も引き止めていました。
和田
ああ、『シェンムーII』の開発ラストを思い出しました。もう開発が終了し、マスターアップ用のROMを焼いている最中に、夜中に裕さんから連絡が来て「ここさぁ、こうしたいんだけど……」って相談が飛んできて(笑)。「何言ってんですか、いまもうマスターROM焼いているところですよ!」って止めたりして。もう終わらせればいいのにって瞬間に……。
岡安
終わらせればいいんだけど、裕さんは何かしたい人なんだよね。本当に最後までおもしろさのために粘る。
平井
ちなみに『シェンムーII』だけじゃなくて、『一章』でも同じことがありました(笑)。
岡安
『III』でもあったから(笑)。
宮脇
けっきょく裕さんの話にはなるのですが、裕さんのために集められた人材なんですよね。立場的には裕さんという魔王を倒すために集められた、兵士のような。裕さんが悪じゃないですけど(笑)。クリアーするために現場のスタッフたちはとくに団結していたように思います。
平井
先ほど笠原さんと岡安さんが防波堤になってくれていたと言いましたが、飲み会や麻雀のときに裕さんから「平井ちょっとやりたいことがあるんだけど……」と言われることはしばしばあって、僕は飲み会に行くたびに「仕事が増えるんだな」とは思っていました(笑)。
松田
いやあもう、関わった人数が本当に多いので、いろいろなところに散らばっていきましたね。中には本当に関わっていたのか怪しいレベルの人までいるんですが(笑)。
宮脇
ゲーム問わずいろいろな分野の業界に行きましたが、“自称『シェンムー』スタッフ”、“エセ『シェンムー』開発者”にはたくさん会いましたよ(笑)。
平井
いた! 僕、「じつは『シェンムー』のメインプログラマーを担当していました」って人、過去に4人も会ったことがある。「それ俺のはずなんだけどな……」って内心思いながら(笑)。
松田
平井さんにそれ言うのはヤバいですね(笑)。
平井
すっとぼけて「へえーすごいですね、あのゲームってどうやって作ったんですか?」とか聞くんですけど(笑)。和田さんが言うならわかりますよ? でもぜんぜん知らない人でした。
宮脇
僕も『シェンムー』のキャラクターデザインを担当していたという人に会いましたが、その人は実際には表示系で少し関わっただけで、一瞬で消えた人でしたね。
笠原
そういうのが本当に多いんですよ! ですから、誰かのところにそういう人が現れると、僕らのネットワークで「『シェンムー』の開発やってたって言う人がいるんだけど、本当にいた?」みたいな確認が来がちで。
――そんなに“エセ『シェンムー』スタッフ”は業界内にいる……と。
和田
ゲーム的な部分は別として、技術者としてはドリームキャストであれだけのゲームを作れた人たちなんていないんですよ、日本中のどこを見わたしても。あのハードであれだけの描写というのは……。そこに「関わっていました」と言えば、ゲーム業界なら確実に仕事があると思います。
岡安
実際、『シェンムー』開発スタッフは優秀な人が多かったんですよ。私は『シェンムーIII』の開発にも携わりましたが、『シェンムーI』、『II』と同じ感覚で人を集めようとしても、なかなかああいう優秀なスタッフは集まらないんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a661b21b2acb1529219fd3ce062db6a6c.JPG?x=767)
――『シェンムー』はオープンワールドゲームの先駆けと語られるほど、ゲーム技術の革新的な要素がたくさんあると言われています。そう感じている部分はありますか?
平井
QTEとかはわかりやすいですよね。仕様自体は昔のLDゲーム時代にもあったのですが、それを現代風にというかムービーシーン中やアクションシーン中に入れ込んで緊張感を保つというのはその後多くのゲームに取り入れられていますし。
黒岡
技術的にはキャラクターの口パクもですよね。当時3Dでは初めて“クリッパー”という音声データの「あいうえお」に合わせて、唇の形が動く技術をゲームに取り入れていて。その技術はその後“リップシンク”と名を変え、ほかのゲームにも伝わっていったと聞いています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/affd4026026e3b0f3f5dcf617d4342c43.JPG?x=767)
和田
いまとなっては当たり前の技術かもしれないのですが、当時はほとんどありませんでしたから。小さいのから大きいのまで3段階の開きかたがあったり、より人間に近い動きをしていたんですよ。
平井
当時も口パク自体はあったんです。ただ当時として画期的だったのは、“ま行”になったら、一度唇を閉じてから発音するっていうのがリアリティーになるんです。これはすごいなと……まあ、このアドバイスしたのは僕なんですけど。
岡安
また自分の手柄に持ってく(笑)。
――25年前に実装されていたということを思うとすごいですよね。どこまで遡れるのかわからないですけど、3D表現のゲームにおける汎用性のあるリップシンクシステムとしては初という可能性は高いのではないでしょうか。
平井
そう言えば、じつはプレイステーション2版『一章』を一度作ったことがあるんです。リリースはされていませんが、内部的にはプレイステーション2で動く『一章』があったんですよ。Xbox版も作りましたが、北米で『シェンムーII』のみが発売されましたね。
――えっ、『シェンムー』にPS2版があったのですか!?
和田
発売にはいたりませんでしたが、移植はできていました。
平井
アセンブラで作っていたソースも直して。Cに戻すのたいへんだったんですよ。
和田
あと、移植の話では、Xbox版も『一章』は発売されませんでしたよね。技術的な問題ではなく、権利的な問題だったんだと思います。ほら、TIMEXの腕時計とかコカ・コーラ社のドリンクとか、実在の企業とタイアップしていたんですよね。その契約が、ドリームキャスト版『一章』のみの契約だったので、他機種版では使えないなどの理由でお蔵入りになったんじゃないでしょうか。
――PS2版は実際に遊べるくらいのものだったのでしょうか?
平井
動きましたね。グラフィックの仕組みも変えて、しっかり全部遊べるものでした。
和田
ドリームキャストはシェーダーが固定で、プレイステーション2はプログラムでシェーダーに対応しなくてはならなくて。プレイステーション2とドリームキャストではGPUがぜんぜん違う発想なので、そこも作り変えて搭載しました。ゲーム的には発売しようと思えば、行けましたよね。
――ほおお……。
さらに広くなった『シェンムーII』開発
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9bb3a0e742e52ba333de0749f1e20b4b.jpg?x=767)
――ここまでは基本的に『一章』のお話だったかと思いますが、『II』の開発苦労話はありますか?
平井
『II』はシステムプログラムは僕が全部制作しました。ただほかのゲーム部分は、ほぼ和田さんが作っていましたね。
和田
もともと『一章』は、日本の街並みですし、表示させる人間もそこまで必要とせず、すぐ曲がり角曲がり角で、狭い街ですから遠くまで描画する必要はありませんでした。ですが『II』はかなり大きな香港が舞台となり、遠くまで見える。つまり表示させる一般人をもっと増やさなくてはならなくて、大きな街を表現するために遠くも描画する必要がありました。
そうなったときに、絶対に『一章』のシステムでは絶対に不可能です。平井くんや技術スタッフたちと相談して、けっきょくのところイチから作り直す必要がありました。
平井
スクリプトもエンジンも、Cの構文解析ももうほとんど全部変えましたね。そのとき僕は『スペースチャンネル5 Part2』に関わって、ことあるごとに困ったことが起きたら、『シェンムーII』にちょくちょく戻っていました。
――水口哲也さんの渋谷のオフィスに行かれていたんですね。だけど『シェンムーII』開発で何か行き詰まると……。
平井
羽田に呼び戻される(笑)。レガシィな作りかたをしていましたねえ。笠原さんと僕はAM2研に入ったときは、給料めっちゃ安かったよね!?
笠原
うん!?
平井
最安値ふたり組くらいだったと思うんですけど、ある程度開発が進んだタイミングで岡安さんに直談判して上げてもらったんだよ。
笠原
いっしょに話をしにいった記憶はある(笑)。
平井
だから僕は『シェンムー』開発中に給料3倍くらいになりましたよ。
一同 おお~。
笠原
私はなってない、3倍になんかなっていませんよ!(笑) 岡安さん!!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9d535f6f5dcb5bc7fd2e0d9d71a937ba.JPG?x=767)
岡安
しょうがないじゃん、あのころチャラチャラしてたんだよ。髪の色も紫だったりして。
笠原
チャラチャラはしてないですよ(笑)。
宮脇
なんとかとかいうチームで、岡山で笠原と言ったら知らない人はいないと……。
――そんな笠原伝説が!(笑) また、岡安さんや宮脇さんは『III』の製作にも関わっています。どのような経緯で再び裕さんと組むことになったのでしょうか?
岡安
僕は、僕のほうから声掛けをしたんです。外から見ていたらとてもたいへんそうに見えたので「もしアレだったらお手伝いしましょうか?」と電話したら、「明日から来てくれ!」と(笑)。まあ即日は無理なのでしっかり話し合いをして契約を結んでから、参加しました。
宮脇
僕は裕さんからお声掛けいただき、そのとき別のゲーム会社で仕事をしてたので「あまり深くは関われませんよ」と断りを入れつつ、週1程度で見たりしていました。
岡安
当時はたいへんでしたが、逆にいまの立場で裕さんと関わることになったら、どうなるのだろうかといった興味がありました。当時は上司と部下の関係でしたが、会社と会社の付き合いですから、横の関係性になって、昔よりも言いたいことを言えるようになりました。でも裕さんは昔と変わらず気安い感じで(笑)。
平井
裕さんはとりあえず岡安さんに相談したいんですよ。
岡安
裕さんって、自分がこうだと思っていることに関してはすごく自信があるんですね。そうじゃない部分は折れるというか、わりと素直にほかに意見を求めたりするんです。だけど、同じ相談しているようでも、自信があるときは「岡安、そうだよな?」と、同意を求めているなこれは、ということもよくありましたね(笑)。
黒岡
なんかそのフレーズよく聞いた気がします(笑)。
もしも『シェンムーIV』を作るなら……?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/cd990dd9fd04be1ee8c35b88399593b16.jpg?x=767)
――仮に“シェンムーIV”を作ることになったら、皆さん関わりたいと思いますか?
一同 ……。
――急に無言にならないで!(笑)
松田
物語を最後まで世に出したい、出してほしいとは思いますよね。当時入社したスタッフは、オフィスに裕さんの秘密部屋みたいのがあって、そこに連れていかれて『シェンムー』の全章がアートとテキストで、全物語を読むことができたんです。最初にそのイニシエーション(洗礼)を受けるんですよ。ですから、知っているスタッフは多いと思いますね。
宮脇
シナリオも何版もあるので、当時とは変わっているかもしれませんが。でも、もしつぎがあるのならば、本当に最後まで作り切る目算を立ててほしいですね。
笠原
セガの人間なのに適当なことを言いますと(笑)、龍が如くスタジオが作るのならば、ものごっついシェンムーができると思いますよ(笑)。
――なるほど!?
岡安
僕は『シェンムー』開発当時、開発中にもうさんざん遊び続けてきたので、発売後は1回も遊んだことがないんですよ。そんな状態で、『III』の開発に入ったとき、スタッフは『シェンムー』好きがすごく多かったんです。それは日本人スタッフのみならず海外の人も含めても。そのとき、「ああ、こんなに『シェンムー』って評価が高いんだ」と初めて知ったといいますか。中のスタッフからすると、しんどい思い出ばっかりでわからないんですけど(笑)。
ちなみに『III』も、最後の最後まで作り込む裕さんのスタイルは変わりませんでした。開発が終わってもまだ改善しようとしていたのは『III』も同じでしたね。
平井
純粋に、最後の最後までよくしたいという方ですよね。
岡安
『シェンムーIII』開発の後半になると「笠原がいればなあ」って裕さんも言ってましたよ。
笠原
いやいやいや、言ってないでしょう(笑)。
岡安
前半は言ってなかった、後半は言ってた(笑)。やっぱり後半のほうが開発しんどくなって行くんでね。
松田
裕さんに「こういう風にして」と言われてなんとか実現させて完成度が上がったものを見せてみると、つぎは「これができるなら、つまりもっとこういう風にできるよね?」となって、仕事をひとつ達成するたびになぜか仕事が増えていくんですよ(笑)。
平井
毎週毎週、高速化してたなあ……。
岡安
いま思うとああいう作りかたさせてくれていたセガってすごい会社だなあと思いますね。
平井
僕は楽しかったですよ。
岡安
なんで平井はそんないい人になろうとするの?
平井
いやいやいや(笑)。最後の最後までクリエイティブで、課題があって作り込めるというのはプログラマーとしては楽しいんですよ。「デバッグだからもうコーディング書くな」とは言われなかったのでね。
それぞれの『シェンムー』とは?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a16c854e426707369c8ef4bc5ac5a16b6.jpg?x=767)
――そろそろシメに差し掛かるといったところで、芭月涼役の松風雅也さんよりコメントをいただいていますので、発表させてください。
松風雅也さん 25周年コメント
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a791eeabc1d1fea479d2a57bef48f98fe.jpg?x=767)
『シェンムー』にまつわる思い出が多すぎてどうしようかなと悩んでしまいますが……。
まずはオーディションのお話。オーディションには極秘でたくさんの人が参加しており「守秘義務の書類に押すためのハンコ持参、なければ帰ってもらう」と言われたのが印象的でした。不思議に思いながらも「忘れたら落ちるどころか受けられないって間抜けすぎるから、ハンコだけは忘れないようにしよう」と確認したのを覚えています。奇跡的に私はオーディションを通るわけですがその合格理由は、「たいへんな制作現場になることはわかっていたので、頑丈そうで性格のよさそうな奴」といった理由だったそうです。
それから何年か経って、発表会がバシィフィコ横浜で開催されました! 数年間、守秘義務を守り、極秘の施設で親にも言わずに作ってきた『シェンムー』。大きな舞台に上がるにあたり、事前衣装チェックで問題が発覚します。それは、「松風の衣装がダサい」と。急遽、前日の夜に、東京の百貨店で衣装を購入しに行くことに! 前日ではサイズ直しをする時間もなく、少しサイズが合っていなかったのもひとつ思い出です。
モーションキャプチャーの楽屋では、、俳優の蛍雪次郎さんに「松風くんまだ若いよね。若いうちは何でもやった方がいい、そのうちやりたくないものを増やしていくと、やるべき道が見えてくるから」というお言葉をいただきました。私はあの日以来その言葉を実行しています。鈴木裕さん、藤岡弘、さんにいただいた言葉も宝物ですしシェンムーで出会った方々の影響を強く受けていまにいたります。
中止に復活。「『II』でシリーズはいったん中止」と言われたときは、心臓が止まるほどショックでした。すでにかなり先までモーションキャプチャーは収録してるのに……と。そして10数年ぶりに「続編を作る!」と聞いたときも言葉にできないサプライズでした……! その後のアニメ化でしたり、『シェンムー』は本当に何が起こるかわからないおもしろさがあります。と、話し始めると本当にキリがないですね。
そういえば最近趣味で涼の革ジャン作りました!
笠原
松風さん、ありがとうございました。いいですね、涼の革ジャン。そういえば今日、和田は涼の革ジャンを着ているよね?
和田
会社で作ったものですね。定年祝いのひとつとしてもらったものです。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4f997074ed7eacf91a8d308b4fe408b0.jpg?x=767)
笠原
これは本物の革で作られた、1着しかないものですよ! フリマアプリに出しちゃダメですよ! 『シェンムーIV』の発表会で松風さんに着てもらいますから!!
――それでは最後の質問ですが、『シェンムー』は皆さんにとって、どのような存在でしたか?
平井
『シェンムー』は本当に僕の大事な1ページです。これがなかったら、周囲から信頼してもらえるエンジニアにはなれなかったと思います。関わっていなかったら、単なるプログラマー人生で終わっていたかもしれません。いま会社を興して、仕事もたくさんできるようになったのは『シェンムー』があったからだと思います。実際に、いま当時『シェンムー』開発をしていた人とプロジェクトを進めたりしています。
――おお、『シェンムー』の絆で!
平井
あ、『シェンムーIV』ではないですよ(笑)。30年間プログラマーとして関わってきて、これ以上の作品はないと思いますし、いまでもやっぱり“シェンムー平井”と呼ばれたりするほど、自分のパーソナリティになりました。あの4年間は、僕にとっては本当に青春だったと思います。
和田
僕にとっての『シェンムー』というのは、本当に難しい質問ですね。とにかくこのゲームを世に送り出そうと、それだけを一念に考えて仕事していました。裕さんの夢想家の部分を、僕は尊敬しています。あそこまで本当に最後までいいものを作りたいという、その信念はものすごいです。
僕はあくまでクリエイターではなくビルダーなので、裕さんの願いを叶えるためにただただ作り続けていた、それが僕にとっての『シェンムー』です。
黒岡
僕は当時からセガの人間ではない中、20代前半の2年間関わらせてもらって、開発者としての最初の試練だったように思います。開発者の人数もすごかったですし、ずっと泊まり込んで開発して、精神的にタフになったように思います。
“虎の穴”に入れられて、無理やり鍛えられた結果、その後どんなことがあっても「『シェンムー』に比べたら」と、耐えられるようになりました。
松田
『シェンムー』は僕にとって、ゲーム制作や会社経営においての羅針盤のような存在です。皆さんが今回語ったように、『シェンムー』は“中身が固まってないけれども、目標だけはみんな共有されている”ゲームでした。仕様がないのに、おもしろいゲームを作らないといけないクリエイターって、どう立ち回らないといけないのかを知ることができました。
僕は独立し、自分でゲームを作るときに“企画が決まっていなくても、人が集まればゲームは作れる”というのは、勘違いだとわかりました。本当に『シェンムー』開発は天才が揃っていた現場だったんです。ゲームをお客さんに楽しんでもらうための方法を、『シェンムー』に全部教えてもらったと思っています。
宮脇
僕はシンプルに、自分のチャンスをいただけたのが『シェンムー』でした。漫画家を目指していただけの人間が、いきなりものすごい環境に放り込まれたと言いますか。多業種の人が関わっていたからこそ、いろいろな人と知り合うことができて、学ばせていただいたものもあります。
いまはフリーランスですが、いまもゲーム制作に関わっていますし、そのとき知り合ったアニメ監督さんとアニメ制作に関わったりもしています。自分の好きなことをいまも仕事として続けられているのは、『シェンムー』のおかげです。
笠原
いちばんつらいプロジェクトでしたが、いちばん思い出も深いです。たくさんの戦友たちといっしょに死線をくぐり抜けたのが『シェンムー』です。この絆は、スタッフたちが在籍する会社が変わった後でも、ずっとつながったままでしょう。
鈴木裕さんという、天才の仕事を間近で見ることができた現場でした。いま思い返しても「すごいな!」と思うことがたくさんありました。当時作りながらではわからない部分も多かったですが、2018年に発売した『シェンムーI&II』を移植したときに「あれ、このゲームすごくない!?」と改めて思えました。
開発当時はみんな若くて、開発スタッフの多くは20代でしたからね。よく作れたなと。裕さんも30何歳で。
宮脇
僕、当時のドキュメンタリーの録画データを持ってきたんですけど、やっぱりみんな若いんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/aefc2bcfd7906a651432e2d6c99ab5316.jpg?x=767)
一同 おお、若い。懐かしい。岡安さんそんなかわらないなあ……。お、これ僕です……
平井
ああ自転車だ。このプログラムも作ったんですよ。
松田
自転車のループモーション作った気がするなあ。
――それでは最後に、岡安さんにとってシェンムーとは。
岡安
間違いなく人生が変わったタイトルです。裕さんと長く仕事をしていますが、裕さんの考えたかたがいちばんわかったのが、『シェンムー』でしたね。この話を皆さんにしていいものか迷うところなのですが、裕さんから『III』制作時に「俺がもしあの世に行ったら、お前が『シェンムー』を完結させろ」みたいなことを言われたことがあって。
一同 おおおお。
松田
後継者指名ですか?
岡安
ある意味では後継者としての指名なのかもしれないですが、そのとき僕はYESともNOとも言ってないんですよ。気軽に言えるわけもないですし(苦笑)。
『シェンムー』の開発は辛かったんですけど、のちにオープンワールドゲームが流行ったときに「ああ、裕さんの見ていた景色はこれだったのか」とわかるんですよ。ですから、裕さんのやりたかったことは当時はわからなかったけどいまはわかる、正解だったわけですよね。まあ、後継者になるかどうかは別ですし今後の展開はわかりませんが、とにかく個人的には『シェンムー』の物語は完結させてほしいですね。
平井
岡安さんがやるなら僕もやりますよ。
笠原
なら僕も。
松田
ダチョウ倶楽部みたいになってきた(笑)。
岡安
どうぞどうぞ……。
一同 (笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9e4e3f8a285308028ad7b66e1b194b77.jpg?x=767)
~完~
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/abb91a98e9e575757490b36a2b6388d60.jpg?x=767) ※本記事では『シェンムー 一章 横須賀』を『一章』または『I』、『シェンムーII』を『II』と表記する場合があります
※本記事では『シェンムー 一章 横須賀』を『一章』または『I』、『シェンムーII』を『II』と表記する場合があります![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9ba96b4801ef7ee4fbd5b6c1dca1aaba.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a7ff0e638cbaca73da5f854d82cee5adc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/addc4f72e86589a99337e4ec6c737fc47.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a7226a177be9d417f7028ff4ac53b2d5f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9a859bf779cc1a142000ea3dbdf5dfd9.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9156feef718f6780a4556e218c441ec5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a3e3bbe134c4b6e11446281d76550f7b5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a05fd0e805476516948a712b8a8c1bb3f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a949cde8a20faa473af9ac99186d7aeef.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a024d5ae83c40fe708327987e8858bded.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a0b8e3df37b6375b6e90a08f5dd4662ce.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/ad38c6f43953342d6c1f722b444cddc5e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/aec30f6ed50a7283a3d137f421028919b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a1bc0f9034ce9daa8ae80b054421b049a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a2712082f21ce7849c6323b5f7aee3c7a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/b4b572ef0fb0adbc303c3a2ada32b91a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/ad008dd08315b2fa36bd7df6f803ece50.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4fb14ef374284531c35eba42579ea592.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a886358b0c76b3c22302a1eebda4371f7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/c022a38c6740f8aa840eac0880612fbaf.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9376f3e00dfa26a0f591af56d6003f61.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4421bdb81fbf12e9bc1eba276e1c2c00.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a86a01576be85b6f0169b517804d28334.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4053d78e3e03064ed90e22bea6eefb95.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9bb3a0e742e52ba333de0749f1e20b4b.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/cd990dd9fd04be1ee8c35b88399593b16.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a16c854e426707369c8ef4bc5ac5a16b6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a791eeabc1d1fea479d2a57bef48f98fe.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a4f997074ed7eacf91a8d308b4fe408b0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/aefc2bcfd7906a651432e2d6c99ab5316.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29221/a9e4e3f8a285308028ad7b66e1b194b77.jpg?x=767)