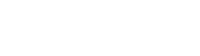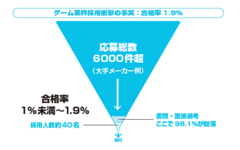本稿の主旨は以上となる。『シェンムー』についてただ語る。
今日で『シェンムー』発売からめでたくも四半世紀が経って、『シェンムー』について詳しく知らない、まったく知らない若い読者も多いことだろうと思う。
また、ゲーム概要やストーリーについては現在でも検索すればある程度ヒットするけど、当時の空気感であるとかゲーム業界全体の流れみたいなものがあまり記録されていない気がする。この機会に、“『シェンムー』とは何か”ということについて語るのがいいだろうと思ったからだ。
書いているのは2018年に“2代目シェンムーリスペクトチャンピオン”なる名誉称号を手に入れたファミ通.com編集者の堅田ヒカル。発売当時は中学生でドリームキャストを手に入れたばかり。ハイグラフィックとインターネットの未来性に頭がクラクラするほどの衝撃を受けつつ遊んでいた。
本稿では、そんな当時のプレイヤーがどのような気持ちで『シェンムー』を待ちわび、遊び、なぜ“伝説”と語られるようになったのか紐解いていきたい。
書き出しながら「シェンムーおじさんの思い出語りという原稿になりそうだなあ!」という気がのっけからビンビンするけど、ま、年末の余暇に、のんびりお付き合いください。
- シェンムーとは
- 総製作費70億円
- 本題:で、『シェンムー』ってどういうゲームだったのよ
- リアリティーにこだわりすぎた街並み。それは“バーチャタウン”
- リアリティーにこだわりすぎたシステム
- 先進的過ぎたインターネット要素
- 声優がモーションキャプチャーする意味とは
- リアルにこだわりすぎない遊び心
- ストーリー 少年の成長×武道(武術)×旅×超常的な……?
- 奇跡の『シェンムーIII』発売。『IV』はまだか
- まとめ:なぜ『シェンムー』は“唯一無二”で伝説なのか
- 余談
シェンムーとは
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a2eb69e358390f85a0fb43b08edb7fa58.jpg?x=767)
ドリームキャストのキラータイトル
セガ最後のハード、ドリームキャスト
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/aae872dd2abacb9374461f2b8d4d6aef2.jpg?x=767)
“セガは、倒れたままなのか?”。
1998年5月21日、刺激的なコピーが新聞各紙に踊った。背景には、刀折れ矢尽きた戦国時代の足軽兵たち。セガロゴの幟が破れている。A2サイズの新聞1ページをまるまる使った全面広告は、荒い白黒写真があたかも黒澤映画のワンカットのようだった。ゲームメーカーの広告としてはかなり型破りなものだ。
各プラットフォームのシェア争いが“ゲームハード戦争”と呼ばれ、多くの注目を集めていた時期、プレイステーションの後塵を拝する形となっていたセガサターンを念頭に起きながら、自虐的な新聞広告を打った。隅にこうも書き添えてある。“明日の広告に続く”。
そして翌5月22日、再び全面広告が掲載された。
“11月X日 逆襲へ、Dreamcast”。
この瞬間、噂されていたセガの新ハード、コードネーム“KATANA”の正式名称であるドリームキャストの名前とそのロゴが発表されたのだ。そこから約半年後の1998年11月27日、ドリームキャストは発売された(【余談1】)。
そのドリームキャストは、あらゆる面でこれまでのハードとは一線を画していた。高性能な演算能力はもとより、白くコンパクトな本体デザイン、液晶画面を搭載しそれだけでゲーム機になるビジュアルメモリ、そして何より通信用モデムを標準搭載し電話線を差し込めばそのままインターネットにつながるという仕様(※)。
初めての体験。初めてのインターネット。当時、企業も個人もホームページを制作し始めている時代で、あれこれとURLを直打ちしながら閲覧した記憶がある。家庭にそこまでPCが普及していない時代、「ドリームキャストで初めてインターネットを楽しんだ」という人もじつはけっこう多いんじゃないだろうか。(【余談2】)
そんなドリームキャストは、湯川専務が出演した広告の話題性も相まって国内発売開始から売上はよく、売れて売れて、チップが足りずに本体が製造できないというくらい売れた。
売れた……のだけど、大きな問題を抱えていた。それはソフトラインアップだ。本体と同時発売のローンチソフトはわずか4本。もっとも強力なのは『バーチャファイター3tb』で30万本弱を売り上げた。ソニックシリーズ初の3D作品となる『ソニックアドベンチャー』の発売までは約1ヵ月を待たねばならず、その後もアーケードゲームからの移植作はあるものの、「これぞ!」という大型タイトルがなかなか出てこない。
「このソフトがやりたいからそのハードを買うのだ、買うしかない」という1本、つまり、キラータイトルの登場が待ち望まれていた。
ドリームキャストユーザーは1本のソフトを待ち望んでいた。『バーチャファイター3tb』に同梱された特典ビデオディスク“プロジェクト バークレイ”。別のゲームに新作のプロモーションビデオがわざわざディスクとして同梱されていたのだった。鈴木裕とAM2研が開発する、RPGと噂されていた。ビデオではRPGではなく“FREE”という呼称が大写しにされた。Full Reactive Eyes Entertainment。鈴木裕が語る構想は新時代の到来、その宣言のようでもあった。
キラータイトル
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a962774952d5ad7ca957db60ea6fee61b.jpg?x=767)
RPG的な『シェンムー』が作られた背景にはそういった要請もあったろうと思う。高性能な新ハードでしか味わえない、物語性の強いゲーム。手掛けるのは、『ハングオン』、『バーチャレーシング』、『バーチャファイター』の鈴木裕であり、AM2研だ。
『シェンムー』はドリームキャストのキラータイトルである、キラータイトルとは他ハードで言えばプレイステーションでは『FFVII』のようなものである、つまり『シェンムー』発売はドリームキャストに『FFVII』が出るくらいのインパクトをもたらすはずだ! と、当時純真な中学生だった筆者は思った。子どもらしい短絡的直情的思考回路と言うほかないけれど、乾坤一擲、この1本がドリームキャストに福音をもたらすのだと、それほどに期待値が高かったことは間違いない。
鈴木裕が初めて家庭用ゲーム機向けタイトルを、ドリームキャストに向けて作る。それはキラータイトルにならなければいけない。『シェンムー』はドリームキャストの命運を背負い、セガ・エンタープライゼスの社運を懸けて開発された。
ドリームキャストの行く末も、会社の業績も、セガファンの想いも『シェンムー』が背負っていた。
総製作費70億円
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/04b7a0dac4f1428bad4bb67d180fc704.jpg?x=767)
当初、セガサターン向けに開発されていたが、性能や規模の問題で実現せず、「これを新ハードで出そう、ドリームキャスト向けに作り直そう」と決定された。必然的に開発は大規模なものとなる。
人員も開発期間もほかに例がないほど、開発規模は巨大化した。一説には、関わったスタッフ300名超、内訳の正確なところはわからないが、総製作費70億円。その金額はもっともゲーム制作に使われた最高額として当時のギネスブックに記録され、テレビCMでも大々的にアピールされた。
とくにAAA(トリプルエー)タイトルの開発においては、現代でこそその何倍も掛けて制作される作品は多くあるが、当時ゲーム開発において、70億円規模、またそれ以上の規模と予算で開発しようという発想も、それを実現できる会社も当時存在しなかったと断言してしまっていいのではないか、とも思う。セガだからできた作品であるし、鈴木裕とAM2研だからこそ実現できた作品だった。
逆に言えば、『シェンムー 一章 横須賀』は、AAAタイトルの嚆矢であり、その後のゲーム開発を予言する存在でもあったと言えるかもしれない。ハイクオリティー3Dマップを作り、キャラクターを多数作り、重厚なシナリオを用意し、フルボイスを収録すると、ゲーム開発はそのくらい費用と開発期間を必要とするものになる。ハードのスペックアップに応じて訪れる開発規模の巨大化。その流れを体現した原初のソフトだったのではないかと思う。開発面でも業界標準の、やはり10年先を行っていたのかもしれない。
小まとめ:ドリームキャストとシェンムー
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a650d5c114cb4d1fb9f7cdf6cb2959c88.jpg?x=767)
また、ユーザーの期待も“プロジェクトバークレイ”ビデオ映像で十分過ぎるほどに高められた。ドリームキャストファンは、キラータイトルを渇望していた。当初1999年春と発表された発売時期は、数度の延期を挟み冬まで伸び、1999年12月29日となった。ドリームキャストファンは、発売延期を重ねる『シェンムー』を待ち焦がれていた。
本題:で、『シェンムー』ってどういうゲームだったのよ
ジャンルはアクションアドベンチャー、かつ“FREE”
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a898f63c4bb31d67613de38e60fea22d9.jpg?x=767)
ゲーム進行はRPG的ではあるけど、数字として目に見えるステータスは存在せず、HPや技の威力なども玉の数やグラフで表現されるなどできるかぎりファジーな表現となっている。また、戦闘は『バーチャファイター』風の格闘アクションであり、カットシーン中にはQTEイベントなども発生することから、アクションアドベンチャーという表現が適しているだろう。
しかし、『シェンムー』を一般的なアクションアドベンチャーから一線を画すのは、“FREE”を自称するその部分に大きい。“FREE”にあり、ふつうのアクションアドベンチャーにはあまりないという部分を中心に、その特色を紹介していこう。
リアリティーにこだわりすぎた街並み。それは“バーチャタウン”
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/ad7b38e6935b3ed09a5ce46efa0ea0d07.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a466e0fbfc57aed899b40449b42410b08.jpg?x=767)
主人公はこの芭月涼だが、ゲームのもうひとつの主人公は3Dで精密に作り込まれた“街”である。
舞台は神奈川県・横須賀。“ドブ板”という実在の商店街をもとにした地名も登場し、魚屋や肉屋、スポーツショップに蕎麦屋に寿司屋に薬屋にピザ店など生活感溢れる店々が並ぶ。
3Dポリゴンで再現された昭和日本の街並みというだけで珍しく(これは当時だけではなく現在でも珍しいと思う)、筆者はそれだけで異常興奮してしまう。芭月家には巌の盆栽が並び、100人乗っても大丈夫そうな物置があり、庭の池には鯉が泳いでいる。駄菓子屋の玄関は木製の引き戸で、開けると「ガラガラ」という音がする。アパートの外階段を登ると「カンカン」と高く鳴り、寿司屋には新鮮なネタがガラス越しに並ぶ。中華料理屋には油煙でくすんだ短冊のメニュー書きが貼られており、蕎麦屋ではサラリーマンがそばを持ち上げてはすすっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a4f275d1d97c6a13cb45368a0e156e4fe.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a8b667c75d8874de4686871effef51626.jpg?x=767)
特筆すべきは、そのどれもが、ゲームプレイ・進行には直接寄与しないのだ。たとえば蕎麦屋があったとしても食事を摂ることで回復したりはせず、ただそこに存在するだけだ。
ゲーム進行に関係のない部分でも、世界はできる限り緻密に再現されている。たとえばゲーム開始直後は、巌の事件について何か知っている人がいないか探し回るのだけど、この際、プレイヤーはどこの誰に話しかけてもいい。道端でおしゃべりしているおばさんでもよければ、仕事をしている工事の人でもよく、そこらの家をノックしてもいい。ただし誰もが正解の情報を返してくれるとは限らない。不在ならば涼が「留守かな……」とつぶやく。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a064aa6d54241096dc65fe8047721ed47_au7OXaY.jpg?x=767)
町の住民も全員に名前と経歴、年齢や性格が設定され、それらの設定はゲーム内で会話にあらわれることもあればあらわれないこともある(大部分はあらわれない)。
ひとりひとり異なる顔と名前を持つ住民たちはそれぞれのスケジュールに沿って行動しており、たとえば学生や勤め人であれば平日は朝街なかを歩くけれど、休日は歩かない。全員がフルボイスでしゃべり、いつでも、誰にでも話し掛けることができる(とは言えご飯を食べているところに話し掛けると、「疲れてるんだ……またにしてくれよ……」と、寸時の会話すら断るサラリーマンが非常に多かったりするけれど、それはまあ、ご愛嬌というものだろう。24時間戦うことを求められた昭和のサラリーマンのつかの間の休息を邪魔する涼が悪い)。
とにかく生活感がすごい。ドブ板で表現された日本の街のリアリティーは、現在においても最高と言えるレベルにある。筆者のような“生活感萌え”なプレイヤーにはたまらないものとなっていた(【余談4】)。
また、この異常なまでのこだわりは街や住民のビジュアルだけではなく、システム面にも現れている。
リアリティーにこだわりすぎたシステム
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/ac4b58916baddf6c3dbdfe09fba5b9133.jpg?x=767)
代表的なものは芭月家にあるミカンで、ミカンを持って、ためすがめつ眺めることができる。そのほか、仏壇の近くにはマッチがあったりロウソクがある。引き出しは開けられるし、額縁は取り外したりできる。電気のひもを引っ張れば電気が消える。
ゲーム進行には大きくかかわらない小物でもきちんと作り込むこと。手に持てること。現代の視点からすれば、これらはすべて“実在感の表現”や“世界観の作り込み”といった言いかたもできるのだろうけど、当時はそういう発想自体がなかったように思う。
「なんでこんなに作り込んであるんだろう? このミカンがきっとこの後キーアイテムになったり、ストーリー進行に関係あるに違いない!」
と思ったものだ(もちろんミカンはキーアイテムにならない)。
さらに、天候が随時変わっていく。これは“マジックウェザー”と名付けられ、午前中は晴れていても、午後から雨が降ったり雪が降ったりする。しかも、雨が降れば住民は傘を差す。しかもしかも、その天気は、実際に作中と同じ1987年の横須賀地方の実際の天気記録を取り寄せて、ゲームが同じ天気になるよう組み込まれたというのだから、その労力とこだわりに脱帽するしかない(【余談5】)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/aef0a77e0c6a9981d0e373a4814187295.jpg?x=767)
不合理なまでの作り込みが生み出す世界観
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a36e08279fe785d40974c24d61596a2d6.jpg?x=767)
また、ガチャガチャもあって、ゲーム内でミニフィギュアを収集できる。一度回すたびに、100円を入れてハンドルを回すアニメーションが挿入される。景品には、ソニックや『バーチャファイター』シリーズなどセガタイトルのキャラクターが用意されていて、なかなか収集欲を刺激する。さらにゲーム内で走っているクルマなども小さくなって景品になっているのは、「こんなにも作り込まれているのか」とじっくり眺められるニクイ仕様だ。ただし、『一章』の段階では集めたアイテムの換金などはできず、オマケ要素の域は出ていなかった(【余談6】)。
とにかく、ゲームの本筋、ストーリーの進行と関係のない要素が多く、またその作り込み具合が異常なのだ。「なぜ、ここにこれほどまでの労力を……?」と、宇宙猫のような顔で大田区・大鳥居方面(当時)を見つめたくなるような作り込みが、全方面に向けてなされている。
留守にしていて誰も出てこない家はゲーム的に考えれば無意味なのだから、最初からインタラクトできないようにしておけばいい。玄関を設定し、ノックできないように、“玄関の見た目をした壁”にしておけばいいのだ。そちらの方が開発側もひょっとするとプレイヤー側も、余計な手間が掛からずに済むというものだ。
しかし『シェンムー』はそれをやる。不合理をやる。ゲームづくりのセオリーから外れているであろう、異常と言えるまでの細部へのこだわりを見せる。なぜなら、おそらく、“玄関に見える壁”というのは現実には存在しないからだ。
鈴木裕氏がアーケードゲーム向けに手掛けてきた作品を振り返ると、とくにポリゴン技術が使用できる時代になってからは、『バーチャレーシング』(1992年)、『バーチャファイター』(1993年)と、“3D表現で現実の何かを再現する”という方向性が感じられる。つまり、氏が『シェンムー』において希求したのは、『バーチャレーシング』でレースを3Dにしたように、『バーチャファイター』で格闘技を3Dにしたように、『シェンムー』においては、現実世界を限りなく3D空間に再現することだったのではないか……と筆者は推測している。たとえて言えばそれは“バーチャタウン”、“バーチャワールド”というような発想だ。
なぜならそう考えると、『シェンムー』が持つ、ゲーム的には不合理と断ぜられそうな仕様にも説明が付けられるからだ。なぜ、誰もいない部屋のドアをノックできるのか? 現実がそうなっているから。なぜ、街並みや店舗の壁がやたら薄汚れているのか? 現実がそうなっているから。なぜ、電話を掛けられるのか? 現実がそうなっているから。なぜミカンが持てるのか? なぜ仏壇に線香を上げて手を合わせられるのか? なぜ電気にヒモがついているのか? なぜ紐を引くと一段暗くなり、もう一度引くと完全に消えるのか? なぜ、住民全員の顔と名前が異なり、しゃべり、異なる会話をするのか? 現実がそうなっているからだ。
重ねて言うが、しかもそれがゲーム本筋の進行に何か寄与するかと言えば、あまりそうではない(たとえば詳細に描かれた事件現場の痕跡から犯人を推理するようなシステムということはない)。あくまで背景のリアリティーを増すだけといったところにとどまっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a0f93cb02e94d6738fb49754065a3d9b6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a5d2b0782e875939765beff3b74b768a9.jpg?x=767)
街の空間の現実感、住民の実在感、人々の顔つき、魚屋のオッサンの深いシワ。数十年を屋外で働き続けてきた男たちの人生が刻み込まれたような、あえて言えば汚い顔(しかし、いい顔)! そして思い返してほしいのは、このゲームはドリームキャストとセガの命運を左右する超大作なのだ。何か気まぐれや冗談でそうしているのではない。ハードの運命を掛けて、社運を掛けて、一生懸命にそれを作っているのだ。そのシワはただのシワではない。ハードの売れ行きを左右するはずのシワ一本だ。セガはオッサンの顔の深い皺に社運を懸けたのだ。
……とまでいうと言い過ぎな気がする。セガの人から「さすがにオッサンの顔のシワに社運は懸けてないわ!」と怒られそうな気がする。けれど、当時の開発陣は伊達や酔狂ではなく、リアル感のある街や住民を作り上げることに心血を注いでいた。それがもっともユニークで、唯一無二性を生み出す結果となった。『シェンムー』とはそういうソフトだった(【余談7】)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/accc6b968b7a42896028a4ad59a3ad8a2.jpg?x=767)
先進的過ぎたインターネット要素
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a745df660d3131d333879a525762b9a70.jpg?x=767)
このシェンムーパスポートを通じて、ゲーム進行に応じたアドバイスが見られたり、ゲームセンターのハイスコアをネット上に登録して全国で何位か、都道府県別で何位かといったランキングを見ることができた。さらに、ドリームキャストの記憶媒体である、小さな白黒液晶画面付きの“ビジュアルメモリ”の機能を活かした“あつめてシェンムー”というミニゲームも楽しめた。
本編に登場する街のキャラクターが、ビジュアルメモリ上でドット絵になって見られるというもので、登場人物ひとりひとりにそれぞれ固有のドット絵とアニメーションが用意されていた。現在ネット上に漂うそのドット絵やアニメーションを見ても、舌を巻く、嘆息してしまう作り込みだ。
(これは前述の通り『シェンムー』が、通信機能で勝負を懸けるドリームキャストのキラータイトルであったことと無関係ではなく、インターネットを活用した遊びを何か盛り込む必要があったためでもあると思われる)。
これらのインターネットを活用する“ドリームパスポート”要素は、2018年にリリースされたプレイステーション4版『シェンムーI&II』ではオミットされてしまったので、現在ではもう遊ぶすべがない。いまとなっては貴重な思い出となった(【余談9】)。
声優がモーションキャプチャーする意味とは
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a1d2288fd2af28e6552155861c415bd29.jpg?x=767)
収録に掛かる時間も当然ながら、音声データが膨大なものになることは自明の理だ。実際、音声データが巨大になりゲームディスクの枚数もかさんでいる。しかしそれでも全員全セリフのフルボイスを成し遂げた。
また、キャラクターの動きを収録するモーションキャプチャーの一部を声優本人が務めているというのも特徴だ。芭月巌の動きは藤岡弘、さん本人が務めており、芭月涼のあらゆるモーションは松風雅也さんが収録を行ったそうだ。松風さんは当時の思い出を「ネックハンギングされるところは本当に首をガーッてつかまれて演じたんですよ……」と語っていた。開発スタッフのみならず、俳優にも100パーセントの本気を要求する現場だったようだ。
モーションキャプチャーの中の人は、いわばスーツアクターやスタントマンのように、別人が演じても大きな問題はないはずだ。しかし、声優本人が演じることが、演技とキャラクターの一体感を生み、リアリティーが増し、ほかのゲームとの違いが生まれると信じて収録を行ったのだろう。きっと。
リアルにこだわりすぎない遊び心
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a07b553b17126f3fb8eeb4c6a07c8dce2.jpg?x=767)
これがまた、小憎たらしいほどきちんと作られている。フォークリフトに慣れないうちは後輪で操作する独特の操作性に翻弄されてうまくいかず、運転に慣れてくると小さなショートカットルートが見つかり上位入賞ができるようになるという、絶妙なバランスとなっている。
フォークリフトレースに限らずさまざまなミニゲームにはおそらく長年のアーケードゲーム開発経験が存分に生かされており、思わずくり返しプレイしてハマってしまう中毒性を持っている。
また、港では「妹が非行に走ってしまいそうで、なんとかしてほしい」という依頼を受け、サブストーリーが発生する。ほくほく弁当のひさかさんとその妹の舞ちゃん、さらに涼の“舎弟”となるゴローは忘れられないサブキャラクターたちだ。このイベントも少しマンガっぽいというか、1980年代の東映ドラマ的なムード漂う、リアルからはちょっと離れたエンタメ的な筋書きだが、おもしろい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a7c4da3a6d614e00eade88a268aab907a.jpg?x=767)
ギャンブル、アルバイト、ミニゲーム
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a83b622b8ff477f0c4ce51d200e5b0ee9.jpg?x=767)
『II』以降はさまざまなギャンブルもゲームに加わり、サイコロを使った“大小”やアームレスリング、ストリートファイトなど多くの種類が登場した。これらもまた、(お金を稼げるというゲーム的メリットはあるものの)寄り道要素であり、ストーリー進行とはあまり直接関係がない。しかし、だからこそ、プレイヤーの記憶に強く残るのだろう。
ストーリー 少年の成長×武道(武術)×旅×超常的な……?
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a29f557200173ca8d7576fd1643628803.jpg?x=767)
その中で、愛すべき友と出会い、武道の精神性である“武徳”や新たな技を学び、危険な事件にも巻き込まれ、人間的に成長を遂げていく。何やら清王朝のお宝にまつわる話も出てくる。『シェンムー』の物語は父の仇討ちの物語でもあり、少年・芭月涼の成長物語でもある。だから壮大なうえに爽やかな味わいもあり、じつに骨太な感じがする。莎木の木になぞらえて「太い幹としっかりした根を持つ物語」と言ってもいいかもしれない。
『シェンムー』ファンが何より気になっているのは、けっきょくこの物語がどう決着されるのか、である。藍帝との戦いはどうなるのか、莎花の不思議な力はまた出てくるのか、鳳凰鏡と龍鏡の秘密とは何なのか、清王朝の財宝は見つかるのか、秀瑛さんは生き別れた兄とは再会できるのか、気になる未回収の伏線は山程残っている。
今後のストーリーの一考察(妄想?)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a713f215629a789e60be70d3bb1a63fc3.jpg?x=767)
それは、『シェンムー』の続きはファンタジー要素というか、少し超常的な要素が入ってくるのではないか? というものだ。そう考える理由はいくつかある。
※以下、『シェンムーII』のエンディングのネタバレを含みます。
まずは『シェンムーII』の終盤、莎花が不思議な力を見せるシーンだ。涼は「日本ではタンポポの綿毛を吹いて飛ばす」という話をしたのだが、莎花は「私もやっているわ」といって、咲いている花に触れもせず、不思議な力でそこら中に咲き乱れる花びらを飛ばし、花吹雪を涼に見せた。涼は宇宙猫のように困惑した表情を見せるだけでこのシーンはおしまいとなったが、続いて思い出してほしいのは、全プレイヤーをその顔にさせた『シェンムーII』のエンディングである。
涼と莎花が採石場を訪ね、謎の装置を稼働させると、謎の剣が光り輝いて現れたのである。
そう、謎の剣が光り輝いて現れたのである。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/adebc3f574a3ef6a05a58fb73bf71cacd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/adaf176c80524d16790696d6c9af5de5e.jpg?x=767)
さらに、2004年に公開された、『シェンムー オンライン』という、サービス開始にいたらなかったオンラインゲームの発表PVでは、まるで“波動拳”のような技を駆使する映像が公開され、またもや『シェンムー』ファンの度肝を抜きつつ「???」を量産させた。
そして今回、記事作成にあたって先述の“プロジェクトバークレイ”映像を改めて見てみたところ、莎花が敵と戦うようなシーンで、体術的には中国武術を使いつつも、ちょっと爆発が入るようなエフェクトが描かれていたのだ。それは爆薬の破裂という意味ではなく、もうちょっと“気功”的な雰囲気だ。
また、仇敵“藍帝”が所属する中国マフィアの組織名は“蚩尤門(しゆうもん)”という。この蚩尤(しゆう)というのが、中国神話に現れる、日本風に言えば妖怪、あるいは悪神で、無数の魑魅魍魎を従えて古代中国皇帝から帝位の簒奪を試みたのだという。
たとえば、蚩尤門が目指すのは、蚩尤を現代に呼び覚まし、この世とあの世をつなぐ門を開いて魑魅魍魎が満ちる世界にすること。鳳凰鏡と龍鏡はそのために必要だった。そしてそれに対抗するのは、もちろん我らが芭月涼と莎花と仲間たちである。レンや秀瑛、涼の前に現れる中国の悪魔や妖怪、そしてマフィアたち。涼は旅で身に着けた新しい必殺技でそいつらと戦っていくのだ! いくぞおおおお!! うおおおおおおお!!! ……という、“シェンムー 最終章 ガーゴイル編”的な展開がありえるのではないか、というところまで妄想が膨らんでしまう。
この予想が当たる確率については筆者はまったくもって自信がないけれど、何はなくとも本来の続きが見てみたいものだと考えている。実際に『シェンムー』のこの先の展開がどうなるのかは誰にもわからない。神のみぞ知る、いや鈴木裕氏のみぞ知る、といったところである。
奇跡の『シェンムーIII』発売。『IV』はまだか
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/ac0b2e1c64431497382a0556ef58a22fe.jpg?x=767)
『II』で謎の剣が光を帯びながらあらわれたときはみんなビックリしたわけだけど、その後18年もその続きを待たされるとは思わなかった。多くの『シェンムー』ファンは「今年こそ『シェンムーIII』出ないかなあ……出ないよなあ……」となかば諦め、自嘲的に語っていたものだが、急展開が起きる。
『シェンムーII』が発売されてから14年後の2015年、E3会場に鈴木裕氏が登壇する。そして、『シェンムーIII』の開発と、開発費を集めるためのクラウドファンディングを発表した。その発表は世界中のシェンムーファンを驚愕させ、財布の紐を一瞬でびよんびよんに緩めた。世界中からバッカー(出資者)が集まり、“世界でもっとも速くクラウドファンディング100万ドルを集めたゲーム”として、『シェンムー』の名が再びギネスブックに登録されることとなった(16年ぶり2度目)。
10年以上続編の音沙汰がなかった作品が、ファンからも諦め掛けられていた作品が、そのファンの力を借りて蘇る。これを奇跡と言わず何と言おうか。
この事実が示すのは、とりも直さず『シェンムー』ファンの作品への愛である。『シェンムー』ファンは『シェンムー』を強く愛している。その理由はこれまで述べてきたところだけど、とにかく『シェンムー』ファンは『シェンムー』味がするものを求め続けている。それはいまも変わらない。
という感動的な経緯で開発された『シェンムーIII』が発売されてから、気づけばもう丸5年が経った。当初からアナウンスされていたが、『III』では物語は完結していない。しかもストーリー終盤では、建物が大炎上したりとても大事なものがたいへんなことになったりした。いったいこの後どうするつもりなんだ、あれ。筆者は物語の続きが非常に気になっている(『II』のエンディング後の困惑ほどではないけれど……)。
そろそろ『シェンムーIV』の動きがあってもいいのにな、あるといいな、とつねづね思っている。筆者は初詣で神社にお願いをするつもりだ。
まとめ:なぜ『シェンムー』は“唯一無二”で伝説なのか
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a0dd69d9a8ccacb2811844feba347c183.jpg?x=767)
『シェンムー』とはどのような作品だったのか。改めてまとめておこう。
時代が求めたキラータイトル
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/ae0f20b873a3a8652b4ac69f5394f5425.jpg?x=767)
最高峰のグラフィックで日本の街やリアル等身のキャラクターが描かれ、格闘アクションも『バーチャファイター』並にリアルにこだわり、全体を通して真に迫る迫力があった。
早すぎたと言えば早すぎた。ビジネス的な見かたをすれば、開発に時間も掛かりすぎた。
たとえば翌2000年夏に発売された、当時いわば“前世代ハード”となっていた初代プレイステーション向けソフト『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』は400万本を超える大ヒットとなった。ボイスは入っておらず、2頭身のキャラクターがファンタジー世界を冒険する。当時高校受験を控えた筆者もクリアーまで一気にプレイした。当時のゲーム市場で、プレイヤーの多くが求めていたのはやはりまだこの慣れ親しんだ表現だったと言えるかもしれない。
AM2研、鈴木裕という時代の寵児、1990年代セガを象徴する人が生み出した、あらゆる挑戦を盛り込んだ作品。それは“あだ花”と言ってしまったら悪いけれど、ビジネス的には大成功したとは言いづらい結果となった。
おそらく、ひとりの天才クリエイターが、「こうやるんだ!」と豪腕で突き通せた最後のタイトルではないだろうか。それも、完全新規のブランニュータイトルである。
それは、現代のように大規模化、超予算化し、失敗するわけにはいかないから果敢な挑戦が難しくなるという、構造的な桎梏を課せられる前、ゲームづくりが“ゲームビジネス”になる前の最後の瞬間だったかもしれない。
ドラマチックな復活の物語
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/e31dc62bdffdb8a16cfaed4d47ec8f46.jpg?x=767)
さらに、2022年には、初代作品発売後20年以上経ってからまさかの初のアニメ化を果たして全世界に向けて配信が行われた。異例尽くしのコンテンツと言えるだろう。
ゲームデザインには“無駄”が多すぎたかもしれない、けれども……
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a40cb36c310d32fa481155610fbe810f3.jpg?x=767)
だけど無駄というのは、ひょっとするとエンターテイメントの本質なのではないか? 僕たちはちょっとした息抜きや寄り道をするために、ゲームを遊んだりするのではないか? 寄り道を許さない人生というのは、マンガを読まず教科書しか読むことを許さない人生なのではないか?
無駄かもしれないけど、ちょっとおもしろい。『シェンムー』はそういうものに満ち満ちている。クリスマスが近づけば商店街をサンタが歩き、1月1日には女の子は振り袖に着替え、雨が降れば街の人は傘を差す。ガチャガチャ、アルバイト、フォークリフトレース……。
ストーリーの本筋に関係のない部分での異常なまでの作り込みや、インターネットを活用したシステムを見て、「なぜこんなところが、こんなに作り込まれているんだろう」と考えるたびに、「だって、そっちの方がおもしろいでしょう?」と微笑む鈴木裕氏の、いたずらっぽい笑顔が思い浮かぶような気がするのだ。
『シェンムー 一章 横須賀』エンディングの莎花のように……。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a439d5d59afb926f6c82376983921cd72.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a880e15789fbdf8125330183c2a29d91f.jpg?x=767)
“シェンムー伝説”を聞いた座談会もチェックを!
というわけでファミ通.com別記事では、当時の開発者を集めて、“シェンムー同窓会”と銘打った座談会を開催した。こちらも『シェンムー』秘話満載なので、ぜひチェックしてみてほしい。
余談
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29283/a3fa5fff17cc24f5303c373ebb658b36a.jpg?x=767)