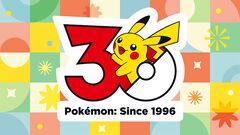累計2億本のセールスを記録する、ライフ シミュレーションゲーム『ザ・シムズ』シリーズ。2024年11月19日に同シリーズのスピンオフ作品『ぼくとシムのまち コージーコレクション』がリリースされたことを記念して、エレクトロニック・アーツ(以下、EA)のフランチャイズ・クリエイティブ担当副社長、Lyndsay Pearson氏にインタビューを実施。
シリーズ開発の経緯や日本市場に対する考え、今後の展望などをうかがった。
Lyndsay Pearson氏
エレクトロニック・アーツ 『ザ・シムズ』フランチャイズ・クリエイティブ担当副社長。2003年のエレクトロニック・アーツ入社以来、すべての世代の『ザ・シムズ』シリーズに携わり、現在はプレイヤー体験やチーム文化の構築、フランチャイズの未来の方向性を牽引。プレイヤーに強力な創造性と自己表現を提供するため、さまざまなプロジェクトに取り組むチームを率いる。
ロード時間を20秒も短縮! ファンの声に耳を傾け、問題点を改善
――『ぼくとシムのまち コージーコレクション』を発売することになった理由・経緯を教えてください。
Lyndsay
『ザ・シムズ』が25周年を迎えるにあたり、これは『ぼくとシムのまち』のふたつの象徴的なタイトルを次世代の新しいゲームファンに向けて復活させるのに、絶好のタイミングだと思いました。私たちは何年も前から、コミュニティが「これらのゲームが新しいハードウェアで遊べること」を望んでいると聞いていたので、こうしてNintendo Switch用に『ぼくとシムのまち コージーコレクション』をリリースすることができ、とても興奮しています。
――同作のオリジナル版に当たる『ぼくとシムのまち』について、こちらはどういった経緯で開発されることになったのでしょう?
Lyndsay
2000年代初頭にかけて『ザ・シムズ』の人気が高まるにつれ、同作を支えてきた価値観や行動を、新しい種類のゲームに拡張するチャンスが見えてきました。私たちはその当時、最新のハードだったWiiを活用して、創造性、個性、構築、探索に焦点を当てた、若いプレイヤーにも親しみやすいゲームを作りたかったんです。これらの目標から『ぼくとシムのまち』が誕生しました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/a0c79ea1715529a25ce443f579806e714.png?x=767)
――ゲーム開発において、ユーザーからの意見を参考にしたり、新要素として取り入れたりすることはありますか?
Lyndsay
はい、もちろん! 『ザ・シムズ』および、『ぼくとシムのまち』について、私たちはファンの皆さんが“どれだけこのゲームを愛してくださっているか”をわかっています。そのためフォーラム、SNS、Reddit、Discordなどを調べて、コミュニティから報告された問題を徹底的に探しました。バグに加えて、エリア間のロード画面が長い……などの問題点もそこで見つけて、対策を考えています。ロード時間は、場合によっては20秒もかかることがあったのですが、これらを大きく改良して(場合によっては1秒未満に短縮!)、そのほかの多くの懸念事項も改善に当たりました。
――『ぼくとシムのまち』シリーズは、『キングダム』以外にも『パーティー』、『レーシング』、『エージェント』などがリリースされていますが、これらも再び遊べる(リマスター化される)可能性はありますか?
Lyndsay
これについては残念ながらコメントできませんが、私たちは『ぼくとシムのまち』のフランチャイズとIPを心から愛しています。従来のファンと新しいファンがどのように反応し、レトロな復刻版を楽しんでくださるか。まずはそちらに期待しています。
歴史と現代性が融合する“日本のゲーム市場”は非常に魅力的
――20年にわたり『ザ・シムズ』シリーズに携わってこられたなかで、ゲーム開発に取り組む姿勢であったり、ユーザーから求められる要素など、さまざまな変化があったと思います。それらを具体的に教えていただけますか?
Lyndsay
『ザ・シムズ』のゲーム開発における最大の変化のひとつは、コミュニティへの関与です。何年ものあいだ、『ザ・シムズ』は活気に満ちたプレイヤーコミュニティを育んできました。たとえば『ザ・シムズ4』では、プレイヤーがゲームのなかで見たいコンテンツによって牽引された、本作のクリエイターとともに直接開発した“クリエイターキット”をリリースしたり。コミュニティとのつながりは、私たちが前を向き、新しいことに挑戦し、よりよいものを創り出すことを可能にしてくれます。そういった意味でも『ぼくとシムのまち』は、私たちが手掛ける『ザ・シムズ』シリーズの歴史のなかでも、非常に明るい可能性に満ちた作品だといえるでしょう。
事実、時の経過とともに、『ぼくとシムのまち』ブランドに対する要望や熱意は明確に見えてきていて。『ぼくとシムのまち コージーコレクション』の開発に着手したとき、私たちはプレイヤーからのフィードバックや、今日のゲーム環境における“同シリーズへの期待値の高さ”を実際に確認することができました。情熱的なファンからの直接のフィードバックと会話は、今日のエンターテインメントにおいて非常に重要なものだと認識しています。
――御社にとって日本市場はどのような位置づけですか? 他の国の市場と比較して、どれくらい力を入れて取り組まれているか……など、ご意見をお聞きしたいです。
Lyndsay
日本はつねに『ザ・シムズ』の活発な市場であり、非常に熱心なプレイヤーコミュニティがあります。日本の皆さんが私たちのゲームをどのように受け取り、プレイしてくださっているかを理解することは、『ぼくとシムのまち』を提供していくうえで大切なプロセスでしたし、同作の成長にともない、今後もより重要な取り組みになっていくと考えています。
『ぼくとシムのまち』には、日本のゲーム作品やプレイスタイルにも通じる多くの類似点があるので、“東京ゲームショウ”での展示をきっかけに、改めて「こちらのシリーズを日本の市場で成功させたい」と強く思うようになりました。
――日本のゲーム市場について、率直なご意見、ご感想などをお聞かせください。
Lyndsay
私たちは日本のゲーム市場が大好きです。EAには日本で働いているすばらしいチームがあり、日本の動向やプレイヤーの好みはつねに共有しています。日本のゲーム市場は長い歴史を持ちながらも、その動向・展開にはダイナミックなところがあります。そこが新鮮ですし、“歴史と現代性の組み合わせ”という部分には非常に魅力を感じています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/abd4dd62cf8af25e1e154d72ea06ce80a.jpg?x=767)
多様なニーズに応えられるよう、つねに新たな展開を探求する
――『ザ・シムズ』の映画化が発表され、話題になっていますが、こちらはどういった経緯で制作されることになったのでしょう?
Lyndsay
『ザ・シムズ』は、つねにアイデンティティとストーリーを探求するゲームで、その永続的な魔法の一部は、プレイヤーといっしょに変化し、進化していくという、本作ならではの“無限に近い能力(特性)”に由来しています。そして本作の世界は、魔法やハート、ちょっとしたカオス、大量の創造性といったもので満ちており、これらは物語として描くうえで、非常に興味深い背景になるものと認識しています。
ここ数年、伝統的なエンターテインメント(映画やテレビ)がゲームに近づいてきており、かつては“分離されている”と感じられたそれらは融合。新しいものへと進化している過程にあるといえます。こちらが『ザ・シムズ』の映画化に踏み切った理由であり、これにより、いままで以上にインタラクティブなエンターテインメントが生み出せるものと考えています。
――こちらの映画化のように、ゲームの枠にとどまらない新たな展開は今後もあり得るのでしょうか?
Lyndsay
『ザ・シムズ』は、ひとつの作品やチャンネルを超えた未来を持つエンターテインメントプラットフォームだと捉えています。私たちは、世界中で増え続ける“Simmer(『ザ・シムズ』プレイヤー)”からの多様なニーズに応えるために、ジャンル、プラットフォーム、ストーリーテリングといった枠を超えて、フランチャイズを継続的に展開しています。プレイヤーがゲームのなかで無限の可能性を探求できるように、私たちは「どのようにすれば『ザ・シムズ』を、いままでにない新しい形で展開していけるか?」ということを、つねに探求しています。
――日本のゲーム作品で、プレイして影響を受けたタイトルはありますか? 影響を受けたタイトルだけでなく、純粋に楽しんでプレイしているタイトルなどもありましたら、教えてください。
Lyndsay
私たちのチームの多くのメンバーは、Nintendo Switchはもちろん、いまなお旧型の任天堂コンソールを愛してプレイしています。任天堂のタイトルはどれも本当におもしろく、私も楽しませてもらっています。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/ae968363febd29452408db26597c5d1a5.png?x=767)
――日本の『ザ・シムズ』および『ぼくとシムのまち』シリーズのファンに向けて、メッセージをお願いします。
Lyndsay
『ぼくとシムのまち』は、日本でも多くの方に遊んでいただいて、そこから派生したオリジナルゲームのいくつかは、日本のすばらしいパートナーと共同で開発したものになります。『ザ・シムズ』も含め、25年にわたり、これらのタイトルを愛してくださったことには感謝の気持ちでいっぱいですし、『ぼくとシムのまち コージーコレクション』を遊んでいただいて、少しでも懐かしさをお届けできれば……と思っております。
東京ゲームショウ(TGS)でのファン皆さんの反応や、日本チームが予約特典として作成してくれたキーチェーンやステッカーのクオリティの高さには驚きつつ、それと同時に作品への強い愛も感じられ、とてもうれしく思いました。皆さんのサポートに心から感謝しています。日本のすべての『ザ・シムズ』、『ぼくとシムのまち』ファンの皆さん、改めまして、本当にありがとうございます。私たちも皆さんを愛しており、感謝しています!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/a0c79ea1715529a25ce443f579806e714.png?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/abd4dd62cf8af25e1e154d72ea06ce80a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/26326/ae968363febd29452408db26597c5d1a5.png?x=767)