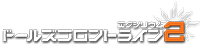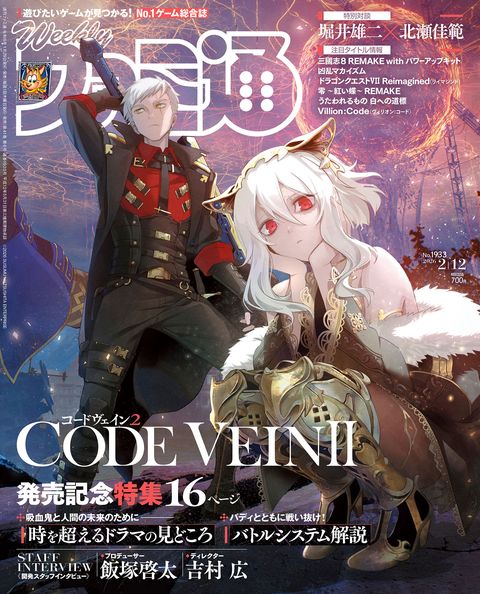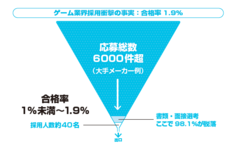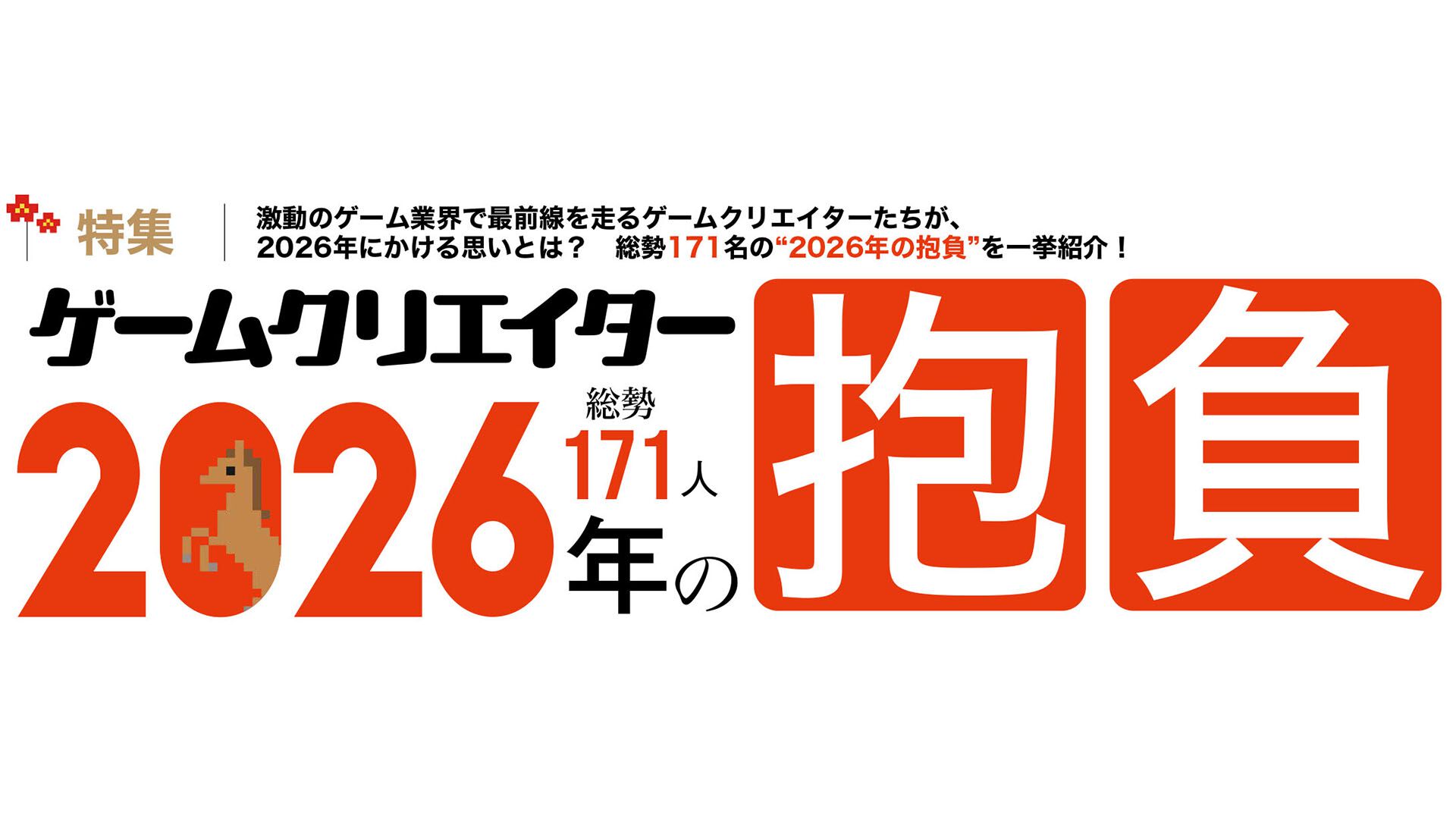2024年5月30日に発売された『東京サイコデミック 公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿』(『東京サイコデミック』)。
発売を記念し、本作のプロデューサー・神崎喜多氏と、オカルト雑誌『月刊ムー』の編集者・望月哲史氏、そしてファミ通のオカルト大好き編集者・藤川Q、3人による座談会が行われた。
超常現象、異能力者、霊感、お参りなど、さまざまなワードが飛び交ったオカルトトークをお届けする。
※本稿には『東京サイコデミック』本編のネタバレが含まれます。
※本稿はグラビティゲームアライズの提供でお送りします。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/ab52ca36940ceaf6b8c8440f68c80c294.JPG?x=767)
左から藤川Q、望月哲史氏、神崎喜多氏。場所は公安調査庁特別事象科学情報分析室……風の、グラビティゲームアライズ社内にて。
神崎喜多 氏(かんざき よしかず)
グラビティゲームアライズ所属。『東京サイコデミック』エグゼクティブプロデューサー。(文中は神崎)
望月哲史 氏(もちづき さとし)
超常現象専門誌『月刊ムー』編集者/webメディア『webムー』編集長。(文中は望月)
藤川Q(ふじかわきゅー)
ファミ通でもっとも超常現象や神話伝承に造詣の深い編集者。『月刊ムー』で、オカルト方面からゲームを語るコラム“藤川Qの月刊ムー通”を連載中。(文中は藤川Q)。
一見すると食い合わせの悪いテーマをひとつの作品にする
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/aa85b52f1983780912e231a3f9650daaa.jpg?x=767)
藤川Q
いきなり気になるところから聞いていくんですけど、やっぱり、この『東京サイコデミック』というゲームを知ったときに望月さんがどう感じたのか知りたいですね。
神崎
確かに。『月刊ムー』さん的な目線だと、どう思いました?
望月
最初は、「食い合わせが悪いんじゃないかな」と思ったんですよ。
藤川Q
食い合わせ。
望月
だって、超常現象を調べて科学的に解明して事件を解決するというアプローチと、そうじゃない、科学では解明できない本物の超常現象を探す、っていうのがどっちつかずになるんじゃないかと思って。
だってファフロツキーズ現象(本編Case2)とかね、「じつは不思議な力が本当にあったんだよ! それが働いて天からの恵みが降って湧いたのだよ……」とかいうオチになったら、事件を解明しようとしている側からすれば、納得がいかない話になるじゃないですか(笑)。
でも、あえてそこを両立させてるのがすごいですよね。
神崎
そう、実際食い合わせは悪い(笑)。
でも、このゲームは裏に“異能力”というテーマを抱えていて、そういった得体の知れないものや怖いものを科学で否定するというアンチテーゼ的な部分もあったからこそ落とし込めたんじゃないかと思っています。
望月
表現のバランス、リアリティのバランスがすごく難しいテーマだと思います。
神崎
そこは「実写にしてよかったな」と思う部分ですね。
超常現象を実写で表現しようとすると、ある程度制約が生まれるんですよ。たとえばCGやアニメ作品であれば、実質的に際限なく、なんでも描けるわけじゃないですか。日本が全部吹っ飛ぶ大爆発みたいな。
でも、実写ではあまり派手なことはできない。
神崎
表現にリアリティーの制約がある実写だからこそ、頭ごなしに「ありえない」と思わないような、「ありえるかもしれない」と思えるギリギリのラインの超常現象が描けたと思っています。
藤川Q
実際にゲーム内で超常現象の映像をくり返し見るから、もともとプレイヤーが持っている自分の感覚になじんでくるんですよね。あのビデオデッキの専用コントローラーが欲しいくらいです。
望月
そのうち本物の解析作業ができるようになっちゃいそうですね。
神崎
そこは本場の捜査を再現できるようにこだわった部分です。ただ、コントローラーやキーの割り振りが複雑になってしまって、操作しづらいというお声もいただいています。(※)
※UI(ユーザーインターフェイス)、操作性は今後のアップデートで改善予定。![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/acac7f7032d6bf58798917e58e5bb5250.jpg?x=767)
藤川Q
途中でめちゃくちゃ単調な作業があるんですよね。ホテル12階ぶんの監視カメラをチェックするっていう。
望月
そんなたいへんな作業があるんですか?
藤川Q
はい。ビデオテープをデッキに入れて、チェックして、また新しいのを入れ直して……というのを12階ぶんやるんです。刑事ドラマで「はぁ……この量の映像チェックすんのかよ。今日は徹夜だな」とか言うシーンあるじゃないですか。あれを思い出しましたね。
望月
そこは「ゲーム的に省略しよう」という発想にはならなかったんですか?
神崎
そういった発想がなかったわけではないのですが、『東京サイコデミック』は捜査ゲームだから、プレイヤーに本当に捜査してほしい、というディレクターの今井(秋芳)さんの考えも汲み取っています。
「わずらわしい」、「面倒だ」という声も出るだろうなあ……と思いつつ、外せなかったですね。
望月
そこを省略したら何にもならない、と。
藤川Q
様式美ですよね。
神崎
様式美を取りました。時代を逆行しているようですけれども。
藤川Q
いやぁ、ロックだと思いました。
実写映像のこだわりは“なるべく演技をさせない”
藤川Q
『東京サイコデミック』は2Dと実写、ふたつの映像技法を取り入れていますよね。ゲームだから2Dはわかるんですけど、実写映像を取り入れた理由は何ですか?
神崎
リアルな説得力を持たせるためですね。たとえば冒頭のニュース映像。我々は現実世界でコロナ禍を経験しているじゃないですか。だから作中で「未知のウイルスによるパンデミックが起こりました」っていう報道を実写映像で表現すると、説得力がある。
逆に、全編実写にしなかった理由もあるんです。それは、実写ではキャスト(演者)を立てたくなかったんですよね。
キャストを立てちゃうと、その役者さんに全部引っ張られるじゃないですか。物語がキャストありきになってしまうので、ドラマパートはキャラクターに動いてもらう形にしました。
ほかにも、実写パートを撮影する際に意識したのは、「なるべく演技をさせない」ということです。たとえばCase1の、薬局でエタノールを買うシーンではエタノールを買っている人(被害者)はエキストラの方なんです。
ですが、店員さんはロケ地の薬局で働いている方そのままなんですよね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/a5b5d2b118a2c854d94cb6bbd5cf11b59.jpg?x=767)
藤川Q
キャラクターたちはLive 2Dでけっこうバリバリ動きますよね。
神崎
ただ、実写映像で超常現象的なことを撮影するとなると、なかなか無理が出てくる。どうしてもチープな仕上がりになってしまうんですよね。
だからそういうシーンは実写から遠ざけて、劇画的な印象の映像にしました。
最初は死体もかなりリアルに人形で作っていて、プロトタイプにはその人形を使っていたんですけど、「これ使うとCERO:Z(18歳以上のみ対象)になっちゃうかなあ」となり、さすがにCERO:Zはやめておこう、という話になりまして、人形の出番はぐっと少なくなりました……。
望月
でもCase1の焼死体もけっこうリアルですよね?
神崎
あれもけっこうチャレンジングでして……。
僕の勉強不足だったら申しわけないんですけど、実写のゲームで死体を直接的に映しているものって過去にないんですよ。殺人の最中ではなくて捜査現場の描写とはいえ、ご遺体を直で出すのは許されるのかなという不安はありました。
望月
テレビドラマでも、ブルーシートをめくって、それを観た刑事役の役者が「ぎゃあ」とかっていうリアクションだけが描写されるような形が多いですよね。傷口とか切断面とかはあまり映されないんじゃないかな。
神崎
いちおう撮影はしたのですが、そういった表現はだんだんと縮小していって、Case2の死体描写なんかはほとんどカットされていますね。
望月
超常現象だからセーフにしてよ、人形だからいいじゃないの……というわけにはいかない?
神崎
そうですね。いくらフィクションだからと言っても、あまりにも生々しいとちょっと。
藤川Q
Case2のファフロツキーズ現象の映像なんてめちゃくちゃ地味ですもんね。
バラバラ死体が空から降ってきたのに、それを見た通行人はパニックになるわけでもなく、「うわっ」って驚くだけで、その後はそそくさと通り過ぎていく……生々しいなと感じました。
神崎
あのシーンはエキストラを使っているんですが、たまに一般の通行人もいて、その方々の反応がね、みんな落下物を避けていくんですよ。
死体が落っこちてきたらパニックになるんじゃないかと予想していたのですが、実際落としてみたらそうじゃなかった。だから本編はそれを参考にして作っています。落ちた瞬間は驚いても、ある程度時間が経過すると「作り物なんじゃないか」という考えが先行するんですよね。
望月
「こんなものがここにあるわけない」と思って、受け入れる形に切り替えていくと。
神崎
現代人だととくにそうかもしれないんですけど、さらに「関わりたくない」という思いもあって避けていくという。
望月
UFOを目撃した人もわりとそうですよね。見た瞬間はパニックにならないんだけど、他の人に話してみて「それって異常じゃない?」と言われて初めて気づく、みたいな。怪談話とかでも、「そんなとこに人がいるわけなくない?」って他人から指摘されて初めて「あれってお化けだったのかも……」と自覚すること多いですよね。
神崎
異常なものを見てしまうと、無意識下で日常に戻ろうとしてしまうのかもしれません。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/a4d131d9709ce36646bc78dd775cba48e.JPG?x=767)
藤川Q
ムーさんのイベントで、夜通しスプーン曲げをしようっていうのがあったじゃないですか。
望月
あぁ、500本曲げるやつ。最初はみんなできっこないと思っていても、いざ目の前でスプーン曲げを見て「こうやってやるんですよ」って教えられたら「いけたいけた!」ってなるんですよね。
藤川Q
そう。それも異常が日常になる瞬間ですよね。
神崎
何か事象が確定したと人が思ったときに具現化する、っていうことがあるんでしょうか。
望月
気持ちが切り替わっているタイミングは確実にありますよね。
通常、スプーンは曲がらないものだと思っているから「曲げてください」って言っても、そもそも力を入れないとか。でも曲げるものだと認識すれば曲がるようになる。
これを可能にしているのは最終的に筋力かもしれないけれど、認知は変わっていると思います。
だから「スプーン曲げを見るだけで変わるわけないじゃん」とか「言われただけで変わるわけないじゃん」というのは、その人の持つ筋力は変わらないかもしれないけど、見えないところで、その人の“認知”、つまり“常識”がじつは変わって、それで持っている能力を発揮できるようになっている……のかもしれない、という話はありえるのですよ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/a3065124e895065667212125fe41cafba.JPG?x=767)
神崎
ほかにもそういう例ってあります?
望月
うーん……占い師さんっているじゃないですか。霊感のある占い師さんは霊視の結果をタロットや水晶を使ってお客さんに伝えることが多いんですね。それってある意味、パフォーマンスでしかないけれど、ただ何もせずに「これが見えました」と言われるよりも、タロットなどの装置を使って、目に見える結果のあるほうがお客さんも安心して納得するからそうしているらしいんですよ。
で、本題は霊感のない占い師さんの話なんですが。占いの象徴を読むことに徹して、霊感ではなくてロジックや手順に基づいて占っていると、とそう自負していた占い師さんがある日、そういった技術を考えなくても自然に結果が“視える”ようになってきたと気づく瞬間があるそうなんです。
だから、最初は理屈で考えてやっていたとしても、くり返し訓練すれば超能力じみた力が身につく場合がある、という話は聞いたことがありますね。
藤川Q
『東京サイコデミック』に当てはめると、占い師さんの“カードを引く”確認作業が、科学捜査に該当すると思うんです。超常現象に人間が立ち向かおうとしたら、そうするしかないんじゃないかなと。
望月
泥臭くわからないことを追究していくしかないですよね。
何かわからない怖いもの、をとことん追究していく
神崎
このゲームで僕がこだわっているもののひとつが、よくわからないものをハッキリさせたい、というものです。
僕からするとオカルトとか超常現象は恐怖でしかなくて。お化けとか信じてるほうで、怖いもの苦手なんですよね。僕はもともとエンジニアで、プログラムとか書いていた人間でして、証明できないものって怖いと思うし、本来はリアリストなんですよ。
だからオカルトなんて信じてない、これはこういう事象なんだって思いたいところが本作にも少しは反映されている気がします。
望月
エンジニアさんの世界って、コードにないものは発生しないですもんね。
神崎
そうなんですよ。事象は基本的にYESかNOか、くり返すか、分岐するか、くらいしかないですからね。
望月
そういった世界観のなかで、“バグ”というのはどういう扱いなんですか?
神崎
それこそまさに“最初はわからなくてもきちんと調べれば原因があるもの”でして。
コードを丁寧に読んでいくと「あ、ここが原因で出てるな」とわかるものなんです。必ずどこかに理由はありますね。でも自分で組み上げたコードが予想外の動きをするとやっぱり怖いですよ。
望月
オンラインゲームのサーバールームにお札が貼ってあるのってやっぱり都市伝説なんですか?
神崎
いやいや、実際に貼ってるところはありますよ。僕が関わった実例だと、以前サーバーの入れ替えで大規模なメンテナンスがあったんですけど、必要なこと全部終えてどこに行くかというと、神田明神にお札をもらいに行くんです。
藤川Q
雷除けみたいなやつですか?
神崎
そうそう。それで「何も起きませんように」とお祈りする。で、僕たちのほうは何も起こらなかった。
望月
僕たちのほう“は”?
神崎
ほかの人たちが担当したサーバーは大規模な問題が起こっていたんですよ(笑)。
藤川Q
お札がめっちゃ効いてるじゃないですか!(笑)
神崎
こういう験担ぎ的なことはけっこう信じてます。習わしや風習はロジックではなく、習慣だから取り入れてますね。
ところで最近はオカルトも、「絶対にありえない」から「もしかしたらありえるかも」と描かれる傾向にあると思うのですが、『月刊ムー』さん的にはどう思われますか?
望月
補助線的な枠組みでは、リアルな部分はありますよ。ゼロからは作れないですからね。何か出来事があった上でないと。
藤川Q
ある意味、作りかたとしては『東京サイコデミック』と同じですよね。起点が現実であり、そこからどういう図形を描いたかという話で、かつエンタメであり……。
神崎
そうですね。リアルな事象に“異能力”という味付けがされて、それが本当に存在するのか探っていくという流れは、『月刊ムー』さんと同じですね。
望月
でも『東京サイコデミック』一応結論が出るじゃないですか、『月刊ムー』の場合は最後に「さらなる研究を待ちたい」とか、結論を濁すことが多いですからね。いったいいつまで待ってるんだと(笑)。
藤川Q
今月号で出なかった結論は、また次号に掲載されているかもしれませんからね。
望月
そうか、それで毎月買ってもらえばいいんだ(笑)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/a0a5828f8cee8509e6b4080764fbdf0c4.JPG?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/aa85b52f1983780912e231a3f9650daaa.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/acac7f7032d6bf58798917e58e5bb5250.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/7449/a5b5d2b118a2c854d94cb6bbd5cf11b59.jpg?x=767)