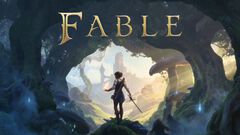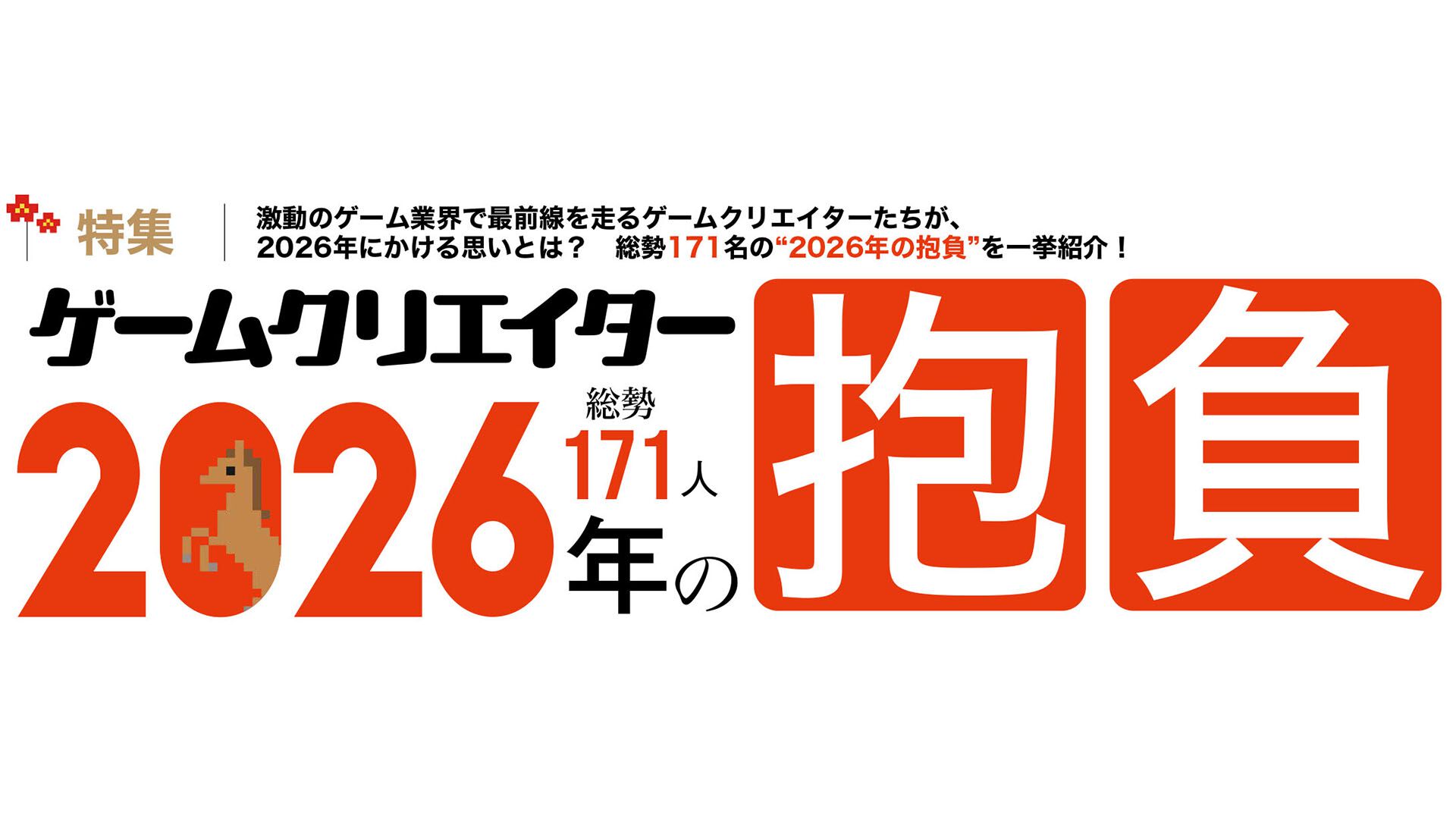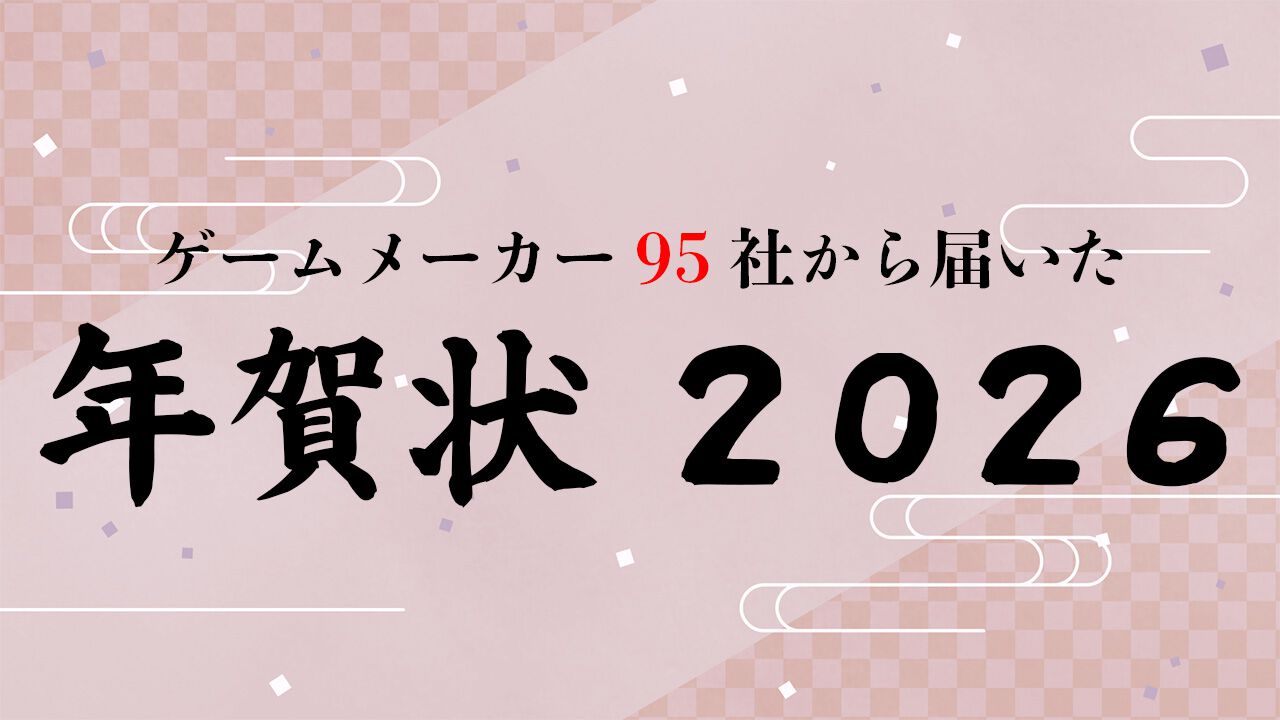タイトーから2025年8月7日に発売された『オペレーション・ナイトストライカーズ』特装版に先行版のダウンロードコードが付属しているので、すでにプレイした方もいるだろう。本稿では、正式発売記念に『ナイストGEAR』レビューをお届けする。
- アーケードライクなのでエンディング到達までは短め。くり返し遊ぶたびに上達を実感
- 夜景の美しさに目を奪われる。疑似3Dだからこその疾走感
- やり込み要素も充実。パシフィストモードをノーマルモードと分けたのは英断!
- 令和の最新ゲームとして十分なポテンシャル。今後はスコアアタックで盛り上がれそう
アーケードライクなのでエンディング到達までは短め。くり返し遊ぶたびに上達を実感
そしてGEARチェンジボタン(※)を押すとGEAR形態(ロボット)に変形。変形中はゲージを消費して強力なホーミングショットを連射できる。
効率よくGEARゲージを溜める方法を模索するのも楽しい。たとえば敵編隊の中に1機だけ存在する赤色の隊長機を撃墜すると残りの敵機も誘爆できる。この隊長機を手っ取り早く落とすために一瞬だけGEAR形態になるというテクニックも。自分なりのやりかたをアレコレ試すうちに、いつの間にか自身の腕が上達しているのに気付いた。
夜景の美しさに目を奪われる。疑似3Dだからこその疾走感
疾走感も見事に感じられた。3Dのゲームなんて、いまやすっかり見慣れているはずなのに、どことなく懐かしく、それでいて臨場感もしっかり伝わってくる。その理由はおそらく“疑似3D”によるものだろう。
そう、『ナイストGEAR』は昨今の3Dゲームで当たり前に使われているポリゴンではなく、初代『ナイスト』と同じ疑似3Dを用いて地形を見せている。具体的に言えばビルや柱などのオブジェクトを拡大していくことで、それらが眼前に迫っているかのように見せているのだ。
1989年はポリゴン技術が浸透していなかったため、いかに立体的に見せるか四苦八苦していた時代だった。現代では3Dのオブジェクトを画面に出すことは容易いのに、なぜ当時と同じ疑似3Dを用いているのか。その答えは本作をプレイしたことでわかった。疾走感だ。
3Dグラフィックの中を飛べば確かにリアルだが、リアルなゆえに地面を走行し続けるでもない限り、直接的なスピード感は得られない。ジェット機に乗っているときにいちいち時速900キロを体感しないのと同じだ。めちゃくちゃなスピードで飛んでいることを体感させ続けるために、あえて疑似3Dにしているのだと(あくまで筆者の想像だが)解釈している。
思えば、筆者が『ナイスト』にハマったきっかけはBGMのカッコよさだった。『ダライアスII』目当てに買ったサウンドトラックにカップリングされており、「なんだこのイカす楽曲は!」と、近所のゲーセンを探しまくって初代『ナイスト』に出会えたときは本当にうれしかった。
やり込み要素も充実。パシフィストモードをノーマルモードと分けたのは英断!
スコアと言えば、本作には“パシフィストモード”なるものが存在する。このモードではショットが撃てず、ひたすら敵の攻撃をかわしながらゴールを目指すというもの。
もともと初代『ナイスト』の時点で、弾を1発も撃たず、かつ被弾せずにステージクリアーしたときに膨大なスコアが入る“パシフィストボーナス”というシステムがあった。当然ハイスコアを狙う際はパシフィストボーナスを狙うことになり、(それはそれでおもしろかったのだが)敵を撃つ要素を完全に排除した別ゲーとなることが少々残念に思った記憶。
しかし『ナイストGEAR』ではモードを完全に分けることで、ワイプアウト(※)狙いも含めて存分に敵を破壊する楽しさを味わいつつスコアアタックに臨める。これは本当に英断だと思う。
令和の最新ゲームとして十分なポテンシャル。今後はスコアアタックで盛り上がれそう
ただ、スピード感がものすごい反面、近距離で発射された敵弾をいきなり食らうことが多々あるのだけは気になった。一応、自機の正面にいる敵に対しては“弾封じ”というテクニックも用意されてはいるが、それも安全が保障されるものではない。
幸い難易度が選べるので、この手のゲームをやり慣れていない人は、まずイージーで様子見してから徐々に難易度を上げていくのがいいと思う。プレイしていくうちにクレジットが増えていくので、コツをつかむまでコンティニューしまくってもいい。
ちなみに本稿執筆のためプレイしているうちに、いつの間にか“Bサイドモード”という第3のモードも解放された。こちらはステージセレクト要素がなく、たくさんのステージに続けて挑んでいくというロングプレイ仕様のモード。
各モード・各難易度ごとにハイスコアランキングが用意されているので、これからじっくりやり込んでいきたい。
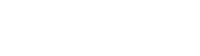




![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)