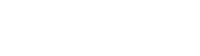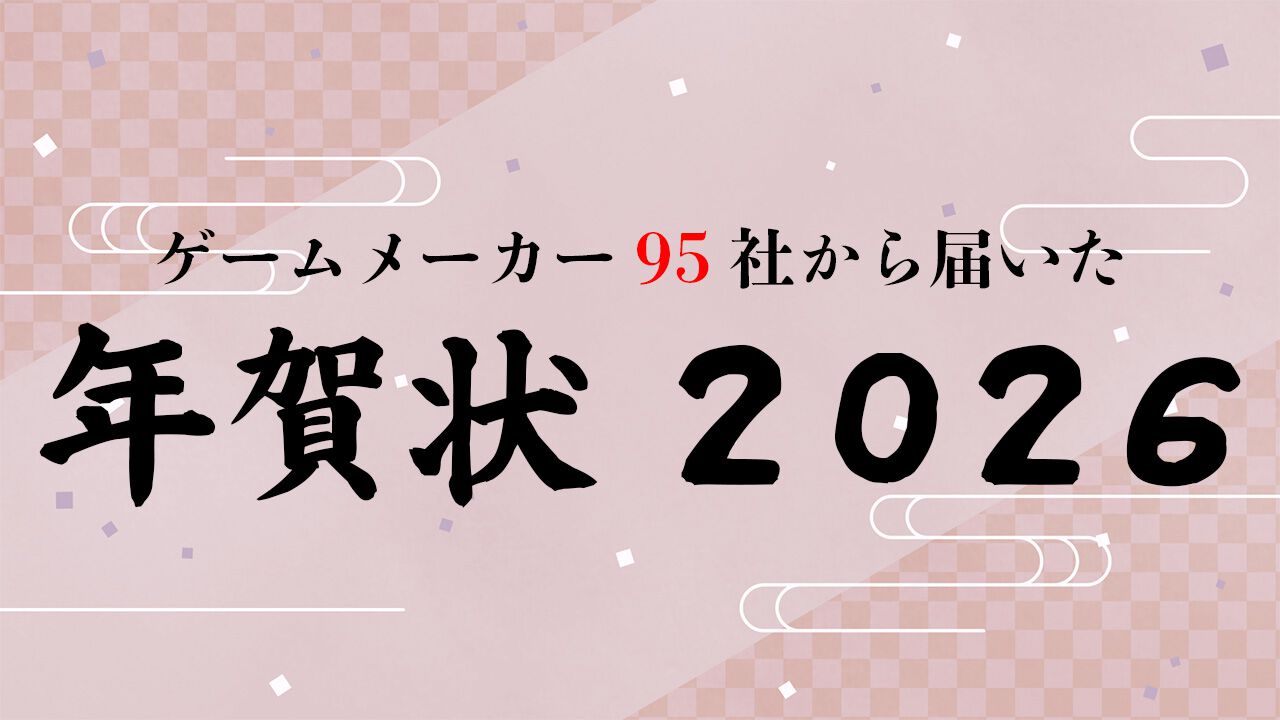アメリカンコミック(アメコミ)で知られるマーベルのキャラクターたちが集結した対戦格闘ゲームで、開発は『ギルティギア』シリーズなどを手掛けるアークシステムワークスが担当している。
そんな本作のクローズドベータテストが、2025年9月6日~7日の期間に実施され、ファミ通.com編集部はSIEから招待を受けて参加できたため、クローズドベータ版を実際にプレイした感想と、ゲームシステムの詳細をお伝えしよう。なお、体験できたのは開発中のバージョンとなっているため、細かな部分は製品版と異なる場合があるのでご注意を。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adbb320c76cc62538aa73d371b2a8b89e.jpg?x=767)
ジャパニメーション×アメコミ!
本作でもアニメ調のグラフィックは踏襲されており、見応えバツグン。そこに日本のアニメ作品のようなテイスト・キャラクターデザインが加わりながらも、アメコミ調の影の付けかたなどが取り入れられ、和洋折衷のマーベルワールドを表現している。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/aaf6acadd301d2164e41d55924141bfdd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a91de30ac80ef96ab5f51db6a8e4ec2de.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a3e6fd5e0cf4c25f59919af8b72e548ab.jpg?x=767)
いまのところマーベルキャラクターたちがバトルをする、といった内容にはなっているが舞台設定などは明かされておらず、どういった次元の世界になっているのかは不明。おそらく原作モチーフの世界観やストーリーがあるのだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac3a5c5bdda25e13936fdd8788574313c.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a3ed003438ba685bd666644fdca505930.jpg?x=767)
ジャパニメーション×アメコミといったアートスタイルは見ているだけでも美しく、カッコイイ。これまでにないマーベルキャラクターたちの活躍が楽しめるのは、ファンにはたまらないものだろう。アークシステムワークスのタイトルの例に漏れず、どのシーンを切り取って見ても「もうこれイラストか、アニメのカットでは?」と思えるほどに美麗だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4117b680cee164e16baa2ea81bff1c2a.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adcc246537392572e6e5222360a3c2105.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a40495d4b50a16f1396cc1706fbac82b1.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a98728397cf726faad4f403acc874ffc9.jpg?x=767)
クローズドベータ版について
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a8687de5e3c641d0b6406552ee8816a21.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a6ece0ea3e5eea2403e70d8be7733fb4a.jpg?x=767)
ルームはアークシステムワークスらしく、大きなゲームセンターのようなロビーにプレイヤーたちが集まって、コミュニケーションなどを取りながら対戦できるシステム。アバターもデフォルメされたキャラクターに変更できたほか、エモートなどにもキャラクターが描かれているのでとってもキュート。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a679b500e6058662b8596f9c13ed5f443.jpg?x=767)
一応ジャンプもできたが、対戦と観戦以外は基本やれることはなかったので、あくまで基本に忠実な対戦用のロビーといった感じ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a7f425575143b4f233a24b166d47128ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/aa98b92e0e13d9ee579496ffe70d05163.jpg?x=767)
独特の4対4システム
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a061e450d3ba1ff9b293b08cbca6e4a49.jpg?x=767)
4対4のチームバトルでありながら、独特のシステムを採用しているのが特徴的だ。チーム方式の格ゲーは、キャラクターが倒されたらつぎのチームメンバーに交代、もしくはチームメンバーの誰かが倒れたら敗北、というようなルールが多い。
本作はチーム全体で体力を共有しており、操作しているキャラクターが倒されてしまったらラウンド敗北となる。そのため、チームメイトがサポート攻撃をくり出しながら(いわゆるアシスト)、多数のキャラクターが入り乱れるチームバトルのよさは残しつつ、基本な立ち回りは1対1の対戦格闘ゲームのような味付けになっている。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a701e2b130abb66d520a03029565961a9.jpg?x=767)
と言いつつも、対戦中にチームメンバーへの操作交代も可能だ。使用するキャラクターを変えながら戦うわけだが、チーム方式の格ゲーはここがおもしろいところでもあり、ジャンルとして抱えるネックの部分でもある。多数のキャラクターを操作できるのは楽しいが、それはキャラクターを使いこなせてこそ味わえる魅力。
初心者にとってはひとりを使いこなすだけのもたいへんなのに、複数のキャラクターを使いこなすのは難しく、ハードルの高さを感じるだろう。体力の共有によってそこの解消にアプローチしているようで、システム側が“キャラクター変更してもいいし、1キャラクターだけ使い込んでもいい”といった作りを狙っていると、筆者は感じた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/af046c9fdddc60e7e149fcfd14760d0b1.jpg?x=767)
強制的に交代することはないので、ほかのチームメンバー3人はアシストとして使うだけでも戦えるのは、チーム格ゲーではとてもうれしい仕様だ。また、2キャラクターだけ使えるようにして幅を広げる、対戦相性に応じてキャラクターを変更する、などの運用方法も可能だろう。もちろん4人扱えれば、ものすごく自由度の高い戦術を作り出せるのも魅力だ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a0a3ef9851970545ceaae6fb6270b49c5.jpg?x=767)
カンタン操作でバトル!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a7cad041ac0c269f516193092b41de5a9.jpg?x=767)
操作の基本は2D格ゲーのオーソドックスな形態で、スティック操作で移動やガード・ジャンプが可能。ボタンの基本は弱・中・強攻撃の3つ(正確にはライト・ミディアム・ヘヴィ)。そこに、アシスト系のシステムを発動する“アッセンブル”ボタン、キャラクターの固有能力を発動する“ユニーク”ボタンを加えた、計5つのボタン+スティックが基本操作となる。
さらにワンボタン必殺技の“クイックスキル”、ボタンでダッシュ&バックステップができる“クイックダッシュ”などの便利なボタン機能も搭載。使用するか否かはプレイヤーの好みによるだろう。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adc4b249b4d1accb09291440f7efb21e6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/af49ddf06c2f66125586018fdb927e927.jpg?x=767)
移動周りは非常に軽快で、空中行動では基本空中ダッシュ、二段ジャンプ、ハイジャンプなども可能。地上でも高速バックステップ連打が可能でビュンビュン動き回れるため、ゲームスピードはそれなりに速い。
必殺技ボタンの“クイックスキル”は初心者にも上級者にもうれしい要素で、難しいコマンドを入力せずとも各種必殺技を発動できるのはとてもやさしい。簡易コマンドながらに弱・中・強版の撃ち分けもできるので、上級者でも咄嗟の場面で活用するケースも出てくるだろう。ちなみに、強版の必殺技はスキルゲージを少し消費する、いわゆるEX必殺技のような立ち位置。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ae63ea84ba5a2008dbcbea9bc279e05c8.jpg?x=767)
なお、コマンド入力でも必殺技をくり出すことができ、コマンド入力で技を出すと威力が少しだけアップするボーナスがある。また、超必殺技(スーパースキル、アルティメットスキル)もクイックスキルボタンを絡めた、ボタン同時押しだけでくり出せる。このあたりの仕組みは、『グランブルーファンタジー ヴァーサス』と似たようなシステムになっている。
そして、ワンボタンで簡単にコンボをつなげてくれる“リンクアタック”といったシステムもある。押したボタンによって、超必殺技につなげてくれるものや、相手を吹き飛ばしてくれるものなど、さまざまなコンボをくり出してくれる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac871e871d61de3af9249066016cd6cb4.jpg?x=767)
リンクアタックは即実戦投入できるほどに便利で、初心者でもガチャガチャとボタンを押しているだけで相手に大ダメージを叩き込める。もちろん伸びしろはたくさん残されており、ちょっと慣れればリンクアタック→アシスト→リンクアタック……のようなコンボも可能だ。
なお細かい部分だが、格ゲーにおけるボタン連打コンボシステムは、空振りしたら2段目に移行しないこともある。本作は弱攻撃の場合、空振りしても2段目以降が出たりするので、相手に密着せずとも弱ボタン連打で相手に近づけたりする(『ドラゴンボール ファイターズ』に近い仕様)。
本作ならではのチームシステム
残りのメンバーは、自分がラウンドを落とすと1キャラクターずつ合流。または、相手に投げや特定の技を決めて吹き飛ばし、画面端から別のエリアに移行する際(ブレイクと呼ぶ)にも1キャラクター合流する。メンバーが増えるたびに、体力、スキルゲージの最大値がアップし、合流したメンバーのアシストが使用可能となる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ad9c1733ca97d350c41813ae4d2300040.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/aa6892eeaa731d4f3ccecb4f1115838aa.jpg?x=767)
ラウンド敗北によるメンバー合流は試合の逆転要素に近いが、攻めによる合流は、狙って起こせば攻め手側が有利な状況になるシステムとなっている。ただダメージを取りに行くのか、それとも合流を狙って特定の攻撃や投げを狙うのか、といった駆け引きがある。
アシスト攻撃のアッセンブルアシストは、通常時に呼ぶだけならばアッセンブルゲージは消費しない。呼ぶメンバーはスティック入力で選択し、発動する技はメンバーの立ち位置(キャラクターセレクトで選んだ場所)などで決められている。
また、攻撃中に呼び出せば“アッセンブルラッシュ”となり、コンボをつなげるのに最適な技をくり出してくれる。こちらは1回の発動に、アッセンブルゲージが1本必要だ。コンボを伸ばす、攻撃の隙をフォローするなど、使い道は非常に多い。いずれのアシストも無制限に呼べるわけではなく、呼び出したメンバーにはクールタイム的なものが存在し、連続ではすぐに呼び出せない、一連の行動中に2回呼び出せないなどの制限がある。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ad1e0d1a98c19f95eecb21fd361bc5277.jpg?x=767)
メンバー交代は、その場でアッセンブルボタンを長押しすると可能。どのメンバーに交代するのかは、呼び出す際と同じようにスティック入力で決める。そしてさらに、メンバーを呼び出したあとにアッセンブルボタンを押すと、そのキャラクターに操作を交代できる。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adcc246537392572e6e5222360a3c2105_mezUl17.jpg?x=767)
これが本作の奥深いチームバトル要素で、コンボ中にアシストで呼び出して交代、立ち回りで交代して攻めを継続するなど、自由自在な使いかたができる。アシストで相手のガードを固めたのち、操作キャラクターは相手の裏に回って、アシストしたキャラクターに交代して表と裏からガードを崩す……など、メチャクチャな連携も可能だったので、交代を絡めた立ち回りはものすごく自由度が高い。また、アシストは同時に2キャラクターを呼び出すなども可能だったので、研究が進めばものすごく幅広い使い道がありそうだ。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac871e871d61de3af9249066016cd6cb4_MHgYKLW.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a070f303223a07a57349724950cbb2883_Ibgz71p.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/af3a8b0d3b346a09d20da695ee34dfc21_9C3VHpb.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adbb320c76cc62538aa73d371b2a8b89e_qX6gUku.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7_Naqs20W.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4117b680cee164e16baa2ea81bff1c2a_wxQYcgR.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/add257dafea8dd6d79a62c3ba5a7caa1c.jpg?x=767)
細かなアッセンブル関連のシステム
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a070f303223a07a57349724950cbb2883.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/af3a8b0d3b346a09d20da695ee34dfc21.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adf678bd7a1d30238e9f92dfb9f5c76e0.jpg?x=767)
ディフェンス行動の“アッセンブルカウンター”は、発動したのち攻撃を受け止めると、自動でカウンター攻撃を仕掛けてくれる。アッセンブルゲージが必要で、こちらもフルメンバーじゃないと効果は薄いが、カウンターから大ダメージを狙える要素になっている。
また、ガード中にはほかのメンバーが相手を迎撃してくれる“クロスオーバー”が発動可能。アッセンブルゲージがあると使用できる、いわゆる“ガードキャンセル攻撃”だ。ただし、反応がよければ同じ操作をすることで、クロスオーバーを仕掛けられた側が、さらに仲間を呼び出して阻止することも可能だった。さらに超必殺技から、ほかのメンバーが超必殺技で追撃する“スーパーアッセンブル”も存在する。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a35192cf132876a54500816ed209a76f0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a7452eb0d980839668a14c49165b3ca34.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adf3aac186bf50b05d86cf5e92638624e.jpg?x=767)
といった具合に、アッセンブルゲージを絡めたアシストまわりの共通システムはかなり多く、そしてやや複雑な作りになっている(システム名の問題もあると思うが)。このあたりは上級者向けのシステムにも見えるが、アッセンブルスマッシュとアッセブルカウンターは、覚えておくだけでピンチを抜け出しやすい行動となっていた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a98728397cf726faad4f403acc874ffc9_tbUNTIk.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a32c8d462716792e1fcad02a32b9ae6bc_KEpTIb9.jpg?x=767)
アークシステムワークスの集大成のような作品
なお吹き飛ばし攻撃などで画面端から別画面に移行する“ブレイク”は、有利な効果を得られるが戦いが仕切り直しとなるので、逆転のチャンスにもなりうる要素。このあたりは『ギルティギア ストライヴ』の“ウォールブレイク”を彷彿とさせるが、演出的にもかなり短く、ブレイク自体頻繁に起こるので、遊んでいるとウォールブレイク的な印象は薄かった。
ほかにも『ブレイブルー』シリーズを感じる要素があったりと、システム面はアークシステムワークスの集大成のような格ゲーだと個人的には感じた。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/abeca5f1666869894975346f2879735a0.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a5be4b2df56155072d87ccdb0d10cd307.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/af59b092f7f9c4027fee4f5367ad66577.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a36511e3da0953f29efc0dba089148f9f.jpg?x=767)
また、システムが多いので複雑そうに見えるが、キャラクターチェンジさえ考えなければ予想外にも手触りはシンプルな印象。キャラクターそれぞれ技の数はそこまで多くないことや、読み合い自体は格ゲーの基本が詰まっている点など、基本部分がオーソドックスな作りになっているので、多少慣れていればすぐになじめるはずだ。
使用できたキャラクター
今回使用できたの6キャラクターの特徴を、ざっくりと解説。マーベルを代表する人気キャラクターが参戦しており、いずれもジャパニーズアニメのようなデザインなっていて、かなり新鮮味があった。
ちなみにマーベル系のゲームは担当声優が作品によってけっこうバラバラで、ゲームオリジナルの声優陣を起用することもしばしば。本作はマーベルアニメ、または映画の吹き替えを担当した声優陣を採用していることが多く、いちマーベルファンとしてはそこもうれしかった。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/afdfd669eb38df817c4c6e97b6266dc6c.jpg?x=767)
キャプテン・アメリカ(声:中村悠一)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/abcd57b6a3e86a606f8a8ebff5b502487.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7_Tp10S2l.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adbb320c76cc62538aa73d371b2a8b89e_q1zqS2a.jpg?x=767)
基本はシンプルながら、盾を用いたカウンター技や投擲攻撃など、ユニークな性能も兼ね備えている。飛び道具として投げた盾を蹴り飛ばして何度も跳ね返す、といったこともできたので、シューティング性能もそれなりに高い。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a55c84c1d9ee12445e4ffc90ebc2f4726.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a44cb95fa586c4efcf83c130235cc865e.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4117b680cee164e16baa2ea81bff1c2a_xoJy5pm.jpg?x=767)
アイアンマン(声:川原慶久)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a32c8d462716792e1fcad02a32b9ae6bc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adbb320c76cc62538aa73d371b2a8b89e_qCvoepP.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7_YphSJGX.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ab7c6dd240ccdf6ae68cb9d4030132cdc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a9fb9f4946d5e37c40f4a3e9c27053b97.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ae6886890c6984dc1aafe0dcd21967bcb.jpg?x=767)
ミズ・マーベル(声:黒木ほの香)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a3e83f2b514dc79d2ac847fcf5030aad5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a9046490e6a4b9b0380fb18f6a6f9fd85.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4117b680cee164e16baa2ea81bff1c2a_GzyB2EO.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a0e5345b8f1a1f2b38a33b7b6c3166c45.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a1098aef4b28c091713ed27a9c1cd1c07.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adcc246537392572e6e5222360a3c2105_nWUxnX6.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac11b8dd0668ed7d310a25b88be3b4a67.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a40495d4b50a16f1396cc1706fbac82b1_RmtytAk.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a98728397cf726faad4f403acc874ffc9_ivSOJG8.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a32c8d462716792e1fcad02a32b9ae6bc_vLHCnJd.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac871e871d61de3af9249066016cd6cb4_F4k7jwp.jpg?x=767)
スター・ロード(声:山寺宏一)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a8df2b80a376fd8eaf3fc3c7810a054ec.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a6648a8fd2aa57660638365c685d09b09.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a18ac083c982b3dd6a719fab1a1ed38ed.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a653e02559245ca2d91d5fc992ae066f7_jXvNtrF.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/adbb320c76cc62538aa73d371b2a8b89e_ErseDKP.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a45bd96c28daa555bfc86f5e5099acb29.jpg?x=767)
ストーム(声:沢城みゆき)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a55f061fadb167e939f56a3ad8c2fd088.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/abfde11c02f34bf2ce5c768799668eb69.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a77ab483f537515862ff2a542a2845192.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a7e1caa488b4f8a67b180ce8f79c882fc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a1bb1cd7603fb4b79a155bdb0eaa4dc58.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4ba80f26ea77495edc79888103a5d7c4.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ab8ef5626428635ccb7006fb4d04ba7ee.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ad45dbc0ee8fab02b1af3cacc4b0cd1c7.jpg?x=767)
ドクター・ドゥーム(声:土師孝也)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ad5b8b12c093a92d98c47529f0ae279fc.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a4b2f7ccb220410ecabaea5b6d1cfe23f.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a25df79483e6a2c2137649cf129f6c146.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a9db492ed6c8f045751e098d18d575e62.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ac1c3882f2316578f969711d37b87a1ab.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a6069fdf4d719a0896906277209f5c0d5.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/ad68cc9117dabd78f49fba4605c388eb3.jpg?x=767)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a0e00e4253d884b0eab67074c59d50829.jpg?x=767)
チーム格ゲーに革命を起こせるか
本作はそこにメスを入れており、チームだからこその楽しみも味わえるし、1キャラクターだけを極めるようなプレイも可能と、プレイスタイルの両立を図っているタイトルだと感じた。なお、今回のバージョンはいろいろ試し試しにやった感じ、コンボだけで見るとだいたい2~3回読み勝てばラウンドを取れるようなダメージ量だった(複数人巻き込み除く。もしかしたらもっと減るコンボもあるかもしれないが)。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a73ea18841d066c8a679c3e2260f8f517.jpg?x=767)
そうした目新しさはありつつも、難点としては、やはりシステムが多いため、ハードルが高いように感じてしまう人が多そうなことだろう。カジュアルな作りを目指しつつも、中身はやはりアークシステムワークスお得意の緻密な攻防が練り込まれている印象だ。ただ前述の通り、ボタンをガチャガチャ押しているだけでもガッツリ遊べるような作りになっているし、チームメンバー交代を絡めなければそこまで複雑ではなかったりする(ほかの格ゲーに慣れていれば、だが)ので、間口は広めに感じられた。
やはりわかりやすい魅力となるのはアークシステムワークスが描くマーベルキャラクターたちの数々だ。今回の試遊では6キャラクターしか使えなかったが、すでにタイトル画面にいるように、スパイダーマン、ゴーストライダーは発表されていることからも、アニメチックな世界観で多くのヒーロー・ヴィランたちの活躍が楽しめるはずだ。今後の続報にも、ぜひ期待したい。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/51717/a2fb39ebcdf7ad53671e1b10fae6d7d90.jpg?x=767)